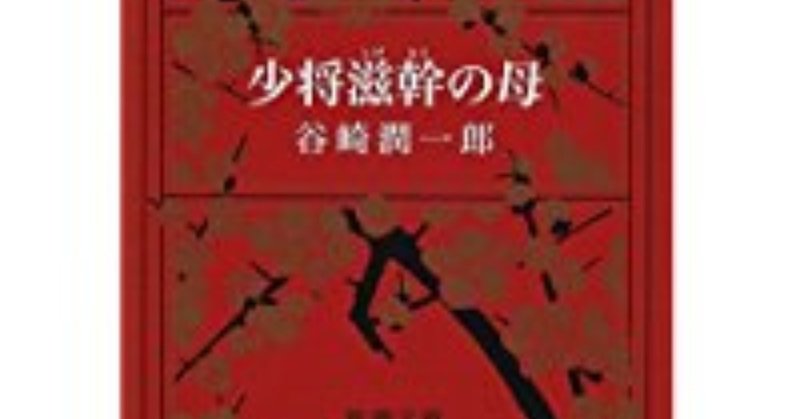
題:谷崎潤一郎著 「少将滋幹の母」を読んで
谷崎潤一郎の作品は、「刺青」などの短編や「痴人の愛」、「春琴抄」、「鍵」、「細雪」を読んでいるが、「少将滋幹の母」なるこの作品が気になっていて、読んでみたのである。すると、谷崎潤一郎に新たに魅せられる。たぶん、谷崎の作品を区分けすると、「吉野葛」などの短編に代表される抒情と郷愁に満ちた世界、「痴人の愛」や「鍵」などの作品における精神に打ち勝つ肉体の欲望、「春琴抄」における精神と肉体の解き難き融合、ところが「細雪」では肉体が影をひそめて、日常の連続した時間の内に永久に在り続ける人間となる。これらに分けられるが、主テーマは人間なるものの肉体と思っている。ところ、この「少将滋幹の母」はこの肉体が欲望から崩壊へと繋がっているのである。そして、そこはかとなく母への郷愁を混ぜて、作者は作品の内に入りながら語り部となって、文章はきめ細やかさを欠くように粗く見えながら、大胆に迫ってくる力強さがある質の高い作品になっているのである。
「痴人の愛」や「鍵」などの単に肉体への欲望を描いた作品は他の作品に比較して作品の完成度は若干落ちるが、この「少将滋幹の母」は他の作品に比較して完成度がとても高い。崩壊する肉体への捨て難い愛着と執着、執念と怨念とを美しさと醜さを織り交ぜて書いているからに他ならないからであろう。あらすじを簡単に紹介する。なお、本小説は「今昔物語」など平安期の古典に題材を得ている。「少将滋幹の母」とは大納言国経の妻である。年老いた国経はこの若くて美しいこの妻を愛し寝床を常に共にしている。国経が若い妻に生ませた子の一人が少将滋幹である。ところが本作品の最初に登場する兵衛佐平定文、字を兵中という在原業平と同等なこの色男は、国経の妻と過去に密通している。左大臣藤原時平に問いただされて兵中は仔細を言わざるを得ない、事情を知った藤原時平は国経に贈り物などして宴を儲けさせる。そして、国経を酔わせて都合よく若くて美しい唯一の宝物を捧げ出させるのである。平中は悔しくてたまらず、時平の邸に住む若い母に子なる滋幹が訪れる時、滋幹の腕に歌を書くなどしてよりを戻そうとするが無理である。
そして、大納言国経は若き妻を失った悲しさ、辛さ故にか不浄観に陥っていく、その姿を滋幹は見聞きする。夜な夜な墓場に出かけて、腐りゆく若い女の死骸に国経は見入っている。不浄観とは滅んでいく肉体を知って悟りを得ることであるけれど、国経は決して悟りを得ることは無い。この国経は滋幹に対して母のことなどについて語らう、でも滋幹は美しい母を、腐りゆく死骸に擬して思い込もうとする国経を許すことはできない。国経の死後一年後に藤原時平は死に、その後時平の一門は滅びていく。少将滋幹は時平以後の母の行方に思いを馳せている、もう幾余年過ぎただろうか、川の辺の清水の流れ、山吹の黄色い花の咲く庵の前で母に会い地上に跪いて、下から母を見上げ、膝にもたれ掛るような姿勢を取り、甘えているように近づき母の袂で涙を拭うのである。本書の読みどころは、時平が若き妻を奪う場面のリアリテイさと腐りゆく死骸に見入りながら忘却しようとする国経の若き妻の肉体への執念である。
谷崎潤一郎について肉体と肉愛は切っても切り離せない。それに心理が微妙に絡んでくる。芥川龍之介は谷崎純一郎のこうした性向を批判する。筋(プロット)論も加わってくる。これには触れないでおこう。もう記憶が薄れている。でも、谷崎潤一郎を論じる場合に主テーマである肉体は避けて通れない。ただ、エマニュエル・レヴィナスが示すように受肉した身体性と知覚の構造から論じる以上に、谷崎潤一郎の場合、身体性が知そのものと結びついている。知とは精神であり心である知性である。無論、谷崎潤一郎には、身体性の即ち肉体の優位性がある。肉体に執着する心があり、心を占有し狂わせようとする肉体があるためである。ただ、肉体を語るその時のこれら肉体と知との相互関係、即ち肉体と知の揺らぎの強度によって谷崎の作品の性格が決まっているに違いない。「痴人の愛」や「鍵」など作品が他の作品に比較して劣るのは肉体の優位性からのみ記述しているためである。心が知へと昇華して知が溺愛する肉体を語る時、「春琴抄」やこの「少将滋幹の母」、更に「細雪」なる傑作が生まれている。無論、身体性と知だけの空間ではない、谷崎潤一郎には空間を彩る平安朝文学や日本文化や風景など稀に見る知性の広がりがあり、これらが作品を彩って絢爛豪華に仕上げている。もしや、レヴィナスが述べている他者へ向けて発せられる言語、即ち谷崎の描く小説の言語空間から放たれる文章構造そのものがある種の肉体を持つ生命の連続性なる意味を表しているのかもしれない。こうした谷崎潤一郎の世界を論じるには、並大抵の力量ではできない。まあ、読者は彼の小説を読んで楽しむだけで深入りするのを避けた方が良いのかもしれない。調べるにはあまりにも多くの時間を必要とするためである。でも魅力的ではある。
「不浄論」で思い出したのが、夢野久作の「ドグラマグラ」における腐乱していく死屍を書き写した確か六枚の遷移図である。絵は永代に伝えられる秘蔵の家宝でもある。谷崎が描いている死屍は知覚に訴えて知を覚醒させるその場限りの死屍である、これが生々しくとも、ある種の幻覚とも錯誤される一過性であることが救いになるのではない、この一過性が死屍の絵画と同様に永代性を兼ね備えている点に注意したい。なぜなら読者の頭の中に否応なく叩き込まれるためである。谷崎を論じるには、身体性と心との関係の揺らぎとして、言い換えるならば量子力学的な位置と運動との関係に基づいて論じるのが一番良いのかもしれない。たぶん、この関係性が作品構造を解明させるには役立つはずである。この揺らぎに郷愁や歴史伝統性のパラメーターを加えれば、作品ごとに相当に理解し得る関係・関連図を描き切ることができるはずである。それでもきっと谷崎を解き明かすことは難しいに違いない。でも、もしや簡単でもある。肉体に拘泥する深層心理が見透かされているためである。難しいのは、言語空間から放たれる文章構造が何を意味しているか、言語論との絡みで瞬間性と連続性を論じることなのかもしれない。
以上
詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。
