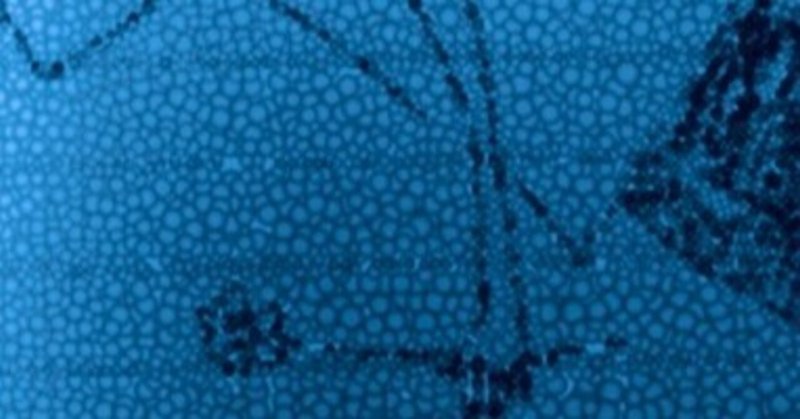
ガブリエル・夏 33 「フォン・デル・パピールとプレッツェル」
4本のスキー板のついた脚をバラバラに、元あったように2本ずつの組に戻した。その辺の雪で、みかん、団子、ジャムパン、地球儀、バスケットボール、ダンくんの消しゴム、鼻をかんだ後のティッシュなどを作った。どれも丸っこくて、言わないと何かわからない。それを小さな雪だるまにして、マトリョーシシカみたいにたくさん並べた。いつまでも遊んでいられそうだったが、レイが不意に身震いして立ち上がる。
「ぶるるる、さぶ!」
夏の雪は、冬の雪の、粉砂糖の軽いふわふわではなく、上白糖のようなぼったりした感じで水っぽい。普段着の2人の服にも水分がしみ込んできていた。
「ガブくん、お尻のところ、お漏らしのパンツみたいになっちゃったよ。」
「えー。」
レイがズボンのお尻を触ってみる。じわっとした感じがある。
「やだー。あ、ヤバい。」
レイは胸ポケットに手をやる。
まずは外側から触ってみるが、お尻ほどではないもののだいぶ湿った感じがある。心配そうに手をポケットの中に入れる。
「あ。よれっとした。」
ものすごく大きな問題に直面して困っている人の顔になった。
レイが取り出した、紙のカタツムリ のメーステル フォン・デル・パピール(バスの中でレイが名付けた)は、その紙が吸い込める水分の8割か9割吸い込んでますという風で、破れかけているところが数カ所あるが、まだぎりぎり1つのかたまりの状態を保てている。
「どうしたら元気にできる?」
賢いレイが困っている。良い方法を思いついて解決してあげたい。可愛がっているフォン・デル・パピールを、またレイが寄り目で愛おしそうに見つめるのを見たい。
「水分を吹き飛ばしたらいいんじゃない?」
「風にあてる? ふーふー吹く??」
「ああ、それなら。」
2人は、パピール氏をレイのポケットに戻し、ジャンジャン滑って、Tシャツもろとも乾かす方法を取ることにした。それほど画期的なアイディアではなかったが、うまくいきそうな感じはした。吹き付ける風が強過ぎてパピール氏の負担が大きくて、体がちぎれそうになっても、後ろでレイの胴体がしっかりガードしていれば、ちぎれて飛んでいってしまうということにはならないだろう。何しろパピール氏はレイにとても大事に思われているのだから、こんなピンチの時にはそれを感じて、力にすればいいのだ。
手袋もはめ直して、じゃあ滑り出そうかという時、グフスタインの駅で列車を降りる時にレイの首輪になって、その後どんどんよれよれになっていった車のハンドルサイズのプレッツェルは、もうレイの首からぶらぶらしていなかった。
「ガブくん、プレッツェルの首輪、どっかいっちゃったみたい。」
「あ、あ〜〜〜あ。」
首に手をやり、自分の首しかないのを確認して、残念そうにレイが言う。
「ん? 待って。」
リフトの降り場の小屋の脇の斜めになっているところで、白い雪の上につぶれた豆の輪郭の一部のような形の茶色が、まみもの視界に入った。ストックは借りていないので、スキーを左右にスケートのように蹴って進み、まみもがその茶色の豆の輪郭に近づいていく。確信する。あの妖怪顔のプレッツェルだ。もうだいぶ変形しているし、顔に見える要素も全然残っていなかったけれど、そのくたびれたパンから、生きる意志のようなものを感じた。まみもに足りないやつだ。
これも雪の水分を吸い込んで、脆そう。崩れないようにそっと拾って、向こうにいるレイに見せる。少し離れているので、細長い全身が見えている。レイの小さい顔が笑って、口が大きく横に伸びる。頬の長いエクボが深く折り込まれる。レイが喜んだ。昨日散歩に登った山で、おなら質問に答えたときの誇らしさを感じながら、レイのところへ雪を蹴って戻る。息があがる。犬が、これから飼い主に大いによしよしされると確信している時は、こんな気持ちなんじゃないだろうか。 まみもがよれよれのプレッツェルを差し出すと、レイはプレッツェルではなく、まみもを見ながらそれを受け取った。これ以上は無理、というぐらいの時間、多分ほんの1呼吸か2呼吸ぐらい、2人が目を合わせている時間があってから、レイはプレッツェルを2、3回上下に振って、多分バイ菌をほろい落としたことにして、大きな口で、ガブリとかじった。もぐもぐしながら、口の中にパンがいっぱい詰まったままの声で、「しめしめしてる」 と言ってまた長いエクボを出した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
