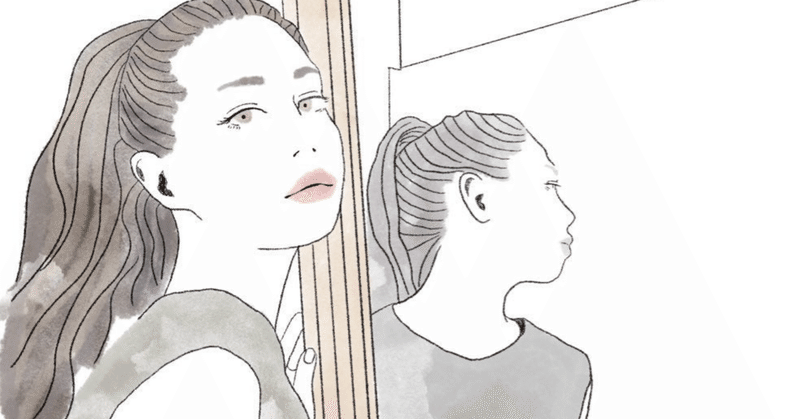
鏡のない世界。
この世界に鏡がなかったとして。
すると他者からの評価でしか自分の外観がわからないということになるでしょ。
ちやほやされたら結構かわいいわけだし。ぞんざいに扱われているなら、それなりの顔ではないかしら。
私は、他人の顔がわからない。別のものが見えて邪魔をするからだ。その人の本性があふれ出てなんとも醜い姿をした者ばかりだ。
パソコンで文字を打っていると、目の前に男性が立った。
飯塚部長は目のあたりに女性の乳房がぶらさがっており、鼻は卑猥なもの。女性の尻のようなものが首についている。たぶん、そういったことにしか興味がなく、性欲の塊なのだ。幾人か若い女性に手を出していると噂を聞いている。私にもこうして声をかけてくる。挨拶を目を合わせず会釈して仕事をするフリをする。
次にやってきたのは、技術部の中村さん。みんながとてもきれいな人だと言っていた。私には彼女の顔は見えない。いつも真っ黒だったからだ。ブラックホールのごとく、闇が覆っている。ものすごい闇を抱えているに違いない。飯塚部長に殺意を抱いているのかもしれないと推察する。なぜなら、飯塚部長にいつだって闇がまとわりついているからだ。
私は彼女が怖くてたまらないので目を合わせない。
その中村さんに熱い視線を向けている総務の青年。
彼は中村さんと思われる顔をしていた。きっと彼は中村さんの虜なのだろう。私は中村さんの顔を直接みたことがないが、こうして社内には幾人か中村さんの顔をした男性社員がいるので、彼女のことが頭でいっぱいな人が多いのがよくわかる。
「お昼だよ、一緒に行こう」
やっと、ほっとできる人が現れた。とても綺麗な顔をした私の友人。整ったすっきりとした目鼻。形のよい唇。真っ黒な瞳がこちらをじっと見ている。
彼女は営業の立花さん。立花さんは社内でも不細工で通っており、この前は別部署の女性から「どうして、あんな人と食べているの」と言われた。不細工な人とはお昼を食べたらいけないのだろうか。そもそも、こんなに綺麗な顔立ちをした女性をみたことがない。
綺麗な心の持ち主だろう。
出会ったとき、私もあなたのようにきれいな顔が良かったとつい口から出てしまった。
それは嫌味? と言われたけれど私は自分の顔がよくわからないと言ったら彼女は、ほほ笑んで言った。
「そういう病気かな? だったら悲しいわね。私とお昼を食べてくれるのもそういった理由なのね。あたなはみんなが嫉妬してしまうくらいに綺麗よ」
一瞬、私は彼女が私の顔をしてくれているのかと考えた。
けれど、それは違っているのはよくわかる。
実は子供のころは普通に人の顔を認識していた。大人になったころから、内面が現実化して見えるようになってしまった。
子供の頃の顔を思い出す。
とても立花さんとは似ていなかった。地味な顔をしたおとなしそうな女の子がこう成長しないだろう。あまりにも二つは繋がらない。
抽象的な私の話を立花さんは茶化すことなく聞いてくれる。
鏡ではどう見えると問われた。
鏡の中の私はいつも曇っていてよく見えない。首から上がぼやけている。
飯塚部長はなびいてこない私を気取っている女だと称し、中村さんは被害にあっていない私を妬み、空気が読めないブスと称し、総務の青年は、中村さんに比べたら綺麗じゃないよ、と話していた。
「不細工な女にしか見えないわよ」
「ネガティブねー」
立花さんは思いついたように、明るく言った。
「あなた、女優の北原景子に似ているわよ」
あんなに綺麗な女優さんに似ているだなんて。
私は赤くなって否定した。それでも翌日、鏡を見ると本当に綺麗な顔立ちがそこにあった。他者がいうように、大した顔はしてないはずだったのに。
していないけれど、そう思い込むと毎日、この顔に出会えるのだ。私はメイクすように自己暗示にかけた。
すると、最近「きれいになったわね」と声をかけてもらえるようになっていった。
いや、他人から言われなくても私は私が美しいことを知っている、という人になることを決めたのだ。他人評価ほど、当てにならないものはないからだ。
鏡の前で笑顔を作る。
それなり、というか結構イケてるじゃん。
実物はどうか知らないけれど。もしかして、今見えているものが本当の私なのだろうか。立花さんが言うように、あの綺麗な女優さんに似ている?
ふふ、と笑って玄関の鍵を閉める。
鏡がない世界では他人の評価を気にするけれど、ある意味、綺麗だと思ったもの勝ちでいいのかもしれない。
ヒールを鳴らして、私は今日も会社へと歩んでいく。
おわり。
サポートしていただけただけで、めちゃ元気でます。あなたのこと好きになって、みんなが私もやろう、って思う記事を上げれるよう精進して参ります。主に小説関連!
