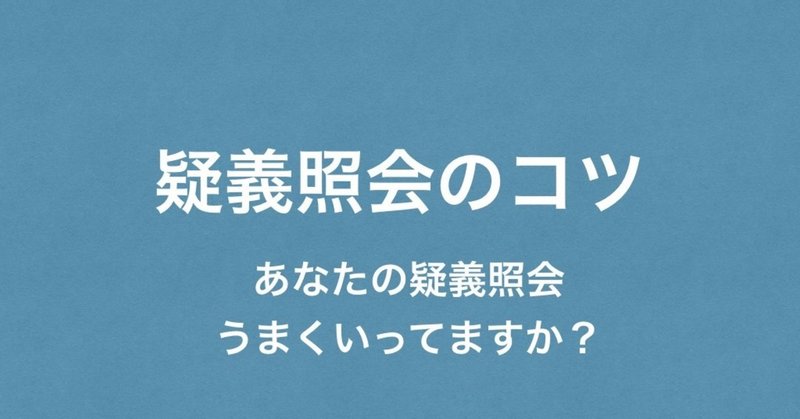
受け入れられる疑義照会の方法
疾病禁忌や併用禁忌の処方を発見し、電話で医師に疑義照会したけど聞き入れてもらえなかった・・というケースありませんか?
今日はこれを解決する考え方と方法について書きます。
例えば前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患のある患者にPL配合顆粒が処方された場合。
薬剤師「排尿困難を悪化させる可能性があるため併用禁忌となっておりまして・・。」
医師「いつも出してるからそのままでー。」
みたいな感じです。
これ、絶対うまく行かない伝え方です。
もちろん禁忌を見つけた場合はリスクヘッジ的に照会しておく必要があるかもしれませんが、この伝え方を何度続けていてもうまく行きません。
原因は2つあります。
1)伝えるタイミング
解決策は「決断する前に情報を提供する」ということです。
医師も薬剤師と同様にPDCAサイクルを回しながら治療にあたっています。
採血をして(Check)医学的に評価し(Assessment)治療方針を決めて(Plan)処方して(Do)患者さんを送り出します。
この一連のサイクルのDoより前に情報を提供するのがベストです。
引っ越しするために荷物を全てダンボールに梱包してトラックに積み込んだ後で同居人から「このお皿とぬいぐるみも追加で梱包して欲しい」と言われたらむちゃくちゃムカつくし、実際ムダな労力を使うことになりますよね。
Doの後にそれを覆そうとする情報を提供するということはこういうことです。
一度回したPDCAを逆行する必要があるので、むちゃくちゃムカつくし疲れます(僕だったら)。
人として正しい伝えるタイミングに立ち返ることが必要です。
(過去記事より引用)
とは言えどうしたって処方の方が先に来るんだもんよぉ〜という方もいらっしゃると思います。そりゃそうです。解決方法は後述します。
2)医師と薬剤師の目標設定が異なる
そもそも医師と薬剤師の目指している目標にズレがあるためにコミュニケーションに齟齬が生じているように思います。
「いつも出してるので・・」とか「前医からの引き継ぎなので・・。」
医師のこれらの発言の背景を理解することが必要です。
例えば上述したPL配合顆粒の件。
医師の目標は患者の感冒症状の改善、ありていに言えば患者さんが良くなることを目標にしています。薬剤を中心に時間軸をみてみると、薬を飲んだ後を見ています。
一方で薬剤師は「(添付文書に禁忌と書いてあるから)」「(抗コリン作用で尿閉しちゃうかも)」というのは多くの場合、薬を渡すまでを見ています。(抗コリン作用で・・というのは一見薬を飲んだ後を見ているようですがそうではありません。後述します。)
どちらが正しいというわけではありません。
薬剤師は疑義のある処方を調剤してはいけませんし、疑義は行うべきです。
ただ、医師と目標設定が異なるために結果として受け入れられないのです。
医師は自身が患者を診察しているという自負もありますし、自分が診察・処方したのと同じタイミングでネットに書いてあるレベルの情報で問い合わせをされてもなかなか首を縦に振れません。(僕が同じ立場でもそう思います)
これらを解決する方法はただ1つです。
服薬後のフォローを行い、次回の受診までに医師にフィードバックします。
医師と異なるタイミングでフォローした情報を薬学的にアセスメントを行い、トレーシングレポート等で情報提供します。
医師と異なるタイミングというのは、薬剤を中心に置く時間軸では薬を飲んだ後(未来)のタイミングです。添付文書上の禁忌はある意味で未来予測なので、それを確かめるためにしかるべきタイミングで実測・検証してみるのです。ここで得た情報は医師と同じ視点かつ医師と違うタイミング(ニュース性が高い)で得た情報のため医師にとっても価値が高いはずです。
フォローの方法は再来局していただくか、電話によるフォローが妥当だと思います。
ですので冒頭のやり取りはこうなります。
薬剤師「排尿困難を悪化させる可能性があるため併用禁忌となっておりまして・・。」
医師「いつも出してるからそのままでー。」
薬剤師「わかりました。引き続き観察して何かあればご報告いたします。ありがとうございました。」
そして患者さんにはこう伝えます。
「ちょっと心配だから来週の同じ時間にまた来てね」
ポイントは自信たっぷりに堂々と当たり前の顔で言うことです笑
ちょっぴり恥ずかしくても、あなたが患者さんが良くなると信じているなら行動すべきです。
全ての薬剤師が今まで抱えてきた疑義照会のストレスを解消して、そのエネルギーを患者さんのために使えば地域医療は変わるかもしれません。
知らんけど。
今日もありがとうございました!
いつも読んでくださりありがとうごさいます。みなさんが読んでくださることが活力になっています。
