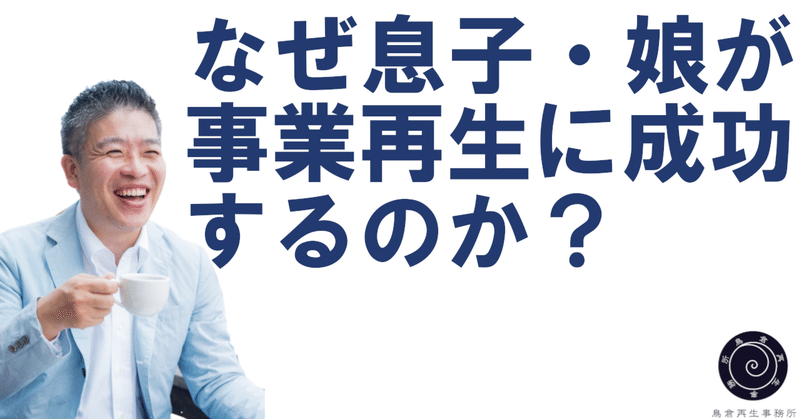
なぜ息子・娘が事業再生に成功するのか?
事業再生は難しい
事業再生は専門家でも往々にして失敗します。金融機関が音頭を取って取りまとめる事業再生でも失敗します。ですが、経営者の息子や娘、一族の素人が事業再生に成功したお話しを聞いたことはありませんか?意外によくある話です。なぜプロでも失敗する事業再生に、経営の素人である息子や娘が成功するのか?いつもと違う切り口で説明したいと思います。

事業再生の失敗のパターンを考える
金融機関の場合
金融機関はその名の通り、資金調達への支援が基本となります。事業再生フェーズではお金を足して何とかするタイミングを越えてしまっていることが多いです。その為、最大の長所である資金調達支援ができないのです。事業再生に対する支援も計画作成が中心であり、それ以外の支援については組織の仕組みが整備されていません。結果として、不良債権の引当を進める事が最大の事業再生の出口戦略への支援となりますが、前向きな事業再生支援のパートナーとはなりません。
専門家の場合
専門家(弁護士・会計士・税理士・診断士等)は事業再生に精通するプロです。ただそのプロでも事業再生を百発百中で成功させる事は難しいのです。事業再生を本職にするプロの仕事は、法律、会計、税務に関する支援がメインとなります。その支援の多くは、専門職としてのサポート業務やコンサルティング業務になります。コンサルティングは分析に対する費用であり、事業再生の実行支援はしてくれないのです。事業再生の入り口を整備する専門家であり完遂をする専門家でないことが通常です。
経営者の場合
経営者自身が金融機関や専門家の支援を受けて事業再生に成功することはできないのか?という素朴な疑問も湧いてきます。ただこれも難しいです。事業再生が必要な経営の苦境に陥ったとは言え、自ら一生懸命専念し作り上げてきた会社です。過去の路線を自ら否定することは難しいです。リストラとはリストラクチャリングの略で日本語では再構築と訳されますが、人員整理や取引先の選別など、労苦を分かち合った仲間に負担を強いることができない経営者の方は多いです。自分の片腕を自分で切り落とすかのような痛みを伴う改革を実践できないのは無理もありません。

なぜ何の経験もない息子・娘が成功するのか
むしろ逆に専門的なノウハウがないから成功するとは考えられないでしょうか。業界慣習、通例、前例を踏襲をしない、できないとも言えます。業界の当たり前を実践すれば、ライバルは多く、業界平均の利益率以上に利益をもたらすことは難しい。古くなったビジネスモデルに拘泥しないことは、新たな発想でチャレンジするための基盤になります。また、若い力はそれだけ行動量が増えます。ビジネスの世界は実力主義であり、約束された成功などありません。リスクをとってトライアンドエラーをすることが大切なのです。経営者の年齢が多くなると行動量が減ってしまい、トライアンドエラーを試行する回数が減ってしまいます。ビジネスにおいてこれは機会を失うのと同じ意味があります。
息子・娘ならではの成功の土台もあります。それは物心ついて幼少のみぎりより、経営者である親の背中を横で見て企業の歴史を知っていると言うことです。企業の歴史はブランディングをする上で大事です。流行を取り入れたにわか仕込みのブランディングをしても、顧客は流されません。過去の歴史を体感している息子・娘がその企業の本質を現在の表現方法に置き換えたとき初めて威力を発揮します。どんな優れた広告代理店が仕事をするより、遙かに多くのリソースを息子・娘は有しています。

事業再生は債務超過状態にある事が多いですが、事業価値を高めて再建する事が求められます。その為には利益を捻出する必要があり、専門家はコスト削減による縮小均衡が読みやすく、実施もしやすいためそこに終始することがあります。短期的には必要な過程ですが、コストカットしかアイディアがないのでは、事業再生を完了することができません。
息子・娘は、小手先のコストカットではなく、売上改善とブランディングという結果が出にくいことに対しても、挑んでいく覚悟があることが多いです。抜本的に事業再生を出口戦略までもって行くためには必要な姿勢です。成否が必ずしも明確でないため、外部関係者は着手しにくいです。当事者であるが故に挑戦できる領域でもあります。

旗頭になることへの信認と自覚
地方の改善は「わかもの・よそもの・ばかもの」が主軸となって実践されるという言葉があり、私も納得するところでありますが、事業再生は会社という資産・資源・負債もたっぷりある中で、改善を進めるという困難な仕事です。他人が背負ってくれる仕事ではないのです。息子・娘は家督相続の正統な後継者です。他のどんな人間が手を挙げるよりもみんなが納得する形なのです。誰が?なぜ?その事業に深くコミットメントするかを、会社の内側の人間も、外側の人間も納得するとみんなが協力をしてくれるようになります。事業再生は“火中の栗を拾う”仕事です。倦厭されますし、腫れ物に触る仕事であり、経済的苦境も伴います。それでもなお「自分がやらなくてどうする、自分がやらねば誰がやる」という圧倒的なコミットメントが改革の先導役としてのエネルギーにつながります。行動する事、変化させる事が何より事業再生を成功させる力になります。

失敗例はどんなパターンか?
親子の確執がまず挙げられます。既に述べたように従来の経営者である親は、改善改革する力を失ってしまっている事は多いです。ですが連帯保証人が必要であり、経営者として残留する事は多いです。その為、改革の実践者である息子・娘に対して権限の委譲が行われていないという事態が起こります。
親は子に対する愛情故に失敗しないように様々に指導や誘導をしたくなる生き物です。子どもは約束されたものが何もない困難な課題に挑んでくれています、更に様々な制約をお仕着せされても納得がいきません。
子どもの再生に成功しなくてはいけないというプレッシャー、親は子に失敗をさせたくないと、愛故に衝突してしまうのです。誰もが望まない、家業の再建という困難な道を子どもが志してくれたのに、親は過干渉で潰してしまうことがあります。
子どもは、親は自分の行動を承認してくれるはずだという親子の関係をビジネスに持ち込んでしまいその甘さ故に致命的な対立につながる事があります。どちらが必ず正しいと言うことはありません。ビジネスに対しては真摯でありながら、お互いを認め合う器量が重要です。
息子・娘が若さ故に暴走する事もあります。ビジネスの正否以前に人間としての礼節をわきまえない、長幼の序を無視し経営者という権力を背景に傲慢に人と接する、従業員と経営者という共存関係を理解せず労使関係を対立させてしまう、などは典型例と言えると思います。
世阿弥の『風姿花伝』はビジネス書として読むことをお勧めしますが、24,25歳の若者が陥る点を指摘していますので意訳します。「若い盛りの美しさや物珍しさは、かりそめの魅力。有頂天となり初心を忘れ、人に教えを請わず稽古を怠れば、すぐに花は失われてしまう」
息子・娘さんへは贈りたい言葉は、事業再生という困難な課題への成否もそうですが、成功しても失敗してもそこから学ぶ機会が失われてしまえば人生を無駄にしてしまうということです。

ここから学ぶべき事業再生のポイント
専門家ではない息子・娘が事業再生に成功するケースがあると言うことから学ぶべきだと思います。知識があるからといって事業再生に成功するわけではありません。強烈なコミットメント(責任・参加・関与)がなければ事業再生は進みません。既に失敗が現実のものとなった会社を再建するためには、意図して変化をつける、変化の幅を作ることが大切です。行動量がなくては成功も失敗も結果に至りません。
最後に
親の会社を再建したい、息子・娘の情熱に私は大変共感致します。また、素人だからと言って会社が再建できないとは全く思わないため、今回の記事内容と致しました。ただ事業再生には知識経験が必要な面も多いです。何も考えずに連帯保証人になる、負債を承継する、負債を相続するといった人生において大問題が生じる場合もあります。実行に当たっては注意点をお伝え致しますのでご相談くださいますようお願い致します。
無料面談のご予約はこちらから https://torikura.com/contact/ あなたの事業再生が優しくできるようご支援します。 難問解決を得意としています。あなたの仕事にきっと役に立ちます。 フォロー、スキでの応援お願いします。
