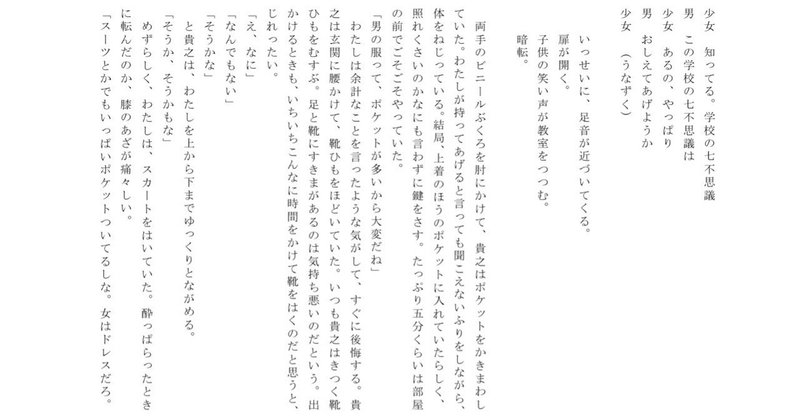
水族館物語(5)
両手のビニールぶくろを肘にかけて、貴之はポケットをかきまわしていた。わたしが持ってあげると言っても聞こえないふりをしながら、体をねじっている。結局、上着のほうのポケットに入れていたらしく、照れくさいのかなにも言わずに鍵をさす。たっぷり五分くらいは部屋の前でごそごそやっていた。
「男の服って、ポケットが多いから大変だね」
わたしは余計なことを言ったような気がして、すぐに後悔する。貴之は玄関に腰かけて、靴ひもをほどいていた。いつも貴之はきつく靴ひもをむすぶ。足と靴にすきまがあるのは気持ち悪いのだという。出かけるときも、いちいちこんなに時間をかけて靴をはくのだと思うと、じれったい。
「え、なに」
「なんでもない」
「そうかな」
と貴之は、わたしを上から下までゆっくりとながめる。
「そうか、そうかもな」
めずらしく、わたしは、スカートをはいていた。酔っぱらったときに転んだのか、膝のあざが痛々しい。
「スーツとかでもいっぱいポケットついてるしな。女はドレスだろ。そうか」
「聞こえてたんじゃない」
「うん」
「腹立つなあ」
キッチンを通り抜けて、貴之は部屋のほうに荷物を置きに行った。きっちりとそろえた靴を見て、わたしはなぜかあがっていくのをためらっている。
わたしは膝に手をあてた。スカートをはいてきたのは、貴之になにか言ってほしかったからではないかと思った。貴之がどんなことばをかけるか考えているし、そのひとつひとつにどう返事をするか用意していることに、あらためて気づく。
「もうつくるよ。いい。おなかすいただろ」
「おなかすいた」
「なにしてんの。あがれよ」
「あがるよ」
貴之は、服を着がえているところだった。一瞬とまどったが、無視することに決めて、カーテンをあけようと窓際に立つ。
「あ、そのままにしといて」
振り返ると、貴之はもう着がえをすませ、買ってきたものをひとつひとつふくろから出していた。
「どうして」
「むかいのアパートから見えるから。落ち着かないんだよ」
「ずっと閉めてるの」
「そうだよ」
「こんなに日あたりがいいのに」
クリーム色のカーテンを通りぬけた光は、部屋のなかを黄色く染めていた。かわいたほこりにまじって、たばこのにおいがした。
わたしはベッドに腰をおろす。いまだに実感のないわたし自身に言い聞かせるように、何度もここが貴之の部屋だと、ここで寝たり起きたり、ごはんを食べたりしているのだと考えてみる。
「テレビでも見てれば」
わたしの返事を待たず、貴之は材料をかかえてキッチンに行ってしまった。わたしは壁にもたれて、ななめ上のほうをぼんやりながめていた。大きな梁が通っている天井はとても低く感じ、おしつぶされそうなくらいに、きゅうくつだった。
「ああ」
「どうした」
貴之の声と、まな板をたたく音が、キッチンからひとつになって聞こえてくる。
「この部屋、なにかに似てると思ってたけど、歯医者の待合室だ」
「なにそれ」
「こんなところでよく生活できるね」
「おれは、自分の部屋だとしか思ったことないけど。テレビつけてる」
「つけてない。見ないからいい。こっちに来てから、あんまり見なくなった」
「ああ。あの家、テレビなかったっけ」
「浪人生だし」
大学受験も浪人もしたことがない貴之は、こういうことを言うとすぐに考えこむ。わたしを傷つけないように気をつかっているらしいが、大きなお世話だった。浪人したのはわたしに受かろうという気がなかったからで、いまの勉強態度を見ていれば分かりそうなことだと思う。
わたしは、あきもせず天井を見ている。貴之が見ている天井だと思う。今日も早起きして朝からはたらいていたのに、不思議なほど目がさえていた。
「今年は、受かるよ」
貴之はそう言って、フライパンを火にかけた。油のはねる音がおさまるのを待って、わたしはキッチンに目をやる。
「さあ」
「自信ないの」
「もういいよ、そんなこと」
強く言ったつもりもなかった。それでも、貴之はきっとあやまるだろうと思う。これ以上、貴之から話しかけてくる心配はなかった。料理の手をとめて、わたしのとなりに来るまでのまっ白な時間に、いろんなことを考えつくしてしまおうとしていた。
わたしは魚になって、眠ったようにただよっている。そこは水槽のなかで、わたしの記憶で、でも、わたしはこんな場所を知らない。わたしのまわりの黄色くにごった空間はとてもつめたい。目を閉じて、過ぎ去っていくのを待っていることしかできない。かたちのあるものは、結局つかまえられない。わたしは、胎児のような姿になって、寝たふりをしているわたしを見つける。
「膝、どうしたの」
貴之がいた。とっさに、わたしは言い訳を探している。どうして、わたしは認めることができないのだろう。貴之のことばにたよりきって、わたしはなにもかも膝のあざのせいにしてしまう。
「ころんだ」
「いつ」
「分かんない。この前飲んだときだと思う」
「痛そう。紫になってる」
貴之は親指をあざに押しつけた。別に痛くはなかった。うすくなった皮膚をつきぬけて、貴之はわたしのなかに入ってこようとしている。わたしはそれを、こばんだりはしない。
「ごはんは」
「いま煮こんでる」
「なにつくってるの」
「え、カレーだよ」
「なんだ」
「ふつうのカレーじゃない。まあ食ってみろよ」
親指がわたしの膝からはなれていった。貴之がおしたせいか、少しあざが広がったような気がした。
分かっていた。貴之はわたしの肩に腕をまわす。そんな気がしていた。たおされる前に、わたしからあおむけにベッドに寝転んだ。
「やだ」
わたしは、両手で貴之の口をふさいだ。貴之は荒っぽく振りほどいたが、気のぬけたような顔をして、じっと見下ろすだけだった。
「なんで」
「好きじゃない」
「おれが」
「そういうのが」
「別に、おれ」
「つかれちゃった、もう。歩きつかれた」
「歩きたいって言ったのはおまえだろ」
「そうだね。あの夜は歩けたんだ。わたしの家から、駅まで。けっこう遠かったね」
「遠いね」
「うん」
ゆっくりと貴之は体を横たえた。
「だめだ」
と貴之は笑いまじりに言った。そんな貴之を、はじめてわたしはいとおしいもののように感じている。貴之はわたしの手を探しあて、強くにぎった。わたしも貴之の手をにぎり返した。痛いくらいに、力をこめた。
「いつも怒ったような顔してる」
「また言われた。そうなんだ。わたしは、怒った顔してるらしいね」
「怒ってはないのか」
「怒ってないよ。自分ではどんな顔してるか、よく分からないけど」
「本当に」
「本当に」
「泊まっていくか。今日は、ここで」
「いい。帰る。カレー食べたら帰る。明日こそ予備校に行く」
「じゃあ明日は」
「水族館は行かない。ひとりでがんばって」
「そうする」
「いつまでやってるの」
「終わらないよ。開店するまでずっと。行ってみれば、なにかやることは残ってるもんだ」
ふとんから、ひなたのにおいがする。風が吹いている。窓は閉めているはずだと思う。カーテンが舞いあがる。わたしは、光の粒つぶに沈んでいくような気がする。いまここにいるわたしが、たしかに存在しているということを思いながら、しかしそれは、たとえば同時にどこかにいるかもしれない、もうひとりのわたしを否定することにはならない、というようなことをぼんやりめぐらせている。わたしは、ひまわりのある風景に、いつでも最後には帰っていかなければならない。
貴之をゆさぶって起こし、たこ焼きが食べたい、かき氷が食べたいとねだる。祭りにでも行きたいのか、と貴之がめんどくさそうに言う。
「そう、行きたい」
「いつだろう。そのうち、どっかであると思うよ」
まだ間に合うと、わたしは信じたかったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
