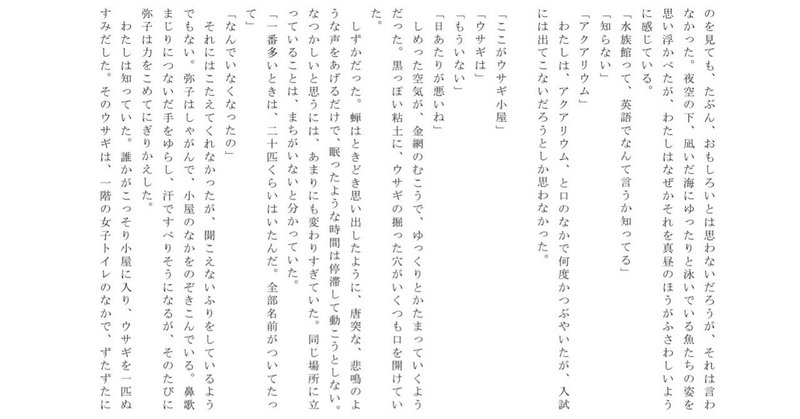
水族館物語(2)
「ここがウサギ小屋」
「ウサギは」
「もういない」
「日あたりが悪いね」
しめった空気が、金網のむこうで、ゆっくりとかたまっていくようだった。黒っぽい粘土に、ウサギの掘った穴がいくつも口を開けていた。
しずかだった。蝉はときどき思い出したように、唐突な、悲鳴のような声をあげるだけで、眠ったような時間は停滞して動こうとしない。なつかしいと思うには、あまりにも変わりすぎていた。同じ場所に立っていることは、まちがいないと分かっていた。
「一番多いときは、二十匹くらいはいたんだ。全部名前がついてたって」
「なんでいなくなったの」
それにはこたえてくれなかったが、聞こえないふりをしているようでもない。弥子はしゃがんで、小屋のなかをのぞきこんでいる。鼻歌まじりにつないだ手をゆらし、汗ですべりそうになるが、そのたびに弥子は力をこめてにぎりかえした。
わたしは知っていた。誰かがこっそり小屋に入り、ウサギを一匹ぬすみだした。そのウサギは、一階の女子トイレのなかで、ずたずたに引き裂かれて死んでいた。やはり、夏休みのことだった。新学期がはじまって、やっとウサギの死体は見つけられた。鍵はこわされていなかった。いま思えば犯人は学校のなかの誰かにちがいないのだが、そんなことを言いだしたりする人間はいなかった。わたしは、ただ、かなしかった。
わたしは弥子の手を引いて、立ちあがらせようとした。いつのまにか弥子は暗いウサギの穴から目をそらし、奥の壁板を見上げているようだった。板と板の隙間に、七月の日の光が、金の糸を織ったように輝いていた。松の葉をすかして、かすかに緑色をしているようだった。風はなかった。
「そのうち、ウサギがまた来るのかな」
「どうして」
「まだこわさずに、そのままにしてあるから。弥子はウサギが好き」
「好き。たぶん」
「ウサギ以外だったら、なにがいい」
弥子は膝をのばし、わたしの顔をじっと見つめた。弥子の目は茶色がかっていて、日陰ではさらにあざやかで、ほとんどオレンジ色に近いくらいに濃くなる。弥子はどんなふうにこの世界を見ているのだろうと思った。
「次は、あっち」
「うん」
わたしは、どこまででもついていこうと決めていた。わたしの学校に、わたしの知らない場所はないはずだった。わたしと弥子はフェンスにそって、物置のある角をまがった。校舎の裏をこのまま行けば、山のほうに入っていく。
「暑いね」
「うん」
「なんでこんなに暑いんだろう」
「知らない。夏だから」
「最近、雨ふらないね。水不足らしいよ、全国的に」
わたしの声が、わたしの頭の上からふりそそぐぐように、遠くから聞こえた。なにもかもが、たよりなかった。一歩踏みだすごとに、わたしの存在は希薄になっていく。七月の空気は、なにもかもをそのなかに溶かしこんでいた。あまいにおいが、胸のなかから広がっていく。涙がこぼれるくらいに、それは痛くて、心地よい瞬間だった。
ひまわりが咲いていた。いつか、わたしは弥子とはぐれ、小さな空のまっ白な雲を見上げている。わたしは急に力がぬけて、尻もちをつくように地べたにすわりこむ。空はかくれた。でも、ひまわりが咲いている。大きく息を吸った。あまいにおいがした。目を閉じれば、すぐに眠ることができそうだった。ぼとり、ぼとり、と重くにぶい音が近づいてくる。わたしはそれを足音のように思った。やがてわたしの上を通過し、それでもしばらくは去っていこうとはせず、わたしのまわりをぐるぐるまわっているようだった。わたしは膝をかかえて、それが遠くへ行ってしまうまでじっとしているつもりだった。こわいわけではなかった。それをずっと待っていたようにも思った。見てはならない気がした。わたしは両手で目をおさえた。
「ここは、焼却炉があったとこ。いまはもうない。草もはえずに、ずっと四角い空地になってるんだよ」
「つかわれなくなっても、しばらくそのまま置いてあった。針金で開かないようにしてあったけど、いつのまにかとれてて、なかに入って遊んでた。わたしもかくれんぼとかでよく入った」
弥子には、わたしがこの学校の卒業生だとは言っていなかった。弥子の知らないことまですらすらと話すわたしを、弥子はくやしげににらんでいたが、不思議そうではなかった。細い指で、そっと髪をかきあげ、あらわになった耳が朝顔のようにぽつりとそこに咲いていた。うすい耳の肉は透明な光をあびて、血管まですけてみえた。風が吹きはじめていた。しずかにそよぐ髪の一本一本が、かがやきながら空気に溶けて見えなくなる。弥子が消えていく。わたしは急にたばこが吸いたくなる。
「もういいよ」
頭の上から、かくれんぼの鬼を呼ぶ子供のように、奈津実が声をふらせてくる。わたしは目を細め、三階の窓からわたしを見下ろす奈津実を見つけた。弥子が、わたしの服を引く。わたしは奈津実に目をむけたまま、弥子の手をにぎった。
「あがってきて」
「分かった」
「なにしてた」
「ひさしぶりの母校を探検してた」
「誰、その子」
「友達。そこで会った」
一番近い一年生の教室から、なかに入った。奈津実と先生もそこから入ったらしく、開けっぱなしだった。肌色のシートをはりつけた廊下が、目に痛く、素足にはりつく感覚が不快だった。
弥子ともつれ合いながら、げた箱の横にある階段までたどりついた。踊り場から差しこむぼんやりした光を背負い、奈津実はゆっくりとおりてきた。
「どう」
「なにが」
奈津実は影のように立ちつくし、くっきりとした輪郭を光にさらしていた。うつろな、子犬のような目だけが、いまにも泣きだしそうそうなくらいに、たよりなかった。
「本当に、ここをつかうの」
「もうちょっと考える」
「とりあえず、今日はもういいの」
「もういい。帰ろう」
「先生は」
「上」
弥子がいなくなっていた。振り返ると、肌色の廊下が、ひっそりと足もとから永遠のようにのびている。ぼとりとにぶい音がする。わたしはふいに、言いようのない幸福を感じた。実体のある過去が、その瞬間、わたしとひとつになっていた。視界のすみで、奈津実が手を振っていた。指先の濃いマニキュアが、目の先でちらちらした。花びらの舞い散るように、迷いなくポケットにおさまり、奈津実は背中をまるめて、階段に足を踏みだした。
「何年前」
「えっ」
「卒業したのって、何年前になるの」
「七年前だと思う」
「そうか。そうだね」
「どうして」
「なにかかわった」
「なにも。たぶん」
なにも、ともう一度わたしは言った。ニスでつやつやした木の手すりにふれる。たしかめるように、わたしは手のひらをすべらせていた。
「ひさしぶり」
わたしと奈津実をむかえた先生は、教卓に手をついて校庭をながめていた。
「いつ帰った」
「七月くらい。こっちのほうがまだ予備校には近いから」
「びっくりした。卒業したあと連絡してくれる子なんてなかなかいないし。別人みたい。もう大学受験か」
「落ちましたけど」
先生は少し考えたが、うまいことを思いつかなかったのか、笑ってごまかし、教壇から降りた。わたしのそばで机に腰かけ、上目づかいでわたしの顔をのぞきこんだ。膝に置いた左手の薬指に、包帯が巻かれていた。
「どうかしたんですか。手」
「別に」
「痛いですか」
「もうすぐ包帯もとれる。だいじょうぶ」
「そうですか」
ぽた、ぽた。わたしはふせた目を窓にむけ、雨のにおいを探した。足の先に、こつりとなにかがあたった。ビー玉だった。空のように、青く、透明だった。次のひとつは、赤かった。やはりわたしは空を思った。夕焼けの空を思った。深い緑は、明けがたの空だった。ぽたぽた落ちてくるのは、雨の音ではなかった。
奈津実が首をかしげ、教室のまんなかに立っていた。小さな箱をさかさに持ちあげ、自分のせいではないと言い訳するように、わたしたちと見くらべる。そこから流れ落ちたビー玉は足もとにたまって、ゆっくりとわたしのほうへ転がってきた。
わたしはあわててしゃがみこみ、ひとつひとつ、つまみあげ、手のひらに乗せていく。ビー玉のなかのわたしと、わたしは、そのたびに目が合う。ビー玉は、電線がうなるような低い声をたてながら、ゆっくりとわたしを、かこんでいた。しばらく、先生も、奈津実も、わたしが拾うのをぼんやりながめているだけだった。わたしの手は、すべてのビー玉をのせるには少し小さすぎて、つまみあげるそばからこぼれていく。ひとつも割れないことが、なにかおそろしいことのように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
