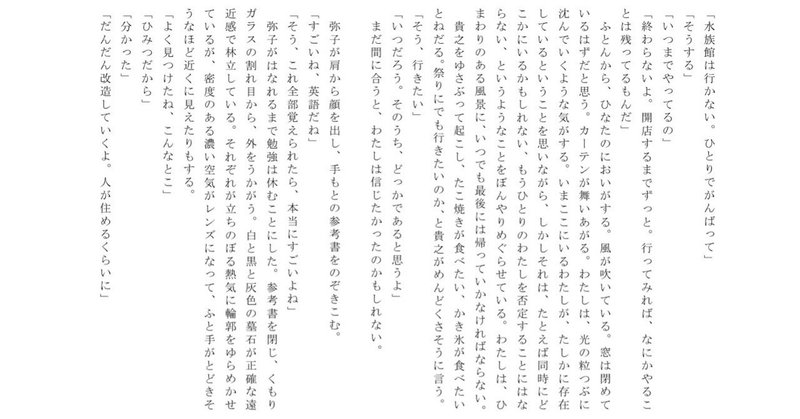
水族館物語(6)
弥子が肩から顔を出し、手もとの参考書をのぞきこむ。
「すごいね、英語だね」
「そう、これ全部覚えられたら、本当にすごいよね」
弥子がはなれるまで勉強は休むことにした。参考書を閉じ、くもりガラスの割れ目から、外をうかがう。白と黒と灰色の墓石が正確な遠近感で林立している。それぞれが立ちのぼる熱気に輪郭をゆらめかせているが、密度のある濃い空気がレンズになって、ふと手がとどきそうなほど近くに見えたりもする。
「よく見つけたね、こんなとこ」
「ひみつだから」
「分かった」
「だんだん改造していくよ。人が住めるくらいに」
「いいね」
さびた釘や、かなづちが、むきだしの黒い土にころがっている。なんのための小屋なのか分からない。まわりの板もなにもかも腐っているらしく、しめったにおいがこもっている。
ランドセルや教科書、勉強道具が、ベニヤ板に置かれていた。ブロックで高さをつけ、机にしているらしかった。おとぎ話のパンくずのように、ときどき目につく小さなおかしのつつみまで、なにかの意図でちらかしているように思える。
「もう、家にはごはん食べに帰ってるだけ」
「じゃあ、ここで寝てるの」
「そうだよ」
「蚊が多そう」
「そう、かゆくて、よく夜中に起きる」
昼間から暗く、こんなところで本を読んでいたら、目が悪くなるだろうと思う。トイレは、と聞きかけたがやめた。
「こわくないの」
こわくない、と得意げに言うだろうと予想していたが、弥子はわたしの髪をかきまわすばかりで、強がってはくれなかった。
「髪、暑苦しくないの」
「別に」
「切ってあげようか」
「弥子は髪を切れるの」
「切れるよ。自分で切ってる」
「すごいね」
そう言ったのを弥子は切ってほしいという意味だと受けとめ、ランドセルのなかからはさみをとりだす。あきらかに紙を切るための、工作用のはさみだが、どこまで弥子が本気なのか分からない。
前髪を人さし指と中指でつまみ、弥子はしきりになにかうなっていたが、急にはさみを入れられた。声をあげるひまもなかった。
「あ、本当に切ったな」
「切るよ」
「まだやるの」
「そうだよ」
「だいじょうぶなの」
「だいじょうぶだよ。自分の髪切るよりかんたんだもん」
わたしは弥子の髪を指先でなであげ、引っぱったりしたあと、わたしの前でひとまわりさせてみて、たしかにこれだけ自分でできるのならたいしたものだと素直に認めてやる。
「嘘だ。お母さんが切ったんでしょ」
「ちがう。自分でやった」
「信じていいの」
「いいよ」
わたしは、参考書の表紙に落ちた前髪に目を落とす。わたしの髪の毛はかたく、針のようにぴんとしたまま、かさなり合っている。一週間も洗っていない髪だと思うと、大事にしてやることもないような気がしてくる。
弥子はもうわたしの後ろにまわって、はさみをしつこく鳴らしている。髪を片手にわしづかみすると、わたしの覚悟する余裕もなくばっさりやられてしまった。頭がかるくなって、首すじがひんやりするのをはっきりと感じた。ここまでされれば、かえって気持ちがいいくらいだった。
「けっこう切るね」
「だって暑いでしょ」
「うん」
「いまはおおざっぱに切ってるだけだから、あとでもっとちゃんとととのえるよ。いいでしょ」
「わたしも自分で切るんだよね」
「そうなんだ」
「前髪がうっとうしくなったら、ちょっとずつ切りそろえる。そういえばもう一年くらい髪なんて切ってもらったことがない」
「へえ、じゃあ、みんなおどろくね」
「たぶん、わたしが一番おどろくと思う」
「どれくらいにしようか」
「弥子くらいがちょうどいいんじゃない」
「じゃあ、わたしよりちょっとみじかくしよう」
「なにそれ」
襟から髪の毛が背中に入りこむ。汗にからんだ一本一本が肌に刺さる。弥子はかまわず切りつづけているが、きっとなにも考えていなかった。右耳の近くで、また大きな束が刈りとられた。もうここまで来てやめさせることもできず、わたしはせいぜいいまから心の準備をしておくしかなかった。
弥子が後ろから頭を押す。足もとにはわたしの髪がうずたかく、影のようにわたしをかこんでいた。
はさみがまた前髪にかかり、わたしは目を閉じる。墓地の隅で弥子に遊ばれているということをあらためて思うと、急に馬鹿馬鹿しい気持ちになる。一瞬からっぽになった頭の、その真空状態に、ふと死体の髪の毛を集める老婆の話が浮かんでくる。高二の現国でやったこと、芥川竜之介が書いたことはすぐに思い出せたが、題名が分からない。
「どうなってる」
「まだ。待って」
弥子は真剣そのもので、わたしのほうが怒られてしまったかのようだった。はさみの音だけが頭のまわりをまわっている。まぶたを、かたくにぎりしめ、わたしは、耳を通過するたびに切られなくてよかったと安心しなければならない。なにも見えず、蝉の声さえさえぎり、わたしの感覚はばらばらにされ、それでも死なずに、分裂したままの刺激を送りつづける。
ここはどこだろう。立ちならぶのは墓石だろうか、ひまわりだろうか、山積みにされた本のようでもある。指をそらせた手のひらにも見える。もやもやした白いものが、ふってくる。わたしは、それをたばこの煙のように思った。次には入道雲のような気がした。入道雲は、足もとに送電線と鉄塔を連れている。鉄塔は川のむこうにあった。それをながめているわたしは、土手に立っているにちがいない。こんなにも満ち足りた孤独を味わったことがない。
「弥子」
「うん」
「まだ」
「まだ」
わたしに弥子の声はとどかない。わたしの声は、割れた窓からしみこむ蝉の声ほどにも響くことはなかった。わたしの髪を黙々と切り落とす弥子がなにを考えながらはさみを動かしているのか、想像もつかないということが、なぜかわたしの心をなぐさめる。
「髪、切ってるね」
「切ってるよ」
「イメージは、どんな」
「みじかく。さっぱり」
「もてるかな」
「さあ」
「髪、切ってるね、本当に」
「うん」
「女の子が髪を切るって、どういうことか分かるか、弥子」
「なに」
「好きな男子にふられるとか、だから、失恋とか、なんかそういうすごい事件が起こって、よし、やるぞ、って、決心するとき」
「へえ」
「なのかな。分かんない」
決心しなきゃいけないんだ。なにかを。髪を切る。切るってことは、切断ってことで、断ち切る、ここから先はだめだって、区切ること、否定すること。とにかく、わたしの髪は切られる。切ったあとは、ごみだから、燃やされる。燃やされたら、死んで、埋めてやらなきゃいけない。墓はすぐそこだ。燃やすには、外に出しておけば、こげて、ビニールみたいに溶けながらオレンジの火をふいて、そのまま消えてなくなってくれないだろうか。夏の空気といっしょになって、道路にころがっている蝉の死体のように、雨がふったら洗い流してくれる。流れたら、海に行って、すずしい。でも、雲になって、雨になるのはいやだから、わたしは、魚たちの口のなかを通りぬけて遊んでいる。
ひんやりした、そのつめたさだ。
「弥子」
耳の上を切っている弥子の顔は、いま、一番近くなっていて、息がかかる。わたしは、思わず、弥子の髪にふれようとした。
「あ、あ。あぶない。動かないでよ」
「弥子の髪、さらさら。細い、ちょっと茶色いね。いいにおいがする」
指のあいだに、からみつけて、弥子がはなれられないように、でも、痛くないように、ひとつかみの髪をにぎりしめる。弥子のほうから、じりじり近づいてくる。はさみを持つ右手は、けがしないように、どんどん遠ざける。足もとで、ささくれたベニヤが、がざがざ、荒れた肌みたいな感触の音がして、弥子の頬が、わたしに、くっつく。肩にあごを乗せて、左のちいさな胸をおしつぶして、体をささえている。弥子、あったかい。牛乳みたいな子供のにおい。いいな。
「弥子」
気持ち悪いくらいの猫なで声が出て、弥子もびっくりしただろうけど、わたしだってびっくりした。大きなパンくらいの弥子を、脇の下で持ちあげて、でも、アメかなんかをひと口で食べるみたいに、弥子にキスした。やわらかい。髪の先が、鼻にあたって、ちくちくくすぐったい。
はさみが落ちた。からん、と、かるい音がした。こんなものでは、なにも切れないと思った。切ってたのか。切ってたのか。わたしの髪はもろくて、たよりなくて、かんたんに切れて、こんななさけない格好で、まとめて、山にされて、それはとてもくやしいことだ。
「なにすんの」
「弥子、おいしそうだったから」
「おいしくないよ」
「おいしいよ。本当に、食べちゃいたいくらい」
「気持ち悪い。やめろ」
「うん」
でも、もう一回やった。舌を入れてやろうかと思ったけど、口唇がぬれていてそれを味わえば十分という気がした、かき氷がとけたあとの水のような、つめたさと、ほんのりあまい感じ。すごくいいな、と、思った。
「弥子」
「なに」
「この前の模試、D判定でした。へこむわ」
「なにそれ」
「大学落ちるかも」
「いいじゃん、行かなきゃ」
「行かなきゃ、か。なるほどね。行かなきゃいいんだよね。でもねえ」
気持ちいい。
「弥子」
「なに」
「好きな男子、いないか」
「いない」
「そうか」
「なに」
「なんでもない。好きな男子いないなら、この話は、これでおしまい」
泣けてた。なまぬるい。気持ち悪い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
