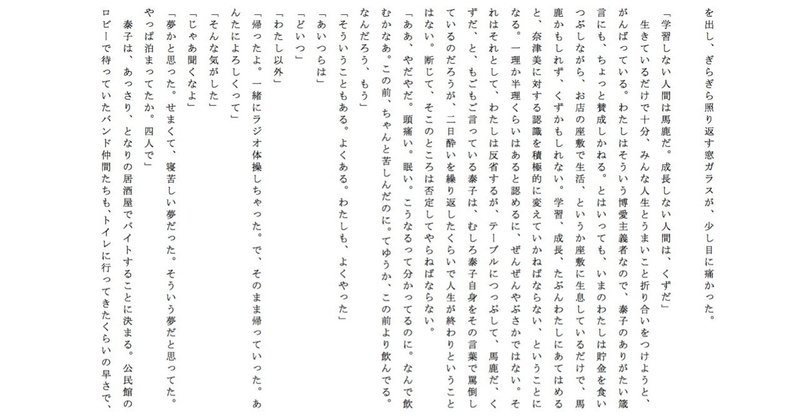
落下傘ノスタルヂア(10)
「学習しない人間は馬鹿だ。成長しない人間は、くずだ」
生きているだけで十分、みんな人生とうまいこと折り合いをつけようと、がんばっている。わたしはそういう博愛主義者なので、泰子のありがたい箴言にも、ちょっと賛成しかねる。とはいっても、いまのわたしは貯金を食いつぶしながら、お店の座敷で生活、というか座敷に生息しているだけで、馬鹿かもしれず、くずかもしれない。学習、成長、たぶんわたしにあてはめると、奈津美に対する認識を積極的に変えていかねばならない、ということになる。一理か半理くらいはあると認めるに、ぜんぜんやぶさかではない。それはそれとして、わたしは反省するが、テーブルにつっぷして、馬鹿だ、くずだ、と、もごもご言っている泰子は、むしろ泰子自身をその言葉で罵倒しているのだろうが、二日酔いを繰り返したくらいで人生が終わりということはない。断じて、そこのところは否定してやらねばならない。
「ああ、やだやだ。頭痛い。眠い。こうなるって分かってるのに。なんで飲むかなあ。この前、ちゃんと苦しんだのに。てゆうか、この前より飲んでる。なんだろう、もう」
「そういうこともある。よくある。わたしも、よくやった」
「あいつらは」
「どいつ」
「わたし以外」
「帰ったよ。一緒にラジオ体操しちゃった。で、そのまま帰っていった。あんたによろしくって」
「そんな気がした」
「じゃあ聞くなよ」
「夢かと思った。せまくて、寝苦しい夢だった。そういう夢だと思ってた。やっぱ泊まってたか。四人で」
泰子は、あっさり、となりの居酒屋でバイトすることに決まる。公民館のロビーで待っていたバンド仲間たちも、トイレに行ってきたくらいの早さで、店長と泰子が喫煙コーナーからもどってきたのに、おどろいていた。みんな、夕ごはんをどこで食べようかと相談していたところだったので、せっかくだから店長のお店で飲んでいくことにした。歓迎会もかねて、ということで、店長も賛成し、安くしておくなどと言ってはりきった。
わたしは、みんながそんな相談をしているなか、最近は公民館にスタジオがあるのか、などと、さもめずらしそうなふりをして機材の表をにらんでいた。落ち着かなかった。なにしろ、泰子のバンド仲間たちは、こわかった。わたしは、お店に着くまではぴったり泰子にくっついて、たぶんひと言もしゃべらなかった。ドラムの女の子。右耳にみっつ、左耳には数え切れないほどの、ピアスがじゃらじゃらぶらさがっている。口唇にも右端に太いのが貫通しているが、それが見ていても一番痛そうで、口のあたりがなんだかむずむずした。ギターの男の子。坊主頭で、ちょっとハーフっぽい顔立ちをしている。ランニングシャツを着ているのは、タイヤのように盛り上がった筋肉を見せびらかしたいからかもしれない。GIにしか見えなかった。ベースの男の子。長髪で、長袖のTシャツで、外見はこのなかでは一番まともそうだったが、常になにか口のなかでぶつぶつ言っているのが、また別の意味でこわかった。なぜかわたしも飲み会に加わっていて、二時間くらい様子を見守ったあと、ようやく、みんなただの人見知りで、むずかしい顔をしていたのも、威嚇行為というわけではなかったのだと分かる。
「ネットで知り合ったんだっけ」
「いや、もっとアナログです。スタジオの、はり紙でボーカル募集していたので、それで」
「わたしもバンドやってたことあるよ、ボーカル」
「聞きましたよ」
「あっそう」
「もしかして、お姉ちゃんと」
「そうそう。あいつはギターでした。へただったね。CDなんかつくってたけど、あれはまだ残ってんのかな」
「いいなあ。CD、つくりたい」
「簡単だよ。わたしにもできたもん。まあ、いい思い出だよね」
「思い出か。そんなつもりでもないですが」
「なに、けっこう本気なんだ。思い出じゃなくて、もっと、メジャーデビューとかねらう感じの」
まさに息絶えようとしている人のように、泰子はしぼんでいった。細く息を吐いて、長くしゃべりすぎた体を休ませている。なにか考えているようでもある。
わたしは足をぶらぶらさせて、待つともなく待っている。あいかわらず、外では子供たちが遊んでいる。缶けりか、鬼ごっこでもしている。蝉は馬鹿みたいに元気だった。わたしが寝ていて気づかなかった日も、同じように、あきもせず、こんな朝が何度も来ていたのだ。七月二十日から数えて、もう一週間以上たっている。一週間も同じことをやっていれば、永遠に続くのとかわらない気がする。馬鹿みたいに、晴れが続く。毎日、どこかで最高気温を更新している。晴れ女だと昔から言われてきたが、まだこっちに来てから一回も雨が降ったことがないのと、関係があるのか、どうか。このままだと水不足になるかもしれない、というやや深刻なうわさも聞き、そろそろ潮どきか、と東京に帰りたくなることもある。未練はない。でも、ここをはなれる理由も、いまのところない。いまのところ、ないことになっている。
「分かんない」
テーブルの上で長くなり、抜けていく空気と一緒に、泰子は吐き捨てるように言う。考えた結論がそれかよ、とわたしは泰子をたたく。つっこみのつもりで、ダメージをあたえるつもりはなかったが、いまの泰子には、それさえ致命傷に近かった。頭が、頭が、とのたうちまわる。たたいたのは、肩だった。わたしは、笑いをこらえていた。
「ごめんごめん」
「まあいいです。わたしが悪いんだ。わたしが悪いんだ」
「またそういうことを言う。でも、バンドやっていくなら、けっこうこういう世界だよ。打ち上げとかやるでしょ。必要があれば接待もするだろうし」
「そっか。じゃあ、やめた。次のライブで、終わり」
「そんな」
「わたし、歌へただし」
「いい声してると思うけどな。いや、お世辞じゃなくて」
手も細くてきれいだし、などと言って泰子の左手を持ち上げ、
「ギターやってもいいんじゃないの」
と無責任なことをすすめる。クモがギターのネックを這いまわるイメージは、美しいというよりは、ひょっとするとグロテスクかもしれない。おもちゃのように軽く、ゆするとからから音がしそうだった。それが、バイバイ、とわたしに手を振るようで、ちょっとさみしくなる。これはちがうな、とこぶしを握らせ、ぐっと突き上げる。泰子は、されるがままにしている。
人さし指と中指をつまんで、のばして、ピースをつくってやる。
「夢をつかめ。な。うじうじするな」
「別に夢じゃないです、バンドは。ちょっとやってみたかっただけ」
「ああ、そうなの」
「やってみれたから、もういいです。熊本にいたときから、ためしてみたかった」
わたしは、熊本からバンドをやりに出てきたのだと信じこんでいて、がんばって夢をつかんでほしいものだと、ひそかに祈ってやっていた。浪人生である事実と、わたしのなかでは矛盾しないのだった。というのも、わたしが昔やっていたという、例のバンドで、五人中、奈津美をふくめて四人までが熊本出身者だった。まったくの偶然だった。遅刻、暴力、協調性の欠如、未熟なテクニックなどを理由に、二週間でわたしと奈津美は自主的に脱退させられたが、テクニックの責任はわたしが引き受けるにしても、あとはすべて奈津美だと思う。残留した三人で、メジャーデビューしたとかしないとか、そんなうわさを聞いたことがある。奈津美は例外だが、熊本の人は、みんな、けっこう熱い感じで、音楽やりに上京してくるのだというふうに、わたしは熊本人の県民性を覚えこんでしまっていたのだ。そうじゃない人も当然いる、と、すぐ、この場で熊本に関する情報欄を書きかえる。
「じゃあ、バンドじゃなくていいよ、じゃあ。なら、バイトがんばりなさい」
「がんばれないです」
「なんで。せっかく採用してもらったのに。それは失礼だよ。言いつけるぞ。酒飲むと気が弱くなるんだから」
「だって、八月で終わりじゃないですか」
「なにが」
「お店が」
「は。誰の」
「知らないんですか」
となりの居酒屋は店をたたむのだ、という。意味がよく分からなかったが、こんな状態で嘘をつく余裕があるとも思えず、とにかく本当のことらしいと、ひとまず仮定してみる。なるほど、公民館までの道のりでは一切そんなことに触れなかったが、しかし、あの人のことだから、強がりだというのもありそうなことだった。どちらかと言えば、短いあいだしかやとえないけど、それでいいなら、という店長側の条件を飲むかたちで、泰子は採用されたのだという。あの喫煙コーナーでそんなドラマがあったとは、まったく知らなかった。
そう思えば、ピアス、筋肉、長髪と飲んでいたあの時間も、一期一会という感じがしてくる。ピアスがボイスパーカッションのまねをして、筋肉が飾りの三味線をてきとうに弾き、長髪は幻術のような手踊りをしていた。そして、わたしは、沖縄民謡風にアニメソングを熱唱していた。苦情なんてなくて、店長も一緒になって騒いでいた気がする。客はいなかったようだ。つぶれるはずだ、といまさらしみじみする。いらないものはあそこに持っていこうと、さっそくブロック六個を寄付し、とてもよろこんでもらえた。これからもごみ捨て場のように利用しようと考えていたが、そんなこともできなくなる。新聞の勧誘でプーさんのぬいぐるみをもらったと話したら、くれと言っていたが、あの約束はまだ生きているのだろうか。いい思い出だ、と落ちをつけかけて、いまから思い出にされてはたまらないだろうと、打ち消す。なんとなく、そういうまとめかたが、くせになっているらしい。まさか、思い出づくりのためにお店をはじめたわけでもないだろう。未来に目をむけていなければ、なにもかも無意味だ。
無意味だ、と、もう一度、お腹の下までゆっくりと落とす。われながら、力なかった。
思い出づくりのためでなく、本気で日本一を狙うわけでもなく、なんとも知れない動機でやっていかなければならない。そんなのも、あったっていいと思う。あんなこといいな、できたらいいな、でやっている。みんな、そうだ。あんな夢、こんな夢、いっぱいあるのに、猫型ロボットがいないせいで、空を自由に飛べない。誰も悪くない、悪いのは、あいつだ、と博愛主義者のわたしはせちがらいこの時代を代表して、怒る。と見せかけて、実は、わたしの健康ジュースを言いわけしているだけなのかもしれない。ひきょうだ。つくづく。
「ここは田舎なのに」
「うん」
「星は見えないんだな」
「うん」
「中途はんぱ」
「うん。そうだね」
またわけの分からないことを、泰子が言う。でもきっとあとでなにか関係があるのだろうと、あいづちをはさみながら、聞いていた。うん、とはじめに大きくうなずきすぎたのか、足の小指でもひっかけたように、頭のなかでおもちゃ箱をぶちまけてしまう。ひとつひとつ、拾い集めようと、手にとるそれらは、昨日の居酒屋で見たものたちだった。片づけるのを待っていてくれたかのように、泰子は、ゆっくりと話しだす。
「熊本の星は、すごいですよ。熊本というか、わたしの実家、山のなかですからね。空に近いほど、きれいなんですよね、きっと。町も暗くて、月の光って明るいんだ、って分かりますよ。そんな、田舎」
「ふうん」
池袋サンシャインのプラネタリウムより、もっときれいだろうか、どうだろうか。考えても分かはずのない問題なのに、わたしはひたすら考えた。おもちゃ箱の中味が、星座のように、夜空へのぼっていく。
三味線。ローリングストーンズ。バス停。
「でも、そんなことをあらためて、というか、はじめて認識したのは、今年のセンター前です。もう、受験勉強でノイローゼみたいになってて。はじめて教科書開いたのは、三年の夏でしたね。理系の教科なんか、基本的なルールさえ理解していなくて。マイナスとマイナスをかけるとプラスになる、って知って感動したくらいです。勉強がきらいなわけじゃなくて、そうやってひとつひとつ知識がついていくのを、どこかでたのしんでさえいたところもありました」
大漁旗。マネキン。人体模型。世界地図。カエル。
「でも、いくら勉強しても、問題はいつも少しだけわたしのレベルより上で、なかなかはっきりした手ごたえがないのが、ぼんやりしたストレスになって。たまっていたんでしょうね、ストレス。過去問に挑戦したとき、決定的な無力感におそわれました。とても最後まで行けずに、問題集を放り投げました。机につっぷして、少しのあいだ、目を閉じました。まっ暗になりました。それだけでした」
モナリザ。鉄球。くさり鎌。木馬。
「目を開けると、わたしの机と参考書、そのむこうにティッシュの箱がありました。それも、あたりまえのことですけど。なぜか、それだけのことが新鮮な事実として、からっぽの頭のなかで、こう、あざやかに跳ねまわるわけです。ティッシュの箱を持って、台所に行きました。シンクにティッシュをばらまいて、コンロの火で、燃やしました。ああ、燃えているなあ、と思いました。水道の蛇口をひねりました。水が勢いよく出て、火は消えました。ああ、消えたなあ、と思いました。それだけでした。わたしは、コップに水をくんで、頭からかぶってみました。濡れました」
バンドネオン。ハイヒール。アフロ。蓄音機。
「それだけでした」
ブロックが六個。
魂の抜けそうなため息をつく。死にそうだった。まるで遺言のようだった。がんばれ、と肩をたたきかけたが、その手はひっこめる。
「わたし、悟りを開いたのかもしれない、そのとき。なせばなる、とは少しちがいますけど、とにかくわたしがなにかやれば、なにかは起こる、それはそれだけのことだけど、なにかにはなってる、でも、じっとしてたら、なにも起らない。そんな感じなのかな、言葉にしたら。そのまま、外に出たんですよ。たぶん十二時ごろでした。山のなかを、とりあえず歩きました。なにかしなければならない、っていう、あせりで、どこへ行くのかも分からないのに、ひたすら急いで。それで」
「星がきれいだったわけ」
「そう」
「なるほどね」
「星のひとつひとつ、すべてが、わたしの自由なんですね」
「どういうこと」
「わたしにも、分かんない。でも、宇宙はわたしのものだって、思った。あせってた。なんかしなきゃ、なんかしなきゃ、って、熊本なんかで勉強してる場合じゃないって、思いました」
それほどあまくはなかった、という口調だった。そんな若い、宇宙的な思いあがりなど、わたしには、それこそ思い出の世界にしかもうない。あせってた、という言いかたは、とてもよく分かった。芝居をやり、バンドをやり、ときどき自暴自棄としか思えないような恋愛もした。奈津美のアシスタントで、麻雀劇画なんか描いていた。どこかの雑誌に読み切りで掲載されたらしいが、そういえば確認していない。
「やっちゃん」
「はあ」
「歩くの好きだな、わたしは」
「そうですか」
「景色がかわっていくのが、単純に」
「ああ」
「そういうことかな。じっとしてらんないってこと。わたしもきっとこまるよ、地震が起きたときね。どこに帰ればいいのか、ってね」
わたしは、宇宙のなかのちっぽけな存在にすぎない、という第二の悟りを開き、だんだんつまらない大人になっているらしい。それでも、できたらいいな、で目をつむって、つっぱしっているうちはまだまだ夢があるほうだと思う。裏切られると知っていても、それでも止まらない。よけいに、馬鹿馬鹿しいようでもある。なんだ、と結論のあっけなさに、気が抜ける。わたしは、馬鹿なのか。学習せず、成長しない、馬鹿のくずだった。つまらない大人に落ち着くよりは、ぜんぜんましだと思っているのが、まずい。第三の悟りも、ここがくずれなければ、どうしようもなかった。あんなこといいな、できたらいいな。ドラえもんはいないのに。
「しかし、星は本当にないね」
わざと、なんでもないみたいに、わたしは言う。
「でも、知ってる」
「なにを」
「UFOは飛んでるんだよね。暗い空に、毎日偵察してる」
「へえ」
「信じてないでしょ」
「うん」
ふと目を落とすと、ずっといじっていた泰子の手が、赤くなっている。
「バンド名、いま思いついたから、つけてやるよ」
また話を変える。
筋肉が、まだバンド名がない、と叫んでいた。名づけ親になってください、となぜかわたしを指名する。ピアスも長髪も、同意する。酔っぱらった勢いなどとは解釈せず、わたしは、その権利がまだ自分にあると思っている。
「サイボーグ4、ってどう」
「アメリカンコミックのヒーローか」
「決定ね」
「それ、ドラムの人がサイボーグっぽいからってだけじゃないですか。耳のピアスが。わたしはサイボーグじゃない」
「お、よく分かったね。名前の由来」
「あいつのことをサイボーグっぽいって言ったの、わたしじゃないですか」
「そうだっけ。酔っぱらってて覚えてない」
「ひどいな」
と言い残し、いびきを立てて、泰子は眠りに入った。わたしが片手をピースにしてやったことに気づかず、ずっとピースし続けている。泰子に幸あれ、と願いつつ、おもしろいので携帯で写真をとっておいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
