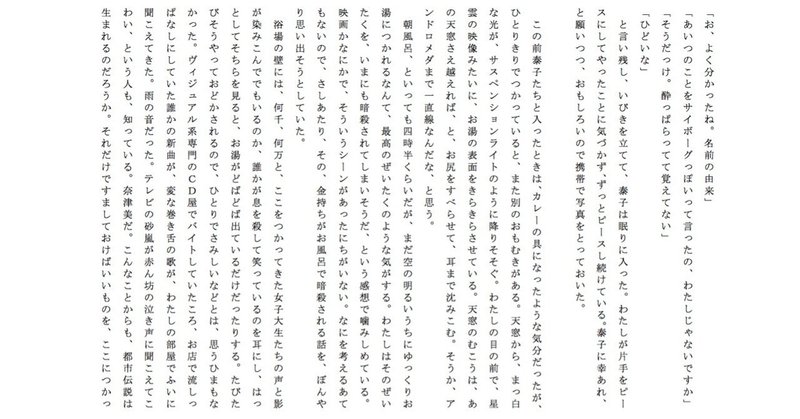
落下傘ノスタルヂア(11)
この前泰子たちと入ったときは、カレーの具になったような気分だったが、ひとりきりでつかっていると、また別のおもむきがある。天窓から、まっ白な光が、サスペンションライトのように降りそそぐ。わたしの目の前で、星雲の映像みたいに、お湯の表面をきらきらさせている。天窓のむこうは、あの天窓さえ越えれば、と、お尻をすべらせて、耳まで沈みこむ。そうか、アンドロメダまで一直線なんだな、と思う。
朝風呂、といっても四時半くらいだが、まだ空の明るいうちにゆっくりお湯につかれるなんて、最高のぜいたくのような気がする。わたしはそのぜいたくを、いまにも暗殺されてしまいそうだ、という感想で噛みしめている。映画かなにかで、そういうシーンがあったにちがいない。なにを考えるあてもないので、さしあたり、その、金持ちがお風呂で暗殺される話を、ぼんやり思い出そうとしていた。
浴場の壁には、何千、何万と、ここをつかってきた女子大生たちの声と影が染みこんででもいるのか、誰かが息を殺して笑っているのを耳にし、はっとしてそちらを見ると、お湯がどばどば出ているだけだったりする。たびたびそうやっておどかされるので、ひとりでさみしいなどとは、思うひまもなかった。ヴィジュアル系専門のCD屋でバイトしていたころ、お店で流しっぱなしにしていた誰かの新曲が、変な巻き舌の歌が、わたしの部屋でふいに聞こえてきた。雨の音だった。テレビの砂嵐が赤ん坊の泣き声に聞こえてこわい、という人も、知っている。奈津美だ。こんなことからも、都市伝説は生まれるのだろうか。それだけですましておけばいいものを、ここにつかったことのある人で、死んだ人も何人かはぜったいにいるだろう、といやな想像をする。お湯の表面をなめるもやもやが、また、妙にそういう雰囲気をかきたてるのだった。
脱衣所で人の気配がする。もう少し貸切気分を味わいたかったが、しかたない。まだ湯気もうすく、入口の四角い枠をすかして、ぼこぼこの百円ロッカーまで、はっきりと見通せた。せいぜい入ってくるときに目を合わせて、気まずい思いをさせてやろうと、待ちかまえた。
「あ、ノリピーじゃない」
山本だった。なぜかわたしは、目をそらす。苗字が酒井というだけで安直につけられたあだ名が、心底恥ずかしい。酔っぱらった勢いの産物は、けっこう生きのびる。
「なにしてんの、ノリピー」
「なにったって、風呂入ってるじゃないですか」
山本は体を洗うのもそこそこに、わたしのとなりへ飛びこむ。はねたお湯が、くるくるの金髪に玉を結び、お湯に照り返す外の光を、さらにやわらかい色に閉じこめる。真珠をまとったビーナス、と半分お世辞で思ってやる。
「そりゃそうだ。なんで、こんな早い時間に風呂に入るかと思って」
「別に。通りかかったら、開いてたから、なんとなく。今日暑いし汗かいたから、まあ、ふらふらとね。図書館行ってた」
「へえ。勉強」
「いや、ひまつぶし。目的もあることはあるけど。『人間失格』を読んでみたくなって」
「ああ、太宰治。なんで」
「最近、人間失格なんじゃないかと思いはじめて」
「ふうん。借りてきたの」
「いや、図書館で一気に読んじゃった。てゆうか、探したけど、大学の図書館、文庫本ってあんまり置いてないもんだね。岩波とか新書とかはあるけどさ。太宰治全集を借りるのも、どうかと思ったから」
「うん、どうかと思うね」
学生でもないのに、付属の図書館に入ったのも、どうかと思う、と、思う。学生証のカードを差しこんで、ゲートを開く方式の入口だった。出口は、こちらも一方通行だったが、しかし、退出するのには認証もなにも必要ない。フリーである。だいたいどこの大学図書館でもこんな感じだろうとたかをくくって来たが、まんまと出口のバーを引っぱって、そこに体をすべりこませる。人目のない真空状態を逃さなければ、そんなにむずかしい仕事ではない。『人間失格』以上に、ひょっとしたら期待していたのかもしれないが、書架にたどり着く前に、その兆候があらわれる。おっ、と腹に手をあて、あまりにも期待どおりなのにちょっとこわくなりつつ、トイレへ駆けこむ。一週間の便秘が、あっさり解消された。わたしはインクと紙のにおいをかぐと、大きいほうをしたくなるという、特異体質だった。排泄行為というより、やったことはないが、出産に近かった。それもかなりの難産の部類に入ると思う。それだけに、産み落としたあとの爽快感は、格別だった。
生まれかわったような気分で、書架の林立するなかを練り歩く。腕を組んで、たまに後ろ手にかえて、にやにやして、ごきげんな足どりで、変な人に見えただろうと思う。特異体質とは無関係に、わたしはあのにおいが好きだ、ということもあった。ところどころ、放置されている蛍光灯のちかちかが、やけに目についた。博士論文のコーナーに迷いこむ。背表紙の金文字が、コガネムシの標本みたいに整列している。博士だぞ、えらいぞ、という感じも目を引き、なんとなく足をとめる。すると、待ちかまえていたように、ちかちかする。ふっと暗くなる。また明るくなる。コガネムシなら、ちょっと身もだえでもした拍子に、反射のかげんがかわったかのよう。わたしが見ていたのは、堂、というその一文字で、なんだかぱっちりした目とまつ毛に見えなくもなく、ちかちかに合わせて、まばたきしているのだった。わたしは、恐れ入って、顔をそむける。論文のタイトルだか、著者の名前だかしらないが、その堂に、勝手に入ってすいません、と心のなかであやまり、『人間失格』をさっさと探すことにした。
「何年かぶりに読みなおしたけど、おもしろい。読んだことある」
「ない。重そうだから」
「重いって、ああ、重量じゃなくてね。ちょっと、全集の十巻が頭にあったから。いや、笑えるよ。前に読んだときと、同じ感想を持ちました。そんなに失格でもないような、気が。人間らしいじゃないか、って」
「はあ。なに、最近、心中したの」
「誰が」
「ノリピーが」
「してないですけど。てゆうか、心中したの、って聞きかたもすごいな。生きてるじゃん」
別に笑わそうと思ったわけでもないが、反応にこまる、というような露骨な沈黙に、わたしもさすがに傷つきそうになる。店長をあまり馬鹿にもできない。ジェネレーションのへだたりが、いまになってわたしと山本の関係をひずませたのではないかと、気が気でない。なぜか、山本の年では干支がなにになるのか、計算をはじめている。取調べでもはじまりそうな不安に、びくびくしている。ため口をききあうような仲になったというのに、いまさらばれるのは、いやだった。それなら、最初から女子大生のふりなんかしなければよかったようなものだが、なぜこういうことになっているのか、いまいち覚えていない。
ただの杞憂にすぎないことを実感するには、それからさらに一分弱の沈黙と、山本のあくびが必要だった。おそろしく神経質になっているのがわれながら変だったが、けっこう山本のことを好きになっているのが原因らしかった。こんなことになるなら、とまた、初対面の謎の自己紹介を悔やむループに入りかける。
「そういう山本は、どうしたの」
汗と湯気でしっとりした髪の毛が、重そうに垂れ下がっている。頭の線が見えてくる。山本は髪を持ち上げ、勢いをつけて、後ろへ全部流す。おでこを出した山本の頭は、どこか野菜っぽい。わたしが見とれていると、山本は、なに、と聞き返す。
「あんたも、こんな時間に風呂に入ってるじゃないか」
「そう。気持ちいいね。最近、急にいそがしくて」
「いそがしいと」
「いや、十時半に間に合わないからさ、今日で三日目か四日目か、お風呂に入ってなくて。ちょっと女の子としてどうかと思ったから。夏場だし。まあ、こうやってひまなときに入っとけば、まちがいないよね」
「ずっとひまだって言ってたのに。なんで、いそがしいの」
「やどかり」
「え」
「やどかり」
なにか、女子大生にとって、共通の知識として知っておかねばならないことらしく、わたしはそれ以上問いつめるのはやめておく。ふうん、としか、言えなかった。まず、やどかりでも飼いはじめたのかと、単純に解釈した。しかし、もうわたしの想像力では限界で、次にはもう、二度聞いたにもかかわらず、自分の耳をうたがう。推理していこうとするほどに、奇妙な言葉で、さっきからCGのようなうろ覚えのやどかりが、頭のなかをぎこちなくうろうろしている。
わたしに謎のようなことを言い残し、本当につかれているのか、山本は後ろのタイルに頭をもたせかけ、正面をじっと見ている。その目は充血している。なのに、うつろだった。
わたしは山本の視線をたどってみるが、話しているうちに蓄積された、うねりながら天井にのぼっていく湯気ばかりで、なにもたのしいものは見えない。白い日差しが、細かい粒に乱反射、一色に塗りつぶす。分厚く、濃く、重く、浴場を埋めつくす。巨人のようにそびえ立ち、はるかかなたの空からわたしを見下ろす、田舎の、新潟の入道雲を、そこに重ねていた。小学二年か三年だった。夏休みの友に、雲がなにかのかたちに見えないでしょうか、という課題があった。わたしにはその意味がよく分からず、雲は雲だ、という意味のことを書いた。わたしは、いま、いくつかのことを、とりとめもなくめぐらせている。智恵子さんのように、東京には空がない、とは、泰子は言わなかったかもしれないが、わたしは実家を出てから、わたしを納得させるような雲らしい雲を見ていない。もしかすると、と思ったが、湯気がやどかりに見えるわけもない。それに、夏休みまっさかりだということを、いまさらのように噛みしめている。頭が三センチくらい伸びたような、変な感じがする。
「思ったより、気持ちよすぎる。お風呂っていいね。温泉とか行きたくなっちゃった」
「いいねえ。免許あったらな。車で行けるね」
「ああ、出たくない。また入りなおしたい」
「だから、なにがいそがしいのさ」
「営業、営業、営業」
「なんの」
「広告とり。お店をまわって、広告料をもらう」
「サークルかなんか」
「やどかり」
ふらっと立ち寄ったわたしに、お風呂の用意はない。扇風機にかじりついて、体がかわくのをじっと待っている。洗面台の前で、山本は長い髪にドライヤーをあてている。かわいたところから順に、髪はくせをとりもどし、ぴんぴん跳ねていく。くるくるになっていく。
「ふうん。佐藤ちゃんも」
「そうそう。別のブロックで、あいつも集金してるんじゃないかな」
「やどかりね」
「そう」
山本は、ドライヤーを切った。
「たのしいの」
「そうでもない」
「じゃあ、やめれば」
「でも、やらなきゃ」
わたしの肩ごしに吹きつける風で、山本の髪がわかめのようにゆれている。まだ、ところどころあきらかにしめっているが、最後にバスタオルでがしがしかきまわし、それでいいことにして、山本は服を着はじめる。汗は完全に引いていて、少し寒いくらいだったが、置いていかれるのはいやなので、わたしも風力を最大にして、強引に髪の毛の湿気を飛ばす。
視界のすみに、目に痛いような蛍光色がちらつき、振り返ると、山本が黄緑色のハッピに袖を通そうとしている。
「なにそれ」
背中に、捨学、と筆文字で麗々しく大書きされている。こちらを向くと、襟の部分には、酒会学部、山本優子、と左右にそれぞれ白く抜かれていた。
「社会学部のメンバーはさ、活動中は、これ着てなきゃいけなくて。めんどくさいよね。比文は、こういうのないんでしょ。なさそうだよね」
「優子っていうんだ。山本優子。けっこう、ふつうの名前だね」
わざと見当はずれの感想ですまし、わたしもさっさと服を着る。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
