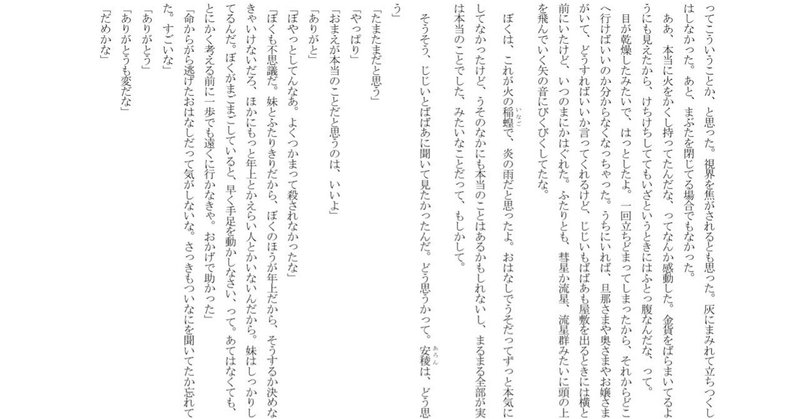
銀匙騎士(すぷーんないと) (31)
「命からがら逃げたおはなしだって気がしないな。さっきもついなにを聞いてたか忘れてた。すごいな」
「ありがとう」
「ありがとうも変だな」
「だめかな」
「だめじゃないけど。おれもこんがらがって帰ってこれなくなること、あるし」
「やさしいな。こんなにちゃんと聞いてくれる人、あんまりいない。お母さんは聞いてくれた。あと、ばばあ。じじいは耳が遠くていちいち、ああん、って聞き返すのがむかつくから」
「おれは、耳がいいぞ」
「うん」
「うーん」
「なに」
「おやじさんは」
「聞かない。口をきいたこともないな。なんとなくはおしえてもらったけど」
「複雑だな。ごめんよ」
「そうでもないよ。簡単だ。お母さんが、奴隷でね。神さまの手がついたんだ。それが、神さまが、ぼくのお父さん」
「手がついたってなんだ」
「なんだろ。知らない。じじいとばばあがよく言ってた。宝石屋さんも言ってた。肉屋さんも、水屋さんも、いつもやさしい」
「よかったな」
「話したことはないけど、なんとなく、いろいろおしえてもらった。神さまみたいなもんなんだ、神さまじゃないけど、ぼくたちよりかしこいし、きれいで、しなやか。井戸を掘ってくれた。けんかしてたら、つまらないからやめろ、って石を投げておしえてくれた。ぼくが生まれたころには、もう神さまはうろうろしてたから、ぼくはふつうのことだと思ってたけどね。
やっぱり、すっとして、ほかの村の人とはちがってたな。よそから来た感じがするもの。ぼくたちはしぼったぞうきんみたいだけど、あの人たちはすっとした棒って感じ。砂は黄色い、草はちょびちょび、青黒い、天幕は灰黄色(べーじゅ)、空も黄緑だと思ってた。水だけが透明だ。ぼくたちの先祖は、砂をつばでこねて草を髪にして、空のかけらを胸に埋めて心臓にした。家は自分たちを入れるものだから、自分たちの肌の色と同じにした。
水はやっぱり、あの人たちのものだと思うよ。地べたに円匙(すこっぷ)をつきさせば、それはまあ、水が出てくるはずだよ。砂から生まれたぼくたちがいけないんだ、水の人だから水を呼べるんだ。
海から来たとか、川からどんぶらこ流れついたとか、あと、雨がたまってかたまって人のかたちになったとか、そんなふうに村に来てくれたらしいけれど、なんか、どれもありそうな気がするよ。海ってなに」
「海は大きな湖」
「湖って」
「大きな池」
「池は大きな水たまり」
「そう」
「そっか。水たまりの何倍もでかいんじゃ、それはすごいな。そんなすごい海を渡ってきたんだから、神さまはえらい」
「何倍どころじゃないよ」
「何倍なの」
「何百倍、何万倍、何億倍だな」
「へえ」
「分かってないな」
「あんまり」
「地べた見ろよ」
「見てるよ」
「ずっとつづいてるだろ」
「はてしない」
「終わりが見えないだろ」
「空と土がぴったり合わさってる。あの、山と山のあいだのことでしょ」
「土と砂と石が無限にあるように、水が無限にあるんだよ、もっとあるんだよ」
「やべえじゃん」
「そうだよ」
「神さまはすごいよ」
「おれも海くらい船で旅したことあるぞ」
「でも、神さまは、はだしで歩いた」
「そりゃすごい」
「井戸の掘りかたをおしえてくれて、素敵な花の種を持ってきてくれた、家の建てかたもおしえてくれた。神さまへの感謝のために、大きな像を、岩を刻んでつくったんだけど、ぼくたちの村(あいる)を見守っているようでもないし、あさっての方角を向いて口を菱形にあんぐりして、大あくび。でも、あれは海をながめてたのかな。神さまたちのふるさとをなつかしんで」
「そうかもな」
「下に字が彫ってあるんだよ。
つき、
って。だから、年寄りはみんな、つきさまって呼ぶ。火の支配者としては、ぜん、稲穂の頭をたれさせる人としては、しき、歌をつくった人としては、さん、光る人って意味で、ぞん、いつでもただしいお裁きをするから、とき、とも。あと百個くらい名前があるけど、ぼくは神さまっていうのが一番いいと思うな。
神さまから流出した文字があって、それが、あ、た、か、さ。三百二十の窓のある輪のなかに、それを適当に置くじゃない。前にまわせばいいことで、うしろにまわせば悪いこと。ざ、が切り裂いて、た、がたたいて、か、が黙ってる、さ、がしゅっと音をたてて燃えるでしょう、その組み合わせで、つき、ぜん、しき、さん、ぞん、とき、ってことばができて、その働きひとつひとつを神さまだと思ってしまっただけ。本当は、全部なのに。全部の働きが、神さまのちがう顔をあらわしているんだ、こんなことも分からないのかな」
「分かった」
「安稜(あろん)はかしこいから」
「おまえのおとっつぁんが神さまなんだって」
「そうだよ。手がついて、お母さんからぼくが生まれた。こうやって握手したのかな。ああ、なんか、ひざまずいて、女の人の手をささげ持って口づけしたのかな。こうやって、むかしばなしみたいに」
「気持ち悪いな、やめろよ。でも、そうかもしれない」
「ぼくはこんな肌の色だけど、目を見て。きれいな水色でしょう。これが神さまの色なんだ。ぼくが、ただの子供じゃない証拠で、海の色だよ。夜、寝るときに、がさがさ草が鳴るでしょう、そうしたらまぶたの裏で水色がちらちらするんだ。水の底に沈んでいく気がして、それは気持ちいいんだ。沈んでも溺れないし、死なない。だってぼくの体のなかで、神さまの胸に抱かれてるようなものだから」
「ちらちらしたなら、それは本当に海だよ。波だ、それ」
「波」
「水が風で段々になって、こっちにせまってくる。繰り返し、繰り返し、きりがないんだ。ざざあ、ざざあ、って」
「へえ。ありがとう。あーあ、なんか、帰りたくなってきたな」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
