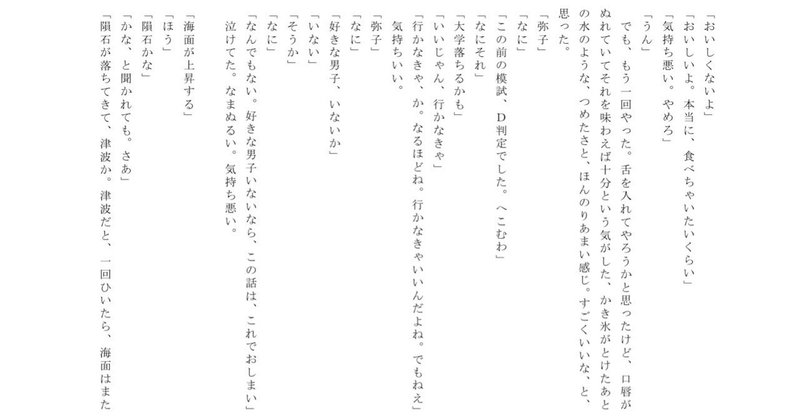
水族館物語(7)
「海面が上昇する」
「ほう」
「隕石かな」
「かな、と聞かれても。さあ」
「隕石が落ちてきて、津波か。津波だと、一回ひいたら、海面はまた落ち着くのか。日本とか沈没するかもしれないけど。やっぱり、温暖化あたりか。じゃあ、太陽が異常に活発化して、気温が上がる。隕石も落ちてくる」
「いいんじゃない」
「隕石が落ちてくる、それをきっかけに、急激なものだろうね。三週間とか、せいぜい、二ヶ月くらい。そのくらいのあいだに、どんどん、南極の氷が溶けて、日本にも押し寄せてくるだろうね、そうなると、すずしい北海道の、高地にみんな集まってくるんじゃないかと思う。でも、少子化とはいえ、一億何千万とかの人口があるわけで、そうすると、みんなは入れなくて、あぶれる人はいるでしょうね。抽選で、日本政府が行ける人を足切りして、それで、おじいちゃんおばあちゃんとか、子供は優先されるだろうけど、まあ、当選確率は千分の一、もないか。分かんないけど、当然、ここでいろいろきたないことが起きて、金で権利を売買したり、政治家にコネつかったり、いろいろ、ふつうに起きてることくらいは起きるわけだから、まあ、パニックだよ。そういう選ばれし人々が、北海道に新しい日本をつくって、そのほかの人たちは、外国に逃げる、日本より安全なところはけっこうあるでしょ、中国とか、ロシアとか、チベットとか。で、逃げ遅れたり、金がなかったり、選ばれなかったりして、どうしようもない人がいるじゃない。現実的にいるよね。そういう人たちは、地下だね。地下鉄のホームに、入口ふさいで、住む。駅ごとに、村みたいにひとつの家族が住んで、それが線路でつながってて、新宿あたりだと百家族くらいはいけるかもしれない。歩いて交流もできて、案外、おもしろそう。考えながら、話しながら思ったけど。わたしも、地下の人だろうね。たぶん、こんな状況になっても、人間、ヒエラルキーみたいなのをつくって、住んでる駅のグレードで差別するだろうね」
「なに食うの」
「え、キオスク、とか。地下の店の、食料を食べる。まあ、それはいずれなくなるので、なんとか自給自足できるように考える。北海道の人たちは、もう、わたしたちのことなんて死んだことにしてるから、助けてくれないだろうね。知らないふりして、こっそり電気を送ってくれたりはしそうだけど。生かさず、殺さず。日があたらないから、どうすればいいだろ。もやしとか育たないことはないと思うけど、品質は落ちるでしょうね。日本人、ぜいたくだから、けっこうそんなときでもわがまま言うと思う。沈没前の食料が異常に価値がでたりね。缶詰とか、保存食とか、おかしとか。やっぱり、物々交換にもどってるだろうね、あっというまに、全部のものに持ち主ができる。わたしは、ここから山を伝って、泳いで、線路を歩いて、わざわざ東京まで来ることになってるから、きっと出遅れるし、なんにも持ってないだろうし、どうすればいいのかね」
「それ、いつの話」
「だから、一九九九年」
「未来じゃないんだ」
「そうだよ」
「だったら、若さがあるんじゃないの」
「若さか。つまり、女の子の若さを売ればいいということになるわけか」
「いや、それにかぎらず、単純に労働力というか」
「なるほど。じゃあ、それで、なんとかなることにしよう。あとは、なんか問題あるかな、特にないか」
「なんで、東京に行くの」
「なんでだろ。実家、捨ててるね。なんとなく、なにも考えず、そうなる気がして、なんでかは分からん。そんな、地球規模の災害、というか、滅亡で、わたしは家をあえて捨てる人なのか。地震くらいだったら、家族を大事にしたいんだけど、なんだろうね、そこまでめちゃくちゃになるくらい地球も滅亡すると、思い出とか、そういう場合じゃなくなるかもしれない。自分の身は自分で守らないといけないし、というか、母親とか妹とか、どんな顔して、なに考えてるのか想像もつかない。わたしの想像力か。海に沈んだ日本とか、正直、すでにわたしの想像力を越えてるからね。海が青いのも、人があたふた走りまわってるのも、CGみたいな感じに見えてる。あざやかすぎて、なめらかに動いて気持ち悪い」
「どうすんの、東京で」
「とりあえず、来てみた」
「なんで」
「なんでだろうね。なんでだろう。ちょっとでも、上がいいんだろうね。なんかにはなりたいんだよ、滅亡しても、田舎で腐るのはいやなのさ。夏暑くて、冬寒くて、バスは一時間に一本だし、わたしの家と学校をむすぶ線からはみだして遊びに、買いものなんかでも、行くべきところもなくて、夜は暗いし、畑ばっかりで、地を這うように家が建ってて、重力がちがう、大きな、大きな空におしつぶされるみたいに土下座してる、家が。べたっと、頭を押さえられて、上に伸びる意志もないような、広すぎる土地で」
「うん」
「だから、選ばれし北海道の人々じゃないからには、外国に行く金もないし、地下の女王になろうと、それで東京まで行くのか。あってる、それで」
「知らない」
「きっと、そういう人がいるでしょ、東京の地下にも、やくざとか、前科のある人とか、なんかそっちの悪い方面のことは、ぜったいに繁栄するね、まず。いい人でも悪い人でも、誰かえらくなりはじめると、また、それをよく思わない人たち、ちょっとちがう方針の人たちが徒党を組んで、なんか、派閥ができるじゃん、すくなくともふたつ以上は。なんだろ、地下を出て、北海道へ攻めこもう、みたいな、そういうのだろうか。で、保守派と対立するわけね。地下でも、戦争が起きるのか。いやだ、なんか、ねちねちしてて、あんまりいい感じはしない。せまいし、暗いし、いやがらせみたいな精神攻撃じゃないのか。ネズミとかゴキブリとか、食料にまぜて食べれなくするとか。武器もないだろうし。で、わたしは、そうやって対立が本格化するのを、さめて見てる気がする。こんなことしてるうちに、ちゃんと穴をふさごうよ、海水がもれるんだよ、とか。土のあるところを探そうよ、とか。目の前の小さなことを忘れられる。じゃなくて、一番大きいのがあるじゃないですか、北海道の一番高くて広くてすずしい場所に行く、っていう、それを達成したら勝ちだとして、こう、こまかい勝負をいちいちしていくのがめんどうで、でも、それをさけて最終的に優勝はできないはずなんだけど、なんか、意味ないような気がして。単純にめんどくさい、それもある。一発で優勝したいから、保守派と革命派がちまちまやってるとこを、遠い目で見ててさ、北海道も見えてなくて、宇宙ね、ずっと、宇宙、アンドロメダ、考えてることだけは、野望だけは大きく持って、で、ネズミとかゴキブリを、もっと、ぜんぜんくだらないってことにするために、海水がもれるのとか、畑をつくるための土を気にしようとして、そんなつまんないことよりも、もっと気にする価値のない、くだらない小競り合いだな、って、思う。まあ、でも、わたしはずるいから、いい感じに取り入って、なんとなくやる気を見せて、えらい人たちは気に入ってくれると思うよ。おじさんにはもてるんだよ、前から、中学とか高校のときからずっと、国語とか日本史の先生にはやけに親しくしていただいて、外づらがいいもんだから。しょうがないよね。わたし、保守派のような気もする。どうせボスはこわいおっさんでしょ。なんか近くにいれば、なんとかなる。で、たぶん勝つよ、どういうかたちを勝ちと言うのか知らないけど。それで、なんだろ、わたしの役職は。ボスの愛人にはならないだろうから、孫みたいなもんか。でも、体も守りきれないだろうね。なにしろ世界は滅亡してるから、そういうときは種の保存本能もはたらいて、性欲も高まるらしいし、ほかに娯楽もないだろうし、女は、そこで開きなおれるかどうか、体でのしあがっていける女が、男を操縦して、地下で力を持っていくんだろう。一九九九年七の月のあとの世界、地下の下層民の生活も、だんだん分かってきたじゃないか」
「リアルだと思う、ただ、せちがらいね」
「しょせん、そうだろ」
「できたら、しますか。体」
「どうだろ。どうなんだろ」
「え、彼氏とかいたことあるでしょ」
「え」
「なに」
「うん。まあ」
「なに」
「あるよ。ふつうに」
「なんだよ」
「夏でした」
「初体験が」
「一九九九年の七月でした。そのときの男、その後の彼氏は、なんて言ったか」
「なんて言ったの」
「世界が終わる前に、愛し合おう、みたいな意味のことを、百倍むかつく感じで言った、内容も覚えてないし言いかたも再現できないけど、あれは本当にいやだった」
「なにが」
「いろいろあるけどね、一番は、言いかたかな」
「命の危険がせまったら、種の保存したい、という。しかも、個人的な死じゃなくて、人類が死ぬからね。保存したくなったんでしょ」
「なんかね」
「はあ」
「恐怖の大王って、そんなもんだったの」
「どんな」
「え、だから、地下鉄の駅でどうのとか、性的な衝動が高まるとか。宇宙的なことは、どうなった。宇宙的な滅亡でも、死ぬのは人間だからなあ。核だったら、即死できたけど、隕石だから、生殺し的に一番人間のきたないところが見れる。見たくないよ、殺してくれよ」
「残す、あんた」
「なにを」
「子孫」
「子供は好き」
「じゃあ、残せば」
「相手がいないし」
「見つかるでしょ」
「ひとりでも、将来どうなるか分かんないから」
「分かるよ」
「残るかな」
「なんで」
「この流れで、世のなかのどこに希望を見いだせば」
「生まれないより、よくない」
「誰が。子供がか。もう、わたしの子供は生まれたがってるのか」
「分かんない。あんたは、生まれてこなければよかったって、いつも思ってるのか」
「いつもは。まあ、たまに」
「いまは」
「いまは、そんなことないけど」
「だったら、やっぱり生んであげるべきだ。基本的には、生まれてきてよかったんでしょ」
「そういうことになるの」
「まあね」
「よく分からん」
「もう終わってるかもな、日本、世界」
「はじめから」
「一九九九年から、徐々にね。地球、終わってるよ。一九九九年、七の月をまたいでから、徐々に、わたしも死んでる。一気に死ねなかったから。本当は、大王、来てるかもしれない、って、一ヶ月くらいはびくびくしてた、気づいてないだけで、小規模な滅亡はどっかで起こってるんじゃないかと、それがだんだん日本に近づいてきたりして。まあ、起こってるんだよね、世界中、どっかで戦争とか紛争とか起こってるから、そこの当事者的には常に世界は滅亡じゃない。てゆうか、交通事故で死ぬとかも被害者にはそうとう不条理で、世界から心底裏切られたような気がするでしょうね。なにを言おうとしてたっけ。まあ、そういうことだ」
「そういうことなのかな」
「昨日は、飲んだ」
「飲んだよ」
「お兄さんとですか」
「あんたも誘おうと思ったけど」
「元気」
「昨日と同じくらい」
「よかった」
「お兄さま、馬鹿でね。焼酎がぶがぶ飲んで。しかも酒に弱いらしくて、吐いた、片づけも、なんか、わたしがすることになってて、それで、精神的にはけっこうダメージもある。くさかった、トイレにつれていって、全部吐かせて、ちょっとだけ緊張が走ったね、明日だいじょうぶなのか、と、急性アルコール中毒とか。タクシー呼びましょうかって、お店の人が言うけど、ことわった。つれて帰った。店を出たら、それでも歩けるようにはなってて」
「よかったね、歩けたじゃん」
「たのしくないこともなかった、典型的な酔っぱらいなんだ。水族館、通りすぎた。水族館にまつわる、お兄さまの失恋の話を聞いた。いいやつだと、そのとき思った。聞きたい」
「別に」
「まあ、結局、水族館にデートに行ったあとで、彼女の部屋でいちゃいちゃして、そのあと、彼女にふられた、という、それだけの話なんだけど。彼のまじめさが伝わる、すごくいい失恋話だった。実は、水族館、けっこうわたしも好きで、デートにもいいよね。いい感じになる。改装前、好きな人を誘うときは、よくつかった。なんか、いい感じになる。五階にあるじゃない、あの上に水族館があって、と思うと、なんか変だ。東京なら、もっと高いところにある。あんな上に水のいっぱい入った水槽があって、見てると、気持ちのなかでバランスが変になって、気持ち悪くなって、わたしもちょっと酔ってたんだけど、水族館はいいな、とふと思った。地震が起きて、世界が滅亡したらどこに避難しようか、って。水族館に避難すればいい、って、思った。水槽とか割れないかぎり、いいと思うんだよね。デリケートな魚とか、ペンギンとか、ちゃんと死なないような設備がととのってるわけだから、人間にも快適なはずで。水とか、食料もね。水は水槽のがあるし、魚はいっぱいいるし。ビルの上にあるから、日本が水没しても、まあ、あれくらい高ければ窓を開けられるでしょ、海に沈んだ日本を見れる。どんな光景だろ、それ見れるだけで、わたしの勝ちのような気がする。だから、地下の人々が本格的な決戦で、あらそって、いちおう決着がついたら、また平和になる。そのとき、きっと、わたしの領地も増えてて、なんか地位もよくなってるはずで、でも、わたしは遠い目をしてるから、うれしくもなんともないわけだよ。ボスにはいい感じのことを言ってるかもしれないけど、結局、地下全体ではなにも進化してないわけだし、もう、なんか先が見えてる。死ぬまで生きるだけだな、と思う。で、泳いで、脱出する。ひとりで。なんか、気候もおかしなことになって、あったかいと思う。くそ暑い日に、ぐちゃぐちゃに汗まみれになって、鉄パイプとか、コンクリートブロックとか、手近のものをつかってさ、血が、鉄のにおいがして、むわっとして、なんだろ、そういう場面が見えてる。きたなすぎて、人間らしすぎて、わたしは、引くんだろうね。全部見せられた、みたいな。だから暑い、夏。それで、ボスに抱かれて、またなんか、よごれる感じ。風呂に入りたい、と思う。ホームレスと同じだよ、ボスの体臭。水は貴重品だろうから、もう少なくとも半年は入浴してないはずだ。それで、外の海に出て泳ごう、っていうところから連想が広がって、海、魚、水族館、あ、行こう、水族館に行こう、って思うんだ。夜中に起きて、どっかの出口、厳重にふさいでるのを、なんとかして破壊する。わたし、泳ぐのはけっこう得意なんだよ。実は、知らないだろうけど、中学のときに県大会で記録持ってるから、いまはどうか知らないけど。夜中、は、やっぱりあぶないか、明け方、わたしは海に出る。すごい景色だと思う。空を、わたしが泳いで、飛んでる。光が、こう、ぶわっと道に落ちて、ゆらゆら揺れて、いままで誰も見たことないところから世界を見てる。人っこひとりいない。水族館まで、泳ぐ。泳いでるわたしはきれいだと思う。天使だよ。廃墟をひとりで泳いでるとか。しかも明け方、これができたら、もうわたしは満足、映像に残ったら死んでもいい。これくらいドラマチックなこと、ふだんからあればいい。あるかもしんないけど、どんな事件も事故も当事者になれずに生きてきてしまった。そうか、恐怖の大王ね、あれだよ。地球人が平等に主役になれるチャンスがあって、わたしは、見事にそれをのがした。もう来ないかね、あの人、大王」
「来ないよ、ぜったい」
「そうか」
「いや、分かんないけど。平和なほうがいいし」
「平和とか戦争とかじゃないんだよ。中途はんぱはつらい、すごい平和か、もうどろどろの戦争か、どっちかがいいと思うよ。だから、個人的にね。そういう教訓だよ。ノストラダムス。みんな心の底では待ってたんじゃないの。少なくとも、わたしはすっぽかされたのをむかついてる。戦争じゃなくてもいいわ。なんか、すかっと一発なぐられて、ふっと世界が変わる、なんかを破って生まれ変わる、みたいなイベントが。死なない程度の。それで、水族館に到着して。どっかから入るよね。潜ってもたいしたことない深さだから、正面から入ってもいい。問題は息がつづくかってことだけど、気合いでがんばることにしよう。迷うと死ぬね。どう行けばいいか思い出せない。今度確認しとこう。で、泳いで、登って、水族館。しずかで、時間がとまったみたいに空気が動かなくて、わたしひとりだけ、ってこと以外は全部ふつうの水族館みたいで、わたしはとりあえず水族館をぐるっとまわる。水族館の生きものって、本当に生きものなんだよね、ただの。生きてるだけ、最短距離で。ペンギンとか、実はかわいくないんだよね。じっとしてる。子供がカメラかまえてても、愛想をふりまくこともしなくて、ただ、夫婦でじっとプールの端で立ってる。食いものを手に入れるとか、そういう活動の必要がないかぎり、動く意味がないんだよ。野生の生きものは本当に合理的で、むかつくくらい合理的で、生きるのに最短距離なんだ。交尾、セックスだって愛してて気持ちいいからじゃなくて、ただ、子孫をふやそうっていう本能から、やってるだけ。だから、日本が水没してさ、それで水族館はどうなってるんだろ。やっぱり、じっとしてる気がするよ。エネルギー温存しないといけないから。それで、わたしが通りかかると、ぎらぎらした目で食いものを要求する。まったくいやされないね。よくデートで行ったんだ。水族館の魚とかタコとかカニとか、あの無機質な生活を見るのがたまらなくて。むかつくけど、デートするときって、わたしは本当に相手が好きだから、だから、客観的に自分を見るのにも、いい。本能だけで生きてるのを見て、ああ、しょせん子孫繁栄なのか、って思って、あんまりはめをはずさないようにって誓う。水族館で、わたしはそのうち、水槽を見てるのがいやになる。とりあえず生きる、そういうだらしないのがいや。ちがうだろ。わたしは、食いものもらってれば、じっと動かずに生きてる、ってわけにはいかないから、そいつらの視線をさけるために、水族館をとりあえず出るね。となりの、プラネタリウムに逃げる。あれをひとりで動かせるのかどうか知らないけど、なんとかして、見たい、ひとりで。一回、行ったことある。そのときもデートだった。でも、ひとりで見てると、またなんかちがう気がする。ひとりじめした感じは、水族館よりぜんぜん気持ちよくて、ビッグバンは、ブラックホールは、って、わたしだけのために説明してくれて。やってみたいのは、床に寝転がってプラネタリウム観賞ね。で、そのまま寝る」
「いいな。なんか」
「頭のなかで、いろいろちらかってる。なに、魚とか、星座とか」
「片づければ」
「起きたら、どうしようか。わたしが脱走して、地下では少しは騒ぎになってるかもしれない、とか期待しつつ、屋上に出て、水平線が見える。地球はまるい。滅亡する前もまるかった」
「そして、青かった」
「そうね。次は、どこ行こう」
「知らない」
「船でもつくって、アメリカまで行くとかね。一直線だから。海をつっきれば、障害物はないから」
「宇宙も」
「え」
「実は、アンドロメダまで、なんの障害物もないんですよね」
魚だ。水族館で、魚になって、貴之といっしょに泳いで、たまにうろこをこすりつけて、つめたい感触を味わえばそれでいい。わたし、たまご産むし、貴之は精子をふりかける。それで、何百匹と子供たちができるんだろうけど、わたしは意地でもそいつらをわたしの子供だってみとめないだろう。口に入ったら食べるし、死んでもかなしくないと思う。水族館のなかで、わたしは死なない。何百年でも生きて、マイペースに進化して、人っぽいかたちになる。くらげみたいにすけてて、骨もたよりない。ふにゃふにゃで、水槽からあがったら死ぬけど、でも、そのぶんきれいで、人魚姫みたいなんだ。肌が白いとかそんなのじゃない、すけてる。それで、気づいたら貴之も進化して、同じくらげ人間になってる。それで、やっと体温がない、ひんやりしたセックスができる。子供も、できたら、残らないほうがいい。わたしの産むたまごは、にわとりのたまごくらいの大きさで、とにかくきれいなんだ。殻はガラスみたいで、なかで子供が膝をかかえて胎児の格好で、すけて見える。心臓まで見える。脈を打ってる。血は赤い。殼を割って、生まれる前に、全部つぶしてやる。本当にいいな。なんにも意味がない、つめたいセックスにまみれた、こんな生活。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
