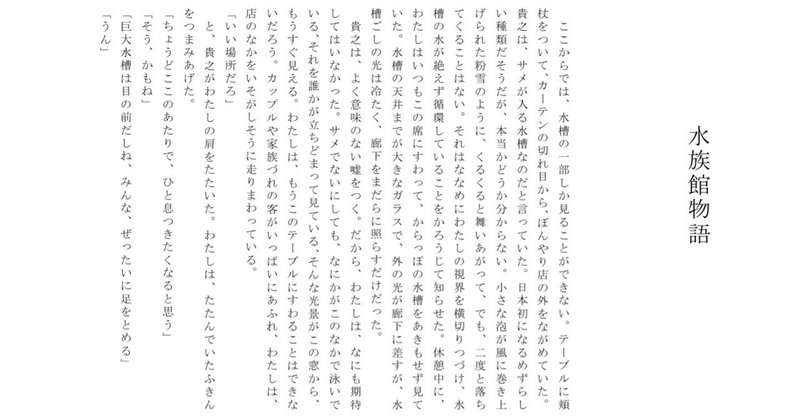
水族館物語(1)
ここからでは、水槽の一部しか見ることができない。テーブルに頬杖をついて、カーテンの切れ目から、ぼんやり店の外をながめていた。貴之は、サメが入る水槽なのだと言っていた。日本初になるめずらしい種類だそうだが、本当かどうか分からない。小さな泡が風に巻き上げられた粉雪のように、くるくると舞いあがって、でも、二度と落ちてくることはない。それはななめにわたしの視界を横切りつづけ、水槽の水が絶えず循環していることをかろうじて知らせた。休憩中に、わたしはいつもこの席にすわって、からっぽの水槽をあきもせず見ていた。水槽の天井までが大きなガラスで、外の光が廊下に差すが、水槽ごしの光は冷たく、廊下をまだらに照らすだけだった。
貴之は、よく意味のない嘘をつく。だから、わたしは、なにも期待してはいなかった。サメでないにしても、なにかがこのなかで泳いでいる、それを誰かが立ちどまって見ている、そんな光景がこの窓から、もうすぐ見える。わたしは、もうこのテーブルにすわることはできないだろう。カップルや家族づれの客がいっぱいにあふれ、わたしは、店のなかをいそがしそうに走りまわっている。
「いい場所だろ」
と、貴之がわたしの肩をたたいた。わたしは、たたんでいたふきんをつまみあげた。
「ちょうどここのあたりで、ひと息つきたくなると思う」
「そう、かもね」
「巨大水槽は目の前だしね、みんな、ぜったいに足をとめる」
「うん」
あてにはならない、と言ってやりたかった。バイト代さえもらえればどうだっていいとはいうものの、もうからないよりは、もうかったほうがいいに決まっている。それでも、貴之の思いつきに、そのとおりだと素直にうなずくしかないのは、くやしかった。
貴之の顔は、半分が店内の黄色い光に、半分が廊下からの白い光に区切られていた。水面にくだけた外の光は、リノリウムに反射して、かすかに顔の上でまだゆらめいているようだった。
「だいたい終わった。そうじ」
「ちゃんと床もやった」
「やった。三回モップかけた」
「窓は」
「やったよ。そんなによごれてるわけない。昨日はめたばっかりなのに」
「そうだけど」
言いながら、貴之はカウンターのなかに入っていった。コップや皿が乱雑に積みかさねられたまま、こちらは、まだぜんぜん終わっていないようだった。換気扇をつけて、貴之は灰皿をたぐりよせた。わたしも反射的にポケットに手を入れ、一本、口にくわえていた。
ライターを持った手が、遠く見えた。あいまいな時間のなか、別の生きもののように呼吸し、脈うっていた。わたしもまた、冷たい光に照らされていた。奇妙な模様が腕の上で揺らめき、見ているうちに、締めつけられているような、くすぐったいようなあたたかさが、全身に広がっていった。わたしは、ここで、たしかにわたしではない、なにかだった。水のなかに落ちていく速度を、うす暗い照明と息苦しさに感じていた。
貴之が灰皿でカウンターをたたき、こっちで吸えという合図をした。わたしは足を引きずるように体を運び、貴之のむかいにすわった。貴之に火をもらってから、わたしはにぎりしめているライターのことを思い出した。
「今日はこのくらいにしとくか」
「終わらせるんじゃなかったの」
「明日から入れないと思ってたけど、やっぱりいいって。だから、あんまりあせらなくてもいいらしい」
「なにそれ」
「いや、工事の関係。よく分からないけど、それなら急ぐ必要もないから」
「明日も来たほうがいいの。わたし」
「なんで」
「来たほうがいいの」
「別に、いやならいいけど。もう、ひとりでやれるから」
「そう」
「なんで」
「まあ、ひさしぶりに予備校行こうかと思ってたから。どうでもいいけど。めずらしく行く気になってたのに、でも、こっち手伝わなきゃなって」
「いいよ、行けば」
「どっちでもいい。わたしも」
「じゃあ手伝ってよ」
「分かんない。明日決める」
鼻から抜いた煙が貴之の顔をつつんだ。貴之は、少しむせながらみじかくなったたばこをもみ消した。わたしは十五から吸っているが、貴之はつい最近、覚えたばかりだった。たぶん、それはわたしの影響だった。
貴之が、次の一本をくわえた。今度はわたしのほうが先にライターに手をのばし、火をつけてやった。
「わたしは、気持ち悪い」
換気扇に吸いこまれていく煙を見あげながら、わたしはつぶやいた。細くたよりなく、まっすぐ天井までのぼっていくが、なにかのかたちを持つ前に、うすれて消えてしまう。
「なにが」
「水族館で、魚なんか食べたくない」
「なんで。おまえだけだよ」
「そうかな。生きて、泳いでるのを見ながら、おいしいとは思えない気がする。つまり、死体を食べてるんだから」
「そういう考えかたをするおまえのほうが、気持ち悪いと思う。そんなこと言ったら、なんだってそうじゃないか」
だんだんむきになって、煙を口にためながらまくしたてる貴之が、水槽のなかの生きものにも見える。わたしには、もう、貴之の声は聞こえていなかった。遠い水のうねりと換気扇の音にまじって、耳鳴りがやまなかった。わたしたちの呼吸する空気は重く、つめたく、体のなかからわたしたちを閉じこめて逃がさなかった。
指にはさんだたばこの火が、ゆらゆら煙のなかを泳いでいた。小さな黄色いつぶは、蛍のようにまたたきもせず、しかし生き生きと泳ぎつづけていた。わたしは、ふいに孤独ということを思った。
貴之はたばこを灰皿に捨てた。なんだか、青ざめた顔をしていた。ばたばたと足音がして、帽子をかぶった作業員の人たちが、店の前を横切った。ぶあついガラスを四人がかりで運んでいた。それが、四組ほどつづいた。貴之とわたしは、黙ってそれをながめ、通りすぎたあとも、からっぽの水槽からしばらく目をはなさなかった。
「地震があったらさ」
とわたしは言った。聞いていないのか、聞こえないのか、貴之はだまったままだった。わたしはかまわずつづけた。
「前から思ってたんだ。水族館に逃げればいいって。地震のとき、そうすれば、とりあえずは食べものにこまらないよね。広いし、ここでも、どうだろ、二百人くらいは暮らせるんじゃないかな」
「食べるの」
貴之は、カウンターから出て、窓のカーテンを引いた。そろそろ帰るということらしかった。時計を見ると、まだ三時だった。九時に来いと言うからひさしぶりに早起きをしたが、こんなに早く切り上げるなら、もっとゆっくり寝ていたかったと思う。
「食べるよ」
「気持ち悪いんじゃないの」
「非常時は、そんなこと言ってられない」
「食べられないのも多いと思うよ。サメなんてどうやって料理すればいいか分からない」
「わたしだって知らない」
「ペンギンも入るらしい。ラッコとか、アヒルとか、あとカブトムシもいるし、屋上にはトカゲとかワニもいる」
まだわたしは、水族館にそれらの生きものがいるのを見たことがない。図鑑を読みあげるように、貴之は勝手に水族館の仲間を増やしていった。わたしはやはり信じなかった。キリン、と言ったときには貴之も笑いまじりで、もうそのときには動物園とかわりないくらい、にぎやかになっていた。
わたしはエプロンをテーブルの上に投げだし、かるく手を洗って、帰る準備はそれだけで終わった。なにも必要ないと貴之が言ったので、さいふだけしか持ってきていない。そのさいふの中身も、往復の交通費がかろうじて入っているだけだった。
「それに」
と貴之は、話のつづきのように、奥から出てきて言った。まだペンギンやラッコがそのあたりにうろうろしているようで、貴之のだらだらした足どりも、踏みつけないように気をつけながら歩いているように見える。なにが出てきてもどうせ嘘だが、水族館が完成するまでは嘘にはならず、わたしはまだ貴之の嘘を嘘だと言って否定したことはない。
「プラネタリウムもできるんだって」
「ふうん。プラネタリウム。水族館に来て、なんでそんなの見るの」
「なんでって、それなら、なんで魚が泳いでるのを見ておもしろがるんだよ。そこからおかしいことになるだろ」
貴之の言っていることはよく分からなかったが、そうかもしれないと納得しておくほうがいいような気がした。わたしは魚が泳いでいるのを見ても、たぶん、おもしろいとは思わないだろうが、それは言わなかった。夜空の下、凪いだ海にゆったりと泳いでいる魚たちの姿を思い浮かべたが、わたしはなぜかそれを真昼のほうがふさわしいように感じている。
「水族館って、英語でなんて言うか知ってる」
「知らない」
「アクアリウム」
わたしは、アクアリウム、と口のなかで何度かつぶやいたが、入試には出てこないだろうとしか思わなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
