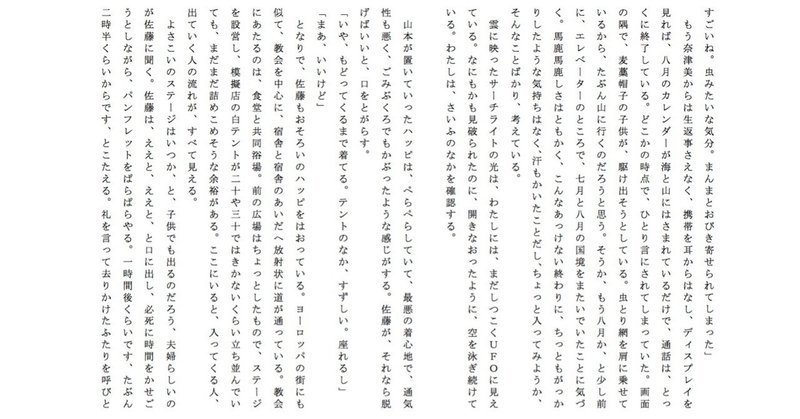
落下傘ノスタルヂア(13)
山本が置いていったハッピは、ぺらぺらしていて、最悪の着心地で、通気性も悪く、ごみぶくろでもかぶったような感じがする。佐藤が、それなら脱げばいいと、口をとがらす。
「いや、もどってくるまで着てる。テントのなか、すずしい。座れるし」
「まあ、いいけど」
となりで、佐藤もおそろいのハッピをはおっている。ヨーロッパの街にも似て、教会を中心に、宿舎と宿舎のあいだへ放射状に道が通っている。教会にあたるのは、食堂と共同浴場。前の広場はちょっとしたもので、ステージを設営し、模擬店の白テントが二十や三十ではきかないくらい立ち並んでいても、まだまだ詰めこめそうな余裕がある。ここにいると、入ってくる人、出ていく人の流れが、すべて見える。
よさこいのステージはいつか、と、子供でも出るのだろう、夫婦らしいのが佐藤に聞く。佐藤は、ええと、ええと、と口に出し、必死に時間をかせごうとしながら、パンフレットをぱらぱらやる。一時間後くらいです、たぶん二時半くらいからです、とこたえる。礼を言って去りかけたふたりを呼びとめ、よろしかったら、とパンフレットを差し出す。
「はじめからそうすりゃいい。自分で探してもらうほうが早い」
お客が去ってから、佐藤に言う。いま、ステージではマジックサークルかなにかの発表をしている。トランプとかのちまちました出しものばかりで、遠くからぼんやり見ていても、なにをやっているのか分からない。それでも、ときどきは暴発したようにトランプがまきちらされたりもするのが、景気の悪い花火大会みたいだった。
「まあ、そうだ」
「案内所とか。意味ないよ」
「でも現に来る人いるし。パンフレット見れば分かるけど、もらいそびれた人もいるから」
「下っぱの仕事なんだ、これ」
「正直」
「だろうね」
足もとの一冊をつまみ上げ、指で一枚一枚ページをはじいていく。そういうわたしも、もらいそびれたひとりだった。広場への入口で、それぞれ手渡しする係が立っているが、ティッシュくばりのような根性もなく、中途はんぱに立ちふさがるので、かえってうっとうしい。つい、いらないものだと判断してしまい、無視することになる。もらうべきだったとすぐに気づき、案内所へと直行したのだった。ちょうどよかった、とかなんとか言って、わたしに番を押しつけた山本は、なにかおつかいを命じられていたようだった。
「あった」
なにが、と佐藤が聞き返すより早く、わたしはもう目の前に突きつけている。
「見て見て」
「応援団演舞。第一五〇回。って、どんなカウントのしかたしてるんだろ」
「下。広告のとこ」
くしゃみのような音を立てて、佐藤は顔をそむける。一瞬間を置いて、うける、ともらす。わたしはおもむろにそのページへ目を落とし、やったな、と、ヒの字のドラちゃんにほほえみかける。
「なにこれ。ノリピーがやったの」
工務店と美容院の広告にはさまれ、ドラちゃんのカメラ目線は、いよいよとぼけて見える。
「そう」
「なんの広告」
「なんか知らないけど、お金はらえばわたしのスペースだから。なんでもいいんじゃないの」
「え、広告料はらったの」
「まあ。高くついた冗談でしたね。山本も、本気にするとは思わなかった。お風呂で偶然会ってね。広告の営業に行くところだって言うから、つい。入口でドラちゃんが寝てたの見て、思いついてしまった」
笑いの余震が、また佐藤をおそい、
「持って帰ろう」
と、パンフレットを、パイプいすにひっかけたかばんにしまう。やどかり祭の記念にと、持って帰るつもりはいままでなかったらしい。まだ、よく見てもいなかったらしい。
「ドラちゃん、って名前くらい入れてあげればよかったのに。写真だけって」
「意味分かんなくて、おもしろいかと」
「ドラちゃんって、定着させられたのに。この前、ジョンとか呼んでる人がいたよ。ちがうんだけど、って、ここまで出かけてた。犬か」
ドラちゃんのかわりに怒ってあげることはない、と思った。ドラちゃんも、ドラちゃんと呼ばれるのが本当にうれしいのか、どうなのか。にせ女子大生のわたしが命名者になって、ドラちゃんという名前が代々語りつがれていくというのも、おもしろくないこともない。佐藤の先輩らしいのが、いそがしげに案内所の前を横切っていく。佐藤とわたしに、おつかれ、と、どなるように声をかける。なにくわぬ顔で、わたしは頭を下げる。まるめた方眼紙や三脚をかつぐ背中には、舌を出した、あやしげなじいさんの顔がプリントされている。小さくなって、見えなくなる前に、英語のロゴを急いで読むが、物理学部のようだった。変なじいさんの顔も、捨学も、どっちもいやだと思った。かすかに流れていた音楽が消え、ステージではマジックショーが終わって、やどかり委員がちんたら片づけをしはじめる。その何人かは、ショッキングピンクのジャンパーを着ている。ここからでは何学部か分からない。器材にしがみついては引き返し、もどってはあらわれ、あざやかなジャンパーは蝶のように、と言いたいところだが、手ぎわの悪さがじれったいばかりで、きれいとも美しいとも感じなかった。時間差でふと、物理学部のじいさんの顔が、アインシュタインのそれだったのだと思いあたる。
山本が帰ってくる。こぎたなく痛んだ軍手を耳まで上げ、子供のようにぶんぶん振っている。水をくぐったくらいに、Tシャツが汗に濡れていた。
「ノリピー、まだいたの」
ビニールぶくろを机に置き、わたしを立たせて、ハッピをはぎとる。ふくろの中味は、小麦粉かなにかだった。
「まだいたよ。やっちゃんの演奏聞くまで、帰れないじゃない」
「あ、じゃあ、わたし、間に合ったんだ」
「たぶん」
パンフレットのはじめのページ、メインステージのプログラムを確認する。開会の辞、委員長挨拶、鏡割り、フラメンコ研究会、パントマイム研究会、殺陣研究会、落語研究会、とプログラムを追っていき、ストリートダンス研究会あたりで、ようやく見覚えがあるような気がする。どうでもいいが、研究会が好きな大学だと思う。
「マジック・ジャグリング研究会の次。いまからはじまるのか。押しまくってるじゃん。もうパンフレットのタイムテーブルなんか見ないほうがいいんじゃ」
「出る団体、多いから」
山本は、ハッピに袖を通しながら、いちおう委員の不肖を言いわけする。暑い、とでももらしかけたのを、がまんして、息をつく。
ちょっと見てくるかな、とわたしは案内所の席をはなれ、山本にゆずる。逃げこむようにテントの影に入った山本に、佐藤はパンフレットをうちわにして、風を送ってやる。やがて自分の手にしていたものに気づいて、例のページを開く。山本は、本当にいいのか、と何度もわたしに確認したくらいだから、特に新しい感動もなく、思い出し笑いする佐藤につられて、ちょっとにやにやするだけだった。佐藤がしずまるのを待ち、おつかれ、と言ってわたしはステージのほうへむかう。ここから見てるから、と、ちょうどそのとき来たお客をさばいてから、追いかけるように、ふたりは後ろから声を上げた。
「こんにちは。トップバッターというか、前座というか、まずはわたしたちの演奏を聞いていただかなくてはなりません。すいません。すいませんじゃない。ええ、実は、ここで、重大発表をしますが、わたしは、この大学にぜんぜん関係ありません。それが、なぜ、いまここに立っているかというと」
なんで、と前のほうでかたまっている人たちが、声をそろえる。そういやそうだ、とわたしはお尻をもぞもぞさせる。パイプいすの、ビニールに触れていた部分がむれて、やたらにかゆかった。
「よく分かりませんよ。メンバー募集してたんで入ったんですが、いいんですかね。てゆうかドラムの人だけなんですけどね、ここの学生。いいんですか、学校的にというか。まあ、いいか」
そのドラムの人のピアスは、だまるように身ぶりで示している。いけないらしかった。いちおう、あとで怒られるにちがいない。でも、わたしは、そういうの、きらいじゃない。
泰子と目が合った気がして、ポケットから手を出し、ピースをつくる。馬鹿正直に、泰子はわたしにこたえて、しかも両手で、ピースする。ステージのバックには、やどかりのキャラクターがおそろしく単純な線で描かれ、変なところから突き出た両手が、やはりピースしていた。泰子は、たぶん、気づいていない。携帯で一枚写真をとったあと、わたしに視線があつまる前に、ちょっとはなれたところへ逃げる。やっと演奏がはじまる。
「エレクトリック・サーカス」
かっこつけて、泰子が曲名を言う。コピーかよ、という肩すかしと、いんちきなラジオのDJ風なのがおもしろくて、笑った。ほんの少し吹き出しただけだったが、まわりの人はみんなまったくの棒立ちで、なんとなく気まずく、さらにわたしはステージからあとずさる。ピアスの、ワン、ツー、スリーを聞く。爆音が鳴り響いた。みんなうまそうだったが、いかんせんPAがてきとうで、気の毒なくらい聞きづらい。歌ってる、歌ってる。なんか必死に、歌ってる。歌ってる、とわたしは胸のなかで繰り返す。クーラーボックスを下げたメイド服の女の子を呼びとめ、ビールを買う。わたしは、泰子をじっと見ている。歌ってる。やはり、そう思う。顔をくしゃくしゃにして、髪を振り乱して、足を踏み鳴らして、のたうちまわって、歌ってる。子供の学芸会を見守る、親のような気持ち。それだけじゃない気がする。わたしは、たぶん遠い目をして、ビールをなめながら、なにかむずかしいことを考えようとしている。影もかたちもなくて、大きさはあるのに重さはなくて、あたたかくて、ふにゃふにゃしていて、でも、触れることはできそうにない。水槽のなか、お店の座敷よりは大きい、お風呂よりもきっと大きい、でも、宇宙とか、歴史とか、そこまでとてつもないものじゃない。やっと輪郭だけ見えかけてきたのに、演奏が終わると同時に、その変なごちゃごちゃしたものも、溶けて、消える。
わたしはビールを一気に飲み干し、紙コップを捨てる。めちゃくちゃに、手をたたいた。モーツァルトのオペラにスタンディングオベーションするつもりで、全身全霊の拍手を送る。しまった、とは一瞬思った。まわりの人がじろじろ見ているのは分かっていたが、もうひっこめなかった。前のほうにいる調子のいい人たちも、やっとわたしの興奮を受け取ってくれる。あとは簡単で、どんどん感染していって、拍手のうずが巻き起こる。ひょっとすると、やどかり祭がひとつになっていた。
とまどっているのは、ステージの泰子、ピアス、筋肉、長髪のほうだった。アンコール、アンコールという声にこたえて、
「まあ、一曲目ですから」
と泰子は、素にもどって言う。
マイクがハウる。
ゆあーん、ゆよーん、と響きわたる。
ドラえもんが、人面犬が、宇宙人が、アトムが、ゆあーん、ゆよーん、ゆやゆよん、とわたしの頭のなかでサーカスをはじめる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
