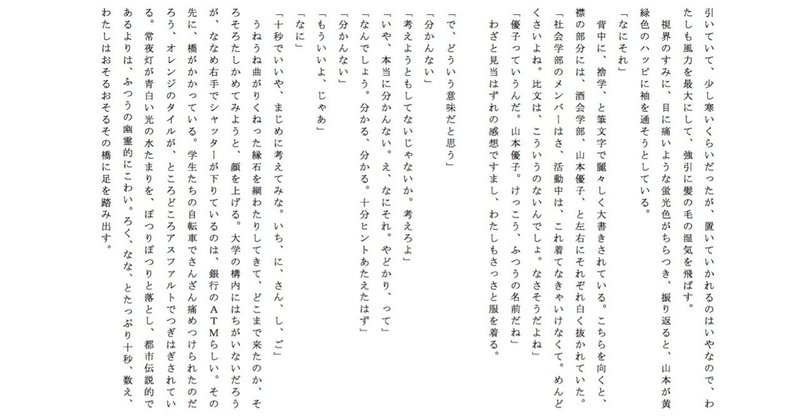
落下傘ノスタルヂア(12)
「で、どういう意味だと思う」
「分かんない」
「考えようともしてないじゃないか。考えろよ」
「いや、本当に分かんない。え、なにそれ。やどかり、って」
「なんでしょう。分かる、分かる。十分ヒントあたえたはず」
「分かんない」
「もういいよ、じゃあ」
「なに」
「十秒でいいや、まじめに考えてみな。いち、に、さん、し、ご」
うねうね曲がりくねった縁石を綱わたりしてきて、どこまで来たのか、そろそろたしかめてみようと、顔を上げる。大学の構内にはちがいないだろうが、ななめ右手でシャッターが下りているのは、銀行のATMらしい。その先に、橋がかかっている。学生たちの自転車でさんざん痛めつけられたのだろう、オレンジのタイルが、ところどころアスファルトでつぎはぎされている。常夜灯が青白い光の水たまりを、ぽつりぽつりと落とし、都市伝説的であるよりは、ふつうの幽霊的にこわい。ろく、なな、とたっぷり十秒、数え、わたしはおそるおそるその橋に足を踏み出す。
ううん、とか、ええと、とか、愛想でもらしたりするような奈津美ではない。携帯をあごにはさみ、テレビをつけている。ボリュームが思ったよりも大きかったので、びっくりしてミュートにする。おもしろそうなのがないな、と、チャンネルを変えまくっている。手にとるように、気配が伝わる。
「はち、きゅう、じゅう」
「分かりません」
「なんか言おうよ」
「だから、そのサークルでしょ。やどかりって名前なんでしょ。なんのサークルかは知りません」
「まあいいや。じゃ、正解。やどかり祭というのがあるそうですよ。小さい学園祭みたいな。なぜ、やどかり祭と言うか、というと、大学全体の学園祭じゃなくて、名目は、宿舎祭なんですね。宿舎に、ね、宿を借りてるわけでしょう。そういうこと。山本ちゃんは、その委員だったんだね。以上」
「よく分かった」
「立て札があるのね」
「なに」
「第二問。橋の横に、この橋わたるべからず、って立て札がある。さあ、どうする」
「まんなかをわたる」
「正解。いま、わたし、橋のまんなかをわたってる」
「大学にいるんでしょ」
「橋があるんだよ。そういう大学。長い橋だ。研究学園都市はね、車がなかったら、自転車がないと生活できないんだね。研究学園都市なら、歩く歩道くらいつくれ、って感じだね。毎朝、北京のようだね。はい、いま、わたり終わりました。ここから、ずっと道がタイルだね。ぼろぼろだ。ブラックジャックみたいになってる」
「どういう意味」
「どういう意味だと思う」
「知らん」
「そういえば、アトムって、二〇〇三年に生まれたんだよ。知ってた」
「それがどうした」
「いや、手塚治虫つながりで。ドラえもんは、ええと、覚えたんだ、二一〇〇年代の、何年だったかな」
また、縁石にひょいと飛び乗る。ときどき枝分かれしながらも、つるつるのきれいなコンクリートは、どこまでもしつこく続いている。万里の長城。橋から急な下り坂になって、自転車で飛ばすのは気持ちいいだろうな、と想像する間もなく、すぐにまた上り坂が学部棟のほうへ伸びていく。積み木のような、好きな色からつかっていった色えんぴつのような、変な構造と色彩が、変な遠近法で迫ってくる。
「おかし食べてるでしょ」
「いや、夕食」
こっちは飽きさせないようにがんばってやっているのだが、奈津美は露骨にそういうことをする。
「着いたよ。学部棟。ここの、自然科学系棟。てゆうか、ふつうに明るい。入れそうなんですけど、あ、入れました。すごいね。こんな夜中に、構内、自由に通り抜けられるし。なんという大学だろう。泊まりこみで研究してる人とか、いるんだろうね。さあ、問題のエレベーターは、もうちょっと先かな。ここの入口じゃなかった。西側、西ってどっちだ、あ、いま、地図見てるよ。描いてもらったんだよね」
「はいはい」
「ついた。じゃ、地下二階に下りますね。はい、押した。下がってる、下がってる」
「いいよ、いちいち実況しなくて」
「いや、こわいから」
「だって、けっこう人いるんでしょ。明るいんでしょ」
「いや、知らない人だから。まだ誰もすれちがってないし。放課後の学校って、こわいじゃない。大学も一緒」
扉の開いた、そこは、放課後の学校というより、大学というより、深夜の病院に似ていた。つきあたりの角まで、まっすぐ廊下はひっぱられ、うす暗い空気の膜を一枚一枚重ね張りしていったような、ミルフィーユ状の闇が、わたしを待ちかまえていた。ちゃんと奈津美に伝えようと、臨場感を出して描写したが、わたしの表現力よりは目の前にある無音のテレビ画面のほうがリアルらしく、ふうん、も、へえ、もなくなった。
「いま、何時」
「うん。十二時前」
「正確に」
「十二時、二分前」
「じゃあ、ここで、あと二分待ちます」
「ああ。その廊下は行かないのね」
「そう。問題は、エレベーターだから」
夜中の十二時ちょうどに、自然科学系棟の地下二階で、エレベーターのボタンを押す。すると、これより地下はないはずが、さらに下からエレベーターが上がってくる。それに乗ると、ひみつの地下通路に行ける。そこで、この研究学園都市のすべてが、あきらかになる。ホルマリン漬けの宇宙人。人面犬の檻。それとも、実験台として拉致された、この大学の学生。山本のクローン。佐藤のクローン。悪の総統が、きっと、ワインレッドの幕のむこうであざ笑っているのだ。わたしは、奈津美に話かけてごまかさず、二分間をたっぷり味わうことに決めた。心なしではなく、本当に肌寒い。地下だからそれはそうかと軽く納得しかけるが、いや、この下は巨大冷凍庫になっていて、ヒトラーの精子が保存されているのだ、と訂正する。わたしはそうやって、雰囲気を盛り上げようと、こわいほうに、こわいほうに自己暗示をかける。それはかなり成功しているらしく、体感時間はマラソンよりもひどい。
「はい、秒読み。じゅう、きゅう、はち」
奈津美は秒針に合わせ、冷酷にカウントダウンする。他愛ない、さっきの仕返しのようでもある。
「にい、いち、ぜろ」
わたしは、ボタンを押す。がこん、とどこかでエレベーターの箱が動き出す。しかし、それが上なのか、下なのか、あまりのしずけさに耳が馬鹿になっていたのと、たぶんわたしの足が多少ふるえていたせいで、はっきりしない。
「来た。乗る。はい、乗った」
「はいはい」
「ボタン押さずに待ってるんだけど、エレベーターに行き先を催促されるので、一階押すね。はい、押した。上がってます、たぶん。あ、ついた。扉が開いて、ええと、ふつうの、一階でした」
「よかったね。じゃあ、おやすみ」
「まあ、待ってよ」
「明日、仕事」
「その時計は正確」
「電波時計ですけど。電波時計って、正確なんでしょ。知らないけど。もらったやつ」
「そうか。いま、棟を出た。入ってくる人とすれちがった。研究室で飲み会でもするのだろうか、ビールをいっぱいふくろに入れてた。ごめんね、実況はしません。じゃあ、いったん切るね」
「いったんって」
「だから、次、UFO」
「おやすみ」
薄情なのではなく、本当に眠いのだ。いいかげん長い付き合いだから、ごはんを食べ終わったあたりから、もう声で分かっていた。四時でも五時でも、起きてさえいれば人に電話をかけてくるやつだが、自分が眠いときは容赦なく寝る。今日はわたしから話をしてくれとおねがいしたのだから、お店のことは一切口にせず、それをいいことに奈津美もなにひとつ触れなかったが、それはいいことなのか、悪いことなのか。その話もせねば、とは思うが、いまさら、新しい不安を掘りおこす気になれない。
すり鉢状の広場を通り抜け、図書館を見上げる。さすがにまっ暗だった。あまりじっと見ていると、なにか発見してしまいそうで、てきとうに目をそらす。図書館に置いてあるような本の作者は、たいてい死んでいるだろう、とまた不吉なことを思う。芥川龍之介、太宰治、三島由紀夫、川端康成、彼らの顔は、人面犬よりは、よほどわたしに親しい。死んでいることも確実なだけに、なんとなく思い浮かべただけだったが、けっこう真に迫ってこわい。全員自殺した作家だとあとで気づき、その瞬間、ちくちくする怨念を全身で感じる。
UFOは図書館に隠れて、見えない。そろそろ方角的には左に曲がらなければならないが、なかなか道が曲がってくれない。馬鹿馬鹿しいことをしている。もどるならいまだと思う。このまま突き進んで、それで、馬鹿馬鹿しい落ちが待っているだろうことも、いいかげん察している。池を横切ると、唐突に大学の施設がなにもなくなる。足もとにこまらないくらいには明るいが、変質者や犯罪者が安心して仕事できるくらいに、暗くもある。しかし、いま、わたしにとって、藤棚の影、自販機のすきま、月の裏、排水溝の底にひそんでいるかもしれないのは、ひたすら人面犬、宇宙人、ヒトラーの精子なのであって、説得も交渉もできるただの変質者などとは、わけがちがいすぎる。また橋がある。わたしは決して焦点をそこからずらさないように、わき目もふらず、一心に足を運ぶ。あやしまれてはならない、警戒されてはならない、と、万が一いるかもしれない都市伝説の産物たちに遠慮しながら、しかし、いつでも泣き叫び、逃げ出す準備はできていた。
わたしは、橋のまんなかを歩いた。この先は、もう大学の敷地ではないかもしれない。青白い明かりがここでもぽつり、ぽつりと人魂のように浮かんでいる。親切のようで、ぜんぜん親切ではない。木々の葉のあいだに見え隠れしながら、後ろへ流れ、たぶん半分も光は歩行者に届いてはいなくて、こわい雰囲気を演出する舞台効果でしかない。意思あるもののように、わたしを監視し続け、虎視眈々と、おどかすタイミングをはかっている。わたしはさっきから、携帯で奈津美の番号をコールし続けている。とっくに起きていなければおかしいが、まだまだ出てはくれないだろう。
林が切れる。なまぬるい空気のかたまりが、わたしの体をすりぬけていく。かすかな弾力のある夜の層へと、ここから、さらに深く入りこむのだと思う。一歩目の足を押し返されたわたしは、その入口で立ちすくむ。すかさず、蝉の声が、わたしを包む。じっとりと汗ばんだ肌は、夏の夜と同じ温度になっている。吸いこむ息も、吐く息も、あまったるい物質を大量に含んで、成分は、ほとんど同じと言ってよかった。ほどけて、溶けて、なくなってしまわないのは、ただ、手のなかでかすかに、奈津美へのコール音が聞こえるからだった。UFOが、見えた。もう近かった。首をそらさなければ、ほとんど真上を飛ぶそれを、視界に入れることができなかった。
どこをどう通ったのか分からない。それが道だったのかどうかも、あやしい。白い車線がぷっつりと夜を切断し、わたしの頭も、張りつめたひと筋の秩序をとりもどす。ここはもう大学ではないと、はっきりする。やっと、携帯が鳴りやんだ。
「もしもし」
「イグアナ」
「うるせえ。なんだ、般若」
「眠い」
「ちょうどよかった。いままさに、UFOの正体が分かるよ」
「ああそう。おやすみ」
「あと三分。すぐ。いま歩いてるよ。もう、すごい、空が明るいよ、ここまでくると。昼間みたい」
「酔ってんの」
「酔ってない」
「よけい悪い」
「けど、けっこう飲んだあとって、歩いたね。なつかしいね。あ、いま、ちょっと、本当になつかしくなってる。池袋から駅みっつって、けっこうあったね。かかって三十分くらいかと思ったら、三時間は歩いた。なんだか知らないけど、やたら歩いた。酔っぱらうと、むずむずするね。馬鹿ほど歩く。そんな気しない」
「する。すごく。いま、まさにね」
「なつかしいでしょ」
「まあ、ちょっとね」
「分かる、外いるの」
「なんとなく。ざわざわしてる」
「また、そういうことしようか。飲もうよ、みんなで」
「みんな」
「知り合いが多少できたから。ああ、たのしいね」
「眠い」
「さっきまでは、肝だめしだったよ。じゃあ、ちょっとあたりを描写しようか。くさい。ニワトリかなんかのにおいがする。生物学部の農場って、このへんかな。馬いるってさ、馬。今度、明るいときに来てみようかな。両側はたぶん研究所だと思うんだけど、暗くて分かんない。まあ、役所っぽい建物。まっ暗。一台、車が前から来た。飛ばしてるね。五十メートル先くらいで、ちょっと曲がってるっぽい。たぶん、そこだと思う。明るい。起きてる」
「起きてる。さっさとして」
「早歩きしてる。あ、だんだん、曲がってる。曲がって、曲がって、曲がって、駐車場が、駐車場だね、これ。ああ」
「なに」
「ああ」
「なに」
「ああ、としか、言えない。なるほどね」
「どうした」
「パチンコ」
「は。パチンコがどうした」
「パチンコ屋だった。でかいね。田舎だからか。ほかに娯楽がないんだよね。ちょっと近づいてみる。まだやってんのかな、照明がすごいんだけど。車もけっこうとまってる。やってんだ。あ、そうか、パチンコはやってない。スーパー銭湯っていうのかな、スパリゾートみたいのがくっついてる。ひょっとして二十四時間やってんじゃないの。うわあ、明るいな。サーチライト。広告みたいなもんか。みんなこれ目指して、車でやって来るわけか。なんか、すごいね。虫みたいな気分。まんまとおびき寄せられてしまった」
もう奈津美からは生返事さえなく、携帯を耳からはなし、ディスプレイを見れば、八月のカレンダーが海と山にはさまれているだけで、通話は、とっくに終了している。どこかの時点で、ひとり言にされてしまっていた。画面の隅で、麦藁帽子の子供が、駆け出そうとしている。虫とり網を肩に乗せているから、たぶん山に行くのだろうと思う。そうか、もう八月か、と少し前に、エレベーターのところで、七月と八月の国境をまたいでいたことに気づく。馬鹿馬鹿しさはともかく、こんなあっけない終わりに、ちっともがっかりしたような気持ちはなく、汗もかいたことだし、ちょっと入ってみようか、そんなことばかり、考えている。
雲に映ったサーチライトの光は、わたしには、まだしつこくUFOに見えている。なにもかも見破られたのに、開きなおったように、空を泳ぎ続けている。わたしは、さいふのなかを確認する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
