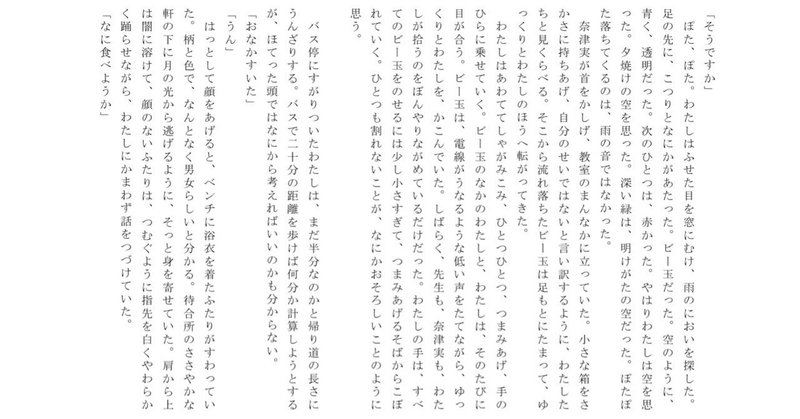
水族館物語(3)
バス停にすがりついたわたしは、まだ半分なのかと帰り道の長さにうんざりする。バスで二十分の距離を歩けば何分か計算しようとするが、ほてった頭ではなにから考えればいいのかも分からない。
「おなかすいた」
「うん」
はっとして顔をあげると、ベンチに浴衣を着たふたりがすわっていた。柄と色で、なんとなく男女らしいと分かる。待合所のささやかな軒の下に月の光から逃げるように、そっと身を寄せていた。肩から上は闇に溶けて、顔のないふたりは、つむぐように指先を白くやわらかく踊らせながら、わたしにかまわず話をつづけていた。
「なに食べようか」
「でもけっこう食べたよね」
「たこ焼きとか、かき氷とかだから、まだ入るよ」
「もうお金ない」
「じゃあいいよ」
「花火」
「なかったね」
「なんでだろうね」
「天気いいのにね」
「まあいいけど。また今度」
「今度、いつ」
「いつがいい」
「いつでもいい。来月、水族館ができるって」
「じゃあ、それ行こう」
「いいよ」
祭りでもあったらしいが、聞いたこともなかった。貴之もなにも言わなかったと思う。どこかへ遠出でもしたのだろうか。わたしのように、バスをのがして、ちょうどここで歩きつかれて休んでいたのだろうか。
風の筋がばらばらにほつれて、頬をなでる。のどが熱くなる。こんなに酔ったのははじめてだった。いっそ吐いてしまいたいのに、ベンチのふたりは、まだわたしに気づかないふりをつづけ、去ろうとしない。
「さっき売ってたよ、駅に。花火」
「そう」
「部屋のなかでやったことある」
「なにを」
「花火」
「ないよ」
「やろうか。きれいだよ、案外」
閉めきった台所でさみしく咲く線香花火を、わたしは知っている。おばあちゃんが、なにかの用事で家にいなかった。ふだんできないことをしようと、貴之は押入れから探しだした花火に火をつける。何年前のか分からない、色もあせた、線香花火のこよりだった。
田んぼにかこまれた田舎の一軒家にさす光は、たぶん、その夜は月さえも出てはいなくて、線香花火は、夜の深さにたえきれず、何度やっても自分の重さで落ちてしまう。闇は濃かった。貴之の背負った大きな影は、線香花火が燃えるあいだじゅう、肩をふるわせ、うつむいていた。わたしも同じ影を背負っているはずだった。線香花火が消えれば、わたしとわたしの影は夜に溶ける。貴之も、夜のなかでひとつになる。
「行こうか」
「ちょっと待って」
「そんなのほっとけよ」
「でも」
「行くよ」
「待ってよ」
げたの音が、小刻みに、男のあとを追いかけていった。男は大またに、なにかを思い出したのか、聞きのがしたわたしには分からなかったが、ずいぶん急いでいるらしかった。藍色の男の浴衣が、まず見えなくなった。女のほうの白地の浴衣は、小さな点になっても、それでも消えようとはせず、わたしは、どうして、と思いながらめまいと吐き気の発作に歯を食いしばっていた。しばらく、女の足音だけが耳の底に残っているようだった。わたしは声をかければよかったと後悔しているが、なんと言ってやればよかったのかは、まるで分からない。
わたしはベンチにすわった。もたれた背中がだらりと後ろに折れ、どうすることもできず、このまま休んでいるよりしかたがなかった。眠ってしまうとあとがめんどうだと思った。どうやらもう目は閉じてしまっているらしく、時間の問題だとあきらめかけてもいた。
「遅かったね」
夢うつつにわたしの耳にとどいた声は、それでも弥子のものだとはっきり分かる。
「ああ、置いていかれちゃった」
「そう。弥子」
「さみしいね」
「ひどいね」
さっきのふたり、弥子の両親にしては若いような気がした。お兄さんとお姉さんでも、なにか変だと思う。
「ねえ、こんな時間までなにしてたの」
「お店の手伝い。そのあと、お酒を飲んだ」
「それで」
「それだけ。終電に間に合えばいいと思ってたら、バスは八時くらいで終わるでしょ。田舎だね。どうしようもないよ。弥子は」
「別に」
「子供のくせに」
「たいくつだから、散歩してる。最近、寝れない」
わたしの首筋に冷たいものが触れた。びっくりした声を上げるのもめんどうだったが、弥子はしつこい。おそるおそる目をあけると、まっ赤な金魚の尾びれが鼻先をなでて泳いでいった。透明なビニールのなかでかすかな光は複雑に反射して、金魚をはさんでにやにやと笑う弥子の顔が、ふと泣いているように見えた。置いていかれたというのが金魚のことだったと、ようやく分かる。
「もらってもいいかな」
わたしにはなにも言えなかった。
「かわいそう。きれいなのに」
今日、わたしは貴之といっしょに水族館を見てまわった。まだどの水槽もからっぽだった。ときどきすれちがう工事の人たちが、青白い顔をしてわたしたちを振り返る。もともと水族館がしずかなことは分かりきっていた。魚は人間のようにことばを必要とはせず、しずかに水のなかを泳いでいればそれでいい。さみしいのは水槽がからっぽなせいではなくて、わたしたちになにも話すことがないからだった。金魚、三匹、知らん顔で、両手におさまるほどのわずかな容積を、夢見るように泳いでいる。
「弥子は、家はどこ。帰ろう」
「おしえない」
「どうして。いっしょに帰ろう。もう寝なきゃ」
「ずっと寝てないから、今日も寝なくていい。帰らなくてもいい」
「心配するよ、お父さんとお母さんが」
「しないと思うよ。たぶん。いま、誰も家にいないと思う」
弥子は、金魚のふくろを、わたしにつきつける。目のなかで金魚たちが燃えている。線香花火よりもたよりなく、いまにも途切れてしまいそうなのにふらふらと動きまわるのをやめない。なにかを照らすこともできず、置き去りにされて、消えていくだけの運命だとしても、わたしはこうして目に焼きつけることしかできない。
酔いはさめていた。わたしは、早く帰りたかった。なにかを言わなければならないことは分かっていた。結局わたしが弥子にかけたことばは、うんざりするほどありきたりなものでしかなかった。
「わたしの家もそう。親たちはわたしのことなんかほっといて、いつもけんかしてた。それで、離婚した」
「それで」
「それで、ええと、再婚した。あたらしいお父さんができた。お兄さんもできた」
「よかったじゃない」
「よくはないけど」
「わたしも、あたらしいお父さんとお母さんができるといいけど」
「できないほうがいいんだよ」
こんな話をするのはいやだった。なにが言いたいのか、自分でも分からない。ふだんのように、なんでもないようにとりつくろうと思う。しかしいつもは、わたしと弥子は話らしい話などしたりせず、ぶらぶら歩きながら呼吸するように感じたことを少しずつこぼしていくだけだった。帰ろう、とたったこれだけでさえ、弥子とのあいだにはありえない、あってはならないやりとりだった。
わたしの目のなかで、金魚たちが燃えている。しめった空気に影をにじませて、しだいに火は視界全体に広がり、もう金魚は、せまいふくろのなかに閉じこめられることもなく、自由にまっ赤な闇のなかを泳いでいた。
「帰ろう、もう。朝になるよ」
「帰るよ。でも、バスを待ってるの」
「来ないよ」
「来ると思うの。もうすぐ」
弥子は浴衣を着ていた。やはり祭りはあったらしい。でも、花火はあがらなかったんだ。
「そんな怪談があったね。なんだったかな」
「なにそれ」
「忘れた」
乗客はきっといないだろう。窓からもれる光に、わたしたちは目を細めるだろう。からっぽの容積に、わたしは水槽を思い出すにちがいない。わたしたちはどこへでも行ける。しかし、そんなバスは決して来ないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
