
アルバムレビュー「SYR4: Goodbye 20th Century / Sonic Youth」
昨年、Sonic Youthのアルバム「SYR4: Goodbye 20th Century」を初めて聴いて、非常に感銘を受けました。
Sonic Youthは、1981年に結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドです。オルタナティブロック界では非常に有名なバンドで、歪み・ノイズを強調したギターサウンドや実験的な音楽性が特徴的です。
「SYR4: Goodbye 20th Century」は、1999年に発売されたアルバムです。1950~1990年代に作曲された13曲の前衛的なクラシック(?)音楽をカバー、というか実演した内容になっています。内容が内容だけに各種レビューサイトでも賛否はかなり分かれているようで、大手レビューサイトの1つであるAllMusicでは5点満点中1.5点と低評価な一方、同じく大手のPitchforkでは10点満点中8.5点と、かなりの高評価です。
※参考までに、Sonic Youthの代表的なアルバム「Daydream Nation」は、ほとんどのレビューサイトで満点の評価になっています。
ジャンル的には一応広い意味での「ポピュラー音楽」になるとは思うのですが、相当に前衛的なアルバムなので、前提知識が無いと十分に堪能できそうにないと感じました。上記のPitchforkのレビューでは、「このアルバムは非常に難解であり、常に「音楽とノイズ」「構造と無秩序」の境界線を考え続けなければ、真に聴いているとは言えない」といった内容が書かれています。
Goodbye 20th Century is difficult music: (中略) you must rethink your categories every minute, you must continuously reassess the boundaries of music and noise, structure and disorder. But if all you hear is dissonance and feedback and Kim Gordon's hot, ghostly musings, you're not listening.
なので、各楽曲について、Web上で調べられる範囲で情報収集してみました。情報量は多くはなく、短期間で調べただけなので正確性も定かではありませんが、日本語の解説はWebではなかなか見当たらなかったので、調べた内容を記録に残しておこうと思い、記事を書くことにしました。もしもこの記事を読んで、このアルバム、もしくは何かしらの前衛音楽に興味を持っていただける方が少しでもいらっしゃれば嬉しく思います。
出典はほとんどがWebサイトからの情報です。その他、書籍からの情報も時々記載しています。出典は極力記載するようにしていますが、情報の信憑性が定かではない、ということには注意していただきたいです。
1. Edges
1.1. 作曲家「クリスチャン・ウォルフ」についての解説
アメリカの作曲家、クリスチャン・ウォルフ (1934年~)によって、1968年に書かれた作品です。クリスチャン・ウォルフはゲスト演奏者としてこのアルバムにも参加しています。
クリスチャン・ウォルフはフランス生まれ(ドイツにもルーツあり)ですが、戦争を機にアメリカに渡り、当時の前衛音楽家と出会い、影響を受けました。同時代のアメリカの作曲家ジョン・ケージ、モートン・フェルドマン、アール・ブラウン、デヴィット・チューダーと共に「ニューヨーク楽派」と呼ばれることもあります。その後、コーネリアス・カーデューとの出会いなどを通じて、より政治的な事柄に関心を持つようになったそうです。書籍「現代音楽史 (沼野雄司 著)」によると、「不確定でゲーム的な要素を持った作品からは、社会における個人の自由、といった左翼的なモチーフが明らかに見て取れる」とのことです。
Wikipediaによると、クリスチャン・ウォルフは1957年から1968年にかけて、自らの作品に「図形楽譜」を用いることを考案した、とのことです。図形楽譜とは、五線譜ではなく自由な図形などを用いて書かれた楽譜のことを言います。五線譜では表現しきれない新しい音楽を創造する手段として、先に述べたニューヨーク楽派の作曲家や、その他様々な作曲家たちが図形楽譜による作曲を試みています。クリスチャン・ウォルフに関する研究論文(久保田翠 著)によると、この年代のウォルフの図形楽譜には「比率ネウマ」「キューイング」「コーディネート線」という3つの特徴的な手法が用いられているそうです。これらの手法は、演奏者同士が互いに反応し合って生み出される「コントロールされた即興」を楽譜上で表現するために用いられました。ただ、このアルバムに収録されている楽曲「Edges」は、調べる限りでは「コントロールされた即興」ではなく、より自由な即興が求められる作品のようです。
1.2. 「Edges」の作品解説
「Edges」の楽譜は、Web上では断片的な情報しか得られませんでしたが、以下のような感じの内容だと思われます。

五線譜ではなく、上記画像のような図形楽譜で書かれている。
楽譜上には25個(?)の記号がまばらに配置されている。これらの記号を各演奏者が解釈して演奏する。
実際の楽譜には、図形楽譜の譜面のみでなく、各記号についての言葉による説明が付与されているらしい。
各記号は「演奏指示」ではなく、「空間を区切り、点・面・道筋・境界を示すためのもの」である。演奏者はその空間の中、もしくは空間の周囲を移動しながら演奏する。他の演奏者が演奏している記号を「キュー」(合図)として、それに反応するように演奏しても良い。もしくは、単に記号を演奏するだけでもいい。
最後の項目はクリスチャン・ウォルフによる指示だそうです。かなり難解で抽象的ではありますが、楽譜に書かれている記号を各演奏者が独自に解釈して即興演奏することが求められているようです。文中にある「キュー」というのは、恐らく上述の「キューイング」の意味で用いられているのだと思われます。上述の研究論文によると、「キューイング」とは、他の人の演奏が特定の条件に当てはまると自分が認識したら、次の記号を演奏する、というような方式の即興に関する記譜法です。例えば、他の人がff(フォルティッシモ)で演奏していことを「認識」した時に、自分は別の記号を演奏し始める、といった感じです。
「Edges」に関する内容は以上ですが、参考までに、クリスチャン・ウォルフの求める即興性が分かりやすい別の曲「Stones (1969年)」の例を挙げます。「Stones」の楽譜は、文章による指示のみで書かれています。Webで調べると、このような楽譜の形態を「Text Score」や「Prose Score」と呼んだりするようですが、この記事では便宜的に「テキストスコア」と表現します(より適切な表現方法をご存じの方は、ご教授いただけますとありがたいです)。「テキストスコア」による楽曲を多く書いている作曲家として、ポーリン・オリヴェロス等が挙げられます。
「Stones」の指示は以下のような内容です。
さまざまなサイズや種類(および色)の石を使用して、音を立てたり、音を引き出したりしてください。
ほとんどの場面では不連続に、そして時々は素早いシーケンスで演奏してください。
ほとんどの場面では石同士を打ちつけますが、他の表面(ドラムヘッドの内側など)に打ちつけても良く、打ちつける以外の方法(弓で叩く、アンプを使う、など)で音を出しても良いです。
何も壊さないようにしてください。
こちらが実際の演奏動画です。
「石」を楽器として用いた、静的な即興的演奏が展開されています。
1.3. 楽曲の楽しみ方の一例
「Edges」の演奏は16分程度と長く、全体的に抽象的なサウンドが鳴り続けている印象です。とは言え、基本的には楽譜に基づいて各自が即興的に演奏を行っているはずです。楽曲の楽しみ方について、私なりに以下のような一例を考えてみました。
単純にノイズ音楽の即興として楽しむ。
それぞれのサウンドがどのように作り出されているのかを想像してみる。
作曲家本人も参加している、というありがたみを持って聴く。
キム・ゴードンの声に癒される。
なお、キム・ゴードンの歌詞(語り?)の内容は、「ゴルディロックスと3匹の熊」という童話の断片だそうです。イギリスでは有名な童話らしいです。
1.4. 演奏者 (Sonic Youthの公式サイトより)
Thurston - ?
Kim - vocals/?
Lee - ?
Steve - percussion
Christian Wolff - ?
Jim O'Rourke - ?
Takehisa Kosugi - violin
William Winant - ?
2. Six (3rd Take)
2.1. 作曲者「ジョン・ケージ」についての解説
アメリカの作曲家、ジョン・ケージ (1912年~1992年) によって、1991年に書かれた作品です。
ジョン・ケージはロサンゼルス生まれの作曲家です。「Edges」の項目でも説明しましたが、クリスチャン・ウォルフなどと共に「ニューヨーク楽派」と呼ばれることもある作曲家で、その中では恐らく最も有名だと思われます。1930年代にアドルフ・ワイスやアルノルト・シェーンベルク等に師事した後、実験的な作曲手法に傾倒するようになりました。1939年頃には、グランドピアノの弦にゴム・ネジ・ボルトなどの異物を挟んで音色を変化させた「プリペアド・ピアノ」を考案し、自らの作曲に用いるようになりました。その後、東洋思想から影響を受けて、コイン投げによって音を決めた「易の音楽 (1951年)」や、演奏者が何もしないことで非常に有名な「4分33秒 (1952年)」等の楽曲を発表しました。また、同時期に図形楽譜による作曲も始めています。
ジョン・ケージの楽曲の思想として、作品の音響結果のコントロールをせずに、単に何かが起こる「場」を提供する、というものがあるそうです。2021年に東京で開催されていた「サウンド&アート展」の目録に、ジョン・ケージ等の実験音楽作曲家に関する記載があります。
ここで重要なのは、ケージ的な実験音楽において重要なことは、環境音・静寂・作曲者の意図を反映しない音など「音の全領域」を取り扱うために、最終的な音響結果に対するコントロールを拒否したこと、である。(中略) 作曲家の仕事は「最終的な音響結果を指定すること」ではなく、「音響結果が生成される機会、状況、場所、プロセスを設定すること」に変化した。音楽作品は、作曲家が作り出すオブジェではなく、音が移りゆくプロセスになった、そうした音楽作品を聴く際には、作曲家の設定した音と音との関係性を審美的に読み解くのではなく、「ただ音の営みに注意を向けること」、つまり音のプロセスから意味や意義を聴き出していく能動的な聴取行為が要請されるようになった。
ジョン・ケージの音楽を真に鑑賞するためには、即興や、さらに言えば「偶然」によって紡ぎ出される音に耳を傾け、その意義を理解しようとする必要があるのかもしれません。
また、このような音楽においては、演奏者にも一般的なクラシック・ロックなどの枠から外れた先進的な音楽への造詣が求められます。従来から特殊奏法や電子的な技術に優れているSonic Youthのメンバーは、ジョン・ケージの作品を演奏、ひいては共に創り上げていくアーティストとして非常に適しているように感じられます。
2.2. 「Six (3rd Take)」の作品解説
「Six」はジョン・ケージの最晩年の作品です。「Number Pieces」という、数字のみのタイトルを持つ作品群の中の1つです。タイトルの数字は演奏人数のことを表しており、Sixは「6人で演奏する」という意味になります。元々は打楽器奏者6人向けの曲ですが、Sonic Youth版では打楽器をメインとしながらもギターやバイオリンらしき音も入っています。
「Number Pieces」の作品群は40曲程度作られています。作品の大部分は、「タイムブラケット技法」を使用して作曲されているそうです。以下、「Number Pieces」の作品群について解説しているWebサイトの引用です。
ケージがこのシリーズで「発明」した作曲技法は〈タイム・ブラケット〉というものです。楽譜上には、音程・音価・強弱や表情記号の付された一音もしくは和音が、それぞれ作品中の何分何秒から何分何秒までの間で演奏されるべきかが記されています。そのとき実際に出す音のタイミングは、演奏者が、自由に判断して決めます。つまり、ある程度の時間の枠は正確に与えられていますが、いつ音が鳴り響き、前後の沈黙が続くのかは、すべて演奏者の判断に委ねられています。各奏者は手元のストップウォッチを見ながら、個々の音を、決められた「時間の枠内」で自由なタイミングで出現させて、音を奏でていきます。
楽譜が入手できなかったため詳細は不明ですが、即興性の強い楽曲ながらも、それぞれの演奏者が音を出すタイミングについては、ある程度の枠が決められているようです。
Sonic Youthは「Six」を4テイク分録音したそうです。このアルバムには、「Six」の3rd Takeと4th Takeの2つが収録されています。4th Take (アルバムの8トラック目)は、LP版では3:02の長さになっているらしいですが、なぜかCD版の音源では約1分短い2:10で終わっています。
2.3. 楽曲の楽しみ方の一例
静謐なノイズサウンドを楽しむ。穏やかで比較的聴きやすい楽曲かもしれない。
印象的なギターのアルペジオサウンドを楽しむ。
3rd Takeと4th Takeの聴き比べをしても面白いかもしれない。
なお、上記の解説サイトによると、「〈ナンバー・ピース〉の演奏時には、つねに緊張感と生気に満ちた沈黙が出現します。ケージ自身、そこに日本の能を思わせる、静謐のなかで凝縮されたエネルギーが律動する世界を見出していたようです。」とのことです。
2.4. 演奏者 (Sonic Youthの公式サイトより)
Thurston - ?
Lee - ?
Steve - ?
Jim O'Rourke - ?
Takehisa Kosugi - ?
William Winant - ?
3. Six for New Time
3.1. 作曲者「ポーリン・オリヴェロス」についての解説
アメリカの作曲家、ポーリン・オリヴェロス (1932年~2016年) による、このアルバムのために1999年に書き下ろされた作品です。
ポーリン・オリヴェロスは、アメリカの電子音楽における重要な作曲家の一人です。1961年にサンフランシスコ・テープ・ミュージック・センター(SFTMC)という電子音楽のスタジオの立ち上げ初期メンバーに加わったり、1964年にミニマル・ミュージックの大御所作曲家テリー・ライリーの「In C」という楽曲の初演に(後述する作曲家スティーブ・ライヒと共に)参加したりしました。また、上述のニューヨーク楽派の1人デヴィット・チューダーとも交流があり、彼のために「テキストスコア」による作品を書いたこともあるようです。
ポーリン・オリヴェロスの作品例として、1961年に作曲された「Sound Patterns」という無伴奏混声合唱曲では、電子的に生成されるサウンドを声などで模して表現しています。Wikipediaによると、曲中では「ホワイトノイズ」「リングモジュレーション」「エンベロープ」「フィルター」を模した手法が用いられていることが、後の研究者によって指摘されています。他にも「Sonic Meditation」という「テキストスコア」による作曲シリーズがあります。また、1988年ごろに、音楽と瞑想を組み合わせる「ディープ・リスニング」という用語を生み出し、その後研究や実演を進めていました。
以下、ポーリン・オリヴェロスの「テキストスコア」による作品例を2つ挙げます。 何となく、クリスチャン・ウォルフの即興とは異なる瞑想的なニュアンスが分かるかもしれません。
(1) In Consideration of the Earth (1998年)
参考演奏その1.
参考演奏その2.
楽器または声によるソロ演奏曲です。具体的な音が記載された楽譜は存在しないため、2つの動画で全く異なる演奏内容になっていることが分かります。テキストによる指示は、概ね以下のような内容です。
はじめに東を向く: 東の気分に則して演奏する。東の性質と触れ合う。
次に南を向く: 南の気分に則して演奏する。南の性質と触れ合う。
次に西を向く: 西の気分に則して演奏する。西の性質と触れ合う。
次に北を向く: 北の気分に則して演奏する。北の性質と触れ合う。
次に中心を向く: 中心の気分に則して演奏する。中心の性質と触れ合う。
(2) Rock Piece (1979)
参考演奏 (動画内の23:30頃~)
上述したクリスチャン・ウォルフの「Stones」と同じYouTube動画です。「Stones」からシームレスに続けて演奏されています。瞑想、という文脈で書かれた曲ではありますが、演奏される内容としてはクリスチャン・ウォルフの即興的作品「Stones」と似ているのが興味深いと思います。テキストによる指示は、概ね以下のような内容です。
各参加者は、共鳴する石のペアを、パーカッションとして使用する。各参加者は自身の石と独自にパルス(拍、といった意味?)を確立する。 パルスはリズム的な解釈やアクセントを加えずに、安定して維持する必要がある。全体の音を聞きながら、他の参加者のパルスと自分のパルスが同期している、または単純な2や3の倍数・約数になっていると知覚した場合、一度よく聞くために止まり、他の全てのパルスとは関係のない新しいパルスを開始する。はじめに、参加者は演奏場所全体に移動して散っていっても良い。そうして環境内に存在するパルスを聞いた後、各参加者はそれぞれ独自に、もしくは何かしらの合図に従って演奏を開始する。その後、参加者たちはゆっくりと自由に動き、石のパルスの音を環境の全方位に響かせ、徐々に円の形に密集しながら終わりを迎える。参加者はそれぞれ独自に終了しても、合図に従って一斉に終了しても良い。「Rock Piece」は屋外で開始されて屋外にとどまっても良いし、屋内に移動していっても良い。逆に、屋内で円形に密集した状態で始めて、すべてのパルスが聞こえなくなるまで徐々に屋外に移動していっても良い。
3.2. 「Six for New Time」の作品解説
「Six for New Time」は、アルバム「Goodbye 20th Century」の中で唯一の書き下ろし作品です。タイトルは、同アルバム内のジョン・ケージの楽曲「Six」が意識されているのかもしれません。明確なリズムが感じられる箇所も多く、実際のSonic Youthの楽曲に近い雰囲気です。
この楽曲も「テキストスコア」で書かれているようです。内容はWebで調べてもわかりませんでしたが、楽譜はWebで購入可能なようでした。購入してみれば内容はわかると思いますが、値段が高いので購入していません。また、Webで購入できるポーリン・オリヴェロスの「テキストスコア」のアンソロジー集にも掲載されているようです。10,000円程度の高額な書籍ですが、100曲程度が収録されているので、気になる方はご検討ください。
楽曲の歌詞は、作詞家・劇作家で、ポーリン・オリヴェロスのパートナーであるIone (1937年~) によるテキストです。
3.3. 楽曲の楽しみ方の一例
ノイズロックとして音色の変化を楽しむ。
無調音楽の音組織を楽しむ。
結構盛り上がるので、普通に格好良い曲として聴く。
アルバムの中でも比較的聴きやすい楽曲だと思います。個人的に好きなトラックです。
3.4. 演奏者 (Sonic Youthの公式サイトより)
Thurston - vocals/guitar
Kim - guitar
Lee - guitar?
Steve - percussion
Jim O'Rourke - electronix
William Winant - percussion
4.+-
4.1. 作曲者「小杉武久」についての解説
日本の作曲家、小杉武久 (1938年~2018年) によって1987年に書かれた作品です。小杉武久は、バイオリニストとしてゲストでこのアルバムにも参加しています。
小杉武久は東京藝術大学出身で、在学中から即興演奏グループを結成して活動していました。1960年代前半にニューヨークに滞在し、フルクサスという運動に参加しました。フルクサスとは、1960年代から1970代にかけて発生した、芸術家、作曲家、デザイナー、詩人らによる前衛芸術運動のことを指します。フルクサス作品は、基本的には単純な指示を演奏者が淡々とこなすだけの内容です。書籍「やさしい現代音楽の作曲法 (木石岳 著)」によれば、フルクサスの創始者の一人とされるジョージ・マチューナスによる定義は以下のような内容です。
単一の構造を持つ(単純な自然の出来事、ゲーム、ジャズ)。
わざとらしさをもたない性質を獲得しようと努力する。
「フルクサス」という言葉は、1962年9月にリトアニア出身のジョージ・マチューナスが提唱したとされており、西ドイツのヴィースバーデン市立美術館で「フルクサス国際現代音楽祭」(全4回)を企画したのが始まりとされています。ただ、実際にはこれ以前から、ジョン・ケージ、ラ・モンテ・ヤング、オノ・ヨーコといった複数の作曲家やアーティストによって、フルクサス的な作品が作られ、上演されてきていました。
フルクサスの作品例として、ラ・モンテ・ヤングが1960年に作曲した「Compositions 1960」シリーズが挙げられます(1962年に「フルクサス」という言葉が提唱される以前の作品です)。日本の作曲家、川島素晴のブログ記事に解説がありますが、以下にブログに掲載されている楽曲の概要を抜粋します(以下はあくまで概要で、実際の楽曲にはもう少し細かな指示が記載されているようです)。
《Compositions 1960 #2》火をたく
《同 #4》アナウンスした演奏時間のあいだ、全ての照明を消す
《同 #5》会場に蝶を放つ
《同 #6》舞台から客席を(客席から舞台を観るように)観る
《同 #7》完全5度(ロ、嬰ヘ)をできるだけ長く延ばす
《同 #10》直線をひいてそれを追う
《同 #13》任意の楽曲を可能な限りうまく弾く
なお、この引用元の記事は、2020年に実際に川島素晴が自身の主催するコンサートで「Compositions 1960 #6」を実演した際の解説記事です。コンサートのコンセプトは「無音」ということで、ジョン・ケージの「4分33秒」や、エルヴィン・シュルホフの「5つのピトレスクより 第3曲「未来に」」などの、無音、ないし事実上無音と解釈できる楽曲をたくさん集めて2時間ほど掛けて実演する、という凄まじい内容だったようです。怖いもの見たさで訪問してみたかったですね。
小杉武久に話を戻すと、1964年に書かれたフルクサス作品「革命のための音楽」が(ネタ的な意味も含めて)まあまあ有名です。楽譜(テキストスコア)は非常にシンプルで、日本語に訳すと以下のようになります。
「今から5年間、片目を抉り出しておく。5年経過したら、反対側の目についても同様のことを行う。」
非常に危険な危険なのでまだ演奏されたことは無いようです。良い子は決して真似しないでくださいね。このように演奏が事実上不可能な作品を書くのも、フルクサスの醍醐味と言えます。この作品は、Wikipediaの「演奏時間の長い曲」の項目にも記載があるのですが、実際のところ音楽的な要素は非常に少ないと言えます。そもそもフルクサス作品が音楽と言えるのかどうかは非常に議論の余地がありますが、書籍「やさしい現代音楽の作曲法 (木石岳 著)」に書かれている所によれば、少なくとも表面上は音楽作品だという認識である程度一致しているようです。
フルクサス関連以外では、小杉武久は1969年に音楽グループ「タージ・マハル旅行団」を結成しました。電子音響・フリージャズの要素が取り入れられた即興集団です。この時代付近では、ギタリストのデレク・ベイリーのグループなど、前衛ジャズと前衛音楽が融合した即興集団が世界各国で結成されているようです。私自身、タージ・マハル旅行団の演奏音源は少しだけ聴いたことがありますが、このアルバムの雰囲気とも似た即興演奏が行われています。私はまだ詳しくはありませんが、日本の電子音楽や即興音楽の歴史についても、色々と調べて行くと面白そうに感じられます。特に日本のノイズ系・即興系の音楽は、Sonic Youthにも多くの影響を与えているようです。
4.2. 「+-」の作品解説
作品名の「+-」は「プラスマイナス」と読みます。以下の画像の通り、+と-の記号が並んだスコアです。
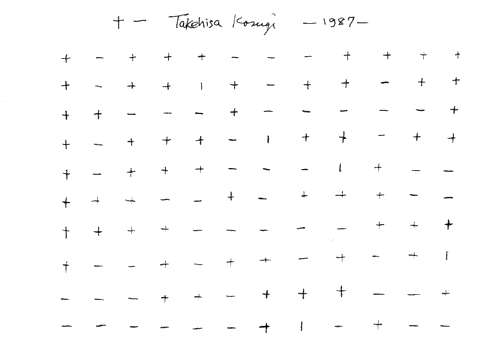
この曲は、元々フルクサス運動の一環として作曲されていたそうです。ただし、1987年当時ではすでに運動が縮小傾向にありました。12 x 10のグリッドに、+と-の記号(と、所々に縦線"|"(パイプ)記号)が書き詰められており、他に指示などは無いようです。明確な楽譜があり、ある意味ではしっかりと構成されていると言えるかもしれませんが、基本的には演奏者が自由に解釈しなければならない作品になります。
4.3. 楽曲の楽しみ方の一例
例によって普通にノイズの即興音楽として楽しむ。
+と-の記号の解釈を想像して聴いてみる。
実際に聴いてみると、何かしらの音色が+と-の要素を持って変化していたり、演奏要素が+と-の切り替わりのように急激・離散的に変化したりしているように感じられなくもないです。 …が、正直よくわかりません。 電気的なノイズサウンドの変化を楽しめる楽曲だと思います。
4.4. 演奏者 (Sonic Youthの公式サイトより)
Thurston - guitar?
Kim - guitar
Lee - guitar?
Steve - percussion
Jim O'Rourke - electronix?
Takehisa Kosugi - violin
William Winant - percussion
5. Voice Piece for Soprano
5.1. 作曲者「オノ・ヨーコ」についての解説
日本の作曲家、オノ・ヨーコ (1933年~)によって1961年に書かれた作品です。
オノ・ヨーコは、イギリスのロックバンド「The Beatles (1960年~1970年)」のメンバーであるジョン・レノンの配偶者として有名ですが、実際にどのような芸術家なのかについてはあまり知られていないように思われます。私も今回調べてみて、初めて知ることが多かったです。
オノ・ヨーコは東京生まれです。家族の仕事の都合で日本とアメリカを行き来していました。20歳の時にアメリカのサラ・ローレンス大学に入学しましたが、在学中の1956年に作曲家の一柳慧と出会い、同大学を退学し結婚して、前衛芸術活動を開始します。その後、前述したフルクサスの創始者とされるジョージ・マチューナス等と共に活動を行いました。例によってニューヨーク楽派のジョン・ケージなどからは大きな影響を受けているようです。
芸術作品としては1960年代にフルクサス作品を多く発表しています。また、ジョン・レノンと共作、もしくは単独での楽曲も多く発表しています。The Beatlesの音楽にも多くの影響を与えており、前衛的なミュージック・コンクレート作品「Revolution 9」の制作ではジョン・レノンのサポートを行っています。「Revolution 9」は、The Beatlesの後期のアルバム「The Beatles (1968年)」(通称ホワイト・アルバム)に収録されていますが、私自身はこの楽曲を高校生の時に初めて聴きました。サンプリングされた複数の理解不能な響き鳴り続ける楽曲展開に非常に衝撃を受けたことを覚えているのですが、その後、大学生になってミュージック・コンクレートなどの前衛音楽の歴史について知った際に、この曲のことを思い出してさらに衝撃を受け、The Beatlesの偉大さを感じました。
5.2. 「Voice Piece for Soprano」の作品解説
「Voice Piece for Soprano」はフルクサス作品で、英語版Wikipediaには単独記事もありますが、実際の所、正当な意味で「音楽」と言えるのかどうかは微妙な所のある作品です。楽曲の指示は以下のような「テキストスコア」による内容です。
風に向かって叫ぶ。
壁に向かって叫ぶ。
空に向かって叫ぶ。
楽曲の歌詞解説サイトのGeniusによると、オノ・ヨーコ自身はこの楽曲を実際にスタジオアルバムに録音したことはないそうです。同サイトの解説には「このアルバムでの録音は実際にはある種の冗談のようなものだが、音楽の限界についての非常に興味深いメタステートメントでもある」とあります。
Ono herself never actually recorded it in any of her studio albums. Electing it as one of the key pieces of 20th Century avant-garde music and comiting it to record, as done here, is actually a sort of tongue-in-cheek but also deeply interesting meta-statement on the limits of music.
また、この作品は、ニューヨーク市近代美術館(MoMA)で開催されたオノ・ヨーコの2015年の回顧展の際に実演されたこともあります。YouTubeに実際の動画が投稿されています。その際には、来場客もマイクに向かって叫んで実演することができたそうです。
Sonic Youth版では、キム・ゴードンとサーストン・ムーアの娘のココ(当時5歳)による演奏(?)になっています。ココが非常階段で叫ぶという内容で、17秒で終わる短いトラックです。
5.3. 楽曲の楽しみ方の一例
5歳の女の子が家族に見守られながら叫んでいる場面を想像すると、微笑ましく思う。
短い楽曲なのですぐに聴き終わります。私自身にも小さい娘がいるので、暖かい気持ちで聴くことができます。
5.4. 演奏者 (Sonic Youthの公式サイトより)
Coco Hayley Gordon Moore - scream
6. Pendulum Music
6.1. 作曲者「スティーブ・ライヒ」についての解説
アメリカの作曲家、スティーブ・ライヒ (1936年~) によって1968年に書かれた作品です。後に1973年に改定されたそうです。
スティーブ・ライヒは、ジョン・ケージと同様、現代音楽の作曲家としてはかなり有名だと思います。ジョン・ケージは代表作「4分33秒」で、ある意味ネタ的にも有名な訳ですが、スティーブ・ライヒはシンプルに「調性のある、聴きやすい楽曲が多い」という点で人気があります。最小限の音型パターンを何度も反復させていく音楽「ミニマル・ミュージック」と呼ばれるジャンルの先駆者的存在である作曲家です。
スティーブ・ライヒは、ジュリアード音楽院などで作曲の教育を受けましたが、十二音技法をはじめとするヨーロッパ的なアカデミズムが肌に合わず、やがて録音テープをループさせて繰り返す、という手法を試すようになりました。例えば代表的な作品「ピアノ・フェイズ (1967年)」は、2台のピアノによる連弾作品ですが、ユニゾンで同じ旋律を何度も繰り返すうちに、第2ピアノのみが少しずつテンポを速め、音型の組み合わせを変化させていく、という内容の作品です。初めて聴くと、まるで手品のような音の変化にかなり驚くと思います。
他にも、調性的で聴きやすい作品が多いです。個人的には、パット・メセニーのギター多重録音による「Electric Counterpoint (1987年)」が非常に好きで、大学生の頃によく聴いていました。楽曲もさることながら、パット・メセニーの爽やかで綺麗なギターサウンドがとても素敵です。大学時代に、今は閉店してしまった御茶ノ水のレンタルCDショップ「ジャニス」まで、当時住んでいた国立(くにたち)からJR中央線でわざわざ行ってCDを借りてきたことをよく覚えています。懐かしいです。
6.2. 「Pendulum Music」の作品解説
作品名の「Pendulum Music」は、「振り子の音楽」という意味です。この楽曲も、英語版Wikipediaに単独記事があります。正式なタイトルは「Pendulum Music (For Microphones, Amplifiers Speakers and Performers)」だそうです。
「Pendulum Music」は「テキストスコア」による指示で演奏される作品ですが、これまで述べた楽曲の「テキストスコア」に見られたような即興的な内容ではなく、演奏のための具体的な手順が指示されています。以下、スコアを引用します。
“2, 3, 4 or more microphones are suspended from the ceiling by their cables so that they all hang the same distance from the floor and are all free to swing with a pendular motion. Each microphone’s cable is plugged into an amplifier which is connected to a speaker. Each microphone hangs a few inches directly above or next to it’s speaker.
The performance begins with performers taking each mike, pulling it back like a swing, and then in unison releasing all of them together. Performers then carefully turn up each amplifier just to the point where feedback occurs when a mike swings directly over or next to it’s speaker. Thus, a series of feedback pulses are headed which will either be all in unison or not depending on the gradually changing phase relations of the different mike pendulums.
Performers then sit down to watch and listen to the process along with the audience.
The piece is ended sometime after all mikes have come to rest and are feeding back a continuous tone by performers pulling out the power cords of the amplifiers.”
日本語訳: 2つ、3つ、4つ、もしくはそれ以上のマイクをケーブルで天井から吊り下げる。すべてのマイクは床から同じ距離に吊り下げられ、振り子のように自由に揺れることができる状態になっている。各マイクのケーブルは、スピーカーに繋がったアンプに接続される。各マイクはスピーカーの数インチ真上、または隣に吊り下げられる。
演奏者がそれぞれのマイクを手に取り、ブランコのように後ろに引き、一斉にマイクを放すことによって、演奏が開始される。次に、演奏者は、マイクがスピーカーの真上または横に来た時にフィードバックが発生する程度まで、各アンプの音量を慎重に上げていく。そうすると、一連のフィードバックのパルス(振動)の先頭は、異なるマイクの振り子の位相関係が徐々に変化することによって、すべてが一致するか一致しないかのいずれかになる。
その後、出演者は座って観客と一緒にそのプロセスを見たり聞いたりする。
すべてのマイクが停止して連続音をフィードバックするようになった後、演奏者がアンプの電源コードを引き抜いて、この曲は終了する。
どういうことかというと、スピーカーの方向にマイクを向けると「キーン」という金属的なノイズが発生する現象「ハウリング」を利用して音楽を奏でます。ハウリング現象の原理は、スピーカーから出た音を再び同じマイクで収音し、その音がスピーカーからさらに増幅されて出力され、それをマイクが収音して…というループによって、マイクの向きを変えるまで無限にノイズが発生し続ける、というものです。「Pendulum Music」は、マイクを振り子で揺らしてスピーカーの前を行ったり来たりさせることで、一定間隔でハウリングを発生させたりさせなかったりすることで、周期的にノイズを出す、という仕組みによって作られています。振り子の振れ幅が小さくなるにつれ、徐々にマイクがスピーカーの前に来る時間が長くなっていき、最後には停止してハウリングし続けることになります。
実際私はこのアルバムで「Pendulum Music」を初めて聴きましたが、トラックが開始して20秒ぐらい経った頃にタイトルの意味と演奏方法に気付き、天才的な発想だなと思って感動しました。その後、作曲者がスティーブ・ライヒだったと知って、大いに納得しました。
「Pendulum Music」は「テキストスコア」に当たるものではありますが、「プロセス・ミュージック」に分類される作品です。先程から時々引用している書籍「やさしい現代音楽の作曲法 (木石岳 著)」によれば、「プロセス・ミュージック」とは、前述した「ピアノ・フェイズ」のように、微細な変化を体験するような音楽のことを呼びます。ミニマリズムの顕著な特徴として、多くの作曲家によって実験されてきました。「Pendulum Music」では、複数のマイクの振り子の振れ幅の変化によって、人間の手を介さずに自然に少しずつ音が変化していく様子を感じることができます。
この曲は一応、Sonic Youthのゲストメンバーを除いたオリジナルメンバーのみで演奏されているそうです(このような楽曲だと、実際の所「誰が演奏したか」という情報はあまり意味を持ちませんが…)。Sonic Youth以外では、前衛電子音楽界の大御所アーティストのAphex Twinがライブで演奏したこともあるようです。
Aphex Twinのライブ映像 (6:50辺りから)
視覚的効果として複数のレーザー光線が使用されています。巨大な金属製の振り子にレーザー光線を反射させて、光の変化も楽しめるようになっています。動画をよく見ると、鉄球の先にマイクがついているのが見えると思います。なお、点滅が多くて非常に目に悪そうな動画ですので、部屋を明るくして画面から離れて見ていただくことを推奨します。
6.3. 楽曲の楽しみ方の一例
実際に複数のマイクが揺れている光景を想像しながら聴いてみる。
音が少しずつ変化していく様子を楽しむ。
最初は耳障りなノイズに思われるでしょうが、聴いていると慣れてきて心地良く感じるようになるかもしれません。右の定位から聴こえてくる甲高いマイクの音が印象的ですが、他のマイクの音にも耳を凝らすと、意外といろいろな音が出ていることが分かります。 個人的には、何度も聴いていると、音の変化が楽しいと思うようになってきました。 ただし、聴きすぎて耳を傷めないよう、くれぐれもご注意ください。
6.4. 演奏者 (Sonic Youthの公式サイトより)
SY - feedback loops/mic swing
以上でDisk 1は終了です。 色々な作曲家の曲が集められていますが、それぞれ丁寧に辿っていくと、同じ音楽グループに所属していたり、同じ作曲家から影響を受けたりしていて、意外と共通する作風が見えてくるように感じられました。 長くなったのでDisk 2は後編に書きます(執筆時期は未定です…。)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
