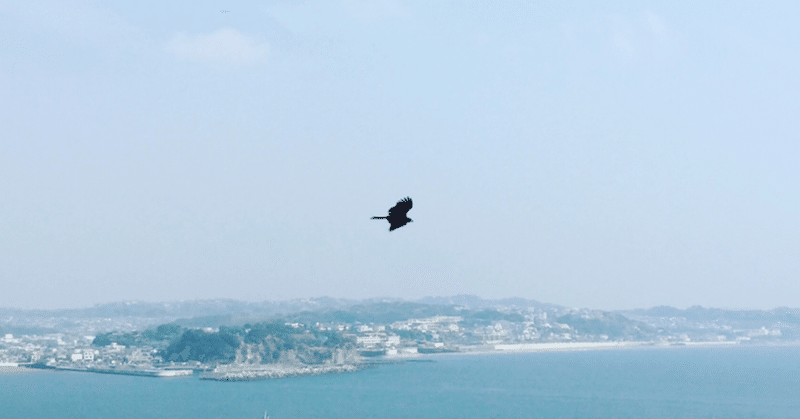
僕には才能がない
文章を書いて生きていきたかった。それで生きていけると思っていた。大学生の頃の話だ。今考えると面映ゆい話ではある。自分には才能があって、それが仕事になるレベルなのだと、表面には出さなかったけれど、しかし心の底では本気でそう思っていた。
今考えると、「『一億総評論家』から『一億総表現者』へ」なんて言われていた時代に、まさにぶち当たっていたんだと思う。例に漏れず小説や絵や写真を、恥ずかしげもなくインターネットに上げてはちっぽけな自己承認欲求を満たしていた。
就職活動を意識しだした頃だと思う。自分が本当にこれからどうやって生きていくのかを考えた時だ。書き溜めた文章を、一から読み返した事があった。
そしてひとつの事実に気が付く。
僕には才能がない。
これは手前味噌ではあるけれど、技術的な問題は一定のハードルをパスしていたんじゃないかと思う。文章における技術的な問題というのは少なくとも僕にとっては何よりも文章のリズムのことを言うのだけれど、読ませる文章というのはいつでもどこか心地いいリズムが響いていて、つまり僕はマスターベーションのように自分の文章を読み返しては自分の作り出した文章に酔っていた。その部分に限定して言えば十分であると、何の根拠もなくそう自分自身を盲信していた。
のだけれど、才能の無さ、というのはそういう技術的な話ではない。と言うよりも寧ろ技術的な問題なんかは最低限のスタートラインの話でしかない。いや、もっと言うとスタートラインですらないのかも知れない。そんなものは習練によって何とでもなるからだ。
自分の書いたいくつかの小説を、並べてみて初めて分かった。そこでは必ず誰かが死んでいた。才能の無さというのはそういうことだ。それに気が付いた時、自分の限界をしみじみと、しかし確実に感じ入った。
僕だってまだ若いつもりではいるけれど、何というのか、「もっと若い」人たちが、時折エゴを丸出しでそれぞれ自分の才能について語るのを見るにつけ、少しばかりもごもごと言葉を濁らせてしまう。失礼な話ではあるのかもしれないけれど、自分の才能の見極めがつけられるだけの能力すらないのではないかと思う、そういうことが多々あるからだ。井の中の蛙、なんて言い方があるけれど、まさにそういう話であって。
「物語」の中心は行為としての「語り」ではなく語られるべき「物」に他ならない。語られるべき「物」を生み出せない人間が何かを語ろうとしたってそれは空虚な言葉遊びにしかならない。それは間違いない。まあ言葉遊びの上手さだって一種の能力には違いないとは思うのだけれど。そこで、能力には違いない、という話でいくと、自分の才能に見極めをつける能力だって一つの能力な訳だ。
一方で傲慢さだって一つの能力だ。自分の才能を信じて突き進むのであればそれはそれで良い。
それでも、と思う。
傲慢さというのはその能力に見合った傲慢さでなければ、周りの人を無暗に憤らせたり悲しませたり心配させたりする厄介なものだ。こいつが言うのなら仕方がないな、というような、根拠のない説得力を孕んで然るべきものだ。それの無い傲慢さはただの盲信だ。
僕はいくつか小説を書いてみて、結果、幸いにも自分の才能の無さに気が付くことが出来た。ある意味、幸せなことだ。おかげで今こうして家族に囲まれて静かに暮らしている。
でも時々思う。自分がその傲慢さを持って自分を盲信し続けられたなら?
そんな疑問が澱のように深いところで消えないから、こうして時々悶々と同じような自問自答を繰り返してみたりするんだろうな。そしてそういう傲慢さを隠そうとしない人間と対峙した時、その人間の(少なくともその段階での)能力が自分の出してきた決定の基準にも満たなかったりすると、沈殿していたはずの自分の決定への疑問(もしかしたら自分にはもっと可能性があったんじゃないだろうか?だとか)が入り混じって、やり場のない苛立ちがふつふつと浮き上がってくるんだと思う。
しかしまあとにかくそういう苛立ちは健全だ。それで何も思わないのならば初めから何も考えていないということですらあるんじゃないかと思ってしまう。少なくともそこで苛立てる人間の方が信頼に足ると思うし、そこで何の苛立ちも無く無条件に支持してしまうような人とは多分友達になれないんだろうな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
