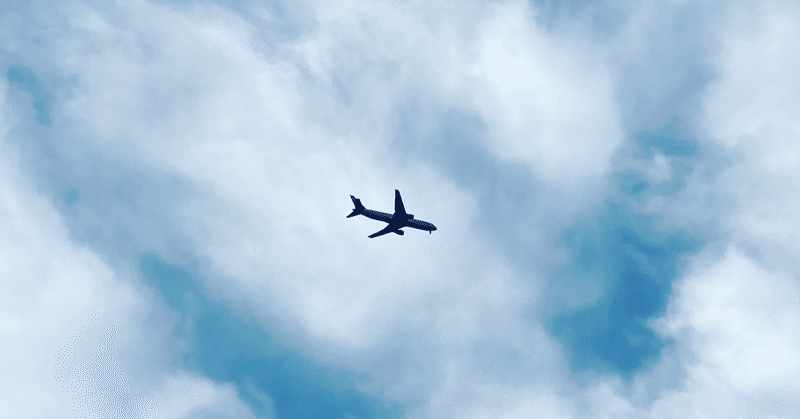
雨音が聞こえる
1
あたりは暗かった。自分の体のぼんやりとした輪郭さえ見えない。完全な暗闇。完全で完璧で、1週間かけて画用紙を塗りつぶしたような暗闇だった。僕にはこの世界にそんな暗闇が存在するということが上手く飲み込めなかった。それくらい現実感のない暗闇だった。単純に黒と言ってしまった方が良いのかもしれない。とにかくそれほど暗かったのだ。
そして不意に光が現れる。僕はその光が背後から照らされているものだと気づく。振り返ると、たった一本の古ぼけた街灯が所在無さげに立って、頼りないほど弱々しい光を放っている。僕は暗闇を見回す。形の見えるはずのない漆黒の肉塊を。
僕は目を閉じる。いや、まばたきをしたというべきか、とにかくある短い時間、僕は瞼を下ろした。目を開けたとき、僕は強い光の中にいる。その光はあまりに強すぎて、光源が何なのかも判別できない。しかも突如僕の目の前に現れたのは光だけではない。大量の人間だった。見回す限り、どこまでも人間の流れは続いていた。彼らはみな一様に、僕の向く方向と逆の方向を目指して歩いている。まるである地点からある地点まで澱みなく流れる水のようだ。そして僕は遡上する鮭のようにその流れに対峙する。
いつまでたっても流れが止むことはない。これだけの人数が一体どこからやってくるのだろうか、と僕は思う。確認しうる限りでは同じ人間は一度も通らなかったし、また誰もが同じ表情で通っていった。表情と呼ぶに耐えるのかさえ自信が持てない、思考・感情の希薄な顔付きで。
次に僕が目を閉じた(あるいはまばたきした)瞬間、僕を流そうとする人々は姿を消している。ずっと向こうまで行列をなしていた、無数の人間が、はじめから存在しなかったもののように姿を消している。代わりに僕が落ちていた。上も下も、地面も空も分からない。そこにあるのは落下しているという曖昧な感覚だけだ。ただ単純に僕は落ち、そして落ち続けていた。他の物はなにもなく、僕が落ちて行くその先に、曖昧な輪郭を持つ黒い引力の塊だけが存在しているようだった。
ああ、落ちている、と僕は思った。
2
汗を掻いていた。腋がぐっしょりと濡れ、体から嫌な臭いがした。不完全な覚醒の中で意識は混濁し、心臓は気味の悪い高鳴り方をしていた。僕は目を擦り、枕元の目覚まし時計を手に取った。六時だった。しかし僕にはそれが夕方なのか朝なのか分からなかったし、もっと言えば正確な日付さえも分からなかった。頭がひどく痛んだ。奥のほうが痺れ、複雑な思考を拒む。カーテンを開けると、弱々しすぎるほど淡い光が窓から侵入してきて僕を射し、僕にそれが朝の六時だということを告げる。朝の六時? と僕は思う。何か大事な用がある気がした。一通り昨日の記憶を辿ってみる。でもたいしたことはない。朝まで飲んでいて、昼から眠っただけだ。大体いつものように金曜日の夜を明かし、土曜の朝を迎えた。そして昼過ぎにまた眠っただけだ。
次にカレンダーを一日一日イメージしてみる。日曜日…。カレンダーの右端の一コマに何か予定が書き込まれていることを思い出す。
何だっけ?
僕は眠気の残る重たい体を精一杯起こし、床に転がった手帳を開く。
「9時、空港に出迎え」
その文字が僕にすべてを了解させる。僕は少し慌てて重い体を起こし、シーツを蹴って、とんとベッドから跳ね上がる。今日はいつまでも怠惰に寝てはいられない。トーストと牛乳だけで簡単な朝食を済ませる。ジーンズを穿き、生成り色をした長袖のシャツを羽織る。髭もそのまま。もともと大した髪型でもないし、時間が惜しいので髪の毛は整えない。かわりにニットキャップを被る。それで身支度は終わり。
僕は家を出ると、港行きのバスに乗るため小走りで近所のバスの停留所へ向かう。港から空港まではフェリーが出ているのだ。
六月の朝の湿った空気が、夏の接近を伴ってじっとりと四肢に絡みつく。僕は汗を掻く。
3
僕は今、神戸のある国立大学に通っている。国立とはいってもあまりぱっとしない地方大学だ。六甲山の中腹に建ち、真冬になると道路が凍結することだってある。少なくとも便利な所とは言えない。特長といえば、景色の良さと時折現れるイノシシくらいなものだ。夜景は素晴らしいし、うりぼうはすごく可愛い。
僕は山の斜面を下った国道の近くで一人暮らしをしていて、毎日てくてくと急斜面を登っている。コンビニエンスストアで深夜のアルバイトをして生活費を稼いでいるが、それも贅沢できるほどではない。僕についてはそんなところだ。残念ながらそれほど語るべきことも持ち合わせてはいない。ごく平凡な大学生。
4
高校時代にふらりと入った写真展で(なぜ写真展に入ったのかは忘れた。写真になんて全然興味がなかったからだ。あるいは他の何かと間違えていたのかもしれない)、僕はある戦争写真家と出会った。彼は外見からして(胸に名札をつけていたからすぐにその人物がこの個展を開いた写真家なのだと分かったのだ)いかにもワイルドで、タフで、クールそうに見えた。短く刈り込んだ坊主頭に、揉み上げから繋がった髭を生やしていた。おまけに小さなフレームの上品な眼鏡を掛けていた。会場にいた彼は時々客に向かって自分の戦場経験について話したりしていたし、実際僕にも話しかけてきた。小さな男の子が女の(恐らくは母親の)死体を無表情で見つめる写真を見ている時だった。
「こんにちは」と彼は言った。声は外見通り、少しばかり野太かった。
「こんにちは」と僕も繰り返す。ゆっくりと声のする方を振り向きながら、すごくすごく慎重に。
「僕の写真展は初めてだよね? いつも会場にはいるようにしているけど、見ない顔だし」
「そうですね」と、僕はそれだけしか答えられなかった。いきなり話しかけられて少しばかり緊張していたのだ。緊張というか、混乱というか。そもそも僕は初対面の人と話すのはあまり得意な方ではない。
彼はにっこりと笑った。すごくワイルドに。
「もちろんアメリカのアフガニスタン攻撃のことは知っているよね?」
「まあそうですね」と僕は言った。もちろん知っている。知らない人間がこの日本に一体どれだけいるのか? と問い返そうとも思ったが、やはり音声としては発せられなかった。2001年、9月11日。嫌でもその日付は覚えるし、それは情報が達する地域であれば世界中の殆どの人に共通して言えることだろうと思う。
「僕はこの1月、ずっとアフガニスタンに行って写真を撮っていた。雑煮も食べずに、年が明けたらすぐに飛行機に乗った。悲惨だったよ、そりゃね。アメリカ軍の爆撃。飢えと寒さ。行ってみたら想像以上のものでびっくりした。テレビで見ている映像はまだましな方さ。なにしろ公共の電波に乗っけて放送しなくちゃならないから、あんまりグロテスクなものは出せない。スポンサーのイメージもあるしね。それにアメリカは爆弾も落とすけど食料も落とすんだ。そいつが何を引き起こすか分かるかい?」
「何ですかね。奪い合いとか…」
「確かにそれもあるかもしれない。でももっと酷いのはそれが地雷原に落ちた時なんだよ。アフガニスタンは世界一地雷の多い国でね、大体四百万個から一千万個は埋まってるっていう話だ。そしてみんなそこに地雷が埋まってるって分かっていても落とされた食料を取りに行く。それほど深刻な食糧不足なんだ。そして足が吹っ飛ぶ。アメリカ的な矛盾したヒューマニズムが引き起こす悲劇としか言いようがないね、これは。ねえ、酷い話だと思わないかい?」
僕は曖昧に頷いた。
「僕はそんなテレビや新聞じゃ映らない戦場のリアルな残虐性を、意識的な残虐性にしろ無意識的な残虐性にしろ、そういったものを皆に伝えなきゃならないと思ってる。微力ながらね」
そう言って彼はもう一度にっこりとワイルドに微笑み、会釈をしてまた他の客に話しかけていた。
僕はもう一度、女の死体を見つめる少年の写真を見る。女は死に絶えながら少年の方へ手を伸ばしている。恐らく最期まで彼を守ろうとしたのだろう。少年の表情は掴みきれない。悲しんでいるのか、状況を飲み込めないでいるのか、ひどく虚ろで輝きの無い眼をしている。おまけに少年自身の指は4本しかない。
それから、リアルな残虐性、と誰にも聞こえないように小さく呟いてみる。何度も何度も。確かにそれはそこにはっきりと存在し、僕のちっぽけな心臓をきゅっと握りつぶそうとしている。僕はどうしようもなくぶるぶると身震いをする。それは一度も感じたことのない感覚だった。ぞっとするほど冷たく、血が滾るほど熱かった。
「あの」と僕はその写真家を呼び止めた。自分でも何を言っているのか分からなかった。
「うん?」
思わず僕の口から言葉が流れる。きちんと整理されないまま、感情のままに流れる言葉。
「何か僕にできることは?」
写真家はうん、と少し唸って、腕を組んだ。何というべきか考えていたのだろう。
「君はまだ学生だろう? 君が今しなくちゃならないことはたくさんある。もし君がこういった世界中の不平等や苦しみに対して何か役に立ちたいと思っているのなら、もっともっと勉強するべきだ。彼らのところへ行くのはそれからでも良いじゃないか」
「でも、今すぐ助けなくちゃならに人たちだってたくさんあるはずです」
「例えば」と彼は言った。「多くのNGOに高い専門的能力を持った人材が不足している。君が今できることは、彼らが今できることよりずっと少ない。君がもっと力を磨いて、自分が本当に何かを成し得るという自信が付いたとき、僕に連絡してくれればいい。それまでは、うん、相談くらいなら乗れると思う」
僕が小さく頷くと、彼は手帳のメモを一枚千切って自分の住所と電話番号を書き、それを僕に渡した。待ってるよ、と彼は言って。にっこりと微笑んだ。すごくすごくワイルドに。
5
そんなわけで僕と写真家は知り合い、手紙の遣り取りをするようになった。彼の手紙はいつも血なまぐさい戦場で書かれ(実際に血の付いた手紙が送られてきたことも何度かあった)、どこかの空港から出されていた。アフガニスタン、イスラエル、チェチェン、そしてイラク…。ニュースに出てくるような地名ばかりだ。僕は時々それらの手紙を読みながら、自分のいるはずのこの世界のリアリティーを無くしてしまう。僕はこちら側にいて、彼はあちら側にいるという実感を、それらの手紙が与えるせいだ。それは少なくともあちら側で起こっている現実であり、こちら側にいる僕と戦場にはぬくぬくと僕らを守る奇妙な壁が存在していた。
それは今でも変わらないし、恐らくは日本にいる限りずっと壁は存在し続けることだろうと思う。距離というものはある場合には信じられないほど強く作用するのだ。
6
港行きのバスはちょうど出発するところだった。
「急いでください」と運転手は言った。ひどく無感動で事務的な言い方だった。おそらく今までに何千回何万回と繰り返した科白なのだろう。おまけに運転手は驚くほど特徴のない顔をしていた。実際、僕は座席に着く頃には彼の顔がどんな顔をしているのかすっかり忘れてしまっていた。
バスは奇妙なほど空いていた。僕のほかは港湾労働者ふうの二人組の男が何も言わず座っているだけだ。彼らは隣り合って座りながらお互いに顔を背け、港まで一度も口を交わすことがなかった。一人はずっと窓の外を眺めていたし、もう一人はずっと腕を組んで正面を見据えていた。
僕はかばんからCDウォークマンを取り出し、くるりの『ファンデリア』をかけた。「続きのない夢の中」とともに窓の外の空に雲がかかり始め、「Yes mom I'm so lonely」が始まるころにはすっかり雨が降ってきていた。まいったな、と僕は思った。家を出るときには新品のテニスシューズの裏みたいに晴れていたし、傘なんて持ってきていないのだ。
海が近くなると街はいよいよ人工的になり、きちんと整理された区画に沿ってバスは走る。単調さと退屈さの専門家たちが寄り添って作り上げたような街だ。単調なビルの横を過ぎ、退屈な交差点を曲がる。そこには生活の痕跡なんてない。あるのは単調と退屈だけだ。あるいはそれはバスの乗客を心地良く眠らせるための装置なのかもしれない。雨の音がきれいなリズムを叩いて、単調さをさらに強めている。二人組の男たちもすでに眠りに落ちていた。僕も当然のように眠りに落ちる。すとん、という音が聞こえそうなくらい、すごく自然な眠りに。
7
「……ましたよ、ねえ、着きましたよ」
運転手の声が僕を呼び戻す。マイクを通した声だ。運転席に座ったまま僕に降りるよう促しているらしい。僕以外の乗客は既にいない。窓の外を見るとすごく直線的で人工的な海岸線がそこにあった。海岸線と呼べるのかどうかもあやしい代物だ。
「どうも」と僕は言って運賃を払いバスを降りる。
潮の匂いがする。でもそれも微かなもので、海に来たときの独特の高揚感なんてまるで起こらない。あるいはそれは雨のせいなのかもしれない。しかし本当は神戸に本物の海なんてないからだ。ただそこには海水があるだけ。水、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、それから……まあいい。それだけだ。それ以上の何物でもない。
大きなくらげが波の動きに合わせてフェリーに打ちつけられている。
フェリー乗り場にある売店で安物のビニール傘を買って、静かに雨に打たれている船に乗り込む。僕は甲板に立ち、思い切り湿った生暖かい空気を吸い込む。チケットを確認していた船員に約束の時間に間に合うかどうかを確認してから、僕はベンチに座った。まだ昨日の酒が残っている。体が重たい。
8
このとき写真家から送られてきた手紙はひどく短いものだった。それまでのようなアメリカ批判も戦場の実情報告もなかった。そこにはたった一行、「日曜日の9時に帰る、迎えに来てくれると嬉しい」とだけ書かれていた。日付も何もない。日曜日。
しかし以前にもそういうことは何度かあったので、僕はいつの日曜日なのか迷うことは無かった。彼は大体いつ手紙が到着するか、それぞれの国の郵政事情も考えた上で手紙を送ってきたからだ。手紙が着いた次の週に空港に行けば、大抵彼を迎えることができた。そういうのはちょっとした才能だと僕が彼に言うと、彼はいやあ、と言うばかりだった。僕は本当にそう思っていたのだが。
9
海の向こうから見えていたあまりに巨大で近代的な建造物は、空港島に上がるとさらに無機質で無感動なものに見えた。ただの思い込みなのかもしれない。でもそれにしては十分に僕を威圧していたし、迎え入れられるなんていう印象は全く受けなかった。
空港に入ると、6月の湿気と冷房のせいか、空気がひどく重く澱んでいた。それでも人々はみんな楽しそうだった。そりゃそうだろうな、と僕は思う。彼らの多くは旅行客なのだ。僕の個人的な見解からすると、旅行者が期待で胸を膨らませないはずがない。僕だって旅行に発つときの空港は自分でも信じられないくらい浮かれた気分になる。でも今のぼくはそうじゃない。迎える側だ。それでも彼に会えるならば、嬉しい気持ちに変わりはない。修飾を必要としない純粋な気持ちだ。彼に会いたい。
僕は缶コーヒーを買ってロビーのソファに腰掛ける。もうすぐ9時になる。彼が帰ってくるはずだった。僕はポケットからしわくちゃになった彼の手紙を取り出し、読み返してみる。
「日曜日の9時に帰る、迎えに来てくれると嬉しい」
時針がまっすぐ左を指す。9時。帰ってくる乗客たちの中に、彼の姿はない。次の便を待っても、その次の便からも、彼は現れなかった。
日曜日の9時、と僕は呟いてみる。誰にも聞こえないくらい小さな声で。 ねえ、その時が、日曜日の9時が、一体何度訪れただろう?
4月の消印が押された手紙を何度も何度も読み返しながら、僕は涙を流した。何人かの旅行客が怪訝そうに僕を覗き込む。
本当は、僕は知っていたのだ。いつまで待っても彼が帰ってくることはない。4月の終わりのニュースで少しばかり話題になったことだ。僕は戦争に関するニュースは殆どチェックしてきた。知らないはずがない。「邦人写真家、自爆テロの被害、死亡。」でもそれは何だかたちの悪いジョークみたいに僕には聞こえた。信じられるはずがなかった。距離という生温かい壁はまだ僕と彼との間に存在していたのだ。僕はただ毎週日曜日、空港に来るしかなかった。彼は帰って来るんだと、自分に言い聞かせた。
今朝みた夢の中で、僕を押し流すように歩いていた人々の中に、暗い向こう側から手を振る彼の姿があった。完全な暗闇へ、彼はもう行ってしまった。
空港を出る。雨は少し弱くなっていた。ビニール傘を開く。ぱらぱらぱら、と優しい音が聞こえた。ひどく優しい雨音が、聞こえた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
