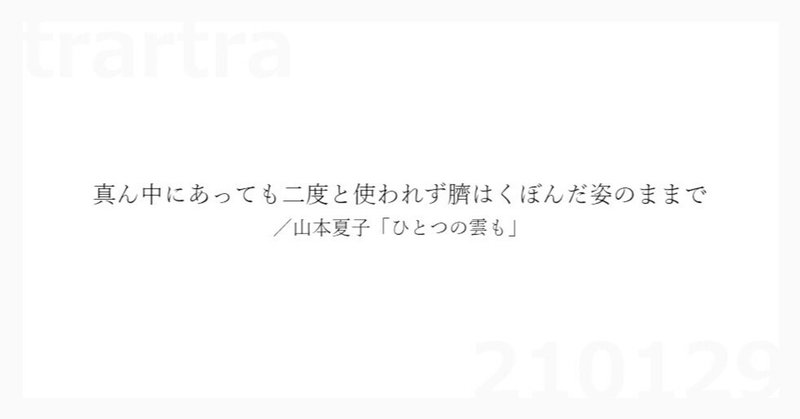
普通のままに/5分で読める現代短歌24
真ん中にあっても二度と使われず臍はくぼんだ姿のままで
/山本夏子
2016年に現代短歌社賞を受賞した山本夏子の、第一歌集『空を鳴らして』より。山本は結社「白珠」にも参加しており、2014年に同結社新人賞も受賞している。(結社というのは、簡単に言えば短歌における同志同嗜の集まりです。代表がいて、その門下に弟子入りみたいな形態が多い)
現代短歌の界隈にも多くの賞があるけれど、自由に応募できる公募制の新人賞では「角川短歌賞」「短歌研究新人賞」「歌壇賞」が歴史・知名度ともに三大新人賞と言えると思う。近年は福岡の出版社 書肆侃侃房の主催する「笹井宏之賞」の存在感も増している。それらの新人賞のどれもが、募集要項として"未発表"の"表題付き三十首連作(角川のみ五十首)"を求めているのに対し、山本の受賞した現代短歌社賞は、"既発表を含めてもよい" "各小題付き三百首"を要項としている点で、毛色がかなり異なる。
笹井宏之賞の受賞者には副賞に歌集出版が約束されていることは前回の榊原や前々回の鈴木の際にも書いたが、現代短歌社賞においても、創立目的に「これまで歌集を出していない人の第一歌集上梓を後押しすべく」とあるとおり、三百首の応募作に基づく歌集の出版が副賞として授与される。『空を鳴らして』も、そのうちの一冊。
真ん中にあっても二度と使われず臍はくぼんだ姿のままで
2017年度まで現代短歌社賞の選考委員も務めた「白珠」代表の安田純生も歌集に寄せて書いているとおり、一冊を通して擬人表現が多い。
掲出歌においては下句〈くぼんだ姿〉がそれにあたるが、この歌ではそれほど効いているとは感じない。上句〈真ん中にあっても〉が同じ臍を主語にしているのに擬人化されていないためか、どことなく上下でズレて句切れ〈使われず/臍は〉がブツ切れになっている気がする。歌集表題歌〈夏祭りの練習続く校庭に空を鳴らして夕立が来る〉や〈上履きが片方道に落ちている木星みたいな裏側見せて〉など、より擬人が効いている歌も多いのでそちらに意識を向けたい。(より率直に言えば、短歌の世界で"擬人"と呼ぶべき修辞は今やそれほど多くないのではないか、と感じさせられた……擬人とはあまりにもヒト中心の思想な気がして……)
掲出歌は、いわゆる発見の歌と言えるだろう。
真ん中にあっても二度と使われず臍はくぼんだ姿のままで
この臍というものは、ヒトを含め哺乳類の身体の〈真ん中〉にある。しかし、その役目は誕生までに終えられており、以降の生命においては〈二度と使われ〉ない。不思議。徐々に消えて無くなるとか、他の用途があるとか、あってもおかしくないのに。
たとえば自身の臍を見て、ふと、そういった発見をする。それを歌にする。読者が、確かにな~と思えば、もう勝ちだ。(何に?) 実際、ぼくも読みながら「確かにな~」と思わされた。なんだこの臍というものは。以後、ぼくのなかの“臍”観に、「真ん中にあるのに二度と使われないもの」という説明が付与されることになる。
また、歌一首のなかで問いと答えの構造になっていることも、歌を読み下すうえでのドライブになる。上句〈真ん中にあっても二度と使われず〉では何の話か不明で、読者には問いが渡される。続く下句で〈臍はくぼんだ姿のままで〉と、いわば上句の答えとして臍の話だったことが明かされる構造。ただ、大変に率直な問いと答えなので、若干説明的になってしまうきらいはある。
(短歌の関係で〈問いと答え〉と言うと、現代短歌の文脈では永田和宏の「問いと答えの合わせ鏡」という論評が合意されるのだが、ここではその話はしていません……「合わせ鏡」を用いた一首評としてはこちらなどもご一読ください)
韻律的に特筆すべきポイントは無いように思われるが、掲出歌においては、一首単体の韻律・修辞・歌意以上に、この歌がこの歌集に置いてあることが強く意味を持つ。
東直子という歌人が〈たくさんの生き物の気配に満ちている〉と寄せているとおり、全体を通して、擬人・比喩表現と相まって感じるのは生き物をモチーフにとった歌の多さだ。本当に多い。飼っているうさぎを初めとし、水鳥、すずめ、犬、猫、ねずみ……と、たくさんの生き物が歌われる。ある見開きなど、四首のうち三首に動物がいた。めっちゃ多い。
先の安田の指摘と通ずるところだが、無機物であっても擬人的な表現をされていることもあり、歌集一冊を通して生命活動なるエネルギーや運動への意識が強く感じられる。とは言っても決してエネルギッシュな文体ではなく、フラットで、のびやかだ。文体の統制というか、どの歌をとっても大きく外れるところが無い。三百首という数を応募するにあたっては、こういった安定感と、飽きさせない工夫のバランスが重要なのかもしれない。(当時の選考座談会の様子を読んでみたくなった)
真ん中にあっても二度と使われず臍はくぼんだ姿のままで
掲出歌は歌集のちょうど中盤にあるが、以後、主体が妊娠・出産・育児と人生を転がす様子が主なテーマになっていく。歌集煽り文の〈普通に仕事をし、普通に結婚して普通のママになり、普通に悩みながら生きる一人の女性の、どこか普通じゃない口語短歌。〉で“普通”ってなんやねんと思いつつ、実際、物珍しい職業詠も、センセーショナルなイベントも起こらない、誰しもに当てはまりうる感覚が通底する。普通と使いたいなら、"普通を普通のままに”まとめあげている。三百首これをやるのがむしろすごいのでは、とすら思う……現代短歌社のご担当者、ぼくはこれらを普通じゃないとは思いません。
先ほど“自身の臍を見て、ふと、そういった発見をする”と書いたが、この発見は主体の意識の水面下に生命への関心があることに起因するのかもしれない。そしてこの発見によってそれまでの歌で登場していた犬猫といった動物たちへの目線が、哺乳類としての自身へも移ることを暗に準備する。
その点で、この歌はこの歌集に置いてあることによって、ぼくにとっては単なる発見の歌以上に目を引く一首になった。
真ん中にあっても二度と使われず臍はくぼんだ姿のままで
/山本夏子「ひとつの雲も」
---
短歌あるあるだが、著者本人の手元にも在庫があったりする。
直接連絡を取ってみても良いと思う。(ぼくはそうしました)
第一歌集『空を鳴らして』
— 山本 夏子 (@yamamotonatsuko) July 3, 2018
山本 夏子
ご希望の方は、私にDMいただくか、現代短歌社さんまでご連絡下さい。大阪の葉ね文庫さんにも置かせていただいています。
またお近くの書店でお取り寄せも可能です。
どうぞよろしくお願いします。
(現代短歌社 2500円)
pic.twitter.com/FXUm5pk4DC
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
