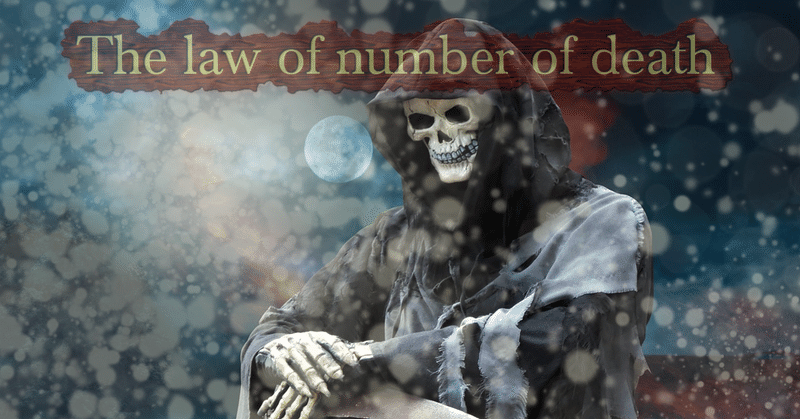
死に目の掟
どれくらい前やろ。
昔、昔、おじいさんが、、ぐらい前だ(笑)。
本屋で「死に目の掟」という物騒なタイトルの競馬本を目にしたことがある。
変わった名前だったので記憶するが、蔦枝史朗氏著。
パラパラと流せる厚みだったで、少し内容を追いかけてみた。
まぁ、当然と言えば当然だが、読者が最も関心のあるであろう、
死に目の決定における判断の根拠や方法論については、何も具体的には触れられていない。
当人曰はく、「墓場まで持って行くそうな、、」(笑)
興味はそそられたが、結局核心には触れられてはいないので、中身は無しや!
因みに、死に目に対し、激走すべき選ばれしゲート番を、彼は「ゴールデンゲート」と呼んでいた。
まぁ、馬券活字本の限界、攻略に直結する部分は簡単には公に出来ないということだろう。
馬券本作家というのは、仮にたいそうな内容を持っていたとしても、
それを全て活字という公の場で晒し出すことはない。
ノウハウは飯のタネ、適当に自身が困らぬ程度で小出し、切り売りというのが常套手段。
昔サイン競馬の草分け的存在とも言うべき中山一考氏と、競馬開催日前日、夜通しで競馬談義をしたことがある。
錦糸町ウインズ前にあった氏のマンション一室での話だが、故高本公夫氏が
競馬ネタを求めて訪ねて来た話や、上記内容(小出し・切り売りの話)を含め、「馬券本は発行部数が少なくて、食えないよ」のボヤキ節も聞かされた(笑)。
あはっ、少し脇道にそれたが、「死に目」について、実際はどうなんだということになる。
自身、ブログ記事等でこれまで多くの人気馬について、独自の競馬構造論からの帰結から、「この馬のアタマ狙いは止めなはれや!」であったり、人気上位馬の「組み合わせの否定」について述べて来た。
まぁ、程々に精度の高い結果で、信じて従った人達には買い目点数の激減に貢献出来たと思っている。
結論は、蔦枝史朗氏の言う「死に目の掟」は実際に存在する。
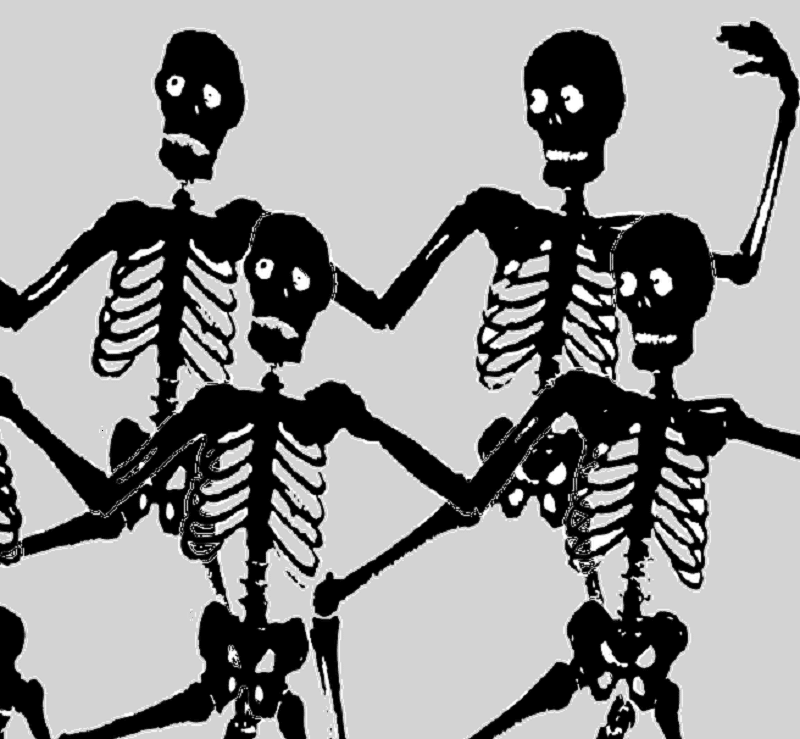
理由は至って簡単、実際誰もが能力比較等で導く2頭が1、2着を繰り返していれば、低配当の連続。
マネーゲームとして一攫千金を望む競馬ファンが圧倒的に多い中、
低配当のオンパレードでは、飽きられ売り上げも衰退への道を辿るのは明らかだ。
勿論JRAは全てを見透かし、売上向上、競馬の未来永劫の繁栄の為に最大限の努力を重ねて来た。
そしてJRAを頂点として、それに関わる、生産牧場、厩舎、騎手、馬主等等、全ての者達もJRAの思惑と同じ方向を向く一つの運命共同体である。
同じ方向で歩まねばならない!逆らうことは許されない。
これが蔦枝史朗氏のいう「掟」、だろうと考えられる。
JRAは年度毎に通年を通した、払い戻しや勝ち馬に関しての青写真を描いているのだろう。
たとえ、鞍上がC・ルメールや川田騎手の1番人気という場合であっても、
JRAの青写真から外れるような場合では、決して勝ち馬になるということはないということだ。
騎手も競馬繁栄を担うパーツ、決して「掟」に逆らうようなレースはしない。
現在の競馬は、C・ルメールと川田騎手を中心に競馬の結果が構成される場合が多い。
まぁ、競馬ファンにとって、両名は5割の確率で馬券圏内には絡んで来るトップジョッキー、常に騎乗馬についての取捨が悩み所だろう。
逆に、彼等が死に目のゲートに配された時、これが見抜けたら、馬券上は大きなチャンスでもある。
死に目が存在するなら、これを見抜き逆手に取る!
その見抜く方法論はがtrueofx競馬理論にはいくつも存在するが、これはこれで稿を変えての機会に。(競馬雑記、了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
