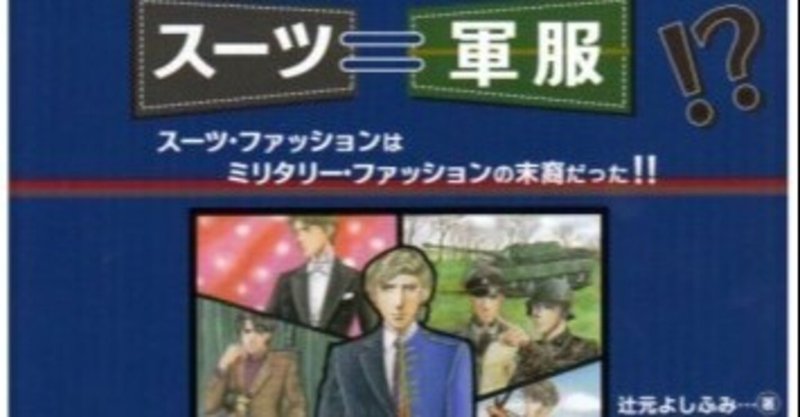
スーツ=軍服!? 1回目
『スーツ=軍服!? スーツ・ファッションはミリタリー・ファッションの末裔だった』改訂版
辻元よしふみ、辻元玲子 著
※これは、2008年3月10日に彩流社から初版が刊行された同名書籍の改訂版です。この書籍は現在も絶版はしていないものの、版元さんの事情もあって、事実上は再版未定となっています。
しかし刊行当時から評判がよく、今でもこの本を基に取材のご依頼があったり、Wikipediaの出典や、ネット記事、YouTubeなどで引用されたりしております。2021年6月にも、日本経済新聞の週末版で引用され、取材も受けました。
この書籍を出した後、あきらかに男性ファッション誌などの記事に書かれる内容が変わってきました。今では日本国内でも通説とされていることも、実は私どもがこの本で2008年に発表するまで知られていなかったこと、間違って流布していた情報というのもあります。一例を挙げれば、外羽根式の靴ブルーチャーの語源、プロイセン軍の19世紀の英雄、ブリュッヘル元帥などのことも、どんなファッション誌の記事もきちんと書くようになりました。それまでは「ブラヘル」などと書いているものが普通に見られました。ヴィクトリア女王の夫、アルバート公と、その息子のエドワード7世(王子時代の名はエドワード・アルバート)を混同している記事も多かったのですが、本書の刊行以後、そういうライターさんも姿を消しました。「なんだ、こんなの知っているよ」とおっしゃる若い世代の方もいらっしゃるかもしれませんが、2008の本書刊行後に、日本のファッション系の記事の質が上がった、と自負しております。
その後、辻元よしふみ、辻元玲子の共著を何種類か刊行してきましたが、私どもおよび出版社の方針から、特にミリタリー・ファッション、軍装に重きを置いた内容の本が多くなりました。2016年の『軍装・服飾史カラー図鑑』(イカロス出版)はかなり、一般の紳士服を取りあげております。しかし最新刊の『図説 戦争と軍服の歴史』(河出書房新社)はほぼ、軍装関連の話題となっています。
私どもが2人とも、防衛省の外部有識者となり、陸上自衛隊の制服制定に関わったことから、やはりそういう方面の専門家と見られることも増えました。しかしながら、私どもは元々、ファッション史全般を研究対象としております。
そして、特に一般の紳士服の歴史をまとめた本、というと、私どもにとっては今でもこの本、ということになります。さらに、2021年現在でも、新聞やテレビなどのメディアから引用が絶えないのですが、それは世間的に見ましても、この本の後、紳士服の歴史を書いた本が出ていない、ということがあります。
どうしてもファッション研究は女性の服中心となり、大学の服飾科やファッション系専門学校の課程でも、女性の服飾史ばかり扱うことが多く、実は日本のファッション史で紳士服全般の歴史が、軽視されているのが実情です。
そういうことで、これからこの本の改訂版を、少しずつ掲載することにいたします。原書は古い内容で、たとえば小泉政権当時のクールビズ政策を批判するような内容など、今となってはそのままでは通用しないものになっていました。また、その後、消えてしまったお店やブランドも少なくありません。そういう部分を考えて、加筆修正していきたいと思っております。
2021年10月12日記
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
序章 「男の戦闘服」であるスーツは、どこから来て、どこに行くのだろうか?
◆本当に「スーツは男の戦闘服」である
よく「スーツは男の戦闘服」とか、「ビジネス戦士の完全武装はスーツから」などと言います。それはもちろん、もののたとえ、比喩として言われているのですが、しかし、本当に男性のビジネススーツの原型が軍服だ、と聞くと意外な感じがするのではないでしょうか。
調べてみますと、われわれが日常、身につけている洋服のスタイルというのは、驚くほどミリタリーに由来するものが多いのです。本書は、そのあたりを、西欧の衣服の歴史をたどって振り返ることをテーマとしたものです。
今、ミリタリー・ファッションというと、迷彩服とか、カーゴパンツ(ファッション誌でいうところの軍パン)を思い出す人が多いでしょう。しかし、迷彩服というのは第二次大戦でドイツ軍の武装親衛隊が採用するまで存在しなかった歴史の浅いものです。カーゴパンツに至っては、そもそもカーゴとは「積み荷、船荷」という意味合いで、軍用ではなく貨物船乗員あるいは荷揚げ作業に従事する港湾労働者が使用したズボンのことです。実際の軍の制服ではカーゴパンツ式の膝に大きなポケットがあるものは、野戦服やパイロットスーツ、整備服、作業服などに見られることが多く、正装や通常のサービスドレス(勤務服)ではまず見られないと思います。
ここでは、もっと広い意味で、軍人が威儀を正す制服の流れから、今のスーツに至った流れを取り上げたい、と思うのです。
「背広」という言葉の語源として有力なものに、ロンドンのテーラー街として有名なサヴィル・ロウの地名がなまった、というものがあります。しかしこれが定説というわけでもなく、ほかにもいろいろあって、中に「シヴィル・クローズ」Civil clothから転じた、というのがあります。つまり「民間人用の服」という意味です。英国人が明治期の日本人にスーツを売り込む際に、わざわざ「これは民間人が着る服だ」と用途を強調した、というのは大いにありそうなことで、軍服とスーツはそもそも一対の概念なのだ、と言える逸話です。
洋服というものが、日本に入ってきたのは戦国時代。甲冑や陣羽織など、当時の戦国武将のミリタリー・ファッションに西洋風が取り入れられたのは広く知られているところです。
そして、本格的に日本に到来したのが明治時代。文明開化の時代に到来したスーツは、実は西欧でも当時、最新式の服装でした。
◆文明開化当時、スーツは最新式の服装だった
明治維新が一八六七年。現在の紳士服の中心にある「背広」つまりスーツの原型が英国で登場するのが一八五〇年代ごろ、ヴィクトリア女王の時代です。つまり、日本人が背広ファッションを着るようになったのは、世界的に見て決して遅くなかった、むしろ当時の最先端ファッションを取り入れた、ということなので、少なくともスーツに関しては時代的にぜんぜん後追いではないことになります。
また、もう一つ、男性の服装の柱であるブレザー、あるいはジャケットというものも、ほぼ同じ頃に登場しております。つまり、大づかみに言えば、今のような上着を羽織り、ドレスシャツにネクタイなどを締める紳士ファッションというのはせいぜいここ百五十年ほどのもの、ということです。
逆に言いますと、それ以前には、西欧でもスーツやブレザーはまだ確立していなかった、違う服装であった、ということになります。
ヴィクトリア時代より前の、ボー・ブランメル(一七七八~一八四〇)が活躍した時代、ナポレオン(一七六九~一八二一)戦争の時代、さらにそれ以前のルイ十四世(一六三八~一七一五)の時代、もっと以前の、ちょうど戦国期の日本にやって来た南蛮人たちの服装の時代……。それはかなり異なったものでした。
軍服というユニフォームも、一国の軍隊全軍が統一した色調を採用したのは十七世紀、スウェーデン王グスタヴ・アドルフ(グスタフ二世、一五九四~一六三二)の軍隊からと言われています。そしてナポレオン時代に多様化し、ヴィクトリア時代に確立した紳士ファッションに大きな影響を与えたのです。
西欧の服飾史について古代から説き起こした本はありますし、ミリタリー関係の、たとえば第二次大戦中のドイツ軍や日本軍の服装の研究書、あるいはナポレオン戦争時代の制服の本、もっと最近の、米軍のパイロットジャケットだけを詳述した本もよく見かけます。
しかし、西欧服飾の通史、特に服飾全体をリードした軍服の歴史をたどり、それが今日のスーツ・ファッションにどう影響を与えているか、ということを時系列的に概観した本が日本には見あたりませんでした。
そこで、そういう観点から「スーツやブレザーは本当に軍服の末裔なのだ」というお話をしようと思った次第です。元より、筆者の知識も不十分で、心許ない記述も多いかと思いますが、今後の研究を進めるための基礎、叩き台として、この一冊をまとめようと決意したものです。
考えてみますと、今日の仕立て技術の基本を確立した英国のテーラーを代表するギーヴス&ホークスは、ネルソン提督の時代から陸海軍の将校向けに特注の制服を仕立て続けてきた老舗。また、英国の「製靴業の聖地」ノーザンプトンは陸軍用軍靴の量産で興業した街です。
洋服を受け入れた日本でも、海軍水交社(海軍士官の社交クラブ)が指定していた東京・芝の山田屋洋服店、植久、麻布の山城屋洋服店、横浜の森田屋などは、そのままわが国のテーラリング技術の素地を築いた老舗です。市ヶ谷にあった太田屋洋服店は陸軍士官の御用達でした。一八七〇年に創業した伊勢勝造靴場は陸軍向け、七二年に創業の大塚商店は海軍用軍靴の製造を託されました。前者はリーガル、後者は大塚製靴として、それぞれ日本を代表する靴ブランドとなり今日に至っています。
近頃のビジネスマンのスーツ・ファッションを見ていますと、着崩しすぎのうえ、なんだかだらしなく、必死におしゃれにしようと努力しているのに、貧相で軽薄に見えます。もちろんその重要な理由の一つは、現代日本人が必要以上に体力がない、腹筋と背筋が虚弱で姿勢が悪く、猫背で、尻が後ろに残る歩き方、ガニ股で、座っても太ももの筋肉がなく、すぐに真横に大股開きするようなだらしなさ、があること。そしてもう一つは、スーツの基本がフォーマルなドレスコードにあることを理解していないから、ただ流行を取り入れ、あるいは奇抜を狙うだけで様にならないことにあると思います。バブル期にはアメフトの選手のように肩が異常に大きなジャケットがはやり、最近はやたらに窮屈なジャケットがはやりましたが、しかし「アームホールは小さくないと」などと流行に泳がされるばかりで、自分の体型も考えず、もともと猫背で肩幅の小さい虚弱な現代日本の若者がやたらにナローでタイトなジャケットやパンツをはけば、ますます頼りなくて仕事が出来ないように見えるだけ、なのに気が付いていないのは本人ばかり、となりがちです。
◆基本を知らなければ崩すことも出来ない
たとえばですが、「赤信号、みんなで渡れば恐くない」という、かつて一世を風靡したビートたけしさんのジョークがあります。これで人はなぜ笑えたのでしょうか。「本当は、赤信号は渡ってはいけないのだ」という常識をみんなが持っているからです。はじめから赤信号を渡ってはいけないというルールを知らない、たとえば原始人とか宇宙人にこのジョークを言っても、なんでおかしいのか理解できないでしょう。
なんでもそういうものであって、基本を知らないと崩すことが出来ません。まじめな常識を知らなければジョークも通じないし、ファッションも成立しません。
今の日本の文化全般がなんだか生彩を欠くのも、「基本を知る」ということを疎かにしているからだと思えてなりません。
日本の若者は気の毒なことに、小学校ぐらいまではほとんど、ジャージーばかり制服のように着て育ちます。余談ですが、このジャージーというのもちゃんと由来があります。英国のジャージー諸島で労働着として着ていた服が原型なのです。決して、突然、最近になって登場した衣服ではありません。
近ごろの教育というと「とにかく自由に育てよう」ということで、必要以上にだらしない姿勢を身につけています。なんでもカジュアルに、リラックスして、楽に、という方向に進みすぎ、ストリート・ファッションなどといって、本来フォーマルであるべき学生服を着たまま地べたでくつろぐ、などというけじめのない風俗が普通になった結果が、いまの有り様だと思います。
欧米の子供たちは、日曜になると教会に行くとか、節目、節目にパーティーがあるとかいう場合に、服装にはカジュアルとフォーマルの区別がある、と教わる傾向にあると思います。英国のイートン校のように、制服がモーニングであるような学校もあり、若い頃から日常的にそういうものを着ていれば、それは着こなしもうまくなるというものです。アメリカでも、青春映画によく出てきますが、ハイスクールなどの卒業記念に行われる舞踏会「プロム」でタキシードやドレスを着る、というのがひとつの憧れになっており、若者たちがフォーマル・デビューをする習慣がありますね。国により、上流階級の子女が社交界デビューする「デビュタント」というものも見られます。
◆「正統」があるからこそ、「反抗」もできる
昔から、あえて社会に反抗する若者が、音楽潮流ともリンクしながら、ロック・ファッション、パンク・ファッションとか、ヒップホップ・ファッションをしてきたのも、一方で正統な着こなしというものがあるからこそ、とんがった、反抗的な、あるいは異端なファッションとして成立するわけで、大人も子供もみんなルーズな社会では、そういう服装もあまり積極的な意味合いを持たない、ただの流行の一種と見なされてしまいます。日本のファッションの流行は明らかにそういうものです。
そういえば、二〇〇七年秋、アメリカの複数の都市で、ジーンズやスラックスのローライズ、つまり「腰ばき」を禁止する条例が可決されて話題となったことがあります。近頃の若い人が好む腰ばき、股上が浅いスラックスを極端にずり下げてはくやり方で、わざと下着を見せたり、極端な場合、尻の割れ目まで見えていたりするような人がいますが……、それにしても、個人の服装について法律や条例で規定するというのが日本人には意外に思われ、「自由の国アメリカ」というのは我々の思いこみに過ぎず、実際には非常に社会的ルールが厳しい国であることを改めて思い知らされたものでした。
一方で、「個人の服装など法で規定するのはいかがなものか」という反応も当然ながら出て、なかなか問題は一筋縄ではいかないようです。同年九月十五日付の産経新聞によれば「米国の刑務所で事故防止のため、囚人たちにサイズの大きな服をベルトなしで着用させたのが原点ともいわれる。刑務所帰りを誇示する貧困層の黒人やヒスパニックの間に広まり、ヒップホップ文化の後押しで世界的な流行の波に乗った。それだけに、腰パン規制に対し、黒人文化の不当な差別との声が上がっているのは半ば当然だとしても、論議には黒人間の意見対立まで絡んでいる」とのこと。
ともかく、「たとえ個人の自由を侵しても社会の規範は守る」という強い意思の人たちと、「個人の服装に権力は干渉してはならない」というもう一つの立場の人々が信念の下に物を言っており、どこかの国のように、その場の思いつきのクールビズだったり、それも命令なのか強制なのか国民運動なのか奨励なのか分からなかったりで、あいまいなまま「他人がやるから真似する」という空気、同調圧力でみんながなびく、という状況ではないのが好ましい気がします。
実のところアメリカ人あたりの成功者の理想の服装というのはきわめて保守的であり、それは、要は英国的な着こなしであり、それに対して古くはサイケなヒッピーや革ジャン、ジーンズ、さらにもっと若い世代のロッカーやヒップホップ系の連中の服装が相対するのは、ただの流行ではなく、そこには常に強烈な反体制の思想があったと思います。ことにブラック系の音楽や服装には常に差別の問題があって、それを表面的に日本人あたりが真似することは非常に軽々しい気がするのです。また、実際に自国の兵士が海外で血を流している国の反体制の装いを、しょせん日本人の若者などが形式的に真似しても格好が付くわけがないようにも思います。
フランスなどでは、公共の場で宗教的な装いをすることが禁止されており、ドイツではナチズムを想起させる制服などの着用は禁止されています。一方で、宗教的戒律を守らない服装をした者は命の保証がないという国もあり、ある種の服装をすることは、場合によっては、それ自体が命がけとなる世界が実際にあります。
かつても、ジャンヌ・ダルクが火刑に処せられた主な理由の一つとして、「女性なのに男装をした」ことが罪だとされました。服装は個人の主張や立場、センス、信念までも表現するもので、他人は見た目で人を判断する、ということはいつの時代にもひとつの真実です。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
