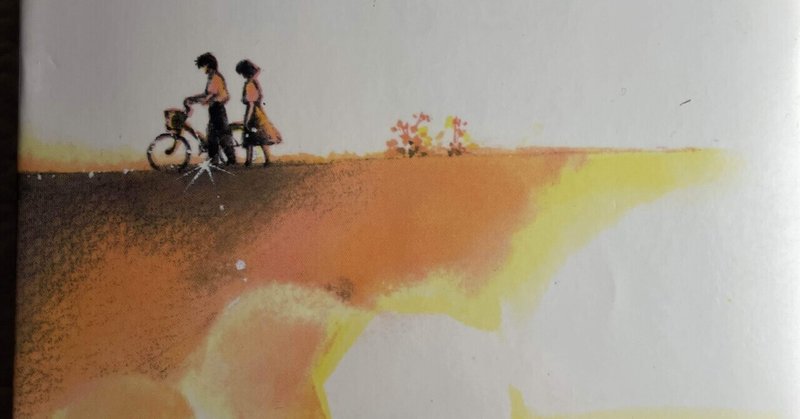
瞬きもせず
紡木たく先生の代表作は『ホットロード』であるが、映画化されたのは2014年の事なので、作品完結から数えると1987年で30年弱の年月を経ての映画化だった。作家の紡木先生は2007年12月に『マイガーディナー』という作品を出したのが最後、現在では活動を休止している。巷では、牧師として活動していると噂されているが、先生の次回作を私はとても楽しみにしている。
この先生、表紙の絵がとても情緒的で素敵なのだ。それを実感したのは『瞬きもせず』という作品に出会ってからだ。水彩画のタッチで描いたのだろう表紙はどれも繊細で、光の当たり方を美しく表現している。
さて、この作品。素敵なのは表紙だけでは無い。そもそも、この作品はネットサーフィンをしていた時に「面白い少女漫画を語ろう」といった内容のページを開いたときに見つけた。興味を持った私はアマゾンで古本が無いか検索したが、なんせ1980年代の作品なので中古は無く電子書籍がある状態だった。
それでも、「本は紙媒体がいい」と謎の執念を持っている私はkindleで読むことは無く、そのまま保留にしていた。
その後すぐ、友人と行った古本屋で偶然にも紙媒体の本書を手に入れることが出来た。(1~7巻の中で3巻だけが抜けていたが、この際それでいいと思った)ちょっと、宝くじに当たったような幸運を噛みしめてから、本書を開いた。
読んだ感想は、「え。これ、私の知っている少女漫画じゃない」だった。
まるで、少女の日常にそのままカメラを当てて撮ってきたような作品なのだ。そう、フィクションでありながらそう思わせないリアルさがあった。
一回、これ原作小説なのか?と思ったほどで、もう、とにかく言葉に言い表せないが、読んでるときに脳内で音が再生されるくらいにはリアル。
びっくり通り越して唖然としている。まさか漫画で音を脳内再生する日が来るなんて思わなかった。
多分それは、風景と共に人物を描いているからだろうなと思う。いや、漫画なら風景も人物も描くだろうって話なのだが、この先生、風景と自然音を中心で描いていて、あまり少女漫画で良くある人物に焦点(人を大きく描くというか)を当てて描かないのだ。
多分この先生の漫画を見たことがある人は何となく言わんとしていることがわかる…と思う。
そして、この作品の最大の魅力は何度でも言うが、自然光の演出の仕方が秀逸なところにある。この『瞬きもせず』に関しては、すべての光が温かい。光に「愛」を感じる。
あと、キャラクターの表情。紺野くんの笑った顔に私は恋したよ。(大真面目)この先生の描く男キャラ、まごうことなきイケメン。後ろ姿さえもイケメン。表情をあまり描かないシーンを取り入れてるのが効果的なのか、想像するのが楽しい。
ストーリーに関しても、話を盛らないというか、進路にしても、恋にしても、家族との絆にしても誰もが通りそうな日常に色を付けたような作りなのだ。ゆえにこの話は淡々としている。それなのに最後まで飽きることなく読み進めることが出来る。ちなみに、学園物語であるが卒業までを描いているのではなく、卒業後の話も書いていて、もはや卒業後の話の方が本題なんじゃないか?と思うくらいだ。
「瞬きもせず」は、主人公の心の成長に焦点を当てて描いている。悩んで苦しんで、自分で決めて自分で進む。物語終盤で、恋人と東京に行くために父親の反対を押し切る場面があるのだが、この時から主人公は子供では無く大人になろうと足掻いていたのではないかと思う。
卒業後、主人公は街を離れるバスの中で追いかけてくる父親を見切って、東京の地へ向かうシーンがある。高校卒業は学生生活の終わりと同時に親からの卒業でもある。そんなふうに感じる。
さて、この後無事東京で生活をする事になった紺野くんと主人公のかよ子ちゃんであるが、家族が倒れたり、東京の厳しさについていけなくなったりで結局二人は最終的に故郷の山口に戻る事になる。
紡木先生なかなかスパルタなことをするが、そんな中でもこの物語は、最初から最後まで愛で溢れているのが不思議なところ。
かよ子ちゃんと紺野くんの純愛、かよ子ちゃんと家族の愛、かよ子ちゃんと親友の友愛…
この物語は人間愛を描いているのだ。
是非、どこかでこの作品と出会ったら手に取って読んでみてほしい。
長々と語ってしまったが、やはり私は最後まで来ると、集中が続かなく疲れてしまうようで、文章にまとまりがないというか、投げやりになってしまう。これを克服するには、やはり数をこなすしかないのだろう。
余談だが、この作品を電子書籍で読まなくてよかった。あの日、古本屋で出会った「瞬きもせず」は経年劣化の為、紙が変色していた。その変色した本のページを捲るたびに、この本の30年以上の歴史を感じた。そのくらい長い間誰かに大切にされて、誰かの本棚の中にいた。
何となく感傷的な、懐かしいような気持ちになれるのが紙書籍の醍醐味なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
