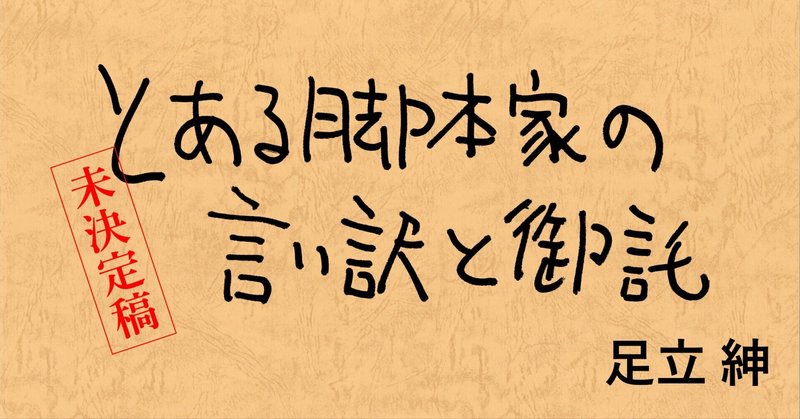
第5回 脚本と小説は仲が悪い?
[編集部からの連載ご案内]
ドラマが話題になるとなにかと脚本家にも注目が集まる昨今。それでも「脚本家」の仕事は、まだまだ知らないことだらけ……。脚本を担当されるNHK朝ドラ『ブギウギ』もいよいよ来月スタート、いま大注目の脚本家・監督の足立紳さんによる、脱線混じりの脚本(家)についての話。(月1回更新予定)
今月、僕の書いた小説が発売されます。書いたといっても2018年から2021年にかけて『キネマ旬報』に連載していた「春よ来い、マジで来い」という青春小説をまとめたものなので、最近書いたものではありません(もちろん加筆修正はしていますが)。内容は僕が脚本家になる前の話で、20代後半から30歳にかけて友人と一緒に住んでいたころの話を元に、お笑い芸人、小説家志望、助監督の若者、そして脚本家志望の主人公4人が共同生活しているといういわゆるトキワ荘ものです。ただし、こちらは全員才能が皆無のトキワ荘です。よろしければぜひ読んでください。
と、のっけから宣伝で恐縮なのですが、僕はこれまでに数冊、小説を書く機会に恵まれまして、今回は小説と脚本の書き方の違いというのか、違うものなので書き方が違って当然なのですが、どっちがどうだみたいな話を書きたいと思います。ただ、どっちがどうだといっても僕は小説に関してはド素人なので、ちゃんとしたことは書けないと思いますと最初に言い訳をさせてください。
僕が初めて小説を書いたのは今から15年ほど前のことでした。小説というのは、脚本と違って「ちゃんとした人が書く」というイメージが僕の中にはありましたので、書いてみようなんてさらさら思いもしませんでした。「ちゃんとした人」ってどんな人なんだって感じですが、日本や世界の文学全集などをほとんど読んでいる人という意味です。もしかしたら小説家の方でもそんなものはほとんど読んでいないという方がたくさんいらっしゃるのかもしれませんがなんとなくそんなイメージがありました。脚本家ですら(脚本家の方々すみません!)、多くの方々は古今東西の名作映画からつまらない映画までよくご覧になっている方が本当に多いので、単純に脚本よりも何倍も文字の多い、歴史の長い小説となると、その勉強量もハンパではないだろうと思っていたのです。雑誌などに小説家の書斎の写真なんかが載ると、床から天井まで本が積み上げられているイメージもあります。僕の部屋に積み上げられているものといえば『週刊プロレス』とホラー映画ムックくらいでしたから。
では、そんな僕がなぜ小説を書いたかと言いますと、妻に「書いてみれば」と言われたからです。といっても妻は僕に小説の才があると思ったわけではなく、当時35、6歳の無職の僕を見て、映画監督という集団作業を司る能力はこいつにはなさそうだと感じ、かといって脚本を書くということも、実は監督やプロデューサーたちとのほぼ集団作業であることもわかったようで、「アンタは人との共同作業は難しそうだから、一人でできる小説というもののほうが向いているかもしれない」と言ったのです。まさにここが小説と脚本の大きな違いです。
脚本は監督やプロデューサー、ほか数多くのスタッフさんや俳優さんたちの意見でどんどん手を入れていきますが、小説は自分と担当の編集者の二人だけ作ります。作りますと思わず書いてしまいましたが、小説を作るという言い方はあまり聞きません。やはり「書く」と言ったほうがピンときます。かたや脚本は「作る」という言い方のほうがポピュラーかもしれません。もちろん「書く」とも言いますが、「今、脚本作っててさぁ」とか「ホン作りに困っててさぁ」なんて監督やプロデューサーの方々はよく言いますし、もちろん脚本家もそんな言い方をします。ああでもないこうでもないと、みんなで寄ってたかって意見を言い合いながら作っていきますので、「ホン作り」なんて言うのでしょう。
初めて仕事として小説を書いて、最初に編集者の方に読んでもらったとき、「きっとこのあと検討稿、準備稿を経て決定稿となるまでには多くの超えなければならない人間たちが出てくるのだろうなあ」と思ってビビっていたのですが、最後まで編集者の方一人だけだったので、僕は驚きました。しかも小説の編集者の方がこれほど書き手に寄り添ってくれるとは思いもしませんでした。寄り添ってくれるというのは面白がってくれるという意味ですが、メールや電話で気分を乗せてくださいます。
逆に脚本というのは、「検討稿」「準備稿」などという呼び名があるように、いつまで叩き台なのだろうかと思うほど原稿を何度も何度も叩いて叩いて叩いて、皆さんが叩き疲れて、脚本家はすでにボロボロ、息も絶え絶え、瀕死の状態になった頃にようやく「決定稿」となります(ちなみに脚本に入る前もプロットを何度も書き直します)。ですので一番大きな違いというのは、孤独な作業ではありながら、実は脚本は集団作業であり、小説は基本的に一人の作業というところかと思います。
で、妻に言われて初めて小説を書いたときの話に戻りますと、その小説は「朝、泣く」というタイトルで、無職の中年男が仕事の帰りの遅い妻に対して浮気を疑い、酔って帰って寝てしまった妻の身体や下着などをくまなく調べて、夜明けに妻の財布から1万円札を抜いて涙するという内容で、その頃からそんな話ばかり書いていたのですが、なんと言っても一番苦労したのは場面転換でした。小説だとどのように次の場面に移っていいのかがわからなくなってしまったのです。
この難しさをうまく説明できないのですが、脚本ですと、2時間の映画でだいたい100個くらいの場面(シーン)があり、ひとつの場面が終われば、次にどんな場面がくればいいのかを熟考することはありますが、どうやって次の場面にいけばいいのかわからないということはありません。その場面の芝居は必ず終わりますから。ひとつの場面はひとつの芝居で作られていて、つまり2時間の映画だと100個くらいの芝居で構成されています。耳慣れた言葉で言うと、100個くらいのコントで成り立っている感じでしょうか。そのひとつのコントが終わらずにシーン1だけで数時間やって終わる映画ももしかしたらこの世にあるかもしれませんが、とにかくその場面の芝居は終わります。終われば次の場面にいくだけです。これが小説になりますと、書いているものが「芝居」ではないので、いつまでも書き続けてしまうことができます。映画やドラマでは省略している部分を、小説では書き続けてしまい、いつの間にそこから抜け出せなくなり、気がつくと話が進んでいないということが今でもよくあります。
初めて書いた「朝、泣く」は、原稿用紙百枚以内という規定の文學界新人賞に応募しようと書き出したのですが(結局は一次審査も通らず)、話の大筋にはあまり関係のない、でもどうしてこの夫婦が一緒にいるのかという重要な説明にもなる妻と夫の出会いのことを書いていると、半分くらい原稿が進んでしまって、肝心の「夫が妻の帰りを待っている話」を書く分量が少なくなって困りました。何を書いて何を書かないかの判断のようなものが小説ではいまだにつかなかったりします。2時間程度の映画だと省略してしまう登場人物たちの様々なバックボーンを、小説では書いてしまいたくなるのかもしれません。
あと、小説を書いていて慣れないのは、セリフの分量が多くなることでしょうか。どうしても脚本を書いているクセがとれなくて、読み返してみると、セリフのやり取りが延々と続いているなんてこともよくあります。これだとどんなに良いセリフが書かれていたとしても、小説としては中身がスカスカのように見えてしまいます。脚本ではすべきではないと言われている情景・心情描写をガンガンしていくのが小説でもあると思いますので(もちろんそうでない形の小説もあると思いますが)、それをもっと書かなきゃもっと書かなきゃという強迫観念のようなものに囚われてもしまいます。
小説は僕にとっては難しいとばかり書いていますが、脚本と違って決まった形式というものもありませんし、基本的には何をどう書いてもいいので、自由度は脚本よりもグッと高いです。ですので、僕とは反対に小説家の方が脚本を書こうとすると(そんなこと滅多にないでしょうが、たまに小説家の人が映画を撮るとご自分で脚本を書いているイメージがあります)、これはモーレツなストレスかもしれません。「怒りをたぎらせるように燃える火」とか「地球を飲み込みそうな猛烈な台風」などという、小説には頻繁に登場する比喩が書けませんし(以前にも書きましたが、そんな火もそんな台風も実際には存在しないので撮れない)、撮影や俳優さんの条件など多くの縛りが出てきてしまうのが脚本です。
そして、そんなふうに自由に書かれた小説というものを、生身の人間が演じてもウソ臭くならないように芝居に起こしていくのが脚本家の作業なので、小説家の方からすると「なにぃ! この脚本家は俺の書いてることを1ミリも理解してねえじゃねえか!」とその逆鱗に触れることもしばしばあります。一方の脚本家からすると「なにぃ! お前の書いてるつまんねえ小説をいろいろ考えてここまで面白くしてやってんだよ!」などと反論してしまい、物別れになるという局面もたまにあります。小説と脚本は同じ文字で書かれていても、文字で完結している小説というものと、映像を前提とした文字という脚本とでは正反対のものなのかもしれません。
そしてこれは、小説家のどなたの言葉だったのか忘れてしまったのですが「映像化できる時点でその小説はたいしたものではない」というようなことをおっしゃっていて(正確ではありません!)、なるほどなあと思ったことがあります。それはお金がかかるとかそういう問題ではなく、小説として最高の作品に仕上げている文章を映像で超えられるのかという意味だと思います。超えられないのであれば、商売を抜きに考えるとたしかに映像化する意味はありませんし(ビジネスなので商売抜きに考えることは無意味なのですが)、小説家の方々も「映像化してほしい!」などと思いながら書くのはよせとその方は言いたかったのだと思います。
なんだか小説家と脚本家はうまく共存できないというような話になってきてしまいましたが、実際、小説と脚本というのは、本来とても仲の悪いものなのかもしれません。ですが僕は、山田太一さんのように、両方とうまく付き合えるような脚本家になるのが目標でもあります。
足立紳(あだち・しん)
1972年鳥取県生まれ。日本映画学校(現・日本映画大学)卒業後、相米慎二監督に師事。2014年『百円の恋』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞、菊島隆三賞など受賞。2016年、NHKドラマ『佐知とマユ』にて市川森一脚本賞受賞。同年『14の夜』で映画監督デビュー。2019年、原作・脚本・監督を手掛けた『喜劇 愛妻物語』で第32回東京国際映画祭最優秀脚本賞を受賞。その他の脚本作品に『劇場版アンダードッグ 前編・後編』『拾われた男 LOST MAN FOUND』など多数。2023年後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』の脚本も担当する。監督最新作『雑魚どもよ、大志を抱け!』が2023年3月に公開。著書に『喜劇 愛妻物語』『14の夜』『弱虫日記』『それでも俺は、妻としたい』『したいとか、したくないとかの話じゃない』など。現在「ゲットナビweb」で日記「後ろ向きで進む」連載中。
足立紳の個人事務所 TAMAKAN Twitter:@shin_adachi_
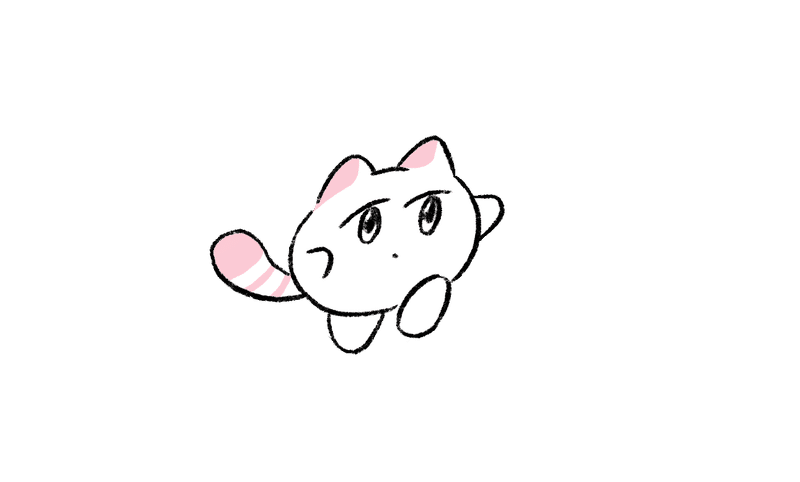
/ ぜひ、ご感想をお寄せください! \
⭐️↑クリック↑⭐️
▼この連載のほかの記事▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
