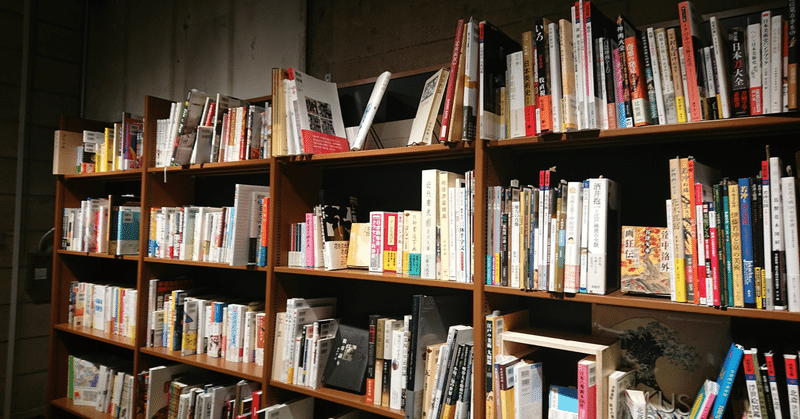
読書会をしています。「7つの習慣」8信頼残高ためてますか??
学年で読書会をしています。
読んでいるのは「7つの習慣」。学年の構成は、初任者、中堅2人、学年主任1人です。それぞれの読み方があって本当に面白い。読書会。大好きです。
前回までは「私的成功」、「自立」をめざすことでしたが、今回からは「公的成功」、「相互依存」について書いていきます。
まず第4の習慣に入る前に
「公的成功」の章があります。
人と人が協力し合って力を合わせて結果を出すことを「公的成功」といいます。
私たちは誰でも人の存在なくして生きていけません。
「悩み事は元をたどれば全て人間関係だ」という人もいます。
私たちは人間関係によって悩み、問題を抱えています。
問題を抱えること自体が、「公的成功のパラダイム」を理解するには重要だとコヴィーさんは言います。
では、よい人間関係はどのように作ればよいのでしょうか?
それは、「信頼残高をふやす」ことです。
銀行の残高と同じように、私とあなたの間にある銀行にお金ではなく、信頼という残高をためていくのです。
信頼残高はどのようにしてたまるのでしょうか。
①相手を理解すること
②小さな気遣いをすること
③約束を守ること
④期待を明確にすること
⑤誠実さを示すこと
⑥残高を減らしてしまったときは心から謝ること
難しい言葉ではないのですが、どれも実行し続けることは難しそうです。
一番は、「相手の話を聞いてやること」だとコヴィーさんは言います。
私のカウンセリングの師匠は「同感」と「共感」は区別しよう
といいましたが、これはなかなか難しい。
「共感」は難しいけれど「共感的態度」はできる。
まず、「相手の話を聞こう」と日常的に意識し、目標にすることはできるのではないかと思います。
余裕ができたところで、①~⑥のどれかを重点目標にしてやっていこうかと思います。
公的成功は私的成功の「自立」なくしてはありえない、とコヴィーさんは言います。
愛の法則は相手が、「自分の内面から湧き上がる意欲に従って行動する自由を与える」ことだと言います。
この辺、私はすごく勇気をもらえます。
信頼残高を増やすことは、難しいことを教えることでも、無理にお説教することでもないのです。
子どもの話を聞き、子供の意欲に従って行動するための自由を与えられるよう、関わっていきたいと思います。
自分で自分を高める子になる
人の心が育つ家HAG
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
