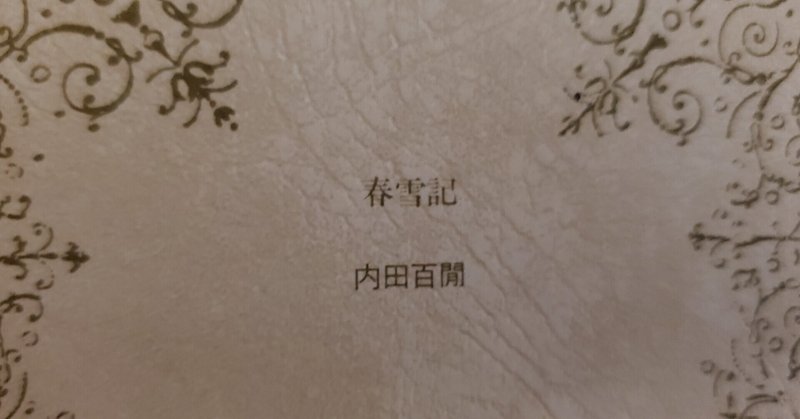
路面電車幻想その4・内田百閒の東京
新宿歴史博物館の「路面電車と新宿風景」という展示の中で、路面電車の登場する文学作品を紹介するコーナーがあり、夏目漱石、林芙美子、寺田寅彦、内田百閒などが紹介されていた。
内田百閒は「東京焼儘」の一節。
「東京焼盡」は今手元にないので正確な引用は出来ないが、路面電車に乗って大空襲の後の焼け野原の東京を見て、良いも悪いもなくただただ馬鹿馬鹿しい、と思った、というような部分だったと思う。
内田百閒と言えば有名な「阿房列車」などで汽車の旅について書いているが、路面電車については何か書いているのだろうか。
noteで文章を書くにあたって勝手に名前を借りたくらい好きな作家ではあるのだが、何年か前に、持っていた本やCDをほとんど処分してしまったので、内田百閒の本もあまり手元に残っていない。
だからすぐに確かめることができないのだが、路面電車についての話があったかと言うと、どうも思い出せない。
今探してみたら手元に残っている内田百閒の本は河出文庫の「芥川龍之介雑記帖」と、福武文庫の「春雪記」の2冊のみ。どちらも随筆集である。
「春雪記」は東京での生活について書いた随筆を集めたもので、あらためてこれを読んでみると意外にも路面電車についての描写はけっこうある。
非日常な面のある汽車の旅とは違って、路面電車はごく当たり前の交通手段であって、日常の描写の中にさらっと書いてあるので印象に残りづらいのかもしれない。
「春雪記」の中から少し引用してみる。
腹がへっていて不安である。来る時電車を降りた停留場の向う側に、「もり、かけ六銭」と書いた紙を表の格子に貼った蕎麦屋があった。その当時、普通の店は八銭であったから、安い。掃除町の裏通を歩きながら、その張り紙の事が頻りに気に掛かる。帰りの電車賃は持っている。七銭であったか、八銭であったか、はっきりしないが、六銭のそばを食べるには事を欠かない。しかしそれだけしか持っていないので、ここで口腹の欲を充たせば、帰り途は歩かなければならない。小石川掃除町は白山の下である。そこから伝通院の安藤坂を降り、又は偕楽園の外を半回りして早稲田の終点の先まで歩いて帰るのは大変である。おなかの方を我慢して、急いで電車に乗ってしまおうか、それとも覚悟をきめて歩くとして、停留場前の蕎麦屋で盛りを食べようか。
(内田百閒「面影橋」より)
単に「電車」と書いているので山手線や中央線といった普通の電車と区別がつきにくい。もしかしたらそれで路面電車という印象が薄かったのかもしれない。「停留場」と書いていれば路面電車ということになるのだろうか。
芥川龍之介君の田端の家を訪ねたが、いなかった。当時の市電の終点だった早稲田の奥の下宿屋にいた時で、そこから電車で途中乗り換えながら、チンチンゴウと田端に近い駒込の停留場まで行くのは随分遠い。
目的地が近くなった駒込籠町まで来た時、電車が停まった停留場の前に洋食屋があって、その軒先に人の目につく大きな立看板が立て掛けてある。「特製ライスカレー十三銭」
特にライスカレーが好きと云うのでもないが、目に見たので食べたいなと思った。こちらの腹の加減もあったのだろう。第一、十三銭は大変安い。その当時は十八銭から二十銭ぐらいが普通の値段であった。
(内田百閒「六区を散らかす」より)
やたらと飯の話が出てくる。
内田百閒の随筆の題材で一番多いのは借金についてではないかと思うくらいで、ずいぶん金銭的に苦労をしたらしいが、なかでもこの「早稲田の奥の下宿屋」に家族からも離れて一人で住んでいた時期は、はっきりとは書いていないが色々大変だったらしい。
私は学校を出て家を持ち、教師になって何年かを過ごしたが、自分の不始末で暫らくどこかに蒙塵し息を殺していなければならぬ羽目に陥った。家の内患外憂を処理出来なくなったのである。
(内田百閒「面影橋」より)
「早稲田の奥の下宿屋」にいた時の話として、下宿の前を流れている川が増水する、という話が出てくる。
その川は「神田上水」で、「すぐ近くの下流で面影橋の下をくぐり」とあるので、高田馬場に近いあたりだろうか。
「下宿屋は早稲田の終点に近い。当時の市内電車のこの方面の系統は、長い間江戸川橋止まりであったが、後に早稲田まで延びて早稲田が終点になった。」
とある。
今も早稲田には路面電車(都電荒川線)が走っているが、江戸川橋は通っていないので、これは別の系統だろうか。
高田馬場附近の、神田川が山手線および西武新宿線の線路の下を流れる辺りは、ぼくが子供の頃まではまだよく氾濫して電車が止まり、西武新宿線で通勤していた父親の帰りが遅くなったりしたのを憶えている。
さて、ここまで引用してきたのは随筆なので、とくに「幻想」の要素は無い。
内田百閒は、小説の方では夏目漱石の「夢十夜」の系譜につながる幻想的な小品を多数書いているが、その中に路面電車が印象的な形で出てくる作品があったかどうか、これもちょっと思い出せない。
けれども、はるか昔の東京で、芥川龍之介やら内田百閒やらが路面電車に乗ってあっちこっちにうろうろしているのを想像すると、その「東京」は、今の自分から見るとやはり幻想の中にあるようにも感じられる。
最期に、内田百閒の「春雪記」の中で、路面電車は出てこないが、印象的かつ幻想的な部分を引用して終わりにする。
大正何年であったか宙では思い出せないけれど帝国劇場へ原信子の帰朝独唱会を聴きに行った。九時頃に終わって外に出て見ると西の空一面に大きな火の手が挙がってそれをうつしたお濠の水が真赤になっている。すぐその足で見に行った。二千軒ばかり焼けた新宿の大火事であって、四谷見附の辺りからは空に映った火の手ではなく、じかに大きな焔の柱が見えた。風に押されて焔が傾き、その尾が千駄ヶ谷の森の上に流れて火の子を雨のように降らした。
その大火事があってから新宿の界隈は少し綺麗になり、段々に今の様な繁華な街になったが、それ迄は駅の前通は馬糞だらけで風が吹けば飛ぶし、雨が降ったら道の泥と馬糞がこったくね返して歩けやしない。四谷の方に出る往来の両側は女郎屋ばかりで昔の宿場の趣きがその儘残っていた。その奥にある馬糞の中の新宿駅から今日の新宿駅を同じ場所に想像する事は六ずかしい
(内田百閒「その時分」より)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
