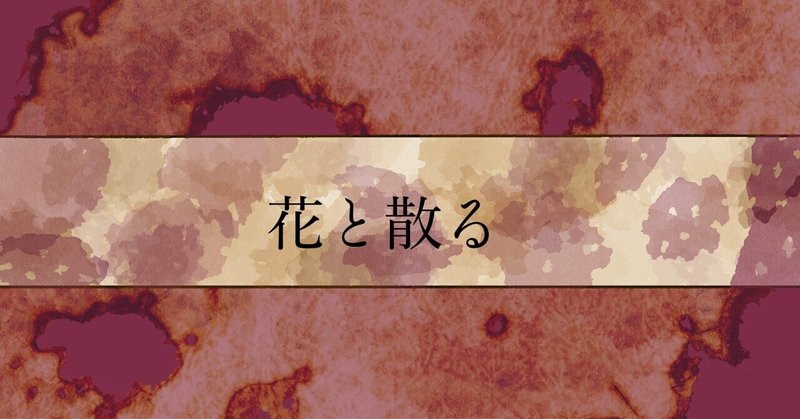
クローサー・エンダー/上【花と散る】
《一》
もう、限界だった。
思い当たる節なんて、腐るほどにある。
責任の重圧や周囲との人間関係、金銭問題、自己嫌悪。無限のストレッサーに心を病んだのだろう。影太はぼんやりとした足取りで、ひび割れたアスファルトの上をさまよう。
気休め程度に着けていたイヤホンからは、適当に流したランキングトップのバラードが流れている。いやに陰気に聞こえるのは世間の流行のせいか、それとも自分の気持ちのせいか。
気がつけば手すりを越え、遠い空を眺めていた。一二月の夜風が頬を撫でる。こんな時でも、自分に優しくしてくれる者は居ないのか。そんな緩やかな絶望は、冷たい鉄塊に絡ませた指の力を抜かせていった。
見下ろせば、ゆらゆらと揺蕩う広くどす黒い水面がある。この町で一番大きな川だ。着衣のまま飛び降りれば、生きて岸まで上がることは容易ではないだろう。そんなこと、素人でも想像できた。
耳元でごうごうとなる車の走行音は、ただ一つとして影太の存在に気づいた様子はない。車道の幅の割に歩道の通行量も殆どない。これから身を投げる影太にとってはむしろ好都合だ。
イヤホンからは絶えずバラードが流れる。
もうすぐだ。もうすぐ楽になれる。
ごくりとつばを飲み、鉄線に絡む両手の片方を解く。古びた柵はパラパラとさびを落とし、耳障りな音を立てる。
この手を離せば、終わる。楽になれる。
心の中でそうほくそ笑むも、体はこれから先の未来を拒むように動かない。
あと少し。あと少しなのに。
気がつけば首筋に冷や汗が流れていた。今更、怖じ気づいたのか?存外臆病な自分の本性を嘲りながら、今一度決心を固める。
「……」
駄目だった。
詰まった息が白い霧と消える。妙な脱力感が全身をつつみ、今日はもう諦めようと手すりを乗り越えた。その時。
「飛び降りないの」
女の声が聞こえた。ややハスキーだが、張りのある声だ。腹の中煮詰まった臓器という臓器が、纏めて飛び跳ねる。
恐る恐る声のする方に視線を向けると、自分と同じくらいの若い女性が立っていた。つんと跳ねた睫に、にっと笑ったように細まった目。冬だというのに薄手のパーカーとショートパンツを身につけている。近所のコンビニへ出かけるかのようなラフな装いだ。
ポケットに手を突っ込みながら、小首を傾げている。さっくりと短く切りそろえた髪がよく似合っている。真っ暗な中に現れた彼女の姿に、思わず呆然とした。
「質問してるんだけど、飛び降りるの?」
彼女は再び質問をする。ほんの少し、不満そうにゆがめられたあまりにも突然の出来事に狼狽える影太は、口をはくはくと動かすも声を出せないでいる。
「ちきってんの。ださいね」
嘲るような一言と共に、女は影太の近くに歩み寄ってくる。想像より小柄な体は簡単に影太の目の前までやってくる。上目遣いですぅっと細められた瞳の奥から、真っ黒な闇が覗く。底知れない深淵を垣間見た気がして、息を呑む。
「でも、いいよ。その顔」
「え、」
「最高にセクシーってこと」
頬に、柔らかいものがふれた。ほんの少し湿り、ささくれだったそれが彼女の唇だと知ったその瞬間。燃えるように体が熱くなった。
「あ、」
片足だけで支えられていたバランスの悪い体は、ぐらりと揺らぐ。最後の一点の支えを失った体は吸い込まれるように川に落ちていく。
これでいい、これで良かった。
そのはずなのに、影太の腕は焦がれるように女の方へ伸ばされる。トラックのヘッドライトに照らされ、一瞬だけ写った彼女の顔は、実に満足げなものだった。
《二》
意識が戻って初めて感じたのは、つんと刺すような薬品の匂いだった。
「あら、お目覚めになりましたか」
ゆっくりと目を開くと白衣を纏った女性が立っていた。看護師だろう、こちらに向かってにっこりと微笑んでいる。彼女は、影太の腕に繋がっている点滴を取り替えていた。
瞬間、「ああ、また失敗したのか」と失望ににた安堵が。
「今から先生読んできますので少し待っていてくださいね」
看護師が立ち去ってしばらくすると、初老の男性がやってきた。目元に深く皺の入った、白衣が特徴的だ。影太は彼が医師なのだろうと悟る。
「天白さん。貴方は自分のことについて覚えていますか?」
「はい、……」
影太は記憶の奥から、あの時の出来事を引き出した。
橋の上から飛び降りようとして、できなくて……
ポツポツと話し続けていく。医師は何かを確認するように、よし、よしと相づちを打った。全てを話し終えたところで、彼はゆっくりと話しだす。
「そうですか、よかった。記憶の方は安定していますね。貴方が寝ている間に色々と調べさせていただきましたが幸運なことに特に異常はありませんでした。もっとも、一番の幸運は貴方が川に落ちた瞬間、近くに居た人がね、通報して川から担ぎ出してくれたことですかね。貴方にとって不幸なことかもしれませんが」
そう言って神妙な面持ちでカルテを捲る。
「念のため、数日ここで様子を見ましょう。退院した後、しばらく通院してもらおうと思います」
「……異常は無いんじゃないですか」
「ここではなく精神科です」
影太の微かな声を、ばさりと医師はかき消した。
「……天白さん。貴方の心は今、病に冒されています。これは治療が可能なんです。治療を受けなければ貴方はいずれ、また同じことを繰り返すでしょう」
「でも」
「貴方は幸運にもたいした後遺症は無く無事ですが、自殺の大半は失敗に終わります。失敗した自殺願望者がどうなったか知りたいですが」
穏やかな瞳の奥から、真剣な眼差しが溢れた。
「……わかりました」
「では、お薬を処方しておきます。毎食後、しっかりと服用するように」
「はい」
医師は会釈すると、その場を痕にした。一人残された影太は、ぽっかりと開いた心を抱き、呆然と窓の外を見つめた。裸の木々が、冷たい風に去れされているのを見るのが、いやに辛かった。
数日後、退院した影太は部屋に帰ってきて居た。会社には入院中、退職の旨を伝えており、帰宅時にコンビニで口座を確認すると、決行な量の金額が振り込まれていた。
だが先ほどの入院費を含めて、治療費や今後の生活日を考えると、もって一ヶ月程。保険料をケチらなければ……と後悔しても後の祭り。この後の生活を思い。ハローワーク、医療費、その他手続き諸々。頭を巡る面倒ごとにため息を吐きながら家のドアに鍵を指そうとしたその時。
「あの、八〇三号室の方ですかー?」
女に呼ばれた。ややハスキーだが張りのある、若い女の声……瞬間、あの時橋の側での光景がフラッシュバックする。ほのかな土の香りと、柔らかな感触。心臓の鼓動が早まり、呼吸は小刻みに震える。
恐る恐る振り返る。
「あ、どうも。私、こないだここに引っ越してきた者です。なかなかお会いできなくて、挨拶できなくてすみませんー」
パーカーに、軽いショートヘア。細まり、美しく濁った瞳。
間違いない、あの時の女だ。
「って、あ!もしかしてあの時の?」
彼女も気がついたのか、何故か目を輝かせこちらの顔を覗き込んで来る。
「そうだそうだ、やっぱり。無事だったんだね」
「ひっ……」
影太は後ずさりするも、女は構わず迫ってくる。
「その様子だと、私のことを覚えてるみたいだね。ね、これから暇?お茶しない?近所に良さそうなカフェあるの見つけたんだけど一緒にどう?」
断ろうにも拒絶の言葉が出てこない。それを黙認と理解した彼女はにこっと悪魔のような笑顔を浮かべた。
「ふふ、じゃあ決定。早速いこうか」
あれよあれよという間に、名も知らぬ女と出かけることになってしまった。
つれて行かれたのは、電車で二駅も離れたカフェ。近くというのだから、徒歩圏内だろうと思っていた。駅の改札を通らされたときは帰りたくて仕方が無かった。彼女にとっては数駅県内は近くなのだろうが、影太にとっては重い腰を上げて向かう距離だ。
カフェにつくと、女はメニューを覗き込みながら、機嫌良く鼻歌を歌う。
「好きなもの食べていいよ。今日は私の奢りだからさ。私ここのパフェ食べてみたかったんだよね。甘い物は好き?私は大好きなんだ。職業柄、どうしても欲しくなってしまうんだよね」
にこにこ顔でメニューを熟読する女とは裏腹に、影太は縮こまり帰る言い訳を考えていた。何故、ついて行くと言ってしまったのだろうか。早く帰らせて欲しい。そもそも名前すら知らないし、本当に隣に住んでいるかも怪しい。
「あの、僕帰ります……」
「遠慮してるの?いいのに」
「いや、だって。さっき会ったばかりの、しかも名前だってまだ知らないですし」
「そんなこと気にしているの?そういえば自己紹介してなかったね、あ、店員さーん、私このパフェとブレンド珈琲。で、君は?」
やってきた店員と女の視線に耐えかね、仕方なくカフェオレを一つ頼む。店員はひとつお辞儀をすると、キッチンの方に向かっていった。
「サヤ」
「え、」
「私の名前。本名じゃなくて、所謂ペンネームみたいなもんだけど。誘う夜って描いてサヤ。どう、我ながらキャッチャーで魅力的な名前だと思うんだけど」
ん?と肯定を待ち望む眼差から逃れるように顔を背ける。
「天白影太、です」
「ふん、いい名前だね。語感もさることながら白に影、相対する様相が並んでいるのもいい。名は体を表すと言うし、君にぴったりだ」
誘夜は笑顔でそう言った。
物心ついた時から、『影』というマイナス要素を孕んだ文字を持つ自分の名前が好きでは無かった。周囲からはそれが理由で揶揄われたこともあったし、どこへ行っても彼女のような皮肉を投げかけられてきた。
むっとした表情に気がついた誘夜は、口元に手を当て微笑む。妙に上品なのが癪に障った。
「ごめんごめん、気を悪くしたなら誤るよ」
「……茶化しているんですか。本当に帰りますよ」
「ちょっとまって」
腕を捕まれた。白くて細っこい割に妙に力が強い。
「褒めているんだ。美しい……耽美って行った方がいいのかな。生白い肌に黒檀のように黒い瞳ががなんといえない。纏う色気も、常人離れした独特のものを感じる。素敵だよっって、言いたかったんだ」
「な、ななな、なんですか!」
顔が一気に熱くなったのがわかる。
冗談はやめてください。
せめてもの抵抗に言い返そうとするも、緊張で言葉が出てこない。そんな影太をよそに、誘夜はもう一方の手も重ねる。
「全部、全てが本心だよ。この目が嘘を言っているように見える?」
子どもをあやすような静かな物言いに、思わず腰を下ろしてしまった。熱くなった目をきつく閉め、呼吸を整える。
「少し早いけど、本題を話そうか。天白くん、君にモデルをやって欲しい」
「も、モデル……?」
モデルと言えば、綺麗な服を着て写真に写るような、アレか?でも、なんで僕が?
沸騰しきった脳では、思考すら侭ならない。ぼうっと視線を泳がせる影太に、誘夜はゆっくりと説明し始める。
「私は画家なんだ。私の絵のモデルを君に頼みたい。初めて君と会ったとき、まるで雷が落ちたかのようだった。ああ、私には君が必要なんだ。君なしでは、私は私を確立することができないんだ。一瞬でそれを理解したよ。君は最高なんだ。今まで出会った誰よりも素晴らしい、私の理想そのものなんだ」
「そんあ、急に言われても……」
「金の心配?大丈夫、私はこう見えて金銭感覚はまともだ。お金なら出すよ」
誘夜はショルダーバッグの中から茶封筒を取り出した。一センチあるだろうその中身を想像しただ家で思考が止まった。
これから療養生活を送る身にとって、纏まった額の収入は実に魅力的だった。
《三》
結局影太は、三ヶ月だけ……という契約でモデルを務めることになってしまった。受ける気など微塵も無かったが、誘夜の圧と手渡された金額に押されたのだ。自分の情けなさにうなだれる。
それから数日後。突然家のインターフォンを鳴らしてきた誘夜によって、もう一つ茶封筒を渡された。
「な、なんですか、これ」
寝起きの目を擦りながら以前より分厚くなった封筒をくるくる回しながら眺める。
「追加分。こないだのは頭金だよ」
前の分と会わせれば、ゆうに半年は生活できる金額だろう。予想外の金額に思わず目を泳がせる。
「簡単にこんな大金を出せますね……」
「いいパトロンがいてね。私が絵を描くためなら何でもしてくれる」
得意げに胸を張る誘夜が、心底忌々しかった。
「そういえば天白くん、もしかして寝起き?」
「そ、そうですけど……」
慌てて寝癖をなでつける。
「待って待って、そのままで居て。今日は何か予定は?」
「特に、ありませんけど……」
口元に手を当て、誘夜はなるほど、と呟く。何がなるほどなのか。
「じゃあ早速、仕事頼もうかな。やだ、そんなに嫌?」
「寝起き訪問されて嫌じゃない人の方が居ませんよ」
「それは申し訳ないと思っているよ?あ、白いシャツ持ってる?」
「持ってますけど……」
「じゃあそれに着替えてきてね、待ってるから」
よろしくー、とひらひら手を振りながら誘夜は隣の部屋へと戻っていった。
「……ったく」
影太は言われるがままシャツに着替え、インターフ玄関を出た。無駄に律儀な性格が嫌になる。インターフォンを押すと、絵の具らしきもので汚れたエプロンを身につけた誘夜がひょっこりと顔を出す。
「お、もう準備できたかぁ。やる気だねぇ。あ、今度から普通に入ってきていいよ」
「お邪魔します……」
一歩、部屋に足を踏み入れた瞬間、鼻孔に独特の匂いが飛び込んできた。クレヨンの香りをもっと濃くしたような、強い油分の混じった匂い。遠い昔嗅いだような、どこか懐かしさを感じる。その正体を探すべく記憶の海をさまよいながら歩く。
「ささ。ようこそ、私のアトリエへ」
ダイニングに繋がる暖簾を捲ると、目の前に現れたのは大きなイーゼルと一脚のパイプ椅子。壁際には何十ものキャンバスに画材用のラック、無数に転がるひしゃげた絵の具チューブが転がっている。
まさに、芸術家のアトリエだ。幼心をじわりとくすぐる空間に思わず感嘆の声を零す。
「おや、気に入っていただけたようだね?ふふ」
「……いや、本物っぽいなと思っただけです」
「本物だってば。面白いことを言うね」
けらけらと笑いながら、誘夜はキッチンへと消えていった。適当に見ていていいよ、と声がしたため、影太は言われるがまま部屋を徘徊する。
キャップが開いたままの油の瓶、閉めかけの蓋の絵の具チューブ、持ち手部分に光沢が乗ったペインティングナイフ。目に入るもの全てが新鮮だった。六畳ほどしかない空間だが、何時間でも歩いていれる。
昔、憧れたはずのこの空間が、妙に心地よかった。
「……これは」
ふと一枚のキャンバスが目に入った。黒に近い藍色の背景に人の横顔が描かれているものだ。制作途中なのだろうか、ぼんやりと輪郭が描かれているだけで、顔つきまではわからない。
影太は、なぜかこの絵に釘付けになった。美しいなどという単調な感情では無く、本能が吸い寄せられるような不思議な魅力……いや、感覚に近いものだった。
「なぁーに見てるんだーい」
「うわっ」
肩口からぬっと誘夜が顔を出す。思わずしりもちをついた影太を見て彼女は笑った。
「そんなに驚かなくてもいいじゃん。ほら、カレー持ってきた。食べる?」
床に浮かれたプラスチックのトレーからは香ばしいスパイスの香りが漂っていた。底の深い紙皿二つにカレーがなみなみと注がれてている。
「レトルトだけど、下手な手作りよりはいいでしょう。はい」
影太は皿を受け取ると、どこか座る場所を探しキョロキョロと辺りを見渡す。そんな様子をよそに、誘夜は床にぺたんと座り込み、カレーを食べ始めた。
「え、床……」
「ああ、君は気にするタチか。いいよ、私は気にしないから。行儀なんてアトリエじゃあってないようなものだからさ」
言われるがまま、影太も床に正座する。プラッスチックのスプーンを受け取り、一口カレーを口に運ぶ、レンチン米独特のビニール臭とパターチキンカレーの強い匂いがぶわりと口の中を満たす。久しぶりに食べる濃い味に、無言でかぶりついた。
食事を終えると、影太はイーゼル前のパイプ椅子に座らされた。
「じゃ、始めようか。ますは、そうだなぁ……服脱いで」
「えっ」
突然の脱衣要望に、影太は身構える。それを見た誘夜はけらけらと笑う。
「か、過激な要望はしないって言ったじゃないですか!」
「あはは、ごめんごめん。冗談だってば。反応がね、君、ほら、可愛いから。シャツの胸元少し開ける程度でいいよ。そうそう、鎖骨がちらっと見えるくらい」
言われるがまま、シャツのボタンを数個外す。誘夜は満足げに頷くとポーズの指示も出し始めた。
「こう、体育座りして片足だけ床に着けて。オーケー。そのまま窓の外を軽く眺めて……最高!そのまま少しだけじっとしていて」
どこからかキャンバスを持ち出してきた誘夜は、一心不乱に鉛筆で線を描き始めた。会話は止まり、独特の筆記音と、微かな呼吸の音が狭いアトリエに響く。
先ほどまで喧しかった誘夜はすっかり黙りこくり、影太とキャンバスを交互に見つめる。髪の隙間からちらりと覗いた彼女の表情は驚くほど真剣で、思わず息をのむ。
どこか生気の無かった真っ黒な瞳の奥に自分がいるのだと思うと、ひどく小恥ずかしい。だが、彼女のそこに入っているのは、少なくとも今は自分だけだと思うと、小恥ずかしいがほんの少しだけ優越感に浸ることができた。
三〇分ほど立った頃だろうか。無機質なアラームの誘夜のふぅっというため息の音で部屋の空気が変わった。
「少し休憩しようか。飲み物飲む?麦茶しか無いけど」
「いただきます……意外でした。もっと長くかかると思ってたんですけど」
「流石に休憩は挟むよ。挟める内にね。短期集中を何セットも繰り返すのが私のやり方……なんてかっこよく言ったけど、以前座りすぎで腰をいわしてね。適度に動くようにしているんだ」
はい、と手渡すされた麦茶は、ほんの少し苦かった。
「三〇分やって一〇分休み。それを今日はあと七セット。合計四時間かな。終わったらご飯に行こう。今日はどうしようかな、さっぱりした料理がいいな」
スマートフォンをつつきながら、口コミサイトを覗く誘夜。その機嫌良さそうな横顔をじっと見つめる。
「あの」
ふと、影太が口を開いた。何の脈絡も無く、突然。
「なんだいなんだい」
「あの夜、なんで僕にキスをしたんですか」
そうだな、と首を傾げ、誘夜は悪戯っぽく笑う。
「人間ってさ、死の淵に立つと色気が凄いって言うじゃない。それなのかな?あの時の君は、粉雪のように儚くて、炎のように熱っぽくて。この上なく美しかった。だから、思わずキスしちゃった」
「……は?」
予想はしていた、して吐いたがその脳天気な言葉にぽかんと口を開ける。
「ま、鳩が豆鉄砲食らったような顔をして」
「名前も知らない男にキスをするだなんて……」
「ははは、私のような人間の貞操観念なんて所詮そんなものさ」
比較的まっとうな付き合いしかしてこなかった影太は、呆れたように口を開く。
「どうかしている」
「あはは。冬の川に飛び込もうとしていた君が言えることかい?確かに、あの時の私はどうかしていたのかもしれない。でもこんな職で生きていこうとする奴なんて、大抵ろくでもないさ」
ぴぴぴ、と携帯のタイマーが鳴った。
「さ、次のセットだ。椅子に座って」
影太は言われるがままパイプ椅子に腰かける。再び、滑らかな芯の音が部屋にこだまし始めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
