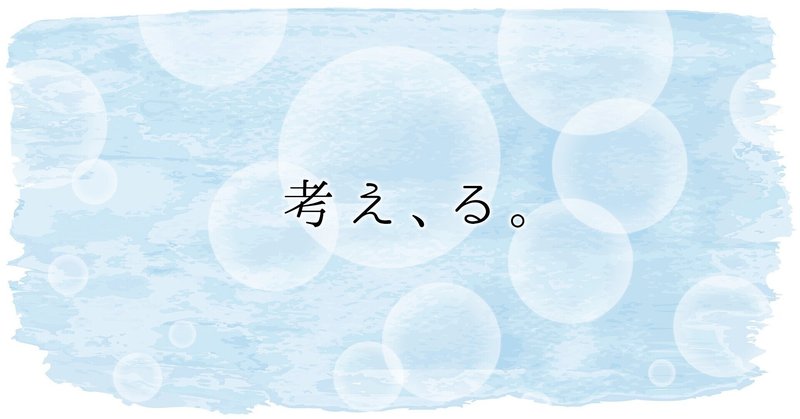
【言語技術で「考える」を強くする②】どうして言語技術を取り上げようと思ったのか?
「考える」ということをどうすれば習得できるのか?そして教えることが出来るのか?
「考える」を理解して意識的に使えるようになることで、生産性も高まり、品質も高まり、コミュニケーションもうまくいくようになる。
「考える」を身につけてもらうにはどうすればよいのだろうか?私の長年の懸案であった。その答えが「言語技術」にあった。
前回は、”私が論理思考力を身に着けるまで”をお話ししましたが、
第2回は、なぜ言語技術を広めなければならないという課題認識を持ったのか?を書きたいと思います。
なぜ課題認識を持ったのか
私自身が論理思考力を身に着ける中で、
日々様々な決定を下しながら生活していることを考えると、意識していないだけで、日常生活においても活用している思考法なのではないか?なぜ仕事になると途端に思考ができなくなってしまうのか?より効率的な学習方法があるのではないか?
と個人的に疑問を持った点については、前回述べました。さらに、メンバーをマネジメントする立場になり、指導・独習することで試行錯誤しながらなんとかやっていました。複数のメンバーのマネジメントを経験してくると、明らかに異なる傾向をもったメンバーがいることが分かってきます。
1を言えば10を理解してくれるメンバー
1を言えば1or それより少ない理解を示すメンバー
前者は仕事のスピードも速く、質も良い。特に指示していることもないのに自由にふるまっても成果を出してくれます。一方、後者の場合、まさに1から10まで細かく指示を出しながら、作業を管理し、必要に応じてフォローする。ということが必要になってきます。
この違いはどこにあるのでしょうか。前向きな姿勢?マインド?そもそもの地頭の良さ?本当にそうなのでしょうか。
理解力(思考力)の差
ということに気が付きました。前者は、言われたことをその場で反芻し、自分の理解と私の理解を合わせるためにキャッチボールを始めます。何のためにやるのですか?誰に対してやるのですか?それはこうやればいいですか?と矢継ぎ早の質問が飛びます。それにこちらが答えることでお互いのアウトプットイメージが次第に一致してきます。
後者は、言われたことを字面のまま理解しようとし、それを実行しようとします。私が話したことを”はい、わかりました。”と。その時に、あ、と感じたのです。尊敬する先輩に言われた一言があります。
お前は ”ハイハイ” っていってわかった風なのだけど、本当にわかってるのかどうかが分からない。自分の言葉でリフレインしてみなさい。
その時は ”わかりました”と、二つ返事をしたのですが、今となっては、その時点で自分の理解力のなさ(自分の言葉でリフレインしていない)に気づくべきだったと思います。その評価を受け、自分自身を振り返ってみると、仕事の手戻りが多かったことに気づかされました。
時には、わかったつもりで50ページになる超大作の資料を作ったのですが、そのレビューの冒頭で、”全体のメッセージとそれを支えるストーリーは何?”と問われて答えることが出来ず。。。そこから数時間ボコボコにされつつ、徹夜で資料を修正しました。
分かっている(つもり)のだけど、なぜ??
それは、つもり、だったからです。そのつもりの部分を正しく合わせることが出来ればこんなことにはならなかった。分からないことを分からないといわず、わかった風にやるからこの結果になったと感じたのです。
これは、同じ轍を踏む人も多いのではないか?自分がリーダーになったら、それを何とかしなければならないと思ったのです。
システムエンジニアとコンサルタントの間の大きな壁
システムエンジニアからコンサルタントに転職してこられる方々がいます。私もその中の一人でした。メンバーをリード・指導する立場になり、さらに分かったことがあります。
コンサルタントの思考法とシステムエンジニアの思考法が全く違う
何が違ったのか?その生い立ちが違うことが分かったのです。
近代のシステム開発はテンプレートに答えを埋める手法が、特に大規模開発になるとメインの作業となります。したがって、出来るだけ、要望を聞き出して、そのフォーマットを埋め、それに従って粛々と物事を進めることが求められます。自分のアイデアを提案するよりも、間違えないように、これまでにあった課題事象などの前例を踏襲し、成功させることが大切になってきています。
一方で、コンサルタントは、そもそも論から考えるべきことが多く、道なきところに道を切り開かなければなりません。課題を発見することから始まり、その解決策を導き出さなければなりません。自分で問いを導き出すことが出来ること、これが必須要件となります。
ここに、大きな壁があるのではないかと感じたのです。
ある時、某SIerさんにプロジェクトマネジメントの支援に入ったことがあるのですが、その当時本部長の方が嘆いていらっしゃいました。
”言っていることが分からないし、言っていることを理解してくれない。
考えているのかも分からないし、その答えが正しいのかも分からない”
これは、私が先輩から受けた指導そのものでした。ということは、私のように理解力(思考力)を身に着けることが出来れば、変われるのかもしれない、とそう思ったのです。
その本部長は、システム開発プロジェクトの中で様々なトラブルや難題に立ち向かいながら何とか乗り越えて成功させてきました。一方で、その過ちを繰り返さないためにどうすればいいのか?という問いに対し、出来るだけリスクを減らしてプロジェクトを成功させるための方法論を考えることも求められました。その中で出した結論が、開発方法論の標準化とプロジェクトマネジメントの中央集権化です。
これによって、システム開発プロジェクトの成功率は高まりましたが、失ったものがあります。それは、”自分の頭で考えられる人材・リーダー”です。
問題や論点を発見し、その答えを出す。というビジネスマンとして当たり前に習得していなければならない技法を標準化によって失わせてしまったのです。彼らには、プロジェクトを開始する時点ですべてのものはそろっています。以前に行われた似たようなプロジェクトをテンプレートとして活用することで60点はとれるようになったのです。
結果、成功率が上がる=利益率が高まるため、事業として短期的には大成功なのですが、長期的にみると大量のテンプレート人材を発生させることになってしまったのです。結果、現代においてSIerが苦境に陥ってしまっていることと大いに関係しているのではないかと思います。
伝えられないもどかしさ
その状況から逃れるため転職を決意し、コンサルタントとして転職してくる方も大勢います。この人たちにできるだけ早くコンサルタントとして自立してほしい。どうにか思考法を身に着けてほしい。
ただ、どう伝えたらよいのか?効果的にその思考方法を学ぶこためにどうすればよいのか?の答えは見つかりませんでした。
私自身がこれまでに試行錯誤しながら学んできた手法(詳細は、前回記事参照)
本を読む
問題を解く
実践で活用
指導を受ける
を繰り返し伝えるだけで、本質的な学び方、学ばせ方を伝えることはできていませんでした。依然としてこのような形で、断片的に指導していったとしても、本当に身についてくれるのだろうか?という疑問は拭い去れませんでした。
出会ったのが、言語技術
これまでも、指導方法の言語化のために、様々な本を読み漁りました。”考える”ということを考えるというのはどういうことなのか?その答えを探しました。
等々、これ以外にも考えるを伝えるために様々な本を読んでみたのです。しかし、それぞれのトピックはやはり断片的であり、全てを包含して理解させるための方法論にはなかなかたどり着くことが出来ませんでした。
ある時、ふとしたニュースを見ているときに目に入った本がありました。記事の内容は忘れてしまったのですが、その本のタイトルと帯の文字がすごく印象に残り、さっそく購入して読んでみたのです。
まさに、私が求めていた指導法は、これだ!
ここにすべてが書かれていました。なぜ、この本にもっと早く出会えなかったのだろうか?とすごく悔しい思いをしました。この本を読了した直後、Amazonで10冊注文し、メンバーに読むようにと渡しました。それだけの衝撃を受けましたし、これをもっと多くの人に知ってほしいと思いました。
これからお話する論理思考術≒言語技術は、テクニックです。世の中ではこれを「地頭力」といったような呼称で、さも生来生まれ持った能力のように呼ばれることもありますが、そんなことはありません。”言語技術”は、その名の通り、”技術”=テクニックであり、正しく学習・習得することで、必ず身につく技術です。
多くの人にその存在を知っていただき学んでもらうことで、より楽しく仕事が出来るようになりますし、自分自身も成長し、ひいては会社や日本に貢献できるのではないかと考えています。
次回は、”言語技術とは何か?”の概要について書きたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
