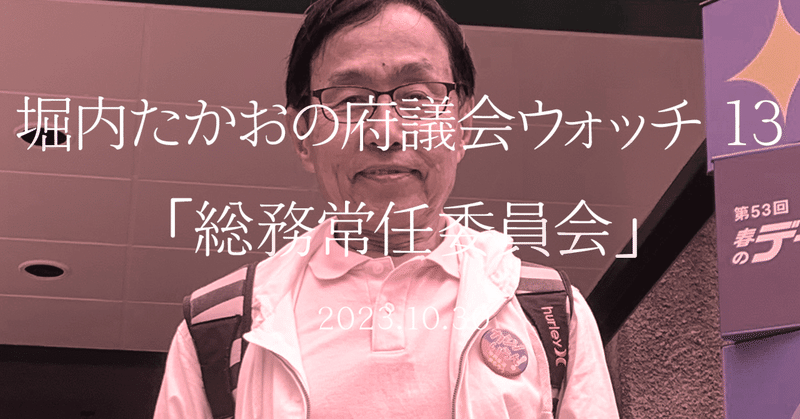
堀内たかおの府議会ウォッチ 13「総務常任委員会」
初めての府議会傍聴。12名の府議会議員で構成される常任委員会、委員会での傍聴は2人のみ。
角谷庄一議員(大阪維新)
人事交流は国への出向28名、民間企業からはスマートシティで27名受け入れ、官民や国との人材交流は大いにやるべしとの意見だった。
しかし人的交流とは、独自の政策立案や法案立案能力の無さの現れであり、何も立案し実行できない中途半端な組織だということだ。
基礎自治体のように市民と直接繋がる訳でもなく、国のような政策決定も出来ない、中間の曖昧な組織であることを物語っていた。
その特に今回の質疑で問題と感じたのは、児童相談所の体制問題でした。
大阪府の不登校や児童虐待の件数では日本でも件数が多く、相談件数は24,700件もあり、その件数を85人の児童福祉司という専門職が対応している現状であることが報告されていた。
府下で6か所の体制は複数の市をまたいで対応するのは、現実的には無理があるのではないかと思いました。
子どもにきちんと対応することは、時間や労力がかなり必要とされることで、「過重労働」となり、今年の採用8名と報告されていたが、20歳代職員の退職が多く、慢性的な人材不足で現場対応の過酷さを感じることができた。
児童相談所の対応をめぐっては、人権を無視した子どもへの対応が全国的に問題視され、収容所に隔離するような児相も多くあり、このような貧弱な体制できめ細かな、子どもの人格を尊重した対応が出来ているのか、大変不安になりました。人口4万人に1名の配置義務ですから、政令指定都市を除く人口520万人からすると、130名は基準であり35%も不足した人数で対応ということで、かなりの「過重労働」であることが分かりました。
これで満足な虐待対策ができるのか、大いに疑問が残りました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
