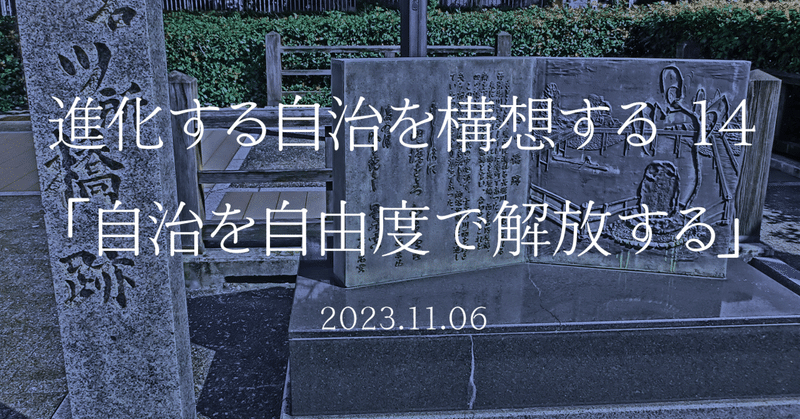
進化する自治を構想する 14「自治を自由度で解放する」
OLA革命でいう自由度と自治
伴年昌さんが提唱する、OLA革命の中で言われる自由度。それは、工業化社会、消費社会の中で「既製品化」された住宅に対する、アンチとなる提案であり、思い込みからの解放という意味がある。住まう人が、より自分の考える生活に合った環境をつくりたいと思う時、既製品として並べられた住宅の中からより理想に近いものを選ぶのか、自身の思う環境にできる限り近づけようと、既製品ではできない「製品」の領域を広げるのか。自由度は、自在につくるということでもあるけれど、意識の解放という面が大きいとも言える。
例えば、自由度の概念を行政と自治の関係、市民と行政の関係の中にも取り入れることができないか。現代の多様な社会課題や時代に即した都市環境について、今ある法整備や、これまでの自治という概念のレールの上で考えることで、硬直化して何もできない、動かない状況があるとすれば、意識の解放することで、新しい自治と行政のあり方がつくれないだろうか。それがucoがテーマとしている「進化する自治を構想する」ということに繋がっている。
ルールをつくる人がルールを破る
あるルールについて、それをつくった人は、なぜそのルールがあるのかという、理由をわかっている。その理由が無くなったり、原因が変わったのであれば、ルールを変えればいいとなる。
しかし普通は、ルールがあるという前提で物事が進むのだが、ルールそのものを疑うということはしない。また、その枠の中でがんばろうとする。
社会としてはルールありきで成り立ってはいても、そのルールがあることで息苦しかったり、つらいというようなことなら、ルールそのものを変えたり、考え直した方がいい。ルールは時代とともに社会にそぐわなくなったり、変更しなくては行けなくなっていることは、「性同一性障害特例法の「生殖不能要件」」が違憲とされたことにも象徴されていると思う。しかし、ルールを変えるためには、声を上げないと変わらないことも現実である。
ルールを変えたいと思っているのか
実際、ルールを変えようとする場合、行政的には条例を新たに作ったり、あるいは現在ある条文を変更したりすることである程度は可能となっている。社会で変えようという意識が働くか、変えてほしいという声に押されるのか、ある種の圧力がないと変わらない、変えられない。
そうしたことを考えた時、里山太郎さんの言うように「みんな変えたいと思ってるの」という話に繋がってくる。しかし、変えたいと思っていても、変わらんやろうな、と思ってあきらめていることが多いと思われる。
里山太郎さんの言う、自治という意識があるのかどうかというと、都市部ではその意識はなくなっているのだろう。けれども、そういう人ばかりでもない。ある種の多様性に対して、行政が対応できてない事態になっている。現在の自治という概念については、昭和時代の自治を行政は引きづっているし、振興町会のようにそうした形のまま残っている。これまでと違う枠組みも含めた、行政と付き合っていく自治集団、コミュニティ集団が必要ではないか。そういう視点から「進化する自治を構想する」というテーマを掲げるきっかけとなっている。
ucoのメールニュースを登録してください
ucoが平日に発信している、複数のパーソナリティがさまざまな視点から自治を語るレポートの情報や、自治に関連した取材レポート、また「進化する自治を構想する」をテーマとした講座に関連した情報を、メールニュースにしてお届けします。ぜひご登録ください。
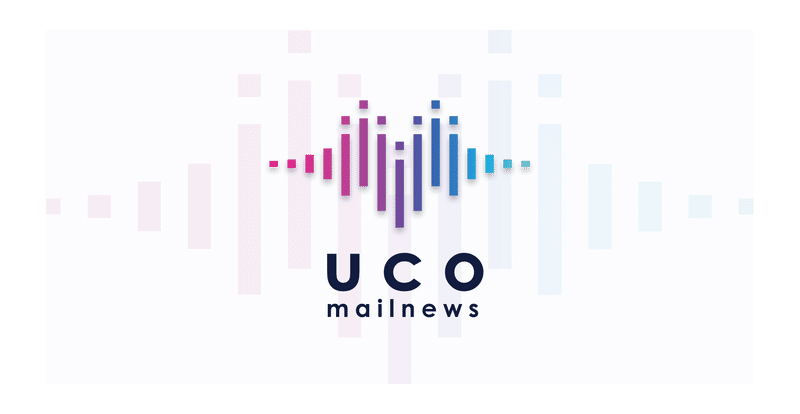
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
