
犬を連れた奥さんの犬の行方
短編小説
◇◇◇
アームに取り付けたWebカメラを天井近くまで伸ばし、真下に向けたまま狙った位置で固定する。パソコンの前に座っている男の白髪頭の頭頂部が、中央付近に収まるように画角を調整した。
これでよし。顔は映らないようにしたぞ。
私は自分のデスクに戻ってモニターを見ながら、すぐそばにいる男にそう声をかけた。真上からなら撮ってもいいよ、と本人から直接撮影の許可がもらえたので、今回初めて彼の生の姿をネットで配信することになったのだ。彼は私の古くからの知り合いで、「ゴテンマリシティ」というハンドルネームを使い、Webに小説の書評や感想などを投稿している本好きの男だった。たまたま同じ小説を読んだことがきっかけでお互いの感想を披露し合っていたらそれが面白くなり、予め読む本を決めて二人で読書感想会を開くようになった。そのうち、私がその様子を文字に書き起こしてnoteで記事にしたいと申し出たところ、どうせなら音声を編集して動画にしてみたらどうか、と彼が提案してくれたのがこの活動のそもそもの始まりだった。二人の対話形式によるブックレビューを音声動画に編集し、有名な動画投稿サイトを使って配信を始めたところ、ぽつりぽつりと物好きなフォロワーが現れ、少しずつコメントが付くようになったのだ。不定期の配信だが、今回で二十回目となり、その記念というわけでもないが、自分たちの生の姿を初公開しようと、前回の配信で公言してしまったのだ。
ただし、生の姿といっても、二人とも度胸がないので顔出しはせず、私は海亀がプリントされたTシャツの上に紺のジャケットを羽織った格好で、首から下の映像のみ。彼の方は俯瞰の位置から、襟足の一部以外はすべて白くなっている頭髪と、眼鏡の紺色のメタルフレームがちらりと映る程度。あとは水色のシャツを着た肩から腕までと、資料を手にしている彼の細い指が確認できるくらいだろうか。
本番の前にハンドドリップでコーヒーを淹れることにした。アイランドキッチンに入って、計量した豆をコーヒーミルに入れてハンドルを回す。キッチンからは、リビングにいて、ノートパソコンの前で資料に目を落として読み込んでいる彼の横顔が見えている。ハリオのV60ドリッパーに挽きたてのコーヒーをセットして、細口のケトルで円を描くようにお湯を注ぎながら、私はこれから二人で語り合うチェーホフの小説について考えていた。正直なところ、チェーホフの作品は『中二階のある家』と『犬を連れた奥さん』という二つの短編しか読んだことがない。彼の方も自分と似たようなもので、『かわいい女』と『犬を連れた奥さん』を読んだきりだという。そこで今回の配信では二人が共通して読んでいる『犬を連れた奥さん』を取り上げることにした。しかし、彼との対話の中でどこまでこの作品を深く掘り下げられるかは自信がない。実を言うと、私は前からロシア文学に苦手意識を持っていて、あのドストエフスキーの『罪と罰』を読み終えるのに三年もかかったほどなのだ。ロシア人の長い名前がなかなか頭に入らなくて、しかも、その名前がいつの間にか意外な呼び名に変化しているものだから、最初のうちは登場人物が増えたと勘違いして混乱したものだった。あと、呆れるくらいに長広舌をふるうのもロシア文学だというイメージがある。ひとりでどれだけ喋るんだ、というくらい延々と意見をまくし立て、途中で誰が喋ってるんだっけ、と前のページに戻って確認することもたびたびだった。そんな自分が、ドストエフスキーやトルストイといった十九世紀ロシアの文豪らと活動時期が重なるチェーホフの作品を取り上げて、好き勝手に語るのは実に畏れ多い気がするのだ。
私の不安を察したのか、リビングにいる彼が、そんなに深刻に考えないでさ、いつも通り気楽にやろうよ、と声をかけてきた。
私はぎこちない笑顔を作り、思わず彼に本音を漏らしてしまう。
気楽にやるつもりではいるんだけどね、自分にロシア文学はまだ早過ぎると思ったら、急に心配になってきたんだよ。今になって、ちょっと気が引けてきた。
そう言って、ドリッパーから立ちのぼるコーヒーの湯気を前にして軽く溜め息をついた。
ところが彼は、私の気持ちを鼓舞するのが余程うまいみたいで、表情を変えずにこんなことをさらりと言ってのけるのだった。
ぼくらはさ、文学者じゃないんだから、間違った読み方をしたって誰かに責められるわけじゃない。むしろ、正統を意識してお行儀良く読んでばかりいるよりは、ちょっと踏み外したり踏み違えたりした読み方を紹介した方が、思わぬ発見があって、聴いてくれている人は面白がってくれるかも知れないよ。ぼくらのような素人レビュアーが文学から価値を取り出したいのであれば、テキストのあちこちに潜んでいる窪みや隙間の部分にこそ目を向けて、真摯に作品を鑑賞するべきなんじゃないかな。
彼のその言葉を聞いて、私は思いがけず胸が熱くなってしまった。さらに彼は、この活動を最初に始めたときに言っていたことを、再び私に思い出させてくれたのだ。
ぼくらが語る本の話は、散髪のときに店主とお客の間でリラックスしながら話す世間話みたいな位置付けでいいのだと思う。言うなれば、本を俎上に載せて語るニッチな床屋談義。この気楽さを忘れないようにしようよ。
そう言うと、彼はテーブルに置いたパソコンの画面に集中しておとなしくなった。その姿を見たら、肩の力がスッと抜けた。私は抽出されたコーヒーが、円錐形のドリッパーの先端からサーバーの中へ落ちていくのを見つめて、ああ、これこそがこれまでの文学の滴りだと思った。気負いが消えて、気持ちが急に落ち着いた。
彼が座るテーブルに出来たてのコーヒーを運び、私もすぐ近くにある自分のデスクに、コーヒーを持って座った。
じゃあ、今回の床屋談義、そろそろ始めるとしますか。
そう声をかけて、リビングのテーブルにちらりと目をやると、パソコンの前で、一瞬クスッと笑う白髪頭の彼の姿が見えた。
◇◇
■私
(noteで短編小説や詩やエッセイを投稿。ときどき書評も)

■ゴテンマリシティ
(書評や読書の感想をWebに投稿。noteではネムキリスペクト39thの【コメント師】企画からこの名前で登場)
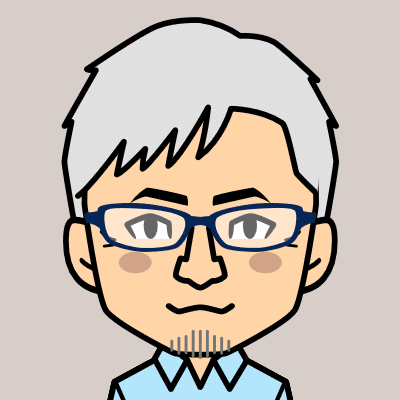
◇◇

今日はチェーホフの短編小説『犬を連れた奥さん』を読んで、お互いに思ったことを話していこうという企画です。
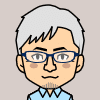
ははは、いいの? 君はこの対談の文字起こしを記事にまとめて、このあとnoteに投稿するわけだよね。不倫小説なんて扱ったら、ビュー数ががくんと減るんじゃないの?

そうなんだよね(笑) 自分も以前、詩を投稿したことがあるからわかるんだけど、不倫をテーマにした作品は、なぜかスキ数やビュー数が伸びない傾向がありまして。これはnoteだけじゃなく、たとえば芸能人でも不倫スキャンダルを起こすと、ファンは激減して、しばらくテレビからも干された状態になりますよね。つまり、それほど不倫というのは大衆から忌み嫌われる不貞行為だということが、実証されているわけです。
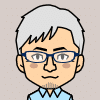
しかも、この『犬を連れた奥さん』は、お互いに配偶者がいるW不倫。

はい。その意味では、どちらかに肩入れして読むということもできません(笑)
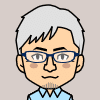
しかし、そんな不倫小説ではあるけれど、ぼくは不貞を働いたこの二人を嫌いになれなかったな。

そこがこの小説の不思議なところで、チェーホフが晩年に書いた短編の中でも『犬を連れた奥さん』は傑作と評判です。実際、この小説を好きだという人は多いですし、これを原作にした映画も何本か作られています。魅力があるんですよね。
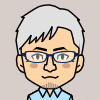
じゃあ、今回はぼくの番なので、作者の簡単な紹介と、作品の途中までのあらすじを……。なるべく短くまとめるように頑張るよ。

フフ、お願いします。
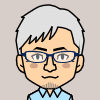
アントン・チェーホフはロシアの小説家であり劇作家です。一八六〇年に南ロシアのタガンログに生まれ、一九〇四年に四十四歳でその生涯を終えました。死因は二十四歳のときに感染した結核が悪化したためです。たびたび喀血をしていたチェーホフは医者の勧めもあって、三十八歳のときにクリミア半島にあるヤルタに別荘を購入し、そこで療養生活を送ります。『犬を連れた奥さん』はその時期に書き始められたもので、発表は三十九歳のときでした。このとき住んでいたヤルタが、今回紹介する『犬を連れた奥さん』の舞台になっています。
さて、その『犬を連れた奥さん』ですが、主人公はドミートリー・ドミートリチ・グーロフという四十手前の男性で、普段はモスクワに住み、妻と中学生の息子が二人、十二歳になる娘が一人いる銀行員です。保養地のヤルタに一人で滞在していたグーロフは、そこでベレー帽をかぶった小柄なブロンドの婦人が、いつも白いスピッツを連れて散歩しているのを見かけます。亭主や知り合いと一緒に来ていないのなら、この若いご婦人とお付き合いしたい、とグーロフは想像を逞しくさせながら考え、ある日、ひとりぼっちで退屈そうにしていた婦人と仲良くなることに成功します。婦人の名前はアンナ・セルゲーエヴナといい、県庁かどこかに勤めている夫とは二十歳のときに結婚して二年が経つらしく、そのうち夫も息抜きにヤルタへやって来るだろうと話します。知り合ってから一週間後、グーロフは人影の消えた波止場でアンナを突然抱き寄せてキスをします。そして、誘いの言葉をかけて、アンナが滞在している宿泊先へ一緒に向かいます。アンナは二人きりの部屋で「あなたに軽蔑されても仕方ない」と言ったり、「私は卑しい女なのよ」と言ったりして、グーロフを困惑させます。ヤルタにいる間は二人の親密な関係は続きます。ところがある日、アンナのところに夫が眼病になったという手紙が届き、急遽帰らなければならなくなりました。もう二度と逢うことはないとお互いに覚悟して、二人は駅で別れます。グーロフも、これを機に家族の許に帰ることにし、ヤルタを去ります。しかし、モスクワに帰ってもグーロフの頭を占めているのは、アンナのことでした。グーロフは十二月の休暇が始まると、妻に嘘をついてアンナのいるS市に向かいます。アンナが住む大きな屋敷は見つけましたが、本人に接近する機会はそう簡単には訪れません。その日、グーロフは、初演が行われる舞台に目を付け、劇場にアンナたち夫妻が観劇に来るのではないかと予想し、待つことにします。思った通り夫妻が現れ、グーロフは、最初の休憩時間で旦那が席を外した隙に、ひとりになったアンナに声をかけようと近付きます……。
というわけで、ここまで紹介してみたよ。

ちょうど第三章の終わり近くまでですね。この短編は全四章で構成されていますが、その中でも、この劇場の場面は、最も緊迫するところです。
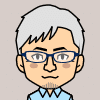
ぼくは、劇場の「立見席入口」へ通ずる暗く狭い階段の途中で、アンナがグーロフに向かって自分の気持ちを吐き出すところを読んだとき、実はキュンとしてしまった。

すごく印象的な場面ですよね。このときのアンナの言葉は、何というか、逆説的だからこそ胸を打つというか。「今すぐ帰って」と言いながら、好きだという気持ちが迸っていますよね。
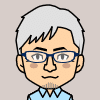
ぼくは二人の恋路を応援したくなったよ。しかし、冷静になってみると、この恋は不倫の恋なんだよなー。

ええ、世の中的には許されない恋です。チェーホフは、そんな不倫に陥る主人公たちの性格付けなど、上手く造形していますよね。
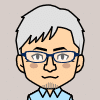
グーロフは、早くからよそに女をつくっていたり、インテリで気位の高いしっかり者の妻のことを煙たがっていたり、女性を「低級な人種さ」と悪く言ったりする。女性の読者からすると、クズ男という印象を持たれても仕方のない人物なわけだけど、一方で、このグーロフには、容貌や性格に女性を惹き付ける天性の魅力が備わっていて、自身も口とは裏腹に、女性なしでは「二日と生きていけない」ほど、女が大好きな男性でもある。

私の知り合いにもいます。男同士で飲んでいるときは浮かない顔をしていたのに、そこに女性が参加してきた途端、生き生きと話しだして、調子がよくなる奴。グーロフってそういうタイプの男なんでしょうね。女性といた方が気が楽な人は、だいたいそういう感じになります。
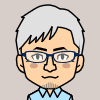
不倫小説であるからには、伴侶との仲がうまくいっていない方が都合がいい。それはアンナの人物造形にも同じことが言える。

アンナは二十歳で結婚をしていますが、すぐに理想と現実の違いを知ってしまったのでしょうね。外の世界への好奇心がどんどん広がっていくのを自分で抑えられなくなっているみたいです。何よりも、従僕のような夫の、召使い根性に対して、心底失望しているようです。
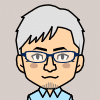
アンナの不満は、早く結婚をさせられてしまったことだと思う。これはグーロフにも共通していて、彼も「大学の二年生だったとき早くも結婚させられた」という経緯がある。チェーホフは不倫関係に陥る二人に、似た境遇の過去をさりげなく用意しているんだ。

あと、風景描写がとても綺麗。初めて二人がアンナの部屋で過ごしたあと、ヤルタの海岸通りや、オレアンダに出掛けて夜明けの景色を眺める場面は美しくて、気持ちを浄化させてくれます。
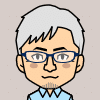
チェーホフの風景描写は巧いよね。短いんだけど印象的な情景が脳裏に焼き付く感じがある。夕暮れの海の色を「藤色」と表現している箇所があって、最高だなとぼくは思ったよ。チェーホフは劇作家なだけあって台詞も巧いし、この短編は完成度が高い。不倫小説だからと毛嫌いせず、多くの人に読んでもらいたい。

同感です。最後の第四章は、再度、逢瀬を重ねることになった二人を描いていますが、不倫小説の結びとしては、こういう終わり方になるよなあと納得です。私の好きなタイプのエンディング。これがベストだと思いました。
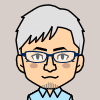
あのレイモンド・カーヴァーもチェーホフの短編に影響を受けているらしいから、ある意味、カーヴァーの小説を読んだときの読後感。

受け継がれてますね(笑)

じゃあ、今回も、最後はお互いのニッチな目線を紹介して終わりにしようか。

何だか人気コーナーみたいになっていますが、鑑賞の役に立つかは微妙ですよ。
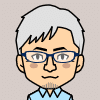
いいから、いいから(笑)

では私から。私が注目したのは、第二章で初めて二人がアンナの部屋で過ごした夜、グーロフとアンナは本当に結ばれたのか。すなわち、二人はやったのかやってないのか問題、について、私独自の変態目線で考察したいと思います。
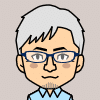
「二人はやったのかやってないのか問題」! そんな問題があるのか。初めて知った(笑)

チェーホフのこの小説には、性描写を思わせるシーンはありません。不倫小説には情事がつきものですが、裸になることもなければ、ベッドで絡み合うこともありません。そのため、読んでいて非常に上品な小説に感じます。キスはたくさんしていますが。
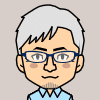
たしかに、二章のあの場面には、二人が結ばれたという明確な記述はないな。しかし、具体的なシーンが描写されてないからといって、二人はやってないとするのは早計だろう。ぼくは極めて自然にこの二人は情交を結んだと理解したぞ。

チェーホフは、読者に理解できるように、二人が結ばれたことを示す言葉をやはり本文に埋め込んでいます。小笠原豊樹氏の訳では「すなわちこの『犬を連れた奥さん』は、今起こってしまったことを何か特別な、非常に重大なこととして(後略)」、神西清氏の訳では「つまりこの『犬を連れた奥さん』は、もちあがったことに事に対して何かしら特別な、ひどく深刻な(後略)」という風に、重大な出来事がたった今アンナの身に降りかかったことを意味ありげに伝えています。これだけでも十分に二人が関係を持ったことがわかりますが、もう一つ、チェーホフは「朝チュン」を用意していました。
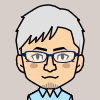
朝チュン!?

ええ。このすぐあとのシーンです。物思いに沈んでいるアンナの傍らで、グーロフはテーブルの上の西瓜を一きれ切って食べます。チェーホフはなぜこのシーンをここに書き込んだのでしょう? 汁気を多く含んだ赤い果実を男がゆっくりと咀嚼する。この行為が明らかに官能的だからではないでしょうか。具体的な描写がなくても十分、とチェーホフは考えたかも知れません。セックスが行われたことを暗示するだけでいいのです。そのためにはどうしてもここで男に西瓜を食べさせる必要があった。口の周りだけでなく、手首まで滴る果汁で汚れる西瓜を、初めて訪れた女の部屋で平気で食べられるのは、深い仲になった証拠でしょう。これがチェーホフの朝チュンです。女のそばで男が西瓜を黙々と食べ始めたら、その二人はやってます。
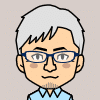
(笑)

というわけで、私のニッチな目線は以上です。次はゴテンマリシティさん、お願いします。
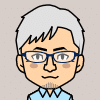
ぼくのは、簡単で、『犬を連れた奥さん』というタイトルのわりには、犬の存在感が希薄だったのが気になったよね。犬は白いスピッツで、洋装のご婦人がリードを持って連れている姿は絵になる。けれども、スピッツとグーロフの絡みは、実質二度しかなかった。最初にアンナに声をかけるとき、犬をだしにして会話のきっかけをつかんだのが一度。次に犬が登場するのは、アンナを追いかけてS市に訪れたグーロフが、アンナの住む家の表玄関から犬が出てくるのを目撃したときだけ。この二度しかない。グーロフはこのとき、犬の名前すら忘れていたからね。

この小説に、犬はあまり重要ではないように思えますね。
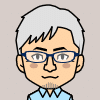
もしも、犬が重要なら、もっと登場させたと思う。たとえば、グーロフとアンナが初めて結ばれた夜、足元でキャンキャン吠えて、二人の邪魔をさせるという場面があったら面白かっただろう。しかし、犬はこのときどこにいたのか、それを示す記述はない。二人が駅で別れる重要な場面でも、犬は姿を見せない。犬はどこへ行ってしまったのか気にならないか?

言われてみると、犬の行方が気になってきた。
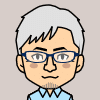
これはぼくの想像だけど、ヤルタに療養に来ていたチェーホフは、実際に、「犬を連れた奥さん」を目撃したのだと思う。それがあまりにも印象的だったから、チェーホフの恋愛小説家的想像力が発動して、この小説を着想したのではないだろうか。主人公のグーロフを、自身と同じ年齢の男に設定して、空想の中で禁じられた恋物語を編み上げていった。ぼくはそんな風に考える。主人公は、その「奥さん」に惚れ込んでいくわけだから、物語としても奥さんを主線にして、重心を移していく作りになる。犬について書く必要がなくなっただけで、つまり、犬はどこへも行っていない。

ということは、犬は……。
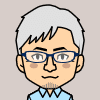
犬は最初から最後までずっと奥さんの元にいたんだよ。ただ、恋に夢中になった二人の目に入らなかっただけでね。
◇◇
文字起こしができあがって、あとは余計な言葉を刈り取り、編集するだけになった。noteには翌日のお昼までには投稿できるだろう。動画の方は、音声を加工しなければならないので、もう少し時間が必要だ。
私はパソコンのデスクから離れ、リビングのテーブルに近付いた。眼鏡をかけた彼はさっきから同じ姿勢のままだ。果たして、このような仕掛けが必要だったのかはわからない。ただ、何となく、二人は別人であった方がいいと思ったのだ。
小説を読んで、アンビバレントな感情を抱くことがある。今回のテキストのように、不倫を肯定できない自分がいる一方で、本当の愛を知った二人を応援したいという気持ちは、同じ自分の中から出てきた偽りのない感情だ。小説を読むことは、自分以外の人間を知る行為に似ている。自分以外の人間を知ることで、人はようやく自分自身を知るのだ。
キッチンに回り込んで、またコーヒーを沸かすことにした。コーヒーミルで豆を挽いて、V60のドリッパーにセットする。好きなコーヒーを淹れる工程は、ものを考えるのにいい時間だ。細口のケトルで円を描くようにお湯を注ぐ。お湯を含んで膨れあがるコーヒー豆の粉を見ながら、この中にチェーホフを始め、私がこれまでに読んできた世界文学、そして、近代の日本文学の作品を思い浮かべて溶かし込むことを想像した。単なる遊びに過ぎない。系統立てて読書をしたことはないが、気付けば、私がこれまでに読んだ文学作品は、皆、見えない細い糸で繋がっている気がするのだ。
今日の本番前にも、似たようなことを思った。抽出されたコーヒーが、円錐形のドリッパーの先端からサーバーの中へ落ちていく。その様子は、先人の作家たちが書いた作品を、次世代の作家たちが読み、その発想や型や観察眼に影響を受けながら新たな作品を生み落とすのに似ていないだろうか。連綿と繋がり続いていくそんな文学の営みが、逆さにした円錐の中でスパイラルに流動し、やがて一点に集約されていく。そうして抽出されたものが、現代の世において読まれているものなのだ。一杯のコーヒーは、そんな文学の滴りでできている。
リビングから通知音が聞こえた。
動画投稿サイトへ書き込みがあったことを報せる通知だった。
コーヒーを手にしてリビングに向かう。ゴテンマリシティ用に起ち上げたノートパソコンのモニターを確認する。書き込みは、このサイトにコメントをよく入れてくれるフォロワーのひとりからだった。前回投稿したブックレビュー動画に、たった今書き込まれたようだ。
いつも配信を楽しみにしております
サリンジャーの『バナナフィッシュ』の回、楽しく拝見しました
あなたたちの解釈と、わたしの解釈がまるっきり違っていて笑えました
テキストの上澄みだけで読んだ気になって、あれだけへんてこな解読を堂々と披露できるのはさすがですね
あなたたちの度胸をわたしも見習いたいです
ひとつだけ助言をしますけど、『バナナフィッシュ』を語るためには、「グラース・サーガ」をすべてさらう必要があると思いますヨ!
ところで、次回の配信で、二人の生の姿を初公開とありましたが、無理しなくていいのに、と思いました
一人で二役を演じているのは、この配信を聞いているファンなら誰もが知っていることです
みんなそれをわかってて楽しんでいるのに、相変わらず人を興醒めさせるのが得意ですよね
まあ、生の姿を公開と言っても、顔出しはナシ、あと、変な構図で(たとえば真上からとか)撮った映像を、ループ再生で流してお茶を濁す、とだけ予想しておきましょうかw
次回は『犬を連れた奥さん』でしたね。わたしもテキストを再読しておこーーーっと!
この方のコメントには、いつも不快にさせられることが多いのだが、今回は不思議と腹が立たなかった。こういうフォロワーがいる限り、私は、いや、私たちはもう少しこの配信を続けていこうと思うのだ。
さて、片付けようか。
ズズッと音を立ててコーヒーを飲み干し、発泡材でできた彼の頭部から、眼鏡を抜き取った。すると、不思議なもので、あんなにも多弁だった彼から表情が消えて、ただののっぺらぼうに戻ってしまった。白髪のヘアピースだけが親近感を漂わせていて、妙に可笑しい。もう現物としての出番は予定していないけれど、しばらくこのままどこかに飾っておこうと思った。
(了)
四百字詰原稿用紙約二十八枚(9,303字)
■参考書籍
『かわいい女・犬を連れた奥さん』チェーホフ 小笠原豊樹/訳 新潮文庫

『可愛い女・犬を連れた奥さん』チェーホフ 神西清/訳 岩波文庫

『ヴェーロチカ/六号室』チェーホフ 浦雅春/訳 光文社古典新訳文庫

■作者追記
この作品はフィクションであり、小説の中に登場する対話型ブックレビューの動画も存在しません。
ただ、「ゴテンマリシティ」なる人物が、そのプロフィールにある通り、ネムキリスペクトのコメント師企画に参加していたのは事実のようです。この企画は、46th【それだけはやめておけ】まで続きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
