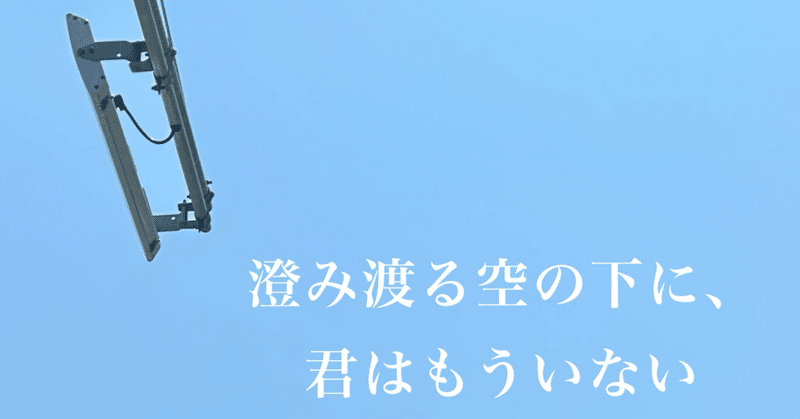
澄み渡る空の下に、君はもういない(2/2)
緊張して、痛いくらいの鼓動が耳の中で響いている。ホテルを出ると、それも気にならないくらい、雑踏の方がやかましかったけど。
迷いながらも辿り着いた、長谷川貴春が住むらしいマンションを見上げる。まだ新築なのか、白っぽい外壁が太陽光を反射させて、少し眩しい。
「……都会は夢があるにゃあ」
思わず、そう独り言ちていた。
十階以上ある高層マンションをぼけっと眺めているうちに、自分が平日のど昼間に訪問していることを思い出した。正規雇用の会社員は基本、この時間は働いている。部屋まで尋ねて行っても不在だろう。
完全に失念していた。
僅かな羞恥心に、自分がフリーターだということと、実家が自営業の居酒屋だから、と言い訳を投げつけた。
来た道を戻り、コンビニに入った。安心する軽快な入退店音に迎えられる。便箋と封筒と、ボールペンを買った。レジ店員に「切手はご利用ですか」と聞かれたのに、手を振って応えた。ここで耳に入る日本語は、当たり前にほとんどが標準語で、自分の強い訛りが恥ずかしく思えてきたからだ。
ホテルに戻り、サイドテーブルに便箋を広げる。
【長谷川貴春様】
と書き始めた手紙の冒頭で自分の素性を明かした。次いで、直弥のことについて伝えたいことがある、出来れば会って話したいが、電話でも構わない、と続けた。自分の携帯の番号を書き、今日から三日は神奈川駅近くのホテルに滞在しているから、その間に連絡がほしい、と締めた。
ぶっきらぼうな文章になっていないか。扱い慣れていない敬語の手紙は、何度目を通しても違和感しか覚えず、校正は早々に諦めた。
再びホテルを出、マンションに向かう。昼休憩なのか、ちらほらとスーツの男女の姿が目に付いた。およそ一年前まで、直弥もこの光景のただなかにいたんだ。マンションが近付くにつれ、そんな感傷に胸が苦しくなった。
マンションのエントランスに入り、遺書に書かれていた長谷川貴春の部屋番号のポストに手紙を滑り込ませた。どうか、明日にでも連絡がきますように。もぞもぞするような緊張感から早く解放されたかった。
「ほんなら、ラーメンでも食べに行くか」
来る道中に、味のある暖簾のラーメン店を見つけていた。一時だけでも気を紛らわせようと、わざと小さく声に出した。
意外にも、長谷川から電話が来たのは、陽が傾き始めた頃だった。想定よりも早い時間に、緊張感が増す。
「初めまして。長谷川貴春です」
少し高い、男性の声がスマホ越しに聞こえる。優しそうな声音だ。
「初めまして。岡野辰希です」
俺今、直弥の元カレと電話しちゅう。そう意識した途端、スマホに触れる耳が熱くなった。
「今、どちらにいらっしゃいますか?」
滑らかな標準語のイントネーションに、天上の存在の、大人の都会人を感じる。喉に言葉が貼り付いてしまって、話しにくさを覚えた。
「い、今ホテルにおり……います」
「では、近くの公園で今から会えませんか? 春には花見としても人気の高い観光スポットなので、検索してもらえると、すぐにルートが出ますよ」
そう言って、公園の名前を口にした。出しっぱなしにしていた便箋の残りに、素早くボールペンを走らせる。
「分かりました。行きます」
「ありがとうございます。それでは、後ほど」
通話を終了した。知らず知らずのうちに固まっていた肩を、ぐるぐると回してほぐす。数時間前、マンションに向かった時以上の緊張感に襲われている。
だって、俺は長谷川貴春のことを、何も知らない。神奈川に住む直弥の元カレだったということ以外、何も知らない。
決して軽くはない足取りで、ホテルを出た。東京湾から吹く潮風に煽られた。湿っぽい匂いがする。いつか直弥の家と、家族ぐるみで行った、海沿いの公園を思い出した。あの頃はまだお互い小学生で、こんまま、漠然を大人になってくち思うちょったなあ。
近付く春の気配を感じさせる公園に着くと、広いその空間の中に、ちらほらと人がいた。犬の散歩をしている人、足早に歩くスーツ姿の人、ラフな格好の学生二人組。大きな木の下のベンチでスーツ姿の男性がひとり、スマホを片手に座っていた。他に誰かを待っていそうな雰囲気の男性はいない。なら、あれが長谷川貴春なのか、と思う。
とはいえ、いきなり声をかけるのはハードルが高い。ズボンのポケットからスマホを取り出し、着信履歴から長谷川に電話をかけた。コールが鳴り始めた時、ベンチの男がスマホを耳にあてた。それで、確信に変わる。
「はい。長谷川です」
「岡野です。公園に着きました」
ベンチの男性が立ち上がり、辺りを見渡す。そして俺と目が合った。
「今そこから電話してます?」
控えめに振られた手に、会釈で返す。
「そっちに行きます」
通話を切り、ベンチに向かって歩き出す。お互いの声が届く範囲まで近付いた時、長谷川が口を開いた。
「遠いところから来てくださって、ありがとうございます」
「いえ。こちらこそ、お時間つくっていただき、ありがとうございます」
長谷川は、直弥とは違うタイプのイケメンだった。焦げ茶色の髪はくせっ毛なのか、緩く跳ねている。太い眉の下は大きく丸い目で、緩く上がった口角と相まって、可愛らしい印象を受ける。小柄でもあるが、グレーのスーツが似合うのだから不思議だ。本人の纏う、落ち着いた雰囲気のせいなのだろうか。
この人が、直弥の彼氏だった人。
直弥と二人で、並んでいるところが、見てみたかった。
「ここら辺は東京湾が近いので、肌寒くありませんか?」
勧められ、ベンチに腰を下ろした。だが長谷川は座ろうとはせず、傍らに置いていたカバンから、財布を取り出した。
「そこの自動販売機で飲み物を買ってきます。何が良いですか?」
「え! いや、自分で買いに行きますよ!」
立ち上がろうとしたが、目の前に手のひらを突きつけられた。
「長旅で疲れたでしょう。わざわざ来てくれたのですから、奢らせてください」
「……では、お言葉に甘えさしてもらいます。ホットの加糖のコーヒーをお願いします」
多分年上の人の圧には逆らえない。
「分かりました」
ふわり、と慈しむような笑みを残し、背を向けた。
薄暗くなっていく視界の中に、ぼんやりと光る自動販売機があった。
優しそうな人で良かった。またもや無意識のうちに強張っていた肩の力を抜く。小柄な長谷川の背中を見つめながら、この人は、直弥とどのような時を過ごしたのだろう、と想いを巡らせた。
楽しいときに笑えていたのか。
悲しいときに泣けていたのか。
悔しいときに怒れていたのか。
長谷川は、それら全てを受け止め、許してくれる人だったろうか。
「岡野さん」
名前を呼ばれ、ハッとした。少しぼうっとし過ぎたみたいだ。
「お疲れですか? 明日また会いましょうか?」
心配そうに長谷川が顔を覗き込んでくる。
「いえ、大丈夫です。少し考えごとを」
差し出されたコーヒー缶を、礼を言って受け取る。温かい。
隣に座った長谷川は、ブラックコーヒー缶のプルタブを開けた。
「それで、お話とは?」
明日の天気は? というような気軽さで、長谷川が問う。その気軽さに見合った話題を提供できないのが、悩ましい。
「えっと」
真っ先に、直弥の自殺を告げなければいけない。長谷川宛の遺書を手渡すのも、それからだ。
「……その」
言葉が続かない。喉にべったりと貼り付いて、剥がれ出てくれない。
遠くから電車の音が聞こえた。それ以外、完全な沈黙に包まれている。全身を突き刺されているように、痛い。
視界が狭まり、両手の中の缶しか見えない。
自分から誘い出したくせに。腑抜け。根性無し。べこのがあ。
「……直くん、あ、中本くんは、元気?」
遠くに視線を向け、何気ない口調で水を向けてくれた……つもりなのだろう。横目で俺を見ながら、喉をこくん、と鳴らし、コーヒーを飲んだ。気を遣うな、とその優し気な瞳が語っている。
その問いに、頷くことも、首を振ることも、出来ない。
「な、直弥、は」
「うん」
長谷川の視線を感じる。待ってくれている。
震える唇を開くと、涙が入り込んできた。それで、いつの間にか自分が泣いていたことに気が付いた。
涙を拭うことなく、嗚咽と共に声を絞り出す。
「……死にました。直弥は、自殺したんです」
口にした瞬間、時間が止まったかのように、木々の擦れる音や、電車の轟音が、消えた。
顔をあげれない。長谷川が息をのんだのが分かった。
「いつ?」
「十二月の十日です」
「じゃあ……もうとっくに、四十九日も、終わってるね」
淡々とした声が呟く。
「はい」
「そっかあ。直くんは、もうどこにもいないのか」
ちらりと視線を送った。
長谷川は、真っ直ぐに前を見据え、静かに涙を零していた。その表情に、悲しみも、怒りも、なにも見えない。ただじっと耐え、目を背けたくなる事実を受け入れようとしている。
その姿があまりにも美しく、涙が止まった。
目元を袖で強く擦り、長谷川に向かう。
「嘘だって、思わないんですか?」
「うん。認めたくなかったけど、二月の末の頃に、直くんがお別れを言いに来てくれたんですよ。だから、やっぱりそうだったんだって思うだけ、で」
端正な顔が歪む。必死に、溢れ出そうになる何かを堪えている。
「長谷川さんに、読んでほしいものがあるんです」
そう切り出し、カバンの中から遺書を取り出した。とどめを刺すようで、気が引ける。ゆっくりと、遺書の最後の一枚、長谷川貴春宛てのレポート用紙を差し出した。
「俺の部屋から、出てきたんです。直弥の遺書。これは、あなた宛てに」
細い指が紙を受け取る。壊れ物のようにそっと開き、茶色の瞳が文字を追っていく。
「見つけたのは最近で……来るのが、遅うなって、すみません」
「あ、あああ……」
大粒の涙を流し、抑えきれない声を漏らした。両手で遺書を胸に抱き、顔を伏せる。
震える背中に、そっと手を伸ばした。痛々しいその姿につられて、一度は落ち着いたはずの涙がまた、大粒となって地面を濡らす。
にゃあ、直弥。ここまで哭いてくれる人がおるなんて、おまんは日本一の幸せもんちや。
何度も何度も、直弥の名前を呼びながら。
二人で、慟哭した。
✿
卒業式の翌日に、直弥は高知空港にいた。チェックインカウンターに並ぶ前に、なんとか見つけられた。
「直弥! 待っとうせ!」
喜んで声をかけたが、対して直弥は、沈んだ様子だ。
「見送りに来なくていいって、言ったやいか」
大きなキャリーケースを引いた搭乗客と、空港内アナウンスで、辺りは騒がしい。直弥の声はかき消されてしまいそうだ。
「だって、何も言わんと大学、決めちょったき。俺も一個くらいゆうこと聞かんでも、バチは当たらんやろう思うて」
「……ごめんちや、なにも言(ゆ)わんで」
直弥の後ろを、指を絡めた男女が、横切って行った。きゃあきゃあ騒ぐ女の声に、気付いた直弥も視線を向ける。
「そがに、おまんにとってここは生き辛いがか」
何も答えない。ただ、遠ざかって行く男女の後ろ姿を見つめている。
「直弥」
「ん。ああ……辰希は、生き方が上手いにゃあ」
泣きそうな顔でそう言うから、黙って抱きしめたくなった。
そんなこと、ここでは出来ないけれど。
「……ほがなこと、なが。ただ卑怯なだけや」
「なにちゃんやっけ。あの子のことは、今だけでも、大事にしたげてな」
「言(ゆ)われんでも。普通の恋人になりきっちゃる、きに」
自分で言った言葉に、背筋が冷たくなった。
「にゃあ、直弥。普通の恋人って、何ちや。俺らは、普通になられへんのか?」
「うん。そうだよ」
チェックインカウンター前には、見送りに来た家族や、恋人と思われる男女の姿がある。複数人で同じ目的地に向かう人々もいる。その普通の中に、直弥は見えない。
「……のうが悪い!」
目の前にいる独りの男が不憫で、哀れで。けれどたかが学生の分際の弱っこい自分では何も見つけれなくて、歯痒い。
「その答えが、東京で見つかればええな、ち思って、期待しちょるんよ」
初めて、直弥は笑った。
空港内の普通の光景の中に溶け込んで、自分だけが弾き出されたような気分だ。
「……おまんが行くがは、埼玉やろう」
「え! でも東京に近いし、電車一本で行ける距離やし、就職先は東京を考えちょるきに」
「こっちに帰って(もんて)来(こ)おへんのか」
慌てて取り繕う中本の言葉を遮った。
地元が嫌で上京するなら、必然的に就職先は高知(こっち)じゃない。少し考えればすぐに思い至ることなのに。薄々気付いてたことでもあるのに。
改めて言葉にされると、ショックだった。
「うん」
「ほうか」
その時、直弥の搭乗する飛行機の、搭乗案内が放送された。
「あ、もう行かないと」
そう言って、電光案内板に視線を向けた。
「おん。行ってこい」
大きく右手を振りかぶって、中本の二の腕を狙う。ばちん。ガウンの上からだが、良い音が響いた。
「いったあ!」
涙目になっているのが面白くって、お腹を抱えて大声で笑った。周りの人々の視線が突き刺さる。
知るか、世間体なんか。
「辛気臭い顔するんやない! 何時間か後にはおまんも関東人や! こんなとこすっと忘れて、おまんがしたいことばあに全力を注ぐんやぞ!」
すぐそばを通りかかった家族が、微笑ましく笑っているのに気付いて、耳まで熱くなった。
「ありがとう。辰希」
訛りのない、綺麗な言葉だった。
寂しさの隙間に、満足感が埋まる。
「夜にはここに、紅葉型が出来てそうだにゃあ」
「しばらくはそれで俺のこと、思い出しとうせ」
「こがなもんが無くっても、思い出すよ、辰希のこと」
顔を見合わせて、二人で小さく、笑いを落とした。
「それじゃあ、行ってくるぜよ」
「おん。体には気い付けや」
二人の手が、宙で一度だけ、揺れる。
それっきり、直弥はキャリーケースを引いて、カウンター前に出来た列に向かった。その足取りは軽い。気持ちが溢れ出したのか、数歩歩いて、速足程度に駆け出した。直後、キャリーケースに躓いて、盛大に転んだ。
噴き出して、笑いそうになるのを堪えた。息が詰まる。
肩を震わせながら、すぐ側にいた老婦人に心配されている直弥に背を向けた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「……落ち着きましたか?」
黙って頷いた長谷川の背中を、さする手を止めた。
「すみません、恥ずかしいところを」
「いえ」
周りから、人は消えていた。木々が擦れる音と、電車の音が響くほかは、俺らの話し声しかかしない。
薄ぼんやりとした街灯の光が、俺らを包んでいる。もし、近くを通りかかった人がいたとして、不審者がいます、と通報されてなければいいけれど。
「あの、今は読めんかもですが、落ち着いた時にでも、全部読んだげてください」
小さく頷き、そこに書かれている自分の名前を、そっと撫でた。
「こんなことを言うと、少し嫌かもしれませんが。ぼくにも、直くんが遺してくれたものがあって嬉しい」
微かに染めた頬が笑う。
「想い出ごと、大事にしたってください。あいつ、結構寂しがり屋なんで」
「ふふ、うん。そうだったね」
深い息をひとつ吐き出して、長谷川がこちらに向き直った。
「岡野さん」
「はい」
何を言われるのかと、思わずこちらも身を固くした。
「君は……ぼくを、責めないんですか」
「どういて、そんなこと、いうんですか」
苦しそうに言うから、胸の奥が刺されるような悲しみを覚えた。
「だってぼく達が出会わなければ。お互いにカミングアウトして、付き合ったりしなければ。直くんは今も、生きていたでしょう?」
「それは、長谷川さんのせいじゃない。直弥が、自分で選んで、進んできた道なんです。後悔しないように、自由にって、直弥が自分に嘘をつかないで生きた結果なんです。長谷川さんひとりが背負って……長谷川さんのせいにして、直弥の……あいつの生きた人生を、否定するようなこと、せんでください……!」
悲しくて、哀しくて、今更どうしようもなくて。
時間が巻き戻せたら、と思ったことは、何度もある。
もっと早くに遺書を見つけていたら。直弥の自殺を、止められたのに。
「ごめん。ぼくが悪かった。ごめんなさい、泣かないで」
「すみません、俺の方こそ。生意気、言いました」
「ううん。岡野さんの言う通りです。ありがとうございます。気付かせてくれて」
服の袖で目元を強く擦り、笑いかける。
「遺書だけでなく、直弥のお気に入りのぬいぐるみでも、持って来ちょったら良かったですね」
そう言うと、長谷川は噴き出して笑った。
「直くんが!? ぬいぐるみ!」
げらげらと腹を抱え、膝を叩いて笑っている。室内なら笑い転げていただろう。
「そがですよ。ちなみに、ピンク色のうさぎの、ふわふわのぬいぐるみです」
「ぴんく!」
上擦った声で復唱した。
「……直弥、かわいい物が好きやったんです。でも厳しい家だったので、風邪引いた末の姉の為にUFOキャッチャーで動物のぬいぐるみを狙ったら、たまたま二個取れた、とか言い訳してましたねぇ。姉の分はすぐ取れたのに、自分の分は全然取れんくて。お年玉のほとんどを注ぎ込んだ、ち言(ゆ)うてました。中学ん頃ですけど」
「そっかあ……」
長谷川は、深く息を吐いた。
努めて明るく喋ったはずなのに、俺らの周りにはまだ、しんみりした空気が漂う。
「岡野さんは、直くんのことが好きだったんですね」
「え?」
「顔に書いてますよ。やだなあ、無自覚なの」
顔が一気に赤くなる。
「や! やめとうせ! それ、直弥の彼氏からどういう感情で受け止めれば良(え)いとですか!」
「別に恋愛感情の好きだとは言ってませんよ。友愛だな、と思って」
遊ばれた。完全に弄ばれた気分だ。
「……確かに、大事な友達でしたよ。同じゲイで、お互いにしか話せないことも、多かったですし」
とっくに温くなったコーヒーを飲んだ。
「ねえ。お酒飲めます? どっか店に入りませんか」
長谷川に誘われ、少しも迷うことなく頷いた。
「良かった。もっと直くんのことを聞きたいんです。奢りますから、色々聞かせて下さい」
「いや。半分出させてください。そん代わり、俺もこっちに住んでた頃の直弥の話を聞きたいです」
「はい。もちろん」
ふわりと笑む顔が、どことなく直弥に似ていた。だからか、まだもう少しだけ隣にいたい、と思ってしまっていた。
❀
思い出は多いのに。覚えていたいことは、もっと多いのに。
まだまだ先があると思って、大事に大事に抱えてこなかった思い出たちが、ふと気が付いたらどこかに落っこちてしまっていた。
「直くんの笑い方が好きだったなあ。声を出して、笑う感じ、が」
あれ? 直くんは、 どういう声をしていたっけ?
でもまあ、いつか神奈川に帰ってくるだろう。その時にまた、直くんの隣で笑い合えたらいい。そう思っていた。
「……僕、もう直くんがどう笑っていたのか、忘れたよ」
一ヶ月が過ぎても、半年が過ぎても、一年が経っても、直くんは帰って来なかった。
「直くん」
いつ帰ってくるの、寂しいよ。そう、既読すらつかないトーク画面に、何度も送った。
直くんは、ぼくと比べてどのくらい背が高かっただろうか。
直くんの手は、どれくらい暖かかっただろうか。
直くんの作ってくれたご飯の味は。
毎日事ある毎に思い出すのに、思い出しきれなくなってしまった。
寂しかった。気が狂いそうだった。
だけど。
「初めまして、岡野辰希です」
高知から、直くんの幼馴染みの彼が尋ねて来てくれて、直くんと同じ言葉を話すから、忘れていたことまで思い出せた。
彼はお酒に強いけど、直くんはお酒に弱かった。
彼はタバコの匂いを嫌うけど、直くんはウィンストンを吸っていた。
彼は豪快に笑うけど、直くんは、口元を手で隠して笑うことの方が多かったなあ。
向かい合って座る居酒屋の一角で。似ても似つかない彼に、直くんの面影を見出していた。
「……長谷川さん」
突然、彼が話すのをやめた。
「うん? どうしたの」
何も言わず、テーブルの端に置かれている紙ナプキンを差し出した。
なんで、と訪ねる前に、熱い雫が、頬から滑り落ちて、手を濡らす。
「ありがとう。優しいんだね」
「ほがなこと。直弥の方が、よっぽど優しかったですよ」
中ジョッキを煽る、その顔を見つめた。
「ねえ。タメ口で、方言で喋ってくれませんか?」
「はあ。別に良(え)いですけど……」
独特なイントネーションで、応えてくれる。
普段は標準語で喋ってた直くんも、酔っ払った時だけは、全く意味が通じないような方言を使っていた。
「直弥が、夏休みに帰って(もんて)来(き)た時の話なんやけど」
懐かしい言葉に、目を閉じる。
今、すぐ傍に直くんがいる。戻って来てくれた。そんな気がした。
ありがとう。彼を僕に会わせてくれて。
❀❀
「幼馴染みの弟が結婚したんだ」
酔いが回ってきた頃、直弥が呟くように言った。
「結婚?」
「そう。隣の家に住んでた、僕の三つ下の男の子。その弟だから、僕より確か七つか、八つ下だっけな。ちょっと年が離れてるけど、辰希にくっついて、よく遊びに来てたんだ。僕が大学からこっちに来たから、弟とは疎遠になってたんだけど。ほら、見て」
手渡されたスマホの画面には、純白のタキシード姿の、幼さの残る若い男性と、ブラックスーツにシルバーのネクタイ姿の男性が映っていた。
ひとしきり泣いたあとなのか、花婿の両目が赤い。対して、花婿に両肩を抱かれている男性は、鬱陶しそうな目をしながらも、照れくさそうに口元を歪めていた。
「幼馴染みの子と、弟さん?」
「そう。次のもスクロールして見て」
言われて、写真を左にスライドした。現れたのは、花婿と、同じく純白のドレスに身を包んだ花嫁のツーショット写真だった。花嫁もまだ幼さが残っている。笑っているからか、頬がぷくぷくして見えて、可愛らしい。
二人とも、幸せそうだ。まじまじと見入っていると、傍らで、静かに直弥が缶チューハイをあおった。
「綺麗な人だね」
「こぉんな美丈夫になっちょったなんて、全っ然知らんかったちや!」
満足そうに直弥が笑う。珍しく訛ったその声が、でかい。
「はーい、もうお酒は終わりだよ、直くん」
取り上げようと思い、缶チューハイに手を伸ばした。
「にゃあ、貴春さんは結婚したないがか?」
胸の奥が、もやっとした。結婚。ぼくが。女の人と?
伸ばした手は、空中で静止している。
「……ぼくは」
「僕は結婚したいぜよ」
「……そう、なんだ」
誰と。
体の奥の芯から、酔いがさめていく。けれど、続けた直弥の言葉に、笑いそうになった。
「写真見て、貴春さんと結婚したくなった」
いや、実際に笑い出してしまった。冷めた体に熱が戻る。
「そんなこと思ってくれたの! 可愛いなあ! 直くんは!」
ぼくも、だいぶ酔っていた。
サラサラのストレートヘアを鷲掴みにして、わしゃわしゃと撫でた。
「貴春さんのドレス姿はきっと綺麗やき!」
「待ってよ、ぼくがドレスなの!?」
いたずらっ気たっぷりの含み笑いで、そおや、と言う。
「だって貴春さんの方が細いし、背も低いし、かわいらしい顔なんやもん」
「面白いこと言うなあ」
ぼくたちは結婚出来ないんだよ。
その事実は今だけ忘れ、二人で有り得ない酔狂物語りに、興じた。
写真で見た花嫁よりも、直くんは幸せそうに笑っていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ぽーん、と小気味良い音が空間に響く。格安航空、高知空港行きの飛行機内だ。
丸い窓の外に目をやる。空港の建物越しに、青々と、どこまでも澄み渡る青空が見えている。
確かに、ここに“中本直弥”が存在していたんだと知れて嬉しかった。まさかお酒が弱いくせに、居酒屋店員に覚えられるくらい通っていたなんて。大学生の頃に車の免許を取って、ドライブデートしていたとか。タバコを吸うようになっていたとか。地元では見せてくれなかった姿が知れて、良い旅だったと、心の底から思う。
長谷川とは連絡先を交換した。直弥の親族に会わないようタイミングを見計らって、高知に招待したいからだ。今度は俺が、直弥と過ごした場所を案内したい。
小学生の頃によく遊んだ公園から、通いつめていた駄菓子屋、通学路を歩くのも良い。緑に囲まれた、何も無い道だけれど、確かにここにも直弥はいた。
「まもなく、離陸します」
アナウンスが響き、機体が走り出す。
さよなら、神奈川。
さよなら、直くん。
心の中でくすりと笑う。地上の重力を振り払って、体が宙に浮いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
