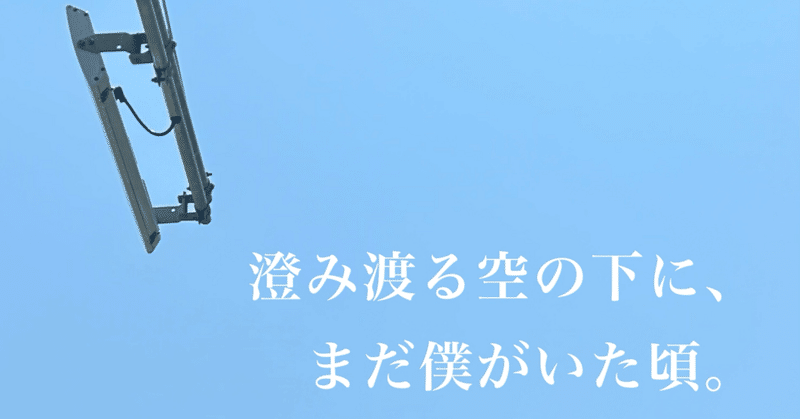
澄み渡る空の下に、まだ僕がいた頃。
・前作「澄み渡る空の下に、君はもういない」のスピンオフ的な感じのやつです。時系列的には本編より前
・中本直弥目線。長谷川貴春と二人の話
・土佐弁は似非
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
部署の新人歓迎会で訪れた居酒屋に、偶然取り引き先の方々も来ていた。部長が聞いたところによると、あちらは送別会をしていたのだそうだ。
寿退社する者がおりましてなあ、と既に酔いが回っているのか、赤ら顔の課長が嬉しそうに部長に話していた。
互いに知らないもの同士でもないし、と、他に席も空いていないことから、隣のテーブルでお邪魔することになった。
付き合いの長い先輩達は早々に取り引き先の方々とも会話に花を咲かせ始めたが、新卒二年目の僕としては、些か肩身が狭い。
最初に壁側の席についていて良かった。ひとりでビールを飲み、枝豆をつまむ。気が付けば完全に二社合同の飲み会と化し、僕の隣には話したことの無い先方の社員が座っていた。
帰りたい。
冷蔵庫に眠る、ふるさと納税の返礼品のカツオのたたきが恋しい。
「……ふう」
ビールを流し込み、小さく、息を吐く。
不意に故郷のことを思い出し、胃が重くなった。
「吉田さん、すみません。隣変わってもらえませんか?」
「ああ、良いですよ」
隣の社員が席を立つ。代わりに誰が来るのかと、ちらりと視線を向けて、思わず破顔した。
「長谷川さん」
「中本さん、久しぶり……てほどでもないですか。お元気そうでなによりです」
大きく丸い目が、優しげに微笑んでいる。今日も茶色のくせっ毛は、自由に跳ねている。
数少ない知り合いが隣に来てくれたことに、肩から力が抜けたのを感じた。
「最近どうしてます? ぼくは今、ひとりカラオケにハマってて。昨日も仕事帰りに駅前のカラオケ店で、三時間も歌っちゃったんですよ」
「三時間!? すごいですね」
楽しそうに長谷川がビールを飲み干す。
「中本さんは、何か趣味とかは?」
「いや、僕は別に。あ、でも学生の頃はよくひとりで国内旅行に行ってました」
「例えば、どんなところに行かれました?」
「楽しかったのは北海道、大阪、山口、福岡です。ああ、あと長野のスキー場も楽しかったですね」
そう答えると、長谷川は驚いた声をあげた。
「山口はぼくの母親の出身地なんです。年に一度は今も、祖父母に会いに帰ってるんです。ねえ、山口のどこに行きました?」
「主に萩市の辺りに行きました。城下町の雰囲気がすごく良かったです」
「分かります。江戸の頃の街並みが、妙に落ち着くんですよねぇ」
満足気に笑っている。その顔が可愛い、と思ってしまった。
ーーいけん。
ばっと長谷川から顔を背けた。
「……あ、えっと……ビールのおかわり、頼んできます」
空になった長谷川のジョッキを返事も聞かずに掴み、席を立つ。
不自然だったろうか。きっと、嫌な気分にさせた。わざわざ気遣って隣に来てくれたのに。
悪いこと、してもうたにゃあ。
罪悪感で胸が締め付けられる。だがそれ以上に、恐怖心が心を満たしている。
ちょうど空いた食器類を下げに来ていた従業員にジョッキ二つも託し、おかわりを頼む。テーブルを少し離れ、喧騒に背を向ける。ひとりだけ、切り離されている感覚に陥る。それももう、慣れたものだけれど。
「お待たせしました〜」
ジョッキを受け取った時、誰かが大声で長谷川の名前を呼んだ。つい、柱の影になったまま、耳が続きの会話も拾ってしまう。
「長谷川ー! ひとりならこっち来いよ!」
「は、長谷川さん、一緒に飲みたいです」
聞き覚えのある女性社員の声もする。いつもより固く、上擦った声に、さり気なさを装っているくせに、もしかしてと邪推してしまう。
もやもやする。言いようのない黒い感情に支配されていく。
このまま黙って帰っても、きっと誰も気付かないだろう。そう思った時だ。
「ごめん、ぼくゲイだから。それでも良い?」
はっきりと、長谷川の声が響いた。
正直、奇跡や、ち思うた。酷いかも知れんけんど。
「あ、そ、そうなんですか」
消沈した女性社員の声がする。それを背に、足早に席に戻った。
「長谷川さん、今の……」
「……聞かれてました、よね」
初めて困ったように、長谷川が笑った。胸がずきんと痛む。
そんな表情、しないで。
「すみません。急にこんなこと言って。もう帰ります。課長、すみません。お先に失礼します」
痛々しい響きに、返す言葉が見つからないまま、長谷川はさっさとテーブルを離れた。
行かないと。
違う、行きたい。追いかけたいんだ。
「ごめんなさい! これ、あげます!」
長谷川の隣に座っていた先方の社員二人に生ジョッキを押し付けた。
「部長、体調が優れないのでお先に失礼します!」
「おー。お大事に」
機嫌の良い部長に見送られ、走って店を出た。駅に向かう道の数メートル先に、長谷川が歩いていた。
「長谷川さん!」
コートの後ろ姿に声をかける。すぐに立ち止まって、振り返った。
「中本さん……?」
「一緒に、帰りましょう!」
明らかに困惑している。ほんのり朱に染まった頬に、もう笑みは浮かんでいない。
「どうして……あ! もしかして、ぼくのせいで何か言われました? それで気まずくなって、出てきたとか」
「そんなことないです。僕が、長谷川さんとまだ一緒にいたいと思ったからです!」
酒の勢いとは、本当に怖いものだ。つくづく思う。
顔が熱い。
「……きみは、ぼくがさっき女性社員に言ったことの意味が、分かってるの?」
毒々しさを纏って、吐き捨てるように言う。細められた目に、あの優しそうな光は宿っていない。
「分かってます。だって……僕も、そうですから」
声が震えている。心の中で、格好つかないな、と自分を嘲笑った。
「え……?」
「僕は、自由に心の望んだまま生きたくて、地元高知を捨てて、都会に来ました」
「そう、だったんですか」
長谷川の声が、視線が、沈んでいく。
心臓が痛い。耳の奥で鼓動が響いてうるさい。大量に手汗をかいているし、肩も震えている。
苦しまないでほしい。
笑っていてほしい。
「長谷川さん。聞いてください。……僕は、長谷川さんのことが……好きなんです。好きに、なってしまいました」
言葉が喉に張り付いて、上手く話せなかった。けれど伝えられたいことが言えて、幾分か心が軽くなった。
知らなかった。自分が好いた相手に、好意を素直に伝えることが、こんなにも勇気が要ることだって。同時に、こんなにも幸福なことなんだって。
長谷川は何も言わない。だけれど真っ直ぐ、柔らかい視線で、目を見てくれている。
「長谷川さんの……底抜けの明るさと、強さと、笑顔に惹かれました」
「ありがとうございます。ぼくを、好きになってくれて」
ふわり、と冷たい風が吹いた。長谷川が微笑んでいる。それだけで、嬉しく思えた。
つい緊張の糸が切れてしまい、両目から涙が溢れ出した。
「えっ! なんで泣くんですか!?」
カバンから取り出したハンカチが頬に押し当てられる。
「す、ずみません。なんか、安心しちゃって」
反対の目を袖で擦る。泣きやめ、と強く。
「だめですよ! 擦ったら! 綺麗な顔が台無しです!」
手首を掴まれた。が、その手を振り払った。
「綺麗なんかじゃないですよ!」
「はあ!? ぼくは好きですよ、中本さんの顔! ……あ」
「え?」
一瞬のうちに、長谷川は耳まで真っ赤になっていた。
「……ごめんなさい。実を言うと……一目惚れ、なんです」
「えっと……じゃあ……」
「こちらこそ、よろしくお願いします……という感じ、です」
「あ、は、はい! ありがとうございます」
ばだばだと涙が溢れ出して止まらない。
笑いたいのに、泣いているせいで筋肉が突っ張って上手く笑えない。
あーあ。人生初告白が、こじゃんと格好悪くなるなんて、思ってなかったぜよ。しかも多くの人が行き交う都会のただ中で。抱きしめることも、手を繋ぐことも出来ないけれど、今はまだ、これでえいと思った。
「日本一の幸せもんぜよ」
熱い涙を拭う。濡れた両手は、震えていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
