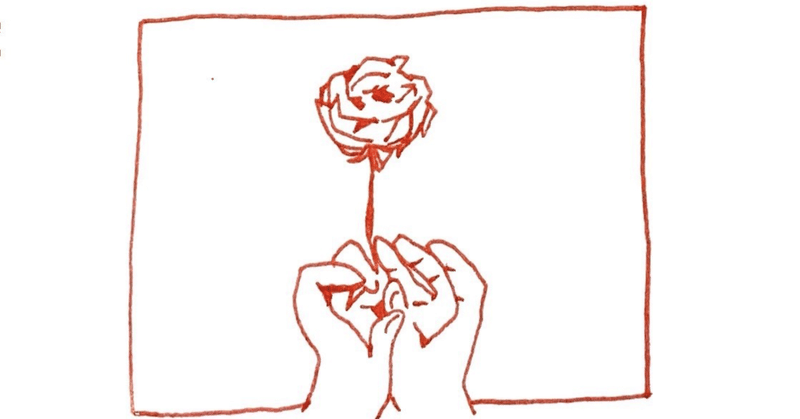
石川博品「あたらしくうつくしいことば」のノート
最近、「表現者」とか「表現すること」がテーマの本をいろいろと読んでいて、その流れで手話を題材に表現の可能性を探求した青春小説「あたらしくうつくしいことば」を読んだ。そのまえに読んだ、同じ石川博品作品の『先生とそのお布団』のテーマが「小説家であり続けること」だとしたら、「あたらしくうつくしいことば」のテーマは、「小説を書くまで」だろうか。
とてもよかったので、感じ考えたことをほんのちょっとだけ書いてみる。
まず気になったこと。「あたらしくうつくしいことば」とはいったんどんな言葉なのか。手話に限定せず、わたしたちのことばのどこにあたらしさがやどるのか。
たぶんそれは、自分のことばと、だれかのことばの「混ざりかた」にやどるのだと思う。作中では、別々の手話の話者同士が仲良くなるうちに、それらが混ざり合った新しい手話が生まれる、というかたちで描かれていたけど、たとえばいまわたしがキーボードを打ってコツコツと書いている日本語の文字だって、人によって使う言葉はぜんぜん違うから、だれかが使っているわたしがふだん使わないような言葉をわたしが使ってみるとき、わたしの言葉はあたらしいものになっているのだと思う。混ざり合うことで、変化する。使えば使うほど、馴染んでいく。そうやって、わたしだけの言葉が編み上げられていく。
こういう、小説の言葉が既存の言葉のマネから生まれるという発想は、高橋源一郎『一億三千万人のための 小説教室』(岩波新書)をはじめとして、ある創作的な立場からすれば、それほど珍しいものではないのだと思う。『先生とそのお布団』でも、なにもないところから生み出される絵と、すでにあるものから生み出される言語芸術というちがいは触れられていた。
だから、この作品の魅力を高めているのは、そういう発想自体ではなく、しっかりとそれを青春小説に根づかせている点だと思う。どういうことか。
大前提として、なにかをマネて自分のと混ぜ合わせるためには、まず「相手をよく捉える」必要がある(ろう者は意図を汲みとるために相手の表情をよく見る)。だから、「あたらしくうつくしいことば」をつくるためには、相手をよく見つめなければならない。そして、今度はそこに混ざり合う。それは相手への愛のためなのか、それともあこがれのためなのか。別々の手話と手話が混ざり合うように。
でも、たぶんそれは、なにかに真剣に向き合うときには避けられないもので、かんたんに否定していいものではないのだと思う。かつて、愛を否定した作中人物は、後からそれをこんなふうに振り返る。
人を愛するということを本当には知らなかったわたしにとって、三宅に対して抱いた感情こそがもっとも愛というものに近かったのではないか。
アイデアは浮かぶものの「ことば」を見つけられなかった彼女だけど、失った相手を思い続け、こんなふうに認められたからこそ、小説を書けたんじゃないか。
わたしはそんなに多くの石川博品作品を読んでいるわけではないけど、いろんなテーマを取り上げつつも、そこにいつも彼らしさがあるみたいな作風のヒントが、ここにあるような気がする。なにかをよく捉えるというのは、愛なのかあこがれなのか(あるいは文学なのかエンタメなのか)が混ざり合う地点までみる、ということであり、それをそのまま、ほのめかしも遠慮会釈もなく明け透けに書けるのは、ひとつの「力量」なのだと思う。
以下、蛇足。
偶然にも、明日は新作の『冬にそむく』の発売日。恋愛小説っぽい雰囲気があらすじからは出ているけど、以上のようなことを書いてきたあとだから、そこに愛(らしきもの)が描かれていたとしても、そこに同時に描かれているかもしれない愛ではないなにか、に注目したくなってしまうのだけど、どうだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
