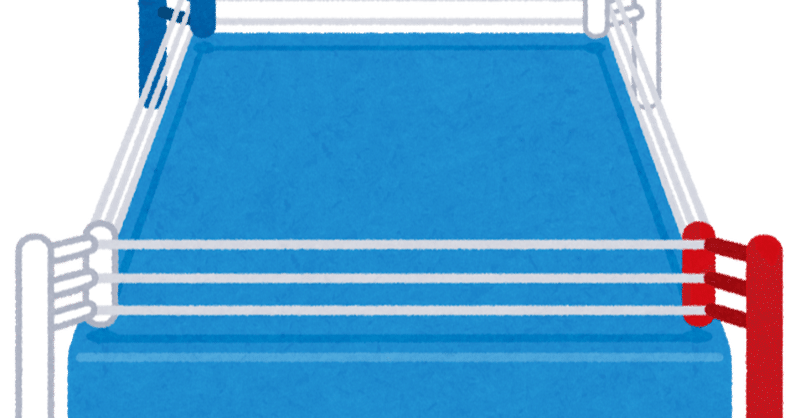
ワーク&シュート 第7回
長い夏休みが明けて久々に大学を訪れ目に入った掲示板には、ぼくらの学年向けの就職ガイダンスの通知が張られていた。この大学生活もあと一年ちょっとで終わってしまう。この先、どこで働き始めようが、同じような孤立を続けるだろうことは想像に難くない。親からも就職のことを聞かれ始めた。特に希望はないのだが。働ければどこでも、いや、できれば家の外に一歩も出ずに済めば何よりもいい。と親に言ったら今まで見たこともない表情で様々な叱責を受けた。
大学に通うまでは、将来はただプロレスを楽しめる環境であれば何でもいい、あわよくばプロレス雑誌の記者になれればいいなと思っていた。だが今はそのモチベーションが下がっている。結局ぼくが求めていたのは楽しみを共有できる仲間であり、今までどこに行ってもそれを得ることが叶わなかった。親にこっぴどく叱られた晩飯後はテレビも雑誌もゲームも何も気持ちが向かず、無音と暗闇の中で朝まで体育座りで時間を送った。
就職活動をしている一学年上の先輩の話を聞いてみるのもためになる、とガイダンスで言っていたので久しぶりにアサクラさんに会うことになった。唯一電話番号を知っている他人だ。アサクラさんは広告代理店とかゲーム会社とか、テレビ番組の制作プロダクションとかいろんな方面の会社に出ていって面接を受けているらしい。「まあ欲張りすぎってよう言われるけどな。やるからにはおもろいことやってみたいやん」ぼくらと舞台に立っていた頃はこの人がスーツを着てサラリーマンをやるだなんて想像がつかなかったが、大学内の喫茶室で話を聞いているとアサクラさんはそれなりに順応していくのではないかと思えた。会社訪問がどんなものか、履歴書の書き方とか面接の作法など、ガイダンスで聞いたときは何と味気ない世界にこれから突入しなければならないのだろうと思っていたこともアサクラさんから聞くと、まあ何とか我慢できなくもないかと思えてくる。
「ところで最近もプロレス見とんのか」
「あ、はあ……」
「何や全日がえらいことなってもうたんやなあ」
アサクラさんから久々にプロレスの話題が出てきた。ぼくはあえて自分からは口に出さずにいたのに、アサクラさんから言ってくれるなんて。まさかサークル内で孤立していたぼくに気を使ってくれたのだろうか。ぼくは就職活動のことなどすっかり忘れて今の新日本と全日本の対抗戦の話題を返しているうちに目が潤んできた。
「川田と渕と太陽ケアしかおらんのに夢の対抗戦って言われてもなあ」
「そうなんですよ。今度の東京ドームのメインが健介と川田って、猪木と馬場の面影が微塵もないのにどこに感情移入せえと言うんですかねえ」
最近のプロレス界のマッチメイクのジリ貧ぶりを嘆き、ぼやきながら、すっかり最近の鬱屈していた気分を忘れていた。それから話の流れは懐かしい80年代のプロレスの思い出話に移り、ぼくに感化されて昔のビデオを見るようになったアサクラさんとの楽しいひとときは時間を忘れるほど盛り上がった。
「そうや。俺も就職先決まったら、またプロレス見に行こか」
「え」まるで入学したての頃に似た高揚感がアサクラさんのその言葉を契機によみがえり、あの頃自分の体を満たしていたエネルギーが再び自分に充填されていくのがわかった。そう、プロレス界がどうこうなろうがそんなことが問題ではない。一緒に見に行く人がいればどんな中途半端なプロレスでも至高の時間が過ごせる。また大声を出して選手の名前をコールしたり、カウント2・9の度に地面を激しく踏みつけて会場に地鳴りを起こしたりできる。
「行きましょう、絶対」
ここ最近の行き詰まり感はアサクラさんの一言でずいぶんと解消し、アサクラさんと試合を見に行くという目標が毎日の暮らしを導く灯台となった。生活のサイクルは今までと特に変わることはなかったが、次のプロレス観戦を機にすべてが好転しそうな気すらして、幾分か強気にもなっていた。
バイトにおいても久々に一緒にシフトに入っていたユミカワさんに自分から雑談を切り出したりして、今までろくな会話ができなかったのに、いつの間にか自分も少しましなフリートークもできるようになっていたことに驚きもした。しかも彼女におすすめされた映画の話題をやんわりとスルーしながら。しかしそれだけでとどまっていてもいけない。ぼくはユミカワさんに思い切って自分の趣味の話もしてみた。
「プロレスですか? ああ、深夜にテレビでやってんの見たことありますよ。何か、激しいですよね。よう死なへんなあって思いました」
あ、この子、プロレスという単語に対して眉をひそめなかった。この反応にぼくは手応えを感じた。これは話の持って行き方次第で誘える。今日はプロレスについてどんな激しくダイナミックなものかと、それに反してお茶目でコミカルなところがあるかを解説するにとどめて、いい印象を残して次回の会話の糊しろを作った。
ユミカワさんをプロレス観戦させてファンにさせるなどということができたらどれほど天国なのだろう。次にユミカワさんと一緒になるシフトが来るまでの間にそう考えるようになったそういえば今までこんな地道なことをやってえこなかったのではないか。いきなりプロレスコントを披露して、伝わってるのか伝わってないのか不明瞭なことを続けていてもそりゃ人との繋がりが広がるわけがない。まずはこうやってコミュニケーションしていかなくてはならないのだ。そのきっかけにプロレスを使えるなんて最高ではないか。
新日本プロレスは毎年年末に大阪府立体育会館で試合を行なう。年の瀬の興行だけあって、タイトルマッチが組まれたり、すぐ後の1・4東京ドームにつながる大事な前哨戦など、見所が多いイベントになる。そして今年は新日本対全日本のタッグマッチ、永田・飯塚対川田・渕というなかなかの試合がメインに据えられた。おまけに前座でもスペル・デルフィン率いる大阪プロレスとも対抗戦が行なわれるという、多方面戦争が楽しめる。これはお得だ。ついでにサノも誘ってみるか。
就職課で会えるかと思ったが、そういえば就職課でサノに会ったことは一度もなかった。あいつは何をしているのだろうと久々に部室に行ったらサノもぼくと同様にライブにも顔を出さず最近ほとんど来ていなかったという。何の用ですかと完全に招かれざる客のように応対する後輩の態度も気にしないように務めながらしばらく学内をさまよってサノを探そうかと思ったら、別の部室の開いていた扉からサノの姿が見えて足を止めた。
「サノ、何やっとん」ぼくが外から声をかけると「おお、久しぶり」と手を挙げて返事を返してきた。部室から出てきて話してくれるかと思って待っていたが全くその素振りを見せず、部屋のなかのテーブルから「何?」と聞いてくるので「いや、久しぶりやしプロレスの話でもしよっかと思って……」と言ったら「おいでよ、中で話しようよ」との返事である。ぼくは渋々よそのサークルの部室にお邪魔することとなった。
中に入ると部屋の壁は本棚が並び、びっしりと難しそうな本で埋め尽くされていた。「第二次大戦の……」「レイテ戦……」「天皇家の……」「ーマニズム……」といったタイトルが並んでいる。内容はよくわからないが。
「就活、どうなん」プロレス観戦の話の前に、とりあえずまずはサノの近況から軽く聞いておこうと思った。
「今のぼくには興味がないことだね。何もやってないよ。そんなことよりやらなければいけないことがあるし。ドイ、君は今のこの世界情勢をどのように考えている?」
「?」
「アメリカで大きなテロがあっただろ。あれが新しい戦争の形だよ。今までの国家対国家という形はもう終わって、これからは非対象の戦争、対テロの戦いが始まるんだ。アメリカの核の傘で守ってもらっているこの国だって、もはやターゲットになっているんだよ。そんなとき、憲法九条なんていうものがあったって国民を守れると思うか?」
「はあ……」
「ぼくらは今まで生ぬるいお花畑的な発想で世界を捉えていたんだ。戦争を永久に放棄する、なんていう幻想をバカみたいに本気で信じてた。テロリストからしたらこんなおいしいエサはないよ。自分たちを守るために、ぼくらは変わらなければならない」
という、「就活どうなん」の一言の問いに対するサノの膨大な回答に圧倒され言葉を失っているぼくに、さらにサノは自分の主張を続けていた。かつて全日本プロレス四天王の凄さを語っていた頃と同じ熱意で。天下国家のことなど気にかけたことが一度もなかったぼくは少し自分の思慮の浅さが恥ずかしくなってきた。こんなサノに「またプロレス観に行こうや」と誘えるだろうか。
「今、こっちのサークルで活動しとるん?」
「うん、あっちは辞めてないけどほとんど行ってない。こっちの勉強会が面白くってね。ドイもどう? プロレスなんかよりずっと刺激的で熱くなれるよ。ここにはプロレスなんかの偽物じゃない本物の“戦い”があるしね」
あ、これはあかん。サノは完全にプロレスを見限ってしまっている。彼女はどうしたんだとか、就活せんかったら卒業後どうすんねんとか、いろいろ気になることはあったが、もうサノを止めることは誰にもできないと思った。「ところでドイは何の話しようとしてたんだったっけ」とサノが小泉政権の構造改革の素晴らしさを語り終えたあとにようやく本題を思い出したが、「いや、久しぶりに部室寄ってサノどうしとるかなって思っただけやから、ええよ。ほな、バイトの時間やから」と切り上げて政治サークルの部室を後にした。
あいつは駄目だったが、気持ちを切り替えてユミカワさんである。元々はこっちを誘おうと思っていたのだ。時期的にそろそろチケットを手配しなければいけない頃である。また同じシフトに入る日が到来したが、今日を逃したらもうチャンスはない。店のレジや納品などを行ないながらまた雑談をする機会を伺っていた。ちょうどいい具合にこの日は客が少なく店内の棚の掃除を時間つぶしがてらにやる程度の忙しさであった。掃除がひと段落したユミカワさんがカウンターでおでんの具を補充している。どこから見ても話しかけていいタイミングである。しかも今日は彼女から「今日ぐらい静かだといつも楽なんですけどねえ」と話しかけてくれたのである。今だ。
「この前話したプロレスやけど、今度さ、大阪で試合があるんやって」
へー、とユミカワさん。まだこちらの狙いは伝わっていない様子。「あれから、またテレビで見てみた?」
「ああ……はい。凄いですよね。あんなごっつい体やのにぽんぽん飛んだり投げられたりして」
ああ、この新鮮な食いつき方。これだ。こんな純粋な感想ほど美しいものがあるだろうか。彼女は続けてその日の放送で見たがたいの大きな男たちの熱きぶつかり合い、常識を越えた命の削り合いに驚いたことを語ってくれた。日本中の人々がこんな無垢な瞳でプロレスを見るようになれば、きっと楽しく優しい社会になるはずだ。そうに違いない。ぼくは彼女のこの感性を美しいまま育てあげなければならない。
「でもあれってやらせなんですよね?」
途端にぼくのユミカワさんの評価が瓦解した。何だったんだ、さっきまでの彼女の赤ずきんちゃんのような疑いのなさは。「違うよ」とすぐに否定したが、彼女がどうしてそう思ったのかが気になった。
「だって、何か真剣に戦ってるようには見えへんし」
「真剣や。一歩間違ったら死んでしまうかもしれないところで戦ってるんやで」
「でもあんまりスポーツっていう感じは、ちょっとドラマとして出来すぎてる感じもするし……」
「いや、違うねん。もちろんショーアップはしてるんやけど、あくまでも勝負は勝負やねん。それに、真剣勝負したってやっぱり強いんやで」
必死になればなるほど、当初の目的が遠くに離れていくことがわかった。ただ彼女にプロレスの面白さを知ってもらって、一緒に生観戦しようと言いたいだけだったのにむしろ険悪とすら言える雰囲気である。もうどうしたらええかわからんと思っているところに客が増えてきて、雑談は中断された。
「おー、元気?」
と、そこへ現れたのが深夜シフトの男だった。彼もユミカワさんとよく話をする大学生のバイトで、ぼくにとって脅威の存在であった。彼がカウンター越しにユミカワさんに話しかけると実にまた楽しげなノリに早変わりする。今までぼくが苦労してたどり着いた山の中腹を奴は三段跳びで乗り越えていく。
「な、今度サニーデイサービスのライブのチケット買うねんけど、行くやろ?」
といきなり彼女にお誘いの声をかける。もうぼくの苦労など泡沫のごとし。しかもユミカワさん「行く行く!」と即答するではないか。もう心が折れた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
