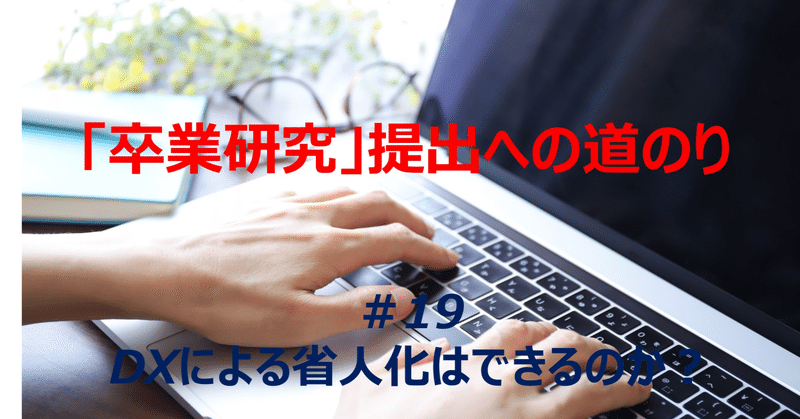
DXによる省人化はできるのか?(「卒業研究」提出への道のり#19)
【通信制高校進路決定プロセスのDX化】
前回は、この通信制高校進路決定プロセスのDX化について、実現可能性があるのか?について考察しました。
DX化のメリットとして、「省人化」(省力化)が挙げられます。
具体的にこのケースの場合にはどういうことなのか?どんなメリットがあるのか?を上げてみたいと思います。
【DX化による省人化(省力化)の具体例】
今、現在は、地域(地方)にもよると思いますが、やはり中学生の進路決定には、中学校が大きく絡みます。当然のことです。
あえてわかりやすく例えると、不適切な部分もありますが、中学校は高校側からすると、「問屋」のような存在です。
決して、生徒のみなさんは商品ではありません。決して!しかし、構造上、通信制高校にとっては、中学生は中学校の管理下にあり、中学校の先生方が紹介してくださったり、後押しをしてくれないと高校を知ってもらえなかったり、進路決定がスムーズにいかなかったりする事情があります。
そのような事情から、問屋のような存在である「中学校」に通信制高校は足しげく通う「御用聞き」のような訪問を行います。いわゆるこれが「生徒募集活動」です。
もちろん、教員(通信制高校職員)の本来の仕事は違います。
校舎を運営し、生徒に授業をし、指導をします。
そのような理由で採用された教員(職員)が、営業マンのような活動にかなりの時間が取られます。
もし、進路決定プロセスがDX化された場合には、この中学校への訪問活動が最小限で済むことになるでしょう。もちろん、大切な局面では中学校の先生とフェイストゥーフェイスも必要ですが、今はズームもありますよね。
残念ながら、中学校の先生方と通信制高校側がZoomで話すというのも、あまり一般的にはなっていません。デジタルでのやり取りはほとんどありません。DX化により、訪問活動の省人化、中学校への伝達の省力化などが考えられます。これが一番大きいでしょう。
【さらに、中学生・保護者にも恩恵が】
当然、DX化がなされれば、中学生・保護者にもオンラインチャットなどでリアルタイム、双方向のやりとりができたりします。
それも上記のような訪問活動の省力化があってこそ実現ができるものです。
中学生の保護者にとっても、今までは学校を経由してしか入らなかった情報を手軽にリアルタイムに直接集めることができようになります。
世の中や社会の流れとしても、流通機構の中間にある問屋の存在意義は薄くなっています。中学生の進路決定については、中学校が問屋のような存在としての色彩が現在も色濃く、それが効率化を妨げている側面があります。
DX化により中学生と保護者が通信制高校の情報を最適に集められるようになることで、中学校の生徒と中学生・保護者が進路決定において力関係がフェアになり、対等なパートナーシップが築けると思われます。
次回は、「DX化により、生徒募集で成果が出る(見込みがある)」について書きたいと思います。
【運営者からのお知らせ】

「基学」(きがく)及び「あたらしい地球プロジェクト」の主旨をご理解いただける方には、サポートをお願いします!サポートいただいた協賛金は、運営のために必要な機器購入費等に充当させていただきます。
