立原道造の灯した明かりのもとで
駅からの帰り道。少しずつ早まる日暮れの時間に合わせて、家々にも明かりが灯りはじめる。夕食の匂いが流れる路地を抜けるとき、少し冷えた頬で眺める窓辺の光が好きだ。灯のまわりには人がいる。そう思うだけでほっとする。
立原道造の詩にも、明るい窓辺で親しい人たちが語りあう光景が描かれたソネットがある。その詩はこう始まる。
ささやかな地異は そのかたみに
灰を降らした この村に ひとしきり
灰はかなしい追憶のやうに 音立てて
樹木の梢に 家々の屋根に 降りしきつた
その夜 月は明かつたが 私はひとと
窓に凭れて語りあつた(その窓からは山の姿が見えた)
部屋の隅々に 峡谷のやうに 光と
よくひびく笑ひ聲が溢れてゐた
(「はじめてのものに」)
ここで降るのは雪のようには溶けていかない「灰」。それは何かが終わってしまったことを告げる印として感じられる。「かなしい追憶」のような「灰」に覆われたこの静かな世界が詩の最初に描かれるからこそ、次の連の部屋に満ちる「光」と「笑ひ聲」の澄んだ明るさが際立つようにも思える。
三連目では「人の心を知ることは……人の心とは……」という翳りを含んだ問いが呟かれることからも、この明るさはつかのまの安らぎかもしれない。けれどたしかにいま、部屋の光は「私」を包んでいる。詩人の好んだ夜と昼のあいだの薄明のように。
この光景を思うたびに、道造のソネットという詩形は、彼が愛し、失ったものたちをその内側に住まわせた部屋に見えてくる。
そして「室内楽的な小詩集」と詩人自身が呼んだ詩集は一軒の家のように。
萩原朔太郎や中村真一郎は、道造の詩のなかの建築的な知性や数学的形式感覚に言及しているが、彼の詩篇を建築物として眺めてみるのも鑑賞の一つの方法かもしれない。たしかに道造のソネットは、描かれる世界の淡さや優しさに惑わされずに読むと、単に私的な感傷に流されるままに言葉を連ねたものではなく、意識的に造形されたものであることが、語彙の慎重な選択や各行の的確な配置、連想の繊細な広げ方、そして歌うような独自の呼吸などからもわかる。
このように「はじめてのものに」の部屋の光を道造の眼とともに外側から眺めているうちに、建築家の吉村順三の言葉が浮かんできた。
「日暮れどき、一軒の家の前を通ったとき、家の中に明るい灯がついて、一家の楽しそうな生活が感ぜられるとしたら、それが建築家にとっては、もっともうれしいときなのではあるまいか」(「朝日ジャーナル」1965.7.11)という言葉が。
道造もそんな思いで、ソネットという澄んだ光源を眺めたことはあっただろうか。
道造のソネットを一つの住まいとして見れば、単語一つひとつは建築物を構成する材料なのだろうが、『萱草に寄す』『暁と夕の詩』『優しき歌』といったソネット形式の詩集でもほかの詩篇と同様に、風、雲、空、霧、月、光、夜、小鳥、夢、花、窓、眠りなど、彼の好む言葉=素材がくり返し用いられている。それらは、ほとんど形容を持たない素の姿で置かれており、見方によっては、余計な飾りや汚れを落とされ、研磨された状態にあるといえるかもしれない。
しかし、ヴォキャブラリーや修飾の少なさは、川村二郎がエッセイ「貧しさの聖化」で指摘したように「貧しさ」とも受け取られかねない。なぜこんなにシンプルな裸の姿のままで言葉は用いられているのだろう。
フランス文学者の宇佐見英治のエッセイ「戦地へ携えて行った一冊―山本書店版『立原道造全集 第一巻 詩集』」を読んだとき、それを理解する手がかりを得た気がした。
宇佐見英治は、そのエッセイのなかで道造の詩の語彙の単純さに触れている。
たとえば「……時、青空、冬、望み、馬、花、雲、光、金、葡萄、無花果、草、山」などの単純な語彙について、宇佐見は「これらの言葉は辞書のいわゆる基本語ではなく祖語としての性質をもつもの、家庭のなかで用いられる極めて普通の語、ただしそのうちの自然にかかわるものを拾い集めたもの」「どんな民族、どんな地域語をも越える本原の語、Ursprache(原始語)というべきものだ」と記す。
「聖書の中の、野の花、風、山、夜、火等々の言葉がそうであるように立原が用いているこれらの言葉は始源へのまなざしを感じさす」のだと。
「祖語」「始源」に届くまで純化されたもの。道造の語彙をそう捉えたとき、先ほど触れた建築家、吉村順三が「建物の純粋さ」について語った次の言葉が思い出された。
「建物の純粋さとは何か。それは建築材料を正直につかって、構造に必要なものだけで構成するということである。柱は常に屋根をささえる役割をもち、障子の桟は、造形的なパターンであるとともに、しっかりした構造的な役割をもっている。これらの構成は、もっとも簡単で、しかも清楚な美しさを創り出していて、これが私は、純粋さということであると思う」(「同」)。
道造の語彙も、「もっとも簡単」で「清楚な美しさ」を備えた詩を創るための、それ自体も「純粋」な材料だといえないだろうか。
この「純粋さ」とは、まだ誰にも所有されていない「始源」の状態の「純粋さ」だとすれば、詩のなかの風や空や光もまた道造個人のものではなく、誰のものにもなり得る。だから私は自分のなつかしい部屋に帰ったようにソネットのなかでくつろぎ、空を見あげ、風を感じ、笑い声を聞くことができるのだろう。
そう、いつまでも消えない、言葉という名のあたたかな明かりのもとで。
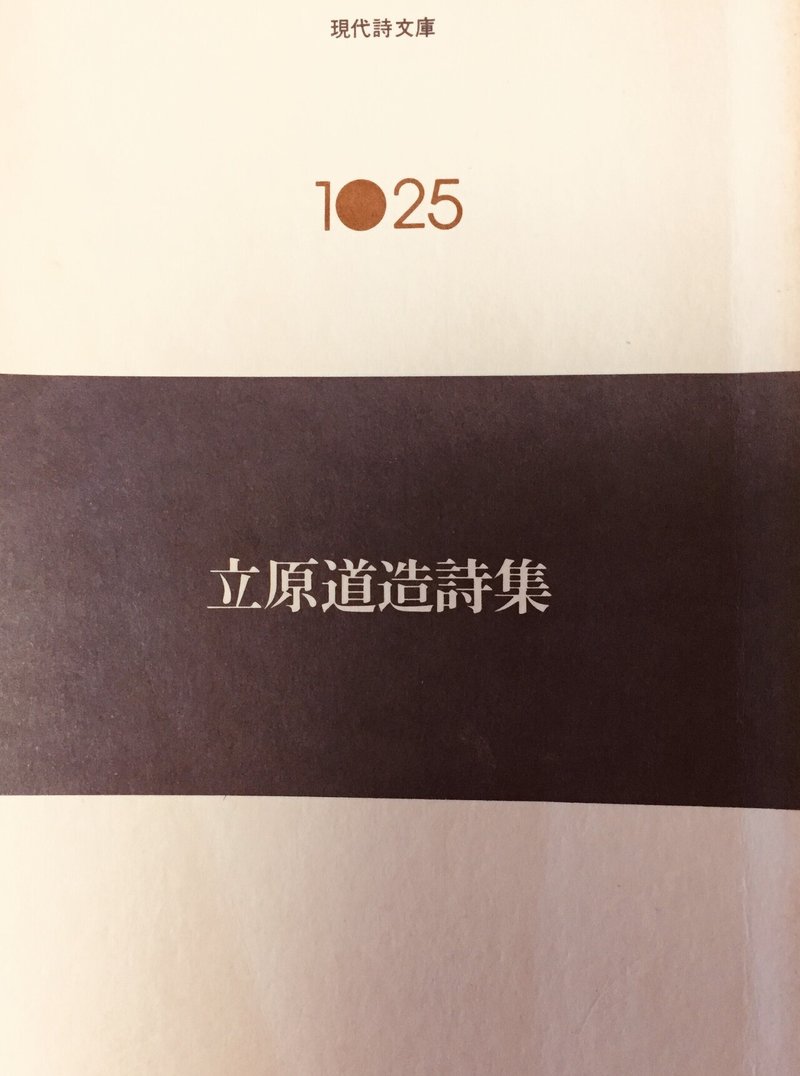
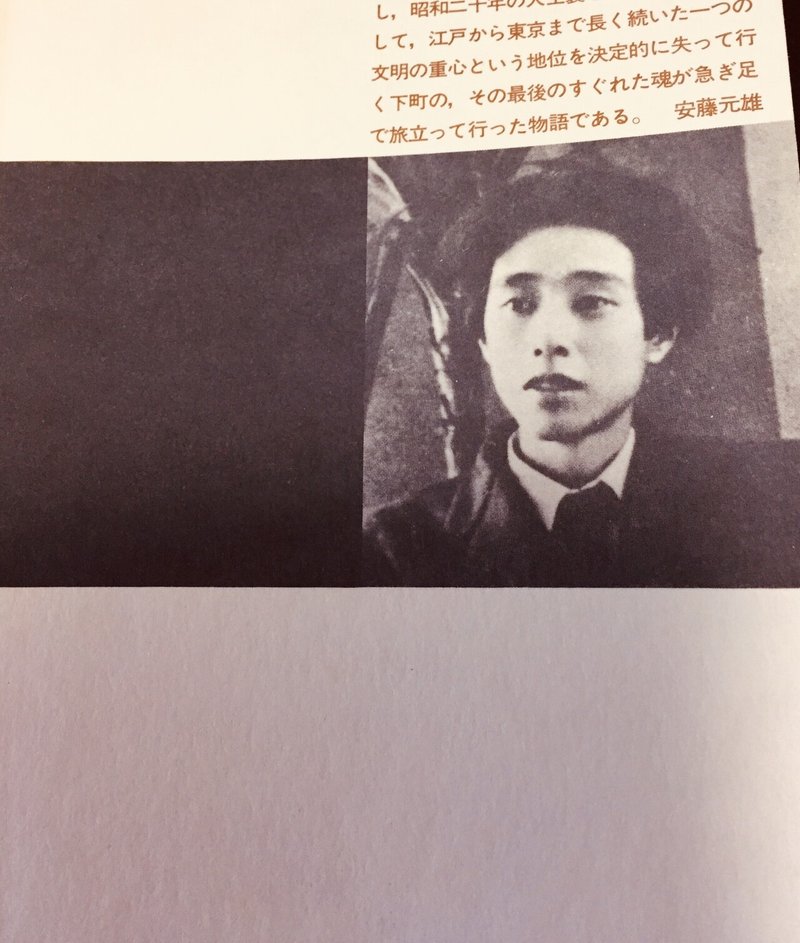
※このエッセイは「四季派学会会報」2020年冬号にゲストとして寄稿。
note掲載にあたり改行位置などの修正を行いました。
