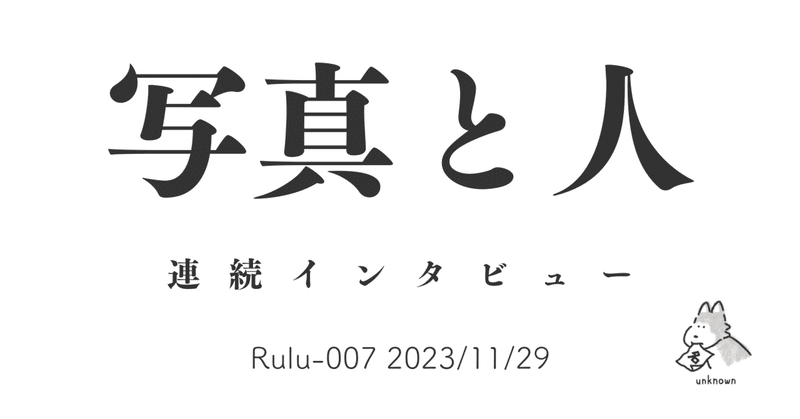
写真と人インタビュー Rulu-007 2023/11/29
これは人間の記録。
ある時あることをしようと思いたち、実際にそれを始め、それを続け、そのことについて考えたことの記録である。
この「写真と人」というインタビューシリーズでは、Ruluさんという、SNSで募集した無名の人たちを撮影するプロジェクトをしている人の言葉を記録している。
1回目は2023/8/2に行われた。
実際に行われたプロジェクトの撮影の様子を聞きつつ、撮影者と被写体の間に「ゆらぎ」があることを発見した。
ゆらぎとは、撮影者が撮影に没頭し、それまで意識していた被写体である他人という存在を忘れ、ただシャッターを押し続ける状態のことを意味した。
2回目は2023/8/16に行われた。
実際に行われた撮影の様子を聞きつつ、引き続き、撮影者と被写体の間の「ゆらぎ」について聞いた。
プロジェクトの始まったきっかけも聞いた。
3回目は2023/8/30に行われた。
実際に行われた新宿歌舞伎町の激しい撮影の様子を聞きつつ、Ruluさんの過去についてすこしふれた。
4回目は2023/9/13に行われた。
実際に行われた撮影の様子を聞いた。部屋での撮影だった。「ゆらぎ」が発生したかどうかについて聞いた。
Ruluさんが過去に精神科に通院し、自由連想法のように言葉を紡いだ経験があることを聞いた。“単語がバラバラになって、文字がバラバラになって、洗濯機みたいになって、頭の中でぐるぐる回ってるみたいな感覚”
5回目は2023/9/26に行われた。
実際に行われたプロジェクトの撮影の様子を聞いた。1回目の被写体と同じ被写体だった。撮影者と被写体について、詳しく聞いた。
6回目は2023/10/25に行われた。
実際に行われた撮影の様子を聞いた。今回も部屋での撮影だった。
Ruluさんが、「顔が写ってないんですよね」と言った。その他、窓や鏡といったモチーフの写真についても考察した。
今回は、7回目で、2023/11/29に行われた。
まえがき:qbc(無名人インタビュー主催・作家)
導入

——今回は、どんな状況なんでしょうか?
Rulu:撮影をコンスタントに続けつつ、今のプロジェクトを撮り始めてちょうど1年ぐらい経ったので、作品をどうまとめていくか、という作業を今やっています。
これまでの「写真と人」インタビューでは、撮影の様子をずっと話してきたんですけど、その撮影したものが、その後どうなっていくのかっていう話を、今日はできればと思います。
——はい!
Rulu:作品をアウトプットする、発表するっていうのは、個展とかの展覧会だったりとか、写真集が主なものになるんですけど。
私は今、写真集を作り始めていて。
写真集といっても、どういう大きさにするとか、ソフトカバーにする、ハードカバーにする、何ページぐらいにするとか、あと被写体へのインタビューを結構やっているので、写真だけじゃなくて、テキストとか文章も入れていきたいから、その割合というか、どのくらいがいいかなとか。
それから、紙の薄さとか厚さとか、紙の種類だったりとか光沢がある方がいいのか、それともマットの方がいいのかとか
そういうのをいろいろ考えたり、決めたりするために、まず、見本みたいなのを作るんですね。
いきなりもうこれですってパンって決めて業者とかに出してみても、全然思ったのと違ったなとか、失敗したなってなっちゃうと、ちょっと悲しいので。まず見本を作っていくと。
あと、印刷屋さんに頼んで本を作ってもらうことももちろんできるんですけど、そういったものは、お金さえ払えば100部でも200部でもできるんですけれども、ただ凝ったことは出来ないんですよね。もしくは凝ったことをやろうと思うと、すごくお金がかかる。
なので、しがない個人の作家では、それもちょっと現実的ではなくて。
例えば写真集の中でトレーシングペーパーを入れるとか、テキストのとこだけ紙を変えるとか、そういったことをするだけでも、やっぱり既製の業者に頼むと、簡単ではないですね。
ただ、逆に言えば、手作りで製本していけば、紙をどれだけ変えようが、どんなものでも自分が作れる範囲のものだったら作れるっていうことで。
あとは、いろんなことができるっていうことは、写真のイメージだけじゃなくて、例えば紙をめくるときの感触だったりとか、ツルツルしてたり、分厚くてふわふわしてるとかでも結構、その感じ方が違うと思うんですね、写真集とか見るときでも。
なので、自分の世界観だったり、イメージをより伝えていくためにはどういったものが一番ベストなのかっていうのを、せっかく手作りでやるんであれば、最大限活用していきたいというふうに思っていて。
で、そういったものをアートブックって言ったりするんですけれども。
作家自身が、もう本を縫ったり切ったり貼ったりとかして、手作りで1冊の凝った本を作り上げるっていうアートブックっていうものがあって。
今、そういうアートブックこそ価値があるというか。そういう流れもひとつあるんですね。
普通はデザイナーさんが入ってとか、印刷業者がやってとかなんですけど。
作家が自分で印刷したプリントを貼り込んだりとか、そうなっていくと、例えばもう10部作ったらもう嫌になっちゃうとか。
すごく頑張る人で、例えば数字に意味があれば、なんだろうな、国道35号線の本を作るから35部にするとか、発行部数もそういうふうにこだわって決める人もいますし。
全てにそうやって意味づけをしていく。
それによって、アーティストの作品発表の一つとして、展示とか額に入れて写真を飾るにとどまらない表現の形にできるのがアートブックかなと思っています。
で、それを作るための、ダミーブックを作ってます。
ずっとずっと私が喋ってるんですけど、何かありますかね?
——アートブックの手前がダミーブックということですかね?
Rulu:そうですね。アートブックの試作品というか。
例えば平成の時代だと、携帯電話のモックとか、模型みたいなものが売ってたりとかしませんでしたっけ。
——あ、売ってましたね、ハードオフとかで。
Rulu:そうそうそう。
店頭で触ったりするための模型みたいな。中身は本物ではないけど、このくらいのサイズ感ねとか、手にすっぽり収まるねとか、確かめられるっていう。
そういう位置づけのものが、ダミーブックになりますね。
ダミーブック

Rulu:あとはやっぱり、いろいろ凝ったことをするのもそうなんですけど、どの写真を選ぶとか、どう並べるとかによっても、意味が変わっちゃったりとか、するんですよね。
で、この「写真と人」インタビューでは、qbcさんに写真を選んでもらってますけど、写真ってどんな感じで選んでますか?
簡単にパパッて決まりますかね。
——ちょっと長くなりそうですが。
基本は感覚ですね。言語化、論理で選ぶとめちゃ時間がかかるので。実際にドキュメントの中に写真を配置した時に「なんかこれ違うな感」があった時に、チューニングとして論理的に考えたりはしますけど。さんざん論理的に考えてきたので、しみついてしまっていちいち考えなくてもわかってる状態です。
基本は呼吸をイメージして選んでますね。
文章を読むって行為には、基本的に緊張があると思うんですよね。意味を理解しようとする行為は、ちょっと疲れる。なので、それの息抜き、息継ぎ、という感じで写真を置いています。
もちろん、緊張感のある写真を置くとそのまま緊張が継続するわけですが、ゆるみのある写真を置くと、意味を理解しようとする緊張から解放されて、お休み時間ができると。
具体的には、カメラマンと被写体の心理的な距離について追求しようとしているようなインタビューシーンがあったとして。その内容は、ちょっと抽象的でわかりにくい。読者も自分の脳内でイメージを作っていきながらでないと読み進めにくい。
そのあとには、例えば部屋の風景写真を置いてあげる。
人間は人間に緊張を抱くことが多いですから、人間がそこにはいないほうがいい。注意力をあんまり使わなくていいから。
逆に、ここでモデルがギっとこちら正面を向いている場合は、緊張は継続しますね。にらまれっぱなしと。窒息の構成ですね。これは、悪意があってやることもできますね。
でもさらに、あえてここで人間を入れる、でも正面を向いてこちらを見るような写真ではなくて、ゆるんだ笑顔の写真だったら? 読者もゆるみますよね。
こうやってリズムを作って行く感じです。
インタビューの構成は、実際に話した流れから基本いじらないので、どんな写真を選ぶかで、緊張感の濃淡をいじっている感じです。
あとは、最初に置く写真は、読者の日常と記事をつなぐ橋渡しになるようなものを選ぶとか。例えば人間の写っていない室内の写真だったりとか。あるいは、その回の撮影全体を象徴するような強すぎない写真とか。強すぎると、読者が恐怖して読者に入りこめなくなるので。
こういう構成は、禅寺のお庭を念頭に置いてます。禅のお寺って、歩きながら考えごとにふけるために、小さい庭だけど、一つの対象が見る角度によって違ったように見えるように、興味をそそるように作られているんですよね。
鎌倉に竹林で有名な報国寺というのがあるんですが、私はそこが好きです。
Rulu:へえー。なるほど。すごい勉強になりました。
時系列だとすごく単純だし、例えば飯田橋駅で待ち合わせましたみたいになるのは、すごく説明的で楽しくないし。
あとは、いきなりどぎついのから入っていくと、引いちゃうし。
最初の1、2、3ページとかパラパラって見たときに、続きを読むかやめるかっていうのがあると思うんですよね。そこで拒絶反応を起こさない程度に、この写真の世界に入っていけるように、最初と最後の写真を選んで。
私の場合は、最初の写真を選んで、導入の部分で、最後の写真になるものを選んで。
あとは、これはこの物語の中でとても重要な写真だ、って思うものを決めていって。この写真は全体の意味を包括してるとかそうではないけど、何か説明できないけど、これは重要な気がするとか、その程度のもので。そういうなるべく具体的じゃないものを、これを起承転結の転じゃないけど、半分よりちょっと後半に入れるとか。
あとはその間を繋げていく。
繋げていくときには、自分が気に入ってる写真とか、いつも大体100枚ぐらいセレクトしてqbcさんに投げてたりとかするんですけど。そこから漏れたもの、なんか使いようがないなみたいな、ちょっと微妙なゆるい写真とか弱い写真とかが、この間にでも必要になってきたりとかするので、そこからまた選択に漏れてたものが復活してきて。
大体L判ぐらいにもう写真バーッて印刷して、机とか床にバーッて並べて、これ入れ替え、入れ替え、入れ替え。
あとは、Webだと縦にズズッとこう来るんですけど、本なので、見開きで左右があるじゃないですか。
最初から最後の流れだといいけど、左右で並べたときに何か変だなとか思って。どっちか外してしっくりくるものに入れ替えたりとか、ビジュアル的にとか、そういう感じで選びますね。
今回の写真集にはテキストが入りますけど、私は、もともと文章の人ではないので。
例えば小説に入ってくる写真とか、写真と言葉の関係ってすごい難しいから、どうしたらいいんだろうみたいなことがあるんですけど。
だからその、文章の呼吸がある、インタビューの呼吸があるとか、息継ぎをするとか。
私の作業で言えば、例えば息継ぎは間を繋ぐような写真とかにちょっと近いのかなって。
あとは、緊迫感とか、1回ここで緩めるとか、表情が変わって場面が転換するとか。
今回、違う考え方を聞けたので、すごく良かったです。ありがとうございます。
四人

——写真と映画も比較すると参考になりますよね。
Rulu:写真と映画で違うのって、例えば見る時間を自分で調整できるかだと思うんです。
映画はずっと、見る時間の流れは固定されてるじゃないですか。
でも写真集とか個展とかだと、見る時間って、すぐパッて次に行くとか、パッパッパッて見るとか、立ち止まってじっと引きこまれて見るとか、もっかい戻って見るとか。そういうきっちりしてない、ちょっと余白がある部分が好きだったりもするんですけど。
リズムもありますよね。写真集は紙をめくっていくリズムだったり、展示もやっぱり自分の体を動かしながら見ていくリズムだったり。
例えば個展で、ギュウギュウに凝縮されたおどろおどろしい展示の仕方だと、やっぱり窒息しちゃうし。イレギュラーなものとして、ずっともう窒息させたまま絶望して帰すみたいなこともありだと思うんですけど。
——どういう本に、具体的になっていくんですかね? サイズとか。
Rulu:サイズはA5判にしました。
B5とちょっと悩んでるんですけど、ひとまず構成とか並びとか流れを決めるのに、A判が、紙がたくさんあるので。まずはA判で作っています。あるいはA5かB5か、もしくはバイブルサイズというか、手帳ぐらいのサイズっていうのもちょっと考えていて。
サイズはそんな感じですね。
でも大きくして、モノクロだしビジュアルを迫力があるように見せたいみたいなのも、なくはないんですけど。
A5の小さい本って、写真集にしては小さい方だと思うんですけど。なんか小さい方がすごく、自分だけがこっそり見れるみたいな感じの、ちょっとした親密さを感じて欲しかったり。
パブリックな場所で人目を気にしながら読んだりするっていうよりは、家に自分1人でいて、立ち止まった時とかに、またちょっと開いてみてみたりとか読んでみたりとか、眠れない時にちょっと見たりとか。
この写真集を届けたい先として、まず一つそういったところを想定してるので。
あとは、私が読者としてまずイメージできるのは、やっぱり今まで撮影で会ってきた女の子たちなので。あの子たちだったら、どんなふうに見るかなとか、どんなときに見るかな、見たいかなとか考えていくと、あんまり大きいサイズじゃないかなっていうのがありました。
それから文章を入れていくので、大きいと、文章をちょっと読みにくいかな、みたいな。寝る前とか。
——なるほど。
Rulu:最終的なページ数はまだ未定なんですが、今作ってる分は40ページで、チャプター1からチャプター4までっていう感じで、4人の女性に登場してもらってます。
ページ数はこれから増えていく可能性もあるんですけど、私が教えてもらった先生が言うには、いきなり長編は書けないから、フレーズをまず作って、短いフレーズを完成させていって、そこから長くしていきなさいっていうふうに言われたので。
4人ぐらいだと全体の中でイメージしやすいので、今は40ページ4名。
これがもしかしたら、最終的には10人とかになって、80ページとか、100ページとかになるかもしれないっていう状態ですね。
文章もそういうものなんですかね。それとも最初っから、例えばエッセイとかショートショートとか、書く分量を決めて書くんですかね。
長編とかも書かれますか? qbcさんは。
——私、長編が描けないんですよ。飽きちゃって。短編で文章のアイデアを試しちゃうのはものすごく好きなんですけど。
Rulu:なるほどなるほど。noteにも短編の作品をあげていらっしゃいますもんね。
qbcは小説も書くんです!
Rulu:今回の写真集は一番最初に発表する作品になるので、自分が何をやってるのか、何をやりたいのか、っていうことがまず伝わらないといけない、伝える必要があるかなと思ってるんですね。
無名の写真家の初の個展だったり、初の写真集だったりする場合は、前知識とか全くない状態で見て、短時間で、40ページ読めばやりたいことがわかるという物をベースに作ろうと思って。
それで選んだ4人ですね。エピソードが重いとか軽いとか、すごく話題性があるとか、そういう基準では選んでなくて。
最初、1人目は「短歌と人」にも出てもらってる、安野ゆり子さん。
一番最初の撮影で行こうかなと思ったんですけど、結局、すごく新しい、わりと最近のものから始めることにしました。
何でそうしたかっていうと、撮影が彼女の自宅だったり、1日の流れがわかりやすかったりとか、それから話をしたり、彼女がどういう人であるかとか、そのパーソナリティがわかりやすかったり。あと、ちょっと外に出た写真とかもあったり、1日密着みたいな撮影になったので。
最初の導入としてこれを持ってくると、全体図がちょっと把握しやすいかなって。
2人目は、杏堂蘭さんという方を入れて。
この方は2022年の10月21日撮影なので、もう1年前ぐらいになるんですね。1枚目は最近のものにして、2枚目はプロジェクトの中ではちょっと古めの写真を持ってきました。
やっぱり写真の雰囲気とかトーンも変わってくるので、前半新しい・後半古いと明確に分けてしまうと、ちょっと違和感があるかもしれないんで、前のほうから持ってきました。
それから、彼女のエピソードが、自分の顔が認識できないっていうエピソードなんですけど、なんでしょう、一枚目の安野さんが具体的なのに対して、こちらは抽象的な、精神的な話になるかなと思って。そういうところでも選んでみました。
3人目は、なつさんっていう方を選んで。
この方は、私と共通点がすごく多い方だったんですね。
なので、撮る人と撮られる人との関係性だったり、共通点を見出していって、お互いに相互利用するというか。そういう関係性の手応えを予感させるような写真です。
最後、4人目は、まんげつさんという方で。
この方も看護師なんです。急性期の看護師さんなので、私と共通点がありつつ、ただバックグラウンドは、結婚してらっしゃるとか子供がいらっしゃるとか、自分とは違う部分で抱えてる問題とか悩みとかがあって。
この方のエピソードですごく印象的だったのが、その方が自分が言いたいことを彼氏さんに全然話せない、自分の話をしてはいけないではないけど、彼の話をちょっと聞くぐらいで、自分の話はしない。それですれ違ったりとかしていて。
大事な人に自分の話をちゃんとできてますかって、彼女に質問されたんですね。
それが自分の中で、すごく印象的に残ってたので。それってこれを読んでる皆さんもどうですかという意味で、投げかける。
鑑賞者と読者も繋いでいきたくて選んだセレクトです。
あれこれたくさんの写真を選ぶのではなく、4人しか選ばないことで、自然に表現したいテーマが生まれた感じですね。
ABC

——載せる写真は、あっさり決まりましたか?
Rulu:あっさり。
いやでも、悩みましたね。なんか悩みますね。
インタビューに2回出てきてもらったRyokoさんとかも、やっぱり彼女は入るだろうとか思って始めてみても、結局泣く泣く落として、また違う人が入ってくるとか。
そういうこともありますし。
けっこうね、やっぱ悩みましたね、4人に決まるまでは。
いやもう、修正修正修正していって、この今のプランしかないんですけど。
このプランが製本まで終わって頭がすっきりしたら、あと2プランぐらいは考えて作ってみようと思ってます。
まだ全然ぼんやりとしたアイデアなんですけど。
Bプランは、判型をちょっと変えてみるとか。
これがベストかなっていうものを、ダミーブックのデータで1冊作ったんですけど。本当にこれでいいのかなっていうのもあるので。
あとは、このプランはちょっと説明的すぎる可能性もあるので。
今度は、文章とかを省いて、自分の世界観とかイメージとか、写真重視にして。別冊のブックレットとしてエッセイを別添えにして、判型もそれぞれにするとか。写真はもうちょっと大きいサイズにして、っていうものがもう1パターン。
これはちょっと作ってみなければいけないなって思ってるやつで。
で、Cは全然まだノープランですね。
AとBのバランスを取ったようなものがCになるかもしれないし。でも今のところ、3つまでは作ってみようと思ってますね。
——制作の半ばですが、今、どんな気持ちですか?
Rulu:けっこう、なんでしょう。
距離感が、取れている。まあ、いいのかな。
彼女たちに入っていく、寄り添っていく分量のバランスが、いつも難しいですよね。
作品を発表していったり編集していったりして行くときに、自分をもう1人作って、第三者的な目でまた今度見ていかないといけないっていう部分で、難しい。
でも、その辺の距離感は今は取れてるかなっていうのを感じています。
これが例えば2、3ヶ月前とかだと、こういう作業ができない時期だったと思うんですよ。今は、割と整理されてスッキリしていて、引いて客観的に見れる。
今月撮影が少なかったっていうのもあって、すごく写真集のアイディアが浮かんでくる時期なので、もうこの時期に、ちょうど1年だし、勢いに乗って作れるときに作ろうっていう感じですね。
文章も書ける時期書けない時期ってあったりとかして。
やっぱモヤモヤして、んーってなってるときは、やっぱり写真なんですよね。
文章を書けない、並べたり整理したりすることを考えられない。1枚の写真を黒くしたり白くしたりとか、そういうことはできるけど。でもどう構成するとか、そういうちょっと理性的なことができなくて。
そういう、ただ写真を撮るしかできない時があるんですよね。
逆に、今は写真を撮影しない期間ができたので、最近すごく文章が書ける。筆が乗るというか。
文章が書けるし写真集のアイディアも浮かんでくるし。でも写真撮らないと死ぬみたいな気分では全然なくて、っていう感じですね。
今はそういう時期です。
——文章は、写真集に必要だと考えていますか?
Rulu:なんでしょうね。
例えば最終的に人に見せる段階で、文章が全部なくなったとしても、自分的には全然いいんですよね。
ただ、だから文章がいらないかっていうと、そんなことはなくて。
自分にとっては絶対要る、絶対必要だった、と思って。
写真って、何も考えなくてもシャッター押せば撮れるじゃないですか。
それで見てもらった写真が全てだって、甘えじゃないけど、作家として無責任な気がして。自分が深掘りもしてないのに、読者に投げちゃうみたいなのは。
上手に撮れてSNSで発表するとかだったらいいんですけど、そうじゃなくて、ちゃんと作品として発表していこうと思ったら、それはちょっと無責任だなって思うから、やっぱり考えないといけないと思うんですよね。
自分がやってることが何なのかとか、自分の立ち位置がどこかとか、どうしてこれを撮りたいんだろうみたいな。
わかんないけど、考えることってすごく大事で、その考えるときに絶対言葉って伴ってくるはずなので。
連想ゲームみたいに、リンゴ=赤みたいな感じで、ずっと連想だけで考えていけるわけじゃないじゃないですか。
今まで文章を全く書いたことがなくって、文章にするのは結構、不慣れだから苦しいというか大変というか、難しかったんですけど、それをやっていく作業っていうのが、自分がこういうことを考えてるんだっていうことを、理解する補助線に、すごくなっている、助けられていると思ったので。
撮影中のインタビューに関しては、最初は文字起こしをしてるだけだったんですよね。
でもせっかく彼女たちの話を聞いたから、みんな後で読み返したいかなとか、残した方がいいかなとか、それくらいのノリで始めたんですけど。
やっぱり文章に表すことで、自分の思考っていうのが、ちゃんとそこで向き合って深められるっていうことに気づいたので、けっこう頑張ってますね。
その文章を最終的に読みたい人がいるんであれば、読んでもらってもいいし。
でも写真家なのであくまで写真表現として、なんでしょうね、写真に限らなくてもよくて、自分のself-expressionとして、自分をアウトプットできればいいので。
最終的に言葉があってもなくても、言葉なしで作ったものと、言葉があって作ったものと、同じ写真を載せていても深みが変わってくるんじゃないかなというふうな希望があって、やってますね。
——少なくとも、今回のプロジェクトの写真を撮影するのに、文章は必要だったのでしょうか。
Rulu:そうですね。必要でしたね。
ワークショップ

——ダミーブックの制作は初めてなのでしょうか?
Rulu:そうですね。
いくつかのワークショップに行ってるんですが。
一番最初に行ったのは、金村修ワークショップっていうところで。ここがもう私のホームだと勝手に思ってるんですけど。
金村修さんという写真家の方と、あと女性の小松浩子さんっていう方と、写真批評家のタカザワケンジさんっていう方が3人でやってるワークショップで。
普通、例えば、写真家が1人でワークショップをやっていて、写真を持っていって、ああでもないこうでもない講評を受けるものだったり、撮り方とかやり方を教えてもらうような所かレビューをもらうっていうスタイルが大体多いんですけど。
このワークショップの場合、3人なんですね、見てくれる人が。
男性と女性と、作家ではない、見る専門の人がいて。タカザワさんは文章とか文字の方、書くほうの方なので。そのワークショップの中でインタビュー録音してるのとか、インタビューの文字起こしをしたらって最初すすめられて、書き始めたのがきっかけで。
毎週月曜日の18時過ぎから21時とか、遅ければ22時すぎぐらいまでずっとやってて、週に1回を10週連続でやるんですね。
で、週に1回撮った写真を、100枚とか200枚とか、新しい人を撮っては週に1回持ってって見せて、文章も書いてっていうのをやって、もうめちゃめちゃハードワークだったんですけど。
2022年の11月から行き始めたんで、ほとんどプロジェクトを始めたのと同時ぐらい。
でも、週に1回誰かに会って写真を撮って、選んで文章を書いてっていう、そのすごいハードワークのおかげで、ルーチンができたような感じなのと。
インタビューを文字起こしするだけだと、文字起こしができるようになったらだんだん物足りなくなってきて。撮影後記みたいな、アフターシューティングっていう形で、ちょっと主観的なものとか入っていいんですかねって質問して、面白いからいいよって言われて。
このときもやっぱり、作家であってすら自分語りしちゃいけない、みたいな意識がまだあったんですよ。
あんまり主語が大きいと、ちょっとうざくないかな、みたいな感覚。だから、「私はこう感じた」みたいなことはやっぱり書かない方がいいですかって聞いたら、いや書いた方がいいよって言っていただけて。
まあ書いたものを赤入れしてくれるとかそういうことではないですけど。
読んでくれて、なんか文章面白いねとか、文章うまいねとか適度に褒められて、だんだん書くのが楽しくなっていったみたいな感じですね。
でも写真は、やっぱり選ぶとか見るとか、ちっちゃいフレーズから作るとか、そういったことは、ワークショップとかで話を聞いて教えて助言を受けたりとかして、それでまた聞いたこと持って帰って家で自分でやってみてっていう、その繰り返しっていう感じで、ちょっとずつ、まだまだですけど、何とかやってるような感じですね。
——そのワークショップは、どういった方が対象なんでしょうか?
Rulu:どうなんでしょうね。初心者の人でもいいし、初心者じゃなくてもいいし。
1クール10週、10回が年に4回あるので。まだわかんないなとか思ったら、もっかい続けていってもいいし、いいかなと思ったらやめてもいいし。
最後に例えば、みんなでグループ展をやって、それに向けてどういうものを作って終わりにしますっていう形ではないので、ここは。ただ1週間ごとに写真を持って行き、見てもらい、写真を持って行き、見てもらい、の繰り返しだけですね、基本的には。(グループ展は無いけど、年間受講者の中で1名選ばれてその人には個展の権利が与えられます。2023年度で選出されたので来年はWSからの企画展として個展をさせて頂ける予定です。)
ただ、やっぱり、もうずっと通ってる人とか、半分以上いるので。
新規の方というよりは、ずっとみんな続けてるので。今度は写真集を作ってきたので見てくださいとか、今度個展が決まったので、こういう構成にしようと思うんですけど、どうですかとか。
それぞれ自分が見てもらいたいものを持ってきて、自分の与えられた時間の中で、これを見てほしいとかこれ教えて欲しいとか、自分で持って行ってやるみたいな感じですね。
あと他に、2つ新しく通い始めたワークショップがあって。
その2つは、半年で5回とかぐらいで、一番最後にゼミに参加してるメンバー全員で、グループ展で展示をやって終わりっていうのが2種類ですね。
なんで2種類かっていうと、ひとつは大和田良さんという写真家の方がやってるやつなんですけど、工芸大の芸術学科、写真学科の先生もされていて、自分とは全く違うスタイルで制作に取り組んでいる方のところへあえて行ってみましたが、凄く親身に見て頂いています。
もうひとつは、写真史とか写真批評をやっている打林俊さんのワークショップで。
また学ぶ視点だとか得るものが違うだろうなと。
今はこの2個に行ってます、という感じです。
なので基本的にはどれも、今日はみんなで写真を並べますとか、今日は写真を作りますとかそういうものではなくって、1人大体15〜20分とか与えられて、作品を持っていって。
金村さん以外のところは、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ペースで、その間に作ったものを持っていって、グループ展ではどうしていこうか相談したり、写真を見せて講評してもらう。基本的には講評スタイルが多いですね。
やっぱり、人の目で見てもらうのがけっこう大事かなと思うので。
自分ではこの写真は明るい写真と思っても、人から見たらめちゃめちゃ暗いねーこの写真、って見えるかもしれないし。
そういうことを常に、どんなふうに見えてるのかな、こういう立場の人だったらどう見えるのかなとか、男性だったらどう見えるかな女性だったらどうかなとか、そういうのを常に確認、立ち位置を確認しとくっていうのは大事かなと思うので、それを確認しに行ってるような感じですね。
——あらためてですけど、プロジェクトのスタートって、いつでしたっけ?
Rulu:2022年の、大体10月末です。
——東京に来られたのは?
Rulu:7月ですね。6月末に仕事を辞めて。
6月末まで熊本にいて、7月に東京に来て。2、3ヶ月ぐらいはもう疲れて、寝たきりみたいになってて。で、久しぶりに写真を撮ろうかなと思ったのが10月末。一番最初の撮影は10月25日でした。何がやりたいか考えたときに、やっぱりまた写真やりたいなって思って。
でもこの間に、ブランクが6、7年あるんですよね。なので、ちゃんと写真を習いに行った方がいいのかなと思って。
最初は、ちゃんとした普通の写真教育、絞りがどうとかシャッタースピードがどうとか、カメラの構え方がどうとかライティングがどうとか、そういう技術を習いに行こうと思ってたんですね。だけど今まで独学で来たから、もはやそれを貫きたい気持ちにもなっていて。
あるイベントで、金村修さんの、そのときは映像作品だったんですけど、作品見たときに、なんかもう頭がゴーンって殴られたような気分になって。
技術とか、そういうのじゃなくて、もっと違うことが何か強いものを感じて、家に帰って調べたら、ちょうど来月からのワークショップの募集をしていました。
スタート直前だったけど申し込んで、11月からすぐ行き始めて。
20週行ったのかな、連続で20週なので、10月、11、12、1、2、1年の前半の半分ぐらいは、自分の写真を見てもらいながら、お尻を叩かれながら、必死で毎週モデルを探して、片っ端からもう撮っていったような感じで、始まっていきましたね。
——熊本では看護師だったんですよね。
Rulu:そうです。ちょうどCOVID-19が出てきた頃から。その前は看護大学に4年間。
さらに前にはドレスショップを母親と経営してて、水商売の女の子向けの。
そこで、新しいドレスが入荷しましたよとか、商品の撮影とかができたらいいなっていうので、カメラ買って、独学で、友達に最低限の設定を教えてもらって撮ってたっていう感じですね。
なので、一番最初にカメラを触ったのは12、3年前とかになるかもしれないですね、ブランク入れて。
終わりに
このインタビューを始めたきっかけは、Ruluさんが写真の撮影時にインタビューをしていたからでした。SNSで見つけてすぐにオンラインミーティングを設定して。
話して、何か一緒にするべきだと思って、シリーズインタビューを思いついて、誘った。
勘が冴えているよね私。
編集:なずなはな(ライター)
制作:qbc(無名人インタビュー主催・作家)
#無名人インタビュー #インタビュー #コミュニケーション #写真 #カメラ #Rulu #金村修ワークショップ
いただいたサポートは無名人インタビューの活動に使用します!!
