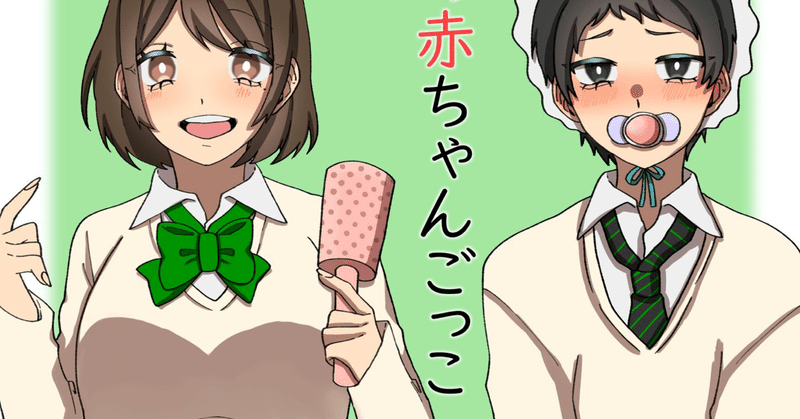
愛と正義の赤ちゃんごっこ【10―A】
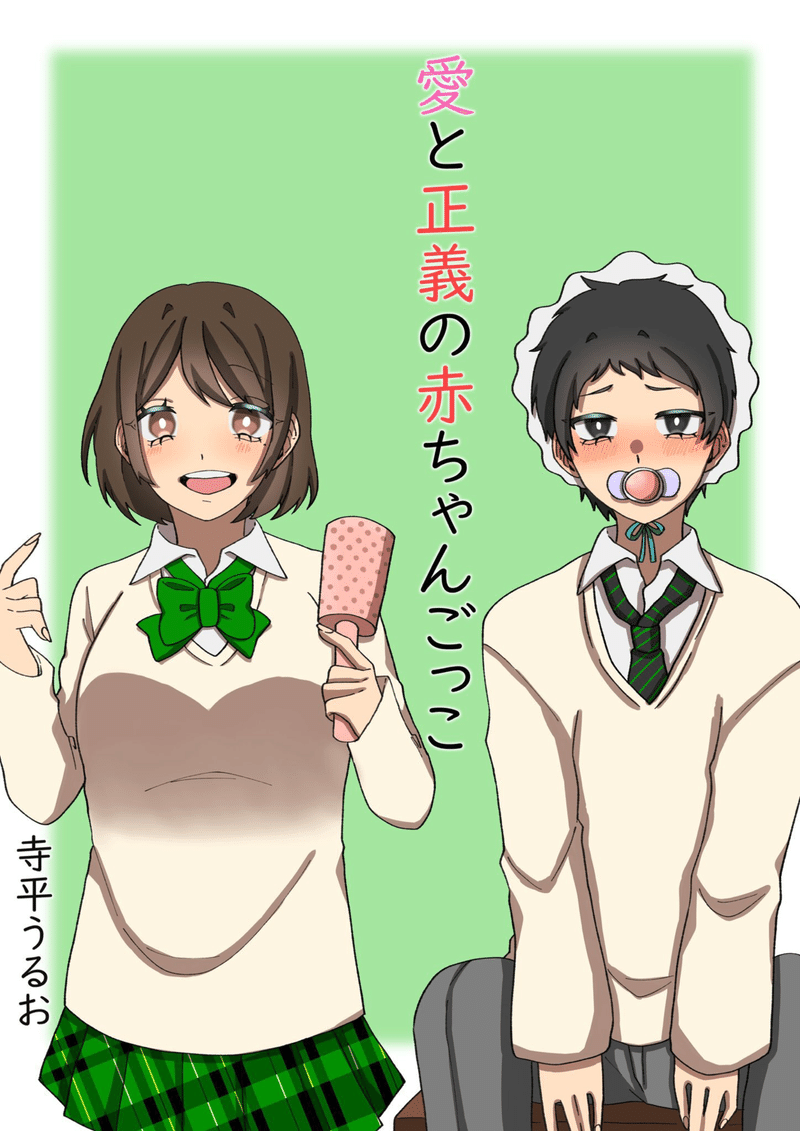
授業が終わるやいなや、突然後ろから名字を呼ばれた。茶山(ちゃやま)の声だ。五、六十人はいるだろう、この人混みの中から目ざとく僕を見つけたらしい。しぶしぶ振り向くと、あろうことか茶山の隣に愛ちゃんがいた。
「どうしよう」
こちらへ近づいてくる二人を見て、カナモトさんが僕にささやいた。
「エミナ緊張してきちゃった」
見知らぬ女の子が僕に話しかけていることに気づき、茶山がわざとらしく声を張り上げた。
「その娘は? ナンパでもしたのか?」
「マー君の友だち?」
愛ちゃんに訊ねられ、しどろもどろに答える。
「いや、あの……たまたま隣に座ってて……」
言葉を濁す僕に構わず、愛ちゃんはカナモトさんに話しかけた。
「桃下愛です。よろしくね」
「カナモトエミナです。こっちこそよろしくね」
自己紹介をし合う女子2人に、いやらしい笑みを浮かべ茶山も加わった。
「俺は茶山剛(ごう)。ここの塾には入ったばっかだけど、よろしく」
「そうなんだ! エミナも夏期講習から入ったんだよ。よかったらみんなと友だちになりたいな」
「もちろん。だけど赤地には気をつけたほうがいいよ。こいつ浮気者だから」
茶山は笑顔のまま、しかし敵意を露にそう言った。カナモトさんと僕の間にあらぬ関係をでっち上げ、事を有利に運ぶつもりだろうか。
「ねえねえ、エミナちゃん」
愛ちゃんがカナモトさんの顔を覗き込むようにして問いかけた。
「学校どこ?」
「文女って知ってる? 文芸女子大の付属高校」
「ああ、聞いたことある」
「愛ちゃんたちは?」
「明晰学院。白金にあるミッション系の学校だよ」
「ミッション系かあ。なんか響きがかっこいいねえ」
どうやら金本さんは“mission”の意味も知らないらしい。思わず鼻で笑ってしまった。
「何にやにやしてんだよ赤地。可愛い女の子に囲まれて幸せそうだな」
茶山の挑発には乗らず、僕は黙って奴をにらみつけた。授業の始まった時点では、愛ちゃんも茶山も教室にはいなかった。おそらく二人は遅刻して、授業中にこっそりと後方のドアから入室したのだろう。電車で通塾している茶山が、塾まで徒歩で十分強しかかからない愛ちゃんと一緒に遅刻するなんておかしい。入り口でばったり出くわしたということも考えられなくはないが、おそらくこいつのことだ、うまいこと愛ちゃんをたぶらかして、どこかで何かしていたのだろう。
「エミナ喉渇いちゃった。どっかに自販機ないかな?」
そう言うとカナモトさんは机上の勉強道具一式を、ブランドものらしいハンドバッグに手早く詰め込んだ。
「談話室にあるよ自販機。行こ」
どうやら愛ちゃんも、すっかり彼女と意気投合したらしい。
女の子たちを見送り、急いで机上を片づける。教室に残った茶山は、じっとこちらをにらんでいる。
「どうかした?」
「いや、別に」
当惑する僕を残し、茶山は教室を去っていった。
廊下に面したはめ殺しの窓から、談話室の中をのぞいてみる。十人ほどの塾生が四つのテーブルにまばらに着き、本を読んだり缶ジュースを飲んだり、思い思いに過ごしている。愛ちゃんとカナモトさん、それに茶山の三人は、自動販売機の前で楽しそうに立ち話をしている。ドアを開けると、カナモトさんの甲高い声が響いた。
「そうなんだあ。剛(ごう)君かっこいいし、服のセンスもいいもんね」
「そうかな?」
ほんの数分前まで僕をにらみつけていたとは思えない、だらしない顔でへらへらしている茶山。愛ちゃんのことを狙っていながら、カナモトさんに好意を示され、まんざらでもなさそうだ。下品な笑みを浮かべる茶山に、カナモトさんがなおも話しかける。
「ポジションはギター?」
「いや、ヴォーカル」
「ヴォーカルかあ。剛君にぴったりだね。その髪いいなあ。エミナも明るい色にしたいんだけどさあ、うち校則厳しいから黒髪しか駄目なの。最悪なんだよ。靴下まで指定されてんの。夏は白の短いやつで、冬は灰色のハイソ。超ださいの」
ピンピンとはねた茶色の髪をいじりながら、茶山が言った。
「今度うちの文化祭でライヴやるんだ。よかったらエミナちゃんも来てよ」
「えええ、行く行く! 剛君が出れば絶対盛り上がるね。ていうか、今からみんなでカラオケ行かない?」
カラオケと聞いて、暗鬱な気分でうつむいた。僕はカラオケが大嫌いだ。誰があんなものを考え出したか知らないが、考案者に憎悪すら感じている。なぜならあの場では、しばしば歌の苦手な人間までもが歌うことを強いられるからだ。
そもそもカラオケというものは、歌の得意な連中がご自慢の美声を他人に聞かせ、自己満足を得るための施設である。とはいえ、カラオケの料金は皆が一律に払わされる以上、さすがに自分だけがマイクを独占するわけにもいかない。参加者全員が楽しんだという既成事実をでっち上げる必要があるのだ。だから連中は音痴な者にも強制的にマイクを握らせ、何か歌え、歌わないと場がしらける、とあからさまに圧力をかけてくる。しぶしぶ曲を登録し、無理して声を裏返らせながら歌っても、奴らは次の曲を選んだり、スマートフォンをいじったりするばかりで、誰も他人の歌声など聞いていやしない。いやまあ、それはむしろこちらにとって好都合なのだが、それにしても曲が終わるまでの、あの薄ら寒い空虚な時間には耐え難いものがある。カラオケは日本の悪弊だ。ハラキリやカミカゼと同様に、極東の蛮習と言っていい。なぜこんなものが世界に受け入れられるのか、僕には到底理解できない。
「だったらうちに来なよ。カラオケ屋なんだ」
茶山の提案を聞き、カナモトさんはいよいよ狂喜した。
「マジで? 剛君ちカラオケ屋さんなの?」
「そそ、チェーン店のフランチャイズやっててさ」
「えええ、フランチャイズ? すごーい」
すぐ近くのテーブルで参考書を読んでいた、神経質そうな男子生徒が片眉を吊り上げて振り返ったが、そんなことにはお構いなく、カナモトさんは無邪気に驚嘆している。
「あたしも知らなかった。自分ちでカラオケできるなんて最高だね」
どうやら愛ちゃんまで乗り気らしい。
「愛ちゃんってさ、歌うまいの?」
カナモトさんの問いかけに、愛ちゃんは少しはにかんで答えた。
「歌うのは好きだけど、別にうまくはないよ。声低いし」
「えええ、愛ちゃんくらいがちょうどいいじゃん。エミナなんて声高すぎてみんなからうるさいって言われちゃうもん」
「あたしはエミナちゃんくらい高いのがよかったなあ」
「そうだ、愛ちゃんエミナと一緒にバンド組もうよ」
急に話が飛躍し、愛ちゃんの返事も待たずに金本さんはしゃべり続ける。
「やっぱエミナも茶髪にしよっかなあ。バンドやるのに真っ黒のままなんてかっこ悪いもん。でもうち校則厳しいから絶対無理だし。なんであんなに厳しいんだろ。意味わかんない。ああ、剛君みたいに明るくできなくてもいいからさ、せめて愛ちゃんくらいの色に染めたいなあ」
カナモトさんに髪をいじられ、困惑した表情で愛ちゃんが言った。
「これね、地毛なんだ」
カナモトさんがぎょろぎょろした目をさらに大きくする。
「えー、いいなあ! もしかして愛ちゃん、外人の血が入ってるの?」
「お父さんがね、イギリスと日本のハーフ」
「えええ!」
カナモトさんと茶山の声が重なり、部屋の中に響き渡る。かくいう僕も声を上げそうになった。なるほど。日本人とは思えないほど色素の薄い目や髪、凝脂とも言うべき美しい肌の起源はそこにあったわけか。
「すごい!」
日本人なら誰しも多少は持っているだろう西洋への憧憬を、清々しいほど剥き出しにしてカナモトさんがまくしたてる。
「何だっけそういうの。お父さんがイギリス人のハーフってことは……クォーターだクォーター! へええ、クォーターかあ。愛ちゃん顔濃いもんね。いいなあ。エミナもクォーターに生まれたかったなあ」
隣の参考書少年は、今にも舌打ちしそうなほどいらだった様子で眉をひそめている。僕は見かねて小声でカナモトさんに言った。
「ここではあんまり大声出さないほうがいいよ。そろそろ出ない?」
「あれ、赤地君いたんだ」
存在すら忘れられていた僕は、気まずさを誤魔化すため笑い声のような空気を漏らした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
