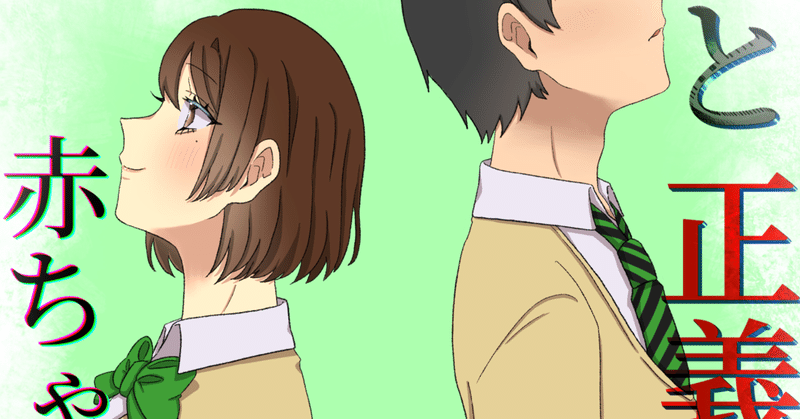
愛と正義の赤ちゃんごっこ【12―A】
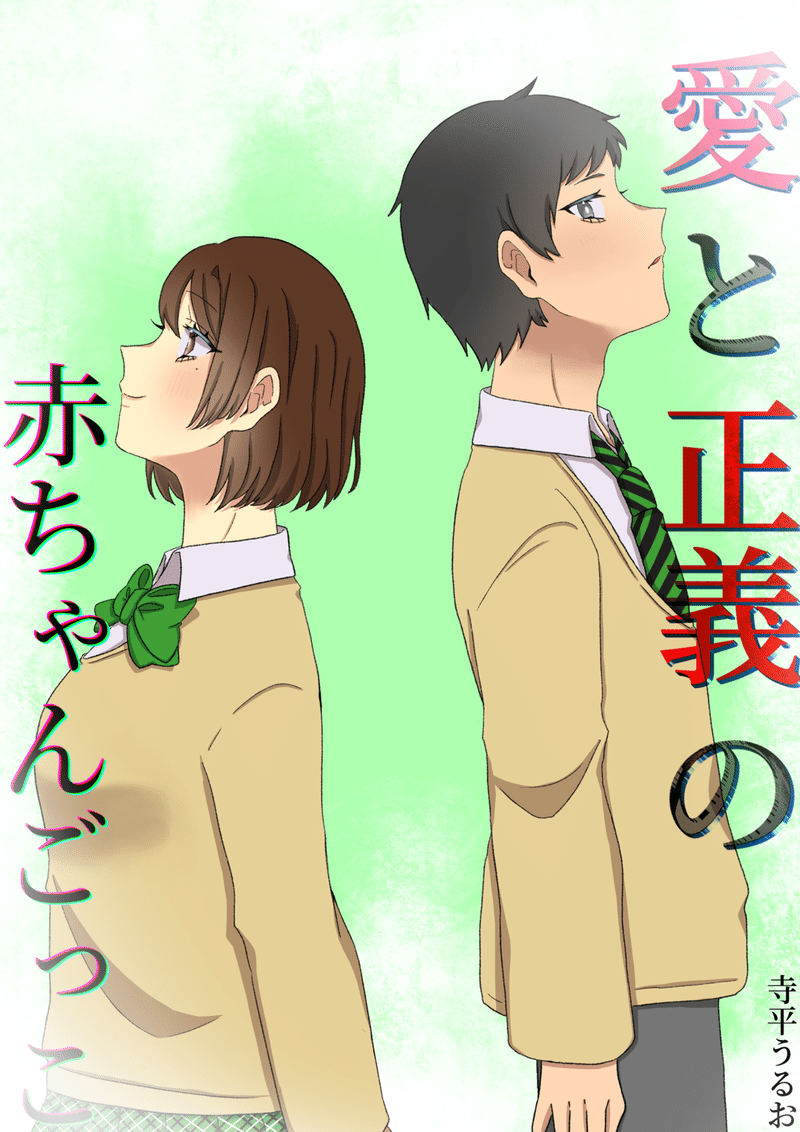
井の頭公園を独り当て所(ど)なく歩く。時刻は午後七時をまわっているだろうか。木々の新緑を照らしていた太陽が電灯に代わり、ようやく薄暗くなってきた園内は、デート中らしい若い男女やジョギングをしている初老の男性、犬の散歩をする中年女性など、老若男女を問わず多くの遊歩者で賑わっている。
歩き疲れた僕はベンチに腰掛け、自動販売機で買った炭酸飲料を一口飲むと、スマートフォンを取り出した。ディスプレイの中では、ウェイトレス姿の愛ちゃんが相変わらずにこにこしている。彼女はもう、心も体も完全にギュンターのものになってしまったのだろうか。答えを知る術はないし、仮に知ったところでどうしようもない。それでもやはり、僕は愛ちゃんのことがあきらめきれない。
大きな池の彼方に光が見える。池の真ん中を通ってボート乗り場に連絡する長い橋の照明だ。底なし沼のように見える真っ暗な水面が、通路の脇に等間隔で設置されたいくつものライトに照らされ、輝いている。
「もしもし? 今、大丈夫?」
電話の向こうで速水さんは、一度咳払いをしてから話し始めた。
「大丈夫だよ。どうしたの?」
「あのさあ、あさっての話なんだけど、速水さん、何か予定ある?」
「土曜だよね? 特にないけど」
「花火観に行かない?」
「え?」
少し間が空いた後、彼女は答えた。
「うん、いいよ」
「実はね……」
大きく溜め息をついてから、僕は続けた。
「愛ちゃんがギュンターと花火大会に行くらしくてさ、茶山(ちゃやま)と茶山の彼女も一緒にって話なんだよ。こんな機会でもないとギュンターがどんな奴か見届けることはできないだろうし、俺も行こうかなって思って。まあ見届けたところでどうってわけでもないんだけど」
「ああ、そういうことね」
「いつも面倒くさいことに付き合わせちゃってごめん。ご飯奢るから、お願いします」
「いいよそんなの」
「じゃあよろしく。時間は決まり次第伝えるね」
「あ、赤地君?」
電話を切ろうとした時、呼び止められた。
「浴衣着てく?」
「浴衣? いや、俺は持ってないな」
「そっか」
「速水さんは持ってるの?」
「うん、まあ」
「せっかくだから着てくれば? 似合うと思うよ。速水さん、すらっとしてるし」
「そうかな。じゃあ、着て行こうかな」
電話を切ってからもしばらくの間、僕はぼんやり橋の光を眺めていた。
☆ ☆ ☆
男は僕と視線が合うと、微笑を浮かべて目礼した。突き出た眉の下の深い窪みに、二重瞼の切れ長な垂れ目が見える。その瞳には、一見すると人当たりの良さそうな印象もあるが、視界に入った者を無言で恫喝するような迫力がある。真夏の夕陽と人混みの熱気に晒され、頬がやや上気している。襟元から伸びた長い首は、黒い髪や紺の浴衣とは対照的に、不気味なほど生白い。
「はじめまして。愛ちゃんの友だちのエミナです」
「灰塚です」
金本さんの挨拶を受け、灰塚ギュンターは低い、落ち着いた声でそう答えた。周囲のお祭り騒ぎとは一線を画す泰然(たいぜん)とした面持(おももち)で、しかし目口には微笑を絶やさない。見れば見るほどぞっとする男だ。
「どう?」
愛ちゃんに向き直った金本さんは、可愛いでしょとでも言わんばかりに両手を広げて見せた。真っ赤な帯が巻かれたピンクの浴衣は、毒々しいとは言わないまでもあまり品がない。ついでに言えば、金本さんの隣に阿呆面で立っている茶山の甚平姿も、上衣とズボンの丈が短いせいか、大人が子どもの寝巻きを着ているようで滑稽だ。
「うん、めっちゃ似合ってるよ」
そう答えると愛ちゃんは、襟首の左側に黄色のリボンで束ねた髪をいじりながら、同意を求めるようにちらりとギュンターを見上げた。身長差、およそ三十センチ。この男の隣にいると、彼女はいっそう小柄に見える。紺の浴衣に包まれ、リボンと同じ黄色の帯で締めつけられた小さな体は、胸の部分がひどく窮屈そうだ。
「ありがとう。愛ちゃんも超可愛いよ。やっぱエミナのセンスに間違いはなかった」
金本さんはそう言って、満足気に微笑んでいる。
「愛の浴衣、エミナちゃんが選んでくれたんだ?」
「そうなんですよー」
金本さんと談笑するギュンターを、愛ちゃんはじっと見つめている。時折相槌を打ち、うなずき、一緒に笑う。こんなに幸せそうな表情は、僕には見せてくれたことがない。
「感想は?」
耳元で茶山がささやいた。ついさっきまで金本さんの隣にいたはずなのに、いつの間にやってきたのだろう。
「感想?」
「初めてライバルを見た感想」
僕が黙り込むと、茶山は薄ら笑いを浮かべた。
「完敗だな」
それだけ言うと、金本さんの元へ戻っていった。
たしかに茶山の言うとおりだ。僕は愛ちゃんに想いを伝え、彼女は僕を拒絶した。愛ちゃんはもう、容姿端麗で日独混血、名門三田塾大学の学生である彼氏、灰塚ギュンターのことしか見えていないのだろう。
ギュンターは三年生だそうだから、この冬からは就職活動が始まるはずだ。そうなれば、これまでのように遊んではいられなくなるだろう。そんな折、首尾良く無垢で可愛い女子高生と懇意になることができた。禁欲生活に入るまでの数ヶ月間、この女子高生を思う存分慰み物にしてやろう、そういう魂胆があるのは明白ではないか。この男に彼女を末永く幸せにする気などあるわけがない。仮に本気で付き合っていくつもりだったとしても、就職活動で多忙になれば結局はうまくいかなくなるに決まっている。
だが、いくら僕が理屈を説いたところで、今の愛ちゃんには通じないだろう。彼女が身も心もこの男のものになるのを、僕はただ黙って見過ごすしかない。
「暑いねえ」
速水さんがそう言って、団扇でパタパタと顔をあおっている。黒の浴衣に身を包んだ彼女は、午後六時を過ぎてなお照りつける陽射しを浴び、うっすらと汗ばんでいる。大振りに団扇をあおいでくれるおかげで、隣に立っている僕にまで涼風が届く。汗まみれの額に風が当たり、頭に上った血が冷めていくようだ。
「ほんと、暑いね」
そう答えると、僕は速水さんの横顔へ目をやった。ギュンターを間近に見て、彼女はどんな感想を抱いているだろう。無意味だとわかってはいても、速水さんがギュンターについて何らかの否定的なコメントを発してくれることを期待し、彼女の口元をじっと見つめる。もはや僕にはそれくらいしか救いがない。ともすれば喪失しそうな平静を保つには、共にギュンターを否定してくれる仲間が必要なのだ。
僕の視線に気づくと、速水さんはうっすらと口を開けたものの、何も言わないままうつむいてしまった。
「いやあ、ほんと暑いね」
馬鹿みたいに、いや実際、今の僕は馬鹿そのものだが、僕は同じ台詞を繰り返した。速水さんはうつむいたまま団扇をあおぎ、襟元を少しくつろげて言った。
「浴衣ってさ、全然涼しくないんだよね、実際」
「そうなんだ。でも見た目には清涼感があるよね」
そう言いながら僕は、夕陽に照らされた愛ちゃんの浴衣姿を眺める。喉が鳴り、溜め息混じりにつぶやいた。
「やっぱり浴衣はいいなあ」
「そう?」
「よく似合ってる」
「え、そうかな?」
「うん、愛ちゃん肌が白いから、紺の浴衣がよく似合う」
「ああ、そうだよね」
もう何も考えたくない。このまま愛ちゃんを、ただぼんやりと眺めていたい。
警察による交通整理の指示に従い、延々と続く大行列に身を投じた僕らは、ようやく日が落ち始め薄暗くなってきた街路を牛歩で進む。特に目的地が決まっているわけではないが、できるだけ前進し、なるべく花火がよく見える地点に陣取りたい。それがこの人波の総意でもあるだろう。
僕らの先頭は金本さんと茶山で、その後ろに愛ちゃんとギュンターが続き、最後尾が速水さんと僕だ。前を歩く二人の会話は、花火の破裂音と見物客の喧騒に紛れてよく聞こえないが、愛ちゃんはしばしば、笑顔でギュンターを見上げている。
隅田川の堤防まで出ると、人波の勢いが少し穏やかになった。堤防沿いの遊歩道は比較的広いため、立ち止まって花火を見物する余裕がある。
「あっ」
思わず声を漏らした僕は、愛ちゃんとギュンターを目で追った。二人が僕らの一隊から離れ、さり気なく別行動を始めたのだ。
「どうかした?」
速水さんはきょとんとして、僕の顔を見つめている。
「いや、あの……」
ギュンターは愛ちゃんの手を引き、ゆっくりと堤防へ近づいていく。人混みと闇に紛れ、徐々に二人が見えなくなる。
「あっちの方が、花火、よく見えるかも」
僕がそう言うと、速水さんは黙ってついて来た。
目を凝らすと、堤防の欄干にもたれて夜空を眺める愛ちゃんたちが見える。周囲には同じように、一目をはばからずいちゃつくカップルが何組も並び、その猥雑な風景に、僕の愛してやまない美少女が溶け込んでいく。
ギュンターは、それがごく自然なことのように愛ちゃんを抱きしめるとおでこに口づけ、それから覆いかぶさるようにして唇を奪った。表情まではうかがえないが、愛ちゃんは彼の腰に手をまわし、しばらくそのままじっとしていた。
「おい!」
突然肩を叩かれ、腰を抜かしかけた。
「何覗いてんだよ。変態」
茶山だ。隣には金本さんもいる。二人ともにやにやしながらこちらを眺めている。小刻みに震える膝が、我ながらひどく滑稽に思えた。
☆ ☆ ☆
花火の打ち上げが終わる少し前になって、人波が逆流し始めた。皆、駅が本格的に混みだす前に帰りたいのだろう。
僕らは再び六人揃い、河川敷のテラスで最後の花火を見届けた。
「ねえ、これから俺んちでカラオケしない?」
茶山の提案を聞くと、愛ちゃんはギュンターを見上げ、うなずいてから答えた。
「ごめん、あたしたち先に帰る」
「じゃあ駅まで一緒に行こ?」
金本さんがそう言って、愛ちゃんの袖をつかんで歩きだした。駅までの道程は、行きと同じく人の流れに身を任せた。前を歩く愛ちゃんの頭が鼻をかすめ、香水だかシャンプーだかのほのかな芳香が匂う。うなじの後れ毛を凝視していると、何度が喉を鳴ってしまった。むしゃぶりつきたい、という欲望が、抑えても抑えても溢れてくる。けれども僕にできるのは、ただ溜め息をつくことだけだ。
【12―Bにつづく】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
