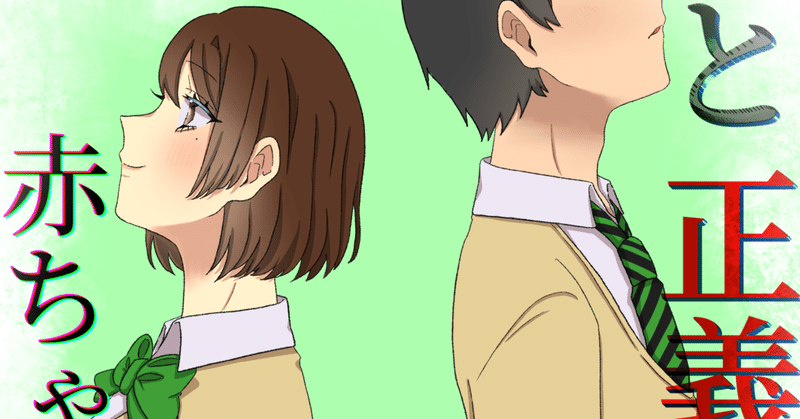
愛と正義の赤ちゃんごっこ【11ーA】
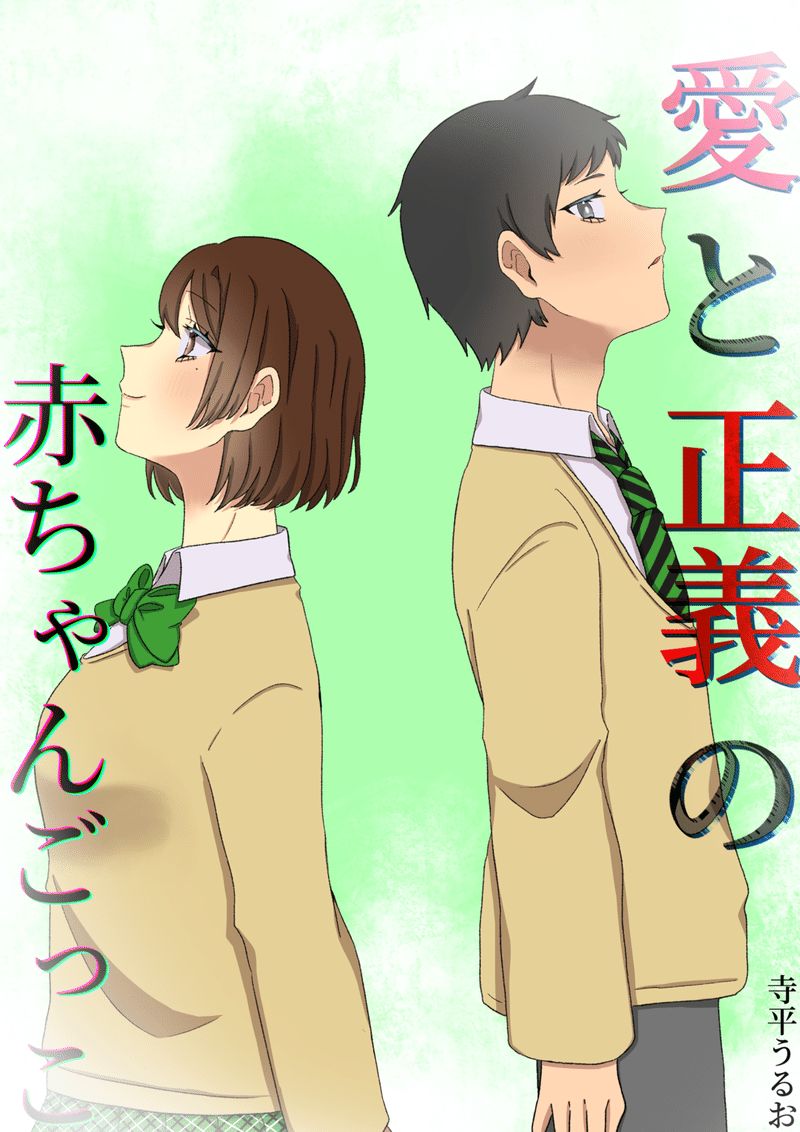
もうすぐ五時になろうかというのに、依然として照りつける陽光を浴びながら駅前の繁華街を歩いた。僕は愛ちゃんの横につき、茶山とカナモトさんの後を行く。駅前にはまだ仕事帰りの会社員は見当たらず、それゆえ彼らを狙う怪しげな客引きの姿もなく、夏休みの開放感に浮かれた学生たちが、海水浴にでも来たかのような薄着で闊歩している。
昨日に比べるとやや厚着の愛ちゃんは、しばらく歩いて外の暑さに堪えかねたらしく、下ろしていた髪をゴムで束ね、小さなポニーテールに結った。少々汗ばんだ艶かしいうなじが露になり、喉が鳴った。
「剛君ちってどこ?」
「井の頭線の永福町ってとこ。急行なら十分もかからないよ」
先を行く茶山とカナモトさんが、先ほどのカラオケ計画を着々と進めている。まずい。迂闊について行ったりしたら、愛ちゃんの前で大恥をかかされることになる。いっそ僕一人だけ帰ってしまおうか。いくら茶山でも、カナモトさんの目の前で愛ちゃんに手を出したりはしないだろうし……。
人波に溺れそうな駅のコンコースで、僕は意を決して立ち止まった。
「あの、俺これから、新しいスマホ買いに行くから」
僕がそう言うと、満面に笑みを浮かべて茶山が振り返った。
「そっか。お前も来ればよかったのに。それじゃ」
「あたしもマー君といっしょに行こっかな」
僕は驚き振り向いて、愛ちゃんの横顔をじっと見つめた。
「そろそろ機種変しようと思って」
愛ちゃんにそう言われると、茶山は頬を引きつらせ、力なく手を挙げた。
「じゃあね愛ちゃん、赤地君!」
カナモトさんがそう言って、茶山と共にエスカレーターの上へ消えていくのを見送ると、愛ちゃんはにやりと笑って言った。
「うまくいくといいね」
「ああ、うん」
そういうことか。おそらく愛ちゃんはカナモトさんに、彼女と茶山の仲を取り持つよう頼まれたのだろう。これで少なくとも、愛ちゃんは茶山を恋愛対象には考えていないということがはっきりした。とはいえ、僕はそのための出しに使われたのだから、いわば奴と刺し違えたわけだ。半分浮かれていた自分が馬鹿らしくなる。
「たしかねえ、サンロードに何軒かあるよ」
「え?」
何の話かわからず、ぽかんとする僕に愛ちゃんが言った。
「ケータイショップ。行こ」
二人で歩く商店街に、夕暮れ時の爽やかな風が一筋吹いた。
⭐︎ ⭐︎ ⭐︎
吉祥寺駅前の喫茶店は、午後五時とあってかなり混んでいる。冷房の効いた店内に入り、席が空くまで二、三分待った。四人掛けのテーブル席で、愛ちゃんの左隣に金本さんが、僕の右横に茶山が座り、愛ちゃんと僕、金本さんと茶山が向かい合っている。愛ちゃんと金本さんはラズベリーケーキ、僕は苺パフェ、茶山はコーヒーをそれぞれ頼んだが、この様子では注文の品は当分来そうにない。
周囲の喧騒に張り合うかのような大声で、金本さんが脈絡のない話をまくしたて、愛ちゃんはにこやかに相槌を打ち、茶山はへらへら笑いながらいい加減なことをほざいている。僕は例によってうまく会話に入れず、手持ち無沙汰にコップの中の氷を回しては、解け出た水をちびちび舐める。
たったの四日間なのに、今回の講習はやけに長く感じた。二日目から金本さんと行動を共にするようになって、僕らはずいぶんと引っ掻きまわされたような気がする。しかしまあ、彼女が茶山とくっついてくれたおかげで、愛ちゃんがちょっかいを出される心配はなくなったのだから、その点に関しては感謝すべきだろう。
ようやく注文の品が供されると、今までしゃべりまくっていた金本さんが一心不乱にケーキを貪りだした。対照的に愛ちゃんは、一口ずつゆっくりとケーキを噛みしめる。生クリームのように白い頬が、咀嚼するたびに可愛いらしく動いている。
「マー君、どうしたの?」
愛ちゃんの声で我に返った僕は、目の前にある苺パフェの存在を思い出した。
「ああ、うん、大丈夫大丈夫」
「でも意外だなあ」
コップに半分ほど残っていた冷水を飲み干して、彼女は続けた。
「マー君って甘党なんだね。そんなに痩せてるのに」
「そんなに意外かな。速水さんにも言われたよ」
僕が笑ってそう言うと、愛ちゃんはテーブルに身を乗り出した。
「え、カズとふたりでこういうとこ来たことあるんだ?」
しまった。余計なことを言ってしまった。
「あ、いや、まあ――」
「誰それ? 女の子?」
金本さんが口を挟むと、すかさず茶山が合いの手を入れた。
「うちの学校の女子だよ。しかし浮気もんだな赤地は」
まっすぐこちらを見つめる愛ちゃんに、僕は平静を装って言った。
「一緒に宿題をやっただけだよ」
「いついつ?」
「えっと、いつだったかなあ。よく憶えてないな」
「じゃあさ赤地君、あさってその娘も誘って六人で花火行かない?」
唐突にそう提案した金本さんに、なぜか茶山が聞き返した。
「六人?」
「そう、六人で」
「俺とエミナと、桃下と赤地と速水と……あとは?」
「愛ちゃんの彼氏に決まってんじゃん」
薄笑いを浮かべ、茶山が僕の顔を見た。
「なあんだ、そういうことか」
何が「そういうこと」なのだろう。困惑する僕に彼は言った。
「そうだ、お前携帯の番号教えろよ」
「エミナにも教えてー」
こいつらに電話番号を教えるのは気が進まないのだが、仕方ない。しぶしぶスマートフォンを取り出した僕は、ディスプレイをのぞかれないよう細心の注意を払いつつ番号を交換すると、すぐにまた携帯をシャツの胸ポケットにしまった。
「わあ、かっこいいー」
愛ちゃんのスマートフォンをのぞき込み、金本さんが声を上げた。
「何? 何?」
すばやくテーブルの向かい側に移ると、茶山が聞こえよがしに言った。
「へえ、これが桃下の彼氏かあ」
真っ赤な顔でうなずく愛ちゃん。彼女の携帯には、以前待ち受け画像に設定されていた仔猫の代わりに奴の、ギュンターの画像が表示されているのだろう。
自分の席に戻ってきた茶山は、したり顔で僕の肩を叩いた。
「あきらめろ赤地。お前じゃあれには絶対勝てない」
「ひゃははは! 剛君ひどーい」
二人が大騒ぎする横で、愛ちゃんは黙ったままちらりとこちらの様子をうかがった。僕はいたたまれなくなり、うつむいた。
「ねえねえ、ちょっと携帯貸して」
愛ちゃんが答える間もなく、金本さんは彼女から半ば強引に携帯を取り上げ、ご親切にそれをこちらへ向けた。液晶画面の中には、ハンサムな西洋人に肩を抱かれて心底幸せそうに微笑む愛ちゃんの姿があった。
「どう? これが赤地君のライバルだよ」
「まあ、これだけ差があればかえってあきらめがつくよな?」
二人を無視して、僕はパフェの中央に載っていた大きな苺を頬張った。
「あーあ、いじけちゃった。剛君がひどいこと言うから」
「よし、お詫びに俺からプレゼントをやろう」
プレゼント? 僕が視線で問うと、茶山はにやりと笑って言った。
「ちょっとお前の携帯貸せよ。桃下の写真撮ってやるから」
冗談じゃない。僕のスマートフォンの待ち受け画面には、速水さんにもらった愛ちゃんの画像を使っているのだ。もしこれを見られでもしたら大変なことになってしまう。
「いや、いいよ」
「遠慮すんなって。ほら」
「いや、ほんとにいいから――」
「いいから貸せって!」
必死で抵抗する僕の胸ポケットから、茶山はスマートフォンを奪い取った。
「ありゃ?」
ディスプレイを見た彼は、きょとんとした顔でつぶやいた。
「もう持ってたのか」
「どれどれ?」
金本さんまでこちらに来た。
「わあ、可愛いー。愛ちゃん、ウェイトレスやってたんだね?」
「え?」
とうとうこちらへやってきた愛ちゃんは、液晶画面をのぞいたきり言葉を失っている。無理もない。知らないうちに自分の画像が、僕のように陰鬱な男の手に渡っていたことを知ったら、驚きを通り越して恐怖すら感じるだろう。だが僕だって被害者だ。あくまでこっそりと、個人的な楽しみのためにこの画像を所持している分には、誰も不幸にはならないはずだったのに……。すべての元凶は、僕の恋路の邪魔ばかりするこの低偏差値カップルだ。
「その画像は、速水さんにもらったんだ。前に愛ちゃんが、レストランで働いてたって話になって、それで……」
愛ちゃんは黙ったまま、真っ赤な顔で携帯を見つめている。
「これくらい許してあげなよ愛ちゃん。赤地君にはこの写真が心の支えになってるんだもん。ね?」
「そうそう、これさえありゃ桃下が相手してくれなくても……な?」
もはや愛ちゃんの顔色をうかがうこともできず、震える手でスマートフォンをポケットにしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
