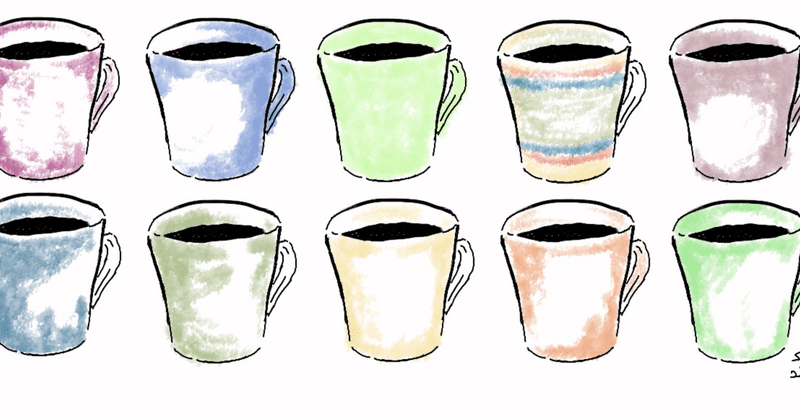
されど珈琲
第一章 転職
サカムラが珈琲の世界に入ったのは、今から十一年前、三十歳になってからであった。
サカムラは山口県の東部の出身である。母一人子一人の家族で、母は元は県内の温泉場で芸者をしていたらしいが、詳しいことは息子に話して聞かせることはなかった。母は田舎町の駅前で小さな大衆食堂を開いていた。サカムラは自分の父親についてはほとんど知らなかった。母がわずかに漏らした話によると、父親は瀬戸内海のある汽船会社の入り婿に入った人物で、サカムラが大人になって思い返してみると、母親はいわゆる愛人関係にあったのはまちがいなさそうだが、どこの誰某という固有名詞については、何の手がかりも得られなかった。
サカムラは高校を優秀な成績で卒業すると、京都の国立大学の理学部に進学した。大学では数学を専攻した。実家の経済状態が芳しくないので、多少でも収入のよい仕事に就くために、企業への就職を希望した。世間はバブル経済の崩壊後十年を経過していた頃で、就職状況は好転しておらず、彼の就職はなかなか決まらなかった。結局、彼は大阪に本社を置く某商社に採用された。
サカムラは商社では、数字こそ扱うものの、専攻した数学とはまるで縁のない経理部に配属になり、企業会計原則をまったくの白紙から勉強することになった。そのうち、会社の経理業務に情報システムを導入することになり、彼は理系出身ということで導入の担当者になった。
サカムラは入社して四年目に、学生時代から付き合っていた大学の同級生と結婚し、まもなく男児を授かった。しかし彼の仕事が多忙を極める中、日付が変わってからの帰宅が毎晩のように続いた。彼の妻は育児を手伝ってくれる身寄りがおらず、家事を独りで切り盛りして、深夜まで夫の帰りを待つ日常が三年ほど続いた。
ところがある日、妻の言動に変調が起こった。
サカムラが、深夜日付が変わってから帰宅すると、妻は彼が上着も脱がないうちに言い出した。
「私の言うことをそのまま実行してください。」
彼は妻の言っていることの意味が咄嗟にとれなかった。妻は、常日頃はサカムラに「です」「ます」をつけた敬語で話すということがなかったので、彼は妻とは別人が自分に話しかけたような感覚を持った。
ようやく妻の言っている言葉を理解して、彼は尋ねた。
「そのまま実行って・・・何?」
彼の妻の目は吊り上がり、額に青筋が立っていた。
「詮索をすれば、危ないです。いいですか、よく聞いてください。あなたは夕方十六時にはここに帰って来なくてはなりません。」
「えっ、会社の定時は十八時だけど・・・」
「いいですか。十六時です。十六時にはあなたはここにいなくてはならないのです。」
彼女の主張はそれから延々と夜明けの四時まで続いたが、同じことを繰り返して言っているだけであり、サカムラが何が危ないのか、話のディテールを尋ねると、彼女は、
「あなたは、私の話を何も聞いていないのですね!」
と激昂して、また同じ話を繰り返すのであった、
サカムラは、これは大変なことになった、しかし妻の名誉にかけて、言動の変調の話は誰にも話せない、と思った。もとより命が危ない云々が本当かどうかは問題ではない。とにかく、彼女には逆らうまい、おれが家庭を省みなかった報いが来たのだ、と思った。
彼女の変調の日々はこうして始まった。サカムラは、会社には自分の体調がよくないと話して、何とかぎりぎり十六時に帰宅するように苦労する日々となった。彼女は、サカムラが会社に出ている日中には、ノートにびっしりと何事か書き続けているようであったが、彼女はそのノートを彼に見せることを拒否した。サカムラは彼女を病院に連れてゆくべきではないかと思って、その方法を考えてみたこともあったが、本人に自覚症状がない以上は、本人が病院に行くことを承諾するのはまったく不可能であることがわかった。彼は、できるだけ彼女の神経に障らないように立ち回って、自分ひとりで何とかするしかない、と覚悟を決めた。
そのような日々が約一か月続いたが、会社は、当然、何かあったのか疑いの目で自分を見るようになり、同僚も
「どうやら女性関係でトラブルになっているらしい。」
と、あらぬ噂をしている節があった。サカムラは妻の変調を会社に正直に話そうかとも考えたが、たぶん雲をつかむような話としか受け止められないだろうと思った。会社の人事部の人が事情を確認するために妻に連絡をとったりすると、妻の精神状態には相当によくない結果になるだろうとも思った。彼は考えた挙げ句、会社に辞表を出した。
会社を辞めたサカムラは、アルバイトで生計を立てながら就職口を探しているうち、神戸の珈琲豆を扱う商社が情報システムに明るい人材を募集していることを知り、さっそく応募して、幸いにも採用された。収入は前の商社の時の半分程であったが、サカムラはこれで子供を経済的な心配なく育てられるようになり、安堵の胸をなで下ろした。彼の妻は、サカムラが会社を辞めた途端に、言動の変調がうそのようになくなって、元の明るい聡明な女性に戻った。
サカムラが採用された商社は、シモムラ商会といい、初代が戦前にブラジルの珈琲園開拓で成功して、帰国後に設立したものであった。
サカムラが入社した時、社長は二代目になっていた。すでに五十代になっていたその社長の下で、従業員は五十名程であった。会社には、珈琲豆を仕入れる貿易部門、珈琲を焙煎する製造部門、系列の喫茶店約二十店を直営する料飲部門、それに総務経理部門があった。サカムラは、まず焙煎工場で三ヶ月間の研修を受けた後、総務経理部に配属され、情報システム開発を担当することになった。
シモムラ商会の仕事の進め方は、サカムラが前みに勤めていた商社とは全く異なっていた。社長が「これは誰々に任せる」と宣言した業務は、ほぼ完全にその任された従業員限りで決めることができるのであった。
ある日、サカムラはシモムラ社長に呼び出され、社長室に入った。
シモムラ社長は、小さい時から資産家の御曹司として育ち、海外留学の経験もあり、喫茶店の店作りには細かい部分まで自分の趣味を反映させた。シモムラ商会の喫茶店は、オランダの珈琲ハウスを手本として、焦げ茶色の木材を豊富に使用したヨーロッパ風の内装であった。そこでは、デルフト窯で焼かせたオリジナルの珈琲カップで、深入りの珈琲を提供した。シモムラ社長は、いつも仕立てのよい英国風の背広に、今では珍しい、手で結ぶ蝶ネクタイを結んでいた。
サカムラが社長室に入ると、シモムラ社長は、さして大きくはないが黒革の張られた社長席で待っていた。
社長はサカムラに言った。
「予算一億円の範囲内で、系列の喫茶店のレジスターのシステム化をやってほしい。その範囲で何でも思う通りにやれ。」
社長は続けた。
「人間、大抵の場合は、任されると言われた仕事は、自分が仕事のオーナーになるんだ。成功も失敗も、他人の財布だという気にはならないもんだ。まあ、最後はおれの財布ということなんだが、それはひとまず忘れてていい。」
そして、社長は普段使っている関西弁で付け加えた。
「うちは上場企業やないから、これでええねん。」
社長は立ち上がって、サカムラの両肩をぽんぽんと三度叩いた。
サカムラが入社したのとほぼ同時期に、彼と同年代のカミヤという男が入社した。
カミヤは、金沢の料亭の次男坊であった。料亭の最盛期は親のまた親の代のことで、現在は凝った宴会を開く旦那衆が少なくなり、観光バスの団体客向けの昼食や、法事の仕出しなどが主な収入源になっていた。ただし往時の盛況の名残として、土蔵には九谷焼や輪島塗の豪華な食器や、書画の類が大量に収蔵されていた。子供の頃のカミヤは、まだ健在であった祖母のお供で、土蔵の虫干しや整理を手伝ううちに、書画や道具の善し悪しがおのずとわかるようになった。
店の後継者と決められたカミヤの兄と異なり、次男坊のカミヤは、好きな進路を選ぶことを許された。彼は小さい頃からクロッキーやデッサンに巧みで、将来は美術で身を立てたいと志し、東京の芸術系の大学に進学した。
カミヤは大学では日本画を専攻した。しかし大学では、カミヤの日本画はあまりに日本古来の形式美にこだわり過ぎていて、まるで骨董品の模造と変わらないという評価を受け、芳しい成績を納めることができなかった。カミヤは画家の道を諦め、教職の単位を取得して、金沢の高校の教師となった。
カミヤは、勤めて三年目に、つぎのような事情で教師を辞めることになった。
カミヤは、高校の教え子の一人である、三年生の女子生徒に、自分の絵のモデルになってほしいと頼んで、彼女を金沢の浅野川の天神橋に日曜の昼下がりに呼び出し、戸外で一時間ばかりスケッチした。スケッチは一度だけでは完成せず、日曜のたびにカミヤは彼女を呼び出して、一時間ばかりのスケッチを続けた。そのような日曜が五回ほど続くうち、二人の間に愛情が芽生えた。二人は結婚の約束を交わし、カミヤは彼女の卒業を待った。二人とも自分の本分を心得て、手をつなぐようなことさえなかった。
彼女が晴れて卒業したところで、カミヤは彼女に正式に結婚を申し込んだ。両家の親は初めは反対したが、まじめな交際を続けていたことは薄々気づいていたこともあり、結局は二人の気持ちが真剣なものであることを理解し、半年ほど経って、結婚に漕ぎ着けた。
ところが、学校関係者の間では、これは教師と教え子との不祥事であると噂され、カミヤの職員室での居心地は悪いものとなった。彼は、ある日、校長室に呼び出された。
校長は、普段とはちがって、妙に丁寧な言葉使いで、言いにくい風を装いながら話した。
「実は、教育委員会の関係者から、依願退職を示唆する話がね、来ているんですね。やっぱり、特定の女子生徒を、個人的に呼び出してスケッチのモデルにしたのは、教育者としてはまずかったでしょう。もちろん、処分とか、強制とか、そういうもんじゃないですよ。でもね、あなたは、実家が地元では名の通った料亭ですから、辞めても生活の心配はないんでしょう。ここは、ひとつ私を助けると思って、しかるべく処していただけないでしょうか。このとおり、頭を下げますから、なんとかお願いします。」
こうしてカミヤは辞職を余儀なくされ、新婚の身でありながら、職を失うことになった。
カミヤは、実家の料亭に戻るよりも、いっそ別の土地で新婚生活を始めたいと考えた。そこで、夫人の遠縁の住んでいる大阪府の摂津にとりあえず引っ越すことにして、一間だけのアパートを借りた。彼は、そこでシモムラ商会のことを知って、採用に応募したのだった。
カミヤは、珈琲の焙煎の研修を三ヶ月間受けてから、商品のパッケージや、系列喫茶店の広告や、店舗改装などのデザインを担当した。彼は、シモムラ社長の了承のもとで、大正時代の商業デザイナーの河村目呂二に範をとって、モダン和風を基調とした意匠を次々に創作した。
サカムラもカミヤも、それぞれが事情を抱えて転職したという共通点があったからか、二人は入社早々から親しくなった。会社の昼時には、めいめい持参の弁当を使いながら、雑談を楽しんだ。
「初めは大きな会社から小さな会社に移ったんで、仕事のスケールとか小さくなるんじゃないかと思っていたんだけど、それははずれだった。採用したての若い者にほとんど全権を任せてもらって、正直驚いたよ。」
「うん、おれのやっているデザインの仕事は、素人でもいろいろ口を出したくなるもんだけど、シモムラさんは、細かいことには口を出さないで、できあがったところで全体的に見て良し悪しの評価をするんだ。おれの大正モダン風のデザインは、河村目呂二という人の画風を学んだもので、目呂二のことは今や世間は忘れていて、あまり名も知られていないんだけど、シモムラさんはこの間もキャンディーのパッケージにおれが描いたモダンガールの図案を見て、
『竹久夢二の画風とちょっと違うな。この女性の顔、にっこり笑っているもんな。それがきみの言う、目呂二の画風なんやろう。』
って言っていた。シモムラさんは大金持ちだから、美術品も陶磁とか西洋骨董とか、いろんなジャンルのものを買って持っているらしいな。眼が肥えているんだね。」
「オーナー企業は、オーナーがどんな人かによって、働く人にとって天国にも地獄にもなるんだろう。おれたちは運がいいな。」
ところが、彼らの入社から二年程経って、シモムラ商会に転機が訪れた。
シモムラ商会の本業の珈琲の事業は順調であった。しかし、バブル経済の時に、当時斜陽になっていた六甲山の老舗ホテルを買収しており、ホテル事業の赤字が経営の重荷になっていた。
その時現れたのが、欧州の大手食品企業であった。その大企業は、シモムラ商会の株式を買い取りたいと申し入れて来た。シモムラ社長の妹二人の持ち株は、すでにその大企業に握られていた。そのため、シモムラ社長は持ち株比率としては三割弱の少数株主となっていて、社長が抵抗する手段はほとんど残されていなかった。
シモムラ社長は、親族の仲がそれまでよくなかったところに、うまく付け込まれてしまったと後悔した。
彼が大企業側に出した条件は、従業員の雇用の確保であった。大企業側はこの条件を受け入れた。
シモムラ商会の社長の革椅子には、ベルギー人の新社長が座ることになった。会社の組織も社則で細かく定義されるようになり、サカムラとカミヤの業務範囲や権限も、非管理職従業員相当のものに縮小された。
シモムラ商会の直営店も、営業形態を大幅に変更された。それまではシモムラ社長のこだわりで、珈琲一杯ずつ、ネルドリップで淹れる方式を続けてきた。カップもソーサーもスプーンも、シモムラ社長の監修によるオリジナルにデザインされたものを使っていた。
ところが、ベルギー人の社長は、世界の最新のトレンドを実現する店舗を望んだ。それはアメリカの西海岸で流行しているスタイルの店舗で、ビートル・シアトルというチェーン名称で展開を始めた。シモムラ商会という会社の商号も、ビートル・シアトル・ジャパンに変更された。店舗は工場生産のパネルを組み合わせた簡易な内装で、飲み物は基本的には紙かプラスチックの使い捨てのコップに入れて提供する形態であった。サカムラは、新業態は、食器を洗浄する人の人件費がほとんどかからないことや、店舗の設備も比較的軽くてすむことに気がついた。サカムラは、これは採算的にはいけるだろうが、はたして使い捨てのコップで珈琲を出して、よいお客さんが固定客になってくれるだろうか、と思った。しかしその心配は当たらず、このような店舗でパソコンを見ながら仕事をするというライフスタイルが流行になって、やがてこの店の双頭のテントウムシのロゴマークは大都会の街角の至る所に見られるまでに急拡大した。サカムラの担当したレジスターシステムは、この急拡大を大いに助けることになり、サカムラは何度も望外の金額のボーナスを受け取った。
しかし、サカムラは、このような方式の店舗であれば、せめて飲み物はもっと良質のものが出せるのではないかと考えるようになった。提供する品数を絞って、純粋に珈琲の味覚を楽しむような店はできないだろうか、それができれば、シモムラ社長が提供してきたことを別の形で継承することになるのではないか、と考え始めた。
勤め先の経営が変わって三年ほど経過したある日、サカムラのもとに、長らく通信の途絶えていた実家の母親から手紙が届いた。
サカムラは、母親が手紙など書いて送ってきたことがないので当惑し、さっそく封を開けてみると、つぎのようなことが書かれていた。
サカムラの実の父親が先月病死した。実の父親は汽船会社の社長であったが、入り婿であり、飾り物の社長で、実権はすべて夫人である創業家の娘が握っていた。彼は名義上は大きな財産を持っていたが、彼が自由にできるお金はほとんどなかった。彼のわずかな月々の小遣いから、サカムラの養育費の補助が出ていた。このたび、彼の遺言がみつかり、自分名義の財産から五千万円をサカムラの母に、同じく五千万円をサカムラに遺贈すると記載してあることがわかった。彼の夫人はサカムラの母子の存在をそれまでまったく知らず、大変に立腹したらしいが、弁護士は遺言を忠実に執行せざるを得ないと説得した。
したがって、五千万円のお金が近々サカムラの口座に振り込まれる運びとなったので、そのつもりでいてほしい、とあった。
サカムラは、母親の手紙の書きぶりが、亡くなった人への感傷の混じらないたんたんとしたものであることを感じた。感傷が起こらないのは、サカムラも同じであった。彼に起こったのは、感傷ではなくて、これが自分の転身のチャンスではないかという思いであった。思いがけないこのお金を元手にして、本来あるべきシモムラ商会の姿を実現するような会社を作りたいと思った。サカムラの構想する店舗は、店舗内装や設備や容器にかけるコストを最低限に抑えたうえで、飲料として良質なおいしい珈琲を提供する形態であった。
サカムラは遺産の着金を確認すると、ただちに会社設立に向けて動き出した。商号はサカムラ商会とし、定款の事業目的には「珈琲等飲料および食品の原材料の販売」「珈琲等飲料および食品の加工、製造、販売」「店舗での飲料および食料の提供」「前各項に関連付随する一切の業務」と定めることとした。
サカムラは、元シモムラ商会であるビートル・シアトル・ジャパンからサカムラ商会に移籍を希望する従業員を、密かに募集した。一級建築士のツネムラはこの募集に応じて移籍した。移籍を希望したのはツネムラの他四名であった。
カミヤは、サカムラ商会への誘いには応じなかった。彼は彼で、独立を考えていたからである。カミヤは、かつてシモムラ社長が自分の美学を世に問うつもりでカフェを営業していたように、自分も自分のやり方で、自分の美学を世に問いたいと思っていた。彼は、自分のデザインの仕事は、カフェでお客様に提供するひとときを構成する不可欠の要素と考えていた。彼は、カフェで大事なことは、単に飲料を提供するというのではなくて、お客様が店舗で過ごすひとときの時間、お客様が店舗で体験するワンシーンを演出することだと考えた。個々の珈琲やデザインをばらばらに工夫するのではなくて、それらをお客様のくつろぎのひとときの提供という目的の下に統合するべきだと考えた。
カミヤは自分の考えをさらにつぎのように展開した。自分の実家の料亭では、たしかに料理を器に盛って出すことにちがいはないものの、料理も器も料亭の主人がおのれの見識をもって見立てたものだ。自分が今担当しているデザインの仕事は、料理に触らないで器だけ準備しているのと同じだ。自分独りで、珈琲豆の選定も、焙煎も、抽出も、食器の準備も、片付けも、すべてをやる店を出したい。そして、かなうことであれば、かつて画家の道を断念して立ち去った東京で、小さくてもよい、珈琲を出す店を開きたい・・・カミヤの夢はふくらんだ。
カミヤは、自分の夢を、社長を引退していたシモムラ氏に打ち明けることにした。シモムラ氏は経営権を失ったとはいえ、個人としては六麓荘に豪壮な屋敷を構える資産家であった。
真夏の日射しの下、カミヤは駅からの坂道を、汗をふきふき二十分ほど登って、シモムラ邸を尋ねた。門を入ると、洋館と日本家屋とが並んでいるのが見えた。洋館の玄関の前には、シモムラ氏の愛車のベントレーが強い太陽の光でサファイア色に輝いていた。
カミヤは、洋館の応接間に通された。応接間はフランスのロココ様式で、壁は虹のような多種類の色彩で文様を織り出したクロスがいちめんに張られ、天井は三重に折り上げられた真ん中に華奢なシャンデリアが下がっていた。
この暑いさなかにいつものようにスーツを着て蝶ネクタイを締めたシモムラ氏は、カミヤの来訪に機嫌を良くした様子であった。シモムラ氏は、自分のお気に入りの深煎り珈琲を、古伊万里風のマイセンの陶器のカップに自ら注いだ。
「これは、けさ、うちのアトリエでわしが焙煎した、パナマ・ゲイシャの豆や。どや?」
シモムラ氏の爪は、入手困難な最高級の珈琲豆であるパナマ・ゲイシャを焙煎した粉末に染まっていた。
彼は、カミヤの新店舗の夢を聞いて、つぎのように言った。
「わしも、あのベルギー人の社長が会社をあんな風に世知辛く変えてしもうたのが残念や。しかも、ビートル・シアトルの店舗展開がどんどん進んで、えろう成功しよるのが、くやしゅうてな。自分ももう一旗揚げることはでけんか、考えていたところや。」
シモムラ氏は、私的な会話は関西弁で、社業に関わる公式な発言は標準語でと使い分けていたが、今は標準語を使う機会がなくなっていた。
彼は、社長であった時のように背筋をピンと伸ばすと、話し方を変えた。
「しかし、先方に株式を譲渡した時に、競業禁止条項を契約書に入れさせられて、自分が同業を営むわけにはいかないんだ。でも、君の個人経営、しかも東京の店であれば、そこになにがしかの出資をするのであれば、差し支えあるまい。よし、君の店に五百万円出資しよう。その代わり、自分が出資者であることは内密にしてほしい。」
シモムラ氏は、社長であった時のようにてきぱきとカミヤに援助の趣旨を伝えると、つぎのように尋ねた。
「それで、君の店は。わしの欧風趣味そのままでもないんだろう。」
「今、私の頭の中にあるのは、日本の伝統的なもてなし、ということですが、具体的にはこれから考えます。日本のもてなしと言っても、数寄屋造りにするような形ではありません。それは総合芸術とでも言うのでしょうか、五感が満足するひとときを提供したいと思っています。」
「総合芸術、日本の伝統的なもてなし、か・・・」
シモムラ氏は蝶ネクタイをいじりながら続けた。
「料亭ならば、お客様をたっぷり一時間はもてなすから、それでいいかもしれないが、カフェでのもてなしはせいぜい十分だ。長居のお客様は、自分の仕事をしたり、連れと話したりで、カフェとは別の時間に入ってしまうからな。おれは、ごく短い時間に勝負を賭けて、カミヤ君が檜舞台で自分を見せるようなのがいいと思う。君は上背があって男前だから、千両役者になれる。自分がいちばん格好良く見えるような店を考えてみることだ。『花』がないと、あかんよ。『花』いうもんがどういうもんか、勉強するんやったら、世阿弥を読んでみなはれ。」
こうして、サカムラもカミヤも、新しい身の振り方が決まった。二人は元シモムラ商会であるビートル・シアトル・ジャパンを去るにあたり、二人がよく通った京都の上七軒のビアガーデンで飲むことにした。
そのビアガーデンは、上七軒の芸妓たちが芸を披露する劇場である歌舞練場を、夏期の閑散期に限って一般に開放しているもので、明治時代からの和風の建物にぼんぼりがともされ、建物の内外の数カ所に客席がしつらえてあった。サカムラは学生時代、上七軒に近い北野のある家に家庭教師のアルバイトをしていて、このビアガーデンの前を通ったことがあった。そのとき彼は、就職したらば必ずこのビアガーデンに行ってみようと思った。彼が大阪の商社に勤めている時は機会がなかったが、シモムラ商会に勤めてから、同僚と毎年夏に一回はここに来ていた。
サカムラとカミヤがこのビアガーデンに来た時は、いつも、冷房の効いたサロンではなくて、夜風に吹かれる庭園の客席を選ぶことにしていた。その晩も、二人は玄関で、上七軒の紋である五つ団子を朱で描いた団扇を買うと、庭園の座席に陣取って、団扇で時折蚊を追いやりながら、びっしりと冷たい汗をかいたビアジョッキを傾けた。
サカムラが言った。
「おれの会社の思想はシンプルだ。建物にも、器にも、金をかけないで、そのかわり店内に焙煎設備を置いて、焙煎したての珈琲を出す。珈琲の本当のおいしさを世の中の人に知ってもらう店にする。」
「おれの方はどんな店にするか、たぶん、店舗の入る物件を見ないと、具体的には決まらないだろうと思ってる。ただね、この間シモムラさんにアドバイスしてもらったら、花がないといけないって言われたんだ。どうも世阿弥にヒントがあるということらしい。」
「世阿弥?あの能楽の?千利休じゃなくて?」
「そうなんだ。世阿弥は、芸には隠された『花』がなければいけないって言ってるんだ。その『花』っていうものが何かというのが、難問なんだ。『花』があってはじめて、観客は舞台に共感することができる、『花』が共感のもとであるということまでは、何とかわかったんだけれどね。観客が、見たいと自分では気づいていないもの、自分が見ることになろうとも思っていなかったような、おもしろいもの、それが『花』なんだろうけど、そういう『花』を見せてあげて、驚いてもらって、感動してもらうにはどうしたらいいのか。これは、おれ自身試行錯誤しなきゃわからないんだろうと思ってる。」
「なるほどね。おれは世阿弥についてはなんにも知らないけれど、千利休については、時々考えることがあるんだ。利休は、聚楽第とか、大阪城とかに、茶席をしつらえたんだけど、茶席の客は、もちろん、城に集まった戦国大名だったわけだ。戦国大名は、それこそ豊臣秀吉に呼ばれて集められる前は、おたがいに命を賭けて戦っていたりしたわけだ。そういうおたがいに敵であって、もちろんそれまで話なんかしたことのない大名たちが、茶席でのひとときを共にすることで、初めておたがいに会話をかわすようになったのではないか、と思うんだ。利害を超えて、同じ席で同じ味を味わう、利休はそういう席をしつらえたわけだ。利休のような、席をしつらえて体験を共有してもらって、会話を成り立たせるような仕事は、ゆくゆくはおれの会社で考えなくてはならなくなると思ってる。世阿弥の方は、役者がよくなくちゃいけないから、おまえの店にふさわしいだろう。」
サカムラは、この上七軒の近くにはたしか観世屋敷の跡もあるし、すぐそばの北野天満宮では秀吉が大茶会を催したことがあるし、今晩ここでこんな話をすることになったのも、因縁めいているな、と思った。前の年にここに来たとき、たまたま隣の席にお客さんとして来ていた、昔は芸妓であったという老婦人から、上七軒の五つ団子の紋は、北野の茶の湯にこの街から団子を献上したことに因むという話を聞いたことを思い出した。
カミヤが言った。
「シモムラさんの言葉には、いつも深いものがあるな。おれたちの人生を変えるようなことを言うんだもんな。でも、もっと大事なことは、シモムラさんのいつもの口癖のとおりだ。」
「うん、そのとおり。」
「たがが珈琲、」
「されど珈琲。」
「ほんとうに、おれたちの人生は、『たかが珈琲、されど珈琲』の人生だと、あらためて思うよ。おれたちは、二人ともシモムラさんに育ててもらった弟子だ。そうだ、これからも、たまには二人で同窓会をしないか。」
「いいね。つぎの同窓会の場所は、東京になりそうだな。」
第二章 ヤマイヌカフェ
サカムラは、自分の会社の第一号の店舗を東京に開店することにしたが、自分には東京の土地勘がないので、東京出身であった部下のツネムラに相談した。
ツネムラは、いつもサカムラから質問があると、黒目を上に向けてきょろきょろ左右に動かし、あたかも自分の脳の中に書いてある情報を参照しているように見えた。ツネムラは黒目を元に戻して、今度はサカムラの目を見ながら、つぎのように答えた、
「焙煎設備が置けること、煙や臭いで近所からクレームが来ない場所であることは、もちろん必須でしょう。今はあらかじめインターネットを見て気に入った店をめざして来るお客さんが多いですから、昔みたいに前面通行客の多い、目抜き通りや駅前に店があることは、絶対の条件ではないと思います。それでも、お客様は、目当てのカフェだけに来るのではなくて、まわりの別の店に来るついでに寄る人が多いでしょうから、それなりのお店が近くに集まっている場所がいいと思います。」
「ツネムラさん、ぶしつけな質問だけど、あなたは東京で学生をしていたから聞いてみたい。あなたは女の子とデートする時、どこに連れて行った?」
ツネムラはまたわずかな間に黒目を左右に動かしてから、にっこり笑みを作って答えた。
「自分は、まずは渋谷でしたね。二、三時間は一緒にいないと仲良くなれませんから、時間をもて余すような場所は困ります。渋谷は、値段が手頃で若者が入りやすい店も多いし、坂道を登れば代々木公園で散歩できるし、天気が良くなくても映画館やプラネタリウムがあるし、自分は渋谷が定番でした。
あとは、バイトでボーナスが出たりした時は、銀座です。これも日比谷公園や映画館が使えます。客層の年齢がわりと高くて、学生にはちょっと背伸びの街でしたね。
ほかには、それぞれの通っている学校の近くというのもありましたね。東京の西側とか、高校や大学が多いですから。そこからちょっと足を伸ばせば、渋谷に着きます。自分は新宿も便利だったんですけど、新宿は、洋服や本を買うとか、自分だけの用事があって行く感じで、彼女と散歩する感じではなかったですね。」
「ツネムラさんが今選んでいる候補物件のなかに、渋谷の物件はあるかい?」
「あります、あります。都内の物件情報を三十ばかり集めて、そのうち候補をまずは十件に絞って、先週の出張でどれも見てきました。サカムラさんに先入観を持たせてはいけないかもしれないんですけど、渋谷の物件は自分のイチオシです。」
「来週、おれと出張して、その物件を案内してくれないか。」
「もちろん、喜んで。」
二人は翌週の火曜日の午前の新幹線で新大阪から東京に向かった。
東京駅に着くと、二人は地下鉄丸ノ内線に乗り、赤坂見附で地下鉄銀座線に乗り換えて、渋谷に向かった。
ツネムラは、渋谷駅で下車しながら、サカムラに言った。
「渋谷を初めて見るのでしたら、午後の方がいいんです。朝の渋谷は、通勤の人が多くて、まだ店があまり開いていませんから、このぐらいの時間がいいんです。」
ツネムラは、まず駅前の広場にサカムラを案内した。
「これが有名なハチ公の銅像です。ハチ公は昭和の初めに実在した犬で、東大教授の飼い犬でした。いつも教授の帰りをここで出迎えていたのですが、教授は病気で亡くなりました。ハチ公は教授が亡くなってからも、それまでと同じように、それまでと同じ時間にここに独りで来て、教授を待っていたという話です。ちなみに、自分の祖母は、小さいころハチ公の頭をなでたことがあると話していました。渋谷と犬との関係はそれだけでなくて、渋谷というところはなぜか犬と縁が深いんです。まずは、自分が渋谷のへそだと思っている場所にご案内しましょう。」
ツネムラはサカムラを伴って、mから線路のガードを東にくぐって、宮益坂の下に来ると、そこにはビルの谷間にコンクリートの長い階段が現れた。階段の脇には、
「宮益御嶽神社」
と書かれた石柱があった。
二人が長い階段を登りきると、そこは建物の屋上のような場所になっていて、玉砂利が敷かれ、奥に神社の社殿があった。
「ここは『みやますみたけじんじゃ』と読むんです。元々は吉野の狼の神様をお祀りしていた場所のようです。ほら、この狛犬さん、実は狼です。江戸時代よりもずっと古くからここに祀られているそうです。」
サカムラは、ずいぶん高くまで階段を登ってきたように思ったが、まわりを見渡すと、この境内よりも高いビルが林立していて、あたかも鎮守の森のように境内を囲んでいるのが見えた。ビルの間からわずかに見える、十月らしい乾いた青空を見上げながら、サカムラは言った。
「どの街でも、地元のお社は、その街の成り立ちのストーリーの記憶を呼び覚ます力を持っていると思う。たぶん、このお社の呼び覚ました記憶が、さっきのハチ公の伝説につながっているんだろう。」
サカムラの脳裏に、ふとある考えがひらめいた。
「狼は、山犬とも呼ばれることがあるよな。」
「たしかそうですね。」
「もしも渋谷に店を開くのならば、店の名前は『ヤマイヌカフェ』にしよう。よその商標と重なっていなければ、これで行こう。」
二人は、神前で前途の無事と商売繁盛とを祈願した。
ツネムラは、あらかじめ自分が目当てを付けた物件に案内する前に、サカムラにひとわたり渋谷の街を見てもらおうと思った。
「サカムラさん、女の子とのデートでなくてわるいですが、今から渋谷の街をひととおり案内します。
渋谷の地理をざっと説明します。渋谷という名前でわかるように、ここは谷になっています。駅とJRの線路、そしてその東に線路にほぼ平行に走っている明治通りのあるあたりが、谷の底です。その谷底に、東からは宮益坂、南西からは道玄坂が下りています。北側の代々木公園からは、公園通りが下りています。谷底と、この三つの通りとを、骨格としてまず押さえてください。」
サカムラは、境内の片隅で、先ほど東京駅で買ったばかりの東京の地図帳を開いて、ツネムラの言う地名を確かめた。
「まず、公園通りを案内します。ハチ公前で待ち合わせて、公園通りを代々木公園まで登ってゆくのが、自分のデートの定番コースでした。」
二人はもう一度ハチ公の前に戻ってから、北に進み、公園通りを登っていった。
「ご覧のとおり、公園通りには、西武や丸井やパルコが並んでいて、渋谷の目抜き通りになっています。大型店が目立つ通りです。小さくて個性的な店となると、この通りよりも南側に谷底の方に下る斜面があって、そこを下りる細い坂道に面した小さな建物でやっていることが多いです。このあと代々木公園の入り口に着いたら、通りを途中まで引き返して、その坂道を案内します。」
二人はNHKや体育館の建物の見える、公園通りの終点に着くと、そのまま踵を返して、公園通りを途中まで下りて、右の小道に折れた。ツネムラの言うとおり、南側に下がってゆく斜面には、自動車が通らない坂道が井の頭通りに向かって下りていた。
ツネムラは、サカムラと肩を並べて坂道の階段を下りながら解説を加えた。
「大手チェーンが新業態のカフェを試すのであれば、普通狙うのはこのあたりなんですけどね。」
やがて二人は井の頭通りに出た。
「このあたりは先ほどの駅前の谷底の続きで、夜の繁華街になっていて、飲み屋の多いところです。ここから先に行くと、道玄坂に向けて南側に上る斜面になっていて、あちらは風俗店やラブホテルが多い街になります。」
二人は百軒店と呼ばれる街の迷路のような小道を抜けて、道玄坂に出た。そして、道玄坂を下って、再び駅前に立った。
「秋の日は釣瓶落としと言いますが、急に暗くなってきましたね。自分が探した物件に急ぎましょう。現地で落ち合う不動産業者の方との約束の時間が近いです。」
二人は駅前から再び東にガードを越えて、今度は明治通りに沿って北側に進んだ。
「あそこに、ピンク色に塗られた建物が見えてきましたが、あれがかつて一九五〇年代ファッションを現代に流行させたピンクドラゴンの店舗です。卵のオブジェがシンボルになっています。この通りはピンクドラゴンの社長の命名で、キャットストリートという名前になっています。」
キャットストリートを少し進んで、細い路地を右に入ると、路地の奥に、ツネムラの選んだ物件があった。
「この路地はこの物件の前で行き止まりになっていて、目の前の崖の上は団地になっています。駅前から歩いて五分ぐらいしかかからない場所なのに、渋谷の駅前とは違って、ずいぶん静かでしょう。隠れ家の感覚がいいというのが、この物件の第一印象でした。」
二人は物件の前で、不動産業者の男性と落ち合い、名刺交換した。
物件は二階建てのコンクリートの建物で、一階はほとんどがガレージになっていて、二階は住宅であった。
不動産業者はタケダという男性であった。タケダは、見たところ三十代前半で、浅黒い精悍な顔立ちで、体にぴったり仕立てられたイタリア風の黒いスーツで、先のとがった革靴を光らせていた。
タケダはアタッシュケースから物件の鍵を取り出して、ガレージのシャッターの錠を開けた。
タケダはシャッターを上げると、二人を中に案内しながら言った。
「この物件は、持ち主が二階に住んでおられて、一階には自家用車を三台駐めておられた、車好きの方です。今は高齢になられて、老人ホームに入っておられます。珈琲の焙煎設備を入れるというお話ですが、ここは路地の行き止まりで、隣はエスニック料理店、裏はオフィスビルですから、煙や臭いでご近所のクレームが来ることはあまり想定されないでしょう。このあたりは元々、住宅と商業店舗とが混在している場所ですから、住んでいる方が出店に反対されるようなこともないでしょう。」
タケダは、分電盤の扉を上げると、ブレーカーを上げて通電させ、ガレージに下がっているペンダント式の照明に点灯した。
ガレージは、大きめの自家用車が三、四台は駐車できる広さであった。
タケダは説明を続けた。
「ここはご覧のとおり、天井は張っていませんから、上の階のスラブの下端がそのままむき出しになっています。スラブの下端までの天井高は、三メートルあります。個人の住宅だった物件で、これだけ天井高のあるものは珍しいです。たぶん、設計の時は、店舗とかアトリエとかができるように考えられたのでしょう。今の持ち主は、今から二十年ぐらい前に、この物件を前の持ち主からお買いになったんですが、キャデラックとか、リンカーンとか、お持ちになっていたアメリカ製の大きな三台の自動車を駐められるから、というのが購入の動機だったそうで、ここはそれからずっとガレージとしてお使いになっていました。結構天井高が高いので、焙煎設備とか、入れるのが楽だと思います。あっ、それから、多少古いタイヤとか残っていますが、全部捨てていただいてだいじょうぶです。」
ツネムラは説明を補足した。
「持ち主は、建物の内装や設備は、もう古いもので、解体してしまおうかとも思っていたぐらいだから、こちらで思うように変えてかまわない、と言っておられます。」
タケダは、サカムラの目を見ながらつぎのように付け加えた。
「賃貸物件はどれも改装は制約があるものですが、あらかじめ貸主側からそう言ってもらえることは珍しいんです。二階はつい半年前まで住宅としてお住まいで、それなりに手入れされていますから、そのままで住んでもだいじょうぶです。」
サカムラとツネムラは、巻き尺でところどころの場所を測りながら、物件の一階と二階とを見て回った。
ツネムラがサカムラに言った。
「自分が探した物件では、これがイチオシです。賃料も渋谷にしてはまあまあ手頃です。ほかの物件をご覧になったうえで判断していただければと思います。」
「ツネムラさんがイチオシの最大の理由は、ツネムラさんの設計の腕のふるい甲斐があるというところだね。」
ツネムラはサカムラにうなづいた。
タケダが二人の横から言った。
「実はこの物件、先行で検討されているお客様が二件おられまして、早い者勝ちになります。」
サカムラが尋ねた。
「さしつかえなければ、先行客はどういったお客様か、教えてもらえませんか?」
タケダはすこし躊躇した様子であったが、つぎのように答えた。
「守秘義務がありますから、詳しくは言えないのですが、ひとつは大手企業さんで、新規事業のパイロットファームと言っておられました。渋谷という土地柄で、学生や若い人を集めて、智慧を出してもらうようなことらしいです。もうひとつは、IT企業さんで、かっちりしたオフィスビルではおもしろい人材が来てくれないから、と言っていましたね、どちらも今日明日には返事をすると言っていました。」
タケダはそう言うと、自分の携帯電話の画面をちらっとのぞいた。
ツネムラが言った。
「サカムラさん、うちの返事はほかの物件をあした見てからにしますか?」
サカムラは言った。
「ひとつだけもういちど確認したい。ツネムラさんは、この物件がイチオシなんだね。」
「はい、」
「よし、ここに決まりだ。タケダさん、うちが借ります。手付金をここで打ちましょう。」、
タケダはアタッシュケースを机代わりにして、書類にサカムラ商会の押印をとり、サカムラから手付金を受け取り、領収書をサカムラに渡した。
ひとわたり事務手続きが終わったところで、タケダの携帯電話の着信音が鳴った。
「・・ええ、今決まったところです。御社は二番手になりますので、一番手の方で契約締結に至らなかった場合は、お声をかけさせていただきます。どうかあしからず。よろしくお願い申しあげます。」
タケダは携帯電話を切ると言った。
「サカムラさん、今のは大手企業さんからの電話で、お聞きのとおり、もちろん早い者勝ちですから、サカムラ商会さんが優先ですので、大手企業さんは二番手になると申しあげました。タッチの差でチャンスをものにされましたね。その大手企業さん、このあたりがご自分たちのテリトリーと思っていらっしゃるようで、ずいぶんくやしがっておられました。」
つぎの日の朝、サカムラとツネムラはタケダから鍵を借りてもう一度物件を訪れた。
「ツネムラさん、どんな感じの店にしたいのか、イメージを聞かせてよ。」
「内装はなるべく今のままを活かします。ただ、二階のスラブは半分ぐらい落としたいと思ってます。二階で自分たちが寝袋で寝泊まりできるぐらいの部分は残します。」
「それならば、二階の残った部分は、一階を見下ろすバルコニーみたいにできるかな?」
「おっしゃるとおりのイメージを持ってました。」
「家具はどうする?」
「基本は、高校の教室にあるような椅子の古いのをどこかで手に入れます。部屋の真ん中に、ビリヤード台の古いのを据えて、これを机代わりにしようと思ってます。お客さんの滞在時間は珈琲一杯を普通に飲み終わるぐらいの時間で考えています。それならば、人数分の机はいらないでしょう。カップは紙で使い捨てでいいですね。エスプレッソはそれ用の機械が必要ですし、紙カップでは出しにくいので、当面はやりません。」
「焙煎設備だけど、それほど大型のものは入れられないな。」
「ここで焙煎できる量でまかなえなくなったら、別の場所で焙煎したものを持ってきましょう。それが第二号店になるでしょう。」
「第二号店か。ちょっと気が早いが、意識しておこう。おれはここでは豆はなるべく浅く煎って、珈琲豆がまだ赤い生だったころの香りが残るようなのがいいと思ってる。」
「浅く煎るのであれば、思っているよりも量がいけるかもしれません。」
店舗の内装工事が終わって、開店したのは、翌年の二月であった。
店頭には、親子連れの狼をデザインしたヤマイヌカフェのロゴマークが染め抜かれた大きな暖簾が掛けられた。
スタッフはとりあえず男女一名ずつ採用した。サカムラは、従業員の髪型・服装などの身なりは自由とし、ただし深緑の生地にロゴマークが染め抜かれたエプロンを必ず着用させることにした。
サカムラはインターネットにホームページを立ち上げ、SNSでも新店舗の開店を発信した。もとより情報テクノロジーの利用は、サカムラが得意とする分野であった。
この土地柄は、欧米系の外国人の居住者が多いので、英語とフランス語でもメニューを表示し、ネット上もこれらの外国語での発信を積極的に行った。日本に居住する外国人のコミュニティー誌や、外国人がよく読むジャパン・タイムズにも、広告を出した。
この広報戦略が効いて、ヤマイヌカフェには外国人のお客が集まってきた。外国人の間での口コミが広がった。焙煎したての珈琲を提供するというコンセプトが受け入れられたのであった。
サカムラ商会は、一年後には、東京の深川に焙煎工場を主にして試飲コーナーが付属している形態の店舗を出店し、次いで京都の出町柳に渋谷と同様の形態の店舗を出店した。第一号店を出してから約六年で、サカムラ商会のヤマイヌカフェは、メジャーなマスコミにもたびたび取り上げられる有名ブランドに成長した。
第三章 カフェ・リュビ
カミヤは、サカムラが渋谷に第一号店を開店したのと同じ頃に、東京の築地に貸店舗を探した。築地は、カミヤが学生時代にデザインのアルバイトをしていた小さな出版社があったところで、彼にはそこに土地勘があった。物件は、元は東京都電が走っていたという、片側二車線のメイン道路から、路地を入ったところで、地下鉄日比谷線の築地駅に近い場所であった。銀座の目抜き通りからは、歩いて十分弱といったところであった。築地の卸売市場からはやや離れていて、市場の喧噪はここまでは伝わって来なかった。
カミヤは、シモムラ氏の示唆した世阿弥の「風姿花伝」を何度も読み返していた。彼は、世阿弥が演劇に不可欠の要素として示す「花」というものについて、つぎのような考えに至っていた。
「花」とは、観客の心を動かす何ものかであることは、まちがいない。それが、演じる者と観客との間に共感を起こすための要素のはずだ。しかし、観客にとっては、その要素がどのようなものであるか、予想さえついていないのだ。それが「花」が秘密であるということの意味だ。観客は、自分がそれを見聞することになろうとは思いもしなかったおもしろいものを舞台の上に見いだすとき、心を動かすのだ。だから、たとえば、観客にアンケートをとって、どんなものを見たいか尋ねたりしても、「花」はわかりっこないのだ。現代的なマーケティング調査では拾いようのないものだ。演じる者としては、「これは必ず人の心を動かすだろう」と確信できるものを舞台にかける他には、方法がない。そして、その確信を抱くためには、自分がそれをおもしろいと思っていなければならない。逆に、自分がおもしろいと思えることにしか、「花」はありえない。
人がカフェに滞在する時間は様々だ。シモムラさんが言うように、カフェに長時間滞在する人は、本を読んだり、雑談したり、眠っていたりで、珈琲を最初に一口啜った跡は、それぞれ思い思いの時間に入ってゆく。つまり、勝負は、最初に一口啜るところまでに、せいぜい五分だ。お客様が思い思いの時間に気持ちよく入って行けるように、わずか五分間をどう演出するか。おれはそこに賭けてみたい。
その五分間のクライマックスは、お客様が自分の注文した珈琲のカップを目の前にして、カップの縁に初めて口をつける瞬間だ。その瞬間は、自分が注文して自分のために用意された珈琲に、視覚、嗅覚、味覚、温度感覚をはじめ、五感をフル稼働させる一瞬だ。たとえそれまで自分の世界に入っていた上の空のお客様であっても、カップをたぐり寄せて、口に運ぶことだけは忘れないはずだ。珈琲豆も、珈琲カップも、それをお客様に届ける動作も、そのときにスタッフがお客様にかける一言も、すべてこの出会いの一瞬のためのものだ。
おれはこの一瞬のために付け加えたいものがある。それは、珈琲を淹れる動作だ。おれが一杯のカフェラテを、そのお客様のために、どうやって淹れるのか、それが見えるような店にしたい。もちろん、お客様の中には、珈琲を淹れる動作には興味がない人もいるかもしれない。淹れる動作がわざとらしければ、かえって逆効果にもなるだろう。だから、珈琲を淹れる動作を、ひとつの文様として演じたいのだ。一日何十杯という珈琲を淹れる動作は、回数を重ねるたびに、定型化されて、ひとつの文様になってゆくはずだ。そのような文様を、朝も、昼も、夕方も、今日も、明日も、繰り返し繰り返し演じてゆくのだ。それこそが、おれの考える「花」の発信だ。
「花」の発信の舞台になる店は、珈琲を淹れる人とお客様とが対面になれるような配置が必要だ。珈琲を淹れたらすぐにお客様に手渡しできる方がよい。「花」が究極のテーマだから、店の真ん中には、一抱えはあるような大きな壺に季節の花をふんだんに活けよう・・・
カミヤは、金沢の実家の蔵に入り込んで、九谷焼の食器でおよそ珈琲の容れ物に使えそうな小ぶりの碗や鉢を選び出した。店の真ん中に据えるつもりの花器には、備前焼の水瓶を選んだ。彼は選んだ陶磁器を一つ一つ丁寧に新聞紙でくるむと、自分で抱えて東京に持って帰った。
カミヤの借りた店舗は、元々は畳職人の攻防であった。カミヤは店舗の引き渡しを受けると、壁材を自分ではがして、コンクリートの素地にした上で、全体をやや青みがかった白色に塗り、左右の壁に日本画の手法で鮮やかな紅色の大きな牡丹の花を一輪ずつ描いた。
彼は、牡丹の花を描き終わると、つぎのようにつぶやいた。
「カフェの名前は、この紅色にちなんで、『カフェ・リュビ』にしよう。」
「リュビ」とは、紅色の宝玉ルビーのフランス語であった。
カウンターの向こうでカミヤが珈琲を淹れる作業をすることになるはずの作業場の壁、すなわち店の奥の壁に、カミヤは日本の伝統的な宝珠形をした紅色のルビーを描いた。
店の床はコンクリートの打ちっ放しであったが、これはそのまま使うことにした。天井は、設備をむき出しにしたまま、手を加えないことにした。
客席には、昔の茶店にあったような木製の長いベンチを店の左右の壁際に置いた。
カミヤは、営業時間を午前七時半から午後三時まで、年中無休と設定した。スタッフは、自分と夫人の二人では足りないので、アルバイト従業員をまずは一名採用することにした。
カミヤが採用したのは、リサという名前の、演劇の専門学校に通っている女性であった。
カミヤはリサに採用する旨を伝えたあと、つぎのように言った。
「うちの仕事は長時間立ったまんまになるよ。」
「わかってます。」
「服装と髪型は、店の決まりがあるんだ。基本としては無地の白のトレーナーかTシャツに、単色で柄のないパンツ、寒いときはジャンパーを羽織っていい。」
「舞台衣装ということですね。」
「そう、そのとおり、舞台衣装だ。この店は舞台なんだ。舞台に上がる役者の服装だ。髪型は、リサさんはベリーショートだから気にしなくていいんだけど、長くするときはゴムか何かでまとめてね。キャップをかぶるのはOK.」
リサはうなづいた。カミヤは続けた。
「店では、おれのことを『師匠』って呼んでね。家内は『マダム』って呼んで。」
「わたしのことは、『リサ』と呼んでください。」
二月に、「カフェ・リュビ」は開店した。
店内には二〇〇〇年代以降のフレンチポップスがバックグラウンドミュージックで流れ、店の真ん中には、半畳の畳の上に備前焼の水瓶が据えられ、白梅の枝が五本ほど活けられていた。カミヤは紅色のトレーナーに黒いパンツをはいて、カウンターの内側で、ほとんど口をきかずに珈琲を淹れる作業に従事した。彼の隣には時間帯によってマダムかリサのどちらかが立っていて、お客様の注文をとり、できたての珈琲をお客様に渡した。
もちろん、時間帯によっては、カミヤ独りの時もあった。カミヤが出られない時は、マダムとリサの二人の時もあった。
マダムすなわちカミヤ夫人は、幼稚園生の息子の送り迎えの時間は店をはずした。
リサは学校がある時間は、店に来ることはできなかった。
マダムは、もの静かで、店でもハスキーな小さな声で話した。彼女は、いつも黒く長い髪をゆるやかに束ね、化粧は薄めであった。外国人観光客から、歌劇の「蝶々夫人」を連想したのか、「マダム・バタフライ」と呼びかけられたこともあった。マダムは、見たところは古風なタイプであったが、店の会計はマダムの仕事で、お金に関わる税理士との打ち合わせは、マダムがほとんど独りでこなした。
リサは、マダムとは反対に、舞台できたえたはっきりした声で、店に快活な雰囲気をもたらしていた。彼女はマダムより頭一つ分背が高く、眼が大きくて彫りが深かった。彼女は店で働いている時は、晴れた日の海の色のような明るい紺色のキャップを被っていた。キャップのつばの、いつも脱ぐときに指の触れる部分は、日が経つにつれて、次第に珈琲色を帯びるようになった。キャップの下に見える髪は、短く刈り上げられていて、均整のとれた卵形の顔の輪郭を引き立たせていた。
マダムがリサに、どこで髪を切っているのか尋ねると、リサは、左手の指でうなじを撫でながら、
「美容院じゃなくて、アパートの近くの理容院で、男のお客さんといっしょに散髪しているんです。理容院のカットの方がシャープで、自分には合っていて、キャップを被ったときにかっこいいんです。」
と答えた。
彼女は話し方や動作に少年のような機敏さがあり、女性客でリサのファンだと話す人も何人かいた。
リサはマダムより四歳年下であった。マダムとリサとは気が合って、二人は仲の良い友だち同士のようであった。マダムとリサとだけで店を切り盛りしている時、お客様に、
「ごきょうだいですか?」
と聞かれたこともあった。
二人とも、カミヤの仕事を見るうちに、珈琲の淹れ方を覚えて、カミヤのいないときには二人のどちらかが淹れる役目を担った。
開店して三ヶ月ぐらい経って、固定客も相当の人数ついてくるようになった。カミヤは、予想していたよりも女性の固定客が多いことに気がついた。
五月になって、シモムラ氏が予告なく「カフェ・リュビ」を訪れた。
彼の来店に気がついたカミヤは、仕事の手を止めてカウンターから出ようとしたが、シモムラ氏はそれを手で制した。
「今日は一人の客として来店しとるんや。ほかのお客さんと同じようにしてくれれば、ええんや。」
リサが
「ご注文は?」
と尋ねると、シモムラ氏は、
「エスプレッソ。」
と告げた。そして彼は、代金をリサに渡すと、カミヤがエスプレッソマシンに珈琲の粉末を盛り込んでセットする様子を眺めた。
カミヤは、九谷焼の茶碗に、抽出したエスプレッソを注いだ。
シモムラ氏は、リサの差し出す茶碗を、
「ありがとう」
と一言言って受け取って、ベンチに座った。
シモムラ氏はまもなく、空になった茶碗をリサに返した。
「ごちそうさま。カミヤ君、もうちゃんと形になっとるやないか。この分なら心配なさそうや。
今日店を見て気付いたこと、一つだけ言うとくわ。お客様の中には、たまには珈琲は苦手やいう方もおいでになる。そういう方のために、一品でええから、珈琲とちゃうもんもメニューに出した方がええんとちゃうか。たとえばバナジュー。」
「バナナジュースですか?」
「そうや。初めからバナジュー目当てのお客様もお越しになるようになるかもしらんな。
わしは、今日はこれからすぐに神戸に帰らんとならんから、ゆっくり話もできへんで悪いけど、また手紙書いてや。電子メール始めたから、メールでもええよ。」
シモムラ氏は懐から軸の太いモンブランの万年筆を取り出すと、名刺の裏に自分の電子メールのアドレスをさらりと書いて、カウンターに置き、右手を高く挙げて店の扉を出て行った。
しばらくすると、店の前を、シモムラ氏の乗ったサファイア色のベントレーが、快いエンジン音をたてて過ぎて行った。
カミヤは、店の外を走り去るベントレーを眺めながら、シモムラ氏が、神戸の名士の間では、
「カフェの殿様」
という愛称で通っていることを思い出した。
第四章 白拍子
カミヤの店であるカフェ・リュビは、開店して一年半ほどの間、カミヤと、マダムと呼ばれるカミヤの夫人と、リサとの三人で営業していたが、リサに映画出演の仕事が入って、リサがアルバイトを続けることはできなくなった。
リサはその年の春に演劇学校を卒業していた。映画関係者が、卒業前の学校での演劇の舞台でリサに目を留め、スカウトして、彼女は映画の脇役を与えられた。
リサはそれから二年ほどの間、合計で三本の映画に出演した。
最初の映画は、明治時代の外交官とドイツ人の夫人の物語で、リサはその夫妻の娘の役であった。台詞は少なかったが、長身で西洋的な彫りの深い顔立ちのリサが、当時のヴィクトリアンスタイルの洋装で、国賓として来日した某国の王子とワルツを踊るシーンは、映画の予告編やポスターにも使われて、多くの人の記憶に残った。
二本目と三本目は、準主役級であった。いずれもかつて銀熊賞を受賞し、世界的に有名で映画界の大御所と目されるオガミ・アラタ監督の作品であった。二本目以降、彼女の名前は世間に広く知られるようになった。
二本目は、戦前のフランス語の専門学校を舞台にして、そこに通っている作家志望の三人の学生を描くもので、戦争直後に無頼派として知られたある作家の学生時代の実話をもとにした物語であった。リサは専門学校の学生の一人で、作家志望の三人がマドンナとして憧れるという役どころであった。映画の中で彼女は三人と対等で文学を論じ、自作という設定の現代詩を朗読した。彼女の役は演劇学校での台詞の稽古が奏功し、純粋で知的な女性をリアリティをもって好演したと評価された。
三本目は、時代物で、平清盛をめぐる、祇王・祇女・仏御前の三人の白拍子を描く物語であった。リサは仏御前の役であった。仏御前は、清盛の愛妾であった祇王のとりなしで清盛にお目通りがかなうのであるが、和歌や管弦の才で清盛の気持ちを惹き付け、まもなく祇王に代わって清盛の愛妾になった。清盛の寵愛を失った祇王と、その妹の祇女とは、世を遁れて出家した。ところが、ある日、祇王の草庵に、一人の尼僧が訪ねて来た。祇王が会ってみると、その尼僧は、清盛の屋敷を密かに立ち去った仏御前であった。仏御前は、清盛の寵愛を一身に受けて何不自由ない生活をしていたが、やがてはその寵愛も失せるであろうことを予感し、権力者の男性に依存する生き方に疑問をもって、清盛のもとから去ったのだと語った・・・このようなあらすじの物語であった。彼女は、実際に琵琶を奏でる二分間のシーンのために連日きびしい稽古に耐えた。撮影現場となった京都の平安神宮の回廊で演奏のシーンを撮り終えると、映画の音楽監督は立ち上がって彼女に拍手を送った。リサの演じる仏御前が、門前の桃の散り初めた春の曙に、白い被布に墨染めの衣を着て、自分の囲われている清盛の別宅から出立する姿は、自分の本当の幸福をもとめて歩み始める人間の強さと美しさを無言のうちに表現するものとして、批評家から絶賛された。
カミヤ夫妻はリサの活躍をマスメディアの報道でいつもフォローしていた。
リサが映画に出演するようになってから一年半ほど経ったころに、彼女は一度、雑誌の取材記事のためにカフェ・リュビを訪れたことがあった。事前に連絡を受けていたカミヤ夫妻は、リサとの久しぶりの再会を楽しみにしていた。それはリサも同じ気持ちであった。取材は、リサがプライベートに訪れる、「とっておきの隠れ家」の紹介記事のためであった。店の選択はリサに任せられたので、彼女は迷わずカフェ・リュビを選んだのであった。
久しぶりにカフェ・リュビに現れたリサは、以前のベリーショートから、肩までのソバージュの髪型に変わっていた。雑誌の発売が三月ということで、彼女は一月の寒いなか、白を基調としたフレンチカジュアルで踝まで丈のある、春物のドレスを着ていた。彼女には、雑誌記者だけでなくスタイリストとカメラクルーが一緒に来店し、予定されたリサの滞在時間は大半が彼女の撮影に費やされ、リサとカミヤ夫妻との会話は挨拶程度のほんの二言三言で終わった。リサは帰り際に、カミヤ夫妻に目で一生懸命何か訴えかけるような様子があったが、すぐにマネジャーに手を引かれるように店を出ると、彼ら一行の乗ってきたワンボックスカーに押し込まれた。
リサの慌ただしい来店から半年ほど経った初夏に、彼女の名前が芸能週刊誌を賑わすことになった。
それは、映画女優ヒビノ・リサと、映画監督オガミ・アラタ氏との不倫の報道であった。
報道によると、すでに七十歳近い年齢で妻子もあり孫も何人もいるオガミ氏と、新進の女優であるリサとが、箱根の某ホテルの玄関を二人きりで出発するところを、ホテルの滞在客が偶然に写真に撮り、SNSで発信したことが、不倫発覚のきっかけであった。SNSでは、オガミ氏とサングラスをかけたリサとがホテルの玄関を並んで出る写真に、「サングラスの女、だれ?」という言葉が添えられて、世間に拡散した。まもなく、この不倫事件は、「サングラスの女事件」として報道されるようになった。
オガミ氏は、不倫が報道されると、まもなく芸能記者のインタビューに出て、つぎのように弁明した。
「いや、お恥ずかしいことです。みなさまをお騒がせして申し訳ない。しかしですね、彼女は、こないだのぼくの映画の役を地で行ってるんですね。男性を魅了するのに実に巧みな女性です。ぼくは魔がさしたとしか言いようがない。家内には一笑されました。彼女が二人きりでドライブに行きたいと言った時に、用心しておけばよかったのですが・・・いや、面目ない。」
オガミ氏の隣には、往年の名女優であった彼の妻が、紬の着物を着て彼と手をつなぎ、何ごともなかったかのように、にこやかに付き添っていた。
オガミ氏は、前作の映画で、リサが清盛の寵愛を獲得した仏御前の役で世間の評価を受けていたことを、弁明の下敷きにしたのだった。
このインタビューは、リサに取材が来る前には、世間に広く公表された。知名度ではリサとは比べものにならないオガミ氏のインタビューで、世間はすっかり、リサが次の映画での大役をほしくて、大監督を誘惑したものと思い込んだ。
不倫報道は過熱して、SNSで拡散された写真に写っていたリサのサングラスがどこそこのブランドで、十数万円の代物だといった詮索まで報じられた。有名人のものまねを売り物にする芸人は、人目を避けるように左右を見回しながらホテルの玄関を出る老人とサングラスの若い女性とのカップルを演じて、テレビの視聴率を上げた。
リサの事務所は、初めのうちはリサがオガミ氏を誘惑したという、オガミ氏のインタビューでの発言に反論を試みることを検討していたが、そのうち事務所のほかの芸能人の仕事に差し障ることを懸念して、結局は反論に乗り出すこともなく、リサとは距離を置くようになった。
リサの次の映画への出演はキャンセルとなった。リサは、マスコミへの反論や法的手段も考えてみたものの、かりにオガミ氏の弁明を覆すことができたとしても、オガミ氏の映画界での力を考えると、自分に映画の仕事が今後来なくなることは同じであることに気が付いた。彼女は、迷った挙句、事務所や同僚に迷惑がかからないように、沈黙を通すことを選んだ。
オガミ氏の方は、その年の十一月には、事前の下馬評のとおり、文化勲章を受章した。不倫の一件は彼の名声には何の影を落とすこともなかった。ニュースは、文化勲章を受章したオガミ・アラタ氏が、羽織袴に文化勲章を首から下げた姿でインタビューに応じて、
「要するに、ぼくの原点は、弱者への共感なんです。それなくして、お客様の共感はありえません・・」
と、自分の芸術上の信念を語っている姿が流れた。
カミヤ夫妻は、一連の報道を心配しながらフォローしていた。彼らには、報道ぶりが、オガミ氏の肩ばかり持っていると感じられた。彼らは、リサが映画の世界に入って、人柄が変わってしまったというようなことは、決してないはずだと信じていた。
次の年の晩春のある日、リサがカフェ・リュビを訪ねて来た。
その日も十五時の閉店時刻になり、いつものようにカミヤ夫妻が店を片付ける準備を始めようとしたときに、黒いサングラスをかけて、豪奢な茶色の長い巻き髪を揺らせ、真珠色で光沢のあるジャケットに細身の藍色のジーンズを取り合わせた、華やかな雰囲気の女性が、扉をわずかに開き、店の中を覗き込んでから、サングラスをはずしながら店にすべり込んだ。
カミヤは、
「お客様、申し訳ございません。閉店の時間になりましたので・・・」
と言いかけて、彼女がリサだと気がついた。
来客の様子に、流しで片付けものをしていたマダムが、客席の方を振り向いた。
「まあ、リサちゃんじゃないの。」
「お久しぶりです。私のこと、覚えていて下さったんですね。」
「もちろんよ。忘れたりするもんですか。さあ、ベンチに座って。」
「よく訪ねて来たね。おれもマダムも、リサちゃんに会いたいと思ってたんだよ。」
カミヤは、店の扉に本日営業終了の札を出して、マダムは自分たちが飲むために用意してある普段使いの珈琲を淹れて、商売ものの碗でリサに渡した。
カミヤは言った。
「見たところ、元気そうで、何よりだ。おれたち、リサちゃんの出た映画はどれもちゃんと見たよ。」
リサは、淹れてもらった温かい珈琲を一口啜ると、少しためらうような表情を見せたが、やがて話し始めた。
「去年の夏以降、世間をお騒がせするようなことがあって、このお店にご迷惑がかかるようなことはなかったですか?」
「ああ、あのことで・・・うちには記者が何か聞きに来るようなことはなかったし、そもそもリサちゃんがうちで働いていたこと、ほとんど知られていないんじゃないかな。あの時の報道は、おれたちはずいぶん偏っていたんじゃないかと思ってる。」
マダムが言った。
「リサちゃん、つらい思いをしてたんじゃない?」
「そういうふうに言っていただけるのは、師匠とマダムだけです。」
リサは少しの間下を向いていたが、やがてカミヤ夫妻に顔を向け直して言った。
「お二人ならば、信用していただけると思うので、本当のことを話します。」
リサは、つらい思いに堪えながら、話しにくい話を二人に聞かせた。カミヤが細部を推測で補うと、おおむねつぎのような話であった。
その日の朝、オガミ氏は、どこで手にいれたのか、リサの自宅の電話番号に電話をかけてきた。
「今日あたり、箱根のアジサイはきれいだと思うんだ。今からぼくが自動車で迎えに行くから、いっしょに付き合ってくれるかな。君のマネジャーには、ぼくから連絡しておく。あしたの午後は君もぼくも新しい映画の打ち合わせがあるから、私も今日の夕方には東京に戻って来なくちゃならないんだ。」
リサは、相手が映画界の大御所で、お世話になった大監督なので、疑いを抱くようなこともなく、同行を快諾した。
それから小一時間して、オガミ氏の黄色いフィアットが、リサの住む東京の港区のマンションの前に止まり、リサはオガミ氏の扉を開けた助手席に乗った。
オガミ氏は、いつになく快活な様子であった。運転しながら、自分がパリやベルリンやローマで、誰それに会ったといった話や、某国の王族の別邸に招かれた話など、自分の話ばかりを独りで話した。
「中近東の王族にとってはね、日本みたいに掛け流しの温泉なんて、とんでもない贅沢なんだ。水はオアシスにしかない貴重品で、毎日摂る水分は、ぼくたちには信じがたいほど少ないんだ。それでね、ぼくが箱根の強羅の温泉旅館の話をしたらね、彼はその旅館を一週間借り切って、自家用ジェットでやって来たんだよ。ぼくも二日間そこに招待されたんだ。彼らはお酒を飲むのは宗教的に禁止だから、ぼくだけ飲むのも気が引けて、ぼくにはいい休肝日になったんだ。今日はそっちの旅館の方には行かないけどね。」
リサとオガミ氏とは、芦ノ湖のほとりのホテルのレストランで昼食を摂った。
食後になって、オガミ氏が言った。
「ぼくも七十歳が近いもんだから、若いときのようにはいかないもんで、すっかりくたびれちゃったよ。夕方まで、ホテルの部屋で休憩してから、また車を運転して東京に帰ることにしたいんだ。」
オガミ氏はいっしょに行くというリサを手で制して、ホテルのフロントに独りで行った。
しばらくすると、オガミ氏が戻ってきて言った。
「スイートルーム、うまい具合に空いてたよ。」
リサは、足を引きずるように歩くオガミ氏を気遣いながら、予約された部屋に向かった。
部屋に入ると、ダイニングの食卓に、氷がいっぱいのワインクーラーが据えられていて、そこにシャンパーニュが一本冷やしてあった。
オガミ氏は、ソファーに座って言った。
「せっかくだから、ぼくが特別の演技指導をしてあげよう。これは今までどんな大女優にも教えたことがないことなんだけど、次の役には大いに参考になるはずだ。それはね、さっき話した中近東の王族から聞いた、ニューヨークの金持ち相手の玄人の女性が、どうやって男性の気を引くか、という話が元になっているんだけれど、その話にぼく自身の解釈を加えて設定したシーンだ。次の作品では、まさにこういうシーンをやろうと考えている。だから、今日はその予行演習だ。しっかり勉強するんだぞ。」
オガミ氏はそう言いながら、ソファーから立ち上がると、ダイニングの椅子を応接セットから離れた部屋の隅にひきずって来て、そこに座った。そこで演技の監督をするというのであった。
「いいかね、小道具はこれ。」
と言って、オガミ氏はシャンパーニュ用のフルートグラスをリサの前に置き。冷えたシャンパーニュをグラスの縁ぎりぎりまで注いだ。
「今から、演技のストーリーを話すから、よく理解したうえで、それからぼくがスタートと言ったら、演技するんだよ。おおまかに言えば、相手が自分の体のどの部分に魅力を感じるか、試すというストーリーだ。普段世間の目から隠されているいろいろな部分を、そのままはっきりと見せることはしないで、なるべく仕草だけで示唆して、相手に意識させるつもりでやるんだ。相手の意識するものをはっきりと見せてしまえば、相手の想像力はもうそれ以上膨らまなくなって、あとは幻滅への下り坂だ。
シーンは、あるお屋敷のパーティーで、場所はこのホテルのロビーぐらいの大広間だ。相手は、自分がいる場所の向かい側のソファーに座っている君が気になって、視線を向けている、という設定だ。
まず、君はグラスを目線まで上げてから、シャンパーニュを一口飲む。グラスを飲み干してから、グラスから唇を離して、口を緩く開いて、白い前歯を見せる。見せると言っても、ちょっとだけでいいんだ。グラスから唇を離す一瞬、そこが大事だからね。その次は、グラスを机の上に置くと、左の肘を上げて、手のひらを頭の後ろに回すんだ。そうすると、脇が自然に開く。それから、胸の下で軽く腕を組んで、両腕を鎖骨の高さまで持って行く。それが済んだら、今度は膝と膝とをくっつけて、膝から下を八の字に開く。それで左の膝を右の膝の上にゆっくり擦るように上げてゆく。最後に、相手以外の人の目につかないように、履いている靴を片方ずつ脱いで、靴から足をゆっくり抜くんだ。
そして、今言った仕草をしながら、目は相手の目をしっかりと、ヒョウの目のように見据え続けるんだ。ヒョウの目というのは、相手が自分のどこに興味を示したか、一瞬の表情の変化を見逃すまいと狙っている目だ。相手がちょっとでも興味を見せた場所を、誘惑の武器にして戦うためだ。相手の目というのは、実際にはカメラのレンズだが、今日はぼくの目がレンズの代わりだ。わかったかね。」
リサは真剣なまなざしで、オガミ氏に答えた。
「はい、やってみます。」
「ダメ出しが出るたびに、何回でもやりなおす覚悟はあるか?」
「あります。」
リサはきっぱりと答えて、頭の中で、オガミ氏が語った振り付けを懸命に反復した。彼女は、自分の体を商品の見本として見せる演技など、全くもって好みではなかったが、プロの女優としてそういう演技が必要とされるのであれば、やり遂げるまでだ、と決意した。
「さあ、スタート!まずはシャンパーニュを一口飲んで、唇を少し開くところだ・・・そうそう、・・・それで、・・・カット!
君、動作が速すぎる。もっとゆっくり。それに目がカメラをにらんでないよ。」
オガミ氏はシャンパーニュを再びグラスに注いだ。
「いいかい、スタート!そうそう、いい調子、それで・・・」
オガミ氏は、立ち上がると、テンポの遅い曲を指揮するオーケストラの指揮者のように、両腕をまるで何かの舞踊であるかのように振った。彼は、映画撮影の現場で、映画の見せ場になるような重要なシーンでは、いつもこのように立ち上がって、指揮者のように両腕を振るうのであった、
「カット!惜しいな。口の演技から脇の演技に移るときに、動きが一度切れてしまっている。」
オガミ氏はシャンパーニュを再びグラスに注いだ。
リサは、お酒は強い方ではなかった。そのことは、何度か宴席に同席していたオガミ氏はよく知っているはずだった。
オガミ氏がダメ出しをするたびに、グラスにシャンパーニュが注ぎ足された。リサは、三杯ほど飲んだところで、頭が朦朧としてきた。
「そうだ、膝が八の字になったとき、足の先は足首よりも内側になるようにするんだ。そのまま、左腕を伸ばして手の指で左の靴の踵を、次に右腕を伸ばして同じように右の靴の踵をはずすんだ。」
やっと最後の靴を脱ぐところまで、リサは何とか通しで演じ終えた。
オガミ氏が言った。
「すばらしい。ぼくの言うとおりに体を動かしているだけのはずなのに、まるで君がこういう仕草にいつも慣れているかのように、リアルに見える。ぼくが振り付けた演技のはずなのに、ぼくは君にすっかり誘惑されちまったよ。大した演技力だ。今までいろんな女優を見てきたけれど、君の筋肉の動きは天才のものだ。すばらしい。」
リサは、普段オガミ氏が撮影現場で辛口の批判を誰彼かまわず浴びせるのに慣れていて、オガミ氏は自分のことを褒めすぎているという気がした。
オガミ氏は続けて言った。
「では、次のレッスンに移ろう。君、風呂場で、洋服の上からでいいから、バスローブを衣装として羽織るんだ。バスローブを着て、それから、このハイヒールを履きなさい。そしたら、次のシーンを説明するから。」
オガミ氏は、持ってきた鞄から、赤いエナメルのハイヒールを一足取り出した。
リサが後で考えると、オガミ氏がハイヒールを持ち歩いていることは、奇妙なことであったが、彼女はアルコールで頭がくらくらしていて、その時は気が付かなかった。
リサは、オガミ氏の言うとおり、風呂場にあったバスローブを羽織った。そして、貸し与えられたハイヒールに足を入れた。ハイヒールはリサの足よりも一回り小さく、リサは苦労して足をねじ込むようにハイヒールの中に納めたが、彼女の記憶はそのあたりで曖昧になった。リサがぼんやりと覚えているのは、そのあと風呂場から出ると、オガミ氏が扉の前に立って自分を待っている姿であった。
それからどれだけ時間が経ったのであろうか、リサは意識を回復した。それはベッドの上であった。彼女は、自分が昼の洋服の上にバスローブを着て横たわっていることに気が付いた。彼女は、自分の着衣に乱れがないことをしっかりと確認して、少しだけ安心した。
彼女が枕元のスタンドを点灯すると、隣にはまばらな髪に赤ら顔の老人が、バスローブの胸をはだけて大きないびきをかいて眠っていた。もちろん、それはオガミ氏であった。部屋のカーテンは開いたまま、外には月光に照らされた芦ノ湖の湖水が見えていた。腕時計を見ると、午前一時であった。リサは、自分が何時間もの間、月光に白く照らされて横たわっていたであろうことを思ったが、オガミ氏との間で何があったのかの記憶は、風呂場でハイヒールを履いて扉を開けたところからは失われていた。彼女は二日酔いの頭痛と吐き気をこらえながら、水を求めてダイニングに向かった。
ダイニングの食卓の上には、オガミ氏がルームサービスを注文したらしく、スープ皿やメインディッシュの皿が、どれもきれいに平らげられて、乱雑に置かれていた。リサはまったく食欲がなかったが、自分の食事が注文されていた様子がないことに気が付いた。
リサは、ダイニングに付属するキッチンの蛇口を開いて、水を一杯飲んだ。
彼女はそれから、月が湖水の西の端に沈む早朝まで、まんじりともしないで、窓の景色を眺め続けていた。彼女は、おぼろげながら、風呂場の前で自分を待っていたオガミ氏が、自分を抱き上げようとして、リサの体の重さを支えきれず、床に尻もちをついたことを辛うじて思い出した。
朝五時になると、オガミ氏はぱっちり目を覚ました。
「さあ、もう出立だ。早く支度をしよう。人目に触れるとまずい。」
リサは化粧を直す時間の余裕も与えられず、腫れた目をサングラスで隠して、オガミ氏と客室を出た。
「腰が痛いんだ。ゆっくり歩いてくれ。」
オガミ氏は、腰から下を引きずるかのような前傾の姿勢で、玄関を出て車に乗り込んだ。
帰りの車の中では、二人の間に会話らしい会話はなかった。
リサのマンションの前で、オガミ氏は車を停め、急に彼女に哀願するような視線を彼女に向けて言った。
「君、これだけはお願いだ。君はわかっているだろうけど、きのうの晩、ぼくは、その・・・」
オガミ監督が不自然に口ごもった。
「その・・・もう・・・赤ん坊みたいに君にしがみついたままで・・・腰も痛くなっちまって・・・結局のところ何にもできなかったっていうことは、絶対に口外しないでほしい。そんなことを人に知られたら、ぼくは生きてゆけない。」
リサは、オガミ氏が言おうとしているのは、自分が男性としての役を果たしえなかったことを、内密にしてほしい、という意味であることに気が付いた。
リサは、思わずオガミ氏の頬を平手打ちにした。
赤ら顔のオガミ氏の頬に、リサの掌の跡がさらに赤く加わった。
リサは、何も言わずに助手席の扉を開けて車を降りた。オガミ氏はがっかりしたような表情で、運転席から手を伸ばして扉を閉めると、車を急発進させて去って行った。
リサが自宅に戻ってしばらくすると、マネジャーから電話がかかり、午後のオガミ監督との打ち合わせはキャンセルになったと連絡があった。
ここまで、途切れ途切れに話を続けてきたリサは、カミヤに言った。
「私も不注意でした。オガミ監督は、年配で社会的地位のある方なのに、こんなことになるとは思いもよりませんでした。それに、オガミ監督を尊敬していただけに、悲しくなりました。私は、弁護士を立てて戦おうか、迷ったんですが、事務所は及び腰でした。それに、たとえ反論が世間に信じてもらえたとしても、映画の仕事はもう来ないことがわかったものですから、事務所や同僚に迷惑をかけないように、何も言わないで事務所を辞めて、映画の世界から消えることにしました。」
カミヤもマダムも、リサの話に言葉を失っていたが、カミヤはようやくつぎの一言を喉から絞り出した。
「つらかったね・・・」
マダムが続けた。
「さぞや話しにくかったでしょう。オガミ氏の策略にはまったのね。私たち、そんなことじゃないかって、話していたのよ。私たちでよければ、相談してくれればよかったのに。」
カミヤも言った。
「世間が信じなくたって、おれたちたちは信じる。おれたちも、前に話したことがあるけど、事情があって故郷に居られなくなった過去があるから、人の噂がどんなものかっていうこともわかる。映画の世界のことはわからないけれど、おれたちはリサちゃんの味方だ。」
リサが言った。
「私はあの一件の後で、舞台演劇の仕事をしたいと思って、いろいろ探したんですが、今のところ色よい返事をいただけていないんです。それから、私は自分の演技に自信はあるんですが、私が映画で準主演をさせてもらえたというのは、私の演技が評価されたからでなくて、私の容姿が彩りに使われただけなんじゃないかという気がしてきたんです。」
三人のそばにある水壺に活けられた桃の枝は、花びらを散らし始めていた。リサは床に落ちた紅い花びらに目を遣った。
三人の間で沈黙がしばらく続いた。
その重苦しい沈黙を、リサが破った。
「それで、今日こうしてうかがったのは、お願いがあるからなんです。私をこのお店で、またアルバイトとして使っていただけないでしょうか。前にこのお店で働いている時は、一日一日が、舞台を踏んでいる実感がありました。演劇の仕事は、もうめぐって来ないかもしれませんが、このお店で前みたいに、毎日精一杯舞台を務めたいと思ったんです。勝手なお願いってことは、承知の上です。」
リサは深々とカミヤ夫妻に頭を下げた。
カミヤは、マダムと目を合わせながら、言った。
「リサちゃんならば、アルバイトは大歓迎だ。大歓迎だけど、」
カミヤは一旦そう言ってから、言葉を選びながら続けた。
「今のリサちゃんの生活感覚と合わないようなことがあれば、続かないんじゃないかと思うんだけど、どう?」
「アルバイト料は前と同じでいいんです。女優の時は事務所から給料をもらっていたんですが、家賃とか、おつきあいの飲食代とか、衣装代とか、それからお稽古の月謝とかが天引きされて、自分で自由になるお金は学生の頃と大して変わりませんでした。それに、もう港区のマンションは引き払って、前に住んでいた鐘ヶ淵で、前と同じようなアパートを見つけて、先週引っ越したんです。それとも、やはり私ではお店にご迷惑がかかるでしょうか・・・」
カミヤ夫妻は激しくかぶりを振った。
「とんでもない。おれの方で要らない心配をして、悪かった。アルバイト、うちの店でよければ、ぜひ来て下さい。準備もあるだろうから、一週間後からでどうだろう?」
「私、あしたからでも働きたいんです。」
「あしたから?うちはそれでいいけど。」
「あしたの朝七時に、前みたいに来てもいいですか?」
「うん、今うちの店には、アルバイトの女の子が二人来ているんだけど、朝の早番の時間には二人とも都合が合わなくて、どうしようかと思っていたんだ。じゃ、早番でお願いするよ。」
「それでは、よろしくお願いいたします。前のときよりも、もっとがんばります。」
そして彼女は、この店に入ってきてから初めてにっこり笑って、カミヤ夫妻に頭を下げると、嬉しそうな様子で帰って行った。
翌朝七時少し前に、リサはカフェ・リュビに出勤した。
カミヤは、リサの身なりが昨日からは一変していて、以前の自分の見慣れた姿に戻っていることに気が付いた。彼女の被った紺色のキャップのつばには、カミヤに見覚えのある珈琲色の染みがあった。
リサは店に入ると、カミヤに会釈して、慣れた口調で挨拶した。
「師匠、おはようございます。掃除、始めます。」
カミヤは、笑顔になって、前の晩にマダムといっしょに考えたとおりの挨拶の言葉を、芝居の掛け声のような調子で返した。
「リサちゃん、お帰り!待ってました!」
彼女は、カミヤに一瞬ほほえみを返すと、前と同じように、店の奥に立てかけてある箒を取ると、水壺に活けられた枝から散って床に落ちた桃の花びらを掃き始めた。
彼は、掃除をする彼女の敏捷な動作を見て、彼女が前に働いていた時とまったく変わりがないことを確認した。彼は、リサはこれならばこの店でまた続けてゆける、だいじょうぶだ、と確信した。
リサは再びカフェ・リュビで働き始めてから三ヶ月後、アルバイト従業員からこの店の専従の従業員になった。
それから間もなくして、インターネットのニュース速報に、世界的大監督オガミ・アラタ氏が急逝したとの記事が掲載された。箱根の温泉旅館の風呂場で倒れて、そのまま意識が戻らなかったという報道であった。その晩のテレビには、ニュースに故オガミ氏の生前の映像が流れて、その逝去を惜しむ各界の著名人の声が紹介され、臨時番組として故人が監督した映画作品が上映された。それからまもなく、芸能界を挙げての盛大な葬儀が、カフェ・リュビにほど近い、築地本願寺で営まれた。
遅番のアルバイトの女性が出勤して来ると、リサに言った。
「今、築地駅から来たんですけど、今日は本願寺の前に報道関係者が大勢来ていて、芸能人が続々とお寺の門を入ってゆくのを取材してました。報道のヘリコプターも飛んでます。オガミ監督のお葬式があるみたいですね。」
カミヤは、その話を聞いて、リサがどう思うか、はらはらして見ていた。その子の話はそれ以上続かず、リサの表情にも変化はなかった。
カミヤは、その子が買い出しで出かけたところで、リサを店の隅に手招きした。
「ごめん、あの子、何も知らないもんだから・・・。」
「私、気にしてませんから。」
リサは、今は店の客席が空になっていて、カミヤと多少の話ができる時間がありそうなことを確認してから、続けた。
「私もさっき買い出しに表に出た時、お寺の向かい側を通りました。映画の世界は、もう私とは関係のない世界です。あの世界では、あの一件はとうの昔の話で、覚えている人も、もうそれほどいないでしょう。
実は、私がこの店の専従社員になって半月ぐらい経ったころに、オガミ監督から手紙が届いたんです。それには、
『君が沈黙を守ってくれたおかげで、文化勲章の受章ができたのだから、内心感謝している、君が沈黙を守ってくれたのは、ぼくへの愛情だと思っている』とか、
『あの時に君の演技をほめたのは本心だ』
とか書いてありました。
手紙の最後には、
『映画の仕事に戻る気があれば、ぼくの秘書に電話をかけてくれ、世話をするように言ってあるから』
とも書いてありました。」
カミヤは尋ねた。
「それで、返事はしたのかい?」
「ご自分の言うことはまわりが聞いてくれてあたりまえみたいな、駄々っ子が書くような手紙でしたから、まともに取り合う気はしなかったんですが、返事をしないと、私を訪ねて来たりして、このお店に迷惑がかかるようなこともあるといけませんので、
『師匠のもとで修行の身ですので、今後ご連絡はご容赦のほどお願い申しあげます。』
って一行だけ書いて、返事を出しました。」
「じゃ、秘書の方にも連絡しなかったんだね。」
「私は、ここで毎日舞台を務めていますから、ほかのお仕事は一切お受けいたしません。」
そのようにきっぱりと話すリサの目は、カミヤには明るく輝いて見えた。
リサは、カミヤへの話に付け加えて言った。
「そうだ、あのときに世間で取り沙汰されたサングラスの話、しましたっけ。あれはブランドものでもなんでもなくて、前のアルバイトのときに百円ショップで買ったものだったんです。」
彼女はそう言うと、パンツの後ろのポケットに無造作に差してあるサングラスを取り出してカミヤに見せて、にっこりと笑った。それから、またそれをポケットにねじ込むと、何事もなかったかのように自分の持ち場に戻って、いつもの笑顔で、店に入ってきたお客様の応対を始めた。
第五章 エスプレッソの客
その日は五月のよく晴れた土曜日で、屋外を散歩するのには快適な気候であった。
テンドウは、亡き妻ヒサエの三回忌を築地本願寺で行った帰りであった。独りで寺での手続きと儀式とを終えてから、彼は黒ネクタイをはずして、上着と共に紙の手提げ袋に突っ込むと、築地の街をあてもなく散歩することにした。
テンドウは妻のヒサエを心不全で突然亡くしたのであった。
テンドウにとっては、三十年近く連れ添った相手であった。テンドウは、あまりに思いがけない突然のことで、ヒサエが自分より先に永遠の世界に帰って行ったことを悲しむ気持ちさえ起きなかった。彼にわかったのは、彼女が先になり、自分が後になった、単にそういうことだということだけであった。ヒサエは、この世では体が不自由になって苦労をしたが、今はその苦労から解放された世界に住んでいるのだ、と思った。しかし一方で、テンドウは、涙の出て来ないのは、よほど自分が彼女への愛情が薄かったのかもしれないとも思った。自分が何でも彼女の言うなりの形になってきたことは、実は彼女との関係を変えることに絶望した、捨て鉢な行為だったのだろうか、何か自分にはあるべくして欠けたものがあったのではないか、ヒサエは、本当は幸せではなかったのではないか・・・このような思いがテンドウを責めた。
そのようなことを考え続けながら歩き始めて、彼は喉が渇いていることにようやく思いを致した。
彼は通りかかった左の路地を入ったところに、カフェなんとかという黒い立て看板が出ていることに気が付き、その店に入ることにした。
「カフェ・リュビ・・・ルビーのカフェ、か。」
彼が店に入ると、正面のカウンターで、背の高い役者のような男がエスプレッソマシーンの前で珈琲を淹れる作業をしていて、その隣には小柄な女性が来客の対応をしていた。
テンドウは、冷たい飲み物でも飲もうと思って店に入ったのだが、ここは珈琲の名店にようだから、氷の入ったものではなくて、熱い珈琲そのものをしっかり味わったほうがよいという気がした。喉が渇いた分は、あとで自販機で水でも買って補えばよいと思った。
「エスプレッソをください。」
「ありがとうございます。三百六十円です。」
テンドウは店のベンチに腰掛けて注文のエスプレッソができるのを待った。
テンドウの前の客は、カフェラテを注文していた。
男の店員は、珈琲の粉を、取っ手の付いた金魚すくいの道具ほどの大きさの器具に盛ると、版画の馬連のようなもので粉を固め、エスプレッソマシーンにかけて、エスプレッソを抽出した。そして、それを九谷焼と思われる大きめの湯飲み茶碗入れると、今度はその上からあらかじめ熱せられていたミルクを注ぎ込んだ。ミルクがエスプレッソと混ざり合いながら、渦を描いているのがテンドウのいるところからもよく見えた。
テンドウは、その様子を眺めながら、かつて自分がヒサエに送った現代詩を思い出した。彼は大学の文芸サークルで別の大学の文芸サークルにいたヒサエと知り合って結婚したのであった。
わたしたちが生まれる前の世界は
ちょうど黒いエスプレッソに白いミルクが注がれたときのように
あたかもあなたとわたしとがこのように結び合っているように
存在と不存在とがお互いを求めつつ
一つであったにちがいない
テンドウとヒサエとが出会ったのは、彼らが大学生の時であった。彼は文芸サークルに所属していて、現代詩を書いたり、英語の詩の翻訳をしたりしていた。ヒサエは、彼の大学の近くにある女子大学で同じく文芸サークルに所属していて、彼らは両大学の文芸サークルの合同コンパで知り合った。
テンドウとヒサエとの交際は、お互いの書いた文のやりとりで続いた。テンドウは、せっせと現代詩を書いては、ヒサエに送った。
テンドウは大学を卒業して東都電鉄に就職したとき、ヒサエもまた大学を卒業して外資系の金融機関に秘書兼ドイツ語の通訳として就職した。
彼らは就職して二年後に結婚した。
結婚後は、二人ともそれぞれの仕事が忙しく、平日に顔を合わせるのは朝食の時間だけであった。休日は、それぞれの休息のため朝遅くまで起床せず、午後はそれぞれが自分の読みたい本を読んで過ごすことが多かった。それに、テンドウは住宅販売のために、休日出勤することも多かった。
ヒサエは家事のなかでは洗濯を好み、どんなに疲れていても毎日自分の気に入った方法で二人の衣類を洗濯しないと気が済まなかった。テンドウは、掃除と食器の後片付けを担当した。
テンドウにとってヒサエは、文通していた時と、お互いの距離がほとんど変わっていないと感じた。テンドウがヒサエの手を握ろうとしたことがあったが、ヒサエは電撃を受けたように手を引っ込めるのであった。二人とも忙しくて子供を持つことには関心が向かなかったが、実際そのような生理的な可能性があり得ないのであった。
テンドウは、文芸作品によく表現される女性の官能性など、全くのフィクションである、と自分の中で整理した。彼の整理によると、女性の官能性は、男性の勝手な妄想の産物にすぎず、この世のどこにも実在するものではない。実在すると見えるのは、女性が演技として行うにすぎない。結局、男性の一人芝居があるだけだ・・・彼は、ヒサエが毎日乾燥機をかけてくれる自分のベッドの中で、体を何度も反転させながら、自分にそのように言い聞かせた。
彼としてはそのように整理をつけたつもりになっていたので、他の女性を求めようという気も起こらなかった。万一相手に演技をさせるようなことになれば、それは相手に気の毒だとさえ思った。彼は会社で同僚が女性関係の武勇談を語るのを聞く機会が何度もあったが、自分には共感が起こらず、どう相槌を打ってよいものか、見当がつかなかった。
それでいて、テンドウは、自分の官能性がフィクションではないことを持て余した。彼は、官能性とは、生まれる前の世界での全能感を、この世で曲がりなりにそのレプリカとして再現するものであると考えた。それであれば、生まれる前の世界に戻れば、言い換えれば、死後の世界に行けば、その時は官能性が全能感のもとに十全に満たされるはずだと思った。そうすると、自分の人生は、死への待合室で、来たるべき完全なる官能性を待つあり方しかないと思った。
テンドウは、このように思ってからは、黙想を独習して日課とした。生きながらに生以前すなわち死後の世界と扉一枚を隔てて座ることが、自らの官能性を管理するうえでの最善の方法と考えたからであった。
ヒサエは、テンドウが、休みの日に自室にじっと籠もっていることを歓迎した。テンドウが、一人で旅行に行ったり、本屋に出かけたり、学生時代の友人と会ったりといった自主的な行動をやめて、ヒサエの管理可能なテリトリーで、ぬいぐるみ人形のようになって存在することに満足を感じた。ヒサエにとっては、テンドウがそのようになったことは、自分への愛情の証であり、テンドウをそのようにしておくことが、自分のテンドウへの愛情の証であると信じていた。そして、テンドウが自分以外の社会での生活のために費やす時間を最小限にして、自分の見えるところにテンドウが所在することを常に望んでいた。テンドウの交際範囲は年々縮小し、三十代になると、正月の年賀状は十通も来なくなった。
若い時分からこのような生活に入っていたテンドウは、ヒサエが倒れてから、会社を定時退社する生活に入ることにさしたる抵抗は覚えなかった。テンドウは、それまで会社生活と妻の傍での生活とを共存させるために、具体的には時間的なやりくりのために、毎日苦労していたが、妻が倒れたことによって、会社には定時に退社する理由を明確に説明できるようになり、その分テンドウの気は楽になったというのが本音であった。ヒサエは、倒れてから外資系企業の仕事を辞め、自宅でリハビリテーションをする生活に入ったが、彼女は以前よりも明るくなり、夫に対して青筋を立てて怒ることも少なくなった。テンドウは、妻に代わって、別々の部屋にある二つのベッドに、毎日乾燥機をかけた。そして、彼は自分の人生をすっかり達観したつもりになり、死というゴールに到着するまでの待ち時間として毎日を暮らした。
テンドウはこのように回想しながらエスプレッソを待っていたが、急に、彼は、ヒサエがつぎのように話す声が聞こえたように感じた。
「黒いエスプレッソに、黒いエスプレッソを注いだら、あのような渦にはならないわね。」
テンドウは、ここ数日、ヒサエとの関係の誠実さについて、自分を責めていたが、その言葉ではっと気が付いた。
「自分とヒサエとの関係は、そもそも普通の男女の関係ではなかったのだ。磁石のプラスとプラスとが、あるいはマイナスとマイナスとが、向き合って同じ屋根の下で暮らしていたのだ。彼女は自分が彼女と同じであることを当然と思い、自分も彼女と同じであることを当然と思っていた。それは自分が二人いていっしょに住んでいたようなものだ。二人のどちらにも責任はない。ただこのことに気が付くのに時間がかかりすぎたのだ。二人とも、それぞれが独りぼっちだったんだ。ヒサエは、最後まで独りぼっちで死んだんだ。」
テンドウは、急に自分の目から涙があふれるのに気づいて、急いでハンカチで目頭を押さえた。
「エスプレッソ、お待ちどおさまでした。」
カウンターに、テンドウのエスプレッソが、元は酒杯であったと思われる、背の低い小さな器に盛られて準備されていた。
テンドウは器とチェイサーの水の入ったグラスとを受け取ると、エスプレッソに口をつけた。
彼は、雑物の一滴も入らないエスプレッソの純粋で強い苦さを、少しずつ味わった。
エスプレッソを啜りながら、テンドウは、
「ああ、ヒサエもおれも、純粋だったことはまちがいがないな。お互いに相手の強い苦さに耐えているような人生だったもんな。」
と思った。
テンドウはエスプレッソを五口ほどで飲み干した、そして、グラスの水を器に注いで、底に残った珈琲をきれいに洗ってその水も味わった後、表れた器の底の模様を眺めた。そこには、能の「高砂」の詞章の冒頭の一部が小さな毛筆で書かれていた。
心に少し余裕のできたテンドウは、店の中を見渡した。壁には牡丹と思われる花が日本画の手法で描かれ、店の奥には、赤い宝珠の形の文様が描かれていた。店の真ん中には、大きな壺が畳の上に据えられていて、背のすらりと高いあやめが数本活けられていた。
テンドウは器をカウンターに返しながら、女性店員に言った。
「いいお店です。ここに来てよかったです。」
「ありがとうございます。またぜひお越しください。」
男性店員が、テンドウの後ろ姿に、
「またお待ちしてます。」
と声をかけた。
男性店員はカミヤ、女性店員はマダムで、二人はテンドウが店から出ると、つぎのように会話した。
「今のお客様、エスプレッソをお出しする前には泣いていらっしゃったけど、何かあったのかしら。」
「店に入って来られた時は、さびしそうなお客様だと思ったけど、店を出る時は多少元気になったみたいで、よかった。」
店を出たテンドウは、もういちど自分の人生をやり直す気になっていた。死を待つために費やすのには、人生はあまりにももったいないと思った。そして、それを気づかせてくれたのが、妻のヒサエで、ヒサエの声と出会わせてくれたのが、あのカフェ・リュビだと思った。
それからテンドウは、休みの土曜日の午前十一時ごろには、カフェ・リュビに通うようになった。彼が店で頼むのは、いつもエスプレッソであった。カミヤもマダムも、すぐにテンドウの顔を覚え、彼が店に現れると、
「こんにちは。エスプレッソですね。」
と声をかけるようになった。
テンドウと同じ年に東都電鉄に入社した同期は二十人ほどであった。彼は同期と共に、まずは全員が体験を義務づけられている、電車の車掌としての勤務を二ヶ月経験してから、不動産事業部に配属された。
彼は以後現在に至るまで、不動産事業部からよその部署に異動したことはなかった。
彼が入社したころ、電鉄系不動産会社は、それぞれの運営する鉄道の沿線での住宅開発事業が主力業務であった。それと共に、東京都心部における高層住宅の供給に、各社はこぞって参入していた。
彼が新入社員の時に担当したのは、高層住宅であった。東都電鉄が高層住宅用地として仕入れるのは、いわゆる高級住宅地の邸宅跡地が多かった。東京都心の高層住宅を購入する客層は、比較的高い所得があって、日中は多忙で職場との往復時間の節約を望み、その一方で社会的地位のある人々が多く住んでいるような場所に自分も住んで、自分もそういう人々の一員として暮らしたいと考える人々であった。このような客層は、当時は人数的に限られているうえ、海外経験がある人も多く、高層住宅業者としては、欧米の集合住宅に遜色のない、現代的で高い品質の建物を供給する必要があった。
彼が最初に担当した物件は、東京の三番町に計画されたものであった。その物件の幼稚は、旧華族の屋敷跡の六百坪ほどの土地であった。
東都電鉄の高層住宅事業の方針は、供給する物件が土地柄に適合し、地域と融合して長く地域の良好な環境の維持向上に資するような物件の供給であった。そのような条件に合わない物件は、地域の環境を劣化させ、その物件自体の評価も落とし、将来的に物件価値を下げると考えられた。そのため、東都電鉄は、自社の住宅のブランドの維持向上のため、厳しい設計条件を設定していた。
テンドウは、図書館や法務局に通って、その土地の来歴を調べた。三番町のその土地は、江戸時代には上級旗本の屋敷であり、その旗本は、代々京都所司代や長崎奉行を勤める高い格式の家であった。明治になって、旧堂上公家であった某家がこの土地を入手した。その家は、明治維新の時に朝廷と薩長との間を斡旋する仕事に従事した功績で、伯爵に叙せられた。戦前にはこの土地に純和風の建物があり、皇族方も行啓されて雅楽の会が催されることもたびたびであったが、この建物は戦災で焼失した。戦後は、旧伯爵の一族の三つの家が敷地を分けて三件の住宅を建てて住んでいたが、それぞれが財産税や相続税を初めとした困難な経済問題に直面した。そのため、三つの家が同時に東都電鉄に土地を売却することとなり、竣工後には高層住宅の住戸のうち三戸を受け取る条件で契約締結に至った。
新入社員であったテンドウの所属する不動産事業部は、当時六十歳を超えた専務取締役が統括していた。彼は戦前の大連で生まれ育ち、日本に引き揚げるまで、純西洋式の集合住宅に住む経験を持っていた。戦前の大連や上海など外国人が集まる大都市では、もちろん少数ではあったが、富裕層向けの本格的な高層住宅が建設されていた。彼は戦後東都電鉄に入社して、不動産事業の担当になると、戦前に高層住宅の設計に携わった経験があって、日本に引き揚げていた技術者を訪ね歩き、当時の高層住宅の構造、意匠、設備にわたる設計の基本条件を収集し、それを日本での高層住宅に応用するべく整理を実施した。東都電鉄の高層住宅事業は、彼の集積し整理した設計条件を標準として展開された。竣工した建物は、戦後日本で流行したモダニズムの装飾を排した外観と異なり、装飾的要素を贅沢に採用した物件で、廊下やロビーといった共用部分は、他社の物件と比べるとやや過剰に思えるほどの余裕をとったものであった。他社の目から見れば、もっと共用部分を縮小すれば、売却可能な住戸が一、二戸捻出できるはずであったが、欧米の集合住宅の品質以上をめざす東都電鉄としては、そこは譲れないところであった。
テンドウは、竣工間近の三番町の物件を販売する業務も担当した。販売事務所には、国会議事堂に近い土地柄から、政治家で購入を希望する人も多く訪ねて来た。
ある高齢の購入希望者は、パンフレットの完成予想図を見て、
「この完成予想図は、私が戦前の上海のイギリス租界で見た集合住宅にそっくりだ。外壁に小口の濃い茶色のタイルが貼ってあって、バルコニーが白に塗られているところや、玄関がホテルみたいに広いところは、実によく似ている。上海の集合住宅は、玄関の前に旗竿があって、ユニオンジャックが翻っていて、住んでいたのはイギリス人と大富豪の中国人だった、今度の建物にはさすが旗竿はないんだろう。なつかしくてなって、この物件が気に入った。」
と話した。
その後、テンドウは、独学で建築の基礎知識を身に付け、やがて自社物件のための設計標準を整備する業務を担当するようになった。当時は東都電鉄が高層住宅の供給を開始してから二十年近くが経過しており、彼の仕事は、過去を含めた個別物件の事業過程で得られた知見を設計標準に反映して、日々改善してゆくことであった。
こうしてテンドウは、物件の商品企画の第一人者になった。
しかし、彼が三十五歳になった年に、彼の夫人のヒサエがくも膜下出血で倒れた。夫人は一命をとりとめたが、若干の後遺症が残り、一人では十分に家事を行うことは無理になった。
テンドウの両親もヒサエの両親も、すでに他界していた。彼らには子供はいなかった。
彼は会社に事情を話して、商品企画の第一線から離れた。日中は家政婦に来てもらい、彼は定時に退社して家事を行う生活に入った。
テンドウが会社でサラリーマンとしては異例の思い切った発言ができたのは、このような彼の境遇が背景にあった。彼にとって、会社人生で、もっと言えば人生で何か成功するということは、まるで眼中になかったので、自分の利害を考えて発言を控えるような必要性を感じなかった。だからといって、テンドウは捨て鉢になって出まかせを言ったわけではなかった。テンドウは、自分の思ったことに忠実であろうとしたのだった。テンドウの発言を聞いた人が実際に行動に移すことが多かったのは、彼の自己防衛のない純粋な信念が伝わったからであった。しかし、それもテンドウにとっては、この世の仮の事象の一つにすぎず、特に感興を催すこともなかった。
彼のいたポストには、彼の同期で、彼とは親友であったクマガイという男が就いた。クマガイは、鉄道畑で育ってきており、不動産事業はまったく初めてであった。
テンドウは、その後も商品企画のセクションに席があり、部門の広報対応や情報セキュリティ対応など、どの組織でも誰かがやらなくてはならない総務的な仕事を担当し、時々若い人から実務的なアドバイスを求められるのに対応した。空いた時間には、建築関係の新聞や雑誌から同僚の役に立ちそうな記事をピックアップして電子メールで周知する仕事に従事した。
テンドウの表向きの仕事はこのようなものであったが、彼には会社の同僚に知られていない、もう一つ重要な仕事があった。
それは、クマガイへのアドバイザーとしての仕事であった。
クマガイは、いわゆる親分肌で、目下の面倒見がよかった。この会社の多くの人がするように、上司の顔色を部下の都合より優先させるようなことはなかった。それでいて、クマガイの仕事ぶりは、上司から信頼されているのであった。
クマガイは、自分一人が理解したり考えたりできることは、限界があると、はっきり自覚していた。そのため、自分が判断に迷うような事態に遭遇したときは、その分野に詳しい人に一度は尋ねることにしていた。彼の考える、その分野に詳しい人というのは、たまたまその時にその分野を担当している人や、その分野を担当する組織の責任者ではなくて、その分野の仕事を自分の職分と心得ている人であった。その分野を自分のライフワークとしていて、自分の所属する組織や現時点の担当職務に関わらず、一家言を持っている人であった。クマガイは、たいていの分野では、そういう人がごく少数ながら会社のなかにいることを、感覚的に知っていた。彼はそのような人のことを、「プロ」と呼んでいた。彼は、そのプロが自分よりも職位が上であろうと下であろうとこだわることなく、正直に自分の扱いかねている案件の問題点を話して、アドバイスを受けるのであった。クマガイは、自分が順調に組織で出世していることに関して、他の人にはない秘訣があるとすれば、この一点だと思っていた。
そのような意味で、クマガイにとって、テンドウは、高層住宅の商品企画のプロであるだけでなく、元々鉄道畑の自分には不案内な不動産業務全般のプロであった。
クマガイがテンドウにアドバイスを求める頻度は、その時々によって異なった。半年ぐらいアドバイスを求める機会がないこともあれば、毎日のようにアドバイスを求めることもあった。
クマガイがテンドウの去ったポストに就いた当初は、敷地の境界の画定の方法、住宅の床の遮音性能の改善方法といった、実務的な質問が多かった。
同じ部署に同じ職位で働き続けるテンドウとは異なり、クマガイは二年から三年ごとに職位が上がり、十年後には高層住宅事業の部門長になった。
その頃のクマガイの最大の仕事は、いわゆるバブル経済の崩壊の過程で、バブルの時に簿価の高い用地を仕入れたことの始末をどうつけるかということであった。
それは、用地自体の処分の要否と、会社のバランスシートの健全化とが混ざり合った問題であった。
クマガイは昼休みの人目に立ちにくい時間帯に、自分の部長室にテンドウを呼んでアドバイスを聞くことにした。テンドウはつぎのようにアドバイスした。
「クマちゃん、この後始末の問題は、時間との勝負だと思う。時間が経てば経つほど、処分するための条件は厳しくなると思う。」
テンドウは、会社の同僚の前でクマガイと話す時には、クマガイをテンドウの上司のそのまた上司として敬語を使ったが、二人だけの時は親友として敬語なしで話した。
「厳しくなるっていうのは、売りにくくなるっていうことだな。」
「そのとおり。クマちゃんは、収益還元法って聞いたことがあるだろう?」
「うん、言葉は聞いたことがあるが、それが関係あるのか?」
「バブルのときは、不動産は骨董品や美術品と同じで、売り手と買い手が価格を合意すれば、相場より少々高い値段でも成立していただろう。ところが、不動産鑑定の基準で、収益還元価格が前よりも重視されるよう変わったんだ。つまり、売買取引の相場価格よりも、不動産を貸したときの利益を還元利回りで還元した価格が大事という考え方だ。基準が変わったっていうことは、銀行の融資の時の担保査定が変わったっていうことだ。収益還元で価格を出すと、今までの売買取引価格を割り込むことがほとんどじゃないかな。」
「いつの間に、そんな大事なことが決まっていたんだ?」
「これは国会で決めるものじゃないからね。おれも、役所でそんな議論をしているということは噂で聞いていたんだけれど、本当に決まったってことは、つい先日新聞で知ったばかりだ。」
「町の不動産業者とはたくさんつき合いがあるけど、みんな、近々もう一度、値が戻ることもあるさって言ってるよ。戦後ずっと土地の値段は上がり続けてるんだから、今は踊り場だっていう感覚だ。」
「たぶん、そうはならない。戦後の不動産価格の大前提を変えられたからだ。だから、売れるものならば早く売った方がいいと思うんだ。」
「いいことを聞いた。『収益還元』、だな」
クマガイは手元の手帳に、大きな楷書で「収益還元」と書き込んだ。彼は続けて言った。
「おれの部下に、収益還元にはアンテナを張るように言った方がいいな。」
「このキーワードで、できるだけ情報を集めてみたら、おれの言っていることが当たりそうかどうか、見当がつくと思うよ。」
その時、部長室の扉を、部長秘書の女性がノックして、扉を開けた。
「クマガイ部長、そろそろつぎの会議です。」
クマガイは、何の話をしていたかを秘書に気づかれないように、声の調子をわざと大きくして、秘書の聞き耳を意識しながら、つぎのように言った。
「じゃ、おまえは同期会には、また出られないんだな。残念、残念。」
「クマガイ部長、いつもご心配いただいて、恐縮です。」
それから十数年が経過し、クマガイの奮闘の甲斐があって、東都電鉄の不良資産問題は曲折を経てほぼ解決の目処が立った。政府が不動産の簿価に含み益を算入して利益に計上する特例を認めた時、他の多くの会社と同様、特別損失をその利益と同時計上することで、巨額損失による債務超過を免れることができたのが、転換点であった。また、都心の大型の不動産は総額が張るためなかなか処分ができなかったが、投資家から金銭を集めて投資法人を設立する制度ができて、総額が張る不動産の新たな買い手となったことも、不動産市況の改善に貢献した。クマガイが、世の重要な節目ごとに、後手の対応に回らないですんだのは、テンドウをはじめとするプロの話を一度は聞いてみるということを励行したからであった。少なくとも、クマガイ本人はそう思っていた。
テンドウとクマガイが五十五歳になる年に、クマガイは、東都電鉄株式会社代表取締役社長兼社長執行役員という、会社で最高位のポストに就任した。
クマガイが社長になってからしばらくすると、東都鉄道の本社事務所をどうするかという問題が起こった。
東都鉄道は、関東の南部と北部とを結ぶ鉄道網を経営していたが、本社は、これまで都心の東京駅八重洲口近い場所に置いていた。それは、優秀な人材を採用するためには、都心の一等地のビルに本社を置くことが有効であることを、経験的に知っていたからであった。東都鉄道としては、会社資産はもちろん重要であるが、それを動かすのは人間であり、人材こそが会社でもっとも重要な財産である、という考え方が、会社の不文律の基本理念であった。クマガイが社長になった時は、高層賃貸オフィスビルの上層階に事務所を構えていた。
ところが、情報技術の進展で、従業員がデバイスを持ち歩いていれば、どのような場所にいても、ある程度の仕事はできる時代になった。一部の論者は、このことは、人間にとっての不動産というものの意味を変える可能性があると説いた。
東都鉄道の社内でも、本社は郊外の自社の操車場に土地が余っているから、そちらに簡単な建物を建てて、映ってはどうかという意見があった。その方が年間十数億円に上るオフィス賃料を節約することになるというのであった。
テンドウはクマガイから社長室に呼び出された。東都鉄道では、部門長でも課長でもない一従業員が社長と話すことは普通まず考えられないことで、そのようなことをすると必ずその従業員の上司の課長、そのまた上司の部門長、そのまた上司の本部長、さらにその上の役員が、何の話であったか気にすることは必定であったが、テンドウに限っては、
「テンドウさんは社長の同期だから」
ということで、一同に暗黙の了解ができあがっていた。
テンドウがクマガイに会うのは、クマガイがその年に社長に就任してから初めてで、アドバイスを求められるのはテンドウの記憶ではたしか二年ぶりであった。
テンドウは昼休みの秘書部を尋ね、秘書に来意を告げた。
社長は前の打ち合わせが延びているとのことで、テンドウは秘書部の待合用のソファーで十分ほど待たされた。
やがて秘書から声がかかり、テンドウは社長室に向かった。
廊下では、テンドウは上司の本部長や部門長とすれ違った。
部門長がテンドウに言った。
「おや、テンドウさん、また社長のお呼びですか?今はあまりご機嫌がよくないので、気持ちの和む昔話でもしてあげてください。」
そして本部長と部門長は、なにごとか小声で話し合いながら、廊下を通り抜けて秘書部の部屋を出て行った。
テンドウは社長室の扉をノックした。
「失礼いたします。テンドウです。」
「待っていた。入って、入って。君の上司達がなかなか帰ってくれないんで、今やっと追い返したところだ。」
クマガイは、社長席から立ち上がって、自分の机の前の応接椅子に移動し、テンドウに座るように促した。
「社長ご就任のお祝いも申しあげないうちに、ずいぶん時間が経ち、失礼しております。」
「テンドウ、他人行儀はよしてよ。おれのことはクマちゃんって呼んでいいんだよ。
おれも今や分刻みのスケジュールで、会いたくもない人にも会わなきゃいけないし、自分であって自分でないような生活だ。自分が聞いたことも考えたこともないことを、いきなり判断しろって持ってこられることもある。おまえならどう言うだろうかと思うこともいろいろあるんだけど、待ったなしだと、自分の直感で決めなきゃいけない。」
「じゃ、時間もないだろうから、要件に入ろう。今日は何の話?」
「本社移転の話だ。」
「操車場に移る、移らないという話?」
「そうだ。」
「おれは、できることならば、都心にいたほうがいいと思う。」
「うん、話が早い。そこのところの話が聞きたいんだ。」
そこで、テンドウは、手短に、つぎのような話をした。
たしかに、今はデバイスを持っていれば、どこででも仕事ができそうに思えて、もう現実の場所というものは意味がなくなるのではないかという見方もある。
でも、ヴァーチャルの世界は、実は自分が知りたい情報しか触れられないのだ。検索ワードに自分が探したい言葉を入れて、その結果を読むのだから、そもそも自分の興味や関心で、情報が限定されている。現実の場所では、自分の興味や関心のない情報に、偶然に触れる機会がたくさんある。人間は、自分以外のものに出会わないと、行き詰まってしまうと思う。
都市とは、そういう偶然の出会いが集中的に起きる場所だ。それが都市の価値だ。出会いがもっとも集中的に起きうる場所が都心であるならば、そこに会社の拠点を置くに越したことはない。
現代は、高度成長期と違って、特定の品目を効率的に大量生産すれば儲かる時代ではない。特に日本では、最低限の物資は一通り行き渡っているのだから、欲しいものは人によってさまざまだ。つまり需要が細分化している。その細分化された需要に応じて多様な商品を供給してゆかないと、儲からない時代になってきた。これまでの供給のプロフェッショナルが思いもよらなかった需要が多様に生まれる時代だ。そういう時代は、多様性のある新しい情報との出会いが勝負を決する。会社の財布の問題はあるだろうが、許されることであれば、都心にいるべきだ。
そして、できることならば、同じ都心の中でも、そのような新しい情報との出会いを積極的に起こそうとする街づくりの活発な場所に本拠を置くべきだ。そして、さらにできることならば、その街づくりの中心になるような物件に入居するべきだ。
もっとも、都心にいる値打ちというものは、言葉で語ることはできても、数値化して説明することは、誰にもできない。だから、経営者自身がそう信じるかどうかという問題だ。
クマガイは、聞いてすぐに飲み込めなかった細部についていくつかテンドウに確認した後、つぎのように言った。
「なるほど、都心の値打ちを、社長のおれが信じるかどうかだな。誰もこういう話を社長に上げて来ることはないから、とても新鮮に聞こえた。よくわかった。」
彼は、自分の手帳を開いて、大きな楷書で「都心の値打ち」と書いた。それから、その字の隣に、「多様性」と書き加えた。
「それで、かりに新本社を都心に構えるとすると、そのオフィスは、そこに都心の値打ちが凝縮されたものにしなくては意味があんまりない、ということか?」
「そのとおりだと思う。そのオフィスは、オフィスのある街の、いわば相似形のレプリカとして、出会いの機会を生み出すものでなくてはいけない。」
「新しいオフィスが、おまえの言うようなレプリカになるためには、どんなしつらえが必要になるんだろうか?オフィスの核になる何かの仕掛けをつくる必要があるんじゃないか?それがうまく行けば、そのオフィスは都心のレプリカというよりも、逆に都心のプロトタイプになって、都心の値打ちを高める中心になり得るんじゃないか?」
テンドウはしばらく考えてから言った。
「新しいオフィスの核になる仕掛けか。それは、宿題にしてくれないか。答えに心当たりはあるんだけど、少し考えてみたい。」
テンドウがクマガイ社長にアドバイスをしてからほどなく、クマガイ社長は、本社を現本社所在地に近い八重洲に二年後に竣工する予定の最新鋭のビルに移転する計画を取締役会に諮り、その決議を経て、社内で公表した。新本社のコンセプトは、「多様な人々のセッションの場」と発表された。
通常、本社の事務所関係の業務は、会社の総務部が担当するのであるが、社長は、このたびは将来の社運に関わる一大事業として、不動産関係に詳しい不動産事業本部が全面的に協力するように通達した。
このような非日常的な業務は、不動産事業本部の中で、テンドウの所属する商品企画のセクションの仕事であった。テンドウのセクションに所属する四人が、新本社移転の担当となった。
テンドウは、社長のクマガイから、
「新しいオフィスが、おまえの言うようなレプリカになるためには、どんなしつらえが必要になるんだろうか?オフィスの核になる何かの仕掛けをつくる必要があるんじゃないか?それがうまく行けば、そのオフィスは都心のレプリカというよりも、逆に都心のプロトタイプになって、都心の値打ちを高める中心になり得るんじゃないか?」
という宿題を与えられているのを思い出した。彼は、この宿題の答えは、カフェだと思った。彼は、街の中での意外な出会いをとりもつのが、カフェの機能だと考えた。
「自分があのとき偶然にカフェ・リュビに入ったからこそ、自分が気づかなければならないことに気づくことができたんだ。自分は、そこでそれまでの人生の中で思いもしなかった考え方に出会ったんだ。カフェは、そういう出会いの機能を果たすことができるんだ。だから、宿題はこの線でまとめてみよう。」
テンドウはクマガイ社長につぎのような電子メールを送った。
「先日の宿題の件、時間がかかり恐縮ですが、わたしなりの答えを出しましたので、お伝えします。新しい本社の持つべき都市の機能の核になる仕掛けは、カフェだと思います。店舗フロアにカフェを入居させるのではなくて、オフィスの執務フロアの中に、専用のカフェを設置します。そのカフェは、ただ飲料を提供するのはなくて、人と人との出会い、人と新たな情報との出会いを促す機能を持ちます。人が集まる空間で大事なのは、いろりのような場所です。温かくて、ちょっとした飲食ができて、ほっと一息くつろげる場所です。そこでの休息は、労働時間の無駄ではなくて、その場を共にする人が共通の経験を持つ重要な意味を持ちます。カフェは、オフィスに集まる人が協働作業を円滑に進めるうえでの基軸になります。そのようなカフェを運営できる委託先をいかに選び出すかが最大の課題です。以上ご参考になれば幸甚です。必要があれば参上して補足します。おいそがしいなか、お体に気をつけてご活躍ください。わたしも自分の持ち場で応援しています。」
クマガイから返信があった。
「了解。その線で検討するように、おまえのところの本部長に話すから、手伝ってくれ。移転まで二年もなくて、忙しくなるだろうけれど、よろしく。」
会社で新本社移転チームが発足して、まずはスケジュールの検討が始まった。新社屋の内装工事計画を固めなければならない時期は、引っ越しから逆算すると、その一年前の四月がタイムリミットであった。つまり、社長の移転表明から一年足らずで本社各フロアの内装工事計画を決めて発注し、工事に着手する必要があった。実際のカフェの委託先は、遅くとも引っ越しの前年の六月には決まっていなければならなかった。
テンドウは、新本社移転プロジェクトチームにオブザーバーとして入るように上司から指示された。
彼より十歳は若い、社内では切れ者で通る上司は、努めて丁寧な口調でテンドウに言った。
「テンドウさんは経験が豊富ですから、メンバーの連中には何でも思うことを言っていただいていいんですよ。」
テンドウは、長年の経験から、まわりの人がそのように「何でも言ってよい」という場合は、「多少の賛成意見は言ってもよいが、基本的にはひっそりと陪席するだけにしてほしい」というのが本音であることを知っていた。
しかし、テンドウは思った。
「おれも会社生活の残りは少ないし、この先、出世がかかっているわけでもないし、ひとつ遠慮なく自分の思うことを言ってやろう。おれに残されているのは短い時間なんだから、思う存分やって、悔いの残らないようにしよう。」
テンドウは、毎週の移転プロジェクトチームの会合では、たいていは会議の終盤になって、口を開いた。
「それで、現時点で、決定的に遅れていて、全体工程の足を引っ張っているのは何ですか?」
「このたびの工事は、通常の入居工事と、会社の実験としての研究開発のための工事とが混ざっていますが、それぞれが坪単価でいくらなのか、説明できるようにしたほうがよいと思われます。」
「新本社のコンセプトの『多様な人々のセッションの場』というものを具体的にどう展開しているのかについて、社外の人にわかりやすく説明できるように、今の段階から意識しておいた方がよいのではないでしょうか?」
つまり彼は、実務担当ではなかなか気付けない、プロジェクト全体を俯瞰して、その最も急所になる問題点を確認するような発言に務めた。逆に、彼はそのような急所以外はメンバーに任せることにしていて、口を出さなかった。
チームのメンバーは、最初のうちは、「年寄りは引っかき回さないで静かにしていればいいのに」と思っていたのか、テンドウの話が始まると、ノートパソコンを畳んで席を立つ準備を始める人も何人かいるほどであったが、定例会を重ねるごとに、テンドウの力量が若いメンバーに明らかに認識されるようになり、彼の話している最中に席を立つ準備をするような人はいなくなった。
カフェについては、新本社のコンセプトの中核として必要ということで一同了解し、具体的にどのような施設とするかについては、プロジェクトチームの下に委員会が設けられ、委員会で詳細の検討を行うこととなった。テンドウは、上司からこの委員会にもオブザーバーとして加わるよう指示を受けた。
委員会では、このたびのカフェは、単なる飲食提供の場所ではなく、オフィスの中でさまざまな出会いを促す人的なサービスがむしろ主になると考えた。そろそろ具体的な業務委託先を決めるべき段階となり、委員会では、ある程度の人的資源のある、すなわち従業員が十名程度以上雇用していて、新しいカフェに専従で何人かを派遣することができるという条件を満たした会社を選定する方針とし、これまでの東都電鉄の取引先だけでなく、世間的に評判の高い飲食業者を含めたロングリストを作り、それぞれのメリット・デメリットを洗った後、最終選考に三社を選んだ。それらは、東都電鉄と資本関係にあって同社の鉄道の特急の喫茶サービスを経営している東都レールウェイサービス、国内外できわめて多数の店舗展開をしている、業界の大手企業ビートル・シアトル・ジャパン、そして一切の無駄を省いて焙煎したての珈琲を提供するオリジナルな店舗展開で注目を浴びているヤマイヌカフェの三社であった。ヤマイヌカフェは、テンドウがインターネットで目星をつけた店の一つで、彼自身三度ヤマイヌカフェの各店舗を見て、委員会のロングリストに推薦したのであった。
第六章 プレゼンテーション
東海道新幹線のぞみ号は定刻きっかりに東京駅のホームに到着して、夕方十六時からの会議に急ぐ大勢の出張客を扉から東京の街に送り出していた。
のぞみ号を下車して改札口を出たサカムラは、同行していた部下のツネムラに言った。
「東都電鉄の会議にはぎりぎり間に合うな。」
「はい、ここから車に乗るとかえって時間がかかりますから、雨ですけれど歩きましょう。」
「車中で話しておけばよかったんだが、おれは寝ちゃったもんだから、今更の話なんだけど、東都電鉄の本気の度合いはどんなもんかな?」
「新本社ビルのセールスポイントが『多様な人々のセッションの場』で、その目玉がカフェスペースですから、オフィスのフロアの真ん中にカフェを作ること自体は本気です。ただし、うちが選ばれるかは別問題ですがね。」
「プレゼンテーションでは紙資料を配るのかな?」
「いえ、パワーポイントで画面に映してくれと言ってました。」
「ならば、先方は少なくとも、机の書類をにらんだままということにはならないね。プレゼンの時におれたちの表情を見てもらうのも、こちらの発信のうちだからね。」
サカムラとツネムラは、東都電鉄の会議室の控室に通され、プレゼンテーションの順番を待つように言われた。
彼らが通された控室は、東京駅の八重洲口にほど近い高層ビルの三十階で、晴れた日には遠く南西方向に富士山が望めるはずであったが、その日は梅雨空で、黒ずんだ雨雲の下に、東京の街並みが白黒写真にように俯瞰された。
サカムラは、最近は滅多に着ることのないスーツが窮屈であった。
ツネムラは、自分のパソコンを覗き込んで、本日のプレゼンテーションの予習に余念がなかった。
東都電鉄は、約九ヶ月後の春に、現在仮入居中のこのビルから、現在日本橋に建設中の高層の新本社社屋に移転することが決まっていた。
この新社屋への移転は、交通産業と不動産業とを経営の二本柱とする東都電鉄にとっては、ただの事務所の移転以上の大きな意味を持っていた。
つい最近の新聞に、東都電鉄の社長が、インタビューに応じてつぎのように語る記事が掲載された。
現代は、ICT技術によって、手元にモバイルパソコンやスマートホンのような端末さえあれば、離れた場所の人とでも容易にコミュニケーションができる。買い物も、そのような端末を通して手軽に行うことができる。すなわち、ヴァーチャルの世界の拡大によって、現実のリアルな場所の意味が自明のものではなくなっている。しかし、自分が思うに、ヴァーチャルの拡大ということは、リアルが駆逐されるということではない。ヴァーチャルの進展は、リアルに変化を迫り、変化に対応できたリアルが生き残る。リアルとヴァーチャルとはそういう関係にある。リアルな場所は、その場所を共有している人に対して、活動のシーンを規定する機能がある。オフィスで働く人は、オフィスビルに来ることによって、自分にオフィスで働く時間が訪れたことを、ほかの何物によるよりも明確に認識するのだ。それは言い換えれば、オフィスには、働く人が集まって協働して働くという活動シーンを提供する機能があるといえる。
ヴァーチャルの世界では、人は自分の気に入ったキーワードしか検索しない。ヴァーチャルな世界から受け取る情報は、自分の気に入ったものにほとんど限られる。しかしリアルな場所では、自分と異なった人が、自分の思いもよらなかった情報を発信しているのを、偶然的に受信することができる。思うに、経済活動にとって、複数の主体の間において価値の差異があることが、取引発生のための必須の条件である。お互い、ほしいと思う物と、手放して良いと思う物とが異なるからこそ、物の交換が成り立ち、取引が発生するのだ。取引が発生することで、利潤が生まれる。つまり新しい価値が世の中に創造されることになる。新たな価値創造のために、それぞれが異なる価値観を有する多様な人が接触する、セッションのシーンを提供すること、そこにこそ、リアルなオフィスの将来的な可能性が潜んでいる。東都電鉄の新社屋は、そのようなリアルなオフィスの将来的可能性を世の中の人に広く訴えるものにするつもりだ・・・
東都電鉄では、社長の言う、多様な人々のセッションの核となるものとして、オフィスの真ん中にカフェを設置することを企画していたのであった。
サカムラは、社長の記事と、東都電鉄の担当からの依頼趣旨とから、
「うちが提供できるのは、言うなれば『利休のメソッド』だな」
と直感した。そして、つぎのように考えをめぐらした。
おれの考える「利休のメソッド」というのは、多くの人がイメージするような、総合芸術によるもてなしよりも、もっと根本的なものだ。天下人の膝元で、それまでお互いに文字通りの死闘を繰り広げていた武将同士が、天下という秩序の中で、それぞれの位置を占めて、ひとまず矛を納めるには、どうすればよいか?そのためには、お互いに会話が成立するようにしなくてはならない。お互いの会話を成立させるには、どうすればよいか?お互いが共通の体験を持っていなければならない。共通の体験を持つための近道は、一緒に遊ぶことだ。一緒に遊ぶことによって、お互いに共通の体験が生まれ、その共通の体験をいわばパイプラインとして、お互いに会話をすることができるのだ。千利休の茶の湯は、たしかに総合芸術ではあるが、その目的は、戦乱の世の中に一期一会の遊びのひとときを実現することにあったのだ。
東都電鉄の求めている、セッションの中核としてのカフェとは、あたかも利休が聚楽第や大阪城の座敷の一角に、風炉先屏風で囲って茶釜を据えた茶席のようなものではないか。茶釜を囲んで、武将たちが同じ味を喫する遊びのひとときを持たせる、そのメソッドこそが、サカムラ商会が提供するべきものの原型だ。
サカムラは、このような考え方で、本日のプレゼンテーションを企画した。新しいオフィスにおけるサカムラ商会のカフェは、ただ単においしい珈琲を提供するだけではなくて、カフェに集う人々に、ひとときの共通の休息を演出し、人と人との出会いと橋渡しを行うものにしたい。そのために、自社で訓練したスタッフを常駐させたい・・・これがプレゼンテーションの幹になる提案であった。
当日は、三社からのプレゼンテーションが行なわれた。
東都レールウェイサービスは、テーマを特急のサロンカーとするという内容のプレゼンテーションであった。鉄道会社の新本社は、その本業である鉄道事業を表現するものがふさわしいという説明であった。
ビートル・シアトル・ジャパンは、その日のプレゼンテーションのために十五分の動画を制作して来た。ベルギー人の社長のスイヤール氏自ら、通訳と日本人の役員とを伴って席に臨み、ヨーロッパの本社の歴史と世界におけるステータスとを自らの言葉で語り、世界的企業と日本を代表する鉄道会社の一つとが提携することがいかに賢明な判断であるかを説明した。
サカムラ商会よりも前の候補のプレゼンテーションが長引いたので、サカムラ商会のプレゼンテーションは予定より四十分遅れて始まった。
サカムラとツネムラは会場に入って、自分たちのプレゼンテーションを聞いて審査する、東都電鉄の委員会のメンバーと名刺交換を行った。委員長を務めるのは、不動産部門の企画を担当する部長で、四十代そこそこに見える男性であった。委員は委員長のほかに六名いて、男女半々であった。委員のほかに、委員長よりずっと年配とおぼしき男性が挨拶した。その男性はテンドウという名で、自分は委員ではなく、委員会のアドバイザーのような役回りだと言った。委員長やほかの委員が審査の対象に対して距離を置いた固い挨拶であったのと異なり、この人は物腰が柔らかく、サカムラたちを会社のお客様として扱う様子がうかがわれた。
ツネムラはパソコンをプレゼンテーション用のプロジェクターにつなごうとした。しかし、ケーブルの規格が合わず、画面が表示できなかった。
手持ちのいろいろな道具を試しているツネムラを見ながら、サカムラは、
「おや、これは縁がなかったのかな?」
と思い始めたところで、東都電鉄の社員の一人が私物のケーブルを貸してくれて、五分遅れでプレゼンテーションが始まった。
サカムラは、最初のうちはカフェで提供する出会いの橋渡しについて、用意してきた文章を読み上げていたが、次第に、自分が商社に勤めていたころの窮屈な感覚を思い出して、
「大会社の流儀にはまり込むと、自分は負けだ。」
という気持ちになってきた。そして彼は、
「自分の言葉で思っていることを話してみよう、それでだめならばもともとだ。」
と腹をくくって、原稿を突然机の上に伏せると、つぎのように話し出した。
「・・・というところまでは、御社のコンセプトの弊社なりの解釈です。ここからは、自分が新社屋で実際に何をやってみたいかという話をします。それは、よその会社ではたぶんなさらないようなことだと思います。」
サカムラの横では、ツネムラが、予定にないサカムラの発言に明らかに当惑した様子で、サカムラの顔と手元のパソコンの画面とを頻りに見比べた。
サカムラは続けた。
「新社屋のカフェは、御社の経営で、われわれ業者が業務受託で運営することが前提とうかがっています。また、家賃も水道光熱費も、御社の一般管理費で負担されるという前提とうかがっています。その条件ならば、客足はどうあれ、採算的には悪くともほぼとんとんでやって行けるでしょう。
それであれば、私は珈琲豆にお金をかけたいのです。それは高級品を使うということではなくて、フェアトレードの珈琲豆を使いたいのです。珈琲豆の価格は、産地を遠く離れたロンドンやニューヨークの商品市場で決まります。開発途上国の生産者には、十分な利益が確保されず、そのために経営が困難になっている農園も多いのです。生産者の持続可能な経営を支えるために、国際市場で決まる価格よりも場合により割高になりますが、フェアトレードの豆を購入したい。そしてそのことを、このたびのカフェについて御社が発信される際に、ぜひ取り上げていただきたいのです。
先ほども申しあげましたように、私どものカフェは、コミュニケーションの媒体としての機能を果たすものとして、カフェに集う人々が共通の体験を持ち共通の言葉をみつけて話すようになるようにすることを促すものにいたします。コミュニケーションの媒体を務める要員は、市場にいくらでもいるわけではなく、お金をかけて募集広告を打っても採用できるというものではありません。それこそご縁の問題です。私どもがご縁あって採用してきたスタッフの中から、見込みのありそうな人材をトレーニングいたします。一口にスタッフと申しましても、前職が公務員であったり、本職が劇団員であったりで、さまざまな人材がいます。御社のおっしゃる多様な人材という意味では、すでに私どものスタッフはきわめて多様です。コミュニティーの媒体を務めるという仕事は、日本にはこれまでありそうでないものですから、御社のご指導を受けながら、試行錯誤で育成してゆくほかはありません。したがって、究極的には、御社がサカムラ商会を新しいカフェの業態を開発するパートナーとして信用しておつきあいいただけるかどうかにかかっています。
以上で弊社のプレゼンテーションを終わります。」
東都電鉄では、委員が候補の各社のすべてのプレゼンテーションを聞いた後に、ただちに選考会議を開くことになっていて、結果は翌日に電話で知らせるということであった。
ツネムラはサカムラに言った。
「サカムラさん、ひょっとして東都電鉄と仕事をするのがプレゼンの途中でいやになってきたんじゃないですか?」
「いや、そうじゃないんだ。ただね、ああしてかしこまって話していると、まるでおれが前に辞めた商社のことを思い出してね。ここはひとつ自己流を出して、あとはだめでもともとだって、割り切ったんだ。これでもしも東都電鉄の仕事がとれたら、打ち合わせの度にスーツを着てこのビルの上まで上がって来なきゃならないからね。」
ツネムラはサカムラのその言葉を聞いて、やっと笑った。
「やっぱりサカムラさんらしいな。大手企業と組むということは、大手企業の言うなりになることとはちがいますからね。」
「言うなりになるのは、本当は相手さんのためにはなっていないんだ。おれ、自分のこと、良心的だと思うよ。」
プレゼンテーションに続く選考会議では、ビートル・シアトル・ジャパンとヤマイヌカフェとの二社の支持が拮抗したが、委員長に意見を聞かれたテンドウの、
「私が自腹でお店に行くのであれば、ヤマイヌカフェの方です。ヤマイヌカフェならば、私の顔と名前を覚えてくれそうだからです。」
という発言がきっかけとなって議論がまとまり、ヤマイヌカフェが選定された。
翌日の夕方は、サカムラとツネムラは深川の第二号店にいた。十六時きっかりに、サカムラの携帯電話に東都電鉄から電話が入った。
「・・・そうですか。お選びいただいてありがとうございます。つぎの打ち合わせの日取りは・・・はい、それでは候補の日時をあとでいくつか教えてください。電子メールでだいじょうぶです。」
サカムラは東都電鉄からの電話を切ると、ツネムラに言った。
「ツネムラさん、東都電鉄がうちを選んだんだって。」
「そうですか・・・私はてっきり選に漏れたと思っていました。プレゼンの画面はすぐには映らなかったし、サカムラさんの話は個性的すぎたし、たぶんミスや冒険がきらいな大企業には合わないと思っていたものですから・・・」
二日後に、サカムラとツネムラは、東都電鉄を訪ねて、カフェプロジェクトを担当している社員のヨシハラと面会した。
ヨシハラは、三十代半ばの女性で、実際のプロジェクトの推進はこの社員が一手に担当していた。大会社であるから、管理職ではないヨシハラには独りで決定する権限はないが、会社意思決定の文書である稟議書を書くのはヨシハラであり、彼女がキーパーソンであった。
「これからは御社とはパートナーですから、選考の様子もさしつかえない範囲ですがお話しておきましょう。
プレゼンをお願いしたのは四社で、あらかじめ私どもの調査で、新しいカフェ業態をいっしょに開発する実力がありそうな会社さんを選びました。
最後に選考に残ったのは、御社と・・・」
彼女は少し口ごもったが、思い切った様子で続けた。
「ビートル・シアトル・ジャパンさんです。」
サカムラもツネムラも、元シモムラ商会であるその会社の名前を聞いて、まあこういう企画では候補に上がるだろうな、と思った。
「あちらは、ベルギー人の社長さんが通訳を連れて来ました。企画や広報の組織体制がしっかりされていて、あのように知名度は抜群ですから、委員の半分はあちらを推しました。御社は、東都電鉄がやろうと考えていることは何であるかを、ご自分たちの言葉でしっかり考えているところと、・・・それから、ご自分たちだけではできないということを率直に認めたところが評価されました。委員の残りの半分は、御社を推しました。委員長は中立です。」
「なるほど。ご存知かもしれませんが、わたしもツネムラもビートル・シアトルにいましたから、むこうの提案内容はだいたい想像がつきます。」
「それで、それぞれを支持する委員が意見を言いましたが、まとまらないものですから、そこで、おふたりはたぶん名刺交換されたと思いますが、陪席していたテンドウという社員の意見を聞いてみようということになりました。テンドウは管理職でなく普通の社員です。会社では古手で、もう定年に近いはずですが、社則とか事務手続きとかをよく知っていて便利だからということで、上の方の意向があってこのプロジェクトに加わってもらっているんです。それで、テンドウは、意見を聞かれて、
『私が自腹でお店に行くのであれば、ヤマイヌカフェの方です。ヤマイヌカフェならば、私の顔と名前を覚えてくれそうだからです。』
と答えました。そこで、委員長が、
『みんな、自腹ならばどっちへ行きたい?』
と委員に尋ねたところ、ビートル・シアトルを支持していた人たちも、それはヤマイヌカフェだろう、と言い出しました。それを聞いていた委員長が、
『自腹で行きたいカフェがいいカフェなんじゃないか?』
と発言して、一同御社に決めることに同意したんです。」
サカムラは言った。
「なるほど、事情はよくわかりました。私どものことを、能力で評価されたというよりも、信用していただいたということですね。自分としてはそのほうがうれしいです。」
サカムラはこう言いながら、テンドウのことは初対面の時からちょっと気になっていたことを思い出し、一度彼とゆっくり話をする機会があれば、東都電鉄をもっと深く理解するうえで役に立つかもしれないな、と思った。そして、ヨシハラさんは、プロジェクトチームに年長者のテンドウが陪席しているのが、何かと煙たいのだろうと推察した。
サカムラとツネムラは、ヨシハラと今後のスケジュールについての打ち合わせを終えて、東都電鉄のオフィスを離れた。
サカムラはツネムラに言った。
「今度の仕事は、今までの仕事とは違って、お客さん同士の出会いの触媒になれる人材を供給しなくちゃならないな。」
「メソッドを開発しなければなりませんね。」
「それはそうなんだが、実際に触媒の役目をん担う人材は、今うちの会社にいる人材から出さなくちゃならないから、まずは社員から候補を五人選び出して、見込みのありそうな人の目星をつけたい。そのために、その五人には、東都鉄道の社長のインタビュー記事と、触媒の仕事のイメージとを伝えて、どう思うか聞いてみたいと思う。とにかく面白いことをやろうとしているんだから、新しい仕事で面白いと思うかどうかを聞きたい。人と人とが共通の体験をする、くつろぎの場の主催者になるんだからな。くつろぎということは、遊びということでもある。それは、新しい場所の生命に関わるような遊びだ。」
ツネムラは、サカムラの話を聞いて、例によって黒目を動かしながら何事か考え始めた。彼の仕事は、サカムラの言葉から、現実的な仕上がりのイメージを引き出して、実際に形にしてゆく仕事であり、彼が黒目を動かし始めるのは、いつもサカムラの言葉が彼の腹に落ち始めた証拠であった。
「それで、サカムラさんのイメージする媒介は、たとえば江戸時代の茶坊主とか幇間とか、そういうものとはつながっていますか?」
「権力者におもねるという意味であればつながっていないけれど、場をとりもつという意味ではつながっている。現代でいえば、スポーツクラブのインストラクターとか、カジノのディーラーとかも、参考になるんじゃないかと思ってる。でも、やっぱりおれのイメージがいちばん近いのは、昔の喫茶店のマスターとか、バーテンダーとか、床屋さんとかだな。店に来る人のことをよく覚えていて、ほかのお客さんのしていた話で、その人が関心のありそうなことをさりげなく話してみるとか、ちょっとした相談事に乗ってあげるとか。」
「だから東都電鉄がカフェに目をつけたんでしょうね。イギリスの保険会社のロイズは、同業者の集まるカフェが会社に発展したものだそうですし、同じ場所で同じ飲み物を飲む間柄ということで、お互いつながりやすいですよね。」
「人間は、誰もいろんな面をもっているのに、働く人は、だいたい、そのうちの一つか二つの面しか他人に見せていないだろう。でも、カフェで休んでいる時ならば、普段隠している別の面が表れるかもしれない。おたがいがそういう面を表し合うことができれば、おたがいの理解がそれだけ深まるし、おたがいが自分だけでは創り出せないような新しいものを発見できるんだと思う。そのためには、まず共通の話題があって、会話が成立するようにしなきゃいけない。」
「スタッフの候補とは、今サカムラさんと自分とでしているような話をしてゆく必要がありますね。」
「そうだね。自分でシナリオを書きながら演じる俳優みたいなもんで、シナリオが書けるようになるのが、一応の到達点だな。まず、候補の五人のリストアップから始めよう。」
テンドウは、同僚で新本社移転プロジェクトチームの正規メンバーであるヨシハラと共に、ヤマイヌカフェとの詳細の定例会議に出ることになった。会議では、テンドウはほとんど発言しないで、いつもにこにことヨシハラの相槌を打った。
ただし、ヨシハラが判断に迷って、テンドウの意見を求めた時は別であった。
たとえば、カフェのスタッフの身なりをどうするかが話題になった時のことであった。
サカムラは、つぎのように言った。
「うちのヤマイヌカフェでは基本的に従業員の髪型も服装も自由です。ピアスしてる子もいます。男の子でポニーテールもいます。うちは、制服のエプロンさえつけてもらえばいいことにしてます。新本社のカフェでは、そういうわけには行かないんじゃないかと思うんですが、どうでしょう?」
ヨシハラはつぎのように反応した。
「うーん・・・うちは見ての通り元々固い会社で、クールビズでも、いざというときにネクタイが着けられるもの、なんて言ってますからね。おじさまがたは、スタッフが茶髪ぐらいでも驚くかもしれない。困ったな。テンドウさん、どう思う?」
テンドウは横でそっとヨシハラに言った。
「それはサカムラさんがあらかじめ認めた身なりならば、という条件にしてはどうでしょう。こちらでドレスコードを作るとすると、しろうとですし、いいものができないと思うんです。サカムラさんが目星をつけてるスタッフさんが、ドレスコードで引っかかって新しいカフェに来れなくなるようなことは、できれば避けたいです。サカムラさんの良識にお任せした方がよいと思います。その方向で、一旦預かって、チーム定例に話を上げませんか?『キーワードは多様性ですから』、という線で推してみませんか?」
サカムラは言った。
「自分を信じていただけるのならば、ご迷惑がかかるようなことはしません。問題があれば、自分が何とかします。」
直近の新本社移転プロジェクトチームの定例で、ヨシハラは、
「それで、スタッフの身なりは、多様性というキーワードがありますので、基本的にサカムラ社長の承認したものであればよいことにしたいと思っています。サカムラ社長も、ご迷惑がかかるようなことはしない、問題があれば自分が何とかすると言っています。」
と簡単に説明した。その横ではテンドウが頷いた。本件は特に異論を差し挟まれることなく、了承された。ヨシハラは、本件が了承された旨を電子メールでサカムラとツネムラに連絡した。
その次の週のヤマイヌカフェとテンドウ達との定例会は、直前になってヨシハラから二十分ほど遅れて出席するとの連絡が入った。
会議室では、テンドウとサカムラとツネムラとの三名が、ヨシハラの到着を待つことになった。
サカムラは、これはテンドウと話をするよい機会だと思って、話し始めた。
「先日はスタッフの身なりの件、ご尽力ありがとうございました。実は、身なりについては、このたびの新しいカフェのお話を進めるうえでは、大きな問題と思っていましたので、私どもを信用していただく形で納めていただいて、ほっとしています。」
テンドウが答えた。
「私もそうではないかと直感したんです。口では多様性と言いながら、身なりでは多様性を認めていないというのは、このたびのカフェのコンセプトとは合わないですから。」
「それで、テンドウさんに前からお聞きしたいと思っていたんですが・・・カフェのコンセプト、考えたのはテンドウさんじゃないですか?」
「どうしてそう思われたんですか?」
「それは、テンドウさんの立ち位置が、ヤマイヌカフェと東都電鉄との橋渡しをしようというところにいつも立っておられるからです。出会いの橋渡しが、新しいカフェのコンセプトであれば、テンドウさんはそれをすでに実行されてます。」
「いえいえ、私はオブザーバーですから。ヨシハラの守り役です。彼女が弊社の常識を世間常識と勘違いしているとすれば、会話にならなくなりますので、そこだけはしっかりと見ているつもりです。」
「選考会議で、テンドウさんの一言が、ヤマイヌカフェの選ばれるきっかけになったという話は、ヨシハラさんからうかがっています。」
「ああ、ご存知だったんですか・・・」
「いろんなカフェを普段からご覧になっているんじゃないですか?」
「まあ、仕事ですからね。会社の連中から見れば、暇があればぶらぶら外に出かけて珈琲を飲んでるみたいで、気楽にみえるでしょうが、私としてはいつも真剣勝負のつもりです。カフェの一つ一つが、異なるコンセプトを持っていますし、その店の売りになっている部分が違います。ビートル・シアトルさんみたいに、紙やプラスチックの容器を基本にして、洗い場にあまりコストがかからないようにして、採算をとっておられるところもあります。」
「テンドウさん、ビートル・シアトルの拡大の秘密がよくおわかりになりましたね。」
「エスプレッソを基本に、そこにミルクを注いでラテを主力にしているお店もあります。そのようなお店では、ドリップの珈琲は出しません。それはスペースや働く人の人数が少なくても、いい店づくりができる業態ですね。」
「テンドウさん、たぶん私たちよりもいろんなお店を見ているかもしれないですね。」
「ここ数ヶ月、毎週四軒は新しい店を見ています。」
「それで、ご自分の行きつけのお店はあるんですか?」
テンドウは、この質問には一瞬沈黙したが、やがて口を開いた。
「あるんですが、秘密です。そこは、私にとって、そこがカフェというものと正面から出会うきっかけになった場所です。でも、三人ぐらいでやっているお店ですから、新しいカフェの開発には向いていません。」
「テンドウさんがそこまでおっしゃるお店は、カフェ冥利に尽きるでしょうね。ヤマイヌカフェではないのが残念です。」
「私がヤマイヌカフェをロングリストに選んだのは、そのカフェと共通した感覚があると思ったからなんです。ただ、その共通したところが何なのかは、具体的に言い表しにくいんですが、あえて言えば、珈琲をお客様に提供することに、『夢』を持っているとでも言いましょうか・・・その『夢』がお客様を惹き付け、しかも、それによって集まる固定客が、お店のビジネスを成り立たせていると感じたんです。」
サカムラは、テンドウの方に上半身を乗り出すようにして言った。
「テンドウさん、よくぞ、おわかりいただけましたね・・・私は、焙煎したての浅煎りの珈琲を、できるだけ簡素な店構えで、なるべくカジュアルに提供することで、ここまで店を広げて来たんですが。最も大事なことは、お客様に『夢』を提供することだと思っています。お客様はカフェにくつろぎに来られるのです。もちろんおいしい珈琲をお出ししないと話になりませんが、お客様が珈琲を前にしたくつろぎの時間を楽しまれるようにするのが、カフェの仕事です。それは一言で言えば、うちのカフェならではの、オリジナルな『夢』を提供することです。」
「プロの方のお話、勉強になります。サカムラさんたちとのお仕事は、今の自分で一番楽しい仕事です。それは、仕事なのに、『夢』があるからです。」
「そうおっしゃっていただくと、仕事のやりがいがあります。実は、テンドウさんには失礼な話なんで、怒らないで聞いてほしいんですが、私たち、テンドウさんに『プロフェッサー』っていうあだ名をつけてるんです。ヨシハラさんは『お嬢』です。今日のお話を聞くと、『プロフェッサー』よりも、新しいカフェの流派を創設した『家元』の方がふさわしい。テンドウさん、『カフェの家元』、どうでしょうか?」
「それはまた、面はゆいですな。みなさんの方がプロで、私の先生なのに・・・」
「コンセプトを立てる人が、家元ですから、まちがってません。ちなみに、『カフェの殿様』と呼ばれてる人もいるんです。それは、私が育った旧シモムラ商会のシモムラ社長です。」
「お名前は存じています。たしか、来年、珈琲とカフェをテーマにした美術館を神戸に開かれるそうですね。インターネットのニュースで読みました。」
その時、ヨシハラが遅れて会議室に到着し、テンドウとサカムラとの会話はひとまず終わった。
第七章 動画の人
テンドウが土曜日ごとにカフェ・リュビに通うようになって、三ヶ月が経っていた。彼は、それまでのように人生の終わるのを待っているような生き方をやめて、もう一度行き直そうと試行錯誤している最中であった。
彼は、手始めに、三十数年間書いたことのなかった現代詩を、再び書き始めた。
彼は、学生時代に愛用の万年筆にインクを入れようとしたが、長い年月の間に古い黒インクが固体化して詰まっていることがわかり、まずはぬるま湯に万年筆をつけて洗浄するところから始めなければならなかった。
毎土曜日には、その万年筆と、厚手の便せん数枚をポケットに入れて、築地に向かった。
カフェ・リュビでは、いつもエスプレッソを注文した。
彼は一ヶ月ほどカフェ・リュビに通ううちに、店で師匠と呼ばれているカミヤと、マダムと呼ばれているカミヤ夫人と顔なじみになった。しかしお互いに名乗ったりすることはなかった。
カミヤは、ほかにお客のいない手すきの時には、テンドウに、店内に流れているフレンチポップスの話をした。
「今流れている曲を歌っている女性歌手は、ラファエル・ラナデールと言って、歌唱力が素晴らしいです。自然で純粋な感じがよくて、私は最近ファンになりました。」
「フランスの音楽というと、六十年代のシャンソンのイメージが強くて、トレネが歌う『詩人の魂』とか、私は好きなんですが、最近の音楽はあまり日本では知られていませんね。」
「そうなんです。せめてうちで聞いていただいて、好きになる方が増えるといいと思ってます。カメリア・ジョルダナという女性歌手も、低い声で独特の節回しがあって、お勧めです。」
「楽しそうですね。私も最近のフレンチポップスをうちで聞いてみようと思います。」
テンドウは、エスプレッソの碗と水のグラスを受け取ると、席に座って、いつもそうするように、碗を軽く乾杯するかのようにわずかに持ち上げた後、濃密な液体の泡だった表面をしばらく眺めながら香りを楽しみ、そしておもむろに数口でそれを飲み干した。彼は店に長居することはなく、エスプレッソを飲むと、すぐに碗をマダムに返して、カミヤとマダムに必ず、
「おいしかったです。ごちそうさま。」
と言った。カミヤとマダムは、必ず笑顔で、
「よい週末でありますように!」
をテンドウに声を掛けて、小さく手を振って見送った。
テンドウは、店を出ると、天気がよければ隅田川の川岸に出て、ベンチを探して、そこで便船を取り出し、詩を心に浮かべ、万年筆で書き付けた。彼のメソッドは、まず翻訳調の文体で、できるだけ多くの言葉を使って仮に書いてみて、それから無駄な言葉を一つずつ削ってゆき、表現を調整して、一つの作品を仕上げるというものであった。
テンドウがカフェ・リュビでリサに初めて出会ったのは、九月の終わりの土曜日であった。
リサは普段は平日の勤務で、休日は非番であったが、その日はマダムが子供の学校の用事で店に出られないので、代わりに出てきたのだった。
テンドウが店に入ると、カミヤは出かける準備をしているところであった。
「あっ、いらっしゃいませ。エスプレッソですね。今日はこの子が作ります。この子はいつもは平日に来ているんですが、今日は子供の学校の運動会で、マダムの代わりです。わたしもちょっとだけあちらに顔を出すところで、失礼します。」
テンドウはカミヤに代金を渡しながら言った。
「今日はまだ暑いから、気をつけていってらっしゃい。」
カミヤが出かけると、店の中はリサとテンドウとの二人だけになった。
テンドウはベンチに座って、見るともなしにリサの作業の様子を眺めた。
彼には、この光景は、以前どこかで見たことがあるのではないか、という気がした。彼は、長身で目鼻立ちがはっきりしていて、長い睫の下の黒い瞳が印象的なリサの風貌にも確かに見覚えがあるのだが、いったいどこで見かけたことがあるのかは、思い出せなかった。彼は、早々に自分の記憶をたどるのを断念した。そして、彼は、どこの誰とも思い出せないリサの作業する様子を、いつまでもここに座って、ただ見ているのもいいだろうな、という気持ちになった。リサの手際は、テンドウをそういう気持ちにさせるほど鮮やかで、敏捷なリズムを感じさせた。
「エスプレッソ、お待たせしました。」
リサは、いつもお店で品物を渡すときと同じように、お客様の目をしっかりと見ながら、エスプレッソの入った九谷焼の碗と水のグラスを渡した。
「ありがとう。」
テンドウはそう言ってベンチに戻り、エスプレッソを味わった。
彼には、そのエスプレッソの味が、この店の師匠のものとはまた異なって感じられることに気が付いた。その異同は、きわめて感覚的で主観的な異同であり、味覚としてはっきり何か特徴をもって異なるものではなかった。彼は現代詩を作るときのように、ふさわしい言葉を探して、つぎのような表現を導き出した。
「師匠のエスプレッソは、英雄的な力強さを感じさせる。この子のエスプレッソは、情熱を感じさせる・・・」
テンドウは、このように導き出した言葉を、心の中の便せんに書いてそのまま折りたたむかのように、口に出すことなく、胸中にとどめた。
この敏捷で快活な女性に、どのような情熱が秘められているのだろう・・・彼は、それを見極めて見たいと思ったが、エスプレッソの碗はすでに空となり、長居をするのもなれなれしいように思ったので、その日はそれで切り上げることにした。
リサは、碗とグラスとをテンドウから受け取りながら、彼の目をしっかりと見て、
「ありがとうございました。またお待ちしています。」
と挨拶した。彼は、その時のリサの表情が、初対面の顧客に対するようなものではなく、よく知っている顧客に対するような温もりを帯びていることを感じた。もっと言うと、それは気心の知れた知人に別れの挨拶をするシーンにふさわしいものであった。
テンドウは思わずにっこりとほほえみを返して、
「また来ます。今度は平日に来てみようかな。」
と言って、右手を軽く挙げて挨拶しながら、店の扉に向かった。
リサは、テンドウの後ろ姿に
「うれしいです。ぜひ、お待ちしています!」
と声を掛けて、小さく手を振った。
テンドウは、店を出ると、つぎのように考え始めた。
この店の魅力は、自分を個性の特定された個人として扱ってくれるところだ。固有名詞といっても、自分はこの店で本名を名乗ったことはないのだが、「土曜日の昼前に来るエスプレッソのお客さん」という形で特定をしてくれているようだ。そして、今日の店員さんがすごいのは、初対面なのに、既知の個人であるかのように、温かい応対ができることだ・・・
彼は、このように理屈っぽく考えることで、本当に自分が気にしているのは、すでに熟知しているこのお店の魅力ではなくて、初対面の店員である彼女の魅力であることを、自分に隠した。
テンドウは、隅田川の岸辺に出ると、天気の良い土曜日にはいつも座るベンチに座った。そして、懐の万年筆と便せんを取り出して、詩を作り始めた。
彼は、便せんに思いつく限りの言葉を翻訳で書き付けてから、一つ一つの言葉を吟味して、不要な言葉を削り、次第に濃縮して行った。
その日の詩は、一旦完成したように思ってベンチから立ち上がった後の帰路においても、彼はしばしば修正の必要を感じて、そのたびに、人にぶつからないように道の脇に寄って。懐から万年筆と便せんを取り出しては修正を施した。
彼が完成させたその日の作品は、つぎのようなものであった。
エスプレッソ
職人の指先にほとばしる
一瞬の魔法の圧力に
異国の豊饒の果実は
もはやこらえていることができず
厳かに黒い雫と化す
彼は、カフェ・リュビから帰った午後もずっと、詩の冒頭の「職人」という言葉を、「あなた」という言葉に書き換えては、また「職人」という言葉に戻し、また「あなた」に書き換えるという作業を何度か繰り返し続けたのであった。そうなると、彼はもはや、初対面の店員のあの女性が自分の心をすっかり占めてしまっていることを、自分に隠しおおせることができなかった。
彼は結局、この詩のバリエーションとして、つぎのように書き残すことにした。
エスプレッソの魔法
あなたの指先にほとばしる
一瞬の魔法の圧力に
異国の豊饒の果実は
もはやこらえていることができず
厳かに黒い雫と化す
彼は、この詩をノートに書き終えると、今日、自分自身が、不可逆的に黒い雫に化したのではないかと思った。
それから彼は、土曜日だけでなく、平日の出勤前の早朝にも一回、カフェ・リュビを訪れるようになった。
彼が初めて平日に訪れた朝は、カミヤとマダムとリサの三人が店にいた。
テンドウの来店に気が付いたマダムが言った。
「いらっしゃいませ。平日にも来ていただいて、ありがとうございます。エスプレッソですね。」
「はい。お願いします。」
テンドウは、代金をマダムに支払うと、ベンチでエスプレッソを待ちながら、念願の通り、彼がまだ名を知らぬ女性店員、すなわちリサの作業を眺めた。
師匠とマダムとは、洗い場の別の仕事をしていたので、エスプレッソは、リサが作った。
彼の耳に、カミヤとマダムとの話が聞こえてきた。
マダムが言った。
「・・・リサちゃんにもあとで聞いてみるわ。」
カミヤが洗い物をしながら答えた。
「ああ、たぶん数は足りるよ。」
テンドウは、それまでこの店に通っているうちに、男性の店長は「師匠」と呼ばれ、小柄な女性の店員は「マダム」と呼ばれて、どうやら師匠の夫人であるところまでは気が付いていた。彼は、この会話は、菓子か何かを分ける相談ではないかと見当をつけたが、「リサ」というのは、師匠とマダムとの娘の名前か、あるいはこの店員の女性の名前か、はかりかねた。会話はそれで終わったので、どちらであるか、それ以上の手がかりはなかった。それで、彼は、まだ名を知らぬ女性の店員を見守ることに集中した。
テンドウは、彼女から注文の品物を受け取るとき、自分の腕が不自然にふるえたりしないか心配であった。彼女は、前回と同様、しっかりと彼の目を見ながら、エスプレッソの碗と水のグラスとを彼に渡した。彼は、固くぎこちない右手で碗を、同じく左手で水のグラスを受け取って、ベンチに戻った。
彼は、彼女のエスプレッソを丁寧に味わった。彼の過剰気味の想像力は、一口ごとに彼女の情熱を感じた。彼は、迫る情熱に堪えるかのように、眉間に皺を寄せて、結んだ唇の端に力を込めた。そして、彼は余韻に浸ることを自分に禁じるかのように、エスプレッソを飲み終わると、ただちにベンチから立ち上がって、彼女に空の碗とグラスを返した。
テンドウは、何とか平静を保ちながら、言った。
「ごちそうさま。おいしかったです。」
リサは、いつものように、彼の目をしっかり見ながら答えた。
「ありがとうございます。またお待ちしています!」
テンドウが店の扉を開けながら、ふと振り向くと、視線がリサの視線と合った。彼は、思わず照れ隠しに笑うと、リサもにっこりとほほえみを返した。彼は、その瞬間に、今までに感じたことのないような幸福を感じた。
彼は、その次の平日の来店からは、自分の感情をいささか制御することができるようになり、挙措動作も自然なものになった。あいかわらず、その女性店員の名前が「リサ」であるかどうかについて、手がかりを得ることはできなかった。しかし、彼の理性は、お店の人と自分との関係においては、社会的にはその程度の距離はむしろあたりまえと知っていて、あけすけに質問したりすることを制止した。
彼は、週の平日に一度、リサのいるカフェ・リュビを訪ねている十分に満たない時間に感じる幸福感は、自分の過去に思い当たらないものであることに思い当たった。亡くなった妻のヒサエとの出会いの時は、自分と同じものを持った人との出会いの喜びがあったが、今自分が感じているものとは異なっていた。彼の理性は、自分がカフェ・リュビを頻繁に訪れるのは、そういう自分の心の動きを観察するためである、と自分に言い聞かせた。
彼は、自分の心の動きを観察する参考になるのではないかと思って、若いときに見たことのあるヴィスコンティ監督の作品である映画「ベニスに死す」を再び鑑賞してみた。彼は、主人公であるドイツの国民的な大作家が、ベニスで遭遇した美少年を、本人に知られることなく追いかけながら人生を終わる姿を見て、それを自分に重ね合わせてみた。彼の観るところ、この大作家は、美少年に現実的な接触を持とうとすることなく、自分の分身としての美少年を、あくまで自分の中だけで追い求めているように思えた。そして、彼は、自分の今の心のあり方は、この大作家とは違うと思った。彼は、今の自分は現実に望みを託しているのだと思った。かといって、彼は、現実における官能性を求めているのではなかった。およそ現実における官能性ということについては、彼は彼女のエスプレッソを飲むという現実だけで十分だった。
彼が自分の心の動きをよく理解することができたのは、十一月のある土曜日にカフェ・リュビを訪れた時であった。彼は、いつものように師匠とマダムとに迎えられた。しかし彼は、そこに「あの人」がいないということを寂しいと思った。
「今日は、『あの人』はここにはいないんだ。」
ということが、素直に悲しかった。自分にとって、ある特定の他者が不在であることを、これほど悲しいと思ったのは、初めてであった。妻のヒサエが亡くなった時も悲しかったが、それは自分の分身のような存在が亡くなったことへの悲しみで、今の自分の悲しみとは質が違うと思った。彼は、自分にとっての他者として、「あの人」に会いたいのだ、と思った。平たく言えば、彼は初めて他人を好きになったのであった。彼は自分の心を、驚きを伴いながら、そのように理解した。
彼は、「あの人」、すなわちリサに、自分の気持ちをストレートに打ち明けるようなことは避けることにした。そのかわり、平日に彼女に会えた時は、精一杯の笑顔で、一言でも彼女の気持ちの引き立つようなことを言うことを心がけた。その言葉は、たとえば、
「ありがとう。」
「今日は晴れましたね。」
「今日もおいしかったです。」
「また来ます。」
といった、日常的な何気ないものであったが、彼はその言葉には自分の心が凝縮されているつもりであった。彼は、何か大げさなことを言ったり書いて送ったりするよりも、そういう短い言葉の方が、よほど彼女を喜ばせるであろうと思った。すなわち、彼は、彼女の常連客という厳然たる前提を守りながら、彼女が自分に会うたびに、ごくわずかであっても、何らかの幸せを感じられるように、精一杯できることをする、という道を選んだのであった。彼は、このようなあり方であれば、「ベニスに死す」の大作家とは異なる生き方になると思った。
テンドウは、生き方を変える試行錯誤のなかで、若い頃から久しく離れていた音楽や演劇の鑑賞を再開していた。
彼は、フレンチポッスを聞き始めた。現代の曲を手当たり次第に聞いているうちに、どの歌手が自分の好みに合っているかがわかってきて、楽しみがひとつ増えたと感じた。
音楽だけでなく、演劇についても、彼は機会をみつけては出掛けて行った。
ある日、彼は、若い頃には、切符が高くて自分にはとても敷居の高かった、能楽を鑑賞してみようと思った。
その日は、十一月の肌寒い日曜日であった。彼はあらかじめ演目の詞章を図書館で調べて、そのコピーを持って、水道橋の能楽堂に出かけた。
その日の演目は、狂言の「宗論」と、能の「仏原」であった。
「宗論」は、旅路で行き会った法華の信者と浄土の信者とが、初めはたがいに己の宗派こそが人を救う正しい教えであると論じようとするが、実はどちらも自分の信じる宗派については生半可に聞きかじったことを言い合っていて、そのうち法華の信者が題目を、浄土の信者が名号を、それぞれが大声で相手に聞こえよがしに唱えるうちに、いつしか法華の信者は名号を、浄土の信者は題目を、それぞれとり違えて唱え出して、やがて二人が間違いに同時に気付いた時、二人とも、それぞれの宗派が一つの救いへの異なる道にすぎなかったことを悟る、という筋書きであった。
「仏原」は、パンフレットには「ほとけのはら」とふりがながふられ、あらすじはつぎのような旨が書かれていた。加賀の某所の小堂に泊まろうとした旅の僧が、地元の女性に、この場所で亡くなった仏御前という人の菩提を弔うように頼まれる。女性が語るところによると、仏御前はかつて白拍子で、平清盛の寵愛を祇王という白拍子から奪って愛妾になり、祇王は出家して尼となったが、ある日、祇王の庵を出家した仏御前が訪れた。仏御前も、自分の身の上のはかないことを悟って、清盛の許を離れたのであった。旅の僧がその夜供養の回向をすると、明け方の夢枕に、白拍子の姿の仏御前が現れて、僧に舞を見せて消える。
テンドウは、三つの演目のうち、ことに「仏原」に感銘した。パンフレットの解説には、すでにこの世を捨てて悟った仏御前が、自分の境地、すなわち詞章の一句「一歩挙げざる前(さき)をこそ、仏の舞とは言ふべけれ」、つまり、舞というものが表れる前の「無」という仏の境地にあることを示すためにこの世に再び現れたのだ、と書いてあったが、彼はこの解説とは別の解釈をした。彼によると、仏御前は、出家の生活に入ったが、白拍子としての芸の道に心が残っていて、その心残りを払ってもらうべく、旅の僧に回向を頼んだのであった。そして、仏御前は、回向の功徳によって再び白拍子として舞うことができ、そこで初めて仏の境地をめざす心となって成仏したのであった。
テンドウは、この世に生きている限り、あの世とは壁一枚が隔たっていて、それをあたかも超えられるように思うことはまちがいだと、自分の経験によって信じていた。彼は、いくらあの世の待合室に住むような生活をしても、それはあの世そのものに住むこととは異なるのだから、むしろこの世の人として、この世の哀楽としっかり出会うことが大事で、少なくとも自分は生き方を変えて、そういう道をめざしているのだと考えた。それだけに、仏御前がもう一度この世に戻ってきたいという気持ちに、自分の気持ちを重ね合わせて、感銘を受けたのであった。能楽では、観客は舞台の橋掛かりから揚幕の内に入って行く演者に、静かな短い拍手を送ることを例としているので、自分もそれに合わせて、舞台から消えて行くシテの仏御前に拍手を送った。
テンドウは、「仏原」を観たあと、たしか最近、祇王と仏御前の話が映画になっていたことを思い出した。インターネットで調べると、世界的な映画の巨匠として名高い故オガミ・アラタ監督の遺作で、「女浄土」という映画があることがわかった。彼は、その記事を読んで、この映画の公開の頃は、映画には関心がなかったから知らなかったが、当時はけっこう話題作だったことがわかった。
彼は記事に添えられたその映画のスチール写真の一枚を見て、あっと驚いた。
「白拍子仏御前 ヒビノ・リサ」
と注記のあるその写真の女優は、カフェ・リュビの「あの人」とそっくりであった。写真では白い被布を被った墨染の衣を着た姿であるが、背の丈といい、大きな目といい、その人目を惹き付ける表情といい、「あの人」そのものであった。
彼は即座に、「あの人」は、ヒビノ・リサであって、師匠の口にした「リサ」というのは、マダムの名ではなくて「あの人」の名前なのではないか、と思った。その一方で、彼は、おれはいつも「あの人」のことを考えているからこんなことを思ってしまうのであって、思い過ごしかもしれないとも思って、自分の結論を急ぐ心を抑えた。
彼は、ヒビノ・リサについてもインターネットで調べた。
彼女は、世間を騒がせたオガミ監督との「サングラスの女事件」の最中に、突然姿を消したことがわかった。インターネットでは、ヒビノ・リサについては、「女浄土」での凛とした好演を惜しむ声と、大役のために監督を籠絡しようとしたことを非難する声との両方が見いだされた。そして、事件からもはや一年が経過し、オガミ監督も亡くなったことで、世間ではヒビノ・リサの事件は過去の話になりつつあることもわかった。
テンドウは、もし「あの人」がヒビノ・リサであるとすれば、どういう経緯でカフェ・リュビで働くようになったのだろうかと思った。そして、彼には、「あの人」が、大役のために監督の籠絡を試みるような人物には、どうしても思えなかった。
彼は、ただちに「女浄土」の動画を入手して、自室で鑑賞した。彼は、仏御前が屋敷を出立するシーンのリサは、彼があらかじめ想像していたような、厭世観ではなくて、新しい人生に出発する一人の女性の確信を堂々と表現していると感じて、共感を覚えた。
彼は次の月曜日の朝、カフェ・リュビを訪ねた。
店に入ると、師匠が「あの人」に、
「リサちゃん、あとで買い出しの時にウェットティッシュも買ってきてくれない?」
と言っているのが聞こえた。テンドウは、初めて、「あの人」がリサと呼ばれていることを確認できた。
彼は、彼女が「あの人」ではなくて「リサ」という固有名詞で認識できることで、彼女との心理的な距離が格段に接近したことを感じた。その喜びで、「リサ」がヒビノ・リサであるかどうかは、とりあえずは彼の関心の外に置かれた。
リサが彼に声を掛けた。
「こんにちは。今日もエスプレッソですね。」
テンドウは
「はい。お願いします。」
と言って、代金を支払った。財布には細かい硬貨がなく、彼は、折りたたんだ千円札を引っ張り出して広げる自分のもたついた動作が恥ずかしかった。
テンドウは、いつものようにエスプレッソを受け取って飲み干し、碗をリサに返すときに、何気ない風を装って聞いた。
「あなたは、ここのお店は長いんですか?」
「はい、お店を開けたときからいます。」
すると、横から師匠が言葉を重ねた。
「そうなんです。創業メンバーなんです。もうかれこれ五年です。」
しかしテンドウは、師匠の顔のわずかな動揺を見逃さなかった。彼は、師匠がリサのキャリアに映画女優をしていた間のブランクがあることを隠していると確信した。そしてそれは、師匠として、リサを世間から守るために、当然なことであると思った。
その一方で、彼は、リサを知って初めて自分の方から彼女に話しかけた言葉が、詮索がましいものであったことを心に恥じ、後悔した。彼は、自分にとってリサが元女優であったかどうかなど、自分が関心をもつようなことではなかったはずだと思った。
テンドウはリサに、いつものように
「ごちそうさま。おいしかったです。」
と言って、右手を師匠とリサに向けて挙げ、見送るリサの声を後ろに聞きながら、店を出た。
第八章 守る
テンドウの会社入社の同期会の幹事は、同期のメンバーの持ち回りになっていて、今年はテンドウともう一人、ヤマザキという、テンドウと同じ大学の同じ学部を卒業している男が幹事となった。
ヤマザキは、東都電鉄の系列会社である、東都映画に出向していて、代表取締役社長を務めていた。
東都映画は、映画の制作と映画館の経営を行う映画業界の大手企業である。ヤマザキは、四十歳ごろ東都映画に出向した当時は、映画館事業はレンタルビデオ等に客を奪われていた。彼は、ショッピングセンターの中に複数の映画館を設けて、自宅の画面で見るのとは異なる大画面で、家族や友人といっしょに映画を見るという形態を積極的に展開し、これにより映画館事業を立ち直らせ、その功績で社長となった。彼は、映画館事業およびそれに関連する不動産関連事業については玄人であったが、映画制作については、映画業界の大立者と目されているオカモトという専務取締役にもっぱら委ねていた。
二月の同期会を半月前に控えて、テンドウはヤマザキと段取りの打ち合わせをすることになった。打ち合わせの場所は、築地に近い東銀座の東都映画の社長室で、時間は昼食時とし、あらかじめヤマザキの方で二人分の弁当を買っておくことになった。
テンドウは、会社を出て、地下鉄銀座線に乗るために日本橋の駅に入り、ふとキオスクに目を留めると、本日発売の週刊誌に、つぎのような見出しがトップで出ているのに気が付いた。
「世界のオガミの秘められた行状 事務所社長が暴露する『サングラスの女事件』の真相」
彼は、急いでその雑誌を買うと、地下鉄の駅のベンチにすわって、目を通した。
記事の内容は、つぎのようなものであった。オガミ氏の遺産をめぐって、元女優の未亡人およびその子供である長女・次女と、先妻の子供である長男とで争いになり、事務所社長のヤマガタ氏は長男側についていた。ところが、オガミ氏の遺言が発見されて、未亡人側に財産の大半が渡ることになり、ヤマガタ氏は会社の株主総会で未亡人側に社長を解職され、取締役も解任された。事務所社長としては、オガミ氏の生前から、同氏の芳しくない素行の尻ぬぐいをしてきたのに、ろくに退職金もなく放逐されたので、このたび自分の知る秘密を暴露することにした。ヤマガタ氏は、暴露するのは義憤にかられてことで、金銭の問題ではないと言っている。
事務所社長が特に苦労したのは、オガミ氏が文化勲章受章を控えた重要な時期に引き起こした、「サングラスの女事件」の収拾であった。
事務所社長は、オガミ氏とのスキャンダルを報じられた相手である、ヒビノ・リサの所属する芸能事務所のタカギ社長から、強い抗議を受けていた。タカギ社長は、リサの話では、個人的に演技指導されたが、不倫関係はなかったと聞いている、オガミ氏がマスコミに不倫であってそれがリサの誘惑によるものだと謝罪したのは、あまりに一方的である、とヤマガタ氏に申し入れた。
ヤマガタ氏は、善後策を立てるために、オガミ氏に真実を言うよう問い詰めた。
オガミ氏は、つぎのようにヤマガタ氏に語った。自分の方からリサをドライブに誘い、ホテルのスイートルームで演技指導をしているうちに、つい出来心で抱きついてしまったが、自分は老齢でそれ以上は何もできなかった。だから、本当は、不倫関係は成立していない。しかし、自分はどんなことがあっても、男性として終わっているということだけは、世間に知られたくない、勲章なんかには替えられるもんか、と語った。
ヤマガタ氏は、膝詰めでタカギ氏と談判する必要があると判断し、東都映画のオカモト専務に相談し、同社社長室で、オカモト専務の立会のもと、ヤマガタ氏とタカギ氏との会談の場が設けられた。
席上、タカギ氏は、リサは法的手段に訴えるような気はまったくないこと、リサが女優業を続ける気力をなくしているとマネジャーから報告を受けていることを話し、すでに彼女のために実施された投資が回収できなくなったらば、その分はヤマガタ氏の事務所で始末をつけてほしいと言った。ヤマガタ氏は、オガミ氏本人の気質から言って、前言を撤回することはむずかしい。しかし本人の叙勲に関わる大事な時期であり、スキャンダルは一刻も早く収斂させたい、と話した。話し合いは平行線が続いたが、二時間ほど経過してから、オカモト専務がつぎのような和解案を提示した。
一、オガミ・アラタとリサとの間には、不倫関係は存在しなかったことを、ヤマガタ氏とタカギ氏とは確認した。
二、オガミ氏が前項に関わらず自分の見栄のためにマスコミに行った発言について、ヤマガタ氏はタカギ氏に陳謝する。
三、オガミ氏が文化勲章を受章するまでは、タカギ氏の事務所は問題を大きくする発言をしないことを保証する。
四、ヤマガタ氏は、オガミ氏の次の作品では、タカギ氏の事務所から、主役を一名、準主役を二名出演させることを確約する。
五、ヤマガタ氏は、オガミ氏が文化勲章を受章した後、遅滞なく、第一項の事実をしかるべくマスコミに説明する。
ヤマガタ氏とタカギ氏はオカモト専務自筆の和解文書に署名した。
ヤマガタ氏は、オガミ氏にこの和解条項を受諾するよう説得するのに苦労した。ヤマガタ氏はオガミ氏に、
「本当に勲章はいらないんですか?この条項を飲まないと、もうチャンスはないですよ。」
と再三言って、何とかしぶしぶ受諾に漕ぎ着けた・・・
週刊誌の記事は、
「ヤマガタ氏は、今の自分には、『サングラスの女事件』以外にもまだ手持ちの秘密情報があり、それを暴露するとオガミ氏の欲望の被害者が多数名乗り出て、未亡人および事務所は訴訟の嵐に巻き込まれるであろう、と語っている。」
と文章を結んでいた。
テンドウが、この週刊誌を持って、東都映画の社長室に十分遅れて到着すると、ヤマザキもそれから数分遅れて出先から戻ってきた。
「おう、テンドウ!待たせたな。弁当代、六百円。」
「おれも今着いたところだ。六百円だな?」
テンドウは小銭を出して、ヤマザキに弁当代を払った。
「まあ、先に飯にするか。」
ヤマザキは弁当を開きながら、テンドウの持って来た週刊誌を見た。
「おっ、もう買って読んだんだな。クライマックスはこの社長室の場面だ。ヤマガタさんは、ちょうど今テンドウが座っている椅子に座っていたんだ。今おれが座っているところがタカギさんで、オカモト専務とおれは、そっちの椅子だ。」
「おまえも立ち会ってたのか?」
「そうだよ。本当はね、初めのうちはヤマガタさんとタカギさんと二人きりにして話をさせたんだ。それからおれたちが入って、二人それぞれの主張を聞いて、またおれたちは別室に移って、そこで和解案を作ったんだ。便せんに和解案を書いたのは、本当はオカモトさんではなくて、おれだぜ。知ってのとおり、おれは東都電鉄の文書課が長かったから、その経験が役に立ったんだ。」
「雑誌に書いてることは、本当なのかい?」
「まあだいたい、ヤマガタさんが言っていた通りだ。ヤマガタさんは義憤にかられて雑誌に公表したように言っているが、何か計算があってのことだろう。」
テンドウは、世間話の風を装いながら、リサについて聞いてみようと思った。
「あの事件の女優は、結局どうなったんだろう?」
「うん、彼女は、もしも一騒ぎすれば、オガミ監督の勲章がかかっていたから、何かしらはオガミの方から引き出せたはずなんだが、本人にはそういう欲はもとからなくって、事務所に辞表を書いてどこかに行ってしまったって聞いた。おれはつい先週タカギさんに会ったんだが、マネジャーのところには彼女から時々電子メールが届くらしくて、生きていることはわかるんだが、『毎日舞台を踏んでいます』なんて書いてあるから、これは地方の演劇にでも出てるんじゃないか、って言ってた。方々探しているらしくて、そのときも、あれだけのスター女優はもったいないって言ってたよ。もっとも、本音では、もう一度あの女優を取り戻して、投資の回収の芽が復活してほしいと思ってるんだろうけどね。女優の親元が茨城の方にいるらしくて、近々訪ねてみるって言ってたな。今日の記事で、マスコミの記者も動き出すだろうから、まあ、見つかるのは時間の問題だな。」
テンドウはこの話を聞いて、心中穏やかならぬものを感じた。リサはこのままではまたマスコミの報道の渦に巻き込まれてしまうのではないかと思った。
彼は、ヤマザキとの同期会の打ち合わせは上の空で終えて、カフェ・リュビに急行した。彼は、会社に電話をかけて、今日は出先からこのまま会社には戻らないで直帰する予定だと伝え、時間を確保した。
カフェ・リュビの扉を開けると、師匠とリサがいた。二人とも、
「いらっしゃいませ。」
と声を掛けたが、顔色がすぐれなかった。
テンドウは、他に客がいないのを幸い、二人に切り出した。
「お二人にとても重要な話があります。信じていただけるかわかりませんが、リサさんをタカギさんの事務所が取り戻しに来る情報を聞いたばかりなんです。それに、マスコミの記者が、すぐにでもここに訪ねて来る可能性が高いです。」
カミヤとリサの顔色がさっと変わった。師匠が言った。
「お客さん、週刊誌を読んだのですね?」
「それだけでなくて、自分は今、東銀座の東都映画の社長と会ってきたばかりです。私のことは、どこの誰だと名乗ったことがなかったですね。私はテンドウと言います。東都電鉄の本社に勤めています。」
リサが言った。
「私は、もう事務所に戻りたくありません。記者にいろいろ聞かれるのも、もういやです。」
テンドウが言った。
「そうではないかと思ったので、とりあえず、東都映画からまっすぐにここに来たんです。できることならば、取り急ぎ、今日は店を早仕舞いした方がいいと思います。」
カミヤが答えた。
「自分もそうしようかと迷っていたところでした。」
カミヤは、メモ用紙に「本日は故障のため臨時休業します」と書いて、扉に張り出すと、錠をかけた。
「あらためて、私はカミヤと申します。気に掛けていただいて、ありがとうございます。」
「信用していただいて感謝します。」
「大事な常連さんですから。芸能関係の方ともお見受けしていなかったので、驚きました。」
「自分は芸能関係者ではありません。東都映画は東都電鉄の系列で、社長がたまたま私の同期入社の男で、映画会社に出向している、という関係です。」
テンドウは、ヤマザキから聞いた、タカギ氏がリサの親元を訪ねようと話したことや、記者が動き出すであろうこと等を手短に伝えた。
「もうすでにタカギ氏はご実家の方には訪ねているかもしれません。」
リサが言った。
「実家の話は事務所の誰にもしたことがなかったんです。どうやって知ったのでしょう?」
「タカギ氏は、必死で情報を集めているんだ思います。それは、あなたを心配しているというよりも、自分のビジネスを心配しているからです。週刊誌の記事を見て、マスコミが動き出すと思います。とりあえず、しばらく身を隠した方がいいです。一刻も早い方がいいです。」
その時、カミヤの携帯電話に、カミヤ夫人すなわちマダムから電話が入った。
「えっ、問い合わせ?」
カミヤはマダムとの電話を切ると、言った。
「家内が自宅でうちのホームページへの書き込みを見ていたら、新聞記者だという人から、リサさんが勤めていた店だと聞いたので、居場所は知らないか教えてほしい、と書いてあったと言うんです。」
カミヤは店のパソコンを操作して、その書き込みを確認した。
テンドウは言った。
「リサさん、しばらく身を隠せるような場所、心当たりありませんか?」
「今は友達ともおつきあいをしていないので、特にないです。」
テンドウが言った。
「カミヤさんのお宅はどうですか?」
「うちに来てもらうのは構いません。」
「とり急ぎ、カミヤさんのお宅に行きましょう。ご自宅、どちらですか?」
「北千住です。」
「私は午後の時間を空けたので、付き合います。お店に記者が来たときは、リサさんの居場所は何も知らないと突っぱねるしかないです。私が道でタクシーを拾って、店の前につけますから、さっと乗って下さい。」
カミヤは夫人に電話でその旨を知らせると、慌ただしく店内を片付け始めた。テンドウは表通りまで出て、タクシーを拾うと、自分は助手席に乗って、店の前につけた。
カミヤとリサはそのタクシーに乗り込んだ。
タクシーが発車してしばらくして、テンドウは車の後ろに黒塗りのハイヤーがずっとついて走っているのに気付いた。テンドウは、これはリサの事務所ではなくて、マスコミの記者がつけているのだと思った。彼はカミヤに無言で後ろを指さして注意を促してから、運転手に言った。
「運転手さん、悪いけど、行き先を変えます。八重洲の地下に入って、駐車場で降ろしてください。」
タクシーは、三人を東京駅の八重洲口の地下駐車場で降ろした。彼らは階段を上がって、東京駅の人混みに紛れた。
三人は、改札口の横の柱の陰で立ち止まった。
その時、カミヤの携帯電話に、再びマダムから電話が入った。
カミヤはマダムと短い会話を終えると言った。
「うちに記者が訪ねてきたという連絡でした。インターフォン越しに、何も知らないと答えて、とりあえずは追い返したそうです。」
テンドウが言った。
「たぶん、カフェ・リュビの会社の商業登記あたりから、カミヤさんの住所がわかったんでしょう。カミヤさんのお宅はもう隠れるには危ないです。リサさんは東京を離れて、どこか転々とするというのはどうでしょう?」
カミヤが言った。
「金沢のおれの実家に行ってもらうかな・・・でも地方都市の方がかえって目立つかもしれないし、うちは料亭で、店で働いている人から漏れるかもしれない。それより、テンドウさん、厚かましいようで恐縮なんですが、あなたのほうで、隠れ家になるような場所の心当たりはないでしょうか?あなたのお宅となると、ご家族のご了承もいるでしょうが・・・」
「私はやもめの独り暮らしで、家族はいませんし、誰の了解も要りませんが、リサさんがいやでしょう。」
リサが言った。
「とんでもないです。毎週お目にかかっている上に、お仕事を休んでこんなに親身にして下さっているんですから。テンドウさんがおいやでなければ、お宅に隠れさせていただけないでしょうか?」
「私はまったく構いません。うちは押上の狭苦しいマンションですが、いいですか?」
「押上ならば、私のアパートがある鐘ヶ淵からすぐ近くです。荷物も取りに行きやすいし・・・」
「もう鐘ヶ淵のアパートも、記者がかぎつけているかもしれないですね。荷物を取りに行くのは、しばらくはやめておきましょう。」
カミヤが言った。
「そうと決まれば、一刻も早く、テンドウさんのお宅に急ぎましょう。」
三人は、東京駅の日本橋口を抜けて、常盤橋を渡り地下鉄半蔵門線の三越前の駅まで早足で歩いて、地下鉄で押上に向かった。
テンドウのマンションは、押上から東に徒歩十分弱の位置にあった。マンションは昭和後期に建てられた、よく管理の行き届いたものであった。すぐ近くには、かつて葛飾北斎が信仰したという、柳島妙見堂があり、テンドウの部屋からは、このお寺越しに、横十間川と、亀戸天神の裏手の街並みが見えた。記者はここまでは追って来なかった。
テンドウは、リビングルームの食卓に二人を座らせて言った。
「私は、外に泊まります。心配しないでここに居てください。」
リサは、かぶりを振って答えた。
「私は一人では心細いです。テンドウさんも一緒にいてください。」
カミヤも言った。
「テンドウさん、外に泊まられるのでは悪いです。リサちゃんのために、一緒にいてやっていただくわけには、いきませんか?」
「わかりました。家内の使っていた部屋はロックがかかりますから、そちらを使ってください。それから、このうちにある物は何でも使ってください。足りない物は、押上駅の上がスカイツリーのショッピングセンターで大抵は買えますから、私が買ってきますが、女性用品の買い出しは、できればマダムに手伝っていただきたくか、インターネットの通販を使うのが安全かもしれません。ここ一週間ぐらいは、リサさんは窮屈でしょうが、外には出ない方がいいと思います。カミヤさんは、あしたはお店を開けてみて、様子を見て休業するかどうか判断してはどうでしょうか。」
カミヤは言った。
「テンドウさんに店に来ていただいて、助かりました。私は出勤の時に電車の吊り広告で週刊誌に記事が出たのを知ったのですが、テンドウさんが来られるまで、どうしてよいかわからないでいたところでした。」
「私は、会社で広報対応にも多少関係していますので、少しは勘が働きました。」
「テンドウさんは、リサちゃんが女優だったことがどうしてわかったんですか?」
「先月たまたま、『女浄土』の映画を見て気付いたんです。」
リサが言った。
「あの映画は、東都映画の制作でした。」
「ああ、そうでしたか。気付きませんでした。」
「たぶん、東都映画の社長さんは、パーティーでお会いしたことがあると思います。たしか、体の大きい人でした。」
「社長のヤマザキは、七福神の布袋様みたいにでっぷりしています。」
「思い出しました。激励するような話をされながら、私の肩をぽんぽん何度も叩かれました。」
「そうですか。あいつのやりそうなことだな。」
リサは、少し落ち着いたのか、やっとわずかに笑顔を見せた。
カミヤは、店の様子を見るため、築地に向かった。彼は、携帯電話でマダムに、テンドウのマンションを訪ねて、リサの滞在の支度を手伝うように伝えた。
テンドウは、カミヤに言った。
「もしも記者が店に来たら、何も答えないとしても、温かい飲み物を、缶珈琲であってもいいですから、出してあげた方がいいです。記者も仕事で取材に来ている身ですから、ある程度丁寧に対応すれば、心証も多少はよくなります。」
カミヤが出発して、マダムが来るまでの間、テンドウはリサと二人きりになった。
テンドウは、亡くなった妻の部屋にリサを案内した。
「ここがあなたの部屋になります。家内が急に亡くなって、そのままになってます。掃除は毎週やってました。辛気くさいようで申し訳ないですが、このベッドを使ってください。」
「辛気くさいなんて、とんでもないです。大切な思い出のお部屋を使わせていただいて、申し訳ないです。テンドウさんは、お寂しい暮らしだったんですね。」
「だから、カフェ・リュビに行くのが、自分には心の支えでした。」
「うちのお店を大事に思っていただいていることは、師匠もマダムも私も、気付いていました。テンドウさんのことは、『エスプレッソの常連さん』って呼んでました。」
「私も、お店の三人の関係がわかるのには、しばらくかかりました。師匠とマダムとがご夫婦らしいのはすぐわかりましたが、リサさんのことは、お名前もなかなかわかりませんでした。もっとも、お店の方同士のお話に聞き耳を立てていたのですから、恥ずかしい限りです。」
「それは、私の巻き込まれた事件のことがあるんで、師匠もマダムも、なるべくそういう話題をお客様とはしないように気を付けていたからです。常連さんには、本来は隠すようなことではないんですが、そういうわけなんです。」
「だいたい察しはつきます。」
「ずいぶんたくさん本がありますね。外国語の本もこんなに。」
「妻は、ドイツ語の専門家だったんです。この部屋でいつも一人で本を読んでいました。私も自分の部屋で本ばかり読んでいました。」
テンドウは、続けて独り言のように呟いた。
「私は、妻を一人にさせているばかりで、幸せにすることができなかった。だから、妻が亡くなる前から、私も妻も、寂しい暮らしでした。」
リサが何か答えようとしたとき、インターフォンが鳴った。カミヤ夫人すなわちマダムが到着したのであった。
テンドウは、玄関を開ける前に急いで付け加えた。
「部屋の鍵はベッドの脇の机にあります。私は合鍵を持っていません。」
マダムは、リビングルームに通されると、早速、準備してきた荷物をリサに見せた。
「これが化粧水とクリーム。これは女の必需品ですからね。それから、下着一式と寝間着。うちの近所で買ってきたの。Lサイズだから、たぶん大丈夫ね。それから、うちの台所から、スパゲッティとオリーブオイルと挽肉の残り。あとでカミヤもここに合流するから、ミートソースでも作ろうと思って。ちょうど実家の母が上京しているから、うちの子の面倒は母がみるからだいじょうぶよ。」
それから、マダムとリサとは、台所に立った。
「テンドウさん、たいていの物は揃ってますね。」
「家内は病気で体が利かなかったから、私がずっと炊事をやってました。」
「今日は、私たちで簡単なものを作ります。召し上がっていただけるかしら。」
「助かります。お言葉に甘えます。」
夕方六時ごろになって、カミヤも到着した。
「記者が三人来ました。アドバイスのとおり、まずはうちのカフェラテを出しました。三人とも体が冷え切っていたようで、うまそうに飲みました。三人は、リサが昔この店で働いていたことはわかっているが、行き先を知らないかと聞きました。私は、何も知らないと答えてから、
『週刊誌で読みましたが、彼女はもう芸能界の人ではないんでしょう。ああいう形で夢を失った不幸な女の子です。そっとしておいてあげるわけにはいきませんか?』
って言ったんです。そしたら、記者の一人が、
『サングラスの女の事件の時は、ヒビノ・リサがずっと沈黙を守ったので、これは何か裏事情があるとは思いましたが、結局オガミの主張だけで記事を書いたので、自分の気持ちにとがめるところはあります。だからリサの側の言い分も知りたいのです。もしも話す気になったら、連絡してください。珈琲、ごちそうさまでした。自分が新聞の生活面の担当になったら、今度はこのカフェの取材に来たいです。』
って言って、そのまま三人とも名刺を置いて帰って行きました。
たぶん、リサさんが芸能人ではなくて、一般の民間人になったということでないと、記者はなかなか諦めてくれないような気がしました。よい方法があればいいのですが・・・」
マダムがカミヤに尋ねた。
「一般の民間人になるって、今だってそうなんじゃない?」
「うん、でもね、もう芸能界には戻らないということがはっきりしていないといけないんだろう。それには、たとえば一般の男性と結婚したとか、何かわかりやすいできごとがあると、大義名分になるんだろうけれどね。」
その晩は、カミヤ夫妻とリサとテンドウは、食卓を四人で囲んで、マダムとリサの合作の夕食を採った。夕食は、カミヤ夫妻の金沢での出会いの話や、リサの演劇学校の話などで、にぎやかであった。テンドウは言った。
「このような事態の時にふさわしくないかもしれませんが、私はこんなにぎやかな夕食を採ったのはたぶん二十年ぶりぐらいです。みなさんのこともよく知ることができました。カミヤさんはおうちにお子さんを待たせておられるから、もうお帰りになった方がいいです。あすは金曜日で、私は会社がありますから、リサさんは一人でここに籠もっていてください。私は、だいたい夕方の七時前には帰ってきます。朝と晩には、カミヤさんたちのどちらかでも、様子を見に来ていただけるとありがたいです。」
カミヤは言った。
「ここは私たちの住まいの北千住から電車で一本ですから、助かります。朝、店を開ける前に、立ち寄ります。」
マダムが言った。
「あす朝は私が来ます。ただ、開店が七時ですから、六時前になると思います。朝、早すぎますか?」
テンドウが答えた。
「私は朝五時にはいつも起きていますから、だいじょうぶです。お待ちしています。」
夜七時すぎに、カミヤ夫妻は帰って行った。
テンドウはリサに言った。
「じゃ、私は、今から歯を磨いたら、自分の部屋に入ります。シャワーはお好きに使ってください。自分はあしたの朝に使います。お疲れでしょう。おやすみなさい。」
「すっかりお世話になってしまって、ありがとうございます。おやすみなさい。」
テンドウは、リサが気を遣わないように、いつものように読書をすることなく、すぐに消灯した。
彼は、すぐ隣の部屋にいるリサのことが気になって、なかなか眠れなかった。
今日の午後からの自分の行動を振り返ると、常連客以上のものではない自分として、出過ぎたことをしたのではないかと自問した。それに、リサはテンドウの存在をそれまでどれだけ意識していたのか、確信が持てなかった。しかし、リサがテンドウの部屋に来たということは、自分を信用してくれていると考えてまちがいないと思った。彼は、リサに信用されている以上は、自分の人生の全てを賭けて、リサを守ってみせると決意した。その腹が決まったところで、彼は眠りに落ちた。
翌朝、五時少し前に、テンドウは起床した。
テンドウは、いつものように、カーテンを開けて、ベランダの越しに妙見堂に手を合わせた。それがテンドウの日課であった。
彼は、シャワーを浴びると、寝間着を普段着に着替えて、リビングルームに現れた。リサはすでに起きて、朝食の支度をしていた。
「おはようございます。」
「おはようございます。よく眠れましたか?」
「はい、おかげさまで、休まりました。」
リサは、目玉焼きを食パンに添えて食卓に運んだ。
二人で朝食を済ませると、リサは珈琲を淹れて持ってきた。
テンドウが言った。
「一人じゃない朝食の珈琲は久しぶりだ。カフェ・リュビの珈琲はもちろんいいけれど、けさの一杯はおいしいな。リサさんの入れ方がうまいんだろう。」
「気に入っていただけましたか?」
「もちろんです。それで、私は会社に出かけますが、あなたは外に出かけないで、ここにずっといてください。退屈でしたらば、私や家内の部屋の本はお好きなように見てください。」
間もなくインターフォンが鳴って、マダムが到着した。
テンドウが尋ねた。
「マダムはずっとここにはいられないんでしょう?」
「お店がありますから、もうしばらくしたら出かけますが、また夕方には来ますから。」
「マダム、もしも何かお困りのことがあれば、私の携帯電話に連絡してください。」
そして、テンドウは会社に行く支度をして、リサとマダムに玄関で送られて出かけた。
リサは、しばらくしてマダムが出掛けたあと、独りでマンションに籠っている間、部屋の掃除をしたり、テンドウの衣類を洗濯したり、食事の支度をしたりしながら、テンドウが帰ってくるのを待っていた。彼女は、店での経験から、手を動かす家事労働が、自分の不安をよく紛らわせることを知っていた。彼女は、テンドウの部屋に勝手に入ることは控えた。
テンドウは会社で、同僚のヨシハラと、ヤマイヌカフェとの定例会に出席した。
開業を二ヶ月後に控え、メニューや価格の設定、スタッフ研修の進捗状況の確認等が議題であった。
テンドウは、リサのことを意識のどこかで気にしながらも、自分の職責を果たした。彼は、いつものように、質問の形で意見を示唆した。
「スタッフの方は、ほかの会社でのキュレーターの実例は、見ておられるのでしょうか?」
キュレーターというのは、元々は博物館の学芸員のように、企画や運営を司る人を意味する言葉であるが、テンドウは、新しい業態のカフェで、場における人と人との出会いを促す触媒の役割を果たすスタッフを呼ぶ言葉として提案し、採用されたものであった。
ヤマイヌカフェのツネムラが答えた。
「本屋で、本を売るだけでなくて、そこで文芸塾をやったり、企画書の作り方の指導をしたり、会員の交流をさせたりする機能を持っているところがあって、そこに見学に行かせています。本屋に、学校の文化系サークルが付属しているような業態です。」
ヨシハラが尋ねた。
「そこでは、本を売る店員が、同時にそういうキュレーター機能を果たしているんですね。」
「そうです。」
「私たちも見学しておきたいです。後で場所を教えてください。いい店員さんがいたら、スカウトしたいぐらいです。」
テンドウが言った。
「ぜひ見学しましょう。ほかにも、たとえばリゾートホテルで、お互いに知らないお客さんをグループにして、ダイビング教室をやったり、ピクニックに出かけたりといった仕掛けをしているという例もあります。見ず知らずの人々に出会いをもたらす人的なサービスという視点で、いろんな情報を集めて、教えてください。」
ヤマイヌカフェのサカムラ社長が言った。
「客船のクルーズで、スチュワードがお客様をオリエンテーリングして、いろいろなグループ活動に導いているという話も聞いたことがあります。つてを頼って、聞いているところです。あと、美術館や図書館で、参加型のイベントをやっているところもあって、そういう情報もとっています。」
テンドウが言った。
「でもひとつ、付け加えて置きたいんですが、自分の考えているキュレーターは、いつも場にいることが最も重要なんです。いつも場にいて、季節の移り変わりでも何でも、その場の共通の話題を提供しさえすればよいのです。今この場がどういう状況かということを、カレンダーのようにみんなが確認できるようにしてもらえれば、それだけで意味があるんです。」
その日テンドウは、この定例会のほかにも、顧客とのトラブル案件の相談や、所属するチームの情報共有会議などを慌ただしくこなした。
テンドウは、いつもの通り夕方十八時すぎに会社を出て、自宅に戻った。
マダムはテンドウよりも先に着いていて、リサと夕食を作っていた。テンドウの帰宅を見届けると、マダムは入れ違いにテンドウの自宅を出た。
テンドウとリサとは夕食を食べながら、その日にあったことの話をしたり、おたがいの過去の思い出を話したりして、人目を避けて隠れている緊張感を努めて意識しないようにした。テンドウは、リサが女優であった時の話になるべく触れないように気を付けた。彼は、久しく思い出したことのない、子供の頃のことを一生懸命思い出して話した。
「私は、中学生までは神奈川県の逗子に住んでいました。体の弱い子供で、学校は休むことが多かったんですが、それでも元気な時は海岸で泳いだりしました。夕方の海岸は、波が金色に輝いて、天気のよい日には富士山が入り江の西の方にそびえて見えるんです。私はもう何年も行ったことがありません。」
「私は鎌倉には仕事で何度か行きました。ロケバスで東京から出かけて、仕事が終わるとそのまままたロケバスで東京に帰るんです。いつか一度ゆっくり歩いてみたいと思いました。」
テンドウは、自分の話がリサの女優としての仕事の話につながってしまったことを悔いた。
このように、リサがテンドウの自宅に隠れる日が、三日ほど続いて、四日目の朝、リサは珈琲をカップに注ぎながら、テンドウに言った。
「私、夜は、部屋のロックをかけていないんです。」
テンドウは意外なその言葉に驚いた。
「ロック、かからなかったんでしょうか?以前は毎晩かけていたけれど、何ともなかったのに。」
「そんなんじゃないです。」
リサは、カップをテンドウの前に置いて、話を続けた。
「私は毎晩、テンドウさんを待ってたんです。
私は、オガミ監督の時には、尊敬していた方なので、ショックでしたが、子供ではありません。ここにお世話になることを決めた時に、心づもりはしていたんです。」
テンドウは、リサの言葉の意味をはかりかねて、手に取ったカップをテーブルに置き直して、言った。
「いったい、何の心づもりでしょうか?私は・・・私は、妻を亡くしてから、今度こそは女性を幸せにしたい、女性を不幸にしない、そのつもりで生きています。私はオガミさんとは違う。自分の気持ちに負けて、あなたを不幸にするようなこと、絶対にしません。」
テンドウがむきになって言った言葉で、リサは動揺し、涙目になりながら答えた。
「ごめんなさい。言葉が足りなかったです。私のこと、本気に心配してくださる人は、テンドウさんと師匠とマダムの三人しか、この世の中にいないんです。ずっと前から、テンドウさんが毎週お店にみえるのを、お待ちしていたんです。いつも私の方に注意を向けておられるのに、気が付いていました。私を目当てに来ている男のお客様は、四、五人はいましたが、テンドウさんはそういう方とはちがって、私を食事やドライブに連れ出そうとかしないで、でも毎週欠かさず来ていただいて・・・今まで私のおつきあいした男の人は、自分が飽きてしまうと、ほかの女の人のところに去って行きました。テンドウさんはそういう人と全然違うタイプの、誠実な方だと思っていました。
私は、奥様のベッドに休ませてもらって、思いました。奥様は、幸せな方だったって。テンドウさんは、自分は奥様を幸せにできなかったという話をされましたが、そんなことはないです。本に囲まれて独りで過ごすのがお好きな奥様を、独りにさせてあげたのですから、奥様は幸せだったと、うらやましいと思いました。でも、私は、奥様のように聡明ではありません。自分の目の前にテンドウさんがいないと、自分の耳でテンドウさんのお声を聞かないと、寂しくてたまりません。
本当のことを言うと、毎晩、本当は独りで寂しくて、あまり寝られなかったんです。テンドウさんが来てくださればいいと思って、待っていたんです。私の方からテンドウさんのお部屋に行くと、テンドウさんの本当の気持ちがわからなくなってしまいますから、待つことにしたんです。テンドウさんに来てほしかったんです。それで鍵をかけなかったんです。」
「言葉を荒げてしまって、こちらこそ、ごめんなさい。もう泣かないで。おっしゃる意味がわかりました。
私は、私のやり方で、あなたを大切にしたいのです。私にとって、あなたは天女です。初めてカフェ・リュビでお目にかかった瞬間から、そう思っています。それに、お互いにふさわしい距離というものもあります。私はあなたの親御さんの世代ですから、身分相応にわきまえていなければなりません。せっかくの今の関係が壊れてしまうと、私は生きてゆけない。それが怖い。わかってください。」
「私は天女ではありません。この世に生きる一人の人間です。映画の世界を辞めて、過去を捨てて、この世で再出発したと思ってます。私も奥様みたいに聡明な人間になれるように、がんばってみます。でも、自分には、心と体とが別々だとは、どうしても思えないんです。
私、テンドウさんのことを諦めませんから。女優を続けるのは諦めましたが、あなたのことは諦めません。」
テンドウは、その言葉を聞いて、自分の心に今まで感じたことのない、熱いものが沸き起こっていたが、努めて声に表さないように、静かに答えた。
「今のお言葉だけで、私は天にも昇る気持ちです。でも、私はあなたが想像しているような人間ではないかもしれない。自分のことしか愛せない人間かもしれない。」
「それならば、私を愛せるようにしてみせます。私、これまで、思い込んだことはやり遂げてきました。今度も必ずそうします。」
テンドウは、その言葉を聞いて、返すべき言葉を見いだすことができなかった。そして彼は、リサはカフェ・リュビで初対面の時に思った通り、情熱の人だ、と思った。
その時、インターフォンが鳴った。マダムが到着したのであった。
リサは、普段の表情に戻って、マダムに尋ねた。
「マダムは、朝食は済ませたの?いつもご迷惑かけっぱなしで、すみません。」
「リサちゃん、いいのよ。気にしないで。今日も何が起こるかわからないけれど、できる限りのことはしましょうね。」
テンドウは、先ほどのリサの言葉が気になったが、出勤前にあらためて再開できるような話ではなく、リサも話の続きをしようとしなかった。テンドウはスーツに着替えて、七時半には会社に出かけて行った。
一方、リサは、テンドウとマダムを送り出してから、一人きりのリビングルームで、もう一杯珈琲を淹れると、朝の自分の言葉を思い返した。
彼女は、テンドウのことを諦めないと言ったのは、自分の素直な気持ちだと思った。
彼女は、女優を辞めてから、世間の好奇のまなざしから逃れるように、友人たちとも連絡を取り合うことなく今日まで独りで暮らしてきたことを思うと、これ以上さびしさに耐えることができるのか、自信がなかった。
カミヤとマダムの好意で、カフェ・リュビで働くことができたので、働いている時間はさしてさびしさを感じることはなかったが、仕事を終えて店を出ると、自分のアパートに帰っても独りなのかという思いで、しばしば帰り道の錦糸町やスカイツリーの人混みの中に身を紛らせた。
カフェ・リュビにリサを目当てに来る男性の客と、食事に出かけたこともあったが、いつ自分が元女優だということが露見するかという不安がいつも胸中につきまとった。誘われたレストランが高額の店である場合は、自分の顔見知りの芸能関係者が来ているかもしれないという危惧で、始終落ち着かなかった。
そのため、彼女にとっては、カフェ・リュビにいる時間が最も安心できる時間であった。その最も安心できる時間に、自分の過去を何も知らない様子の中年の男性が、自分の勤めるウィークデーに一回、必ず店を訪ねてきて、一杯のエスプレッソをはさんで、彼となごやかな会話を一言交わすたびに、彼女はわずかに気が晴れる思いがしていた。彼女にとっては、彼の来訪が生活のリズムになり、彼の来訪と自分の安心とが心の中で自ずと重なっていたのであった。
ところが、週刊誌報道のあった日には、彼女にとってのカフェ・リュビは、安心な生活の場所ではなくなっていた。彼女は、自分はこの店にも居られなくなるのではないかと思って、不安が募っていたところに、テンドウが思わぬ情報を持って飛び込んで来たのであった。
その時、リサは、テンドウは、少なくとも自分を傷つけない、そして本気で自分を守ろうとしていることを即座に了解した。彼女は、このように自分のことを本気で考えてくれる人に出会ったのは、自分の人生では初めてだと感じた。テンドウが自分のマンションにリサを匿うことを承知した時には、リサは本当にうれしかった。それと同時に、彼女は、自分を守るテンドウに、男らしさを見出した。彼女は、これまでも男性との交際をいくたびか経験していたが、いずれの男性にも、テンドウのような情熱を感じたことはなかった。つまり、その時、リサにとって、テンドウは物静かでやさしい笑顔の常連客ではなく、自分と向き合う男性になった。
リサが、初めてテンドウの自宅に泊まった晩、就寝のために自分に充てられた部屋に入ってロックのサムターンに手を掛けた時、胸中につぎのような疑問が湧き起こった。奥さんは、毎晩ロックをかけても、テンドウさんが自分の傍から離れてゆくことはないと確信していたのかしら?それはテンドウさんを信頼していたから?本当のところ、ご本を読んで独りで過ごす時間が大事で、テンドウさんのことは気にしていなかったんじゃないの?テンドウさんはそれで毎晩平気だったの?
リサは、自分は聡明なタイプではないから、二人のことが自分にはわからないのだと思った。
彼女は、自分の出演した二作目の映画のことを思い出した。そのあらすじは、リサの記憶ではつぎのようなものであった。
主人公の文学青年は、同じ文学サークルに属する作家志望の女性に魅かれて、交際を申し込む。二人はいつも、大川端で昼下がりに待ち合わせる。そして、隅田川の向こう岸に冷蔵会社の工場の建物が見える場所で、二人は夕方まで会話をする。その会話は、マラルメと藤原定家とはフィクションにおいて共通なところがあるとか、婚姻はお互いの社会保障以上の法的な意味がないとか、知的で前衛的ではあっても、リサにとってはおよそ男女が二人きりで交わすような会話とは思えないようなもので、二人は手をつなぐこともないのであった。主人公は、作家志望の女性とのそのような関係の一方で、悪所通いを覚えるが、やがて彼女はそのことに気づいたらしく、ある日、彼につぎのように言っ。
「あなたのフェミニズムがよくわかったわ。あなたがわたしにおっしゃっていることは、結局フィクションで、本当のあなたではないのね。」
主人公は、つぎのように答える。
「どうやら、気が付かれたようだな。あなたにも、自分にも、もう嘘はつけないな。」
「あなたは、初めて、嘘でない本当のことを言う気になったのかもしれないわ。あなたが今、本当に思っていることを言ってごらんなさい。わたしも、本当に思っていることを言うわ。」
そこで、主人公は、ためらいながらも、つぎのような言葉を口にする。
「おれは、・・・あなたを支配したい。思うようにしたいんだ。」
女性は表情を変えずにつぎのように答える。
「わたしは、あなたを所有したい。自分の傍に縛り付けて、自分にかしづいてもらいたい。だから、・・・」
主人公は、女性の言葉を遮って、唇に接吻をする。女性は抵抗もしなければ、受け入れもしない。女性は短い接吻が終わると、つぎのように言う。
「だから、あなたと私とは、すれ違ったのです。たった今。」
主人公は、女性の言った言葉の意味を独りでしばらく考えてから、答えた。
「それが男女の関係の現実という意味かい?」
「そうよ。お互い、嘘をついてはいけないわ。男女の関係の現実は、二つの自分勝手がすれ違うだけでしょ。」
主人公は、その言葉にどう答えてよいかわからず、口ごもった。
女性は、言葉を続けた。
「あなたも、自分に嘘をつかない文章を書いた方がいいわ。」
主人公は、その言葉を聞いた途端、一目散にその場を走り去る。
それからの彼は、それまでの外国文学の翻訳調の作風を捨てて、一切の虚飾を排し、自分の欲望の様相を赤裸々に描くことに固執する。その後、彼は彼女と会うことはなく二年ほどの月日が経ち、彼は彼女が独身のまま郷里で病死したことを知る。彼の作品は、自分は嘘をついていないということを、彼女に何とか肯定してもらおうとするかのように、ますます自分の欲望の醜さの描写に固執してゆく。
リサは、このようなあらすじを思い出して、テンドウは、一目散にその場を走り去るかわりに、ロックされた扉に隔てられた自分の部屋に隠れたのであろうと想像した。彼女には、奥さんが扉に毎晩ロックをかけることは、彼にとってむしろ救いだったのではという気さえした。
そして彼女は、自分がテンドウならば、居てもたってもいられずに扉を開けて入ってきて、リサを抱きしめるだろうに、と思った。リサはテンドウの情熱に、自分の情熱をもって応えるつもりであった。それは彼女の頭が命じることではなく、彼女にとり一つのものである心と体とが求めることであった。だから、テンドウを諦めないという言葉は、彼女にとって当然の帰結であった。
彼女は、心の内でつぎのように叫んだ。
「みんな、お利巧だけど、ちっともわかっていない。二人は結局すれ違うのかもしれない、でも、だからこそ、お互いに惹かれるんじゃないの!どうして、おしまいにしちゃったのよ?」
その日の夕方、テンドウは、十八時少し前に会社を出た。
テンドウが自宅のマンションの玄関を入ろうとすると、道路に十人ぐらいの、一目で報道関係者とわかる人々がいるのに気付いた。小型のテレビカメラを担いでいる人も混じっていた。テンドウは、しまった、居場所が露見したのだと悟った。
テンドウがマンションの玄関を入ろうとすると、報道関係者は一斉に彼を取り囲んだ。
「リサさんを隠していることはわかっています。あなたとの関係を聞きたい。」
テンドウは、即座に腹を決め、ここ四日間考え続けてきた対策を実行することにした。
「わかりました。皆さんの質問に答えます。ここではマンションの住人の邪魔になりますから、すぐそこの十間橋で取材に応じます。そこで一時間後でどうでしょうか?」
こういう場合の例のとおり、取材代表に買って出るつもりらしい、大手新聞社の腕章を付けた記者が言った。
「わかりました。一時間後に十間橋で記者会見ということで了解です。」
テンドウは、自宅に戻ると、リサがマダムといっしょに、不安そうに彼の帰りを待っていた。
リサが言った。
「今から三十分ぐらい前に、記者がインターフォンを鳴らしたんです。私は応対に出ないようにしていましたが、帰る様子がなくて、それからも何度もインターフォンを鳴らしてます。テンドウさんの携帯電話に連絡しなくちゃと、二人とも今やっと気づいたところでした。」
「意外と早くみつかってしまいました。こういう時は、開き直って記者会見に応じた方がいい。それで、相談なんだけど、」
テンドウは一旦言葉を切ると、リサの目をしっかりと見て、四日間考えてきた腹案の説明を始めた。
「もともと、リサさんはオガミ監督の被害者なんだから、こそこそ隠れる理由なんかないんだ。でも、芸能人だから、マスコミがそれで放っておいてくれることは期待できない。それで、どうすればいいのか、リサさんが来た日からずっと考えていたんだ。
それで、リサさん、演技でいい、この場だけのことでいいから、リサさんはテンドウの妻だということにしたらどうだろう?私はリサさんを妻として紹介し、リサさんもそうだと答えるんです。そして、リサさんは、オガミ監督の事件は、世間をお騒がせして申し訳ない、昨日の週刊誌の報道は事実であるが、自分は今更この問題を掘り返したくないので、誰のことも責めるつもりはない。今は結婚して、全くの一市民になっているので、そっとしておいてほしい、そう言ってください。半年前から交際が始まり、今月の初めに結婚したことにしてください。そうでないと、愛人になっているんじゃないかとか、どんどん悪い方に話が展開してしまいます。いいですね。この場の演技だけ、形だけのことです。嘘も方便です。それから」
テンドウはきっぱりと続けた。
「それから、マスコミの騒ぎがひと段落したところで、正式に訴訟を起こしましょう。泣き寝入りはやっぱりいけません。」
マダムはテンドウのストーリーに驚いて尋ねた。
「たしかに、今は一市民だ、という話に持って行った方がいいということはわかりますが、結婚したことにするのは、後でお二人とも困りませんか?」
リサはマダムの言葉を遮って、きっぱりと言った。
「テンドウさん、わかりました。おっしゃったとおりにします。記者会見に出ましょう。」
「マダムは、温かい缶珈琲をそこの角の自動販売機で二十本ぐらい買って、十間橋まで持ってきてください。私が合図したら、記者に一本ずつ配ってください。」
リサは化粧を手早く直すと、カフェ・リュビで働く時の服装になった。キャップは被らなかった。
「堂々と、手をつないで出ます。悪びれないことが肝心です。」
テンドウとリサとは、手をつなぐと、記者達の待つ十間橋に向かった。
十間橋まで歩きながら、リサはパンツの後ろのポケットからサングラスを取り出して、顔にかけた。
彼らが到着すると、カメラのフラッシュが稲妻のように一斉に光った。
テンドウは、十間橋の欄干の前で、スカイツリーを背にしてリサと並び、リサはサングラスをはずした。リサは女性としては背の高い方であったが、テンドウは痩せた長身で、リサよりもさらに頭一つ分高く、テンドウの計算のとおり、二人の姿はイルミネーションで銀色に光るスカイツリーとよく調和した画像となった。
二人は、記者に一礼した。まずテンドウが発言した。
「これから記者会見に応じます。私は、ヒビノ・リサの配偶者の、テンドウ・ユウと申します。何も隠し立てするようなことはありませんので、正直にお話しいたします。」
続いて、リサが発言した。
「私は、テンドウ・ユウの妻のリサです。このたびは世間をお騒がせしており、まことに申し訳ありません。」
彼女は深々と頭を下げた。そして彼女は発言を続けた。
「昨日の週刊誌報道は、事実です。でも、今更問題を蒸し返すつもりはありません。私はオガミ監督を尊敬していましたし、今も尊敬しています。私はもう芸能界の人間ではなくて、普通の市民の一人です。テンドウにも迷惑がかかりますので、そっとしておいてください。」
テンドウは言った。
「これから質問を受け付けますが、その前に一言だけ。寒い中ですので、缶珈琲を用意しましたから、よろしければどうぞ召し上がってください。」
マダムは、記者の一人一人に温かい缶珈琲を手渡した。
記者が珈琲で一服入れたところで、テンドウが発言した。
「それでは、ご質問を承ります。できましたらば、ご所属の報道機関とお名前をおっしゃってから、質問してください。」
質問は、まず、テンドウの職業は何か、いつ結婚したのか、リサはどこに隠れていたのか、どこで知り合ったのか、といったものが続いた。
テンドウは、調べればわかることなので言うが、自分は東都電鉄に勤める会社員である、結婚は今月初めであった、リサはある珈琲店でアルバイトをして暮らしていたが、勤務先は迷惑がかかるので伏せさせてもらう、テンドウはその勤務先の常連客で、そこでリサと知り合った、と答えた。
その珈琲店はカフェ・リュビではないか、という質問が出て、テンドウは、一瞬黙って考えてから、
「お調べになったとおりです。」
と答えた。
リサがオガミ監督に引き続き、また年配の男性をターゲットにしたのではないか、という質問もあった。テンドウはまじめな顔でつぎのように答えた。
「私は自分ではまだ若いと思っていますので、ただいまのご質問の意味は、はかりかねます。」
この答えに、何人かの記者から笑い声が漏れた。
例の「サングラスの女事件」について、なぜリサは刑事告発や損害賠償請求訴訟を行わなかったのか、所属事務所に止められたのか、という質問には、リサはつぎのように答えた。
「先ほども申しあげましたとおり、私はオガミ監督を尊敬していましたし、今も尊敬しています。自分の名誉のためには弁護士さんを立てるべきではないかと考えたこともありましたが、事務所に迷惑がかかることや、裁判の過程でいろいろなことを言い合わなければならないことを想像すると、自分としては耐えられませんでした。事務所に止められたということではなくて、自分の判断です。」
この回答には、それはリサの方にも落ち度があったということか、という質問が続いた。リサはつぎのように答えた。
「落ち度という意味がよくわかりませんが、私が誘惑したのではないということは、週刊誌報道で明らかになったとおりです。私は、オガミ監督は紳士だと信じていましたので、とても残念です。」
この回答に、別の記者が質問を重ねた。
「そこがわれわれは腑に落ちないんです。それならば、なぜ、世間に出て来て、堂々と自分に落ち度がないと、主張をしなかったんですか?やはり後ろ暗いことがあるんじゃないですか?」
「それは・・・」
リサは一瞬答えに迷ったが、思い切って続けた。
「それは、オガミ監督を傷つけたくなかったのです。」
「ということは、あなたはオガミ監督を愛していたと。だからオガミ監督を誘惑したと、そう解釈していいですか?」
「そうではありません。オガミ監督に、芸術活動が続けられるようにしてあげたかったのです。」
他の記者達からも、同じように、リサの方に責任があったのではないかという質問が繰り返された。
同じような問答が五回ほど繰り返された後で、テンドウは、問答の間を割って言った。
「あの事件の当日、事実はどうだったかは、証拠のない話です。もしも憶測だけで記事にされるのであれば、今度は弁護士を立てて、名誉のためにおたくと争います。この件は、本人が精神的に深く傷ついていることです。そのために、映画女優を辞めて、今日まで一人で暮らしてきました。どうかこれ以上はご勘弁ください。」
今度は別の記者が質問した。
「リサさんの芸能界への復帰の可能性はあるのですか?」
リサはつぎのように答えた。
「復帰は全く考えていません。映画の世界では、みなさまに勉強させていただいて、感謝しています。勉強させていただいたことを自分の宝にして、これからの人生を歩んでまいりたいと思っています。」
記者会見は、一時間ほどで終わった。
最後に、テンドウが挨拶した。
「本当に、このたびは世間をお騒がせして、申し訳ありませんでした。これからは、リサは普通の市民として暮らします。どうかそっとしておいていただきますよう、夫としてお願い申しあげます。寒いなか、本日はありがとうございました。」
記者は次々に引き揚げて行った。
テンドウ、リサ、マダムの三人も、マンションに戻った。
テンドウが言った。
「こういう記者会見は、堂々としているのが一番です。これからまたしばらくは、あること、ないこと、いろいろ書かれるでしょうが、半月とは続かないと思います。」
「テンドウさん、ありがとうございます。私独りではとても記者会見など、耐えられないところでした。」
「リサさんの演技は、さすがでした。質問の様子からは、たぶん、記者も、結婚しているというところは疑っていないでしょう。」
リサは、テンドウの言葉を聞いて、思わず言い返した。
「あれは、演技ではないです。演技なんかじゃないです。」
マダムが尋ねた。
「リサちゃん、それ、どういう意味?」
リサは、マダムの質問には答えず、テンドウの目を見つめて、気持ちが堰を切ったかのように、つぎのように尋ねた。
「テンドウさん、さっきの記者会見でのお話、全部、嘘ですか?夫としてお願いするって言ったけど、あれも嘘?ねえ、どうなの?」
テンドウは答えた。
「嘘ではありませんが、一時のための方便です。あなたと本当に結婚できるなんて、思っていません。」
リサは尋ねた。
「テンドウさん、私のこと、嫌いですか?」
「もちろん好きです。でも、それは結婚とか、そういうことではないんです。もちろん、しばらくの間は、形だけの夫婦であっても、あなたのことは夫として守ります。それだけは嘘ではなくて、本当です。」
リサの大きな目から、突然、ぽろぽろと涙があふれ出した。
「テンドウさん、『本当です』って言いましたよね。それならば、しばらくの間でなくて、ずっと私のことを、夫として守ってくれませんか?」
テンドウは、急にリサの右手をとって、その甲に、自分の左手の甲を並べた。
テンドウの手は、浅黒く、血管が浮き出て皮膚が薄くなっていた。
リサの手は、やや赤みを帯びた白で、しっとり暖かく艶やかであった。
テンドウは、リサに言った。
「ほら、手を見てごらん。二人はこんなに違っている。年齢の差は、目に見えてはっきりしている。
結婚しなくたって、私はずっとあなたを守っていることができます。それは約束する。私は、結婚の相手としてはふさわしくありません。」
リサは、その言葉にたたみかけるように答えた。
「だって、二人が違っているから、一つになれるのよ。」
「一つになったって、その時間はあっという間に逃げて行ってしまう。そうすると、また違う二人に戻るんだ。私はその時がいつか来ることがわかるんだ。」
「一つになった時間は、逃げて行ってしまうけれど、だから美しいのよ。そして、違う二人に戻っても、そのままで一つなのよ。私はそう信じているのよ。テンドウさん、大丈夫、安心して。あなたに悲しい思いをさせないわ。」
「私は、あなたに悲しい思いをさせたくないんだ。」
「テンドウさん、そんなこと心配しないで。一度でいいから、私の言うことを信じて!」
テンドウは少し考えてから言った。
「一度でいいから・・・そのままで一つ・・・」
「テンドウさん!大丈夫なのよ!」
テンドウは、静かに答えた。
「わかりました。あなたの言うこと、信じます。」
「よかった!」
リサは、しっかりとテンドウの浅黒い右手を両方の掌で包んだ。
彼女は続けて言った。
「私、実は、記者会見の間、気にしていたのは、このことばっかりだったの。もしもこれが記者会見をしのぐためだけの嘘だったら、どうしようと思ってたの。また独りぼっちになると思ったの。本当で、よかった。
だから、私、テンドウさんの、形だけじゃなくて、本当の奥さんになっていいってことよね?しばらくなんかじゃなくて、ずっと奥さんでいていいのよね?」
脇で二人の会話を聞いていたマダムは、やっと事態が飲み込めた。
「リサちゃん、テンドウさんの本当の奥さんになりたいのね。形だけじゃなくって、本当の奥さんになるつもりなのね。しばらくじゃなくて、ずっとなのね。」
リサは頷いた。
続いてマダムはテンドウに尋ねた。
「テンドウさん、リサちゃんを本当に奥さんにすると思っていいんですよね。」
テンドウは、今度は先ほどと打って変わった、はっきりとした口調で答えた。
「はい。」
テンドウは、リサの目をじっと見つめて言った。
「リサさんが今朝言った通りになりました。私は、あなたを愛することができました。ありがとう。私と結婚して、ずっと一緒に暮らしてくれますか?」
リサはその言葉を聞いて、涙に濡れた顔で、テンドウの首に飛びついて言った。
「ありがとう、うれしい!私はあなたの奥さんになります。ずっと一緒に暮らします。」
テンドウは、リサの肩を両手でやさしく抱擁した。
その時、カミヤからマダムに電話がかかった。
カミヤは自宅に帰っていて、インターネットの動画で、記者会見の様子が報じられたのを見たのであった。マダムはカミヤと短い会話を交わしていたが、やがて電話を切ると、テンドウとリサに言った。
「動画の記者は、最後にカメラに向かって、『まあ、お幸せに、の一言ですね』って結んでいたそうです。カミヤは、インターネットやSNSで、報道のフォローを続けています。」
テンドウが言った。
「まあ、半月ぐらいは、いろいろ言い立てられるだろう。でも、もう芸能界の人ではないのだから、それ以上にはならないだろう。」
マダムが続けた。
「カミヤは、それはともかく、『お二人の結婚は本当か』って聞いたので、そうなりました、と答えておきました。」
マダムは、二人に気を使って、すぐに自宅に帰って行った。
テンドウとリサが二人きりになると、テンドウが言った。
「私のことはリサと呼んで。私はテンドウさんのことをこれから、あなたって呼びます。」
「じゃあ、リサ、こっちにおいで。」
テンドウはリサを自分の部屋に入れた。
「ベッドのほかには本ばっかりで、殺風景でしょう。私は、詩を作るのだけが趣味で、このノートに作品を書いています。若い頃にはよく書いたんだけど、何十年も中断していて、この春にカフェ・リュビを初めて訪ねたときから、再開したんです。」
「たぶんこういう生活をしている人じゃないかと思ってたわ。想像どおりよ。私は、二本目の映画では、詩の朗読のシーンを撮ったことがあるの。」
「私は、リサに自分と同じ趣味を持ってもらおうとは思っていない。同じような者同士は、幸せになれるとは限らないから・・・」
「私、あなたのこと、もっと知りたい。あなたも、私のこと、もっと知って。
でも、知るための時間はこれからたっぷりあります。知る前に、もっと急がなきゃいけないことがあるわ。大至急よ。」
リサは、テンドウとわずか十センチほどの距離で向き合って立った。彼女は、テンドウの厳粛な表情の目を、長い睫毛に涙の残りのきらきら輝く目で見上げながら言った。
「早く私を抱きしめて。さあ、早く。大至急よ。私、待ってたのよ。」
テンドウは、一呼吸ためらった後、慣れない手つきでリサの胴に手を回し、それから徐々に力を込めて、リサの体を抱きすくめた。テンドウを見上げるリサの瞳が、リサを見下ろすテンドウの瞳を見つめた。リサは、テンドウにささやいた。
「ずっとこうしていて。独りで生きてきたけど、もう限界だったの。私のこと、離さないで。」
「だいじょうぶ。ずっと離さない。安心して。もう独りにはさせない。」
テンドウは、自分の両腕にリサの体の重さと暖かさを感じた時、つぎのように悟った。
今まで、自分は大きな思い違いをしていた。自分は、愛というものがどういうものなのか、これまで全く知らなかった。愛があって初めて本物の官能性があるのだ。愛のない官能性は、命のない抜け殻だ。愛の何たるかを知らず、本物の官能性も知らなかったから、自分は、官能性という人間の一大事を、早々と卒業したもののように、自分の意思で容易に取り扱えるもののように思っていたのだが、それは不遜だった。
愛と官能性とは、二つの魂が一つの場を共有することで、初めてこの世に表れるのだ。愛と官能性と場とは、愛のもとにおいて三位一体だ。愛から官能性あるいは場を切り離すことはできないのだ。リサは、愛を求めていたからこそ、ロックをかけなかったのだ。愛は、二人が場を共にすることを必ず伴うのだ。愛のない偽物の場や、愛のない偽物の官能性はあり得るが、それらの逆はあり得ないのだ。少なくとも、リサは、テンドウの愛を信じていたのだ。今この時のように、二人それぞれが、自分を相手に捧げて、しっかりと目と目とを、唇と唇とを、心臓と心臓とを重ね合うこと、すなわち二つの魂が一つの場を共有すること、これが愛そのものなのだ・・・
テンドウは、初恋をした少年が気付くようなことを、自分はこの年齢になって、初めて気が付いたことに、恥じらいを禁じ得なかった。
彼は、自分の魂が、自分の意思を離れて、リサの魂と混じり合い、あたかもエスプレッソとミルクとが珈琲カップの中で融合するように、一つの場の中でお互いの区別を喪失してゆくのを感じた。そして、彼はリサをいつまでも抱擁し、リサは彼の腕の中でいつまでも抱擁され続けた。
翌日の土曜日に、テンドウとリサとは、区役所に足を運んで、婚姻の手続きを行なった。そして、二人は手をつないで、堂々と街を歩き、買い物をし、昼食をし、鐘ヶ淵のリサのアパートに行って、二人の持てる限りの荷物を持ち出した。二人は、街中で、自分たちにたびたびカメラが向けられているのに気が付いたが、意に介しないことにした。
それから、リサは何年も音信の途絶えていた実家に電話をかけて、結婚したことを告げた。テンドウも電話口に出て挨拶したが、リサの父親は、静かに暮らしているので、もう自分たちとは関わらないでほしい、とだけ言って電話を切った。
テンドウは、時々スマートホンで最新の報道やSNSをチェックしたが、他人が幸せになったという話はニュースバリューが小さいのか、それとも報道機関が定休日だからなのか、テンドウが懸念していたようなスキャンダルの展開にはなっていないようであった。
日曜日には、二人は築地に出かけ、築地本願寺で先妻ヒサエの霊前に再婚の報告をした後、カフェ・リュビのカミヤ夫妻に、あらためて挨拶に行った。カミヤ夫妻は、その二週間後の土曜日に、閉店後の店内で、ささやかな祝宴を開くことを申し出た。リサは、職場はそれまで休暇をとることになった。
ヤマイヌカフェでは、ツネムラが月曜日の朝事務所に到着すると、自分の机に荷物も降ろさないで、サカムラの机にやって来て、自分のスマートホンに映ったテンドウの姿を見せた。
「サカムラさん、これ、東都電鉄の『家元』じゃないですか?」
「おれもそう思った。旗竿みたいに背が高いし、耳が大きくて立っているし、似ているなと思って動画を見ていたんだけれど、本人が記者に東都電鉄の社員だって言ったから、まちがいないよ。」
「いつも『お嬢』の隣で困ったような笑顔で座っている印象しかないので、こんなに衆人環視の場所で堂々と奥さんを守るような人とは思ってもみなかったです。」
「おれも大きな会社に勤めていたことがあるが、あの人は勤め人としては毛色が変わった人だとは思っていたんだ。」
「『家元』は、今頃会社で何と言われているんでしょうね。われわれとの定例にはこれからも出るんでしょうかね?」
「それは、出てもらわないと困るね。新しいカフェの開業まで、もう二か月ないし、そのうえ新しいカフェの『家元』がいないと、たちまちコンセプトが崩れて、変なものになりかねない。」
「定例で顔を合わせたら、何と言いましょうか?自分はくすくす笑っちゃうんじゃないかと心配です。」
「何にも知らなかったような顔をし続けるほかは、ないだろう。」
「それで、カフェ・リュビの名前が出ていましたね。」
「おれはそっちの方でもっと驚いたよ。カフェ・リュビはおれたちとシモムラ紹介で同僚だった、カミヤの店だもんな。今度の話に巻き込まれて、迷惑していなければいいと思っているんだ。」
サカムラはそう言いながら、自分の言葉で何かに気が付いたらしく、ぽんと膝をたたいた。
「そうだよ、そうだ。『家元』は、行きつけのカフェがあるけれど、名前は言えないって言っていたよな。それはカフェ・リュビだ。『家元』の新しいカフェの着想は、カフェ・リュビから得ていたんだ。」
「サカムラさんは、カフェ・リュビには行ったことありますか?」
「カミヤとは、年賀状はやり取りしているが、結局お互い独立する時に京都の上七軒で飲んでから、会ったことがないな。今は向こうも立て込んでいるだろうから、しばらくしてから行ってみようと思う。」
「インターネットでカフェ・リュビを紹介したブログの記事を読んだことがありますが、
『てきぱきとバナナジュースを作る、スタイル抜群の店員さんがとってもすてき!』
とか書いてありました。たぶん、その、スタイル抜群ですてきな店員さんが、『家元』の奥さんでしょう。何ともはや、うらやましい・・・でも、うちの新しいカフェは、ああいう個人店舗の形態とはずいぶん違いますね。」
「たしか『家元』は、カフェ・リュビには、『夢』があるところがほかの店にない特徴だ、と言ってたな。だから、彼にしてみれば、今、新しいカフェでやろうとしている、キュレーターの仕事でも、場に集まる人になんらかの『夢』を共有してもらうことが大事ということなんだろう。」
「『夢』といえば、元女優で親子ほど年の離れた奥さんをもらうことからして、自分に言わせれば、夢のまた夢ですね。」
「あの人自身、何かしらの夢をあの年まで持ち続けてきたからこそ、ああいう巡り合わせになったんだろう。やっぱり、滅多にいないタイプの人だな。」
テンドウは、その月曜日、東都電鉄にいつもの時間に出勤した。本社の事務所に入るには、オフィスフロア共通のホールに一旦上がって、セキュリティゲートを通ってエレベーターホールから高層階用のエレベーターに乗ることになっていた。
彼がエレベーターホールに入ると、待っていた十人ほどの先客が、ほぼ同時にテンドウの顔を見て、すぐに目を背けた。
オフィスに入るところには、会社受付があったが、二人の受付嬢は、テンドウが自分たちの前を通り過ぎると、すぐに何か一言交わして、きゃっきゃっという笑い声を立てた。
彼がいつものように、
「おはようございます。」
と言って自席に座ると、先に来ていた上司が、テンドウを部屋の隅に手招いた。
「テンドウさん、たいへんだったね。朝一番で、広報部長から、こんな話聞いていない、上司なのに何も知らなかったのか、って言われて、困りました。あまり若い者の肝を冷やさせないでください。記者が広報部を通じて取材を求めているらしいです。」
「私事で世間をお騒がせして、申し訳ありません。」
「あとで広報部が話を聞きに来るといっていましたから、つきあっていただきますよ。その時にお話はまとめて聞きます。」
「うけたまわりました。」
テンドウが自席に戻って、パソコンをチェックすると、朝七時すぎに、彼の同期で社長になっているクマガイから電子メールが入っていた。その文面はつぎのとおりであった。
「結婚、おめでとう!大恋愛だな。今や、東都電鉄の社員の中では、おまえはおれなんかよりも有名だろう。記者対応の手際がよかったみたいだけれど、いったいどこで覚えたんだ?
これから人事や広報が仕事柄いろいろうるさいことを言うかもしれないが、最後のところはおれがうまく納めるから、安心しろ。
近々、お祝いの席を設けるよ。本当は、奥さんにも会ってみたいが、そっとしておいた方がいいかな?」
テンドウは早速返信をしたためた。
「このたびは世間をお騒がせしてすみません。暖かいお言葉、いたみいります。世間の風は覚悟していたつもりで、耐え忍ぶしかないと思っています。お祝いの会、まことに恐縮です。月日が経って落ち着いたら、同期のクマガイに会ってくれないかと、家内に聞いてみます。」
クマガイの電子メールの次には、東都映画の社長のヤマザキからの電子メールが入っていた。
「おめでとう!木曜日におれのところに来た時、おまえが妙にそわそわしていたわけがわかったよ。金曜日の記者会見のすぐ後で、奥さんが所属していた事務所のタカギさんから電話が入って、何とか奥さんに会わせてくれないかと頼まれたけれど、おたくはスターにするつもりの女優を守れなかったんだから、恥の上塗りはやめておけと言っておいた。タカギさんがそちらにアプローチしてきて困るようなことがあれば、おれに連絡してくれ。でも、記者会見の様子を見ると、奥さんは堂々としたものだ。女優から足を洗うのは惜しいな。これはおれの素直な感想だ。」
テンドウは返信をしたためた。
「ありがとう。いろいろご心配をおかけしてすみません。また、暖かいご配慮に感謝します。困って相談することもあるかもしれないけれど、その時はよろしく頼みます。家内は、もう映画の世界に戻る気はまったくないので、そっとしておいてください。同期会は予定どおり幹事を務めます。」
その日、テンドウは、広報部のヒヤリングを受けた他は、面と向かってこのたびの一件について聞かれることはなかったが、それは上辺だけで、自分の聞こえていないところで噂されていることも感じ取っていた。テンドウに断片的に聞こえる会話の端々をつなぐと、「テンドウは年甲斐もなく若い女に手玉にとられている」とか、「前の奥さんが亡くなったばかりなのに、不謹慎だ」とか、「元女優の奥さんは金がかかるだろう」とか、「いずれテンドウは会社を辞めることになるんじゃないか」とかいった話をしているようであった。しかし、本件の事実は、一従業員が元女優と結婚したということ以上のものではないので、そのうち風は収まるはずだと、彼は自分に言い聞かせた。
テンドウの予想よりやや早く、翌週の木曜日になると、世間はその事実以上の展開がないことがわかったのか、報道のトピックにも取り上げられなくなり、勤務先の会社でも、噂をしている様子は感じられなくなった。
その日の午前十一時に開かれたカフェの定例打合せでも、サカムラやツネムラは、テンドウの結婚の話を持ち出すことはなかった。ただし、テンドウは、打合せの最中に、何度もツネムラと視線がぶつかった。
定例打合せは昼前に終わった。
席を立とうとするテンドウを、サカムラが、
「ちょっとお話があります。」
と呼び止めた。
テンドウは、何の話だろうといぶかしむ様子のヨシハラに、先に戻るように言って、座席に座りなおした。
「お話はなんでしょうか?」
サカムラは、ツネムラと顔を見合わせてから言った。
「カフェ・リュビだったんですね。テンドウさんの行きつけのお店は。」
「報道をご存知でしたか。世間をお騒がせして申し訳ございません。」
サカムラは、頭を下げようとするテンドウを遮って、言った。
「カフェ・リュビのカミヤ、ご存じですよね。彼はわれわれと、シモムラ商会で同僚だったんです。カミヤと私は仲がよくて、勤めていた時は、よく昼はいっしょに食事をしていました。テンドウさんのおっしゃる、『夢』のある店というのは、カフェ・リュビのことだったんですね。具体的にどういう店だったのか、やっとわかりました。そのことをお伝えしたくて、お引止めしたんです。」
「ああ、そうだったんですね。カミヤさんが以前は美術の先生だったという話は、家内から聞いたんですが、シモムラ商会の話はまだ聞いていませんでした。」
「仲がよい友達というのは、かえってお互い安心してしまって、音信が途絶えるものです。彼にはもう何年も会っていません。カフェ・リュビは、雑誌の記事に出ていたのは読みましたが、私自身は訪ねたことはまだありません。あいつのことですから、初志を貫徹しているのでしょう。それで、これからがお伝えしたいことなのですが、カミヤは、自分の店のコンセプトは、世阿弥の花だと言っていました。」
「なるほど・・・わかります。そうだったんですね。壁に牡丹の絵があって、店の真ん中にはいつも季節の花が大きな壺に活けられていますから、花がコンセプトに関係することはわかっていたのですが、世阿弥の花だったんですね。それで、カミヤさんのお仕事が舞台芸術になっているわけですね。私が頻繁に訪れても飽きることがないというのは、客の期待をはずさない、確かなサービスがあって、そのうえに、活けてある花や、短い会話や、サービスをする表情の中に、いつも、ちょっとした変化が遊びとして表れているからです。私が以前から言っている『夢』は、カミヤさんのめざしている世阿弥の花と同じものです。お話を聞いてよかったです。自分の中で明快になりました。」
「ご結婚のお祝いを申しあげないうちから、カミヤの店の話を持ち出して、失礼しました。しかし、自分としては、『家元』のテンドウさんに、カフェ・リュビの話をどうしてもしておきたいと思ったので、お許しください。」
「とんでもない。私にとって、とても大事なお話でした。この土曜日に、カミヤさんがお店で結婚祝いの会を開いてくださるので、その時にサカムラさんのお話をしてもいいですか。」
「もちろんです。私も世間が少し落ち着いたころに、カミヤの店を訪ねようと思っています。」
「もしもよろしければですが、土曜日の午後四時ごろご都合が合えば、カミヤさんに、サカムラさんとツネムラさんもご招待していいかどうか、聞いてみようと思いますが、どうでしょう?」
「われわれをお招きいただけるんですか?それは光栄です。もちろん、全ての予定をキャンセルして、お祝いにうかがいます。」
テンドウは、携帯電話でカミヤに連絡をとった。
「・・・それで、実は私の目の前に、サカムラさんとツネムラさんがいるんですが、電話をサカムラさんに代わります。」
テンドウは電話をサカムラに差し出した。
「カミヤか。久しぶり。上七軒で別れて六年も経ったな。今聞いたとおりで、テンドウさんにはお世話になってるんだ。今日までテンドウさんのイメージしている店がカフェ・リュビだっていうことがわからなくて、どんな店をイメージされているのか、回り道してたんだよ。それで、土曜日はお邪魔していいかな?」
カミヤは、電話の向こうで、テンドウの奥さんの方でいやでなければ、自分は構わないと言った。
テンドウは、カミヤとの電話を終えると、続いてリサに電話して、サカムラとツネムラが祝宴に参加してよいかどうかを尋ねた。リサは、
「あなたと師匠との共通のお友達ならば、私もお目にかかりたいです。」
と言って、快諾した。
テンドウは電話を切ると、サカムラに言った。
「東都電鉄の人には、祝いの会のことは内聞にお願いします。社内ではだれも声をかけていませんので。」
「承知しました。それでは、土曜日の午後四時に、カフェ・リュビにうかがいます。」
土曜日の午後四時のカフェ・リュビでは、カミヤ夫妻と、小学校一年生の彼らの息子と、サカムラと、ツネムラが集まり、テンドウとリサを囲んでの小さなパーティーが始まった。
リサは、マダムが実家から取り寄せた、加賀友禅の和服を着た。和服は、桜色の地に、梅と椿が加賀友禅独特の写実的な画法で描かれ、白銀色の地に色とりどりの宝尽くしの文様が織り出された西陣の帯がよく調和していた。
料理は、カミヤが実家の料亭に調製させて航空便で取り寄せたもので、朱色の輪島塗で鶴亀の金蒔絵のある重箱に、料理人が東京に仕出しをするというので腕によりをかけて作った加賀料理が詰められていた。店の客用のベンチには、やはりカミヤが実家から取り寄せた藍色の毛氈が敷かれていた。
写真撮影が趣味のツネムラは、午後三時きっかりに店に来ると、ビデオカメラを三脚に据え、自分の一眼レフのカメラを試した。
サカムラは、最高級の珈琲豆であるパナマ・ゲイシャの極品を、特別なつてを頼って入手して、自ら焙煎して持参した。
マダムは、サカムラの持参したパナマ・ゲイシャをドリップして、いつもはカフェで客用に使っている、能の「高砂」の詞章の書き込まれた碗に注ぎ、テンドウとリサとの固めの杯とした。カミヤ夫妻の娘が、新郎と新婦との間で、碗の橋渡しをした。
テンドウが言った。
「本日はみなさんにお祝いしていただいて、ありがとうございます。ここ一週間余りの間に、こんなに大きな変化が生まれるとは、予想もしていませんでした。でも、振り返って考えると、このようになるべくして、全ての事が運んできたのだと思います。」
リサがそれに続けて言った。
「記者会見を開いた十間橋の上で、私の人生も大きく転換しました。堂々と世の中を歩けるようになったのは、あの時の主人の決断のおかげと思っています。」
サカムラが言った。
「東都電鉄の『家元』には、古い言い方ですが、男気を感じて、大いに心が動きました。しかもそれがカミヤの店が関わっていたなんて、まったく不思議なつながりです。きのう、久しぶりに、われわれの師匠にあたるシモムラさんに電子メールを送って、この一件の経緯を伝えたら、けさ、こんな返事が来ましたので、読み上げます。
『あの記者会見、自分もテレビで見たけれど、女の子がカミヤの店の子で、お相手はサカムラ君のお世話になっている方というのには驚いたよ。自分は若いころに、歌劇団の花形女優とつきあいがあったのを芸能誌にすっぱ抜かれて、えらく苦労したからわかるが、一般の人と結婚したとなると、もうそれほどは騒ぎようがないだろうな。家元さんの一世一代の記者会見、リサさんを救いたい一心が自分にも伝わって、まったくもって立派なものだった。リサさんも、こんなにまでして愛してくれる旦那さんはほかにはいないよ。お祝いをさせてもらいたいから、サカムラ君が取り次いで、渡してほしい。お二人には、一度ぜひお目にかかりたいと、伝えてほしい。』」
テンドウがそれに答えて言った。
「シモムラさんのお言葉、とても光栄です。お礼状を二人で書かせていただきます。珈琲を仲立ちにして、カミヤさんご夫妻、サカムラさん、ツネムラさんを含めた、われわれ全員の出会いが生まれたのは、まったく不思議なことです。」
カミヤは、大きく頷いて、テンドウの言葉に続けて言った。
「まさに、たかが珈琲、されど珈琲、です。」
完
この小説はフィクションです。登場人物や団体は実際のものには関係ありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
