
FF14 Origin Episode -The Ghost in the Machine- Cp1
Chapter 1
0.
はじめに聞こえたのは轟、という音だった。
知覚できたのはそれだけだった。
兵士の体がバラバラに弾け飛ぶ。
眼前にいたその男は赤と黒で染色された内容物を撒き散らしながら、過去形で表現されるべき物体に変わっていった。
瞬間。
僕の体は宙に浮いていた。
僕にはそれが砲撃によるものだとわかった。
海の向こうに白煙を吐き出すガレオン船が見えたからだ。
敵味方関係なし。巨人は白砂の浜を無差別に薙ぎ払った。
運良く命中しなかったけれど、近くの地面に着弾した衝撃が僕に殺到し――体は宙に浮いた。
そしてその勢いのまま海辺から陸地へと押し出された。
着弾の爆発により一時的に聴覚に障害が発生する。周囲の音が聞こえなくなる代わりに、耳の中を甲高い音が満たしていく。
着地しても勢いは止まらない。
僕の体は止まることを知らぬまま横回転を続けた。
視界が空と陸で交互に入れ替わる。別に数えようと思って数えたわけではなかったけれど、少なくとも十回以上はその入れ替わりを目にして、ようやく回転が止まった。
自然に止まったわけではない。
自分で止めたわけでもない。
太い樹木という、単純に僕の体を止める物があっただけだ。
ゆえに『優しく勢いを殺す』ことなど何も考慮されていない。
太い幹は胸と腹の中間地点を強く打った。
骨折時特有の軽快な音が聞こえなかったことだけが幸いか。
それでも打撃は相当なもので、口中に血の味が染み出してきた。内蔵に損傷があるかもしれない。
そもそも砲撃以前の戦いで僕は疲弊し尽くしている。今更骨折など気にしている場合ではない。
「ああ、くそ。最悪だ……」
左肘は曲がっていたし――先程の横回転で『痛む』どころの騒ぎではない。地獄だ。左肘に地獄が宿っている。地獄の悪鬼たちが肘で乱痴気騒ぎを始めている。
――口の端から唾液が漏れてきた。
そう思って吐き出すと、僕の知っているそれよりもずっと赤い。少なくともこれを『唾液』だと他人に信じさせるのはかなり苦労するだろう。
おや、これは思ったより重傷のようだぞ。
そういえば視界の端が心なしか赤いような。
というよりもずっと視界が狭いような。
体は知覚していないのに、地面が揺れているような。
眼帯に覆われた左目が痛むのは――いつも通りってやつだ。気にしないでいい。
「どうしてこんなことしてるんだろうな……」
脳内麻薬が切れたのだろう。全身を痛みに覆われる中、言葉は現実逃避のように零れ出た。
雲の切れ間から覗く陽光が眩しい。
海に浮かぶ島特有の刺すような光だ。
確か、あの日もそうだった。
ナナシを拾った日――。
僕がこうやって死に瀕している原因。
僕がなぜ、『元兵士で構成された傭兵団』とかいうクソ面倒くさい相手に一人で挑むことになったのか。
意識がその端っこから溶けていくにつれて、周囲の情景も溶けていく。
僕の意識は闇に溶けていくについれて、過去へと引き戻されていった。
1.
「死ね!」
その矢は、僕の頭を掠めて飛んでいった。
僕の頭髪を切り落とすことすらなく外れた。見当違いの方角に飛んでいったと形容しても間違いではない。
頭狙いは良くないな。
できるならまず、的の大きい体を狙うべきだ。
どうしても『頭を狙撃したい』というのなら、最新の注意を払って精密な射撃を心がけなければならない。
絶対に即死させたい場合、殺意に見合った実力が必要なのだ。
そういうレクチャーを目の前の男にしてあげても良かったけれど、もはや無意味だった。眉間に矢が突き刺さっている。どんな治療師が見ても「手遅れだ」と診断するだろう。
無論、僕の放った矢だった。
僕は弓を構え、次の矢をつがえている。
三十歩ほど先にいた男は死んだ。おそらく弓術士だろうが、腕は良くなかった。
それより手前、二人の男はこちらを睨みつけて動かない。手には山刀、噂に違わぬ盗賊の姿だ。
「一人殺しておいてなんだけど、投降とかしてみない? 自主的にイエロージャケットに出頭すれば、多少の減刑くらいはしてもらえると思うけど……」
「抜かせ!」
僕の警告を挑発と受け取ったのか、二人は顔を赤に染めて地を蹴った。
どちらも二十歩程度の距離が開いているが――おそらくこう考えたに違いない。
「二人で同時に攻撃を仕掛ければ、確実に仕留められるはずだ」と。
成程、近接武器を持った人間であれば最善策だろう。
相手が並の弓術士であれば間違いのない得策だろう。
けれども、目の前に立っているのは僕なのだ。
申し訳ないけれど僕を相手にするにはちょっとだけ策が足りない。
右の彼が十歩進める前に矢を射る。潮を含んだ風を切り裂いて捕食者は胸に命中した。
左の彼がさらに十歩進める前に矢を射る。一射目よりは幾分時間を消費したけれども大した差はない。こちらは狙って腿に命中させた。
二本の矢を放つのに数秒もかからない。速射は優れた弓使いの基本だ。
その点で言えば――彼らはそもそも弓術士に相対するべきではなかっただろう。
たとえ背中を見せて逃げたとしても、逃さない自信はあったけれど。
片方は命を失ったことに気づかないまま前に倒れる。彼がもし前衛の戦士だったら、この死に様を誇るべきだろう。
まあただの盗賊なわけだが。
腿を射られたミッドランダーも同様に倒れ込んだが、痛む足を抱えてその場にうずくまっている。
「いてえ……いてえよぉ……」
人選に意味はない。単純にどちらかを生かそうと思い付いたから、そのように動いただけである。
僕は彼に近づき、彼が落とした山刀を蹴り飛ばした。
いつもの作業を始めることにする。
「盗品はどこに隠した?」
彼は口を固く結んだ。
しかし瞳には迷いの色があった。当然だ、今は僕が彼の命を握っているのだから。
バイルブランド島及びロータノ海における山賊には大した種類がいない。
大抵は海賊行為禁止令の煽りで食い扶持を失った元海賊。それも、商いを始めるでもなく労働者になるでもなく、それまで通りの生活しかできない――心も頭も弱い人間だ。
――そんな臆病者のために話を単純化してやることにした。
腰からごく短い短剣を取り出して喉に突きつける。軽く皮を切ってやると、彼は身震いをする。土に汚れた顔の中で、口が動く。
「お、奥の洞窟――」
「誰から奪ったか覚えているか?」
「覚えてられるかよ……」
彼は毒づいた。
毎日毎日略奪の日々。そうだな、覚えているわけがない。僕だって数日前の朝飯の内容なんか覚えていない。こういう連中がそんなことを記憶しているわけがない。
こいつらは奪われた人間のことなど考えもしない。そこに涙を流す弱者が存在することなど、考えるわけがないだろう。
再び強い潮風が吹き、僕の髪を撫で付けた。
ここはロータノ海に浮かぶ島の一つ。バイルブランド島近くの名もなき無人島。
曇りと晴れの境界のような空から、曖昧な陽光が差し込んでいる。それは茂った南国の木々にぶつかり、木漏れ日となって僕の頭を灼く。
「だろうな」
僕は短剣を走らせて彼を絶命させた。彼は言葉にならぬ音だけを挙げて生命活動を停止した。意味のある言葉を遺さなかったのが山賊らしいと言えばらしい。
山刀と鞘を拾って奥の洞窟へ進む。
ここを隠れ家としていた賞金首たちも葬り去り、本当の無人島にしてしまった。あとは証拠として山刀を持ち帰れば、ギルドから懸賞金が出るだろう。
――僕の名はロクロ・ウタゲヤ。
ただの冒険者で、『報復代理人』だ。

道とも言えぬ林の中を進む。
他よりも人が歩いた形跡があるだけましだろうか。草地の中でもいくつか土を晒している部分があり、誰か人間がここを頻繁に通っていたことがわかるのだ。
しばらく進むと、小高い崖に行き当たった。そこには横穴が開いており、洞窟となっているようだった。
入り口に立っていても、ひんやりとした空気が奥から漂ってくる。そこそこの深さがあるらしい。
「しまった、松明なんて持ってきていないぞ」
洞窟の存在を確認できたのだから、あとはギルドに報告するだけで済むとは思うけれど――内部の確認は必要だろう。
もしも野生動物の棲家であっり、山賊によって罠が仕掛けられていたとしたら、ギルドの調査員が危険な目に遭うとも限らない。そうして他の冒険者の仕事を増やすのも癪だ。調査を済ませておけば、報酬の増額交渉もできるだろうという打算もある。
辺りを見回すと、地面に布の巻かれた木切れが落ちていることに気がついた。松脂も塗られているようだ。
山賊のものだろう。僕はそれを手に取り懐から取り出した燐寸を擦った。
火を灯した松明を手に、洞窟へと入る。赤と橙の中間色が内部を照らし出した。
奥行き自体はさほどでもないらしい。大きな広間のように円状に空間が広がっているようだ。
「壁は手掘りか。天然のものではないな……。あの山賊が掘ったのか、あるいは以前ここに住んでいた人間がいたのか……」
松明を壁に向けると、不格好な机や椅子が見つかった。山賊が手作りして使っていたものだろう。あまりいい臭いのしない肉や果物が散乱している。空の酒瓶も同様だ。
壁際には皮なめし台があり、野生動物と思われる皮がかけられていた。
左手側には価値のあるものはない。
では、と反対の壁に目を向ける。
――あった。
木箱の数々。輸送団を襲って手に入れた貨物だ。
その大きさにはばらつきがあり、様々な相手から略奪していたことが窺えた。
ただ全体を見ても大きな荷物はない。
孤島の隠れ家に運び入れるにあたって小舟しか使えないからだろう――浜には小舟しかないことを確認済みだ。
一番手前には最新の盗品と思われる、大きな旅行鞄が落ちている。
木箱に中身が詰まっているかどうかを確認するのは骨が折れるが、鞄を開くことくらいはなんてことないだろう。
僕は丈夫な革で作られたそれに近づき、丈夫なフックを四つ外した。
途中で鞄の側面に、いくつか妙な穴が開いていることに気がついた。
何だろう。綺麗に――とは言わないけれどナイフで小さくくり抜かれていることはわかる。事故で開いたものではなさそうだ。
少し気になったが大したことではあるまい。何にせよ中身を確認すればわかることもあるだろう。
思考を続けながら鞄を開く。
「……は?」
鞄には、美しい女が詰まっていた。
「…………」
呼吸が一瞬止まっていたことを自覚した。意識して再開させる。
彼女は死体ではない。
薄暗い洞窟内でも『光っている』と錯覚してしまうような、鮮やかな紅紫色。
まるで魔性の獣のようなそれが、髪の隙間から僕の顔をしっかりと捉えている。
僕を視認している。
膝を折りたたんで抱え、横向きに寝転がった――みっしりと詰まった女は、そこに窮屈さを感じないのだろうか。微動だにしなかった。
銀と白の中間色の長髪が、乱れたまま彼女の体を包んでいるようだった。
彼女は僕を視ている。
彼女は僕を知覚している。
だというのに悲鳴をあげない。
それどころか全く言葉を紡ごうともしないのだ。
異様な光景に戸惑いを覚えた。
じ、とこちらを見つめている彼女から目を離す。そばに置いていた松明を手に取り、心を落ち着かせた。
落ち着け。情報を集めていこうじゃないか。
「えっと、きみは誰?」
女は鞄に収まったまま黙している。
年の頃は二十手前、だろうか。少なくとも『少女』といった雰囲気ではない。
長い長い髪の間から見える目は、僕をじっと見つめたままだった。
「もしかして言葉がわからない?」
もしそうだとしたら面倒だ。
しかし彼女は薄く紅でも塗ったかのような唇を動かした。
「あ、アー、アーアー、あ……わ」
彼女は喉を押さえて唸った。その声色は高低しており、楽器の調律を思わせた。
「――わかる」
冬の凍てついた湖のような声だった。
少なくともエオルゼア共通語は通じるようだ。懸念は一つ減った。僕が扱える言語は共通語と東方語だけだからなぁ。
「起き上がれるか?」
「……できる」
彼女は器用に身を起こした。
相変わらず鞄の中に収まった状態ではあるが。
起き上がったことで新たにわかったことがある。
彼女の皮膚には黒い鱗で覆われた部分がある。首の周りや額から鼻梁にかけて、あるいは腕の周り。見慣れぬ民族衣装を着込んだ部分については見えないが、おそらく手足なども同様だろう。
そしてゆるくうねりを帯びた黒い角が、白髪の瀑布から突き出ていた。鋭い先端は顔と同じ方向を指し示している。
西方ではまだあまり見かけぬ種族――アウラだ。
僕の故郷、東国『紅州』では東方文化圏を構成する一種族ということもあり、白鱗のアウラ・レンは特別珍しいものではなかった。
西方との海路が拓かれたこともあって近年はエオルゼアに進出した者もいると聞くが――まだまだ数は少ない。
しかし、目の前のアウラが身に宿しているのは黒い鱗。
アウラ・ゼラと呼ばれる一部族だ。
彼らはその多くが遊牧民であり、紅州でもほとんど見たことがない。東方に溶け込んだアウラ・レンと違ってオサード小大陸北部の大草原に暮らしている者が多く、独特の文化を育んでいる。
このように西州でお目にかかれるとは思ってもみなかった。
「そこから出られるか?」
「出られる」
僕が手を差し出すとそれを握り、極狭の領地から飛び出した。
そして静止。
驚くべきことに、彼女はブーツを穿いていた。少し土が付いているけれど、比較的新しいものと思われた。
「名前は?」
「名前?」
「きみの名前だ」
「…………」
これには口を閉ざす。
「名前は言えない?」
名を明かせない人間とは何度も出会ってきた。匿名の依頼者、偽名を名乗る犯罪者、自分で付けた名前でしか呼ばれたがらない賊、その他諸々。
山賊の盗品と思しき鞄の中に詰められていたのだ。彼女が『そういったものに関係する人物』である可能性は十分にあった。
「違う」
しかし彼女は否定した。
表情には何の色もない。少しばかり奇妙なことだが彼女は何かを恐れているわけではないようだ。
ちょっと待てよ。嫌な予感がしてきた。
僕は彼女をここに放置して冒険者ギルドに帰った方がいいのではないか、という考えが頭をもたげてきた。
そうだ、『旅行鞄に女性が詰められている』という一種の異常事態に遭遇して思考できていなかったけれど、もしかしてこれは『面倒な事態』に巻き込まれているのではないか?
山賊の盗品。西州アルデナード小大陸ではほとんど見たことがないアウラ・ゼラ。見たことのない民族衣装。言えない名前。
恐ろしくはっきりした応答。突然現れた僕にも動じない彼女。しかしどこか違和感のある話法。
手を引くならここではないか?
――あるいはもはや手遅れか?
「名前がわからない、とか?」
少なくともこの質問は『手遅れへの第一歩』であることは間違いなかった。
僕はしかし、質問を続けてしまった。
ほとんど条件反射に近かった、と思う。
「わからない」
チェックメイト。
我が故郷の盤上遊戯で言うなら王手だった。
この女は厄介だ。
僕がこの職業で培ってきた『本能』とも呼べる部分がそう告げる。
記憶喪失――かどうかはわからないけれど、それに近い状態であるとするなら、彼女との邂逅は面倒を呼び込む可能性が高い。
先程殺した山賊どもがこんな面倒な荷物を狙って略奪するはずがない。それほどの頭脳があるとは思えなかった。
山賊を皆殺しにしてしまったのを一瞬悔やんだが、もし彼らが存命であっても大した情報は得られなかっただろう。……それでもちょっとした手がかりくらいは得られただろうか。
よし、考えてみよう。
山賊たちは略奪行為中偶然にも旅行鞄を手に入れた。この鞄の持ち主は人間を鞄に詰めて輸送する変態的趣味の持つ金持ちであった。持ち主を探して届ければ万事解決、僕は報酬を得られて終わり。
非常に前向きな仮定をしてみたけれど、絶対にこうではなかろうという自信がある。何しろこれまで面倒事にしか出くわしてこなかったからだ。
僕がこうやって『面倒そうなこと』に出会ったということは、この後絶対に面倒事に巻き込まれるのだ。
十中八九、山賊どもは面倒な相手から略奪を行っている。そしてその厄介な荷物が僕の手に転がり込んできたのだ。
彼女をここに置いていきたい……。さっさと海都に戻ってラムでも飲んで寝たい。
しかしそうもいかない。
置いて行ったら行ったで、あとになって良心が痛みを覚えるだろうということは簡単に予想できるし。そもそも彼女をここに放置したことが露見すれば、ギルドから責められるのは間違いないからだ。信用と職を失わないためには多少『良い子』である必要がある。
「ブリジット・マイナー。この名前に覚えは?」
僕は鞄に括り付けられた札を見つけたが、そこに書かれた共通語を読み上げても彼女は大した反応を返さなかった。
しかしなんらかの手がかりであることは間違いない。僕はナイフを使ってタグを切り離し、懐にしまった。
まずは人探しをしなければならない。
その前に彼女を連れて行かなければ。都市に戻れば預け先くらい見つかるだろう。
僕は立ち上がり出口に向かった。
「歩けるよね?」
「歩ける」
「よし、じゃあついてきて」
「ついていく」
どの言葉にも、彼女は律儀に答えたのだった。

2.
名前もわからぬ女と歩いてわかったことがいくつかある。
第一に、彼女は全くの無口であるということ。
知り合いにも比較的無口な人間は多い。請負業という職業柄、依頼者の機嫌を損なわぬよう沈黙を是としているタイプの冒険者は多いのだ。
それだけでなく過去が問われない職業であるゆえ、脛に傷を持つ人間も多い。そういった者は大抵口数が少ないものだ。
彼女は――このアウラは違った。
『口数が少ない』という表現は相応しくない。
『全く口を利かない』のである。
僕が話しかければ応答する。
やや違和感を覚える方法であることには違いないけれど、少なくとも返答する。
「お腹は減っていない?」
「減っていない」
「体は疲れてない?」
「疲れていない」
「どこか痛むところはない?」
「痛まない」
その他諸々、彼女を連れ歩くにあたって質問を投げてみたけれど、どれも似たようなものだった。
これら以外に口を利いたことはなかった。口を引き結んで静かに歩き続ける。
まるで言葉の交わし方を知らないかのように。
言葉の役割を知らないかのように。
――彼女の返答は、ただの反応だ。
意思疎通ではない。
情報伝達でもない。
彼女は無機質に、訊ねられたことを返しているだけのように思えてきた。
だから彼女の言葉が真実なのか僕にはわからない。
腹は減っているかもしれない。
体は疲れているかもしれない。
どこか痛むところがあるかもしれない。
もちろん真実である可能性もある。何を信じていいのかわからないのだ。
このアウラは人間味を欠いている……。
いや欠いているどころではない。
彼女からは人間らしさというものを感じられなかった。
特異な点は他にもある。
たとえば小舟に乗るときのことだ。
僕は無人島に来るために小さな舟を借りていた。小さいながらも帆を張って風に乗ることができる、地元の漁師が使っているものだ。
山賊たちの船着き場まで辿り着き、僕は陸に揚げていた舟を押し出した。
腿まで海に浸かったところで舟は海上での自由を取り戻した。これで乗り込める。
僕はさっさと舟に乗り込み、彼女を待った。
のだが。
「……何してるんだ」
「…………」
無言。
わずかに黄色い浜の上に彼女は突っ立っていた。
波打ち際で静止している。
「何かあったのかい?」
「なにもない」
何もない?
何もないなら別にいいじゃないか。
意味がわからず手招きすると彼女はおとなしく従った。
海というものに戸惑ったようにも見えたけれど、彼女は僕の隣に並んだ。
……また動かなくなった。
「なぜ乗り込まない?」
「乗り込む?」
「この舟だよ」
「ふね」
無表情だ。
疑問を呈するような声をあげても、長い長い前髪の間には何の色も浮かんでいなかった。
「乗り方がわからない?」
「わかる」
「じゃあ乗ってくれ」
「わかった」
彼女は舟の縁を掴み、器用に乗り込んだ。が、揺れることは想定していなかったのか、未経験なのか、小舟から落ちそうになる。次に乗り込んだ僕が手を貸してやると、すぐに安定した。
一体何なんだ。
このアウラ・ゼラへの疑問が消えず、しばらく考え込んでしまった。
帆を張って海に乗り出しても考えは消えず、僕はこれまで彼女と交わしてきた会話――らしきものについて思い返していた。
そうして振り返っていると気づけるものがある。
僕はもしやと思い、彼女に話しかけていた。手がかりを得たかもしれない。
「……なあ、きみ」
人間には何か名前が付いていないと呼びづらいものだ、ということを僕は今回の出来事で学んだ気分だった。
「すまないけれど、ちょっと立ち上がってみてくれないか」
「わかった」
彼女は僕の言う通りにした。
小舟で海に出ると、お世辞にも上品とは言えない揺れに襲われる。
そんな中でも彼女は静止した。平衡感覚が優れているのだろうか。
「座ってくれ」
「わかった」
僕の言う通り、即座に座り込んだ。
「こっちを見てくれ」
「わかった」
これも僕の言う通り。
「もういい。向こうを向いててくれ」
「わかった」
言う通り、だ。
さすがに途中からわかっていたけれど。
――彼女は他人の命令に従う性質がある。
いや、正確ではない。
彼女は他人に命令されないと行動しない、が正しいだろう。
この性質を念頭に振り返れば、彼女の奇妙な行動に説明が付いてしまう。
舟に乗り込む際のことだけではない。
そもそも彼女の返答の奇妙さもだ。
僕の質問にだけ答える。
自分から言葉を発することはない。
もしかすると、『彼女には意思というものが存在しない』のかもしれない。
「……こいつは厄介な人物を拾ってしまったぞ」
潮の香りが鼻腔に張り付く。
僕は静かに操船を続けた。
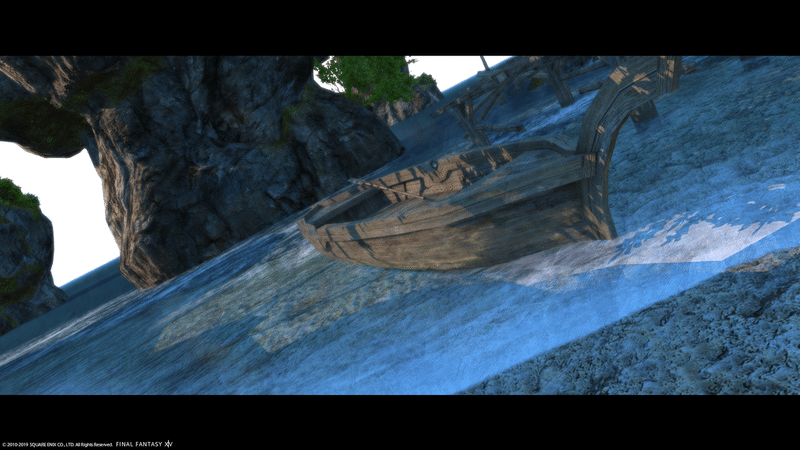
バイルブランド島へは一時間もかからなかった。
潮と風の流れがちょうどよかったのも一因だ。
ブラッドショア――東ラノシアの沿岸。豪商ゲゲルジュ氏によってリゾート化が進められている一帯だが、漁を営んでいる人間が全くいないわけではない。
コスタ・デル・ソルより南、低地ラノシアとの中間地帯に舟を停めた。漁師小屋を訪れ、舟を返却しにきた旨を伝えて出た。
老人は料金に満足していたが、僕が後ろに連れている人間に奇異の視線を投げかけていた。余計な質問が飛んでくる前に場を辞したのは正解だっただろう。
フードのある服でも見つけてやるべきだろうか。
このままリムサ・ロミンサに入るにはやや不安が大きい。
角や鱗のアウラはエオルゼアではまだ稀少な種族――獣人と間違われる可能性はなくもない。
ウルダハと違ってリムサ・ロミンサでは獣人排斥令が敷かれているわけではないが、何らかのトラブルを生みかねない。
そして単純に――アウラを珍しがった『人買い』に狙われる可能性もある。
「さりとて他に安全に入れる街があるわけでもないけれど」
「…………」
エオルゼア都市同盟の中では海都で間違いない。獣人排斥令のあるウルダハは論外。グリダニアは近年ようやく門戸が開かれ始めただけで閉鎖的な街だ。悪目立ちするだろう。
とは言ってもやはりリムサ・ロミンサは元海賊の都だけあって治安は三都市でも最悪なのだが。
ここから近くて補給のできそうな集落はワインポートだが……それでも彼女を連れて行くのは少し気が引ける。
僕はブラッドショアの浜辺に座った。
きみも座りなさい、と言うと彼女もその場に座り込んだ。
漁師小屋に預けていた背嚢から地図を取り出す。
悩んだまま停滞するわけにはいかない。とにかくどこか目的地を決めなければ。
幸いにして背嚢に入っている食糧には余裕がある。二人で一週間程度は持つだろう。
視力の残っている右目だけで地図を精査する。この地図はだいぶ古びているが、冒険者が利用できる商店が書き込まれている。
僕がエオルゼアで訪れたことのある場所を記録しているのだ。いずれ新しい地図に写し取る必要があるだろうが、なんだかんだでまだ使えるので先延ばしにしてしまっている。
「ワインポートは駄目だな。あそこは歩哨が立ってる」
一人旅なら問題ないけど。
「とするとやっぱりここかなぁ」
東ラノシアから更に北上した地図を見る。
高地ラノシアのブロンズレイク沿岸が瞳に映った。キャンプ・ブロンズレイクではない。そこに入るのならワインポートと大差がないだろう。
ブロンズレイクの岸に小さな商店がある。
名を『ジジルン交易商店』。
獣人キキルン族が営む店だ。
ここならばアウラを連れていたとしても問題なかろう。キキルン族は小さなことを気にする部族ではない。加えて交易大好きというジジルンの性格を考えても最適のように思えた。
うむ、これでいくことにしよう。
「さあ行こう。えーと……」
やはり呼び名がないのは会話に困る。
命令を受けて立ち上がったアウラの紅い瞳に、僕の困り顔が映っていた。
「きみ、呼ばれたい名前とかある? 本当の名前とか別に思い出さなくていいんだけど、とりあえずの呼び名を決めておこうと思ってさ」
「……わからない」
『ない』でもなく『わからない』だもんなぁ。
多分きっと、本当にわからないのだ。
彼女には意思がない。己がないから、己が何をしたいのかわからない。
『好み』の問題に適切な返答など存在しない。だから彼女は答えを紡ぎ出せない。
求められていることに応えることはできても、自分が何をしたいのかはわからないのだ。
このアウラは一体どのように生まれ、どのように育ったのだろう。
疑問は尽きない。きっと訊けば答えてくれるだろうが、とりあえず先に決めるべきことがある。
「わかったわかった。きみに何かを決めるのは難しいんだったな。じゃあ僕が決めるけど、文句は言わないでくれよ」
「言わない」
本当にそう思っているのだろうか……。
「きみはきっと知らないと思うけれど、僕が生まれた紅州には『名無しの権兵衛』という言葉がある。僕の故郷では、名前のわからない人間をそう呼ぶんだ。ジョン・ドゥとかジェーン・ドゥ。あるいはジョン・スミス。名前のない者を示す語は世界中にある。だから君は、東方より来たりし僕に名付けられた、『ナナシ』だ」
ふざけて呼ぶ名前だから、本当は良くないのだろうけど。
「ナナシ。僕はきみのことをナナシと呼ぶことにする」
「ナナシ」
「これはきみの本当の名前じゃない。便宜的に僕がそう呼ぶだけだ。だからきみもこれを名前として受け入れてはいけないよ。名前ってのはね、ナナシ――」
彼女は神妙に僕の言葉を聴いている。
それがちゃんと彼女に響いているかはわからない。
人の心中など、他人にわかるものか。
「――『名前』は、人を定義するんだ」
「定義」
「だから、僕はきみに名前を付けない。意味のある名前を与えない。『ナナシ』はきみを区別する単なる記号だ。ちゃんとした本当の『名前』は、きみ自身で手に入れるんだよ」
それは自分で思い出した名前でもいい。
それは自分が獲得した名前でもいい。
――なぜだかわからないけれど、僕の左目が僅かに疼いた。
「それまではナナシ。そう呼ぶから、よろしく」
「わかった」
彼女は――ナナシは頷いた。
その表情に色は相変わらずなかった。
揺らぎのようなものは見えた、気がした。
あるいは、僕の希望を映しただけだっただろうか?
Chapter 1...end
サポートいただけると執筆速度があがります。
