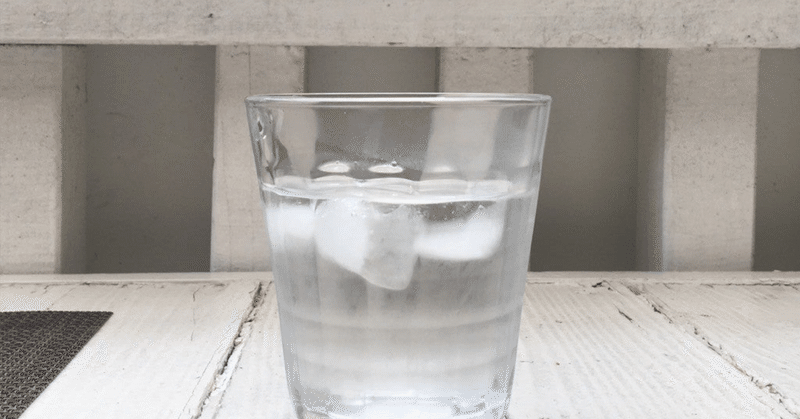
#シロクマ文芸部 #短編 『わたしはあなたの話を聴きたいとおもっています』
約4500文字
この作品には残酷な描写があります
誕生日パーティーから抜けてきて自宅の玄関を開けた。部屋に入ったけど照明を点けたくなかった。カーテンをiPhoneで開けると星明かりが部屋が青く照らす。ハンドバッグとファーのコートを投げすてて、リビングのソファに身体をしずめた。
まだチリからまわってきた『雪』が効いている。ふわふわしていて気持ちがいい。このあとですごく咽が渇くのだろうけど、ただ水を飲めばいい。この程度の異常には慣れた。
一族の嫌われもので主賓たる叔父はあいかわらずいい趣味で、今年は給仕をすべて黒人の幼い女の子で揃えた。男女がジルバを踊れるような『ボールルーム』に、白いクロスがかけられた特大の円卓が用意され、そんな趣味しか知らない性質の一族に、ご賓客のみなさん、そして主賓が『ただただ食べて楽しむ』。わたしは壁際のソファでぼんやり煙草を吸ったり酒を呑んだり、そしたら目の前にしゃがんで泣いている黒い背中のきれいなかわいい子がいたから、手をひいて、横に座ってもらって、わたしの白いコートをかけて、カームダウンカームダウンとなだめつづけることにした。わたしの白いラビットファーのコート、それほど重くはないコート、偽物ではないコート。この世から隠れるためなら、夜の船の甲板のうえで叩きつけられる波しぶきを遮るための、獣臭くてひたすら重い、本当のコートのほうが安心感があったかもしれない、ただの道具としてのコート。ヤエコおばさんがボトル片手に『あらあらネコ飼いはじめたの?』って言って私の横にドスンとすわった。派手な石を散りばめた髪飾り、白い肩、黒いビスチェにレザーの手袋、ワイドパンツにヒールの高いブーツ。デコルテのネックレスの真珠がきれいだった。彼女の演奏会でもドレスに合わせているネックレス。「迷い猫だよ、保護したんだ」ってわたしは言った。彼女が猫の顎をつまんで猫と目を合わせる。
その首をわしづかみにして二人でピュンと隣りの部屋に行ってしまった。好みだったんだろう。
部屋の向こうの音があんまり聴こえなかったから楽だった。手のおおきなヤエコおばさんの弾くピアノは本当にきれいなのだけれど、彼女はむかしからピアノ以外ならあの手でなんでも解体してしまう。蟹でもお人形でも猫でも男でもなんでも。わたしの手はちいさい、だからピアノが下手なのだとおもう。
こんな一族がなんだか苦手で、ひとりこっそり文筆業を身内にばれないようにやっているっていうのに(彼らには「なにもする気がしないからゲームだけして親の買ったマンションにひきこもっている」と説明している、そしたら親類のうちで高級デートクラブにも出資しているセンセイと呼ばれる男の嫁からあなたは不健康だといわれて笑われたのでわたしもつられて笑った)、たまに言うことを聞かないとめんどくさくなる一族の「おつきあい」が年になんどかある。
誘われたらおつきあいする。
世界はびっくりするほど狭いから、人間の自由なんてちょっとしたことであっというまに握り潰されるし、でも、あのひとたちの携わる芸術はたしかに本物ばかりですてきだ。映画にしても音楽にしても絵画にしても。人間ひとりをすり潰すことを良い香りのするハンドクリームをチューブから手の甲に出すくらい何事もなくおこない得る暴力と金銭を背景に芸術を育むわが一族。
仕事で、たまに映画の記事を書くために出演者に会うことがあるけど、そのひとがびっくりするほど普通のひとなことがあって、そういうときは驚きのあまりつい熱心に話しこんでしまう。そうするといい記事が書けることが多くてうれしい。そのひとの片鱗、ほんとうにウロコの輝くいちまいだけ、つまみとれたかのような、そんなような些細な文章だけれど。そのウロコをクライアントにメールでデータを送信して、たまにクライアントに褒められたりする。うれしい。普段は映画は観ない。寝ちゃうから。
ねこ。さっきの猫のことをおもいだした。かいねこ。
ペット。自由か。自由って。
そういえば、あたしいま何歳なんだっけ。部屋で保険証を探してみた。記載された生年月日をiPhoneに聞いたら今年でわたしは26歳だと答えてくれた。双子座だってことだけは憶えているんだけど(星占いは好きだ)自分の年齢に興味を失なっていた。化粧の乗りはいつも悪いし皺なんてちょこちょこあるから、おおよそ20代くらいにおもっていた。
iPhoneにメッセージが届く。
「あたしリカちゃんいまあなたのおうちの前にいるのギャハハ」騒がれるとめんどうなのが来た。
もうコートも洋服も脱いじゃったってのに。外を玄関のモニターで確認して鍵を開けた。チリを部屋に入れる。照明を点けた。夜のタクシーひとりで乗れるようになったのね。
「そんなの余裕だよ! ね、ね、どうだった? よかった?」
わたしが座ってたソファにチリがすわってしまった。その目の前の小さなテーブルにミネラルウォーターのボトルを冷蔵庫から出して置く。どいてって言ってチリの横にわたしも座る。
あれからフワフワしてて気持ちよかったし、まだそんな感じだよ、チリにそう言った。チリはおくすり遊びがいまのマイブームなんだろう。同級生のあいだで流行っているんだろうか。この子、このまえまではファイナルファンタジーシリーズばっかり1から順番にずっとやっていて文字通りゲー廃だったのにこれからはホンモノの廃人をめざすのか。うちの親族はみんな冗談みたい人間ばっかりだ。
人間ってなんだろうなあ。給仕にひかれた椅子に座るのも人間、その卓の皿の上に乗っているのも人間。
「ちっちゃいチョコレートがあったじゃない? さっき、ゼリーとかフルーツとかお肉とかと別のプレートに、そのチョコいっこずつ撒いた雪のうえにコロコロ転がして食べてたらさ、あのピアノおばさんがあたしとおんなじくらいのメイドの子ども連れてきてケースから道具出してバラバラにしはじめたんだよね、わたしいるのわかんなかったのかな、まあもういいけど、ふわふわしてきてなかったら部屋中まっ赤になってすごいかんじだったからびっくりしてたとおもうんだけど、ほんとうあのときのおばさんって夢中なんだね、血眼ってかんじでこわかった、こわかった、それでわたし我慢してたんだけど結局おしっこ止まんなくなっちゃってさ、でもどうでもよくなって、もっとチョコ食べたんだよね、そのうちわかんなくなって、気がついたらこのカッコでメルセデスのシートに寝ててお父さんの横にいたんだ」
グレイのパーカーに、紺色のハーフパンツ、絵本に出てくるようにかわいく描かれたみどり色ときいろのワニのかおが描かれたスニーカーインソックス。叔父の躾けでベンツをメルセデスと呼ぶ小学生。たかが車なのにどうしてそんなことに拘るんだろう。
普通の子ども。
チリの頭を抱きよせる。ショートカットのつやつやした髪。
チリはかわいいよね。
「マジで? やっぱおねえちゃんってレズってうわさほんとう?」
ちがうよ。だれなの、それ言ったの。恋愛とかエッチとかが嫌いなだけだよ。
「なんで? 好きなひととかいないの?」
いない。
「なんで?」
いらないし嫌だから。どんなひとも。チリ、お水飲みなよ。
おおきいミネラルウォーターのペットボトルをわたしは抱きかかえ、キャップを外してあげる。チリがすこし飲んだ。
もっと飲んだほうがいいよ。渇くから。
「ヤだよ、もうおしっことかしたくないよ」
大丈夫、そしたらわたしがちゃんとトイレに連れてってあげるから。
「もうヤだよ」
チリが吐いた。泣きながらたくさん吐いた。吐瀉物で窒息しないようにしたかった、でもどうしたらいいのかわからなくて、ソファに寝かせて吐くだけ吐かせてとにかく慌てて救急車を呼んだ。意外なくらいすぐに来た。
わたしはひとり夜の病院の廊下で待っていた。六時間くらい経っていたはずだった。時間の感覚がなくなっていた。チリ死なないで、チリ死なないで、チリ死なないで、そしてドアが開き医者が出てきて両親はどこかと尋ねたので、病院に着いたときにわたしが連絡したのでもうすぐ来るはずです、そう告げた。医者はチリは助かると言った。
父親が来れば、あのひとが来れば、いろいろ済んでしまうのだろう。
先生、質問させてもらってもいいですか?
「なんでしょう」
あの子みたいなこども、めずらしいですか?
「そんなことを聞いてくるご親族がまずあまり居ませんね」
なぜですか?
「大抵、わたしに交渉してくる親が多いから。裕福だろうか貧しかろうが、皆ああいう子どもを隠したがる。僕を脅す輩も少なくないよ、なぜ質問を?」
わたしは世の中のことを知らないからです。
「たいへんな境遇にある子どもということであれば、珍しくない。あの子はすこしだけ運が良かった。でもこれからが大変かもしれないよ。年齢が幼なすぎた」
彼女も、なにも知らなかったんです。教えることを怠りました。
「あなたが?」
わたしもです。
「世の中のことを知らない、そうだろうか。そんなことよりもだ、あの子が健康に生きる人生を望む大人があの子のまわりにどれだけ居たんだ」
深夜わたしの目の前に吠える医師がいた。
健康に生きる人生を想像できない人々の世界を、先生、わかりますか?
「知らないな」
でもあるんです。
「自分たちの子どもが麻薬で心臓が止まるのが常識的な世界とかが?」
はい。
「あぁ、そうだった、わかりますかと質問されたので答えるよ、わからない。わからなくちゃいけないのか、そんな世界を」
でもあります。
「僕らはやるべきことをやるだけしか知らないし、できない。それ以上の想像力を働かせる余裕なんて無い。親が来たら呼んでください。僕は中にいる。まだ重篤な状況であることに変わりはない」
会えませんか。
「いまは駄目だよ。けれど、時間が経てばある程度まで回復する。待つんだ」
朝になって、チリの母親というひとが来た。はじめて会うひとだった。きれいで、普通のひとの匂いがした。廊下でさっきの医者に説明をされていた。何度か「絶望的」という言葉を医者が言っていた。静かな罵倒のようにも聴こえた。あの母親はそういう役割のために一族に雇われているようなひと、そんな気がした。父親は来なかったが、「代理人」がいた。代理人はわたしに状況を聞くと、わたしに自宅に帰るよう指示した。チリに会いたかった。代理人に「彼女のおとうさまに許可されておりません」と断わられた。
もういちど、今日二回目に自宅の玄関を開けた。汚物の匂いが充満していた。自分で片づけることをあきらめて、契約している清掃会社に連絡をした。突然、強烈にたばこが吸いたくなった。マンションの管理室に清掃会社が入る旨を告げて、部屋着を着替えてから街を歩いた。
昼になっていた。歩きタバコをしながら公園に入る。子どもたちと遊ぶ母親が遠くに見えたのですぐにタバコを捨て靴で潰した。彼女たちの話を聴きたかった。なんでもよかった。
スーツ姿の男が木陰のベンチで眠っている。彼に人工呼吸器をつけるにはまだ早いのだろう。ただ、揺すって、おこして、話を聴きたかった。
チリとは、また話をしたい。きっと生きているチリと、たわいもない話をしたい。
子どもにこの世界で夢を聴くなんて残酷なことは退屈なことだとおもう。
そしておもったのだけど、そういえば、わたしの話はだれが聴いてくれるのだろうか。そんな価値はあるのだろうか。
けれど、どんなひとの人生も、記事にする価値はあるように思う。たとえわたしなんかの話だとしても。目の前に立つひとの話を、わたしは書きたい。
わたしはそうすることにした。たとえ目の前に立つ者が鏡の向こうのわたしだとしても、わたしは書くことにする。
自販機で水を買って、ひとくち飲んだ。つめたい水が咽からからだのなかへ落ちていく。どこへ?
世界は狭くないのかもしれない。わたしはまだなにも知らない。
初稿掲出 2023 11月12日 21時直前
