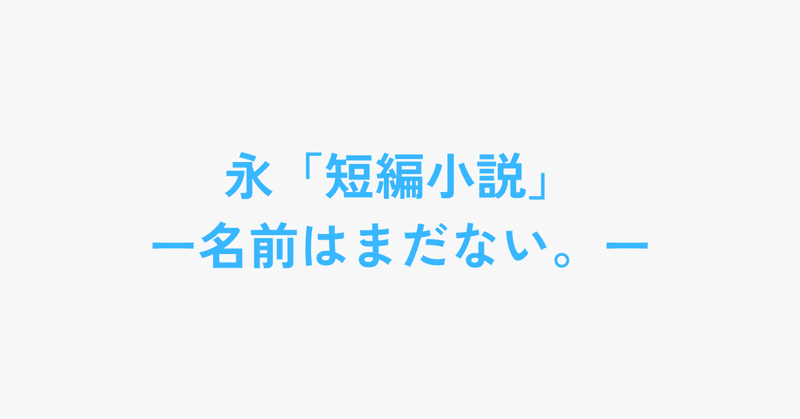
永|小説「名前はまだない。」
巻頭歌
往く夏の樹の根にそつと遺書置けり
夜、或る路地に爆弾を投げたい。
朝には木っ端微塵に消し飛んで、それでも世界が変わらないことを確認したい。
誰かが夜を歩く時、僅かでも思い出されること。
焼け跡でそっと遺書を読み返すこと。
そのためだけに、彼はひっそりと爆弾を造った――。
その日は快晴だった。
蟬の声が柔らかく、ビル街は賑わっている。
「夏樹って覚えてるか」
受話器の向こうは同級生の声。
思えば、この同級生は「同級生」でしかなかった。
高校生の頃はそれなりに話していたし、それなりに会っていた。
どこかの観光地へ出かけたこともある。
いつだったかは覚えていない。
宿泊の記憶もある。
大浴場で風呂にも浸かった。
ただ、いずれも2人きりというわけではなかった。
他の同級生、部活の仲間、そして夏樹。
必ず間に誰かがいて、私はその関係を友人とは思っていなかった。
学生時代の友人は夏樹だけだった。
浅く言ってしまえば、妙に波長が合う、というただそれだけのことだ。
もう少し卑下した言い方をするなら、私は夏樹以外の人と上手く話すことができなかった。
「覚えてるよ」
夏樹とは、つい昨日電話したところだった。
それもおよそ3年ぶりに。
内定が出たと嬉しそうに話していて、その後は他愛のない話をした。
「夏樹がどうかしたか」
道を走る車がうるさい。
蟬の声も柔らかい輪郭をいつしか消して、騒々しく鼓膜を震わす。
反面、受話器の向こうは透き通るように静かだった。
重々しく、しかし明瞭に、同級生は私に言った。
「夏樹が死んだよ」
少し薄暗く見えるのは、私の気持ちの持ちようだろうか。
私は今、夏樹の遺影の真ん前にいる。
たった一人の友人の、たった一回の葬式を、まさか二十歳そこらで迎えるとは思ってもいなかった。
見知った顔が何人かいたが、その日の私は誰とも喋らず早々に帰宅した。
「理系は大変だって言うけどな、文系は文系で大変なんだぜ。就活とか」
「その割には俺より早く内定貰ってんじゃねぇか」
式場よりも暗い自室で、独り先日の電話を思い出す。
私は夏樹の何を聞いていたのだろう。
大学がどうだとか、就活はどうだとか、そんなくだらないことばかり話していた。
恋愛方面はお互い全然だと笑い、理学部のレポートの多さに愚痴をこぼし、社会学部の教授への愚痴を返されて、その間私だけが楽しんでいたのだろうか。
電話の翌日。
夏樹は雲一つない空の下、飛び降りた。
悔やまれる。
苛まれる。
自分は夏樹を救えなかったか。
あの日、電話越しに何を話すべきだったのか。
頭の中であの日の夏樹の声が延々と流れる。
何を喋った。
何と言っていた。
どんな声でどんな様子で。
瞬間。
私の頭にふと、葬式中の誰かの声が再生された。
「遺書は見つかってないってさ」
そして同時に、あの日の電話の終わり際を思い起こす。
「じゃあ。また待ってるから。よろしく」
夏樹からだ。
夏樹から「また待ってる」と言った。
夏樹は私に「よろしく」と言った。
あの日はそれを「今度はお前から連絡してくれよ」という意味だと思った。
でももし、既に死ぬことを決めていたとしたら。
「先に死んで向こうで待ってる、ってこと。あるいは……」
夏樹は、遺書を見つけられることを待っている。
私にそれを、探せ、と。
葬式のための帰省を理由に長期休暇を取っていた私は、それから夏樹の遺書探しを始めた。
警察が見つけていないならば、夏樹が飛び降りた建物周辺や夏樹の家にはないだろう。
親戚宅に届いているということも考えにくい。
そういえば、電話したあの日、夏樹はいまだに実家で暮らしていると言っていた。
私も何度かお邪魔していて、夏樹の両親とは顔見知りだ。
行って話を聞くことはできるだろう。
だが、遺書の存在について語るべきか。
夏樹の実家に行くと、先客がいた。
知らない女性だった。
昔ながらの和室に、夏樹の両親と私と女性。
おそらく冬は炬燵になるであろう茶色のローテーブルを囲むように、私たち四人は各々座った。
「夏樹君の、友人です」
女性は自己紹介として、それだけを言った。
なぜか名前は名乗らなかった。
女性は私の方をあまり見ず、夏樹の両親の方にばかり話をした。
内容は夏樹の生前の様子についてのもので、両親は寂しくも有り難そうに聴いていた。
女性と夏樹がどういう繋がりなのかは全く話題に上がらなかったが、おそらく私が来る前に話していたからだろう。
それにしても、女性が何者かわからない。
大学の友人、とかだろうか。
それから暫くして、それまでほとんどだんまりだった私を気遣ってか、夏樹の母親が私に話を振ってくれた。
「久しぶりだね。今日、来てくれてありがとうね」
私は遺書の話を一切出さず、当たり障りのない思い出話をして、その日は早々にお暇した。
ある夢を見た。
私は古いホームにいて、空は明るく曇っていた。
非常食のように錆びた銀色の電車が流れ着いて、私は一瞬乗車を躊躇う。
行き先を確認しようと車体の上あたりに目をやって、私は「あれ」と思った。
どこにも行き先が書かれていない。
よく見れば窓もない。
扉だけが銀の塊に備えられて、惑っているうちに気づけば私は車内だった。
先のわからない生き方は不安という人がいる。
それを自由と呼んで追う人もいる。
そんな手垢のついた論理が浮かぶ私はいまだに静かな車内だった。
誰もが不安で、誰もが不安に憧れている。
その絶妙なバランスがきっと大事で、どちらかに傾倒したとき、人は死ぬ。
そういえば、夏樹と一度だけ「死」について語ったことがあった。
もし夏樹を救えなかったことを悔やむとしたら、初めはあの瞬間だったのかもしれない。
「最近、丁度墓参りについて考えてたところなんだよ」
あれはどういう話の流れだったか。
何故か墓が話に出てきて、夏樹は私に話し始めた。
墓はどうしてあの形なのか。
外国の墓はまた違った形をしていて、宗教が違えばまた形が変わる。
自分にとって最善と思える墓の形も実はあるのかもしれなくて、それを見つけてから死にたいんだよな。
夏樹はそんな風なことを言っていた。
嬉々として、と言っていいのか。
あんなに熱を入れて話すのは、今思えば珍しいことだった。
「墓参りの意義も、本当は故人によって変わってくるはずなんだよ」
夏樹は私の目を見ながら、諭すようにゆっくりと、それでいて熱く語っていた。
会いに来てもらうのか、何か供えてほしいのか、ただ喋りたいのか、守ってあげたいのか。
夏樹は、故人が墓参りに何を望むか、故人の数だけあるはずだと言っていた。
私が乗り込んだはずの電車は、全く動いていなかった。
また夢を見た。
同じく古いホームで、その日も明るい曇り空が見えていた。
目の前に停まるは錆びた電車。
もう行き先は確認しない。
したところで、行き先は書かれていないからだ。
その日、私は車輌に乗らなかった。
電車は暫くして扉が閉まり、しかし動かず目の前にあった。
何を思うでもなく、銀色の電車の扉を見つめる。
何分くらいした時だろうか。
私の隣に誰かがいる。
歩いてきたというよりは、気づけばもうそこにいたのだ。
「夏樹君の、友人です」
顔はよく見えなかったが、私はその声を知っていた。
「夏樹君は言いました。ようやく見つけた、悔いはない、と」
その女性は電車の方を向いていた。
「どういうこと」
私も、電車の方を向いたまま言った。
「夏樹君は言いました。君も自由を求むなら来ればいい、と」
「だからどういうこと」
女性は「私」に話しかけているのだろうか。
紙芝居をするような、御伽噺でも披露するような、そんな語り口調だった。
「夏樹君は言いました。僕は死ぬけど、生きていても会えると」
「会える?夏樹に?」
私が焦燥気味に問うと、突如女性はこちらを向いた。
「『豌ク(繝医Ρ)』に!」
私は、一人でホームに立っていた。
夏晴れがいやに暑苦しい。
見慣れた電車がアナウンスとともに到着して、私は行き先を確認する。
どこで降りるかは乗ってから決めることにしていた。
席はそこそこ埋まっていて、私は吊り革に掴まる。
電車がゆっくりと動き出す。
電車が動いたことに安心してしまう。
夏でも晴れた日は快いものなのか。
今日家を出る時、曇り空でなくて良かった、と安堵した気がする。
いや、曇り空でも明るければ良かったのだろうか。
夏樹は今でも、私の頭にいる。
彼が死んでからもうひと月が経つ。
小説「名前はまだない。」ー第1話
企画・筆者:山崎幸愛
提案・企画:松田淳也
運営:合同会社Vaccano
続編が気になる方!
また、合同会社Vaccanoにデジタルクローン事業を進めて欲しい方!
には、是非、この記事にいいね!をお願いしたいです!
また、もしお金に余裕のある方は、応援の意を込めて、当記事の応援購入をお願いしたいです!50名の購入があったら、続編の第二話が、有料範囲に公開されます!
【残り50名】
ここから先は
¥ 550
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
