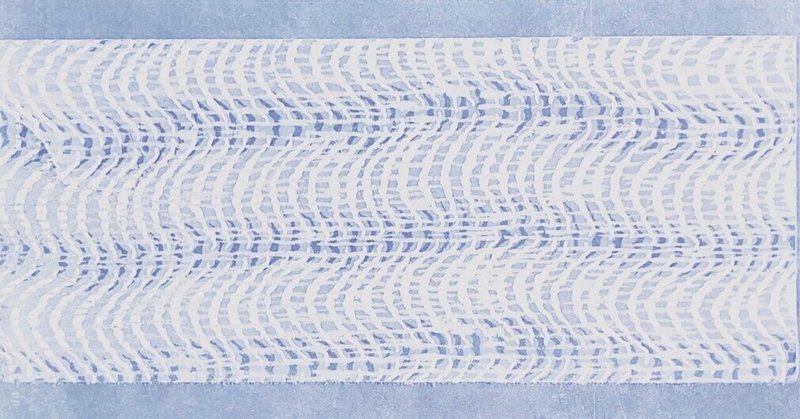
ブルーランド回想録 n.6 【連載小説】
✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎
おでかけの日。空はぼうしパンみたいな雲をいくつか浮かべて、気まぐれに陽を遮ったりしていた。
ちょっと早めに待ち合わせの駅につくと、改札口を出たあたりに黒のキャップをかぶったあおいさんがいた。と…手もとの端末が通知音を鳴らす。
〈いま改札口の横にいます〉
私は彼女から数メートルと離れていない場所で立ち止まって、すばやく返信した。
〈いまあおいさんの目の前にいます〉
ハッとして顔を上げたあおいさんが私を見つけて、キャップの影の下で、へにゃへにゃのだらしない笑顔を見せた。
「あいちゃん、もぉ、目の前にいるとかずるいです…!それにポニテにしてきてる!それもずるいっ!」
「ずるい言い過ぎですよ…ふふ」
「だって、素敵でずるいですもん…」
「す、素敵じゃないです…今日あったかいから、髪うっとうしくなるかなと思って…ていうか私、部屋着みたいな格好で来ちゃいました…」
「ん、それもかわいいと思います。…ショーパン、おそろいですね…うれしい」
「でも、あおいさんのほうが断然おしゃれです…」
「そ、そうですか…?ありがとう」
あおいさんは黒のショートパンツに、真っ白なセーラーカラーのシャツをインしていて、ぴかぴかした厚底の靴、そして淡いグレーのニーハイを履いた足首には蝶結びにしたブルーのリボンを巻いている。どう言えばいいんだろう。ひとつひとつはシンプルなアイテムばかりなのに、その合わせ方というか、着こなし方が、絶妙に斜め上をいっていて…こんなコーディネート、私はぜったい考えつかないな…ほんとうに最高。
「なんか、あおいさんの本気を見せられた気がします…」
「まって!何それ恥ずかしいですからっ…」そう言って彼女は両手で自分の姿を隠そうとするのだけど、当たり前のように全然隠せるはずもなく、しかたなく私の背後にまわって視線から逃れようとした。
「ちょ…あおいさん…」私が振り向くと、またパタパタと背後にまわろうとする。そんなことを繰り返して、あおいさんはわちゃわちゃしながら私のまわりを駆け回るのだった。駅のコンコースでこんなふうにしている私たちは、周囲からどう見えているんだろう。…と、不意に足もとがもつれたように彼女の体がよろめいた。手を差し出す暇もなかった。倒れ込む瞬間、受け身をとろうとしたのか、仰向けで地面にぺたんとへばりつく格好になってしまった彼女は、一瞬無言の後「…ふえぇぇぇ!」と情けない声をあげて顔をくちゃくちゃにさせた。
「あおいさん!大丈夫…?!」
「ぅ、うぅ…な、なゆたって呼んでぇぇぇ…」
何となくそのキャラ崩壊ぶりがおかしくて、私はつい笑ってしまった。
「ふ、ふふ…なんでこのタイミングなんですか…」
「…ひぐっ、だってえ、前から言いたかったんだも…うぐっ…」
「いいですよ…じゃあこれからは名前で呼びますね。それよりケガしてませんか?」
「敬語もやだぁ…ん…ケガはだいじょうぶかも…」
私は胸がどきどきした。あおいさんが感情を抑え込んでいたことを知ったから…かな。上半身を起こして、少し落ち着いてきた様子の彼女は「私ドジ…」とぽつんと言って八の字の眉のままふへへと笑う。私は彼女の服のよごれを手ではらってあげた。
「足もと気をつけてくださいね…」
「うん、今日は厚底なのに油断したぁ…」
「ね、お買い物の前にソフトツイストたべませんか?…あ、ちがう…えーと…ソフトツイスト、たべよ?」
「…わぁ、うん!たべるっ、うれしい!」
二人はそのあと近くのベンチで甘い夢をぱくついて過ごした。こうしてあおいさんは〈なゆた〉になった。そして不思議なことに、私はこの時から、彼女と会話することや、視線を合わせるということに対して、ちょっとずつ臆病ではなくなっていった。
「おいしいね…」
「うん、あいちゃんと一緒だから最高においしいぃ」
どうやったらこんなに口のまわりにクリームつくんだろう…ってくらいのたべかたで、彼女はにこにこしながら私のほうを見てくる。なぜだろう、おなかの奥のほうがきゅっとなるような不思議な感覚がした。
「服にこぼさないようにね?」
「うんうん、気をつけるよぉ」
「あ、あのね…私ストローハット探したいんだけど…いいかな?」
「え、めっちゃいいね!あいちゃんぜったい似合うよぉ」
「ほんと?うれしい。リボン付いてるやつがいいんだけど、でもリボンは別で買って、後で縫い付けてもいいかなーって…」
「すごくいい、あいちゃんの魅力さくれつしちゃうそれ…」
「ま、また大げさなこと言って…」
「ほんとだもん、…ね、その、リボン縫い付けるの、私がしてあげたいってゆったら、やだ??」
「え、いいの?」
「うん、あいちゃんのお手伝いしたい」
「な、なゆた…がしてくれたら、すごくうれしいな…」
「わぁ、じゃあ帽子いいの見つけないとね!」
そう言って彼女は元気よく立ち上がって、今にも歩き出しそうな素振りを見せた。
「あ、待って…」私はあわててカバンの中をさぐって、ポーチからウェットティッシュを掴み出し、彼女の口のまわりを拭う。
「ふぇ…」
「ちっちゃい子みたい…なゆた」
「と…としうえだもん…」
私にとってはここまでのやりとりでも充分すぎるほどだったのだけど、今日はこのあともバチが当たりそうなくらい充実していた。つれていってもらったお店はどこもそれぞれに素敵で…魅力ある品揃えだったり、店内の装飾だったり、流れている音楽まで…私は自分の知らない世界が、こんなふうに街のあちこちに存在しているということ、そしてそんな世界を私に教えてくれる人がいるということを、何だか尊いことのように感じた。
たくさんのものを二人で見て歩いて、言葉を交わし、笑いあう。これが一体どういうことなのか、今の私には分からない。いつか分かる時が来るのだろうか。もしかしたら、ずっと透明になりたいと思っていた私は、最初から透明だったのかな。そして、彼女が現れたことで色づいていった…?こんな意味のないことを意味ありげに思い巡らしているのは、どうしてなんだろう。架空の言葉たちを静かに置き去りにして、私は、目の前にある景色を選びたいと思いはじめているのかも知れない。これって…どういうことなんだろう。とにかく今はすごく楽しい。何度も湧き上がってくる気持ちは、自分でも笑えてくるほど語彙に乏しいこの一言に集約されていく。
「なゆたがつれてってくれるお店、どれも素敵だね」
「ほんと?うれしい…ゆうべね、いっぱい考えたんだよ」
休憩に立ち寄ったハンバーガー屋さんのテーブルで二人は向かい合っていた。みっつめに訪れた店で理想的な見た目のストローハットを見つけて、それに合うリボンを今から探しにいく、というところだった。
「ありがとう…そんなにいろいろ考えてくれて…」
「えへへ、楽しみだったもん。…ね、あいちゃんはどうしてストローハット欲しいと思ったの?」不意になゆたが訊ねてくる。
「え…!えーと…なんでかな…たぶん、むかしの絵画を眺めてて、なんかね、人物画とか…それで、服装がすてきだなって思ったんだよね…」
「ふぇ、すごい…」
「もちろん…今の時代にむかしの格好をしてみても、きっと浮いちゃうというか…その…むずかしいんだけど、でもちょっと雰囲気を取り入れることは…できそうな気がしてて…」
「うんうん、とてもわかる…私もいろいろなところから刺激もらうことある」
「…なゆたは…その、前から思ってたんだけど、どういう世界が好きなの?」
「んー、えっとね…いろいろあるよぉ。ふわふわしてて、夢と現実の境界線がないみたいな感じすき。ジャンルで言うと、インターネットの美学とかゴシックとかエレガントなものとかかなぁ。ほかにも綺麗で可愛らしいお菓子とか、ロシアや中央アジアの民族の色使いとか…あ、妖精の写真もすき。あとはSFとかサイバーパンクもすきで…あとはねー、花とかチョウチョもすきだよ…なんかいっぱいあるね!えへへ…」
「なんか…すごすぎる…」
「んぅ、うまく説明できてないよね…」
「んーん、いろんな物事に目を向けてるっていうのは…よく分かる。私は直接ファッションに関わることにしかつなげて考えれないから、なゆたはやっぱりすごいな…」
「褒めてくれる、ありがとう」
私の目の前でメロンソーダを飲みながらほくほく笑ってるこの人は、内面に向かってものすごい奥行きを持っている人で…きっと彼女の佇まいがどこかしらただならぬ様子をしているのも、そういったことが関係してるのかな。
ハンバーガー屋さんを出たふたりは、少し歩いて、なゆたの行きつけの手芸屋さんに向かった。
「…こういうお店、私はじめて」
「んふふ、ここいっぱいあるよぉ」
「うん…すごい品揃えだね」
「こっちにリボンのコーナーあったはず…!」
私は彼女の青い髪を追いかけて、棚のあいだをすすんだ。リボンコーナーにはたくさんの色とりどりのリボンがリールに巻かれて並んでいて、眺めているとなんだか頭がぼんやりしてしまう。きれいなものを見ると、私の頭はいつもぼんやりしてしまうのだ。
「黒…がいいかなぁ…」つやつやとしたリボンに触れてみる。
「うんうん、黒いいね。顎のしたで結べるようにするんでしょ?…じゃあ、この柔らかい生地のやつとかどうかな?」なゆたが指さしたリボンは、薄く透け感のある素材で、すこし幅のあるものだった。
「これいいね、すきかも…」
「これをすこしギャザー寄せて縫いつけたりしたら、かわいいかも…」独り言のようになゆたが呟いた。
「え、それめっちゃ良さそう…」
「ふぇ…!私の好みでいろいろ提案しちゃってごめん…!」
「んーん、全然いい。私ひとりじゃ思いつかないもん。なゆた、すごいね…。それって、縫い方ふつうよりむずかしい??」
「んーん、そんなにむずかしくないよ」
「そっか、このリボン買って、それお願いしても…いい?」
「うん!もちろんだよぉ」
「じゃあ、これにする…えっと…長さはどれくらい必要かな…」
「ふふ、よかったぁ…すぐ決まったね。…長さは、たぶん1.5メートルあればいけると思うよ。あごの下で大きな蝶々結びできるくらいかなぁ」
今さらだけど、私はなゆたのセンスに感心していた。たくさんの引き出しを持っていて、いちばん適したやり方を示してくれるというか…。しかも、たぶんだけど、彼女はそれを直感的にできてしまうのだろう。
「あの…その…リボン付けてくれるって…言ったけど、どこでやるの?」
「…ん、どうしよう。そこ考えてなかった…」きょとんとした表情。
「…あはは、そっか。…と、とりあえず、これ買っちゃっていいのかな…」
「うん、どこでするかは後で考えよ?」
私はなゆたに教わって、店員さんにリボンをカットしてもらい会計を済ませた。自分がこんな店で買い物をしているということが、なんだか変な気がしたし、何となく思いえがいていただけのことが具体的なものになっていく過程というのが、とても不思議だった。
店を出ると、いつのまにか陽が傾きはじめていた。
街のざわめきの中を並んで歩いている時、ふと、なゆたが遠い目をしていることに気づいた。その視線の先には家族連れがいて、背の高いお父さんが女の子を肩ぐるまして歩いている。後ろ姿だから分からないけれど、お父さんも女の子も、そのすぐ隣を歩くお母さんも、きっと笑顔なんだろう。とても仲の良さそうな、微笑ましい家族の姿だった。そして、それを見つめるなゆたの瞳は、私には、どうしてもさびしそうに見えた。
「…あ、あの」何気ないふりをしたつもりだったのに、変にぎくしゃくした口調になってしまった。
「ん…!な、なになに?」なゆたはなゆたで、何とも言えず不自然な反応をしてくる。
「んーん、もうそろそろ帰る…??その…夜になりそう…だから…」
「う、うん…そだね。そろそろ帰らないとね」
電車に乗り込んで、いつもの路線の窓から、二人はくすんでゆく住宅街を眺めた。なゆたはさっきの家族連れを見かけた時から、何となく様子が沈んで見える。私はなゆたの家族構成のこととか、まったく知らないけれど、もしかしたら、何か関係があるんだろうか…。でも、いまその話題に触れるのはダメな気がする。
「今日…ほんとにありがとう…」
「え、こちらこそだよぉ。すごく楽しかった」
「ん、わたしも」
「ね…あいちゃんの駅まで行ってもいい?」
彼女の降りる駅はふたつ手前だから、てっきり電車の中で別れるものと思っていた。
「…え、もちろんいいけど、時間はだいじょうぶなの?」
「うん、へーきだよ」なんだろう、初めて見るような切ない笑顔。
二人はいつもの公園のベンチに腰かけて、木々の梢をわずかに浮かび上がらせている薄暮を見た。
「…あいちゃん」ささやくような声。
「…ん、な、なに?」
「ごめんね…なんか、最後の最後で変な空気にしちゃって…」
「んーん、…気にならないって言ったら嘘になるけど、私は今日じゅうぶんしあわせだったから、あやまらないで?」
「あいちゃん…うぅ」なゆたがうつむいて、膝のうえにおいた手を固く握りしめた。いつも華奢な体がさらに小さく見えて、なんだかなゆたじゃないみたいに見える。
「…ど、どうしたの」
「あのね…子どもの頃にね…お父さんが折り紙の白鳥をつくってくれたの…」
「え…?そ、そうなんだ」
「うん…でね、それにクリップを付けて、厚紙に絵の具で湖をかいてね。裏側から磁石をあてて白鳥を動かしてくれたんだよ。水のうえを白鳥がくるくると泳ぎまわって、ほんとに私たのしくて、魔法みたいって思ったんだ。ずっと、その不思議な動きを眺めてたよ…」
「…それ、すごく素敵だね」
「…でもね、お父さん、私が中学の時にいなくなったの…」
「…え?」
なゆたの目から透明な雫が溢れて、彼女の手の甲を濡らした。
「お母さんと私を置いて、どこかに行っちゃった…」
「…そんな」
「さっき…街で仲良さそうな家族を見て、つい思いだしちゃったんだけど…でもね、それが悲しいとかじゃないの…」
「…そ、そうなの?」
「今日ね、私ほんとに楽しかったの。それはね、ぜったいあいちゃんといっしょだったからなんだよ?…おでかけの途中で、何回も、あいちゃん最高って思ったもん。…だから、最後にお父さんのこと思いだして…あいちゃんもいつか、私のことを置いて、どこかにいなくなったらどうしよう…って…うっ…そう考えたら、すごく怖くて…うぅ…」
なゆたが私のほうを見つめてぽろぽろと涙をこぼした。そういうことだったんだ…。あの遠いまなざしの奥で、この人は…私と過ごした時間をこんなにも思ってくれてたなんて。
私はハンカチを取りだして彼女の頬をそっと拭うと、キャップを脱がして、その青い髪をなでた。やわらかくて、冷んやりとしていた。
「なゆた…私どこにもいかないよ…だから、何も怖がらなくていいよ。…ずっと、いっしょにいよう?…だって、私もなゆたといっしょがいいから…ね、いいでしょ?」
こんなことを言うのは勝手だろうか。でも、だれにも未来のことなんて分からないというのは分かりきったことだし、それを知ったうえでこんなことを言うのが、たとえずるいことだとしても…今この人をなぐさめるためなら…。いや、そうじゃない。私はなゆたの髪をなでつづけながら、ベンチの横に置いてあるストローハットの入った紙袋をちらりと見た。…そっか、そういうこと…だったんだ。
私はようやく気づいた。なゆたが好きだということに。
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
