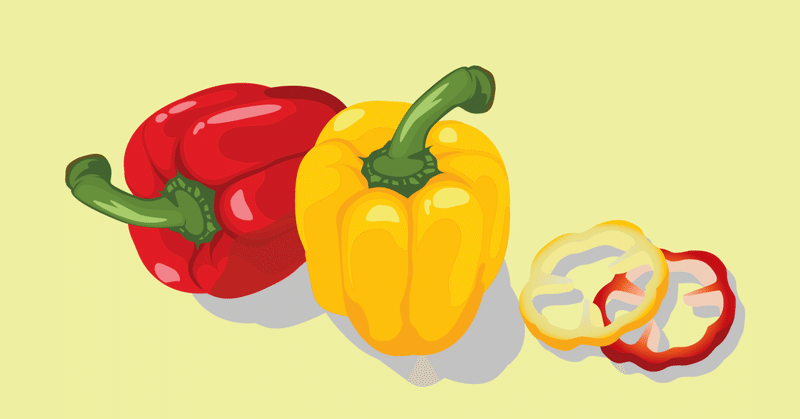
近代の脱構築――野口雅弘『マックス・ウェーバー』を読んで
今回の課題本は、2020年に中公新書から発売された野口雅弘『マックス・ウェーバー』でした。ドイツの社会学者であるウェーバーの代表作『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読む前に、入門書から入って背景を知ろうということで選書されました。
野口の本には、「近代と格闘した思想家」という副題がつけられています。この記事では、「近代との格闘」という言葉が意味するものを、自分なりに整理したいと思います。
格闘とは脱構築すること
といっても、ウェーバーは社会を転覆させようとした革命家ではありません。彼は思想家として、近代とは何かについて深く考えた。ここでは、格闘を「脱構築」と言い換えてみます。ここで言う脱構築とは、あるものについて深く考察し、それが隠し持つ矛盾や偏りを明らかにすることです。つまり、近代との格闘とは「近代の脱構築」です。
また、「近代」とはウェーバーが生きた時代、つまり19世紀後半から20世紀初頭です。ウェーバーは、自分が生きた時代に社会が迎えた変化を鋭くとらえ、その本質を見極めようとしました。
では、そうした近代を脱構築するとはどういうことか。野口の本では、特に2つのキーワード――「客観性」と「合理性」が重視されています。ウェーバーは、単に「近代とは客観性・合理性の時代だ」と言ったのではなく、客観性・合理性とはいったい何なのかを一歩深く考えました。
客観性――主観性の果てに
まず、ウェーバーが考察した一つ目のキーワード、「客観性」とは何でしょうか。それはもちろん主観性の反対ですが、要するに特定の立場や派閥にとらわれないことです。現代にいたるまで、特に政治や報道をめぐる場面で、客観的なエビデンスを重視した思考は当然のように求められています。客観性は間違いなく、近代社会の重要な支柱の一本です。
しかし、ウェーバーは純粋な客観性というものを認めず、全ての観点は主観的なものだと考えました。どんなに主観性から離れているように思えるエビデンスも、それが客観的だと認められるにあたって、認める側の主観的な評価から逃れることができません。別の言い方をすれば、客観性とは主観性をもった多くの人が認めて初めて成り立つものなのです。極端な例ですが、食べログの評価が高いお店を、主観的な星付けの集合によってつくられた評価にもかかわらず、私たちは「客観的においしいお店」かのように扱っています。
ではウェーバーは全ての価値は主観に過ぎないから、共有可能な普遍的な価値など考えるだけ無駄と開き直っていたかというと、そうでもありません。ウェーバーは「価値自由」という言葉を重視していました。それは特定の価値を選択しつつも、その価値づけに囚われないという姿勢を指しています。具体的には、自分や社会がある主観的な観点に拠っていることを自覚することです。普遍的な客観性(に思えるもの)ではなく、自分は特殊な立場であるということを引き受ける。
なぜ人間に価値自由が必要かというと、それがあって初めて政治的な空間が成り立つからです。政治とは、異なる観点に立つ人々が複数集まって意見を戦わせることです。意見の偏り、つまり党派性こそ議論の前提です。党派性がぶつかり、やがてその対立に折り合いがつくことで、仮にでも共通の価値観を設定することができる。
逆に、その場に絶対的な客観性、あるいは真理とされるものが現れると、真理と異なる意見が排除されてしまいます。それは合意の形成ではなく、非政治的な空間の出現、独裁的な政治の始まりであるわけです。こう考えると、ウェーバーは客観性を通して民主主義というものについて考えたとも言えそうです。
合理性――形式化のリスク
もうひとつのキーワード「合理性」について考えてみます。合理性とは一般的に、無駄がないこと、効率的なことを指します。これもまた、近代以降の社会を特徴づける性質であることは間違いありません。
ウェーバーは、合理性を「形式合理性」と「実質合理性」の二つに分けることで、その本質を考えようとしました。実質合理性はそのまま、実際に合理的であることです。一方、形式合理性は違います。先の段落でもふれたように、異なる意見がぶつかる議論の場で、ひとつの合意に至るのは簡単ではありません。そこで要請されるのが、一定の形式に則って物事を決め、遂行する「形式性」です。
例えば、夫婦である日の外食の行き先が合意にいたらないとします。そのとき、「先週は夫の意見が採用されたのだから、今日は妻の意見を採用しよう」という風に決着をつけたら、これは形式合理性に則ったことになります。意見の「実質」ではなく、夫婦の意見は交互に(≒平等に)実現されるべき、という「形式」を重んじているからです。
ウェーバーは、近代が形式合理性の時代だと考えました。それは一か所に権力を集中させないためのストッパーとして機能する面もありますが、何事も形式的に処理されていく、いわゆる「官僚制」につながることにもなります。ウェーバーは官僚制が過度に力をもつことに危惧をいだいていました。
実際の行政に限らず、物事を進めるうえで、何事も文書に記録することを重視するような官僚制は大いに有効です。しかし、それは主観的=党派的な観点を極力排除する必要があるため、先に出た「政治的な空間」と対立してしまいます。議論によって実質合理性を目指す前に、形式合理性が全てに優先されてしまいかねないのです。
官僚制という論点は、責任についての思考につながります。あくまで形式に則っているので、官僚的な振る舞いに個人の責任を問うことはできません。それは時に取り返しのつかない出来事に帰結することもあり、最大のものがウェーバーの死後にヨーロッパで行われたホロコーストです。ユダヤ人の虐殺は、ヒトラー一人の独断で行われたのではなく、無数の職員や市民が官僚的に物事を処理し実現されたものです。社会をより合理的にする、というスタンスは誰もが歓迎するものだったはずなのに、いつの間にか人々の命を奪うような真逆の方向に行ってしまう。形式合理性はそうした危険をはらんでいます。
矛盾から思考する
客観性も合理性も、ウェーバーが生きた時代のみならず21世紀の現代においても重要な、それ自体が社会の「善」とされるものです。ですが、ウェーバーはこれらが「悪」に転じうる逆説を考えていた。
注意すべきは、決して彼が客観性や合理性を排除し、主観的で非合理的な前近代的な社会に戻るべきだと主張していたわけではないことです。社会を運営していくためには、客観性も合理性も欠かせないことだとわかっていた。しかしそれらを絶対化することに警鐘を鳴らしていたウェーバーは、近代が「主観的な客観性」・「非合理的な合理性」という矛盾を抱えていることをふまえて、その上にどのような社会を構築するべきかを考えようとしていた、と言えるのではないでしょうか。解決が不可能な難問を指す「アポリア」という言葉がありますが、近代とはまさにアポリアの産物です。ウェーバーが直面したのは、近代という「矛盾との」格闘なのです。
村上春樹の近代
最後に、少しだけ野口の本から脱線して、この問題を別の側面から考えてみます。
官僚制というキーワードは、村上春樹の主人公たちを思い出させます。哲学者の稲垣諭は、村上の小説が読者を惹きつける理由を、その主人公たちが官僚的であることだと指摘しました(『絶滅へようこそ』)。家事や仕事といった毎日のルーティンを淡々とこなし、どんなグループにも属さない。稲垣は彼らを「はぐれ官僚」と呼びます。読者は、誰もが官僚的であることを強いられる現代において、理想を体現した人物像として村上作品の主人公たちを受け止めている。
だからと言って、村上の主人公はただ官僚的=無責任であるわけではありません。責任をとれないが、しかしその「責任のとれなさ」に向き合おうとしているのではないでしょうか。
稲垣は言及していませんが、私は「一人称単数」という村上の最新の短編小説を思いおこします。そこで主人公は、見知らぬ女性から思いあたることのない過去の悪行を非難され、困惑します。戸惑いながら女性のそばを離れたあと、街を眺めるとそこは「見知っているいつもの通りではな」いように感じられます。「そこを歩いて行く男女は誰一人顔を持」っていないようにも見える。主人公がその光景に呆然と立ち止まったまま、小説は唐突に終わります。
なんとも後味の悪い結末ですが、現代を的確に表現しているようにも読めます。誰もが顔を持たない、つまり責任の主体となりえない街で、主人公もまた責任を取りようのないことの責任を追及される。官僚制が支配した世界です。しかし、主人公はそんな世界で生きていくしかない。小説の前半で、主人公はスーツを着て出かける前に鏡の自分を見て、理由のない「うしろめたさ」に駆られますが、それも同じ文脈で読むことができるでしょう。
身に覚えのない責任をとること、あるいはうしろめたさと共存すること。それは極めて主観的で非合理的な在り方です。ですが、客観的で合理的な近代=現代社会において、人間が個人であるために直面しなければならない矛盾だと考えると、ウェーバーと村上がひと続きに読めてきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
