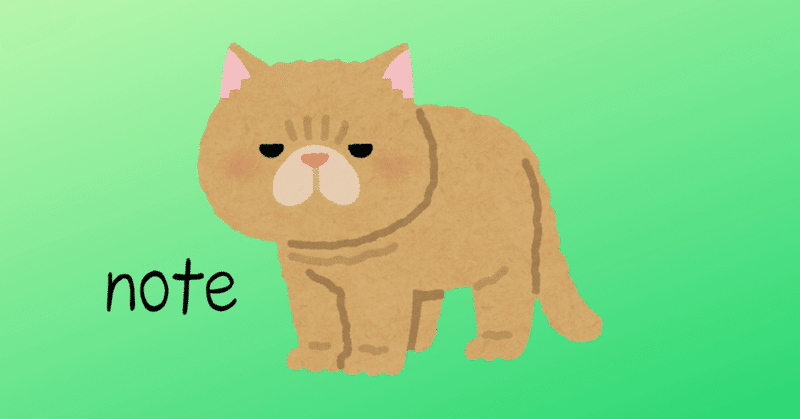
【短編小説】ムネ
俺は高田涼太。料理人だ。
高校を卒業して、うちの家業である料亭に入った。これは当たり前の事で、俺はこの店を継ぐ覚悟だった。店に入ってすぐ皿洗いとなった。これも当然の事と理解した。
一年が経った。そろそろ板場の仕事を教えてもらえるかと思った。下に一人入ってきたし、そいつが皿洗いを引き継ぐと思っていた。しかし、そうはならなかった。新しく入ってきたヤツは、新井誠司という俺より5つも年上で、他の店で修行していたという事だった。
新井は俺よりも先に仕込みの担当をする事になった。
板長である親父が決めた。それは流石に俺は承服できなかった。親父は俺の話を全く聞き入れなかった。それどころか親父は息子の俺を特別扱い出来ないばかりか、辛く当たってきた。
我慢したが、限界が来た。だから家を出た。
東京に来た。
神保町のカレー屋で働き始めた。
俺はカレーが好きだった。
賄いで作る店の出汁を使ったカレーを親父もみんなも美味い、美味いと言って、食ってくれたからだ。
神保町の店はスパイスカレーなのでちょっと違うのだが、ここで頑張って、いつか俺の店を持とうと必死で働いた。
この店では俺のファンがいた。一緒に働くアヤちゃんだ。
俺は厨房でアヤちゃんはホールだが、アヤちゃんは俺の作る賄いを兼ねた試作品のカレーをいつも褒めてくれるし、店から帰る時は一緒に駅まで歩き、将来の話をする。
俺が自分の店を持つ事を話すと、アヤちゃんは、叶うといいねと、言ってくれる。
地下鉄の入口で俺らは別れる。アヤちゃんは地下鉄に乗り、俺は押してた自転車で帰るからだ。
一人で自転車をこぎ、俺は訳も分からずに吠えてる。
3年間夢中で働き、金を貯めた。そして、いよいよ自分の店を持つ日が来た。
東京の郊外だが居抜きの良い物件が見つかったからだ。頑張って貯めた金だけでは足らなかったが、今の店のオーナーが支援してくれた。
内装を整えて、やっとオープンに漕ぎ着けた。
アヤちゃんは俺の店で働いてくれる事になった。
店をオープンさせた。
その日にコロナの影響で東京に非常事態宣言が出された。
この店は俺の最後のチャンスのはずなんだ。
しかし全く客が来ない。一人もだぜ、全く来ない。
残念ながら、客はずっと来なかった。
アヤちゃんに給料も払えない。
あんまりなので、アヤちゃんに辞めてもらう事にした。アヤちゃんは泣きながら俺に、ごめんねと、言った。ごめんなのは、こっちの方だよと、俺は言った。
待ってても良い事は何も無さそうなので、俺は攻める事にした。
キッチンカーを借りて、カレーを売りに行くのだ。
車を借り、仕込みをして、俺は売る場所を探した。
ムチャクチャ探したんだが、いい場所はなかなか見つからず、途方に暮れていると、ある駐車場のオーナーと出会い、その駐車場を借りる事ができた。
下町の小さな工場が建ち並ぶエリアの真ん中にある小学校。
その隣の平日の昼間は誰も車を止めない駐車場で、俺は店開きをする事になった。
初日、客は一人も来なかった。
それから三日間、ずっと客は0のままだった。
四日目は、朝から雨だった。
降りしきる雨を眺めながら、俺はボーっとしていた。
そこに一匹のネコがやって来た。
白い身体に黒い模様のネコだ。首輪をしていないので、多分野良ネコだろう。
ネコは俺の車に下に潜り込んだように見えた。
俺は暇なので、車を降りネコを見に行った。
ネコはいた。後ろの左足を怪我していた。血が出てる。
俺は躊躇した。俺の商売は食べ物屋だからだ。
ネコは一生懸命に血が出ている足を舐めている。
仕方ない。
俺は、店じまいを始めた。
片づけ終わると、車を降り、ネコに手招きをした。
すると、ネコは俺の方に足を引きずりながらやって来た。
俺はネコを助手席に乗せ、動物病院に連れていった。
動物病院で左足の治療をしてもらった。
怪我の程度は軽く、擦り剝いた程度だった。
その後、家出ネコに該当しないかインターネットで検索してもらうと、このネコは家出ネコではないという事が分かった。
そこで、各種の予防接種をしてもらい、俺が保護する事にした。
ネコを飼うためのケージや水のボトルや餌皿は、動物病院から一時的に借りる事にした。
そうしてネコを俺は連れて帰った。
ネコはオスで、大体1歳ぐらいだと分かった。
オスか…
俺はネコにマサムネと名付けた。
顔は殆ど白いのに、左目の回りだけが黒くブチになっているからだ。
まるで、眼帯をしているみたい。それなら独眼竜正宗だ。
マサムネと呼ぶのは長ったらしいので、ムネと呼ぶ事にした。
ムネ、ムネ。
ムネはもう自分がムネである事が分かったみたいだ。
ニャアーと鳴いた。
翌日は朝から快晴だった。
駐車場のアスファルトは熱くなっており、俺は打ち水をした。
ネコは水に濡れるのを嫌がると思っていたが、ムネは違った。
俺がお玉で水をかけると、水の方へ走ってきて飛び上がり、何とか水を前足でつかもうとした。
面白いので、何度もやってみた。
夢中でやっていると、キャッ、キャッという声が聞こえた。
いつの間にか、俺とムネの回りにベビーカーを押したお母さんたちが囲んでいた。
ベビーカーの赤ちゃんは、身をよじらせて喜んでいた。
中には、3歳や、4歳ぐらいの子どももいた。
「飼いネコですか?」
「ええ、昨日から。」
「可愛いですね。」
「ありがとうございます。」
「ここ、カレー屋さんなんでしょう?いつもここの前をお昼前に通るんです。この子を連れて、公園に行く時に。すごくいい匂いがしていて、食べたいなと、思うんだけど…」
「ぜひ、食べて下さいよ。」
「でも、辛いんでしょう?」
「辛いの、ダメですか?」
「いや、私は平気なんだけど、それじゃ、子供に食べさせるものがないじゃない。」
「ああ、なるほど。じゃあ、お子さん向けの甘いカレーも作りますよ。」
「ええ?それって、今?」
「今、作ります、作ります。皆さん、ここで食べます?食べるなら、テーブルと椅子を出しますけど。」
「どうする?」「食べよっか。」「私も食べるわ。」「じゃあ、大人三人と、子供三人でお願いします。」
「分かりました。ナンにします、ご飯、ご飯はサフランライスもありますけど。」
「じゃあ、大人は全員ナンで、子供は全部白いご飯で。」
「分かりました。そこのコンビニまで、ちょっと、買い物をしてきますので、お待ちください。」
コンビニで、牛乳と生クリームとポークウインナーを買って戻ると、俺は、厨房で中華鍋を出し、まず湯を沸かした。湯が沸くと、カツオと昆布で出汁を取る。出汁の中に、大人用のカレーを入れて混ぜ合わせると、そこに牛乳と生クリームを入れる。
よく混ざったら火から離して休ませる。その間に、俺は輪切りにしたウインナーを炒める。よく炒まったら、カレーの中に入れて、また火にかける。
味を見る。辛さは柔らかいはずだ。味見の皿に取り、お母さんたちに配って、味を見てもらう。OKが出た。
続いてお母さんたちのカレーを仕上げる。ナンを焼き、プレートにカレーと付け合わせのサラダを盛り付ける。
全部できたので、外のテーブルに持っていく。みんなが食べている。
子供も美味しいと言ってくれた。何と赤ちゃんもカレーを食べている。
子供用に作ったのは、俺が賄いで作った出汁カレーの甘口版だ。
晴れたお昼時、お母さんたちと子供が、みんなで俺のカレーを食べている。
ムネは、日陰の冷たい地面で寝そべっている。
それからはトントン拍子だった。
暑い昼時、打ち水をする。ムネが飛び上がり、水を取ろうとする。子供が喜び、キャッキャッと笑う。客が増える。
ママ友がママ友を呼び、ママ友の知り合いを呼び、ママ友の旦那を呼ぶ。
たくさん人が並び始めると、近所の工場で働く人たちも買いに来てくれるようになった。
俺はアヤちゃんの電話した。「また、働いてくれないか?」
翌日、アヤちゃんは来てくれた。スゴイお客さんで、アヤちゃんもメチャクチャ忙しかった。
昼時を過ぎ、お客さんがいなくなると、俺はアヤちゃんに「いきなり、スゴイ事になってごめんね。」と言った。アヤちゃんは、「ううん、平気。もう辞めてくれって、一生言わないでね。」と、俺に言った。
横の小学校の先生で、給食が足りなかった先生が、ウチにこっそり食べに来てくれるようになった。
この学校は給食室があり、給食のおばさんがたくさんいるのだが、おばさん達も、勉強のために、と食べに来てくれた。
学校の運動会の日、たくさんの父兄がお弁当代わりにウチのカレーをテイクアウトしてくれた。
学校にすごくお世話になったので、今度は俺が家庭科の調理実習の時に臨時講師をしてあげた。
そこで覚えたカレーを生徒たちが、林間学校で作ると言っていた。
コロナ禍だが、人の輪が増えた。
俺は、幸せだった。
全部、ムネのお陰だが、ムネは意に介する事もなく、おやつを舐める事に忙しくしている。
そうしているうちに、テレビが取材に来る事になった。
朝の情報番組だ。今日の昼時に取材する。
昼になった。テレビでよく見る若い男のアナウンサーがやって来た。
最初に俺とアヤちゃんにインタビューした。俺もアヤちゃんも人生イチ緊張していた。その後お客さんにもインタビューし、最後に自分もカレーを食べてくれた。
このアナウンサーの食べっぷりがよかった。
本当に、美味そうに、パクパクと食べてくれた。
コメントが美味しそうな事を存分に知らせてくれた。
翌朝、放送された。
朝の放送の後、昼時はいよいよ大変な事になった。
駐車場だけでは足りず、長い行列ができた。
ヤバいなと思っていたら、「リョウ、お待たせ!」と、声がした。見ると、神保町のみんなが来てた。
挨拶する間もなく、みんなは一斉に働きだした。
お陰で、俺は勇気が出た。
何とか全員にカレーを出せそうだと、ホッとしだした頃、「リョウ!」と、懐かしい声が聞こえた。
親父だった。お袋もいる。じいちゃんも、ばあちゃんも一緒だった。
「おい、俺らの分のカレーもあるか?」と、親父が訊いた。
「もちろんだよ。悪いが、並んでくれ。」と、俺が言った。
親父達は俺のカレーを食べた。
親父は「美味い!」と言った。
お袋は、涙を流した。
じいちゃんとばあちゃんは、笑いながら食べてくれた。
親父が「よく頑張ったな!」と、俺に言った。
俺は「まあな」と答えた。言ってくれた事が嬉しかったが、その嬉しさは隠そうとした。
ムネはいつものように、冷たくて気持ちの良いアスファルトの日陰で丸くなっていた。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
