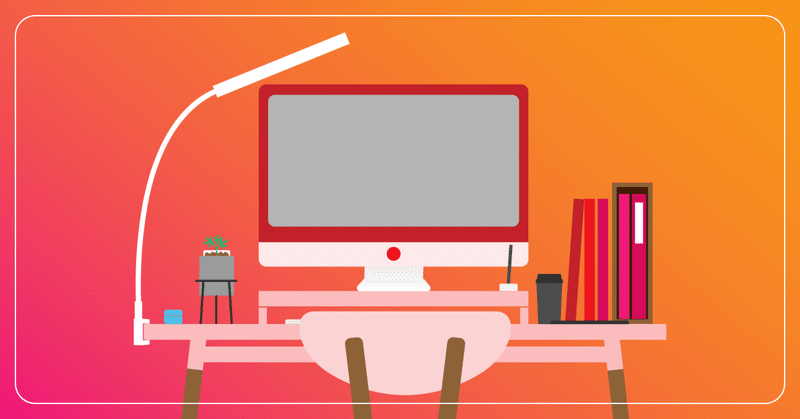
自宅でプロレベルの音楽制作ができるようになるには③MIXルール【制作編】
こんにちは。DTM制作、音楽制作において、MIXMasteringはとても厄介ですよね。僕自身独学あがりですが、今はMIXの指導なども行っている身ですので、なるべくシンプルに、MIXでの主な作業の考え方と役立て方をまとめてみたいと思います。
1.音作り作業と、MIXの編集が混合してしまっていないか?
よくありがちでかつ、複雑な原因に挙げられるのは、その音単体をよくする工程である音作りと、相対的な関係性を調整していくMIXという2つの工程を分けずに、なんとなくで作業を進めている、ということがあります。
例えば、ギターの音があったとします。自宅制作では特に、アンプシュミレーターを使用するときも多いかもしれません。これは、その音単体に対する処理なので、音作りですね。
あるいは、ボーカルデータに対して、音量をトリートメント(音量バランスのばらつきを減らす)ためのプラグインをかけたとします。これも、単体で音を聞いて行う作業なので、音作りです。
逆に、ギターもボーカルも、ソロで聴く分には問題はないが、後々のクリッピングなどを防ぐためにローカットを行う、これは相対的な処理になりますのでMIX作業ですね。
つまり、音作りとは、その音のみを聞いて行うことができる、その音のみのための処理。
MIXとは、そのほかの楽器と同時に再生したときに出てくる問題に対してアプローチする処理、と捉えましょう。
1-2.単体処理→MIX処理の順で行う
ですので、まずはそれぞれの音を単体で聞いてみてください。その音を聞いた時に、何か違和感がありませんか?音選びがあまり適切ではなかったり、あるいはディストーションがうまく機能していなかったり、変なノイズが入っていたりする場合は、まずはそれらに対して適切な対処を行うことを心がけましょう。
ボーカルで例えるなら、歯擦音、低域から高域まで潜んでいるピーク(反響ノイズ)の除去、吹かれなどのノイズなどが該当すると思います。
ギターやベースで言えば、アンプでの音作りがカッコよく仕上げられているかどうか、
ドラムで言うなら、音源はジャンル感に違和感がないか、MIDIの打ち込みは自然か、などが挙げられるでしょう。
単体の音の処理や加工が終われば、次に、MIX作業の開始です。
2.MIX作業で守りたいこと
MIXにおいて、というより音楽制作全体において、本来は絶対などは存在していません。ですので、ご自身の方法やルーティンを確立するのが、最も最適解になることは間違いないと思います。
ただし、デジタルDAWの特性上、あまりにもできることが多くて、全てを理解し自分流にアレンジするのは、正直限界があると思います。初速、あるいは制作途中において、なるべくペースを落とさないための、一つの見解をお伝えいたします。
・音量バランスを最初に取る
全ての音が出揃ったら、まずはフェーダーバランスを整えましょう。基本的には、ドラムのKickの音を基準として、他の音を相対的に整えていきます。
①まず、クリッピングを防ぐためにキックドラムの総量は-10dbになるように、フェーダーを整えると、後々、2Mixの音が大きすぎる、といった問題を防ぐことができます。
②キックドラムを1とした時、およそベースは0.8、ボーカルは1〜1.2ほどを目指すと、聴きやすいMIXを作ることができます。この際に注意したいのは、メーターに表示されているdb数で判断するのではなく、自らの聴感でボリュームバランスを整えることです。(デジタルの数値と人間の感度は同じではないため)
・Compressorで音のテンション感をまとめる
Compressorで①音の方向性、ラウドネス感、すなわちテンション感と、②アタック感、いわゆる前後の定位感を整えます。
①において重要なのは、Ratioとスレッショルドで音の密度を調整し、テンション感を整えること。②においては、Attackで前後感を調整し、音の優先順位を明確にすることが重要です。
・プラグインの使用前と後で音量が変わらないように、makeupやgainを必ず調整する
初めにとった音量バランスを壊さないために、プラグインを挿した後と前で、音量感に相違がないよう、なるべくプラグイン内に内蔵されているGainやMakeUpを使用して音量を調整しましょう。
それでも、プラグインで音量は変わっていないが、作業を進めるうちにもう少し音量バランスを整えたくなったら、その時はフェーダーを使用して微調整します。
・EQは譲り合い→ニュアンスの調整を行う
MIXにおいて基本的にEQは、譲り合いのための手段です。例えばキックドラムとベースの二つの音を混ぜ合わせたい時のことを考えてみます。
キックの最も音量が出ている帯域をアナライザーやEQで確認してください。50-90Hzに最も音量の高い山があると思います。
逆に今使用しているベースの最も音量が出ている帯域は、80-100Hzあたりにありますか?
この時、MIXにおけるEQで最も使用される手段は、ベースのEQでキックドラムの最も出ている帯域近くをカットする、キックドラムのEQでベースの最も出ている帯域をカットする、ということです。
それにより、不必要に共鳴せず、すっきりとさせながら共存させることが可能になります。
・ヴィンテージ、アナログ系を使う
特にMIX時は、デジタルでもOKなのですが、ヴィンテージやアナログ系のプラグインを使うと、より音がプロっぽくなります。倍音の付加、がその主な理由なのですが、もし何かお持ちでしたら、少しプラグインに変化をつけていくことも、おすすめです。
3.目的と手段は別物である
最後に、改めてになるのですが、そのトラックに対して、EQをかける、ということ自体が目的になっていませんでしょうか。同じボーカルにEQを挿入する、という手段でも、
部屋鳴りのノイズを取りたい(音作り)ために500-1kHzを減衰させるのか、
ベースに馴染むように少し太くしたい(MIX)ために200-500Hzを少し増幅させるのか、によって、意味合いが異なりますよね。
世の中には、それらを一つにまとめて解説しているHow toの記事や動画などがたくさんあります。素晴らしい一方で、しかしそれらは工程に慣れている人が行っている、CPU負荷に対応するための方法ですので、少しややこしいことになります。
現在は本当にありがたいことに、機材のクオリティも大変高く、EQやCompを一つ二つ分けてもほぼ全く支障はありません。
ですのであくまで一つの提案ですが、前段で音作り、後段でCompとEQを用いてMIX、という方法を用いてみてください。
後々色々なプラグインを使用するようになっていくとより、シンプルにとらえながら作業ができるようになっていくと思います。
そんな記事でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
