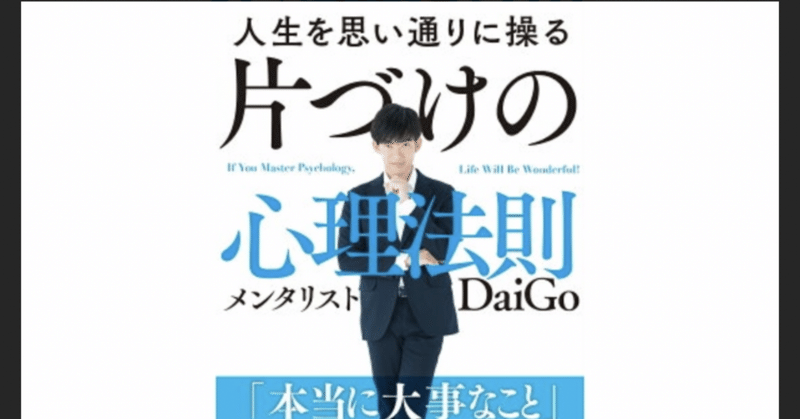
人生を思い通りに操る片付けの心理法則
選択肢を3つにすると即断即決ができる
ものが捨てられないという心理を分析すると3つの心理効果が働いている。選択回避の法則→選択肢が多くなりすぎると人間はものを選べなくなる。損失回避の法則→人間は自分が損をすることを非常に恐れる存在だ。保有効果→自分が一度所有したものにより高い価値を感じてしまう。これらの3つが働くと、人は現状維持をする。
自由な時間を増やし、人生を最大化するための片付けの原則の2つ目は、初速最大化の原則。次の行動に取り掛かるまでの時間を最短にする。では、やるべき事にとりかかりやすい環境とはどんな環境でしょうか。1つ目は必要なものが手に取りやすい環境。2つ目は、手順を減らすこと。ある行動に取り掛かるための手順を減らすと、その行動から生まれるアウトプットが向上し、時間が短縮できる。初速を最大化するために、最適なところまでものを減らす、という発想は大事。
人間は、取り掛かるときに必要な時間を20秒短縮するだけで、それを習慣化できる。逆に、20秒余計に時間がかかるようにするだけで、習慣を止められる
なんとなくとるべき行動がわかる状態がアフォーダンス。そのアフォーダンスを利用して、その環境に置かれた瞬間、何の行動とればいいのかということが一発でわかるようにしておく。そうすることで、取り掛かりを最速化することができる。例えば、前日のうちに、読みたい本を机に置いておく。すると、机に座った瞬間に、この本を読むんだった、とわかる。これがアフォーダンスのデザイン
管理にかかるコストが高いもの、つまり、整理に手間がかかったり、メンテナンスが面倒だったりするものを減らすことで、大きな時間が生まれる
片付けて人生を変えたいのなら、管理するのに細かい手間がかかるようなものは、まとめて捨てるべき
ビジネスパーソンが探し物に費やす時間は、年平均150時間と言われている。1日平均約25分
持っていることでお金や時間、感動といったリターンを生まないものは捨てる。あるいはそもそも買わない
本来の片付けとは、大事なもの、持ち続けるものを選ぶこと。捨てるべきものを選ぶ技術などいらない
ものだけでなく、時間の扱い方にも視野を広げて考えてみると、片付けは生き方を選ぶことであり、未来を選ぶことなのだ、ということがより実感できる
必要になるかもしれないから残しておく、とは結局のところ、不要なものを環境に選ばされているだけ。環境に選ばされている人は、自分で意思決定ができないということだから、周りに流される人生を送ることになる
ワンインツーアウトの法則。何かものを1つ手に入れたときには、入れ替わりに2つのものを処分することを徹底する。衣類や人間関係にも応用が可能。1つ誘いや依頼を受けたら、2つは断る。
毎日、何か1つを人にあげる。利他的行動で幸福度をアップする。人は、もっぱら自分のためにする利己的行動よりも、利他的行動をとったときに、より幸福を感じる。また、幸福度の向上は判断能力や積極性の向上にもつながる
物の置き場所を完全に決める。5秒以内に戻せるルール
置き場所のないものを置くカラッポコーナー作るのもあり
6割収納ルール、取り出しやすく、戻しやすいと言う観点からすると、物と物との間に十分な隙間がある方が良い。スペースの6割しか使わないように収納することをルールにする
水回りは4割収納で掃除を楽に。
数量限定、どのくらいの数を持つかを決める。例えば所有する服の数を決めてしまうなど
同じ機能のものは3つは持たない。例えば、便座カバーを、洗い替え用も含めて2枚持つのはいいとしても、3枚持つ必要はない。また、2つの機能を兼ねているものを持つ、と言うのもオススメ。自分の場合は、ビジネスのウォーキングシューズか。
会社に着ていくスーツ、それに合わせる靴などは4点ずつ用意するのがオススメ。スーツにせよ革靴にせよ、次回の使用まで、間に中3日を空けるようにして休ませる時間を作ると長持ちする。毎日使うものについては、3または4を基本的な数量と考える
衣類の数量を絞るためのコツは、自分のテーマを決めてしまうこと。自分がこういう服を着よう、というテーマを決めて、テーマに合致する服だけを買う。そこまで服に興味がない、という人なら、どんな自分になりたいかを考えるのが良い
写真暗示。片付いた状態を写真に収めて飾る。子供の片付けには効果絶大
If-Thenプランニング。もし、エックスが起きたら(トリガー)、その時はワイをやる(タスク)と言うふうに、条件を事前に決めておくことで目標達成しやすくする。洗面所で顔磨いた後は鏡を拭くなど
仕事と勉強がはかどるデスク整理。やるべきことに集中できる環境を作るためには、デスクではやるべき作業と関係のないことをしないようにしなくてはいけない。デスクに向かった時は仕事や読書をする、そこで映画を見るなんて思いもよらない、という状態を保つ。つまり、アフォーダンス、環境が行動を規定している状態を作る。例えば、デスクの場合には、やっていいこと、を3つまで書いて、そのうちどれかをやるという方式にするとうまくいく。自分の場合は、読書(ボイス機能でメモを取ったり、noteを作るといったアウトプット活動も含む)、英語の勉強、仕事
集中するための照明の基本は、スポットライト。自宅で仕事や勉強するときは、部屋の中の照明を切って、ディスクの手元だけをスポットライトで照らしましょう。すると光が当たっている狭い範囲だけに注意が向くので、集中力がアップします。また、帰宅後の時間をスポットライトだけの少ない光量で過ごす事は安眠にもつながるので、一石二鳥
蛍光灯のような青白い光は集中力をさらに高め、分析思考を強くする。これに対して、白熱灯系の黄色い光はアイディアを生み出すのに役立つ
仕事で普段持ち運ぶ荷物の重さがメンタルに与える影響は思った以上に大きい。荷物が重いという事は、物理的に足取りを重くさせるだけでなく、重い、動きづらいと言うイメージによって行動力を制約することになる
カバンを開けたときの行動は3つに限定。外でカバンを開く時というのは、電車などに乗って移動する時、カフェに入って休む時など、ある程度決まった場面のはず。そこでやりたいことを考え、1から3までに絞ってみる。例えば①仕事②読書③英語の勉強など
頭を使う仕事は午前、単純作業は午後に。研究者によれば、朝には15分で終わる作業が昼にやると30分かかり、夜にやった場合には2時間かかると言われている。午前中に仕事を終えてしまうように集中することが大切。8時から12時までの4時間で仕事を終わらせるつもりで行動してみる。午前中に他人と交流する仕事を入れない。集中力の必要な仕事は、午前中に終わらせよう。打ち合わせやアポイントメントは、午後に入れる。
時間の使い道を先に決める。本当にやりたい事と時間を最優先で確保する
マルチタスクの、「ながら状態」、を脱出する。1つの仕事に専念する環境を作り出す。マルチタスクとは複数の仕事を同時にこなすこと。これは作業を切り替える回数が増えるので、作業効率は下がる。マルチタスクは時間汚染を生むだけで、何も良い事は無い。とっとと捨ててしまうべき習慣。捨てるためには、例えば1時間ごとに携帯のアラームをセットし、アラームが鳴るたびに、①今何をしているか②他のことをしていないか、他のことを考えていないか、をチェックしよう。
スケジュール帳を真っ白に近づける。予定を入れず、出来る限り真っ白なままにしておく。逆に、真っ白なカレンダーを目指したときに排除されてしまうような予定は、実はやらなくてもいいこと
人間にとって本当に必要なのは、何の予定もない時間。空白の時間に自分と向き合い、自分は何をやりたいのかを自問自答すること。その作業を経た上で選択し、行動することで、価値の高い時間を過ごすことができる
スケジュール帳は、埋めることより、産めないことを重視する。1ヵ月以上先の予定を入れるときは慎重に。
スケジュール帳には、予定だけでなく0 △ × 等の評価を書き込む。評価のフィードバックして、今後の行動に生かそう。同じように、飲み会や集まりに参加したら、評価をつけてみよう。評価をもとに判断の精度を高める。
脳科学的に見ると、8週間というの人間の性格が変わるために必要な期間。マインドフルネスや瞑想といったワークが効果を表し、人生が変わったと言える位の変化が起きるのには大体このぐらいの時間がかかるとされている
何もない場所だからこそ、人は見るものを無意識のうちに探す。例えば、1本の木が持つ美しさは、ベトナムの深い森の中でも、大都市の公園でも変わらない。けれども、モノと情報に溢れた都会でなんとなく木が目に入ってくる時と、森の中でじっと目を凝らして気を見るときとでは、感じ取れるものが全く違う
「何もない」からこそ、人はより強く感じる。より深く考える。そして、より多く人生を楽しむことができる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
